5/31�i���j�����@��Ȓ��ʕa�@�@�@�@?2:30�N���C�Ƃ�Ƃ�Ɖ߂����B�j���K���X�����ȂǁB5:15�R�S�~��o�B7:35Taxi�w���ɁB8:50��Ȓ��ʕa�@�O���A�a�@�E�w�Ԃ͉���Taxi�B���T���c���@������㕔�����nj���������Ă����������ƂɁB�����Ï��X�o�R14;30���ʃ��n�a�@�B���߂ɓ����A���@���ґΉ��A�Ō�t2��㐧��������B���낢��v�]����A�Ή��K�{�B�V���`�F�b�N+���́B19:30�A��A�[�H�͍P��̊�䥂ŖˁA20:40�A�Q�B�����v4321���B?�@2011�N5�����Љ��Ö@�l���a���ސE�����B
�@�u�}�����̕a�@�ɍ����t�͕s�v�v�A�u���̎Љ�I�g���͏I������v�A�u�V�Q�A�j���Љ�Q�̈�l�ɂ͂Ȃ肽���Ȃ��v�A�u��t�Ƃ��Ă��I������v�E�E�E�ȂǂƔ������Ă������́A�H�c���̈�t�s���A�@�l�̈�t�s���̂������������Č��݂��@�l���a�@�ŏ�����t�Ƃ��ē������Ă��������Ă���B
�@��N3�������������Ĕѐ�a�@���@�ƂȂ����B�Ɠ����X���ʃ��n�a�@�̏�����Ƃ��ē������ƂƂȂ����B���ꂼ����@���҂�15���قǎ����Ă���B���ɂƂ��Ă͋Ɩ��ʂ��������B
�@���̍s���͉ߋ��̔������e�Ɩ������Ă���B��������S�x��������̂�����B
�@�����A�H�c���͑��ς�炸��t�s���A�����Ė@�l����t�s���B�����g�̈�t�Ƃ��ċZ�\�����߂��Ă���̂��A��t�Ƌ��������Ă���Ƃ��������̎��i�����߂��Ă���̂��͒肩�ł͂Ȃ����A�V�������̒��ł��낢��w�ׁA�o���ł���̂͊y�����B
�@
�@�l���̍ŏI�R�[�X�A�V�s���ɓ������g�ɂ��Ă݂�A���̗l�Ȋ����^�����Ă��邱�Ƃ͖@�O�̊�тŁA���ӈȊO�̉��҂ł��Ȃ��B
�@����2022�N10���͉��������ǂ���̏o���ŁA2023�N5����{�ɂ͐S�s�S��1�T�Ԃ̓��@�����𑗂����B���ɑ傫�Ȍ��ǂ��Ȃ��������A��҂ł͐S�ی�̂��߂ɐ����S�ʂ̗}�������߂��Ă���B
�@�����Ė{�N5�����{�ɂ͕s���̒������s�U��ԂɊׂ����B2�T�Ԃ̌o�߂̒���5Kg�قǑ̏d�����������B���R�ɉ��P�������㕔�����������̌��ʏ\��w����ᇂ����������B�^�̌����͕s���ł��邪�A����ō���̕s���͈�i���ɂȂ�Ǝv����B
�@
�@�قږ��N�Ɠ��������A�ߋ��B
-----------------------------------------------------------------------------
�@���z�[���y�[�W�F�X�V�����S�ɁB�A���X�V�ɂ������Ȃ��B
�@���E�I�[�L���O�B�܂Ƃ܂��ĕ��s�͂ł��Ȃ��Ȃ����B���̕��A���X���܂߂ɕ����Ă���B�ڕW��5000���ɗ��Ƃ����B�ɔ\���h�̑��Ղ�H���Ă̓��{����́A2���ڂŊԂ��Ȃ��R���B�ł炸���������������B
�@���ʋ̌�ʎ�i�F���H��am6:40�o�X�B�̒��ɂ���Ă͉Ɠ��ɓ���B���H�͉Ɠ��ɓ���B
�@����茧�ւ̕��������F�����̎p���Ɏ�q�]�|??�̕��͋C�������A���~�����B
�@�����X�̃��[�`�����[�N�F�^���A�^��A�V���X�N���b�v�A�����X�N���b�v�A�w�p�����X�N���b�v�A���Ђ̎����ȂǂȂǂ͌p���B
�@���Ǐ��~�͈ێ�����Ă���B
�@�����|�F��A�Ԓd�Â���B���S�ɂȂ���邪�A��Ƃ��y�������B
�@���̒��F������Ɩ�������Ɠ������ꂪ����B�����͍ؗ͂����������B
�@�����͒ቺ�GiPad�A�p�\�R���̉�ʂ��r�߂�悤�Ɍ��Ă���B
�@���̏d�R���g���[���F�v������������̕s���łTKg�����ƂȂ����B
�@���I���F�R�c�R�c�Ɛi�߂Ă���B
�@���ȂǂȂǁE�E�E�E�B
5/30�i�j����
�@2:45�N�������̂��Ƃ��B���r�o���͎O��B5:00-6:00�����čēx�����B8:15�Ɠ��ɓ��撆�ʃ��n�ɁA�r�������ǂ���k���A�����������͐L�тȂ��B����Ȃ��̂������̂��H�H�ߑO���@���Ґf�@���u�ȂǁB���H�͑O���̒��ؕ������A���H�B�V���`�F�b�N�Ɠ��́A�����A19:20�ʒ����X�o�R�A��A�[�H�X�e�[�L�A���H�͂������A���ЂƂ������ɖR�����B20:30�A�Q�B�����v3571���B
�k�R�L�ڌ�?
5/29�i���j�@�܂�̂�����@�̒��s�ǔ����ځ@�a���J���t�@EC�@���҉Ƒ��ʒk
2:30�N���B�����̔@���B�����A�k�R�ȂǁB4:00-5:30�Ĕ����A���V��1�T�ԕ����́B8:30�Ɠ��ɓ��惊�n�A�r�������̐�������o�A�H�c�x�@���O����k���B�@��N���Ɏx�����āA�L�E���̎}�Œ�B�g�}�g�E�T�g�C����[�A�V���ɂ��܂����c�w���B�����U�z���������N�͈ӗ~�N���Ȃ��B���H�́u�Ȃ����v�ٓ��B������Ƒ��������H�B�V���`�F�b�N�A�����ǂ݁A���Ɂu�쒹�v�̊C�m�����֘A���W���f���炵���B14:30�J���t�@�A16:00�Ƒ��ʒk�B19:30�A��E�[�H�A���ؕ��������H���B�H���Ɋւ��������͂܂����Ȃ��B20:30�A�Q�B�����v4071���B?
�k�R�L�ڌ�
5/28�i�j�~�J�I���@�̒��s�ǎ����ځA�O��?2:30�N���B�����̔@���B�k�R�Ȃǎ�B5:00�R�S�~��o�B�v�l�͌��ށA�˂���N�������������A�N���������Ȃ������炵���B6:40�o�X���n�a�@�B7:10-8:00�a���Ή��B8:40-12:25���ʕa�@�O���B���ҏ��Ȃ�1���ԑ҂����Ԃ���B13:00���ʃ��n�a�@�A���H�͓V���A���H�B�V���@����Ή��B19:00�A��E�[�H�p�X�^�A�قڊ��H�B20:30�A�Q�B�����v5135���B??�ˑR�̒��s�ǂɊׂ���(7) �{���H�c�]���^�N���u�̍u����̍u�t�S��(3)�@�n�v�j���O
�@����͎��ɂƂ��Ă̍Ō�̍u���ɂȂ邾�낤�ƍl���ē��e�I�ɏ\���ɐ��Ȃ��d�˂������Ă����B7�����o���オ�����ɂ͂������B
�@�u�����O��1�T�ԑO�̏������Ԃ͍ŏI�I�l�߂��s�������ł���A�ƂĂ��M�d�ł���B���̎����̏����Ŏ����玟�Ƙb���������e�������Ă���B
�@�������Ȃ���A���̑厖�Ȏ����ɁA5/18���ߌォ��ˑR�g�̓I�s���Ɋׂ����B�M���A�S�g�I��a���A�����ȊO�̌Ō`������؎t���Ȃ������H�~�s�U�ȂǂȂǂł���B�����̏Ǐ�͖�10���ԑ��������ƁA���X�ɉ��P�Ɍ��������B
�@���̊ԋƖ��Ƃ��Ă̒��ʃ��n�a�@�̊��҂̑Ή��͂قڌ����Ȃ��ł������A�T/20�̌��N�N���j�b�N�A�T/21�̒��ʕa�@���ȊO���A�T/24��Ȓ��ʕa�@�͋x�f�ɂ����Ă����������B�����X�^�b�t�ɂ͖��f�������B
�@����Ȍ��N��Ԃ̒��ł��u���������R�c�R�c�Ɛi�߁A�قږ����ł����ɂ܂ŗp�ӂł����B
�@�����A�u�������v�������Ȃ��A�N�V�f���g�Ɍ�����ꂽ�B
�@���̃p�\�R����Mac�ł���BMac�̏ꍇ�{�ݔ����t���̃v���W�F�N�^�[�Ƃ̑������������e�ł��Ȃ����Ƃ�����B�ŁA���炩���߃��n�[�T�����s�����B
�@5��24���̃��n�[�T���ł͓��e�Ɏ��s�����B
�@5��25���̃��n�[�T���ł͓��e�ɐ��������B����ŏ��������ƈ��S�����Ă����B
�@5��26���{�Ԃł͓��������ŗՂ̂ɓ��e�Ɏ��s�����B�����͕s���ł���B�{�݂̋Z�t�����낢��H�v���Ă��ꂽ���A���ʓI�Ƀv���W�F�N�^�[��p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B
�@���ۂ̍u���͗\�ߏ������Ă��������̔z�z�����𗘗p���i�߂����A���e�̓`�B�x��60-70%���x�ł������ƍl������B50�]���̒��O�̕��X�ɂƂ��Ă��h�������A���낤�ƍl����ꂽ�B�u���I�����ɂ͐\����Ȃ��ďo���ŏo�Ȏ҂̕��X�����������B
�@���ɂƂ��Ă��̗͓I�ɂ����e�I�ɂ��h�������ƂȂ����B
�@�Ō�̍u������̂悤�Ȍ`�ŏI�������̂͋ɂ߂Ďc�O�ł������B
�@
?5/27�i���j�܂�@���N�N���j�b�N�@?2:30�N���B�f�[�^�����B�����̓��L�NjL�����B6:40�o�X���n�a�@�A7:10-8:50�a���Ɩ�
9:00-11:50���N�N���j�b�N�h�b�N11���{���ʔ���13���B�����ɋx�f��ӁB12:00���n�a�@�A���H�A����w���̂��������ٓ��A���H�����B�����A�Ǐ��ȂǁB���@���ґΉ��B19:10�A��E�[�H�A20:30�A���B��5140���B??�ˑR�̒��s�ǂɊׂ���(6) �{���H�c�]���^�N���u�̍u����̍u�t�S��(2)
�@�H�c�]���^�N���u�̌��N�֘A�u����̍u�t���Ђ����邱�ƂɂȂ����B
�@�����������͍���̑̒��s���Ȃǂ͑S���\�z���ł��Ȃ������B�����A���ɂƂ��Ă͍Ō�̍u����ɂȂ邾�낤�ƍl���A���e�I�ɐ��Ȃ��d�ˏ\�����������邱�ƂƂ����B
�@�u������́u�g�������@��ɐH���l���悤�[�[�[�V�����ꌳ�C�ɉ߂����H�v�v�Ƃ����B
-----------------------------------------------------------------------
�@���̎��_���猩�čg�����͂������T�v�������g�̖��ł���A�����đ傫�Ȗ��Ƃ͍l���Ă��Ȃ��B
�@�m���ɐ����ߒ��ňٕ��̍�������������A���҂��o�����A����͐����ߒ��̉������Ń~�X�����������̂ōg�����̂��̂ɖ�肪�������킯�ł͂Ȃ������ł������B�����A���̓_�͍���̓��l�̎��̂�h�����߂ɏ\�ȒNjy���Ȃ���邱�Ƃ͓��R�ł���B
�@����ȏ�ɖ��Ȃ̂́A�䂪���ł͐H�i�ɈӖ��̂Ȃ��h�{�ʂ���̃����N�Â����s���A�����́A���ɍ���҂̌��N�u�������A����҂����L���Ȏ������s��Ɉ����o�����Ƃ�����̂ł���B����҂̎������s��Ɉ����o�����Ƃ͐��������f�ł��낤�B�������A����҂̔��R�Ƃ������N�s�����ɕt�������������͔[��������̂�����B
�@����ɍߐ[���̂́A���N�H�i�̐����̈ꕔ��Z�k���A���܂Ƃ��J�v�Z�������邱�Ƃ�F�߂����Ƃł���B����ɂ���Č��N�H�i�͂��������H�i�̈��E���A�f���炵���Ȋw�I���i�A��i�̔@���̃C���[�W�ɂȂ��Ă��܂����B���ꂪ��D���̓��{�l�̊����ɒ��ڑi�������邱�ƂɂȂ����B
�@���̂��߂ɃT�v�������g�s���1���~�K�͂̋���s����߂�悤�ɂȂ����B
�@�T�v�������g�Ƃ��Ă��邩�Ȃ����̃��x���̌��\�����̐ӔC�̂��ƂŌf���邱�Ƃ͋�����Ă��邪�A���̍L���̓��e�͂�������ǂ܂Ȃ��Ɩ�i�ƂقƂ�Nj�ʂł��Ȃ��悤�ɍI�݂ɍH�v����Ă���B
-------------------------------------------------------------------�@
�@����ɁA���{�̐H�����́A�������Ȃ���鐢�E�̐H�Ǝ���̒��ʼn䂪�����o�ϗ͂�w�i�ɉߏ�ɔ����������Ă��邱�ƁA�p�������H�����������ƁA�H�����������ُ�ɒႢ�܂܂ł��邱�ƂȂǂȂǂł���B
�@�Ⴆ�H�c�̕Гc�ɂŁA������O�̐H�����𑗂��Ă��Ă��A�m�炸�m�炸�̂����ɐ��E�̐H�Ǝ���Ɉ������e����^���Ă���Ƃ������Ƃ����o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�����I�ɓ��{�̐H�Ǝ���͌������Ȃ��Ă�������Ȃ��B���܂ł̍l�����͒ʗp���Ȃ��Ȃ邾�낤�B
�@���̂��Ƃ�����̍u���̒��ŋ����������������Ƃł���B
5/26�i���j�����@�H�c�]���^�u����@?1:30�N���A�{�ǂ݁A�����`�F�b�N�Ȃǃg���g���i�߂�B�u�������A���w���S�B11:00�Ɠ��ɓ��撆�ʃ��n�B13:00�����ی��Z���^�[�ɂču���A������܂��s�����f���͎��s�����B16:00�Ɠ��Ƌ��Ƀ��n�a�@�A������A18:40�A��B19:00�[�H�A�c���ٓ��Ȃ�Ƃ��H�ׂꂽ�B20:00�A�Q�B��870���B??�ˑR�̒��s�ǂɊׂ���(5) �{���H�c�]���^�N���u�̍u����̍u�t�S��(1)
�@����O�A�H�c�]���^�N���u�̉��莟��̍u���\��̈�t���炨�f��̘A�����������Ƃ̂��ƁB����ŁA�}篎����u�t���Ђ����邱�ƂɂȂ����B�����������͍���̑̒��s���͗\�z���ł��Ȃ������B
�@�u������́u�g�������@��ɐH���l���悤�[�[�[�V�����ꌳ�C�ɉ߂����H�v�v�Ƃ����B
�@�g���֘A�����͐����ߒ��ŋ��炭�ٕ��̍������������Ǝv���邪�����_�ł͏ڍׂ͂܂��������Ă͂��Ȃ��B���͂���Ȃ��ƈȏ�Ɂu���R�Ƃ������N�s���v����Ƃ�}�X�R�~�ɐ����A����ɕ֏悵���T�v�������g�ƊE���قږ������ԂŁA����C�܂܂ɐ��i���J���A�H�i�Ƃ��Ă̂��邩�Ȃ����̋@�\��\�����Ĕ̔����Ă��邱�Ƃɖ��������Ă����B
�@����͂��̓_�𒆐S�ɐ����A���{�������Ă��鐢�E�̐H�Ɗ�@�ɑ���ӔC�A�ߏ�ێ�̖��A��ʂ̐H���p���̖��A������39���̔w�i�ƁA�����I�ȐH�����ۂ̍l�����ɂ��G��邱�ƂƂ����B
�@���̂��߁A�����̕\���ɂ̓A�|��17�����B�e�����n���̑S�i�}���ؗp�����B
�@������Ƒs��ȃC���[�W�ł��������A���������Ă��鏫���Ɍ����Ă̐S�z���̈��\����������ł���B
�@�䂪���Œʏ�̐H���������Ă������h�{�f���s�����邱�Ƃ͂܂��l�����Ȃ��B
�@�����āA�Q���҂͍�������������Ƃ��\�z����邽�߂ɕ���Ƃ��āu�V�����ꌳ�C�ɉ߂����H�v�v�Ƃ��A�ؓ��ێ��̕��@�A���s�\�͈ێ��̕��@�A�F�m�ǔ��ǂ��ǂ�����Ēx�点�邩�A�ɂ��Ă����y���邱�ƂƂ����B
�@
5/25�i�y�j�܂�̂��������@�̒��s�ǔ�����?2:00�N���A���W�I�����l�R�Ή��A�ēx�Q���ށB�������������Ȃǃg���g���i�߂�B?�����̍u���S�z�B�l�X�Ə����i�߂�B16:00�ȍ~�͐g�̋x�߁B20:00�A�Q�B�r���o������A������1195�B??�k�R�L�ڌ�
5/24�i��) �̒��s�ǎ����ځ@���{�C�����n�k����41�N�@��ȊO���͋x�f�@�@?3:40�N���B�܂��̒��͂����肹���g���g���B5:00�S�~�o����܁B15:30���ʃ��n�a�@�A�a���Ή��B19:00�A��A�[�H�A21:00�A���A��1200�����B??�ˑR�̒��s�ǂɊׂ���(4) ������������g�Q�������A�̌�����
�ˑR�̒��s�ǂɊׂ���(4) ������������g�Q�������A�̌��������ʁB
(1)����������
�@���͖����I�T�����S�s�S�������Ă���B
�@�S���̋@�\�̂������f������@�Ƃ��ċ����������͏d�v�ł���B
�@�������A����̋����������ɂ͐S�g����Ȃ��ABNP�̒l�����ɂƂ��Ēʏ�̃��x���ł���A�S���R���̕ω��͔ے肳�ꂽ�B
(2)�̌����ʁ@���t�����w�I����
�@�����̌������ʂ����J����ȂǍD�݂ł͂Ȃ����A����͓��ʂł���B
�@����������25���ڒ��A�J���[�����������ȏ��16���ڂɈُ�l���ł��B
�@�X�̍��ڂ��Ƃ̉���͂��Ȃ����A
(1)���������Ă���ŗL�ُ̈�l�A���b�̂ɂ��̋@�\�ُ�A������⍂�l�Ȃǂ��܂܂�Ă���B
(2)�����Ė��T�Ԃɂ킽��Β������̐ێ�ŁA�S�̂ɐ����ʂ͕s�����ĒE����Ԃ��������A���t�͔Z�k���A�t���̋@�\���E����ԂɑΉ����Ă��邱�Ƃ������ꂽ�B
(3)���T�Ԃɂ킽��d�������܂܂Ȃ������̐ێ悾�����̂����A�̓��̉������s�������̂ł��낤�B�����i�g���E���̒l����l�ł������B�Β������Ɋ܂݂Ȃ��炱�ꂾ���ł͕s���ƍl���Ă����̂����A�d�������܂܂��X�|�[�c�h�����N�Ȃǂ͈��ދC������Ȃ������B
(4)���M���ׂ����ڂ�CRP�l�A���������ł���B�����2���ڂ͒ʏ�͍��l�ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��B
�@�M�����Ă����̂ʼn��炩�̕a���̂̐Z�����đ̓��ɏ����ǂ𒆐S�Ƃ��������ǂ����������̂ł��낤�B���ۍŏ���6���Ԃ͎��̈ݑ܂͈�̐H�i���t���Ȃ������B�֒ʂ͓�ւ���������������A����ȏǏ�������Ȃ������B
(5)���T�Ԃ̂̂��ɏ��X�ɏǏ�͌y�����H���ێ�ʂ����X�ɉ��P�����B�������A����̂��߂����܂��ɂ�������Ƃ����C���ɂȂ�Ȃ��ł���B
�@�ȏオ����̌o�߂̉ߒ��ł���B
5/23�i�j�����@�̒��s�ǘZ���ځA�H��X�^�b�t�Ƃ̊��k������?�@2:00�N���B�����̔@�������A�V���ȂǁB8:00�Ɠ��ɓ��惊�n�ɁB�V���`�F�b�N�A�a���Ή��B�Ǐ��B���@���ґΉ��B�Љ��p�ӁB19:15�A��A�����[�H�Ȃ�Ƃ��ێ�A20:30�A���A1350���B??�ˑR�̒��s�ǂɊׂ���(3) �@�̌����������@�[�H���ɏ��߂ČŌ`����ۂ���
�@�̒���6���ڂ��}���A�ɏ��ɉ��P�X���ɂ���悤���B
�@���������ԁA�Ɠ������ꂽ�Β��PL -1,5L�A�ʕ��̊ʋl�̃V���b�v�A�����̔��@�œ����ʕ��W���[�X�Ŗ��q�����B
�@�H�~�͂܂��قƂ�ǂȂ����撣��ΐH�ׂ�Ȃ����Ƃ��Ȃ��悤���B���ɖ{���̗[�H�́u����̂��v���p�ӂ���Ă���A�����ʂȂ�Ƃ��Ȃ�H�ׂ�ꂽ�B6���ڂɂ��ď��߂Č��ɂ����Ō`�̐H�i�ł���B�H�㕠�ɂ�f���C�ȂǂȂ��B
�@���M�@���M���͂܂������Ă��邪�A�S�̓I�Ɍy��������悤���B
�@����I���A�̓v���U�L�T���~�㗂�X���ɂ͏��������B���͕��p���ĊJ���Ă��邪���A�̍Ĕ��͂Ȃ��B
�@�Ɩ��Ƃ��Ē��ʃ��n�̓��@���Ҋ֘A�Ɩ��͌����邱�Ƃ��Ȃ��A���s���邱�Ƃ��ł����B�{���̕a���J���t�@�����X�A�Ǘጟ�����Ȃ�Ƃ����Ȃ����B
�@���ʃ��n�ȊO�̋Ɩ��Ƃ���5/20�i���j�́u���N�N���j�b�N�v�̐l�ԃh�b�N�̋Ɩ��A5/21�i�j�́u���ʕa�@�O���f�Áv�����������A��ǔ鏑����ʂ��ċx�f��\�����B��҂̗\�Ґ���10�����x�Ə��Ȃ����Ƃ��K�������B
�@�O�����x�f�ɂ������ƂŁA�C���������Ȃ�y�ɂȂ����B
�@�������������A�����̔\�͈ȏ�ɂ͖������邱�Ƃ͂Ȃ��A�Ɗ�����čl���邱�Ƃɂ����B
�@�����A����A�u���N�N���j�b�N�v�̐l�ԃh�b�N�̋Ɩ��A�u���ʕa�@�O���v�Ɋւ��Ă͑��̈�t�֑�f��������������f���������B
�@�����g�͂����̊����ǂŎ��Ԃ�������Ύ��R�ɉ��P����Ǝv���Ă������A���߂�ꂽ�ꍇ���q�ϓI�ɐ�����v����Ǝv���A����A���ʃ��n�O���ŋ��������g�Q�������A�̌����������B
�@
5/22�i���j�����@�̒��s�njܓ��ځA���Ȏ�f�L�����Z����??�@1:45�N���B���������ǂ݁A10:50�o�X���ʃ��n�ɁA�ނ�������B���M����B12:30�ɖ�i������A�G�s�y���A���H�ۂ炸�A��lj�A�V���`�F�b�N�A14:30�a�������J���t�@�B�]����c2���������Ă����B���@���ґΉ��B19:00�A��A20:30�A���A��1330���B??�k�R�L�ڌ�
5/21�i�j�����@�̒��s�ǎl���ځA�O���x�f��?1:30�N���B�����̂��Ƃ��B5:00�C�͂ӂ�i���ĉR�S�~��o�B8:20�Ɠ��ɓ��惊�n�a�@���B�O���x�f�ɂ��Ă�������B�ߌ�g�C���������X�^�b�t�ɕs����m��ꂽ�B���@���҂Ȃ�Ƃ��Ή��B���[�`���͂قƂ�o�����A�u���ǂ����݂ł����ł�B19:00�A��A�[�H�ۂ炸�A20:00�A���A���s�v��1778���B??�k�R�L�ڌ�?
5/20�i���j�܂�͂�@�̒��s�ǎO���ځA���N�N���j�b�N�x�f�@?1:45�N���B�r���̃R���g���[�������܂������Ȃ��B6:40Taxi�a�@�A7:00-8:30�a���Ɩ����Ȃ�Ƃ����Ȃ��B���N�N���j�b�N�h�b�N�͋}篋x�f��\�����ށB���n�a�@�ŐQ����N������O�_�O�_�߂����B19:00�A��A�[�H�ۂ炸�A�A���B���s��175���B
�ˑR�̒��s�ǂɊׂ���(2) ���̓���Ԃ̌o�ߊώ@����
�@�H�~��Ȃ��@�����ȊO�͎t���Ȃ��B�H�ׂ�C������Ȃ��B����Ƃĕ��ɂ�f���C�ȂǂȂ��B�Ɠ������ꂽ�Β��PL -1,5L�Ŗ��q�����B
�@���M�@���M�ł��邪�A�S�̓I�ɑ̔M������B��͂���̊����ǂ��H�H
�@���A�@����I���A���������B
�@�����S�[�ד��ɂ��S�����]�[�ǂ̗\�h�̂��߂Ɍ��t�Ìőj�~�܂̈�v���U�L�T�p���Ă���B���Ɍ����S������Ȃ��̂ł���̌��������Ɣ��f�A�������璆�~���Čo�߂݂��B
�@���̓���Ԃ̊ώ@�œ���s�����������̊����ǂƍl�����B���ʑ������Ă���ƍl�����Ȃ��̂ł��̂܂܌o�ߊώ@�Ƃ����B
�@����Ɩ��Ƃ��Ē��ʃ��n�̓��@���Ҋ֘A�͑傫�Ȍ����Ȃ��i�߂邱�Ƃ��ł����B
�@���ʃ��n�ȊO�̋Ɩ��Ƃ���5/20�i���j�{���͌��N�N���j�b�N�̋Ɩ����������������ɋx�f��\�����B
�@�x�f�ɂ������ƂŁA�C���������Ȃ�y�ɂȂ����B
�@�������������������邱�Ƃ͂Ȃ��A�ƍl�����B
?
5/19�i���j�܂菬�J���X����@�̒��s�Ǔ����??�@2:00�N���A���x�̑S�g���ӂ���B���A���Ă���B�v���U�L�T�̂�����??��������3���Ԓ��~�ɁB�f�[�^�����B�k�R�A�Ǐ��S���ł����B12:00NHK�j���[�X�A�̂ǎ����y���ށB���������߂����A�[�H�ێ悹���A21:00�A�Q�B��210���B??�k�R�L�ڌ�?
5/18�i�y�j�����@�Ɠ��]���^�����@�ߌ�}�ɑ̒��s�ǂɁ@�̒��s�Ǐ���??�@2:20�N���A�f�[�^�����B�k�R�A�ȂǁB���̊��Ɏx���A�L�E��2�{�s���B11:00�����ɂ����Ɠ��ɓ���a�@�A�����A�V���`�F�b�N�Ɠ��́A�Ǐ��O���A�f�[�^�����B�̒��s�ǁH�H���ׂ��B15:00�a���Ή��A�ߌ�}�ɑS�g�Ɉ�a���E�̒��s�ǂɁA��ނȂ�Taxi�A��A�`��ʁB18:30�[�H��炸���̂܂A�Q�B��3159���B??�ˑR�̒��s�ǂɊׂ���(1) �{���ߌォ��
�@�ߌ�a�@�Ŏc�������Ȃ��Ă������A16:00������S�g�Ɉ�a���������A�̒��s�ǂɊׂ����B
�@���ӊ����x�Ńo�X�ŋA�ꂻ���������̂ō`��ʂ��Ă�Taxi�ŋA��B�[�H�ۂ炸���̂܂A�Q�B
�@�Ǐ�Ƃ��āA�S�g�I�ɐg�̒u�������Ȃ����\�h�����A����ƂċǏ��I�ɂ݂Ȃǂ������a��̎�����͂����肹���A�����A�ċz��Ԃ͎����̗l�q���猩�Ăقڈ��肵�Ă���悤�ŋ~�}��f�����߂���̂ł͂Ȃ��悤���B
�@���̂悤�ȂƂ��͂܂����Âɂ��Ď����ŗ�ÂɌo�ߊώ@���邱�Ƃł���B
�@�Ƃ������Ƃʼn��������A�����l�������Ԃ̎��p���[�Ɏ����g���ς˂邱�ƂƂ����B
5/17�i���j�����@��ȊO���@�@?1:45�N���A���ށA�����`�F�b�N�B�k�R�B5:00�R���݂܂Ƃ߂����A�J�Œ�o�Ȃ��B7:35Taxi�w���ɁB8:12���܂��A��ȉwTaxi�B8:55��Ȓ��ʕa�@�O���B�A�H�V����5���x�꒷���Ï��X�o�R�A15:30-19:00���n�a�@�B�a���Ή��B19:00�A��[�H�A20:30�A�Q�B���s��4492���B??�k�R�L�ڌ�
5/16�i�j�����[�����痒�@?2:15�N���D�����������`�F�b�N�Ȃlj������Ɠ����B8:30�Ɠ��ɓ���B�V���`�F�b�N�A�Ǐ��ȂǁA�V���`�F�b�N�A���́B10:30�a���Ή��A14:00�Ƒ��ʒkALS��A�C�ǐ؊J�֘A�A���ӂ���A�Љ��L�ځB�u�������B�X���C�h���e�쐬�B17:00����}�ɗ���ԁB19:15�A��A���^�̃W���E���L��܂Ŕ��ł����B�[�H�A20:30�A�Q�B���s�v��2366���B??�k�R�L�ڌ�
5/15(���j����@?�@1:45�N���B�����E�{�ǂݑ��A�����̔@���B�u�������B8:30�Ɠ��ɓ���a�@�A�V���`�F�b�N�A���́B�����B11:00�a���Ή��A�V���@���҂���B�]�O�Ȃ��B�Ή��ɂ��Ȃ�̎��ԗv���B14:30�a���J���t�@�A�Ǘጟ���B19:15�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B���s��3159���B?
�k�R�L�ڌ�
?
5/14�i�j 79��ڊ��ӂ̓� �����@���ʕa�@�O���@?2:15�N���A�����`�F�b�N�A�Ǐ��B���Ԃ��ԈႦ6:00�R�S�~��o�B�������o�X�s�ł͂Ȃ��������Y������8:00�Ɠ����惊�n�ɁB8:45-12:50���ʕa�@�O���B�R����H�呍�����ȏЉ��쐬�A��͘A�g���ɂɔC�����B���n�Ɉړ��A���������A�����B�Ǐ��A�a���Ή��B���ӂ̓��ւ̎�X�̏j���̌��t�A�j���i�����B���Ȃ��̐����o�R19:30�A��A�[�H�A20:30�A���B�����v5217���B??�@79��ڊ��ӂ̓��@
�@���̃R������2001�N������J���Ă���B22�N���o�����B??�@�{���A79��ڂ̊��ӂ̓����}�����B
�@��N�����S�s�S�}�������Ō�������ԂɊׂ������A���o�Ǐ�͊Ԃ��������P���A���̂Ƃ���Ǐ�͑S���Ȃ��̒��������͖������A�����ōs��ꂽ�S�x�@�\�����ł͌��������ʂ�����A���̐l���͐V�����X�e�[�W���}�����B?�@��̎��Ԃ��ǂ߂Ȃ��ق��A�s���I�ɂ̓G�l���M�[�����27METTs�ȓ��ɗ}����\���\���l���ł���B�܂��A����ł��b�܂�Ă���ƌ����悤�B
�@�����̐l�̐������́A�Љ�s����Ő悪�ǂ߂Ȃ��Ƃ����X�g���X�ɂ��炳��Ă���B�����A���݂̂悤�ɁA�Z�p�̐i������E�o�ς̊������ς��Ă��鎞��́A���̎���ɂ����������ƁB�����A����2.7METs�ȓ��Ƃ���w���͋M�d�ł��邪�A���K������������悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B
?�@����I�ɂ͑S�̂Ƀ\���\�������Ă��邪�A���ȐӔC�̂��Ǝ����̌܊����d�����Ă�����Ɠ������L���Ĕ��≀�|�Ȃǂŗl�q�����Ă���B?�@���̂Ƃ���S���Ȃ�Ƃ��Ȃ��̂��������B
�@�����A����79���}�����B���ӂ̋C���������߂Ė{�e����邱�ƂƂ���B
�@
5/13�i��) �~�J�ߌォ�琰 ���N�N���j�b�N�@�Ɠ�����@�o�X�A��@?�@1:20�N���A�k�R�A�Ǐ��B6:40�o�X�a�@�A7:00�a���Ɩ��A9:00-1�O;30���N�N���j�b�N�h�b�N12���{��������Ȃ��B���ʕa�@�ɕ��s�B11:30�z��Ȏ�f�A��1���ԑ҂B12:00���n�ɁB�����A14:00���@���ґΉ��A�Ǐ��B18:20�o�X�A��D19:00�[�H�A20:00�A���B���s��5724���B??�䂪���̐H�Ǝ���i5�j���_�@�H���p�����i4�j�䂪�Ƃ̐H�Ɣp���[���̎���
�@���{�̐H�i���X�ʔN��523���g���̂����A���ƌn��279���g���ŁA�ƒ�n�����244���g���ŁA��ɐH�c���A������̐H�i�i���ڔp���j�A��̔��������Ȃǁi�ߏ菜���j�������v���B
�@�ƒ�n����o��H�i���X�̑傫���ɋ����Ă��܂��B
�@�H�ו���厖�ɂ���!!!����͉ƒ���ɂ�����c������A�H���}�i�[�̍ŏd�v�ۑ�ɂȂ��Ă���n�Y�A�E�E�E�Ǝ��͎v���Ă���������͕K�����������ł͂Ȃ��炵���B�H�ɂ����������͂Ȃ����A�t�@�~���X�Ȃǂő�ʂɒ������������e�[�u���̏�ɐH�U�炩���Ă���Ƒ��A��̎p�����鎖�͋H�ł͂Ȃ��B
�@�䂪�Ƃł́A���͗���������Ȃ��������l�͎O�l����B�O�l�̗����l�͊e�X��肽�������������Ă��ꂼ�ꂪ�H�ނ��C���[�W���ĐH�ނ��w������B�O�l�Ԃł͂��܂�H�ނ�Z�ʂ�����Ȃ��悤�ł���B�����������Ӗ��ł͔�����I�ł���B
�@���ʂƂ��ĐH�i�ɁA�①�ɂȂǂł͏ܖ���������}�����H�ނ��ǂ����Ă��c���Ă��܂��B���͐H�i�p���������������Ă��邱�Ƃ��Ƒ��B�͂킩���Ă��邩�玄�̖ڂ̑O�ɂ̓]���]���Ɗ�����̐H�ނ��o�Ă���B
�@���͂����̖����A���H��S��������B���܂łɂ����Ɍ����Ƃ���H���œ��̕a�C�ɂ͜늳�������Ƃ��Ȃ��B�[���Ȃ�2�|�R�������o�����̂̓U���B
�@���ɂ́A�������H���r�r��悤�ȕ��i������??����邱�Ƃ����邪�������߂�������Ȃ����Ƃ�����B���̎��͒�ɃZ�b�g�����R���|�X�g�ɓ���Ĕ엿������
�B
�@�H�ׂ��邱�Ƃ��Ȃ������H�ނ͔p������������Ȃ����A����炪�엿�Ƃ��Ċ��p�����Ƃ���ΐH�ނ̗L�����p�ƂȂ�B���̖ڂł͔p���ɂ͓�����Ȃ��B
�@�R���|�X�g�ŏn���������엿��2�N��ɂ͊��S�ɗǎ��Ȕ엿�ƂȂ莄�̃_���A�͔|�ɗp������B
�@
?
5/12�i���j�܂�E�[������~�J�@�@?1:40�N���A�{�ǂ݁A�����`�F�b�N�B�u�������A�k�R�L�ځA�����܊��{�A���B�V���`�F�b�N�A�̂ǎ����y���ށB15:00�Ɠ��ɓ��撆�ʃ��n�B���M���ҕ�������Ή��B�V�����́B�u�������B10:20�s�[�R�b�N�o�R�A��[�H�A20:30�A���B��1801���B??�䂪���̐H�Ǝ���i4�j���_�@�H���p�����i3�j
�@�p������}�����邱�Ƃ́A������ĕ�炵��L���ɂ��邱�Ƃɂ��Ȃ���B
�@�Ⴆ�A�����s���c�J��̏ꍇ�A�R���r�j��X�[�p�[�̔���c��H�i�ł��鎖�ƌn��ʔp������1�s�̂��ݏ����ɂ�55�~�̔�p���������Ă���B�ܘ_�A���Ǝ҂��R�X�g���S�������A���ƌn��ʂ��݂Ƃ��Đŋ����g���ď�������Ă���B
�@�X�[�p�[��R���r�j�Ȃǂł́A3����1���[���Ƃ������K���ɂ���đ�ʂ̐H�i���X���o�Ă���B
�@����������ܖ������܂ł̊��ԑS�̂�3����2�Ɂw�̔������x��݂��A�����ɒB����ƁA�܂�3����1�̊��Ԃ��c���Ă���̂ɒI����P������Ƃ����Öق̃��[��������Ƃ����B
�@����҂͒I�̉�����1���ł����t���̐V�������̂����߂��������A���̌��ʁA�܂��ܖ������ɂ͗]�T������̂ɔ̔��������߂������̂��A�ŋ����g���Ĕp������邱�ƂɂȂ�B
�@1/3���[���ɂ���ĐH�i���j�������B����͐H�����������Ⴍ��ʂ̐H����A���ɗ����Ă���䂪���ɂƂ��Ĝ��܂������Ƃł�����B����҂��Ȃ�ׂ��H�i���X���o���Ȃ��悤�A�������̍ۂɋC��t�������B
�@�u�Ƒ��\����H�K���ŏ���̃X�s�[�h�͂��ꂼ��قȂ�B���������Ă��g���ꂸ�Ɏ̂ĂĂ��܂��Ă͈Ӗ����Ȃ��B�܂��A��I�̉��ɒu���Ă���ܖ������̒������i�����������Ă��܂����������A�ܖ��������Z����O�̏��i��3���̂P���[���ɂ���Ĕp������邱�Ƃ������B
�@������������Ƃ��͖����̂Ȃ��͈͂ŐH�א��ʂ����ɂ߁A�ł��邾���I�̎�O�ɒu���ꂽ���i���甃���悤�ɂ��������́B
�@���͔p�����鏤�i�����炷���߂ɔ̔��������ߕt�������i�͒l�������Ă�����������l����ׂ����A�Ǝv���B
�@�X�[�p�[�Ȃǂł͓������̂��Ȃ��ٓ��ނȂǂ͗[���ɂȂ�Ƒ啝�Ȓl�������s���Ĕ̔�����Ă��邪�A����͐H�Ɣp�������炷�����łȂ����l������A�Ǝv���B
5/11�i�y�j�����@?1:45�N���B�������f�[�^�����A�{�ǂ݂ȂǁB�ߑO�y���O���A�_���A�̎��܂��B������B�Ǐ����S�A11:30�]���^�ɍs���Ɠ��ɓ���a�@�ɍs���B���M���Ґ����őΉ������B�ߌ�������A�u�������i�߂�B�����Ȉ���B19:00�A��A�[�H�A20:45�A�Q�B���s��2916���B
�䂪���̐H�Ǝ���i3�j���_�@�H���p�����i2�j
�@���{�̐H�i���X�ʔN��523���g���̂����A���ƌn��279���g���ŁA��ɋK�i�O�i�A�ԕi�A����c��A�H�c���ȂǁB�ƒ�n�����244���g���ŁA��ɐH�c���A������̐H�i�i���ڔp���j�A��̔��������Ȃǁi�ߏ菜���j�������v���B�ƒ�n����o��H�i���X�̑傫���ɋ����Ă��܂��B
�@���{�̐H�i���X��������v���̈�Ƃ��āA ���{�l�́u�ߓx�ȑN�x�u���v�A�u���i�u���v������A�Ƃ����Ă���B
�@���̔w�i�ɂ́A�����őS���H���Y���邱�ƂȂ��A�S�ċK�i�ɍ��������i���X�[�p�[�Ȃǂōw�����Ă���l���������Ƃ��������悤�B
�@�Ⴆ�A�x�����_�Ńv�����^�[�ł����Ă������ŐH�����Y�����݂��ꍇ�A�`�̈�����ɂ������������A����Ɉ����͂��ł���B�����������R�Ƃ̑Θb�������Ȃ�����҂͐H�����y�����邱�ƂɂȂ�͓̂��R�ł���B
�@�ƒ����H�X�ł́A�������̐H�i�̊������A�����ς݂̐H�c����ߏ菜���ȂǂŐH�i���̂Ă��Ă���B�����߂����H�i���g���ꂸ�ɕ��点�Ă��܂�����A���߂���H�c�����������肷��ƁA�H�i���X�̌����ɂȂ�B
���{�̐H�i���X�͂ǂ����ċN����̂�
�@���A�ł́ASDGs�i�����\�ȊJ���ڕW�j�̂Ȃ��ŁA2030�N�܂łɐ��E�S�̂̈�l������̐H�i�p������������ڕW���̑����ꂽ�B
�@�ƒ납�烍�X���o���ȗ��R�́A�u��̔�������ނ��߂��A�H�ׂ��镔���܂Ŏ̂ĂĂ��܂��w�ߏ菜���x�ƁA�ۊǂ��Ă������H�i�̏���������ܖ�������ȂǂŎ�����̂܂̂ĂĂ��܂��w���ڔp���x�A�����āw�H�c���x�B
�@�ƒ납��o��H�i���X�͈ĊO�����B�u���������Ȃ��v�������t�ɁA���ʂ����炷���Ƃ��l������
�@�u��������v�͕ٓ���A�H���ȂǓ����������Ȃ��H�i�ɕ\�������B�q����ł������͏��炷��K�v������B
�@�u�ܖ������v�͂��������H�ׂ�����Ԃ̖ڈ��B
�@�u�e��Ƃ́A�����������□�o�����Ȃǂ����ƂɎZ�o������������������Ɉ��S�W�����|���A��Ƃ�̂�������ݒ�����Ă���B�ۑ����@������ĕۊǂ��Ă���A�����������߂��Ă��H�ׂ邱�Ƃ��\�ł���B������A���͂قƂ�Ǐܖ������ȂNjC�ɂ��Ȃ��B������ȐӔC�͈̔͂ł��邪�B
?
5/10(���j�����@��Ȓ��ʕa�@�O���@�v���E�X�^�C������
2:00�N���B�R�S�~��o�B�Ɠ��̌Â��ߕ����܂�2�܁B7:40Taxi�w���A���܂��B���N�͔��ǂ�����H�H�����A�Ǐ��A�V���f�[�^���A�W:50��Ȓ��ʕa�@�O���A15:30�A�@�B�a���Ή��A�V�����́B�v���^�C�������̂��߂ɎԂȂ��A19:20Taxi�A��A�[�H�A20:30�A���B���s��5214���B
�䂪���̐H�Ǝ���i2�j���_�@�H���p�����
�@���E�̐H�����Ɠ��{�̈ʒu�t���ɂ���
�@���E�l����81��1900���l �O�N���7400���l�������B
�@���E�ł͂��ׂĂ̐l���H�ׂ�̂ɏ\���ȐH�������Y����Ă���B
�@�������Ȃ���A�ȉ��̔@���̖�������Ă���B
????????????????????????????????
��9�l��1�l���Q���Ԃɂ���A
��3�l��1�l�����炩�̉h�{�s�ǂɋꂵ��ł���B
�����E�ł́A�N�ԂŖ�920���l�̎q�ǂ����h�{�s�ǂŎ��S�B
���s�ύt�Ȏ����z���ƌo�ϓI�Ȋi���������Ŕ��W�r�㍑�ł͐H�Ƃ��\���ɒ��B�ł��Ȃ��B
���C��ϓ��ɂ�鐶�Y�̌����A�����A�o�ϊ�@�Ȃǂ̉e�����傫���B
����i���̓��H�͐��E�̐H�Ɗ�@�Ɋ�^�B
���u�ؐH��`�v�́u�_�n�̗L�����p�A����G�l���M�[�̎g�p���ŏ����ɂ���ȂNJ��ۑS�A���g���Ɋ�^����B
���{�̐H���p���̖��?�@�����̍������v�͖�3,300���g���ł��邪�A���͖�2,400���g�� �B�H����������39%�B
�@���̌��������ۓI�H�Ǝ���̒��A�䂪���̐H���A���ʂ��ʂ����ēK���Ȃ̂������Ƃ���B����ł͌o�ϓI�ɗA���\�Ȃ̂ł��낤���A��q�̐H���p���̂��Ƃ��l����Ύ��̐S���`�N�`�N�ƒɂށB
�@���{�̔p���H�i��523���g���Ɛ��肳��Ă���B����́A�Q��ɋꂵ�ސl�X�ւ̐��E�̐H���x���ʔN�Ԗ�440���g��(2021�N)��1.2�{�ɑ����A����͓r�㍑�ɏZ�ސl�X5,000���l����1�N���̐H�Ƃɑ����B���{���p�����Ă���H����1���ŁA���̎q�ǂ������̖����~����B
�@�܂��A�H�i���X��������l������̖����ʂɊ��Z����Ɩ�114g�ƂȂ�B���ꂾ���ł͎������Ȃ����A�u ���{�āJ�͖������ɂ��J���1�����̐H�i���X�v���J�o�Ă���ƕ\������Ɣ���ȗʂɂȂ邱�Ƃ�������B
?�@�[���ň��S�ȐH���Ɂu�N�ł��v�u�ǂ�ȂƂ��ɂ��v�u����E�w���ł���v���Ƃ��u�H�����S�ۏ�v�ƌĂԂ��A���̕ۏ�̂Ȃ��l�X�����E�ɐ��������݂��Ă���B��Ȏ����̗L�����p������ׂւ̔z������A���H�����炷���ƁA�H�i���X�����炷���Ƃ��J�K�v�B
5/�X�i�j�����@?2:20�N���B�����̔@���A�Ǐ��O���B�����A8:30�Ɠ��ƕa�@�B9:00�a���Ή��A�H�������ԂɃ^�C�������̂��Ƃ𑊒k�A�����̃i�b�g�̂��Ƃ͐����������B���Ė��m�̂��߂Ɏ����p�������̂��낤�B�{���i�߂Ă��炤���ƂɁB�V���`�F�b�N�A���͂��āB11:00�Ƒ��ʒk�A���H������A15:30��H�����R�C���a�B�i�J�C�`�R�[�q�[�B19:30�A��[�H�A20:30�A���B���s��6807���B??�䂪���̐H�Ǝ���i�P�j���_�@�h�{�ߏ�ێ�@
�@����͐��E�e������̐H�ނ��L���ŁA�ʏ�̐H�����𑗂��Ă���Εs������h�{�f�͂Ȃ��ƍl���Ă����B���������āA�T�v�������g�Ȃǂŕ⋋����K�v�͂Ȃ��ƍl����B
�@�������Ȃ���A�}�X�R�~��ʂ��ĘA�������������ꍑ���͔��Ό��N�s��������Ă���ƌ����ėǂ����낤�B�T�v�������g�ƊE�͍g�����̂��߂Ɏ�̉e���͎Ă��邪���ς�炸�����ł���B
�@�s�m���ȏ��͕s���̑~�����Ă�B
�@�䂪���̐H�Ǝ���̖��_��3�_�ɍi���Ē��Ղ��Ă݂�B���̂����A�T�v�������g�Ɋւ��Ă͋L�q�̒ʂ�ł���B���͉h�{�ߏ�ێ�ƐH�Ɣp�����ł���B
�@���{�̓��A�a���Ґ��́A�����K���ƎЉ���̕ω��ɔ����ċ}���ɑ������Ă���B
�@���A�a�͕��u�܂��͕s�\���Ȏ��Â̂��Ƃł͖Ԗ��ǁE�t�ǁE�_�o��Q�Ȃǂ̍����ǂ������N�����A���������蓧�͎��Â��K�v�ƂȂ邱�Ƃ�����B
�@�@�����̌���������1�ʂ͗Γ���i20.9���j�ł��邪�A2�ʂ͓��A�a�Ԗ��ǁi19���j�ł���B
�@2022�N���ɂ����� ���͊��ґ�����34.7���l�B�V�K���͓������҂�14.330�l�A�ő��͓��A�a��38.7%���߂Ă���B
�@����ɁA���A�a�͔]�����A�������S�����Ȃǂ̐S���ǎ����̔��ǁE�i�W�𑣐i����B
�@�����̍����ǂ͊��҂̐����̎������ቺ������݂̂łȂ��A��Ìo�ϓI�ɂ��傫�ȕ��S���Љ�ɋ����Ă���A������Љ�̍���ɂ��������đ��傷��ƍl������B?
�@���퍂�l�A���E�^�Ɛf�f���ꂽ���͂������A���A�a�ɂȂ�O���瑁���ɐ����K�����P�Ɏ��g�ނ��Ƃ��d�v�ł���B
5/8(��) �I���~�J�@���Ȏ�f�@�a���J���t�@?�@1:30�N���B�����̂��Ƃ��B�Ǐ��A�k�R�B8:30�Ɠ��ƕa�@�B9:00�a���Ή��A10:00-11:30���Ȏ�f�A���[�U�[�͒ɂ��B�����A�V���`�F�b�N�A���́A�����B14:30�a���J���t�@�A���@���ҏ��u�A�V���@���c���B19:20�ʒ����X�o�R�A��A�[�H�A20:30�A�Q�A��2836���B
�g���T�v�������g�̌��N��Q�i5�j�g�̂ɗǂ��H�i�͂Ȃ�?�@����͈�ʘ_�����A�u���N�ɂȂ��Ȃ�v�Ƃ����ɃT�v���₻�̑��̐H�i�Ɏ���o���O�Ɂu�{���ɕK�v�Ȃ̂��v�A�u�����ɍ����Ă���̂��v�A�u���\�͖{�����v�Ɨ����~�܂�ԓx���A����������҂��g�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�@
�@���{�l�͂Ȃ�ł���ɗ���A��Ђ��ɂȂ�X��������B���̕�����������ӔC�̈�[�͈�t�ɂ�����B
�@����ɗւ��������̂�2001�N�̐H�i�̏��܉��A�J�v�Z���`�����ւ������ƁB���̌`��͈��i�ގ��̈�ۂ�^�����\��M�������邱�ƂƂȂ����B
�@����2015�N�A����҂̒~�����s��ɌĂэ��݁A�o�ς������������邽�߂ɋ@�\���\���H�i���x���n�݂��ꂽ�B�@�\���\���H�i�Ƃ͎��Ǝ҂̐ӔC�ɂ����āA�Ȋw�I�����Ɋ�Â����@�\����\�������H�i�B�̔��O�Ɉ��S���y�ы@�\���̍����Ȃǂ�����Ғ������֓͂��o�����́B����Ғ������̋��������̂ł͂Ȃ��B���݁A6000�i�ڂ���������Ă���Ƃ����B
�@����Љ�Ƃ������Ƃ������Ă��A�u���N�ɂ����v�A�u���炾�ɂ����v�Ƃ����G�ꍞ�݂̐H�i�A�T�v�������g�A���N�p��O�b�Y�Ȃǂ��Ɏ������l�͑�����A���N�r�W�l�X���g�債�Ă���B
�@ �T�v�������g�����ł��A���̎s���5000���~���ƌ����A�u����A�X�ɐ�������2���~�ɒB����s��v�Ƃ���������������B
�@�T�v�������g�͈ꌩ�Ȋw�I�Ɍ������ꂽ���i�Ɍ�����B���̖ڂ��猩�Č����ĉȊw�I�Ƃ͂����Ȃ����������͉Ȋw�I�B���̂悤�ȁu�j�Z�Ȋw�v�͈ꌩ���ۈȏ�Ɂu�Ȋw�I�v�Ɍ����邽�ߊȒP�ɐM�����Ă��܂��B�w�i�ɂ́u�m�ɂ������肽���v�u�M�������v�Ƃ����C�������w�i�ɂ��邩�炾�낤���B
�@�u���N�v�ɊS�����͈̂������Ƃł͂Ȃ����A�u���̔��m���A��w�����������߂�̂�����m���v�u�������F�߂��̂�������S�Ō��ʂ͔��Q�v�ƐM�p�������āu�悢���q����v�ɂȂ�Ȃ��悤�A��ɒ��ӂ͕K�v���B
�@��ʓI�ɂ̓T�v���͐H�i����������댯�͂Ȃ��ƍl�����Ă���B�g�̂Ɉ����H�i�͂��邪100�����S�ȐH�i�͂Ȃ��B
�@�܂��A�P��̐H�i���邢�͐����Ŗ��炩�Ɍ��N�Ɋ�^����̂͂Ȃ��B
�@���̂����L���ł���Ƃ������Ƃ���͖ڂ����炵�āA�y���āA���\�s���̃T�v�������g�Ƃ��ɗ����Č��N�ƒ���������肤����Љ�B����ȏ́A���̂���e���ɂ��Ă��邱�ƂɂȂ����Ă���悤�Ɏv����B
5/7�i�j�I���~�J�@���ʕa�@�O���@?2:30�N���B�^���f�[�^�����B������PDF���A�k�R�A�����A�Ǐ��A�f�[�^�����ȂǂȂǁB6:40�o�X�a�@�A7:10-8:15�a���Ή��A8:45-13:15���ʕa�@�O�������A15:00�a���A16:00�Ƒ��ʒk�ق��B�V���`�F�b�N�A���́B19:15�A��A�[�H�A20:30�A���B��6571���B??�����S�s�S�}������?�ɂċً}���@(3) ����1�N�Ԃ̑̒��͂ǂ��ł�������
�@����1�N�Ԃ́A�o�߂ɂ���Ă͈�u�ɐS�@�\����~���鎖�Ԃ��\���l�����邽�߂ɐS���ɉߕ��ׂ�^���Ȃ��悤�ɂ��낻��Ɛ��������B
�@���̌��ʁA����I�ɂ͑S�̂ɐS����������悤�Ȋ��o�͂��邪�A�ً}���Ԃ��M�킹��l�ȏǏ����Ȃ��A���Ƃ������o�߂������B
�@�����A�ȉ��̂悤�ȏ�Ԃ�����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�����Ö�̂������p�A
�����₷��
�����C�������Ȃ���
�������ɋx�݂����Ȃ�
����Ԃ̐������Ԃ����т�
���������P���Ă��邽�߂ɕp��ɔ����Ƃ�
�����s���}���Ƒ����̑��ꊴ
���K�i�͂�������4F���x�܂Ń\���\���Ɠo��̂����x
���␅�����݂����Ȃ�
�������̌����ɔ��������̋ؗ͌��ނ����o�A����̓}�Y�C����
���ȂǂȂǁE�E�E�E�E�E�E�E
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�@���o�Ǐo����A�g�̂����߂Ă���Ɗ�����đ��킸�ɏ]���B���ꂪ�B�ꖳ��̕��@���낤�Ǝv���B
�@����ɂ��Ă����G�͍~��ʂ����Ȃ��ėǂ������B
�@����Ȃ��Ƃ��l���Ȃ��獡�������ɖ�̕c��A�����B�����A�g�̂ւ̕��ׂ��l�����Ԃ̊Ԋu���L������Ƃ̌y����}���Ă���B
5/�U�i���j ����@�U�x���@?0:30�N���A�l�R�Ή��A�{�ǂ݁A�k�R�L�ڂق��B�����A9:00���ɎU���A���Ԃ̃X�g�[�u�d�����B�X�g�[�u�㕔�̎����ݔp���A�R�ލĐ��B�̂ǎ����A�V���`�F�b�N�B14:00�Ɠ��ƕa�@�B���@���҂͗��������Ă���B�e����́A�f�[�^�����A�摜�f�[�^�A���y�f�[�^�Ȃǐ����B�V�����́B18:30�V�[�K���o�R�A��A20:30�A�Q�A��5938���B??�����S�s�S�}������?�ɂċً}���@����1�N(2) �@���炩�ɍs���������Ȃ��� ?�@�ꎞ�͌������ċz��Łu����ׂ������������ȁH�H�v�Ƃ��v�����B�~�}���̊Ō�t�̋L�^�ł��u�b���ċz��ŏd�NJ������Ԃ͗ǂ��Ȃ��E�E�E�v���̋L�ڂ����邪�A�K���A�_�f�z����͌o�߂͎v�����ȏ�ɗǍD�ł������B
�@�~�}�������͈ӎ����N�O�Ƃ��A�����������킩�炩�������A���U�o�[�t���t�F�C�X�}�X�N�Ŗ���10���b�g���̎_�f�𓊗^����A���A�ܓ��^������͔�r�I���₩�Ɉӎ���Ԃ��ċz������P�Ɍ��������B
�@��ʓI�����̌��ʁA�����͋}���S�s�S�ɔ����ċz�s�S�Ƃ������Ƃŏz��Ȃ̓��@�ƂȂ����B�����1�T�Ԃőމ@�ł����B
�@���͑S���^���������̌��ɐ��܂ꂽ�E�E�ƍ���������������B�������A�������ʂ͌����ĊÂ��͂Ȃ������B
�@���o�Ǐ猩��ƌo�߂͗ǍD�ŁA�������ʂɂ͓��i�傫�Ȉُ�͏o�Ȃ����낤�ƊÂ��l���Ă������A�S���̏�Ԃ͂��̗\�z�͗����A���ʂ�������邽�тɍ���̐l���̉߂���������������������邱�ƂɂȂ����B
�@�l���Ă݂�Ή����Ȃ��S���ł��̂悤�ȏd��Ȏ��Ԃ��}�ɋN����͂����Ȃ��̂��B
�@�����́u���̐��ɖ߂��Ă����v�Ƃ̊�т̊��o�ł��������A���̌�ɍs��ꂽ�S�@�\�̏A�f�[�^�͎v�������ǂ��Ȃ����ʂŁA��X�̐����ɞg���͂߂Ȃ���Ȃ�Ȃ����x�ł������B
?????????????????????????????????
�@���S�������g�����G�S���o��48%�B(�O��2022.�R��62%)�B
�@��CT�ɂ�銥�������e�F���O���~����70%??�̋���@�@
�@��CPX�iCardiopulmonary Exercise Training�j�S�x�@�\�����B�S�x�̑��͂Ƃ���2.7METs�ȓ��͈̔͂ł̍s�����������A�Ƃ������������́B���퐶���̉^���ʂƂ��ẮA���s�Ȃ��2-3Km/���̑��x��20-60���A1��1-2��A3-5��/�T���x���x���B
?------------------------------------------------------------------
�@��L�̌��ʂ͑މ@��̎����̏��猩�āA����������悤�ȋC�������B�����͌����Ă�����͐S���ɉߕ��ׂ�^���Ȃ��悤�ɂ��낻��Ɛ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����B�o�߂ɂ���Ă͈�u�ɐS�@�\���ڍ����}���̃R�[�X���\���l������Ƃ������ƂŁu������Ƃ����������肵���v�Ƃ����̂������ł����������ꂽ�B
�@����ł�����1�N��2.7METs�ȓ��̍s�����ӎ����Ȃ�����_���A���͔|���A�L�E���E�i�X�E�g�}�g�����n���A�o�X�ʋ�1���������邱�ƂȂ����Ƃ������Ɍo�߂������B
�@�����A�^���s���̊��͐@�������ؗ͂̐��������o����B
5/5�i��) �������g�@�q���̓��@�x�ԍՂ� �������@��N�S�s�S�ɂċً}���@?3:00�N���B�l�R�Ή��A�{�ǂ݁A�����ǂ݁A�k�R�L�ڂق��B9:00���ɍ���w���̕c��A����B���Ԋu�����܂ł���L�߂ɂƂ�B��J����������A�A����������B15:00�������AN���̓����o�[�����ւ��A�V�R���}�X�a���Ȃǂ������炵���B�Â����y�֘A�̘^����ς�B�}�^�`�b�`�w���u���b�N�i�[No8�ȂǁB19:00�[�H�A20;30�A�Q�B��3263���B��N�S�s�S�ɂċً}���@�B???�����S�s�S�}������?�ɂċً}���@����1�N(1) ����1�N������??�@����15�N�قǑO����S���ɖ�������Ă����B��{�͐S�[�ד��ł���B�@
�@����Ɉ��N���A���S���r�u���b�N����������B�S�[�ד����ŏ��͎��ܐ����锭�쐫�S�[�ד��ł����������X�Ɏ������̖����S�[�ד��ɂȂ����B���炭�S���ɉ���܂��͐����K���ɂ��ލs���ω����ɏ��ɐ����Ă����̂ł��낤�B
�@��N3���̏z��Ȃ̒���`�F�b�N�͌o�ߊώ@�̃��x���łł��������A�����Ƃ��ẮA�l���̏I���̈�̉\���Ƃ��ċ��S�ǖ��͐S�؍[��?? ���邢�͟T�����S�s�S??�̊m�����������낤�Ɗo�債�Ă����B
�@�]���āA��N5��5���ɐ����������S�s�S�}�������Ǝv����a��͓����͋��������u���ɗ�����!!!!�v�Ƒz����ł��������B������A�����Ƃ��Ă͐v���ɔ��f�o�������A�~�}�ԂłȂ��^�N�V�[�ł��ǂ����낤�ƕa�@�Ɍ��������̂ł��邪�A���ۂɂ͎��ԓI�ɂ͌����������B�������C�����������O�ł������B
�@���͂��Ɛ�����79�ɂȂ�B�v�����낢��a�C���������A�Ǝv���B
�@������@��ɁA���̎��a�������ڂ����������ƐU��Ԃ��Ă݂��B
�@�����̎�Ȏ��a���͈ȉ��̔@���ł���B�@
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
��1945�N�o���B�V�������͋���Ő펞��������炽�Ȃ����낤�Ǝv���Ă����B�@
��1951�N����}���ݒ����ō��𓊂�����B���R�̃C�^�R�Ɋ�|�������B
��1953�N���w��5�N�Ӓ����͔^ᇂŎ�p�B�@
��2007�N8��1���N���z���d����(�o�A���I�؊J)+�N���e����p(���������؊J)�B�@
��2007�N�����甭�쐫�S�[�ד����o�A2012�N�����S�[�ד��B
��2008�N�x����^���@�펿���x���ł��������H
��2011�N�Γ���E������̐f�f�@�_�Ꭱ�ÊJ�n�B
��2012�N10�����ǁ@���w���j�A�ŕ��o����p�B�@�@
��2012�N11���S�����]�ǐ� ���ǂȂ����P�B
��2017�N5�N�قǂ̌o�߂ʼnE�������ɑl�a�w���j�A���傠��A��p�B
��2022�N10���咰�e������o���B�������I�~���p�B�A���ɂ͎��炸�B
��2023�N5���T�����S�s�S�ŋً}���@�i����j
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�@
5/4�i�y�j�����@�݂ǂ�̓��x���@�c3��w��?�P:40�N���B�����ڂ��z���A䉖�Ñ������p�A�Ǐ��B10:00�y�߂ɊO�d���A��������ځA�����A���̂�o�������A�}�t�����B15:00�Ɠ��ɓ���a�@�A�a���Ή��B18:30�A��A19�F00�[�H�A20:00�A�Q�A�����v3818�B??�g���T�v�������g�̌��N��Q�i4�j�@�\���\���H�i(�T�v��)�@����ی��p�H�i(�g�N�z)?�@���ǂ������ɓ����H�i�͈�ʐH�i�ƈ��i�ɕ��ނ����B
�@���́A���N��Q��������悤�Ȋ댯�ȐH�i�Ɋւ���������A�ڍׂ܂Ŗ@�Ō��߂�K�v�͂Ȃ��A�Ǝv���Ă����B�������A���݂͖�i�܂����̍H�Ɛ��i���H�i��T�v�������g�Ƃ��đ�ʂɗ��ʂ��鎞��A�������K������K�v���o�Ă����B
�@�H�i�ƌ��N�H�i�A���N��Q�̗��j��ǂ��Ă݂�B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
1971�N�@���i�܂����̌��N�H�i�������H��敪���ʒm���ꂽ�B
1991�N ??�g�N�z���x�n��
2001�N�@�H�i�̏��܉��A�J�v�Z���`�����ցB
2002�N�@�l�A���Ȃǂ̒������_�C�G�b�g�H�i�Ō��N��Q796
�@�@�@�l�A���S4�l�����B
2003�N�@�ᒃ�Ŋ̏�Q
�@�@�@�@ ?�A�}���V�o�@�ǐ��C�ǎx��8�l�A���S1�l
2013�N�@�č����T�v����2�����}���̉��B
2015�N�@�@�\���\���H�i���x�n�݁B
2018�N�@�v�G�����A�E�~���t�B�J�ɂ�錒�N��Q
�@�@�@�@�@�^�C�ɕ��z����}���Ȃ̐A���B�A�����G�X�g���Q�����܂܂��B�^�C�ł�
�@�@�@�@�u��Ԃ�v�̓���������Ƃ��ꗘ�p����Ă���B
�@�@�@�@�@���{�ł́A�o�X�g�A�b�v��X�^�C���A�b�v���̔��e��ړI�Ƃ������N�H�i
�@�@�@�@�@�Ɋ܂܂�Ă��邱�Ƃ�����B�����s����s���o���ȂǕw�l�Ȍn��
�@�@�@�@�@���N��Q���������B
2024�N�@�g������
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
�@�H�i�͉��\�̔@���Ɉ�ʐH�i�ƌ��N�ւ̊֗^��搂����@�\�I�H�i�ɕ�������B
�@�\�����\���������H�i
������ی��p�H�i(�g�N�z)
�@���N�̈ێ����i�ɖ𗧂��Ƃ��Ȋw�I�����Ɋ�Â��ĔF�߂��u�R���X�e���[���̋z����}����v�Ȃǂ̕\����������Ă���H�i�B�\�����e����S���ɂ��Ă͍����R�����s���A�H�i���Ƃɏ���Ғ����������B
���h�{�@�\�H�i
�@�K�v�ȉh�{����(�r�^�~���A�~�l�����Ȃ�)���s���������ȏꍇ�A���̕⋋�E�⊮�̂��߂ɗ��p�ł���H�i�B���łɉȊw�I�������m�F���ꂽ�h�{���������̊� ���ʊ܂ސH�i�ł���A���ɓ͏o�Ȃǂ����Ȃ��Ă��A������߂��\���ɂ���ċ@�\����\���ł���B
���@�\���\���H�i
�@���Ǝ҂̐ӔC�ɂ����āA�Ȋw�I�����Ɋ�Â����@�\����\�������H�i�B�̔��O�Ɉ��S���y�ы@�\���̍����Ɋւ�����Ȃǂ�����Ғ������֓͂��o��ꂽ���́B����Ғ������̌ʂ̋��������̂ł͂Ȃ��B���݁A6000�i�ڂ���������Ă���Ƃ����B
-------------------------------------------------------------------
�@
5/3�i���j���@�L�O���@����
�@2:20�N���B���������A�k�R�B5:00�ƒ�S�~��o�����̂݁B�Ǐ��A10:00�O����ƁA�{�^���̎x�����A�X�̎}�����ȂǁB13:00���ɂ��ĎO�Y����Ɉ��A�B�Ɠ��ƂƂ��ɕa�@�A�a���Ή��A����}�ς̊��҉��P�X���B�f�Ï����쐬�A�V���`�F�b�N�A���͎��������B�Ǐ��B�Ɠ��͈�U�Ƃɖ߂����Ƃ����B�w�b�h�t�H���̊���~�ߖh�~�o���h�C���A18:15�o�X�A��A19:00�k�C�����Y�W�ٓ̕��B20:30�A�Q�A�����v7800���B
�g���T�v�������g�̌��N��Q�i3�j���ѐ���̑Ή��̖��_
�@���̐��͕s���E�B���Ȃǂɖ����Ă���B
�@���ǂ��͌܊�����g���Đg�̂̈��S���������Ă���B
�@�������A����Љ�ł͊e����Ƃ��ɖ�O���͓��ꗝ���ł��Ȃ����x���̍��x�̋Z�p�A�m������g����Ă���A�l�I�댯����̔��f�͂͂قƂ�ǗL���ɓ����Ȃ���ԂŁA�u�S�đ��l�C���ɂ�����Ȃ��v�ɋ߂��̂�����ł���B
�@�����Ȃ�ƐM�p�݂̂����f�̏d�v�Ȉ��q�ƂȂ�B���ɁA�H�i�֘A�A��܂Ɋւ��Ă͊�Ƃ̐ӔC������邱�ƂɂȂ�B
�@�g�����͖{�N1��15���u�g���R���X�e�w���v �v�̗��p�҂�f�@�����厡�ォ�猒�N��Q�ɂ��Ă̖₢���킹�������Ė�蔭�o�����B�����A�\���Ƃ��ċ�����ꂽ�V�g���j���͖����o�A3��16���ʂ̖��m�̕��������o����A3��21������Ғ��֕A3��22���ی����ɓ͏o�����ƂŌ��J�Ȕc�����c�������B���̊Ԏ��҂����炩�ɂȂ����B�ɂ�������炸����������܂�2������v���Ă���B���̊Ԃ��̔��͌p������Ă����B
�@���ѐ���̑Ή������Ă���Ƒg�D�ɋ��ʂ��������ӎv����̉ߒ����F�߂���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ̈�ۂ����B
�@��͊�ƂƂ��Ă̎��т̐ςݏd�˂Ɠ���ꂽ�Љ�I�M�p�ɍ��������u�ߐM�v�A�s�s���ȏ��́u�y���v�Ɓu�B���v�A��ڂ͉�Бg�D�́u�����́v�ɂ��g�D�������X���ƏW�c���c�̐��ɂ��X�l�̐ӔC�̞B�����Ȃǂł���B
�@�l�́u�����́v�������قǁ@���Ђɏ]�������̐S���������B�W�c�ɂ�����K�͂̌`���ɂ������ẮA�X�l�͕K�����������v���Ă��Ȃ��̂ɁA�u��Ђ̂��߂Ɂv�A�u�����̗������邽�߂Ɂv�̐S�����������Ђ⑽���h�̈ӌ��ɓ������Ă��܂��B���̏�Ԃł͂��͂�W�c�Ƃ��Ă̗����I���f�͂ł��Ȃ��Ȃ�B���ѐ���̋L�҉���ɂ�����V�h�����h���̑Ή������Ă���Ƃ��̂悤�Ɋ�������Ȃ��B
�@���͂Ȃ��Ȃ��q�g���A��Ƃ�g�D��M�p�ł��Ȃ��B���P���Ɛ������Ƃɕ�����Ƃ���Ȃ�Ζ��炩�Ɍ�҂̗���ɗ��B
�@���̗���Ō���A���̎Љ�͕s���E�B���Ȃǂɖ����Ă���ƍl���Ă��ĐS���炩�ł͂Ȃ��B�������Ȃ���A�ʏ�ɗ��ʂ��Ă��镨�i�Ȃǂɂ��Ă͓���I�ɂ͋^���������悤���Ȃ��B���h�ȃu�����h���m�����Ă����ƂȂǂɂ��ẮA������I��ɂȂ�Ȃ���^���悤���Ȃ��A�Ƃ����̂������ł���B�����͌����Ă��A�S�Ăɂ��Ă�100%�M���Ă���̂ł͂Ȃ��B����������������Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����B
�@����ł����ǂ��͌܊�����g���Đg�̂̈��S���������Ă���B�u�悭������Ȃ����������������v�A�Ɗ����邱�Ƃ����_�ł���B
�@�������A�V��������ΘA���̔@���ɓ��ꍼ�\�̔�Q�����Ă���B�u�ǂ��l���Ă������ł��Ȃ��l�ȉ������ȗU���ɏ���Ă��܂��̂��H�H�v����قǃq�g�͎��Ȕ��f�͂������Ă��܂����̂��H�H
�@���ՂɃT�v���ɗ���S�����܊��͂̌��オ�w�i�ɂȂ��Ă���̂łȂ����A�Ǝv���B
5/2�i�j�@�������@�H��X�^�b�t���K�@���ҋ}��?�@1:55�N���B���z�ǂ݁A�k�R�Ȃǃg���g���i�߂�B8:30�Ɠ��ɓ��惊�n�ɁB8���I���A�V���`�F�b�N�A�]���^�����o�[�o�^�֘A�ŌߑO�I���B�����A�a���Ή��A15:00�H��X�^�b�t���K�@16:30���ҋ}�ϑΉ��A���������̂�??�A�V�����́A�����ȂǁB19:30�A��[�H�A20;30�A���B����4301���B�_�ЂƂȂ������A�����猩����i�F�͑f���炵���B??�g���T�v�������g�̌��N��Q�i2�j�u�g���R���X�e�w���t�K �v�Ƃ�
�@���ѐ����������g�����܂ށu�g���R���X�e�w���v �v�ȂǁA�@�\���\���H�i�Ƃ��č��ɓ͂��o��3���i��ێ悵������҂́A����1541�l����Ë@�ւ���f���A����270�l�����@�A5�l�����S�����B
(���ѐ����HP����ؗp)
?�@�ɂ��Ə��ѐ���́u�g?�R���X�e�w���v�v�́A�u���ʃR���X�e���[���v�������邩������Ȃ��@�\���\���H�i�Ƃ���2021�N4���ɔ�������A24�N2�����܂łɖ�110���܂��̔����ꂽ�B
�@�g�����̂͐H�i�̒��F���̈�Ƃ��Ē����̔̔����т����邪�A���܂Ō��N��Q�͂̕Ȃ������B���N��Q�͍ŋ߂̐��i�Ɍ�����B������A�g�����̂����Ȃ̂ł͂Ȃ��A�u�g?�R���X�e�w���v�v�̐����ߒ��ɍŋ߂Ȃ�炩�̖�肪���������̂ƍl����ꂽ�B
�@�����z�肳�ꂽ�t��Q�̂���ٕ��V�g���j���͌��o���ꂸ�A�v�x�����_���������Ă����Ƃ���邪�A�ǂ̂悤�ȉߒ��ō��������̂��A�v�x�����_���t��Q�̌����ł��邩�͂܂��������Ă��Ȃ��B
�@���ѐ����HP�ɂ��ƁA�u�g?�R���X�e�w���v�v��10����1000�~���x�Ŕ�������Ă���B
�@���i�̐��������Ƃ��Ĉȉ����L�ڂ���Ă���B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
���{�i�́A���Ǝ҂̐ӔC�ɂ����ē���̕ی��̖ړI�����҂ł���|��\��������̂Ƃ��āA����Ғ������ɓ͏o���ꂽ���̂ł��B�������A����ی��p�H�i�ƈقȂ�A����Ғ������ɂ��ʐR���������̂ł͂���܂���B
���{�i�́A���a�̐f�f�A���ÁA�\�h��ړI�Ƃ������̂ł͂���܂���B
���{�i�́A���a�ɜ늳���Ă���ҁA�����N�ҁA�D�Y�w�i�D�P���v�悵�Ă���҂��܂ށj�A�y�ю����w��ΏۂɊJ�����ꂽ�H�i�ł͂���܂���B
�����a�ɜ늳���Ă���ꍇ�͈�t�ɁA���i�p���Ă���ꍇ�͈�t�A��t�ɑ��k���Ă��������B
���̒��Ɉٕς��������ۂ́A���₩�ɐێ�𒆎~���A��t�ɑ��k���Ă��������B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
�@�����Ƃ𒆐S�Ɋ�Ƃ��֘A����s����B���͌��Љ�ł͕p��ɐ����Ă���B�������Ȃ���A����̍g���T�v�������g���͒��ڗ��p�҂̌��N�Ɋւ�����̂ŁA���҂��o�Ă��邱�Ƃ��珬�ѐ���̑Ή��̐�����A���������̌����A��Q�҂̋~�ς��}����Ă���B
???
5/1�i���j������⊦���@�a���J���t�@�@?2:30�N���B�l�R�Ή��A�f�[�^�����A���z�ǂ݁A�k�R�Ȃǃg���g���i�߂�B8:30�Ɠ�����a�@�B11;30�V���`�F�b�N�A���B�X�^�C���Ŕ����A10:30�a���A�ߌ�����B�a���J���t�@+���ґΉ��B�V�����́A���������A�H�����A�l�����A19:20�Ђ�̂⏑�X�o�R�ŋA��[�H�A21:00�A�Q�B ���s�v2881���B ��N���������ځB??�g���T�v�������g�̌��N��Q�i1�j���N�̂��߃T�v���@�{���ɕK�v��
�@�g�������������܂ރT�v�������g�������Ƃ݂��錒�N��Q�����炩�ɂȂ����B??�@1������2���ɂ����āA��t���琻�����������ЂɁu�t�����������N�����������܂܂�Ă���̂ł͂Ȃ����v�Ȃǂ̏Ɖ�������������Ƃ����o�̂��������������B
�@����̎��ۂ́u�T�v���͐H�i�ł���A����p������������S�v�ƍl���ė��p���Ă����l�����ɂ͏Ռ��������̂ł͂Ȃ����B??�@�u�����ƌ��N�ɂȂ肽���v�A�u���܂ł��Ⴍ�������v�Ƃ����l�Ԃ̗~�]�ɂ͌��肪�Ȃ��B������āA����҂̑I�����𑝂₷���߂�2015�N�u�@�\���\���H�i�v�Ƃ������x���ł����B����̃T�v�������g������ɊY������B??�@���̐��x�̊NJ��͍����̌��N���������J�Ȃł͂Ȃ��A����Ғ��ł���B����Ғ��͏���Ҕ�Q�̖��R�h�~�E�g��h�~��}�邽�߁A���k���̕��͂⏤�i�e�X�g���s���A���̌��ʂ�����҂ւ̌[���E���ӊ��N�Ɋ��p���A�s���@�ւ⎖�ƎҒc�̓��ɗv�]�E�����Ă��傱�Ƃ��|�Ƃ��Ă���B
�@�u�@�\���\���H�i�v�̐����ɂ́u���S���̊m�ۂ�O��Ƃ��A�Ȋw�I�����Ɋ�Â����@�\�����A���Ǝ҂̐ӔC�ɂ����ĕ\���o������́v�ƂȂ��Ă���B�v����ɁA���Ǝ҂̏������Ƃɏ��i��I������̂́A�����܂Łu����ҁv�ŁA���ɂ͐ӔC���Ȃ��A�Ƃ������ƁB??�@�������A������u�H�i�����v�ł����Ă��T�v�������g�Ȃǂ͎��R�E�ɖ����قǔZ�k����Ă��邩��l�̂ɂ��܂��܂ȉe���������炵����B����Ȃ��ƂɁu���ʂ����܂���҂ł��Ȃ����i�v���u���҂ł������Ȑ��i�v�̕������ӂ��K�v���B??�@�����g�A�f�@���ł���炵�����҂Ɂu�����T�v�������g������ł܂����H�H�v�A�Ǝ��₷��B
�@�����ȏオ�uyes�v�Ɠ�����B
�@���́u�����ł����v�Ɣ�������āu�ł��A���ꂪ���Ȃ��ɖ{���Ɍ��ʂ����邩�ǂ����́A�ۏł��܂����v�Ƃ�������B
�@����Ɗ��҂́u�ł��A������Ă����Ǝ��i���������搶���w�����������߂Ă����ł��v�Ȃǂƌ����B�u�����炠�₵���Ȃ̂��v�Ǝ��͂����B
�@�f�@���ł̉�b�A���u�������������v�Ȃ̂������҂����͐^���ł���B��10�N�ɂ��킽���Č��N�Ǘ������Ă��鎄�����V����TV�ɓo�ꂷ�錠�Ў҂̕��̐M�p�x�������͖̂ʔ������ۂł���B
�@�ŋߓV�C�\��̒��Łu��C���s����v�ŋ}�ɍ~�J����t���芦�������K�ꂽ�肷��B
�@�u��C���s����v�Ƃ������Ƃ͗₽���d����C���g������C����ɂ���s����ȏ�Ԃ������炵���B
�@���V�C�̗\��m�́u���ɋ������C�����ꍞ��ł��Ă��܂��v�Ƃ����\�����g���B
�@���z�Œn�ʂ����߂��Ēg������C�ł�������A�s����ɂȂ��B�v����ɋ�̍����Ƃ���ɗ₽����C������Ⴂ�Ƃ���ɒg������C������Ƃ��̂��Ƃ������킯�ˁB���������Ƃ��ɂ͋}�ɉJ�_�����B���₷�����ł�����B
�搶 ������������Œ��ւ����ɂ�����A�̂��₦��ł��傤�B
����͊��̐��������C�ɕς��Ƃ��ɁA�M��D������ȂB �t�ɐ����C�����ɕς��Ƃ��́A�M���o���Ď�������߂���Ă킯�B
�̂̂����ȂB
������A��C�͂܂����y���܂܂ŁA�����Ƃ����Ə�ɐi�ށB���̂Ƃ��ɐ����C�����H��X�ɕς���āA���ꂪ�_�ɂȂ�B��������āA����������ɂ��Ȃ�u�ϗ��_�v���ł���̂ˁB����ő�J���~������A�����������肷��B
4/30�i�j�������~�J�@���ʕa�@�O���@�@?1:30�N���B�{�ǂ݁A�f�[�^�����������Ɠ����B5:00�R�S�~3�ܒ�o�B6:40�o�X���n�a�@�B7:10-8:10�a���Ɩ��A�A�x�O�̒����K�v�B8:35-12:00���ʕa�@���ȊO���A���Ґ�11�l�Ə��Ȃ��B�ߌナ�n�A������A14:30�f�Ï����쐬�A�Ǐ����̑��B�V�����́A�����A19:00�A��A�[�H�B21:00�A�Q�B��5005���B??���{�̊�@�Ƒ�2023(7) �l����(4)�@�}�X�R�~�͐l�������ǂ����Ă�����(2)?�@(2)2015�N6��8���̋L���u�l�����ւ̊�@�����f�v�ł́A�r�㐴�q���勳���́u�o�Y��q��Ăɒj�����Q��������Ȃǂ̈ӌ���������̓I�ȏ���Ⳃ������������ŁA�u�Љ�S�̂ł̋c�_�Ȃ��ɂ́A�O�ɐi�߂Ȃ��v�Ɛ������B�ۑ�����ւ̋�̘_�����҂���ȂǁA�݂₷���d�g�݂�Љ�̍��ӂ𐮂��邱�Ƃ��d�v���v�Ƃ̎w�E��`�����B??(3)�������Ȃ���A 8��1���̎А��u�l���������l������ /�w�L�����x�݂߂�_�@�Ɂv�ɂ����āA����܂ł̎А��̘_�|��]���������悤�ȕω���������B�_�|���Ԃ�Ă���B?�@�܂��A�u���������u�l������=���x�Ȃ̂��v�Ɩ₢�������B���̏�ŁA�����ېV��͕x�������A���͌o�ϐ����Ƃ����ڕW�Ɍ����āA�u�������d�˂Ă�����J�▵�����ՊE�_�ɒB�������ʂ��A�l�������ƂȂ��Č���Ă���̂ł�??�v�A�u�l�������́A�{���ɖL���ōK������������Љ�������Ă����`�����X�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���v�Ƃ̖^���҂̌������Љ�Ă���B�Y���Ă���B??�@(4)���̈���ł́A2015�N8��8������̘A�ځu�l�������{/�ߖ�������̌x���v�ɂ����ẮA�u�l�������Љ�v���ǂ̂悤�Șc�݂ނ���g�߂Ȏ���ł킩��₷�����A�l�������ɑ����@���������ɑi���Ă���B??�@�L�����̎����ɔ������l�ς̑��l���ƌ����Ȃ�܂������A�l��������O�����ɁA�����b�g�ʂ��瑨�����ӌ��ւ̕ω��͓��˂Ȋ������ւ����Ȃ��B?�@�m���ɒ������ł݂�A�l�����͐V���ȋύt�Ɍ������ω��̎n�܂肾���A����ׂ��l�������ɑ����@�����Â��A�傫�Ȉ�a�����o�����B??�@(5)�܂��A8��9���u�����f�ȁF�낤�� �w�傫�ȉƑ��̂��߁x�v�ɂ����āA���q����O�̉Ƒ����ƓI�Ș_���ɂȂ��肩�˂Ȃ��A�Ƃ̒����炵���x�����������Ă��邪�A�j�Ƒ����Ƃ����s�t�I�ȗ���͋����A����͎������I�A�S�z���߂����낤�B??�@(6)8��13���̋L���ł́u�o�Y�j�ޗv����菜��/��Ƃ̒n���ړ]�x�����v�ɂ����āA���c����E�����������A�w�����������x �w�q�ǂ������������x�Ɓu�肤��҂������v�Ƃ��A�u�o�Y��j�ގЉ�I�A�o�ϓI�ȗv������菜���Ȃ��Ă͂����Ȃ��v�Ǝw�E����B??�@���{�̒����ɂ��A�v�w�����z�Ƃ���q�ǂ��̐���2.4�l�B�Ƃ��낪�A���ۂ̍��v����o�����͖�1.4�l�B���҂̃M���b�v�͏o��@��̌�����o�ϓI���R�A�d����̐���A�ۈ珊�̕s���Ȃǎ�X�̗v�����琶���Ă���\���������A�Ǝw�E���Ă���B??�@�����V�����ނɐl�������Ɋւ���L�������������A�[�����������B?�@�o�Y�\�̏����̐l���������܂Ō�������A�q��Ċ����x�����Ă����ʂ͂���Ă���B�����̍ł���Ș_�_�͕K���ɔ����Ă���悤���B??�@���͎Ⴂ�����𑝂₷���Ƃɂ���������
4/29�i���j���a�̓��@�����@�����U�z����ڂق��@
2:30�N���A�l�R�Ή��A�摜�E�����E�V���`�F�b�N�B��t�^�C���A10:00��d���A�����U�z����ځA�����A��̌��ꕔ�B15:00�Ɠ��ɓ���a�@�A�����ɋ��a�B�V�����́A�����B�a���Ɩ��A19:20�A��[�H�B20:30�A�Q�B���s�v3787���B?
�G�߂̘b��2024(5)�@�{�^���J��
�@�����A��̃{�^������ĂɁA�Ƃ����Ă��l�������ł��邪�A�J�Ԃ����B
�@�����������͕s�v�A�����ȉԂ̎咣��f���Ɏ���悤�B
(�����ȑ�ւ̔Z���s���N�@���^�Ȕ��@�Ԃ͎�O�Ɖ��̓������F�����Ⴄ)
4/28�i���j�����@�����U�z����ځ@���Ҏ���
2:40�N���A�l�R�Ή��A�摜�E�����E�V���`�F�b�N�B�^���f�[�^�I�����p�X�ɓ����B�����ȂǁB10:00��d���A�����U�z����ځA�����̈ꕔ�B�l�R�g�C���R���̒i�{�[�������A���A�X�`���[�������B11:00���@���Ҏ��S�ANHK�̂ǎ����y���ށA�V���f�[�^�`�F�b�N�B�{�^���͊J�Ԓ��O�B�`�F���R���T�[�g�ɍs���Ɠ��ɓ���A����E��H�����̌�ɋ��a�A�k���ɂĕa�@�A���S�f�f���L�q�A������B�V�����́A�����B19:20�A��[�H�B20:30���X�ɏA�Q�B���s�v4787���B??���{�̐l�����2024(19) �����Љ�ۏ�E�l����茤�������v(3)
�@���ԑg�D�u�l���헪��c�v���A�S��744�����̂ɂ��āu�����I�ɏ��ł̉\��������v�Ɣ��\�����B
�@����A�u���ʼn\�������́v�Ƃ��ꂽ�̂́A�u�o�Y�̒��S����ƂȂ�20~39�̏�����2020�N����50�N�ɂ�����50%�ȏ㌸��Ɨ\�z����鎩���́v �B
�@�������A�g�D�͂����̎����̂ɋ��������������ł͂Ȃ��A�����ł��l������h�����߂̕�����u���Ăق����A�Ƃ����Ӑ}�ł��������̂��낤�B���J�̈���͎����̂ł͂Ȃ����ł���B
�@�������Ȃ���A�����̎����̂͂��̂悤�ɑ����Ă͂��Ȃ��B�u�n���̓w�͂ɐ������������v�A�u���łƂ������t�͕s�K�v�E�E�E�̕]�������Ȃ��Ȃ��B���̐^�ӂ͂ǂ��ɂ���̂���_���ė~�����B
�@����ȏ�ɁA�䂪���̍����Ɋ֗^���Ă���l�����ɂ��̕��̈Ӗ�����������Ăق����B
�@�ǂ̎����̂�����܂ł��l���̎��R���◬�o����u���Ă����킯�ł͂Ȃ��A���̎肱�̎��ł��Ă����͂����B
�@�e�����̂̎{������f�B�A�͂�����Љ�܂Ƃ߂č��ɓ˂����Ăق����B
�@�l�����Ɏ��~�߂�������Ȃ��̂͂Ȃ����B
�@���͂��̌����Ƃ��đA�����x���Ɏ����Ă��ĎႢ�q�{���s�����Ă��邩����ʂ��o�Ȃ��Ƃ������ƂƂƁA�����ւ̈�ɏW������E������Ȃ����߁A�ƍl����B
�@�n���n������Ƃ͉��������̂��낤���B
�@���������`�͈ӊO�ɍ������B
�@���Ɉ�ʏ����͎����̔\�͂����������߂ɁA�����邽�߂Ɍ���ł͌o�ϊ����������ȓ����Ȃǂ̑�s�s���ɍs������Ȃ��B�������ł��Ȃ�����ł���B�n�����珗�������Ȃ��Ȃ����ł���B
�@���{���哱���������̈ړ]�͕������̋��s�ړ]�݂̂ł������B����������Ēn���Ɏ�v�ȋ@�\���ڂ��Ȃ���Βn���̌o�ς͊��������Ȃ��B�o�ς̂Ȃ��Ƃ���Ɏ�҂͏Z�߂Ȃ��B
�@�l�b�g�����y���A�X�ɃR���i�Ђ������āu�S���ǂ��ł��d�����ł���v�Ƃ������͋C���ł������̂悤�Ɏv��ꂽ���A��Ћ@�\��n���Ɉڂ���ƂȂǂ͂���قǑ����Ȃ��B
�@��w�������ɏW�܂��Ă���B
�@��s�@�\�ړ]�̘b�����̊Ԃɂ�����Ȃ��Ȃ����B
�@�����䂭�^����w�����Ă���̂́A���̎����̂����̐ӔC�Ȃ̂��B�����͓̂����҂ł�����A���ǂ߂Ȃ�����̔�Q�҂ł�����B
�@�����^���Ɂu�����̂̏��Łv��h���������S�Ɉێ����悤�ƍl����Ȃ�A�܂��́u������ɏW���v�̎d�g�݂̉����ɍēx�{�C�Ŏ��g�ނׂ����B
4/27(�y�j�����@�_���A���A���@�����z�[�X����
2:20�N���A�l�R�Ή��A�_���A���A����������N�̓_�������B�ѐ�a�@����̐L�k�������z�[�X�����A�ȊO�Ƃ��܂��s�����B14:00�Ɠ��ƕa�@�A�Љ��L�q�B�V���`�F�b�N�A���́A����3���E�f�[�^�����A�����B�Ǐ��O���A���y�ӏ܁A�����ȂǁB18:30�A��A�[�H�B20:30�A�Q�B���s�v3488���B�v���̃^�C�������A��p�i�b�g�łȂ����߂ɂł����B
���{�̐l�����2024(18) �����Љ�ۏ�E�l����茤�������������v���\(2)
�@���ԗL���҂ł���u�l���헪��c�v�́A�S�s�撬����4���ɂ�����744�����̂�������A�l�����ɂ���čs���̉^�c������ɂȂ�A�u���ł���\��������v�Ƃ���������\�����B
�@������������10�N�O�ɂ������ꂽ�B����́u���ʼn\�������́v�̐����O������152�������������B�������̗��R�́A�n��̖��_�����������̂ł͂Ȃ��A�J���ړI�̊O���l�������邽�߂ŁA���{�l�l���̉��P�ɂ��Ȃ��Ƃ������́B
�@�u���ʼn\���v�̍����Ƃ��āA�o�Y�̒��S����Ƃ����20-39�̏����l��������A50���ȏ㌸�邱�Ƃ������Ă���B�P���ɍl����A���{�̐l��1���l���ێ�����̂Ɍ���1.2�قǂ̏o������2.0�ȏ�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����A���ꂪ4.0�قǂɂȂ�Ȃ���Έێ��ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�����s�\�A��͎q�{�̗A�������Ȃ��B
�@���{�̑��l���͋ߔN�A60���l�O��̃y�[�X�Ō����Ă���B�������ꌧ�����ł���̂ɓ������قǂ̑��x�ł���B2100�N�ɂ�6277���l�ɔ�������Ƃ����B
�@����29���̍������40���ɒB���A�o�ς͏k�����A�H�Ɛ��Y�͗������݁A����h�ЂȂǍs���@�\�̈ێ�������Ȃ�B����A����ȏ�ɍ����ێ����邽�߂̖h�q�͂���ێ��ł��Ȃ��Ȃ�B
�@������o�Y�́A�l�̈ӎv�����d�����ׂ����B�����A�o�ϓI����ȂǂŌ�����o�Y�̊�]�� ����Ȃ��̂ł���A�ꕔ�̃P�[�X�ɂ��Ă͎x�����菜�����Ƃɂ͂Ȃ邾�낤���A���ۂ̌����͌o�ς̖��ɂ���̂ł͂Ȃ��B
�@�l�ԂƂ��ẮA�����Ƃ��ď���R�����Ȃ��Ă��邱�Ƃ�����ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����B
�@���݁A���{�͏��q����ɕK���ł��邪�A�����猩�Ċu�C�~�y�̊��͐@���Ȃ��B���{���͂����Ă���̂́A���q����ɒ��ډe������{��ł͂Ȃ��ԐړI���ʂ����Ȃ��q��Ďx����ł���B
�@���܂ł̏��q�����܂�ɂ��t�قł��������߂ɏo�����͂����܂ŗ�������ł������A����Ȑ���ł͂����炨�������Ă��o�����͌��サ�Ȃ��B
4/26(���j�����@��ȊO���@�v���E�X�_�� �^�C�������ł���
�Q:10�N���A�l�R�Ή�����B�v���E�X�_�����[�����M�A5:30�R�S�~�A���Ȃ������̂݁B7:40Taxi�w�ɁA8:11���܂��B8:45�O���B���G���敾�A3F�a���s���Ɩʒk�A�Ō�t�̋Ζ�����B15:30���艮�o�R���n�B�V���`�F�b�N�o�����B���@�Ή��B�A�x�O�ŕ��G�B19:20�A��[�H�A20:39�A�Q�B�����v5268���B
���{�̐l�����2024(17) �����Љ�ۏ�E�l����茤�������������v���\
�@���ԑg�D�u�l���헪��c�v��4��24���A744�����̂��u���ʼn\�������́v�Ǝw�E����V���������\�����B
�@10�N�O�ɑS��896�����̂����ł���\��������ƌx����炵�A���{�́u�n���n���v����̋N�_�ƂȂ����u���c���|�[�g�v�ƌ����鐄�v�̌��\����10�N�o�߂����B�������̂ł���B
(2014�N�o�ł��ꂽ���v���|�[�g�@�{�͔��ꂽ���Љ�̉��ςɂ͂��܂�𗧂��Ă��Ȃ�)
�@10�N�O�͌��t����l�������A�܂�ʼn߈悪��������悤�Ȍ�����L���������A�l���������ɊS�����鎄���猩�āA����10�N�Ԃł����Ӗ��ŕς�������Ƃ͂قƂ�ǂȂ��l�Ɏv����B
�@����͓̕Ǝ��̃f�[�^�����͂Ȃ��A���̋@�ւ̐��v�����̂܂ܓ��Ă͂߂��B
�@�u�n�����Łv�Ƃ̓C���p�N�g���傫�����t�ł���B�u���Łv�Ƃ������t���g�������Ƃɂ��ᔻ������B�n��ɏZ�����Z��ł���Ԃ͋�̓I�Ɂu���Łv����̂ł͂Ȃ��A�l�������̂��߂Ɏ����̉^�c�������s���Ȃ��Ȃ�\�����w�������́B��̓I�u���Łv�ł͂Ȃ��@�\�I���ł��w���B���Ɂu���w�Z�p�Z�E�����v�u���h�̍L�扻�v�u���[�J�����̔p���v�u�o�X�H���̔p�~�v�u�H�c���̓�Ì��̓����v�ȂǂȂǂ͐l�������̂��߂Ɏ����̉^�c�������s���Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���̏؍��ł���B
�@10�N�O�Ɂu���Łv�̌��t�ɕ��������������̂́A�u�n���n���v�̉��Ŋe�n�̏��������}�����ŕ`���悤�����A�l�����̊ɘa�Ɍ����������ɋ��o�ꂽ�B���ʓI�ɐl�����h�~���l�����ɓK�������Љ�̖͍������߂�͂����A��҂̒D�������Ƃ������`���ڗ����A�l������Ƃ��Ă͂ނ����ނ����P�[�X���ڗ��B
�@���̔��f�̗B��̘_���́A�n���20-39�̏��������������ȉ��ɂȂ�Ƃ̐��v���B���R�ł���B���̔��f�͐������B�@�l������̗B��̕��@�́u�����̂����A��X�����q�{�̗A���v�����Ȃ��B
�@�e�s�������Ƃ̐l�����v�͌덷�������B���ہA2014�N���̑��c���|�[�g���`���������Ƃ��̌�10�N�̌����ɘ�������������͏��Ȃ��Ȃ��B����Ȃ��Ƃ͓��R�̂��Ƃł���B����ȍ��ׂȂ��Ƃ���ɂ���K�v�͂Ȃ��B
�@���c���|�[�g�̌����Ƃ��鍪���͎��͐������Ǝv���B
4/25�i�j�܂�~�J�@���N�N���j�b�N���ʔ���@�×{�a���^�c�ɂ��Č���?2:30�N���B�l�R�Ή��ق��B�摜���W�����B8:30�Ɠ��ɓ��撆�ʃ��n�B�V���`�F�b�N�A�����ǂ݁A11:00�a���B�ߌ������A�a���B�Ǐ��O���B�V���d�q���A����2���A14;00���҉Ƒ��ʒk�A���N�N���j�b�N���ʔ���A���@���ґΉ��B15:00����̗×{�a���ɂ���U��t��������A18:00�a���w���Ɩʒk�A6������Ō���2��㐧�ɂȂ�Ƃ����B���ʉ��ł��낢��ω�����B19:10�A��A�[�H�B21:00�A�Q�A���s5193���B??�G�߂̘b��2024(4)�@�������ł�C�������R�����Ȃ����@
�@�������͎����Ǝ��̋G�߂̕ς��ڂ̉ԂƂ��đ����Ă���B
�@�ȒP�ɂ����Ώ��Ⴉ�������ꂽ�����t�̖K��ł���A�����U���������肩��Ă��n�܂�B
�@�H�c�n���C�ۑ��4��10���H�c�s�̍��̊J�Ԃ\�B���N���7�������A����܂łōł������������N���6���x���B
�@���̒ʋΘH�e�̍����قږ��J�A�ʂ邽�тɋG�ߊ��𖡂���Ă��邪�A���k���Œʋ��Q�̏�Ԃ����Ă��������������͔����B���̓o�X�Ƃ��Ɠ��ɓ��悵�Ēʋ��Ă��č����Q�̏�Ԃ��߂��Ŋώ@���邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��Ȃ����B
�@�֗��Ȃ��́A���ɃX�s�[�h�������ړ���i�͎��ӂ̎��ۂɑ��銴��a������傫�Ȍ����̈�ł���B���������Ӗ��ł͂����������]�Ԉړ����g�߂Ȏ��R�𖡂키�̂ɂ��傤�Ǘǂ����x�����A�Ǝv���B
�@4��14���̏T�A�H�c�s����H�����̍������J���}�����l�ł���B
�@�H�c�ɗ���1973�N(���a48)���͎s���̍��̖��J��4�����{���ł������l�Ɏv���B�������N���̎����͂ƂĂ��g�����A�J�ԁE���J�������đ����Ȃ��Ă��Ă���B���������̒i�K�Ńp���p���ƎU��n�߂Ă���B���ɉĂ�����B
�@��H�����͗�N�ł�����Ղ肪�s����B���䂪�o����ύ���Ȃǂ��J�Â����B���N��4��14���̓��j�͌ߌ�ɏo�����̂ł��邪�A�ʋΘH�͐�H�����Ɍ������l�����A���邢�͋A��l�����œ�����Ă����B
�@���̑̒������ЂƂł��Ɖ���ύ��ł��邩�킩��Ȃ����A���J�Ԃɔ����C�����̍��g�����r���[�ł���B����ɐl���݂��X�g���X�B
�@15�����j���͌��N�N���j�b�N�̃h�b�N�S�����ł��������A�N�x���߂Ƃ������Ƃ������Ď�f�҂͂����̔������x��11�����ɂ͋Ɩ����I�������B
�@��H�����͌��N�N���j�b�N����k����15�����炢�̋����Ȃ̂ōs���Ă݂��B���j�Ƃ������ƂŐl�o�͏��Ȃ������B�܂������Ȃ�L����ӂɂ����ƕ��ԉ�����������x�ł������B����̏�Ԃ͌��Ȃ��������A�������̖��J�̒n��ɑ��X�Ɉړ������̂�������Ȃ��B
�@��H�����̍��͈�ʓI�ɉԐ����R�����B�V�̂��߂Ȃ̂��낤���H
(4��15�����j�ߑO�̐�H�����L��̗l�q)
�@���͉Ă��D���ł��邪�A�ߔN�̉Ă͉��K��ʂ�z���ċ�ɂȂقǂ̖ҏ��A�����ł���B���N�͂ǂ��Ȃ�̂��A�s�������A�y���ݔ����ł���B
�@
�@
4/24�i���j�܂�̂��J ���̎���?2:20�N���A�����`�F�b�N���B�f�[�^�֘A�����i�ށB8:30�Ɠ��ɓ���a�@�ɁB9:00�a���Ή��A10:00-12:10 ���̎��ÁA13:00��lj�c�B�����A14:30�J���t�@�{EC�A���ҏ��u�A�Ƒ��ʒk�A�V���`�F�b�N�{���́A�Ǐ��B19:20�A��[�H�A20:30�A�Q�B���s�v3542���B??�G�߂̘b��2024(4)�@�ڂ�a�܂��鏬���ȉԂ���?�@�Ԃ̋G�߂ł���B�����ɉ��|��Ƃ��n�܂����B
�@�Ȃ�ʼnԂ͔������̂��H�N�̂��߂ɔ������̂��H�H���̋^��͂܂������Ă��Ȃ��B
�@�������������ł�ԁX�͎�X���ǂ̎肪�����Ă���B����q�g�������B���y���ނ��߂Ɉ�w�Y��ɉ��ǂ���Ă���B
�@�������Ȃ���A�l�Ԃ������O�ɂ������̉Ԃ̌��킪�������͂��B���̎���ɂ��Ԃ͔������炢���ł��낤�B�Ԃ̖ړI�͎ɂ���B��Ƃ�S���Ă���鏬���������ɖڗ��悤�Ɏ�X�̎p�ō炢���ł��낤���A����قǔ��������ʂȎp�ł���K�v�͂������̂��낤���H�H�ʂ����Ĕނ�ɂ͔��I�ӎ��͂������̂��낤���H�H�^��ł���B
�@���ꂩ��X�E���͗ɖG���A��X�̉ԁX�����X�ƊJ�Ԃ���B
�@�����G�߂ɂȂ������A����ȏ�ɖG���オ��u���������������v�Ƃ̑Θb���n�܂�B
�@�����͓V�C�������悤���B���G���̑������n�߂悤���B
(���̏����ȉԂ����@���O�Ȃǎv���o���Ȃ����ڂ�a�܂��Ă����)
4/23�i�j�����@���ʕa�@�O���@�@?2:00�N���B�{�ǂ݁A�f�[�^�����������Ɠ����B5:00�R�S�~��o�B6:40�o�X���n�a�@�B7:10-8:10�a���Ɩ��A8:35-12:40���ʕa�@���ȊO���A���Ґ�9�l�Ə��Ȃ��B98�Γ��@���ꂠ��B�ߌナ�n�A������A�f�Ï����쐬�A�Ǐ����̑��B�V�����́A�����A19:00�Ђ�̂⏑�X�o�R�A��A�[�H�B21:00�A�Q�B��6103���B??�G�߂̘b��2024(3)�@�ؘ@�@��
�@4�������{�ɂȂ�ƉԂ̋G�߂ł���B�����ɉ��|��Ƃ��n�܂����B
�@�킪�Ƃ̖X�A���Ԃ́A2�T�O�ɍ炢���u���߁v��Ƃ��āA��T�ɂȂ��Ă���u���v�A�u�ցv�A�u�����v�A�u���Ԃ��v�A�u����v�A�u���X�J���v�Ȃǂ̉Ԃ����J�ƂȂ�A��C�ɉ₩�ɂȂ����B
�@�Ȃ�ʼnԂ̓L���C�ɍ炭�̂��H�N�̂��߂ɁH�H���̋^��͂܂������Ă��Ȃ��B
�@�䂪�Ƃōŏ��ɍ炢�Ėڗ��Ԃ͐Ⴊ�����Ԃł��J�Ԃ���^���ԂȒցA���Ŕ����ؘ@�ł���B
�@���N�͗��҂Ƃ��ɉԐ������������l�Ɏv����B�Ԃ͗͋��������ɍ炫�A�n�ʂɉԕق��U�炵���B
(�ւ̍炫�l�A�U��l)
�@�ւ͉Ԃ��Ɨ��Ԃ���B��C�ɗ�������̂ł͂Ȃ��������Ԃ������ď��X�ɗ�������B
�@�ւ͎�����p��A�z������̂ŁA���N�������Ƃ��ĕ��m�Ɍ���ꂽ�Ƃ����������邪�A���ۂ͒ւ͕��m�̊Ԃň��D����Ă����悤���B
�@�Ȃ��A���m�ɂƂ��āA�ؕ��͕��m�̖̑ʂ�ۂĂ閼�_�̎��������̂ɑ��āA�ł���͕s���_�Ȏ��ł������B������A���m�͒ւ��������Ƃ������������܂ꂽ�̂�������Ȃ��B�����A���͉Ԃ��Ɨ��Ԃ���ւ��D�����B
?�@����A�ؘ@�͈�C�ɊJ�Ԃ����̂���A��r�I�Z���Ԃɉԕق��o���o���ɗ������ĉԂƂ��Ă̎������I���B����Ӗ��ł̓\���C���V�m�̍炫���A�U����Ɏ��Ă���B
(�Ƃ������Ȃ��Ȃ�قǂ̉Ԑ��ň�C�ɍ炢���ؘ@�@1�T�Ԍ�Ԃт炪�U��U��ɗ�������)
�@���Ȃǂ���ʂɎU�肵���l��⥂ɂ��Ƃ��ĉ�⥂Ȃǂƕ����ɕ\�������B�������Ȃ���A�ؘ@�̉ԕق͎p�`���傫���A�U��������\���ɐ������܂�ł���B������s�p�ӂɓ��ނƊ����Ċ�Ȃ��B�v���ӂł���B�܂��A���ꂪ�����ƒ��F�ɕϐF�����ꂽ���͋C�ɂȂ���̐ɂ����B
�@���ꂩ��X���͗ɖG���A��X�̉ԁX�����X�ƊJ�Ԃ���B
4/22�i���j�_�ЂƂȂ������@���N�N���j�b�N�h�b�N�@��H�����@�@?2:00�N���B�����C�l�R�Ȃǂ����̂��Ƃ��B�ݐH���ĉ����O�ꂽ�B6:40�o�X���n�a�@�A�����Ɖ�f�A7:10-8:40�a���Ή��A9:00-11:00�B���N�N���j�b�N�h�b�N12���A���ʃ�������6���B�^�����ː�H�����R�C���a�B�i�J�C�`�R�[�q�[�A12:10���n�a�@�A�ꎞ�����A�Ǐ��A15:30���@���ґΉ��B�Ƒ��Ή��A19:30�A��A�[�H�A21:00�A�Q�B���s�v7110���B?
�G�߂̘b��2024(3)�@�A�}�����X
�@2024�N�A�����͋L�^�I�Ȓg�~����ƂȂ����B1�A2���͌����e�n�ŕ��ϋC�����ϑ��j��ō����L�^���A�~��ʂ͕��N��傫����������B
�@���͂��̐��N�A�ꔫ�̃A�}�����X�̐��b�����Ă����B
�@�A�}�����X�͔M�ь��Y�̐A���B��N���Ԃ��炢�������������剻�����������Ȃ����̂��Ȃ�ƂȂ��Ԃɐ������������Ȃ������B�t���ƌ������͉��ς��������Ă����B
�@�������K�v�Ɣ��f���A�Ԃ��I���ԍ[���͂ꂽ6�����{�v�����ċ�����3���������B�����������Q�Ƃ�����ł͂Ȃ��_���A�̕����̌o�����Q�l�ɓK���ɕ��������B���̌�������肭���肷�邩�킩��Ȃ��������A�Ă̋�����������؉A�Ŕ����Ȃ���ێ������B�H�ɂȂ��ėΐF�̗t�������n�߂��܂������������Ƃ��m�F�ł����B
�@�A�}�����X�͒ʏ�5���̔��A�����������܂鏉�Ă̂���ΐF���Q��`������B�ԍ[�͓����Ƃɗ͋����L�сA�₪�Ďq�ǂ��̊���B���قǂ̑傫�ȉԂ��炩���A����l�𖣗�����B
(�����ȉԂ��炩�����A�}�����X�@�ʏ��5���ɍ炭�̂ł��邪3����{�ɊJ�Ԃ����@�����̉e�����A�g�~�̂������@�ݒu�ꏊ�̊��������H�H)
�@�t�A�������Ƃ��Ĉ����Ă���A�}�����X�́A���Y�n�͔M�уA�����J�ŁA��80��̌��킪����B���{�ւ̓n���͍]�ˎ���̓V�۔N�ԂɌ��킪����A���ǂ��s��ꂽ�A�Ƃ���Ă���B�M�ѐA���Ȃ̂ŁA���珉���͒g�����ۂ��Đ��瑣�i���͂���A�\���ɔ�|�Ǘ����ċ������傫���Ȃ�悤�ɂ���ƁA���N�Ԃ��炭�B
�@�Ԃ��I���ԍ[���͂��ƁA�t���W�J���n�߁A1�J���ɖ�2���̊����ő�����̂ŁA��������̂悢�ꏊ�ɒu���ď\���Ɍ��Ă�B����A�����ɒ������Ă�Ɨt�Ă����N�����̂ŁA9�����{���܂ł͖�50���Ռ����ėt�Ă���h���B
(4�����{�̃A�}�����X�̏�ԁ@�t���W�J���V��ɂ܂œ͂������@�t�̐F�͐[���Ŋ��͂�������)
�@���̓A�}�����X��n�C�r�X�J�X�Ȃǂ̓�m�̉ԂɁA�����̐O�Ɏ����G���e�B�V�Y����������B������D���Ȃ̂��A�Ǝv���B
�@�z�~�͔����Ɠ���Ȃ��ꏊ�ɒu���ƈ��S�B
4/21�i���j�����@�������@�˂��g�C���P�[�X�V���@?�@1:30�N���A�������������B3:00���Ȋw��V�l��莋���B���A�̂ǎ����ӏ܁B�V���`�F�b�N�B�Ɠ��͐��N�I�P�ɁB14:00-15:15�������o�ȁA110���т̂���9���ȏ�̈ϔC�B�o�Ȃ�20�l�قǁB���N���Љ�����c��ی��������i�ψ��ɁB�����������������Ȃقǐg�̂��S�k�A�����A�˂��p�g�C���̃P�[�X�A�i�{�[���ŐV���A��r�I�悭�ł����B���Ȋw����B���W�I�[��֓��́B19:00�[�H�A21:00�A�Q�B���s�v3410���B��N�I���A��A�H���o�b�N�~���[���{����E���A���}���u�B
?�G�߂̘b��2024(2) �䂪�Ƃ͏���6��@�H�c�͒g�~����ł�����
�@2023�|2024�N�̍��G�A�����͋L�^�I�Ȓg�~����ƂȂ����B
�@1�A2���͊e�n�ŕ��ϋC�����ϑ��j��ō����L�^���A�~��ʂ͕��N��傫����������B
�@�C�ے��ُ̈�C�ە��͌�����ɂ��ƁA���~�̒g�~����͒n�����g���ɉ����A��ăy���[���̊C�ʐ������オ��G���j�[�j�����ۂ̉e���Ƃ݂���B���g���ɋN�����Ă���A������N����\��������B
�@���~�̕��ϋC���́A�H�c�n���C�ۑ��26�ϑ��n�_�̂���1����15�n�_�A2����13�n�_�Ŏj��ō����L�^�B
�@2���̗ݐύ~��ʂ́A�R���{���s��12cm�i���N��12���j�A�H�c�s�ł�20cm�i25���j�ɂƂǂ܂�A����n�̓���s�ł�30cm�i15���j�A����s��57cm�i28���j�������B
�@�X�L�[�W�ƊE�ł̓��t�g�̉ғ�������N�̔����قǂɂƂǂ܂����X�L�[�������A�c�Ƃ�\���葁���I�����������������B
�@��s���͏������s�������������B
�@�������Z���́u�|�����v�͑ł���̈��S���m�ۂł��Ȃ��Ƃ��Ē��~�A����s�́u���܂���v�́A�H�㒬�Ⓦ�������̎R�ԕ��Ȃǂ���v700�g���̐���W�߂čs���A����s�́u�������܂�v�͐ᑜ�̐������炳����Ȃ������B
�@���~�̒g�~�����4�G�Ԃ�B�m����2020�N�̍~��͍��N�������Ȃ������B�C�ے��ł͂��̌X���͍���������\��������A�Ƃ����B
�@���͎��R�E�̓������d�����Ă����B
�@�ŋ߂̏���X���͒n�����̗���A���g���̉e���̌��ʂ��낤�B��͂��낢��l�����Ă���l�ł��邪���ʓI����Ă���Ƃ͌����Ȃ��B���ɒn����̕��ϋC���͏㏸�X���ɂ���B
�@�l�I�ɂ͎����Ԃ̎g�p���T����Ȃǂ������Ⴍ�ȃG�l��ɎQ�����Ă������ł���B�������g�[�A�����Ȃǂ̖ʂł͏\���z�����Ă��邩�H�Ɩ����Ύ��M���Ȃ��B
�@���͓~�G�̏���ɂ��Ă͂��Ȃ�X�g���X�������Ă���B����14�N�Ԃ̏���@�ғ���0�|21��ƃo���o���ł��邪����9.7��ŁA2013�N�ȍ~�͌����X���ɂ���A�{���������ƂĂ��������B
�@����A����Ȃɏ��Ⴞ�Ət�̔_�Ɨp�̐��̕s���A�Ă̊����ȂǑ傢�ɋC�ɂȂ�Ƃ���ł���B
?
?
4/20(�y�j�����~�J�㐰��@�@?�@�S:00�N���A�̒��͖߂��Ă����B�T�v���֘A���������B�Ǐ��B11:00��J�ϐ킵�Ȃ���V���`�F�b�N�B12:00�ߌ�͓Ǐ��O���A13:30�Ɠ��ƃ��n�a�@�A�����ȂǁB�V�����́A���������ȂǁB19:00�A��B20:30�A�Q�B���s�v2590���A��N�_���A���A���B??�G�߂̘b��2024(1)�@�u�������т��@��̐[�����@�q�˂���v�����q�K
�@�P���1���������_�̏���@�ғ���r���鎞���������A�Ƃ������啝�ɉ߂����B
�@2023�|2024�N�̍��G�͏H�c�n���͐Ⴊ�ƂĂ����Ȃ������B
�@���͏���ɓ~�̖K�����������̓��ƌ��߁A�~�̒�`���u���Ⴊ�K�v�ɂȂ���������s�v�ɂȂ������v�̊Ԃɂ��Ă���B
�@���G�̓~�̖K���2023�N12/18�i���j�B�ϐ�Scm���x�Ə��Ȃ�����������ɍ~��\�����������̂ł����ƈꉝ���Ȃ��珜��@�ɂ�鏜���1��ڂ��s�����B
�@���̐����́A�����Ē����䂪�Ƃւ̃A�N�Z�X���H�A���͂�����u�ٔՁE�`�̏����H�v�ƌĂ�ł��邪�A50m�ȏ゠��A�����̏��Ⴊ�Y�݂ł���B40�N������ė��������\��ςŎ蓮�ł͂قƂ�Ǖs�\�ł���B����@��10�N����1���40�N����2�䂠��A��҂̓o�b�N�A�b�v�p�Ɏc���Ă���B
�@����12������18������24���܂ł̊Ԃ�5�Ⴕ���B����ȒZ���Ԃ�5����W���I�ɏ��Ⴕ���o���͂Ȃ���̂��Ƃ��뜜���ꂽ���A�N���ȍ~�͍~�Ⴊ���Ȃ�1��16����6��ڂ��s�����㏜��@�ғ��͂Ȃ������B
�@�܂�����Ȍo���Ȃ����A������Ƃł��蔲������Ɛ����p�i���͂��Ȃ��Ȃ蓾��B�Ⴆ�A�X�֕��A��}�ցA�����̑�z�A�����̑�z�A��z�X�[�p�[�ւ̒������i�A�^�N�V�[�ȂǁB
�@�������̋G�߂͌��N�ɒ��ӂ��A�ْ����Ē����}����B�~�Ⴊ������ɂ͑������x�����m�F��������ǂ̒��x���邩�l������B�����q�K�Ɂu�������т��@��̐[�����@�q�˂���v�Ƃ�����i�����邪���̋C�����͋����ł���B
�@���̐����͓~�̏���𒆐S�ɋG�߂����B
�@���͖��N1�������̒i�K�ł̉䂪�Ƃ̏���@�ғ������o���Ĕ�r���Ă���B
�@���̉��O���t�Ŏ����ƈȉ��̔@���ƂȂ�B
�@(�N�ʏ���@�ғ��ƃO���t�@��N�Ɠ����摜�@���G���͒NjL���Ă��Ȃ���6��ł�����)
4/19(���j���J�I���@��ȊO���@�I���̒��s�ǁ@?2:30�N���A���������A�^���f�[�^�������̑��C5:30�R�S�~2�܁B7:40Taxi�w���ɁB8:11���܂��A8:50��Ȓ��ʕa�@�O�����\�]�T�B�A�H���܂��A������5���x��B15;15Taxi���ʃ��n�a�@�A��U�x���A���ґΉ��ق��B19:20�A��[�H�A21:00�A���B�����v4865���B??�k�R�L�q(��)
4/18�i�j�����@���҉Ƒ��ʒk3���@?2:10�N���B�����ƕς�炸�A�l�R�Ή��A�f�[�^�����ȂǁB8:30�Ɠ��ɓ���a�@�B�W:50�a���Ɩ��A11:00�A14:00�A15:00���҉Ƒ��ʒk3���C�V���@����B�敾�����B17:00���@���ґΉ��B�V���`�F�b�N+���́B19:30�A��E�[�H�A20:30�A�Q�B��3752���B??�k�R�L�q(��)
4/17�i���j�~�J �a���J���t�@+EC�@�d�q�J���e�����ԕs����?�@2:00�N���A�����f�[�^�����C�����̂��Ƃ��B8:50�Ɠ��ɓ���a�@�B10:00�܂Ŕ����A�a���Ή��B12:12�o�X���ʃ��n�a�@�A�a���Ɩ��A�V���@����Ή��A�r���œd�q�J���e�s���ɁB�a���J���t�@+EC���ҏ��u�B�摜�f�[�^�����B19:20�A��A�[�H�A�A�Q�B��3752���B?
��121����{���Ȋw�ȑ���2024(3)�@�e�[�}:�ЂƂ��݂�A��������A���s����?�@�ȉ��̍u���u���A�F��X�V���i���B���薼�����L�^���Ă����B
�@�C�Â��Ȃ��܂������Ă������A���ʓI�ɐ��������ڂ������������̂ł���B�e�X�͑f���炵�����e�ł������B�ڂ����L�^�W�͌�ɓ��{���Ȋw��Ɍf�ڂ���邩�炻�̎��ĕ��������ł���B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
1. ��u��
���ȖƉu�����̍������߂����ā[�[�[�S�g���G���e�}�g�[�f�X�ƍR���������R�̏nj�Q
2. ���ʍu��
�n���̌��N�A�Љ�̌��N�A�l�Ԃ̌��N
3. �����u��
1) ���E�~�l������ӈُ�ǂ̕a��, �a�ԂƎ���
2) �I���R�l�t�����W�[: ��ᇊw�Ɛt���a�w�̐ړ_
3) �����ۂƐS���ǎ���
4) �����ǐf�Âɂ������`�q�����̓W�J
5) �A���c�n�C�}�[�a���Ö@�̐i��
3)�V���|�W�E���F����҈�Â̕�����ۑ�Ƃ��̑�
(1) ���a�E�|���t�@�[�}�V�[
(2) ����҂̑��l�ȔF�m�ǂƂ��̑Ή�
(3) ����Ґf�Âɂ�����t���C���A�T���R�y�j�A�̈Ӌ`���l����
(4) �n���P�A�E�n��Â���̎��_����
(5) �G���h�I�u���C�t�P�A
����u��
6) �R�����̏���������p�Ƃ��̑�
7) ���������������a�̎��Â̐i��
8) �؉��f�f�̍őO��
9) ���S�؏ǂ̐f�f�Ǝ��Â̐i��
10) ����́E�_�������f�Â̐i��
11) ���������p��̎��Â̐i��
12) �����ǂ���Ö@�̐i��
13) �}�����nj�Q�̋}��������
14) �x�[�`�F�b�g�a�̐V���ȓW�J
15) COVID-19�̑���
17) �����ُ�ǎ��Â̍őO��
4/16�i�j�����@�ߌォ��~�J�@���ʕa�@�O���@�Ƒ��ʒk�@?�@2:00�N���B�����E�^���f�[�^�����C�����̂��Ƃ��B5:00�R���݂Ǝ����S�~��o�B6:40�o�X���ʃ��n�ցA7:10-8:00�a���A���҂͗������A8:40-14:00�O���A�{���͗\��25���A�敾�����B14:10�a�@�A�ꎞ�����A16:00�a���Ή��A17:30���҉Ƒ��ʒk�A19:20�A��[�H�A20:30�A���B������6830���B
��121����{���Ȋw�ȑ���2024(2)�@?�@���͓��{���Ȋw���̍u�����D���ł���B
�@���̊w��͖��N4����{�̏T���A3���Ԃɂ킽���ĊJ�Â����B
�@�Ɩ��̊W�ACOVID-19�����������āA���̐��N�͂����������Ă����B���̋L�^�ł�2019�N�́A���É��s�ŊJ�Â��ꂽ��116��Ō�̏o�ȂƂȂ��Ă���B����4�N�����Ȃ����B
�@10�N�قǑO�A���{���t�w��Ȃǂ̐��̈�̎w����A�F��㎑�i�A������i���ԏサ���B�������A�ł���b�I�Ȏ��i�ł�����Ȋw��̔F���͓��Ȉ�Ƃ��ē����Ă���ȏ㎸����ɂ͂����Ȃ��l�ł���B
�@��N3���Ɋw����ǂ���u�F���̍X�V�_�����[���_�ł��̂ŗv���Ӂv�Ƃ̘A���������B�F����2025�N�t�܂ŗL���ł��邪�A������X�V����ɂ͑O��ƍ���̊w��ɑ����ĎQ������K�v���������B
�@�@���������A�F�莑�i�Ȃǂ�������Ȃ���??�@����Ŗ������̂ł��邪�A���N��Web���u�ŎQ���Ƃ����B
�@���̊w��̏͒m��Ȃ����A���{���Ȋw����Web�z�M�͎��ɂƂ��Ĉȉ��̃����b�g������B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
���Ɩ����x��ʼn��ɏo������K�v���Ȃ��B
��Web�z�M�ɂ�钮�u�͎Q����+���u��Ƃ���1���~�̂݁B
���ړ����ԁA�ړ��̂��߂̌o��A�h���o��s�v�ŕa�@�ւ̕��ׂ��Ȃ��B
���I���f�}���h�u���̎����͗�������2�T�Ԃقǔz�M�����B���Ԃɒǂ�ꂸ�D���ȏōD���Ȏ��ԑтɎ����ł���B
���I���f�}���h�u���͘^���E�^����\�œ��e���������茟���o����B
�����̍��G�A���Ȑl���ɂ���킸�ɍςށB
���ȂǂȂǁE�E�E
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
�@����������}�������̂ł���B
�@COVID-19�������炵���ϊv�ł���B����̎��ɂƂ��čō��ł���B?
4/15�i���j���������@���N�N���j�b�N�h�b�N�@�U����H�����@?�@2:30�N���B�V���x�����A�����E�^���f�[�^�����C�����̂��Ƃ��B6:40�o�X���ʃ��n�a�@�A7:00-8:30���@���ґΉ��m�F�A9:00-10:30���N�N���j�b�N�h�b�N5���ƐV�N�x�n�܂�ŏ��Ȃ��A���ʃ�������10���B�k���Ő�H�����A�x�̃R�C���a�A�L��ō��ς�B�A�H�i�J�C�`�R�[�q�[�A���n�a�@�A��������敾�����B�̗͌����H�H�ǔ��V���`�F�b�N�A���́B14:30���@���ґΉ��B���Ȋw��u�������͓�l�Ƃ�����̎��ԂɒB�����B19:30�A��[�H�A20:50�A���B������8272���B??��121����{���Ȋw�ȑ���2024(1)�@COVID-19�������炵�����b�AWeb�Q���̓�?�@���͓��{���Ȋw���̍u����D���ł���B
�@��t�ɂȂ��Ă��獡�N��53�N�ɂȂ邪�A�{�w��ɂ�40��ȏ�͏o�Ȃ��Ă����B���ō����Ă��邾���ōL�͂ȗ̈�ɂ킽���čŐ�[�̍u���u�ł���B���̂ق��Ɋw��F��㎑�i�̍X�V�������I�ɓ�����Ƃ��������b�g���������B
�@���Ă͊w��͊w��̒n���ŊJ�Â���邱�Ƃ���ł��������A�ŋ߂͒n���s�s�ŊJ�Â���邱�Ƃ͋H�ŁA�w����S���ǂ��̑�w�ł����Ă���s�s���ŊJ�Â����悤�ɂȂ����B�m���ɁA�������∮��Ȃǂ̒n�ŊJ�Â��ꂽ�ꍇ�́A��ʃA�N�Z�X�̖ʁA�h���̊m�ۖʂȂǂ���ςł������B
�@���͒����̂����ŁA���o�s���A���s�����ł��邪�A���̊w���ѓ��{���t�w��A�Տ����t�w����͂��܂߂ɖK��Ă����B
�@���̗��s���̂قڑS�Ă͊w��֘A�ŁA�l���E����������قڑS�Ă̓s���{���ɂ킽���Ă���B
�@���Ă͊w��̍��Ԃ�D���Ċe�s�s�̔��p�ُ���A����������������Ƃ��������B���s�̎��@�A����A�L���̌����L�O�قȂǂȂǁB
�@�������A50�㍠����͋Ɩ����ߏ�ɂȂ�A�w����Ԃ͋x�������˂ăz�e���ɘU�������œǏ��Ŏ��Ԃ��₷�悤�ɂȂ����B
�@���̊w��̏ɕω����o���̂�2020�N�̑����ł���B
�@COVID-19���������A�ً}���Ԑ錾���o������ւ̏o�Ȃ�����Ȃ����B���̔N�ȍ~�AWeb�ł̒��u���\�ƂȂ������A���̔F���X�V�ɗ]�T�����������ߎQ�����������Ă����B
�@2022�N�����l�̏ł��������A�Ɠ��̔F���X�V�ɕK�v�ȓ_�����s�����邽�߂ɑ�119���Web�ŎQ�������B
�@�Ɠ��͒��^�ʖڐl�ԁB�w�����3���Ԃɉ����O�����邩��A�Ɩ��̑�s��S�����ɂƂ��Ă���ςŁA���̓_Web�ɂ��w��Q���̓��A���^�C�����u�A�I���f�}���h���u���\�łƂĂ��֗��ł������B
�@�ړ�����K�v���Ȃ��A�ѐ�a�@�̉@�����Ńp�\�R�����j�^�[�ōu�����K���5���Ԉȏ㒮�u���A�Ɠ��͍X�V�F�肪����ꂽ�B
�@Web�ŎQ���͋Z�p�I�Ɏ��̉������K�v�ł���A�������Œ����Ă��ĂƂĂ����ɂȂ����B
4/14�i���j���������Ȃ肻���@�s�A�m���t��?2:40�N���B������c�����V���`�F�b�N�A�����E�^���f�[�^�����C�����̂��Ƃ��B13:00�̂ǎ����㑷�����̃s�A�m���t�̉��t��ɍs���Ɠ��ɓ��撆�ʃ��n�A15:00-16:00�Ƒ��ʒk���}����A���ґΉ��B�ȍ~�͋����ʼn߂����B�V���`�F�b�N�A�f�[�^���A�Ǐ��A�����B�s�[�R�b�N�o�R19:00�A��A�[�H�A21:00�A���B������3425���B??
4/13�i�y�j�܂�@ ���{���Ȋw��2����(Web���u)�@�Ɠ��]���^?2:17�N���B�Ɠ��̃]���^��������B4:30-5:30�����A�V���X�N���b�v�A�����E�^���f�[�^�����B���Ȋw���u����Web�Q��2���ԎQ���B�ߌ㎟�j��Ɨ��P�A�������̐����Ȃǔ�I�B�w��u����Web�Q��3���ԎQ�����������A�}�b�N�����A�Ɠ�19:00�A��A�[�H�A20:30�A���B�����v3383���B??
4/12�i���j ����@��Ȓ��ʕa�@�O���@���{���Ȋw���(Web����)?�@1:50�N���A�Ǐ��A�f�[�^�����B5:30�R����2�W�Ϗ��ɁB7:40Taxi�H�c�w�B8:11���܂��B8:55��Ȓ��ʕa�@�O���B ���{���Ȋw���(Web����)��ȂŁB15:30���艮�Ï��X�o�R���ʃ��n�BCD�����w���B16:30�a���Ή��B�V�����͂ق��A19:20�Ђ�̂�o�R�A��A�[�H�A21:00�A�Q�B6317���B??��t�̓��������v(2024)(7)�@����
�@���������v�̒��́A���݂͐V��ƂȂ��Ă����t�̎c�Ǝ��Ԃɏ����݂��邱�ƁB
�@�����Ƃ��ĔN960���Ԃ�����ƂȂ�A�ᔽ����Εa�@�ɔ������Ȃ����B�����ԓ�����t���w������ȂǁA��Ë@�ւɌ��N�Ǘ����`���Â���B
�@��t����J��������܂܂ł́A���ӗ͂������A��Ã~�X���������˂Ȃ��B��t�̓����߂���h�����Ƃ́A��Ë@�ւ̐Ӗ��ł���B
�@����A�n���Â�S���a�@�̈�t�⌤�C���́A��O�I�ɏ����N1860���ԂƂ���B��t�̊m�ۂ�����n���̎����A�Z�\��g�ɂ��������̊�]�ɔz�����邽�߂��Ƃ����B�����A���̏���͌�155���Ԃ̎c�Ƃɑ������A��80���Ԃ́u�ߘJ�����C���v��傫�������Ă���B
�@�ߍ��ȘJ����ǔF�����ŁA����ł͈�t�̌��N������̂��^�₪�@���Ȃ��B
�@���J�Ȃ̒����ł́A�a�@�̏�Έ�̂����A2022�N�̎c�Ƃ��N960���Ԓ���������t��21���A�N1860���Ԓ���4���������B�������2019�N��蔼���������̂́A�Ȃ��ꕔ�̈�t�ɉߏd�ȕ��S���������Ă���B
�@���߂����Ȃ��̂́A��Ԃ�x���Ɉ�t���ҋ@����u�h�����v���Ζ����Ԃ��珜�O���悤�Ƃ����������L�����Ă��邱�Ƃł���B�u�h�����v�̋Ɩ��͕a�@���Ƃɑ傫���قȂ�A���Z�̕a�@�ł͈�t�ɂƂ��đ傫�ȃX�g���X�ƂȂ��Ă��邪�A���̎��Ԃ�J����@�̓��ስ���ŋΖ����Ԃ��珜�O���鋖��\������a�@�������Ă���B
�@����ɁA����ւ̎Q����_���쐬�Ȃǂɂ��Ă����Ԃ́u���Ȍ��r�v�ƈʒu�Â��A�J�����ԂɊ܂܂Ȃ����s������B
�@���������^�p�����߂Ȃ���A��t�̓��������v�͌`�[�������˂Ȃ��B
�@�ߔN�A�Ζ����s�K���ȋ~�}��Y�ȂȂǂ̐f�ÉȂ͌h�����ꂪ�����B�s�s���ւ̈�t�̏W�������N�̉ۑ肾�B
�@�Ζ���̑ҋ����P���w���̒�������܂߁A���{�͑����I�ȑ����������K�v������B
4/11�i�j�����@�@?�@1:20�N���A�����ǂ݁A�l�R�Ή��ȂǁB8:30�Ɠ��ɓ��撆�ʃ��n�ɁB�ߑO�͔�������B�V���`�F�b�N�A10:30�a���Ή��B���w�B15:30�a���Ή��B�V���`�F�b�N�A���́A�Ǐ��A���w�B19:30�A��A�[�H�A21:00�A�Q�B�ʋΘH�̍��J�Ԏn�߂Ă���B���s�v2910���B??��t�̓��������v(2024)(6) ������Ƃ����g����������
�u������v�Ƃ́A�����œ�����҂̂��ƁB
�@���͏��R����u������v�̌o���͂Ȃ��B
�@������ɂ͑�ʂ���ƈȉ���3�^�C�v������B
1. �u�����ł��A�ǂ����̂��ƂŐ[��������������v
2. �u4�N�Ԃ̑�w�@�����ԁv
3. �u��ǂɗL���E�̃|�X�g���Ȃ����߁v
�@������͘J�����Ԃ͒������ԂɂȂ邪�A�����ł������ł�����Ă�����Ƃ����Љ�I�Ȏ���������B
�@�������A�u�A���o�C�g�Ő������ł��邩�疳���ł����v�Ƃ����_����100������Ă��邪�A�����̎Ⴂ��t���L���̃|�X�g�������Ȃ��Ȃ�~�ނȂ��E�E�E�Ƃ����l���Ė�����ɊÂĂ����B
�@2000�N�Ɉ�t�̌��C�㐧�x���������Ĉȍ~�l�ς�肵�����A����ȑO�͈�t�̑����͑�w��w���̈�ǂɏ��������B
�@��ǂ͋������g�b�v�Ƃ���s���~�b�h�^�̍\���ŁA���^��K���A�g���Ȃǂ͂����ނ˔N������B�L���̃|�X�g�͊e��ǂ�10�����x�ł���A�傫�Ȉ�ǂ���50�����̈�t�������ŏ������Ă����B�����ソ���͊e�X�n��̕a�@�ɔh������A������Ă����B
�@���̍��{�ɂ́A��w�a�@�ɂ͂������������̈�t��L���Ōق��o�ϓI�]�T���Ȃ��������Ƃ�����B��w�a�@�͎���D��Ŗ�����̃V�X�e��������Ă����킯�ł͂Ȃ����A���̂悤�ȃV�X�e���Œn��̈�Â��ێ�����Ă������Ƃ͊m���ł���B
�@��w�a�@�łȂ��Ă͊w�ׂȂ����x����i�I��w�I�m���A�Z�p������A�������\�ł���B���̊��͎��̈�t�ɂƂ��Ă͖��͂��������B
�@���݁A���́u��t�̓��������v�v��i�߂Ă���B����̐��ڂ������邪�A����ł���t�ɂ͉ߍ��ȘJ���������c���ꂽ�܂܂ł���B
�@�u��t�̓��������v�v�ɂ͈�t�̘J���������y������Ηǂ��Ƃ������̂ł͂Ȃ��B���ꂾ����Nj�����Βn���Â�����B
4/10�i��) �����@������@�����Á@�H�c���J�Ԑ錾?�@1:30�N���A�����ǂ݁A�k�R�B�����{�ǂ݁B8:30�Ɠ��ɓ���A�a���Ɩ��A10:00-12:30���ʎ��Ȑf�Ï��B14:00�a���Ɩ��A14:30�J���t�@�����X�AEC�A���u�ق��B���҉Ƒ��ʒk�A�V���`�F�b�N�f�[�^���B19:00�A��[�H�A20:30�A���B�����v3543���B�H�c�n���C�ۑ�͏H�c�s�̃T�N���̊J�Ԃ\�B���N���7�������A����܂łōł������������N���6���x���B??��t�̓��������v(2024)(5) ��t�͘J������悳�ꑱ���Ă���
�@������킸���Âɂ�����Ζ���́A�����ԘJ������ԉ����Ă���B
�@�S�g�Ƃ��ɔ敾���ċΖ�������߂�l������A����Ȃ��t�s�����������z�������Ă����B
�@�Ζ���̉ߍ��Ȓ����ԘJ���ɂ���Ĉ�Ñ̐����ێ�����Ă��錻��́A���S�Ƃ͌����Ȃ��B�e��Ë@�ւ����������v�Ɏ��g�ނƂƂ��ɁA���͈�Â̈ێ��̂��߂̑���������ׂ��ł���B
�@���̍ۂɊ��҂̎�f�s���̐�����Ȃ���Ύ������͊m�ۂł��Ȃ��B
�@2019�N�Ɏ{�s���ꂽ���������v�֘A�@�ł́A��t�ɂ��Ă͉e�����傫���Ƃ��āA���{��5�N�Ԑ摗�肵�Ă����B���ꂾ�����͈�t�̘J���ɂ��āu�g�����v�ɗ����ĒႢ�]���Œ����ԘJ������悵�����Ă����B
(1)��t�̘J�����̎��� �����̃C���^�[����
�@�Ⴆ�A������t�ɂȂ钼�O�܂ł͑�w��w���E��ȑ�w�E��w���w�Z�𑲕\������t�̗��ɂ�1�N�Ԃ̖����̃C���^�[�����x���������B
�@1945�N�i���a20�N�j��GHQ�̎w���ŁA���Ɛ��ɃC���^�[������ƈ�t���Ǝ������`���ƂȂ����B
�@�C���^�[������ł͈�t���i��L���Ȃ��C���^�[��������Ís�ׂ��s�����B��Î��̂̐ӔC���݂����m�ł͂Ȃ������B1967�N�i���a42�N�j�ɓ����w���̃C���^�[�����炪�u��t���Ǝ����{�C�R�b�g�^���v���N���A���ꂪ���啴���ɔ��W�������Ƃ������ĎЉ�ɒ��ڂ���A1968�N�i���a43�N�j�Ɂu�C���^�[�����x�v�͔p�~���ꂽ�B
�@����20�N�ȏ�������̐��x�𑱂��Ă����B
�@����ɂ���āA���シ���ɍ��Ǝ��������i�҂ɂ͈�t�Ƌ������^����邱�ƂɂȂ����B
(2)�������Ƃ����g��
�@�C���^�[�����̔p�~�ɂ���āu���ӂȂ������i��v�̗���͂Ȃ��Ȃ������A��w�a�@���K�͕a�@�ɂ́u������E�������v�Ƃ����Ζ��`�Ԃ��������B
�@����1973�N(���a48�N�j����H�c��w���Ȃɏ����������A���̎��̐g����1�����ƂɎ��i���X�V�������و�t�ł������B�x����Ζ����ԂȂǂ����Ă������ɓ������łق�24���ԍS����ԂŁA�����̋��^��4-5���~���x�B
�@�T���͏H�c�����̕a�@��_�X�Ƃ��Ȃ��琶������҂��ł����B
(2)������Ƃ����g��
�@�u������v�Ƃ́A�����œ�����҂̂��ƁB��X�̗��R�ŋ����������킸�ɘJ�����Ă����t�����݂����B�قƂ�ǂ͈�t�ɂȂ���3�`10�N�ڂ��炢�̎���t�ł������B��t�͒������ԘJ�������o�傷��A���o�C�g�Ő��v�𗧂Ă��铹�����������炻���[���ł͂Ȃ������B���̎�����ς���������炢���A�E����Љ�Ă��炦�邱�Ƃ����҂ł�������ł���B
�@���͏��R����u������v�̌o���͂Ȃ����u�������v��3�N�߂��o�������B
4/ 9�i�j�~�J�@���ʕa�@�O���@�U��?1:55�N���A�l�R�Ή��A�k�R�Ƃ����Ɠ����B5:00�R�S�~�����̂݁B6:40�o�X���ʃ��n�a�@�ցB7:10-8:15�a���Ή��A8:45-12:45�O���A�敾�B13:00�@�������A���ʃ��n�A�����������P�[�L�Ōy�H�B�����B�V���f�[�^���B���@���ґΉ��B19:30�A��[�H�A21:00�A���B��5826���B??��t�̓��������v(2024)(4) ����ɂ킽��Ɩ����ǂ��]������??
�@��Ì���ł͂���܂ŁA�J�����Ԃ�������ƊǗ�����Ă����Ƃ͌����Ȃ��B������A���������v�c�_�̑O��ƂȂ�A�ƃf�[�^���\���ł͂Ȃ������B
�@�Ζ���̓���Ɩ��͑���ɓn��B
�@??����̊O���A??���@���Ґf�ÁA??���Җ{�l�Ƒ��ւ̕a������A??�Љ��E�f�f�����̐f�Ê֘A���ނ̍쐬�A??���S���̑Ή��A??���f�E���f�Ɩ��A??��p�E�p��Ǘ��A??���Ȋw�K���C�A??�������҂̕a�Ԃ̊w�K�A??�a�@�S�̂̊w�K��J���t�@�����X�A??�e�f�ÉȂ̌�����A??�������A�e�f�ÉȂ̍S�����ԁA??��lj�o�ȁA??�ȂǂȂ�
�@���͖����Ȃ����Ǝv�����A�ʏ�Ζ��̂̂��ɂ��̂܂ܓ����ɓ���A�������ʏ�Ζ��A�Ƃ����`�Ԃ͋H�ł͂Ȃ������B
�@�����̋Ɩ��̕]���͋Ɩ����P�̒��łǂ�������ꂽ���H
�@��K�͂̍��@�\�a�@�ł͒�7���䂩�����A�Ǘጟ����s���Ă������܂�ł͂Ȃ��B���e�I�ɂ͐f�ÂɊ֘A�������̂ł��邪�A�Ζ����ԓ��ɊJ�Âł��Ȃ����߂���Ȏ��Ԃ���J�Â����B
�@��t�̓��������v�ł́A��ʂ̈�t�̋Ɩ��͈͂Ɠ���Ώۈ�t�ւ̑Ή��ɕ�������B
�@����̑ΏۂƂȂ��t�̌��N����邽�߁A�ȉ�����Ë@�ւɋ`���t���Ă���B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
���A���Ζ���28���Ԉȉ��ɂ���A
�����̋Ζ��܂ł�9���Ԃ̋x�����m�ۂ���A
���c�Ƃ���100���Ԉȏ�ɂȂ�ꍇ�͎Y�ƈ�炪�ʐڎw������A
���ȂǂȂ�
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�@����ȃo�J�ȁA�Ǝv���B
�@��t�̔�J�̏��q�ϓI�ɂǂ��`�F�b�N����̂��B
�@�h�N�^�[�X�g�b�v�����������ꍇ�ɑ���̈�t���ǂ��m�ۂ���̂��B�������̂���d�g�ݍ����ۑ�B
�@����p�~�͏d�v�ł��邪�A���͓���p�~�Ɏ���܂łɈ�t�̘J�������ǂ��ω����čs���̂��A�ɋ���������B
�@���̍ہA��Â̂�������̎���ł��銳�҂̗����,�u�Â��ǂ�����̊��ґ��v���炩������čs������Ȃ����낤�B
4/8�i���j�����@���N�N���j�b�N�@�@?1:20�N���A�����ǂ݁B�����Ɠ����B6:40�o�X���ʃ��n�a�@�A7:00-8:15�a���Ɩ��A9:00-11:00���N�N���j�b�N�B�V�N�x��10���Ə��Ȃ��B��N�A�؍��o�g���ۋ��{��w�̖^�����ƑΘb���ݓ��̕��̌��������ɐG�ꂽ�B11:00���ʃ��n�A���Ĕ����B���H��ēx�����B15:00�a���A�V���f�[�^�`�F�b�N����ʓ��́A�����B19:30�A��A�[�H�A20:30�A���B��4596���B??��t�̓��������v(2024)(3) ���{�͈�t�����ƍl���Ă���̂�
�@���{�̈�Â͍����F�ی��̂��ƁA���E�I�ɑf���炵�����ʂ��グ�Ă����B���̐��ʂ�WHO�ɂ���Ă��u���E��̈�Áv�ƔF�߂��Ă����B
�@�������Ȃ���A�䂪���̈�t����OECD��i���̒��ł����ʂƏ��Ȃ��A����ł͍����F�ی��̂��Ɗ��҂̎�f�͕p��ŁA����a�@�u��������A�Ζ��オ���ȋ]���̂��ƂɋɌ��܂ł̉ߏd�J���ŎЉ�̗v���ɑΉ����Ă����B
�@���́A������u�P���ɑf���炵���A�ƕ]�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�A�Ƃ̍l���������Ă����B
�@��t�̉ߏd�J���̍ő�̔w�i�͂����Ƌ�����ƈȉ��̔@���ł���B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
�@����t�s���A
�@����t�̒n��݁̕A
�@����t�̐f�ÉȂ݁̕A
�@����Ë@�ւ̓K���ȋ@�\�����̒x��
�@���e�n��̈�Ì����Ƃ̈�Ë@�ւ̓K���Ȕz�u���̌������̒x��
�@�����ґ��̕s�K�؎�f
�@���E�E�E�E�E�Ȃ�
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
�@�����͂ǂ̍��ڂ�����Ă��Ή���������ڂł���B
�@2019�N4���u���������v�֘A�@�v���{�s����A�����ԘJ���̐������}��ꂽ����t�̏ꍇ�͒n��̈�Ñ̐��ɋy�ڂ��e�����傫���Ƃ���5�N�ԃX�^�[�g���x�点�A2024�N4��������{���ꂽ�B
�@�������A����5�N�Ԃ̊ԂɗL���ȑȂ��ꂽ���H�H�Ƃ������_�Ō���ƁA�������ׂ�5�N�Ԃł������ƌ��킴��Ȃ��B���ɁA�Ή����Ԃɍ��킸4���ȍ~�a�@�@�\�̏k����A���ɋ~�}�f�Â̈ێ�������ɂȂ����a�@�����Ȃ��Ȃ��B
�@�����āA2035�N�x���Ɉ�t�́u���ԊO�J�����Ԃ̓����p�~�v����A�Ƃ������A���܂�ɂ����Ԃ������肷����B����܂ň�t�ɍ�����������������炵���B
�@����p�~�̖ڕW�́A���J�Ȃ��i�߂�n��̈�Ò̐��̌��������O���ɏ�邱�Ƃ��O��B���̂悤�Ȍv�悪�v���悤�ɐi�܂Ȃ���A����p�~�����邸��Ƒ����B
�@���J�Ȃ͈�t�̐l�������ƍl���Ă���̂��^��ł���B
4/�V�i���j�܂�̂������Ɂ@����@����?�@�P:45�N���A�{�ǂ݁A�����E�^���E�摜�����B�����ȂǁB�ߑO�͍���̑����A����@�������S�A�o�b�e���[���_���ɂȂ��Ă����B�I�C�����w�����邩�H�H�^�C���I���牺�낷�B�̂ǎ����A14:30�Ɠ��ɓ��惊�n�ɁB���҂͂܂��܂��B�V���`�F�b�N�{���́A�G�������ȂǁB19:00�A��[�H�A20:30�A���B��2643���B??��t�̓��������v(2024)(2) ���������v�Ɋւ��鐭�{�̓���
�@��ʓI�Ɩ��ɂ����铭�������v�Ɋւ��鐭�{�̓������o���I�ɒǂ��Ă݂�B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�@��2016�N9���u���������v������c�v�ݒu
�@��2017�N3���u�����ԘJ���̐����v�u�_��ȓ����������₷���������v�Ȃ�9����ɂ������̓I�ȕ��������������u���������v���s�v��v���܂Ƃ߂�ꂽ�B
�@��2018�N6���u���������v�@�āv�������A
�@��2019�N4���u���������v�֘A�@�v���{�s����A�����ԘJ���̐����Ɍ������d�g�݂������o�����B��Ƃɂ͎Ј��̎c�Ƃ����炵����A�L���x�ɂ̎擾�𑣂����肷�邱�Ƃ����߂��A�ᔽ����Ɣ���������B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�@��ʐE�Ɋւ��Ă͏�L�̗���ł��������A�u��t�̓��������v�v�ɂ��Ă͎Љ�ɑ���e�����傫���Ƃ��āA��ʓI�ȐE��̉��v�Ƃ͕ʂɘ_�����A2024�N�x4���A������������{�s���ꂽ�B
�@�v����ɁA�Ζ��ソ���̑�������t�Ƃ��Ă̎g������w�i�ɁA�l�I�]���ʼnߏ�ȓ��������Ă������ƁA���{�̈�Â�����ɂ���Đ��藧���Ă����ُ�ȏ�Ԃ����ɂȂ��Ă���ƍ����F�߂��A�Ƃ������ƁB
�@�u��t�̓��������v�v�̋�̍�
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
����ʂ̋Ζ���͉ߘJ���̘J�ДF��̖ڈ��ł���u�ߘJ�����C���v������Ȃ���100���Ԗ����A�N960���Ԃ�����Ƃ���B
���������A�n���Â̂��߂ɂ�ނȂ��ꍇ�ƁA���C��������߂�����t�ȂNjZ�\����̂��߂ɏW���I�Ȑf�Â��K�v�ȏꍇ�ɂ́A����ŔN1840���Ԃ܂ŔF�߂�B
������́A2035�N�x�ɏI������B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�@��t�ɑ��ē���Ƃ��āu�ߘJ�����C���v��2�{�߂��c�Ƃ�F�߂邱�ƂɁA�u��펯�Ȑ����v�Ƃ������ᔻ���o���B�������A�ꗥ�ɋΖ���̎c�Ƃ𐧌�����A�n���Â�����Ƃ��������ɔz�����A���̂悤�Ȑ��l�ɗ����������B
�@�n���Â͋Ζ��ソ���ɂ��u�ُ�ƌ������鎩�ȋ]���ɂ���Ĉێ��v����Ă����B
�@���������̍��ɂ͂��̉Q���ɂ������B
�@
4/6�i�y�j�����@��|���@?3:30�N���B�Ǐ��A�f�[�^�������S�B�Ǐ��A���w�B10:00��|���A������14:00��|���A16:00�V���`�F�b�N�B����ȍ~�͓Ǐ��A���w�B�I������ʼn߂����̂͋v�X�B19:00�[�H�A20:00�A���B�����v5342���B
��t�̓��������v(2024) (1)�@���{�ɂ����铭�������v
�@���{�̘J�����͏I�g�ٗp����w�i�ɂقږ������ł������A�ƌ����Ă��悩�����B�������J���g���̉^���Ƃ��ʼn��P���v�͐}���Ă����B
�@��ÊE�A�Ƃ�킯�Ζ���̐��E�ł͎c�Ǝ��Ԃ́A�J�g��������ׂΎ�����V�䂾�����B�܂��A���{�̈�Â͋Ζ���̔�펯�I�Ƃ�������n�[�h�ȋ]���ɂ���Đ��藧���Ă����A�ƌ�����B
�@2019�N4���{�s�̉����J����ŁA���N4���ȍ~�͋Ζ���̒��ߋΖ����Ԃ͌����N960���Ԃ�����ƂȂ�B�ᔽ����Εa�@���ɔ������Ȃ����B���C����ނȂ��ꍇ�͓���1860���Ԃ܂œ���ŔF�߂���B
�@��t�̑����猩�Ċ�������v�ł͂��邪�A���ۂ̈�ÊE�ő傫�ȍ����̌��ɂȂ肻���ł���B
�@���{�̎Љ�̒��œ��������v���K�v�Ƃ����w�i�ɂ́A�傫��2�̎Љ�I�v��������B
(1)���q����ɂ�鐶�Y�N��l���̌���
�@���������v���K�v�Ƃ���闝�R�̂ЂƂɁA���q����ɂ�鐶�Y�N��i15�Έȏ�65�Ζ����j�l���̌�������������B
�@���{�����̐��Y�N��l���́A1995�N�̍��������ɂ�����8,726���l���s�[�N�ɁA�N�X�����𑱂��Ă���B
�@�����Љ�ۏ�E�l����茤���������\���Ă���u���{�̏������v�l���i����29�N���v�j�v�ł́A2029�N�ɂ͐��Y�N��l����7,000���l�������A2065�N�ɂ�4,529���l�܂Ō�������Ɛ������Ă���B
�@���{�̘J���͂̎�͂ƂȂ鐶�Y�N��l��������܂��܂���������Ƃ̌��ʂ�����A���{�S�̂̐��Y�͂���э��͂̒ቺ�����O����A���������v���s�������̐l���J���ɏ]�����邱�Ƃ����߂��Ă����B?
(2)�玙����Ƃ̗����ȂǓ������̃j�[�Y�����l��
�@���݁A���{�ł͋��������т���ђP�g���сi���ю傪��l�̐��сj�̊����������X���ɂ���B1990�N��̒����ɋ��������т̐�����Ǝ�w���т̐����t�]���Ĉȗ��A���������т̐����������Ă����B
�@�܂��A�������̑�����j�Ƒ����̉e�����A�P�g���т�����������B���̂��߂ɁA�ߔN�A�Ǝ���玙�E���ȂǂƎd���𗼗��ł���_��ȓ������ւ̃j�[�Y�����܂��Ă���B���������j�[�Y�ɑΉ����邽�߂ɂ́A�J���ɂ����鎞�ԓI����̊ɘa��A�t���^�C���ȊO�̘J���ɑ��鏈�����P�A�ꏊ�ɂƂ���Ȃ��e�����[�N�̓����ȂǁA���������v�̑��i���K�v�ƂȂ�B
�@���J�Ȃ����\���Ă��铭�������v�Ƃ́A�u�����l�X�����ꂼ��̎���ɉ��������l�ȓ�������I���ł���Љ�v���������邽�߂̉��v�̂��ƂŁA���{��������Ɍf�����u�ꉭ������Љ�v�Ɍĉ��������g�݂ł�����B
4/5(���j �����@��Ȓ��ʕa�@�@?�@2:00�N���B�Ǐ��A�f�[�^�������S�B5:00�R�S�~�����̂ݒ�o�Ȃ��A7:40Taxi�w�ɁA8:11���܂��A8:50��Ȓ��ʕa�@�O���A�����^�N�V�[�B�H�c�͓k���B�ߌ�A�H�̐V�����̒��Ŋ��Ҏ����̘A����B15:30-19:00���ʃ��n�B19:00�A��A21:00�A���B�����v5370���B??�V�N�x(2024)�X�^�[�g�@���ς�炸�����W�͑����Ă���
�@���������Ă��鐢�E�͂ƂĂ������B���͒m�������Ȃ��A�X�ɐ��Ԓm�炸�ł���B
�@����A�����������Ă��鐢�E�͍L���A������A�A���̐V�����`�F�b�N�����ƁA�I����NHK AM���W�I�̒���A�����̏��Ђ̍w���ƓǏ��E�E�E�A�Œm��Ȃ��������E�A�m��Ȃ������l����m��B�ƂĂ��y�����L�Ӌ`�Ȏ��Ԃł���B
�@�A���A�����̖��m���Ċm�F������X�ł�����B
�@�����̊w�K�̂��߂Ɏ��W���Ă�����͈ȉ��̔@���B
--------------------------------------------------------------------
?�V��3��(�����A�ǔ��A�H�c�@) ? ?�X�N���b�v�쐬�@��N����ꎆ���Ȃ��Ȃ���
?���W�I�[��֘^��(am1:00�A3:00�A4:00)�ƒ���
?����w�ǐ�厏(��ÊW�@���{�㎖�V��3��)
?����w�nj�����(���t�A���y�̗F�AMacFan�AWWF Japan�ANational Graphics�A�쒹�A��̉��|�A�������W�I�[��ւȂ�)�@
?�P�s�{�����w��(�����A�G�b�Z�C�A�h�L�������g�E���|�A�S�w�֘A��)�Ǝ���
?N����������^��Ǝ���
?�炶��炶�長�������T�[�r�X(�@���̎��ԁA���|�e��A�̗w�ȁA���j���_��)
?�s������s���̎��W�Ɠd�q��
?���X�̕����̃`�F�b�N
?���̂ق�
--------------------------------------------------------------------
�@�����̏��͘A�����Ȃ�̕��ʂɂȂ�B
�@���Ђ͂������ЂƂ��Ă͎c���Ȃ��B�S�ēd�q������B
�@�f�[�^�͕��ނ��Ȃ���Ζ��p�̒����ɂȂ�B�����̕��ނɂ��Ȃ�̎��Ԃ��g���Ă��邩��A���ɂ́u���̐l���͉��Ȃ�!�@���ނ����̐l�����H�@�����ƗL�Ӌ`�͎��Ԃ̉߂�����������̂ł͂Ȃ����E�E�H�v�Ǝ��Ɏv���A���v��������Ȃ��B���ɂƂ��Ă͍ł��K���Ă��鎞�Ԃ̉߂��������낤�B
�@�ܘ_�����̏��͓K�X��������o���ēǂ݁A���������B���̂��߂ɂ�MP3�v���[���[�AiPad�͗����Ȃ��B�����āA��L�̏�瓾��ꂽ�m���̂����g�ɂ������e�͎����̃u���O�ɃA�E�g�v�b�g���m���̒蒅��}���Ă���B
�@������I�����邱�Ƃ͉������������Ƃł�����B
�@�������ɁA���ɂ͂��̗l�Ȑl���̉߂������ɑ����̋^�������Ȃ�����A�قږ������Ȃ���߂����Ă���B
�@�������݂������Ă��邱�Ƃ́A�Ƒ��A�E��̃X�^�b�t�ȊO�ɂƂ��Ă͂������l�͂Ȃ��낤�B
�@����ɁA�����~�ς�������f�[�^�A������f�[�^�́A���ȊO�ɂ͕s�v���낤�B����ׂ��������}�����玩���őS�Ă��������A�X�b�L�������������B
�@�����c���K�v�������Ȃ����A�Ƒ������͂ǂ����f���Ă���邩�ȁB
4/04�i�j����܁@��J1��?2:30�N���B�Ǐ��A�����`�F�b�N�����w���S�B8:30�Ɠ��ɓ��撆�ʃ��n�a�@�B10:30���@���Ґf�ÂȂǁA���{���Ȋw��2�l���o�^�B�V���`�F�b�N+���́A19;30�A��[�H�A21:00�A���B�����v4380���B??�V�N�x(2024)�X�^�[�g�@�Ō�t�E�����E���E�P���m�̎Q���ň�t�̋Ɩ��͑啝�ɍ팸(2)
�@�Ⴆ�A�a���ɐV�������@���Ă������ɂ́A�V���@�S���Ō�t�ɂ���Ċ��҂̏�Ԃ̔c���A�d�Ǔx�̔��f�A�Љ��Ȃǂ̕K�v���ނ̏����̂ق��A�厡��ɑ��ē��e�̒�����A�厡�オ�܂��ŏ��ɂ��ׂ��Ɩ������߂Ă���B����ŐV���@�̍ۂ̗��G�ȋƖ����������Ȃ����������B
�@�a���ɂ͓��@���҂̏�Ԃ�c�����đΉ����郊�[�_�[�S���Ō�t������A���1-2��A�O������т��̓��܂ł̓��@���҂̏�Ԃ��厡��ɓ`������B���̃��[�_�[�̋��߂ɉ����đΉ�������ʼn�f����Ζ�芳�҂��R��邱�Ƃ͂Ȃ��B
�@�P���W�X�^�b�t�B�̓��n�r���P����ʂ��Ċ��҂ƒ����Ԑڂ���B���R���킳����b�������B��t��Ō�t�Ɍ�������Ƃ����k���邱�Ƃ������B�ނ�̋L�^���瓾���銳�ҏ��͋M�d�ł���B
�@�f�Ê֘A�̏��ނƂ��ẮA�����ی�֘A���ށA�����ی��̐����f�f��������B���Ɍ�҂̏ꍇ�͊e�ی���Ж��ɐf�f���������قȂ�A�L�ړ��e���s������L���܂ő���ɓn��B����𐔖��������Ă��銳�҂��H�ł͂Ȃ��B���̏��ނ̂��߂�1-3���Ԃ��v���邱�Ƃ��H�ł͂Ȃ������B��N5���̎��̐S�s�S���̐f�f���͏��ނ̏��������ł��ʓ|�Ŏ��͋��t�\������߂Ă���B
�@���͈�ÃN���[�N�S�������X�^�b�t�ɂ���đ��Ă������̂œK�X������������̂ŏ������Ă���B
�@�e�{�݁A��Ë@�ււ̏Љ��͓��e�͐��m�ɁA����̗�����l���č��ؒ��J�ɋL�q����̂ł���͑S�Ď����ŗp�ӂ���B
�@�މ@�������܂ފ��҂̏��ނ̑�������ÃN���[�N�ɂ���đ��Ă������̂œK�X�㏑�����Ċ�������B
�@��L�̓}���p���[�ɂ��Ɩ��y���ł��邪�A�d�q�J���e�ɂ�闘�����傫���B�f�ÂɊւ��Ă̓��͖͂w�ǂ���t�����ړ��͂�����Ȃ��B����͌��\��ςł���B���͂̏�ł͓��͂��s���ӂȈ�t�ɂ͕⏕�Ƃ��Ĉ�ÃN���[�N����������ꍇ�����邪���͈�l�ōs���B
�@�d�q�J���e�͒��ʑ����a�@�A���n�a�@�A��Ȓ��ʕa�@��3�a�@�ԂŃ����N���Ă���݂��̐f�Ï�{���ł���B���Ƃ��Β��ʑ����a�@�ŊO���f�Â��Ȃ��烊�n�a�@�̃J���e�ɂ��A�N�Z�X�ł��A������w�����o����B3�a�@�Őf�Â��Ă��鎄�ɂ͓s���������B
�@���ʃ��n�r���e�[�V�����a�@�͈�t�s���̂��߂ɃX�^�b�t�����ɂ��f�Õ⏕�̐��������o���オ�����Ƃ������悤�B���̂��Ƃ������āA����őΉ��͂��ቺ���Ă��鎄���Ȃ�Ƃ��A�]�T�������Ȃ���Ɩ������Ȃ��Ă���ł���B
�@
�@
4/3�i���j�����@�a���J���t�@?2:15�N���B���������A�k�R�ق��B8:30�Ɠ��ɓ��撆�ʃ��n�a�@�ɁB10:30�a���Ή��A12:00�V���`�F�b�N�{���́B14:30�a���J���t�@�A���@���ҏ��u�����B16:00�U����H�����R�C�ɋ��a�B�Ȃ������R�[�q�[�v�X�B�f�[�^�����A�{�ǂ݂ق��B19:30�A��B�[�H�A21:00�A���B����4058���A��H�������������ł͕����L�тȂ��B??�V�N�x(2024)�X�^�[�g�@�Ō�t�E�����E���E�P���m�̎Q���ň�t�̋Ɩ��͑啝�ɍ팸(1)
�@���͏T3��̐f�É��������Ă��邩��A�����ƌ����Βʏ�̔����̋Ζ����ԂŃ��n�r���a�@�̕a���Ɩ������Ȃ��Ă��邱�ƂɂȂ�B
�@����͎��ԓI�Ɍ���ƌ��\�����ɂ���A�ƌ�������B
�@�������Ȃ���A���ۂɂ͌��\�]�T������B����͈�t�̘J�����v�̐i�W�̌��ʂł���B
�@10���N�O�A���ʑ����a�@�̉@����S���Ă����Ƃ��́A�Ǘ��҂Ƃ��Ċ֘A�����c�����ƂĂ����������B����͓��R�̂��Ƃł��������B���ɁA�f�ËƖ����h�b�N�⌒�f�Ɩ��ȂǂƑ���ɂ킽���Ă������ƁA�S�����Ă������@���Ґ��A�O�����Ґ��������������ƁA���M�ŏ������ׂ��֘A���ނ��A�ɂ߂đ����������ƁA����������B
�@���̏ꍇ�A�����������Ǝv���o���ƁA����t��̕�����S���Ă����̂Ŏ��ɑ��Z�ł������B
�@��������O�̓������������Aam2:00�����玩��Ńh�b�N�⌒�f�Ɩ��̏��ޏ����A5:30-6:00���o�A6:30����a����f�A8:45-13:30�O���A���̌�͕a���Ɩ��A��t��֘A�Ɩ��A�@���O�̉�c���̑������Ȃ��Ă����B�A���20:30���ł������B�x�Փ����o���A�c�������ɏ[�ĂĂ����B
�@�����̂��Ƃ��v���o���Ɛg�̖т��悾�B�ߘJ�����C���͒����Ă����B�������Ȃ���A���I�ȏ����W���A��t��Ɩ����S���Ă����̂ŕa�@�Ɩ��Ƃ̖��m�ȋ�ʂ͂ł��悤���Ȃ��A���ߋΖ���\���������Ƃ��Ȃ��B
�@����2�x�Ƃ͖߂�Ȃ������ł������B
�@�����A��t�͎G�p�ɖZ�E����Ė{���̐f�ËƖ��ɑΉ��ł��Ă��Ȃ����Ƃ��N���[�Y�A�b�v����A���̂��Ƃ��䂪���̈�t�s���ɔ��Ԃ������Ă����B�v����ɁA�u�G�p�����߂��Ċ��҂�f�鎞�Ԃ��Ȃ��v��Ԃł������B
�@���̂��߁A��t��f�ËƖ��ɏW�������邽�߂Ɍ��J�Ȃ̎w���������ÃN���[�N�������̗p����邱�ƂɂȂ����B�܂��Ō�t�̒S����Ɩ����g�傳��Ă������B
�@�@�������āA�d�q�J���e����������n�߁A��ËƖ����e�E��ԂŌ݂��ɋ��L����邱�ƂŌ������������Ƃ��傫�ȕω��ł������B
�@���̂��Ǝ��͎b�����@�Ɩ����痣��Ă������A��N���n�r���a�@�̓��@�Ɩ��ɖ߂��Ă݂Ď��オ�傫���ς�������Ƃ��ĔF�������B
�@���Ȃ킿�A���̋Ɩ��͊Ō�t�A�P�[�X���[�J�[���܂ގ����E���A�P���m��̃X�^�b�t�ɑ����ʂ���x�����đ啝�Ɍy������Ă����B
�@��̑O�Ɣ�r�ɂȂ�Ȃ���Ԃł������B
4/2�i�j�����@���ʕa�@�O���@?2:15�N���A�����E�{�ǂݑ��A�~�σf�[�^�����A�k�R�B���{���Ȋw��ւ̃G���g���[���܂������Ȃ��B5:30�R�S�~2�ܒ�o�B6:40�o�X�ѐ�a�@�B7:10-8:15�a���Ɩ��B8:45-12:30�O���B���G�Ȃ����敾�B12:30���ʃ��n�a�@�A�����ȂǁB14:30���҉Ƒ��ʒk�A�a����A�V���@����B17:00�V���`�F�b�N�A���́A�����B19:30�A��A�[�H�A21:00�A���B���s�v6813���B??�V�N�x(2024)�X�^�[�g�@ ���N�x�A�J�\��ƃR�����g(2)�@
�@���͍�N���璆�ʃ��n�r���e�[�V�����a�@�ŏ�����Ƃ��ē����Ă���B���̒��̗×{�a����15-6���̓��@���҂������Ă���B
�@�T�̂����I�����n�r���a�@�̋Ɩ���S����͖̂ؗj���݂̂ŁA���̓��͌ߑO�͖@�l���̐f�Ï��A�a�@�Őf�É������Ă���B
�@�v����ɁA�ʏ�̔����̋Ζ����ԂŃ��n�r���a�@�̕a���Ɩ������Ȃ��Ă��邱�ƂɂȂ�B����͌��\�����B
�@���N�x�͌��j���̌��N�N���j�b�N���̋Ɩ����O���ė~�����|�l���ɐ\�����̂ł��邪�ʂ�����Ȃ������B
�@���̂��߂ɍ��N���A���j�A�Ηj�̒��͖���A���j�̒��͕a���̊��҂̏�Ԃɉ����ĕs����ł��邪7:00�ɏo���a���Ɩ������Ȃ��A���̌�Ɋe�a�@�Ɉړ����Ă���B���j�͐V�����ő�Ȃ܂ŏo������B
�@���������`�Ԃł̕a���Ɩ��̏����͎��ԊO�̒��ߋΖ��ɑ�������B���̏ꍇ�ɂ͋A�@��͔敾���Ă��炭�Ɩ��ɏA���C�͂��N���Ȃ����玩���ŋx�{���Ƃ�B�����瑊�E����Ƃ�Ƃ�̓������Ƃ������ƂɂȂ�B�����璴�ߋΖ��̎葱���͂��Ȃ��B
�@���̐f�Õ���Ƃ��č�N�܂ł͔ѐ�a�@�̓������Ɩ���6�|7��/���قǂ����������݂͈�Ȃ��B���̖ʂł͊J���������邪�A�����T���E�x�����C�ӂŏo���ĕa���Ɩ������Ȃ��B
�@���@�́A50�N�Ԓn��ɖ��������u���n�r���e�[�V�������a�@�v�Ƃ��āA��Q�̂���l�B�����߂��Â╟���̌����ڎw���A���̉��P�̂��߂̈�ÁA���n�r���e�[�V�����Ɏ��g��ł��Ă���B
�@���n�r���e�[�V������Â̖ړI�͏�Q�̂���l�B�́u�����̎��v�u�����̎��v�u�l���̎��v��L���ɂ��邱�Ƃɂ���B���̍ہA���n�r���e�[�V�����́A�u�g�̋@�\�̃��n�r���e�[�V�����v�ƂƂ��Ɂu�S�̃��n�r���e�[�V�����v���d�����Ă���B
�@���͂܂����̕���̌o���͖R�������A���X�ɕa�@�̑��݈Ӌ`��n�r���e�[�V��������̃X�^�b�t�B�̋Ɩ����e���킩��n�߂Ă���B���㎋����L���Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ǝv���Ă���B
�@���@�͊Ō암��A�P������̃X�^�b�t�͑����ĎႢ�B
�@����10���N���������Ƃ̂Ȃ������Ⴂ�l�����̐��𗁂тȂ���A���͍���̐g�̂����t���b�V�����Ă���B�@?
4/1�i���j�����[���~�J�@�V�N�x�X�^�[�g�@���N�N���x�f�@�Ɠ���w��f?1:45�N���B�{�ǂ݁A�f�[�^�����A8:30�Ɠ��ɓ���a�@�A10:00�a���Ή��A�Ɠ���w��f�A�V���@�A�x���������҂���B�ߌ�����l���\���Z�B�V���`�F�b�N�Ɠ��́B�f�[�^�����Ȃ�19:00�A��A�[�H�A20:30�A���B���s�v3407���B??�V�N�x(2024)�X�^�[�g�@ ���N�x�A�J�\��ƃR�����g(1)�@?�@�{���͐V�N�x�X�^�[�g���B
�@���͂��������A���N�͖��a���͏A�ƌp���̐���������Ȃ����낤�A�Ǝv���Ă������A���ʃ��n�r���e�[�V�����a�@�̏�����t�𒆐S�Ƃ����A�J�p���̈˗����������B
�@���̗͑͂�J���\�͂������Ă��邩��A�J�X�V�ɂ͂����ɓI�ł��������A�Ɠ������������Ƃ̈ӌ��������A���̃o�b�N�A�b�v�̂��߂Ɏ��������邱�ƂɂȂ����B
�@�L��\���o�ł��������A��l�Ƃ�����Ō��N��̌��Ă�����B���e�I�ɂ͈�N�_��ł��邪�A���܂ő������͕s���B�Ȃ�Ƃ��@�l�A�a�@�A���҂����ɖ��f�����͂��������Ȃ��B�����������Ӗ��Ŏ�ْ��C���ł���B
�@���j���ߑO�����͉��|�A���d�����A����̊O���̎d�������Ȃ����߂Ƀt���[�ɐݒ肵���B
�@�ȉ������N�x�\�肳��Ă��鎄�ƉƓ��̋Ζ��X�P�W���[���ł���B
�@���N�x�̎��̏A�J�\��
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ߑO�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ߌ�
���j�@�@�@�@�@�@���N�N���j�b�N�@�@�@�@ �@�@�@�@���n�r���e�[�V�����a�@�@
�Ηj�@�@�@�@�@�@���ʑ����a�@�O���@�@�@�@�@�@�@���n�r���e�[�V�����a�@
���j�@�@�@�@�@�@�@(�t���[)�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ ���n�r���e�[�V�����a�@
�ؗj�@ �@ ? ?�@�@���n�r���e�[�V�����a�@�@ �@�@�@���n�r���e�[�V�����a�@
���j�@ �@�@�@�@ ��Ȓ��ʕa�@�O���@ �@�@�@�@�@�@�A�@�ナ�n�r���e�[�V�����a�@?
�y�E���j���E�Փ��̓t���[(�K�X��f�\��j�@
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�@�Ɠ��̏A�J�\��
�@�Ζ��͌��j������j���A�ߑO�ߌ�Ƃ����ʃ��n�a�@
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�@�V�N�x���}���đ����ْ̋��ƕs���������Ă���B
�@�A�J�X�V�ɓ������āA���j�ߑO�̌��N�N���j�b�N�̋Ɩ����甲���邱�Ƃ�l���S���҂Ɋ�]����������Ȃ������B
�@����15-6���̓��@���҂������Ă��邪�A�T�̂����I�����n�r���a�@�̋Ɩ���S����͖̂ؗj���݂̂ł���B�v����ɔ����̋Ζ����Ԃŕa���Ɩ������Ȃ��Ă��邱�ƂɂȂ�B����͌��\�������Ƃł���B
�@
3/31�i���j�����@�R���|�X�g������@�}�Ւd�܋l��?�@2:15�N���B�l�R�����ƑΉ��B�f�[�^�����B�����ȂǁB11:00�Ɠ��������U����t�T���ق̑��V�ɏo�ȁB12:00NHK�j���[�X�A�̂ǎ����A�僊�[�O�ꕔ����B14:00-15:30�O�d���A�R���|�X�g���������A�}�ْf�܋l�߁A�K���[�W2F�����ȂǁB���j�^�C�������ɗ��K�B15:30�Ɠ��ɓ��惊�n�B���@���҂͗��������Ă���B�V�����́A�����ȂǁB19:00���̈�l���w�Z���ƂōL�ʌo�R�A��A�[�H�B20:30�A�Q�B���s�v5013���B�X�L�[�E�G�A�������̍�ƕ��ɒ��ւ��B?
�k�R�L�q��
3/30�i�y�j�ߑO����~�J�@��H�����R�C�ɏ����a?3:30�N���B�O�_�O�_�l�R�Ή��A�V���`�F�b�N�Ɛ���B�����ȂǁA���H������B�Ǐ��B�K���[�W2F�_�������B�U���p�z�[�X�𐅓��Ɍq���B�T�����[���ɃV�N�������p�Ԃ����ݒu�B�o���オ�����R���|�X�g�̓��e�l�߂ɁB15:30�Ɠ��ɓ���a�@�A��H�����̓R�C�������C�B�ېH�����͂܂��݂��B���x�̏�ɒʘH���o�����B�n�X�p�H���҂͗��������Ă���B�V�����́A�����B19:00�A��A�[�H�A20:30�A���B���s�v2094���B�{������Y�{���̃C���i�[���O�����B??�k�R�L�q��
3/29�i���j��������~�J�@��Ȓ��ʕa�@�@�@?�@1:30�N���A�f�[�^�����A�����ǂ݂Ȃǂ����̂��Ƃ��B�k�R�A5:30�R���ݍ~�J�̂��߂ɒ�o�����̂݁B7:35Taxi�w�ɁA�W:11���܂��B9:50��Ȓ��ʕa�@�ATaxi�B�A�H�̐V�����͓�����Ԃʼn^�x������ő�3���Ԃ��x��B15:40���艮�o�R���ʃ��n�B16:30���@���ґΉ��B19:15�A��A�[�H�B21:00�A���B���s��5398���B??�k�R�L�q��
3/28(��) �����@?3:30�N���B�܂��̒���s�ǁA�P�Ƃ����A���M�Ȃ��B���������A�k�R�ق��B8:20�Ɠ��ɓ���a�@�B�x������A���҂͔�r�I����B�V���@����B�ߌ���Ή��B15:00���҉Ƒ��ʒk�A16;30���҉Ƒ��ʒk�A�V���`�F�b�N�A���́B19:30�ʒ����X�o�R�A��B�[�H�A21:00�A���B�����v2389�B??�k�R�L�q��?
3/27(��) �����@���̎��Á@��lj�@�a���J���t�@ �Ɠ������?2:10�N���B���������A�k�R�ق��B8:30�Ɠ��ɓ���ѐ�a�@�B10:00�a���A10:30-12:30���̎��ÁA���[�U�[���ÁB13:00��lj�A�P4:30�a���J���t�@�B�̒����s�ǁA�V���`�F�b�N�Ɠ��́B�Ɠ������A18:20�o�X�ŋA��B�[�H�A20:00�A���B�����v3460���B?
�k�R�L�q��??
3/26�i�j�����@���ʕa�@���ȊO��?1:30�N���B�V���`�F�b�N�A�{�ǂ݁A�k�R���B5:00�R�S�~��o�B6:40�o�X���n�a�@�B7:10-8:15�a���Ή��B8:40-12:50���ʕa�@���ȊO���A�敾�����B�A�@��̒��s�ǁA���ׂ��H�����A�Ǐ��B16:00�a���Ή��B19:15�A��A�[�H�B20:15�A�Q�B��5379���B��N�ѐ�a�@���ʂ�̉�A�퍂��فB??������Ƒ�2024(8) �D�_�s�f�E�E�W�E�W�l�Ԃ̏����p(5)�@�ߋ��̎��s����
�@�u�ߋ��̎��s�͂����ƁA�Y��悤�v�Ǝ����Ɍ�����������̂ɖY����Ȃ��B�����̂������������邽�щߋ��̎��s����݂�����B
�@�ߋ��̎��s�����܂ł�������A���ȋC���ɂȂ�͎̂��ۂɂ́u���s�������Ɓv����������Ǝ~�߂Ă��Ȃ�����B
�@����Ȍ����F�߂Ȃ��ŁA�u�Y���A�C�ɂ��Ȃ��悤�ɂ��悤�v�A�Ɩ����Ɉӎ�����ƁA���s�̃C���[�W���悯���[�����ݍ���ł��܂��B
�@�ߋ��̎��s�����������ɂ́A���̎��s��������ƔF�߁A�������邱�ƁB
�@�ǂ�Ȃ��Ƃ��݂������A���̂Ƃ��������������������A�����ɕ����������A����ɍ��݂��������A�Ȃǂ�ے肹���ɔF�߂邱�ƁB����Ă������̂�������Ǝ��o�����ƂŁA�ߋ��̎������A���̎������[�������邱�Ƃ��ł���B
�@�ߋ��̎��s��Y�ꂸ�Ɏ�����F�߁A���s����������ے肵�Ȃ����Ƃŏ��߂āA�u���s�����v���Ƃ��ł���B
�@�v���b�V���[�͐�������A�ƌ����Ă��A�u�����ɂ���Ȃ��Ƃł��邩��?�v�u���Ԃ����낤�ȁv�Ɗ����Ă��܂�����������B
�@��������U�ǂ��܂ŗ��Ƃ��Ă݂邱�Ƃ́A�J������ɂȂ���B�J������́u����ȉ��ɂ͂Ȃ�悤���Ȃ��v�Ƃ����n�_���m���߂邱�ƁB�����ɗ��Ă}�C�i�X���A�v���X�̉ۑ��ڕW�ɕς��B
�@�u���M�v�Ƃ͉����B
�@�������ǂꂾ���M�����邩�A���ꂪ���M�B
�@�{���̎��M�Ƃ́A�u�����͉����ł��āA�����ł��Ȃ��̂��v�𗝉����Ď���Ă���Ƃ������ƁB���ꂪ�{���̋����ł���B �����đ��l������邱�Ƃɂ��Ȃ���B
�@�{���ɋ����l�Ԃ́A�����̎コ��m���Ă���B�����Ďコ��F�߂Ă���B ���ꂪ�܂��Ɂu���M�v�B
�@�����S���w�̖{�Ȃǂ�ǂݎn�߂��̂́A����ȋꂵ���̒��ł������B�{��������e�Ȃ�Ĕ��X������́B�ǂݑ����ēǂݑ����āA���ɂȂ��Ă���Ƃ��̌��ʂ��o�Ă����l�ȋC������B
3/25�i���j����@���N�N���x�f�E�f�[�^�`�F�b�N�@�z��Ȏ�f�@������?�@1:30�N���B�{�ǂ݁A�k�R���B8:30�Ɠ��ɓ���a�@�A���N�N���j�b�N�͔N�x���ŋx�f�A11:00�f�[�^�`�F�b�N�Ɍ��N�N���j�b�N�ցB�z��Ȏ�f�A���҃f�[�^���͂��̑��B
�����A���@���ґΉ��B3F�ɂăR���i���������A19:00�A��A�[�H�A21:00�A�Q�B��4107���B�����ɓ����A�R���܂�421Km�B�{���܂ł̗v�f�[�^�A3398�����A4006���A6006���� �A27190km�B??������Ƒ�2024(7) �D�_�s�f�E�E�W�E�W�l�Ԃ̏����p(4)�@�u����Ȃ�(2)�@
�@���͐l�O�łɏo�邱�Ƃ͋��ł��������A���������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B
�@�V�^�x���̔������ɂ͂��łɈ��ނ��Ă������A�C���t���G���U�������A�Ƃ�킯�V�^�C���t���G���U�������ɂ͌���t����ǒS���Ƃ��ă��W�I��TV�Ō��������̌[�֊�������10������Ȃ����B������̗[���ɂ�NHK�A����3�Ђ̔ԑg�ɂقړ������ԑтɓo�ꂵ�����Ƃ��������B
�@���W�I��TV�ԑg�ł͂��炩���ߌ��e��p�ӂ���̂ł��邪�A���e�̑��݂��l�������Ȃ��悤�Ȍ����Ő�������̂͑�ςł������B
�@�u���E�u�b�����������B���̏ꍇ�́A�قƂ�ǂ̏ꍇ�A���O�ɗp�ӂ����X���C�h���f���Ȃ���s�Ȃ����B�����Ă���������ɘb���Ă�����e���킩��₷������ړI�����������A��{�͎����̂��߂ɗp�ӂ����J���j���O�y�[�p�[�̗l�Ȃ��̂ł���B
�@�D�_�s�f�E�E�W�E�W�l�Ԃł����Ă������ȏ��z����������B
�@���ꂮ����u���ꂶ��_�����v�Ǝ�����ے肵�Ȃ����ƁB�u�ǂ������������̎������m�肷��v���ƁB�u���͈ȏ�Ɋi�D�ǂ���낤�Ǝv��Ȃ����Ɓv���ꂪ��Ȋ�{�ł��낤�B
�@�u�����͎������A���l����ǂ������悤�ƊW�Ȃ��v�Ƃ�����v���Ă��A�ǂ����Ă��l�Ɣ�ׂĂ��܂��B���͎��ӎ��ߏ�l�Ԃł������B
�@���l�̎�����A���l�̕]�����C�ɂȂ�A���͐l�̑O�ł͂����r�N�r�N���Ă����B
�@����͎d���̂Ȃ����Ƃ��B���͎q�ǂ��̍����炸���ƁA���̎q���Ɣ�ׂ��A�]������Ă����B���ɗD�G�ł������Z�Ƃ�����ׂ�ꂽ���Ƃ��g���E�}�ɂȂ����B
�@�������A���l�̖ڂ��܂������C�ɂȂ�Ȃ��Ƃ�����A���l�̋C���������l�̑��݂��C�ɂȂ�Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�A���l�C�łӂ݂ɂ��肩�˂Ȃ������ɂȂ�B�q�g�͈�l�Ő����Ă��邾���łȂ��A���l�̒��ł������Ă���̂�����B
�@���l�̖ڂɉf�鎩�����C�ɂȂ邩��A�����̃C���ȕ����͉B�������B�����v���͎̂��R�Ȃ��ƁB
�@�����A����ł��݂�ȂɎ���Ă����Ȃ���ƁA�K���ŕʂ̎����������Ă����B�{���͒f�肽���B��l�ł����ق����C�y�ł����B�ł��f��Ȃ��B ���̂��ƈ�l�ɂȂ�ƁA�җ�Ȏ��Ȍ����ɂ����������B
�@�����S���w�̖{�Ȃǂ�ǂݎn�߂��̂́A���̋ꂵ���̒��ł������B�{��������e�Ȃ�Ĕ��X������̂��B�ǂݑ����ēǂݑ����āA���ɂȂ��Ă���ƌ��ʂ��o�Ă����l�ȋC������B
3/24�i���j�I���������A���g�A���O�d���@���R�ō��J�ԁ@�V�����D���o���@?�@1:30�N���B�V���`�F�b�N�A�{�ǂ݁A���B11:30�Ɠ��͕a�@�ցA���g�A���O�d���A���]�Ԑ����A��}����ȂǁB�E�I�[�L���O�V���[�Y�ɁBNHK�̂ǎ����A�V���`�F�b�N�A�����A�}�גf�B�Ǐ��A19:00�[�H�B20:30�A�Q�B��4721���B??������Ƒ�2024(5) �D�_�s�f�E�E�W�E�W�l�Ԃ̏����p(3)�@�u����Ȃ�(1)�@
�@�u���ꂽ���ɐK���݂��邱�ƂȂ��A�����̎��Ă�͂�100%�o�����Ă���l�͂قƂ�ǂ��Ȃ��A���낤�B
�@�������̗͂𐔒l���ł���Ƃ���Ζʔ������A�ɂ߂č���ŐM�ߐ����Ȃ��B�����Č����A����������%-��10%���x�Ǝv����B�����̐l�͎��ӂ̏��v���b�V���[�ɂȂ莩���̔\�͂��ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ���??? �Ǝv���Ă��邪�A���l�̂��Ƃ͂悭�킩��Ȃ��B
�@�������Ȃ���A�����Ȃ����낤���A���ʂȐl�����A�Ⴆ�A�e�E�̃v���Ƃ��ēV�˓I�Ȋ��o���������l��A�|�p�ƂƂ��ĕ\���̕�������l�A�A�X���[�g�B�Ȃǂ́A�������Ƃ����Ƃ��ɗ͂�����s�v�c�ȗ͂�̓����Ă���A�Ǝv����B
�@���y�̕���ł��������̉��t�ƁA�\���X�g�����̉��t�������A�����̏�Ŏ��ɂ��킩��悤�Ȗ��炩�ȃ~�X�ʼn��t���_���ɂȂ�����ɑ����������Ƃ͂Ȃ��B����͓��M���ׂ��A�����ׂ����Ƃł���B
�@���̗l�ȉ��t�Ƃ͒u����Ă��闧������Ď�����\�����A���݂Ɏ����Ă����悤�ȋ��x�ȐS���\���������Ă���Ƃ����v���Ȃ��B���̔w�i�ɂ́A�e���t�Ƃ̐��i�����邾�낤���A�c���̎�����̌��������ȏC���A���K����b�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ͊m���ł��낤�B
�@10���Ȃ��瑽���̓�Ȃ�e�����Ȃ��A�A�����J�̃J�[�`�X���y��w�ɐi�w�������{�l�̖^���@�C�I���j�X�g�����͖���8���ԗ��K����Ƃ����B���������w�i�����Ƃɗ͂������ł���l�ɂȂ�̂ł��낤�B
�@���͉��̓��Z���Ȃ��}�˂ł��邪�A�����u�����u�b�A�e��̈��A�Ȃǂ͑������Ȃ��Ă����B���̏ꍇ�́A��������C�s�������킯�ł͂Ȃ��B
�@�����A�u���Ȃǂ̏ꍇ�A�\���ȉ����������邱�Ƃł��������A����ł����ɂ͂��܂������Ȃ��������Ƃ��������B
�@���͒ʏ�͘b�����ƂɎx��������邱�Ƃ͂Ȃ����A�̐S�̏�ʂɂȂ�ƁA�Ƃ���ɏ��ɓI�ɂȂ�A����������B�Ⴆ�A��ȂǂœˑR�w�����ꂽ�肷��ƁA���t���o�Ă��Ȃ��B
�@������A���O�̑O�ň�莞�ԁu���e�̂���b�v������u���́A���ł������B���A�ǂ����Ă��f�邱�Ƃ̂ł��Ȃ��u���˗�������B��������Ȃ����́A������Ə��������B
�@
�@�悭���e����������Ȃ��ŁA�����悤�ɘb���u�����̐l�����邪�A���������l��S���炤���܂����v���B���ɂ͂��̔\�͑S���Ȃ��B
3/23�i�y�j�����@MISAWA���K���t�H�[�����ς���?�@1:50�N���B�Ǐ��A�f�[�^�������B�ߑO�͍��w�����̔@���B10:00MISAWA���K���t�H�[�����ς���500���~���B��^�I���̈�D15:00�Ɠ��ɓ���a�@�ցA���@���҂̏��m�F�܂����������Ă���B���̌���w�B�f�[�^�����A�����A�����B19:00���c���o�R�A��A�[�H�B20:30�A�Q�B�k����1800���B??������Ƒ�2024(5) �D�_�s�f�E�E�W�E�W�l�Ԃ̏����p(2)�@�K�i�����э~���
�@���͌��f�͂��Ȃ��B
�@�������������傫�Ȍ��f����ɂ������ẮA�܂��������\���ɏW�ߌ�������B�\��������i�߂ꂪ��̑I�����i�݁A�قƂ�Ǔ�ґ���̏܂Ői�߂���B�����܂Ői�߂ǂ����f���Ă��[���ł�����̂ɂȂ�B
�@���̎��_�����͎����Ō��߂��Ȃ�����A�K�i�̒��i�����э~���l�ȋC�����œ�҂̂����̈�������I�������߂Ă��܂��B���̌�͂��̑I���������_�Ɍ������Ė������ƂȂ��܂�������ɐi��ł����B
�@���͎��ӂ̐l����������q�ɗ�����t���t���Ɛ����Ă������A���������f�����E�E�E�Ƃ������ۂ̑傫�Ȃ��̂��v�����܂܂ɋ�����ƈȉ��̔@���ł���B
�@��O�҂��猩��ǂ��ł��������̂��܂ނ��낤���A���̑I���͐_���ł������B
(�P)�Ƒ��̑唽���������ď���̃l�R���Ƃɓ��ꂽ�B
(�Q)�l�R�Ɨ���ɓ]���B
(�R)���������ɂ��䖝���Ӓ����͔^ᇁA�������ɁB
(�S)����̎��ɒ�����эZ��ފw�����B
(�T)�V����w��w����I�������B
(�U)���U�̃p�[�g�i�[��I��
(�V)���̈�Ƃ��Č��t�����̗Տ���I�яH�c��w�ŏC�������B
(�W)��Ö@�l�̒��ʕa�@�Ɉڂ����B
(�X)���s�����Ȋy����w�������B
(�P�O)�����N�̍�����̌��Ăł������N���d���ǂ̎�p�����B
(�P�P)�ސE��͉Ɠ��̕⏕�ɓO���邱�ƂɁB
(�P�Q)�ȂǂȂǁE�E�E�E�E�B
?
3/22�i���j�܂�@�ϐ�2?�Rcm ��Ȓ��ʕa�@�O���@?�@1:50�N���B�����֘A�������A5:30�R�S�~�Q�ܒ�o�B�ϐ�2?�Rcm����A�v�X�\���ʼn^�ԁB���\�S���ɂ���B7:40Taxi�w�B8;11���܂��B8:50��Ȓ��ʕa�@�O���B���艮�Ï��X�o�R�A��B�P5:30���ʃ��n�a�@�ɂē��@���ҏm�F�B19:30�A��B�[�H�A21:00�A�Q�B�k����5162���B??������Ƒ�2024(3) �D�_�s�f(3) �Q�l�ƂȂ�������(2)�@���E�W�E�W�l�Ԃ̃T���v��
�@��l�����E�W�E�W�^��2��i�̏Љ�B
�i�W�j�w�߂���ꍏ�x���������q���@�S15���i���w�فj
�@��ƍ��������q���̒��Җ���B�{���A�p�[�g�u�ꍏ�فv�̔��������ƊǗ��l(���q)�Ɩ��E�̓�����(�ܑ�)�𒆐S�Ƃ�������B��l�Ƃ��T�^�I�E�W�E�W�^�l�ԂŌ݂��Ɉӎ��������Ă���̂����A�ς���Ȃ��B�o��l��������ɓn�邪���̍\�����`�ʂ��f���炵���B
�@�{��i��30�N�ȏ�O�ɂ���x�ǂB���̎��͕���Ƃ��ĐV�N�ȋ������������A����̓E�W�E�W�^�̎�l���������v���o���A�����̎p����l�������ɏd�ˍ��킹�Ȃ���ꌎ�قǂ����čēǂ����B
�@���̗l�ȃE�W�E�W�^�́A���W���̖R�����l�ԓ��m�̖͗l��15���ɂ��y�Ԓ��Җ���Ƃ��ĕ`������҂̍\���́A�{���߂��݂̐S��̕`�����Ȃǂɉ��߂Ċ��S�����B���̗l�Ȗ���͒j����Ƃɂ͕`���Ȃ��̂ł�??
�@��i�̑S�̂̐��i�͂ƂȂ��Ă���̂́A�Ǘ��l���q�̎���l�̖��͂ƓV���́u�͂��炩���v�̐��i�B����ɏ�������E�W�E�W�l�Ԃܑ̌�B��l�Ƃ��D�l���ŁA����̐l�X�A���ɂɗ�����Ďv���������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�@�I�ՂɂȂ��āA�ܑ�Ƌ��q�͂������͂ɂɂȂ�B�Ǘ��l���ŗD�_�s�f�ܑ̌��O�ɋ��q�͂ǂ�����đ���Ɋ̐S�ȑ䎌�����킹�����B�����オ�������q�́A���ɋ߂Â��J�[�e���������ƊJ����B�F���ۂ����p�B���q�́u�����炨�肢���Ȃ��Ⴂ���Ȃ���ł����v�ƁB�����Ɏ���Όܑ�͌��f������Ȃ��B�{�S�����t�ɂ��Ȃ����Ƃő�������炵�A�̐S�Ȕ����������o����l�̋Z�@���B
�@����A�ēǂ��ăE�W�E�W�^�l�Ԃ̔Y�݂Ɛl�ԓI���͂̈�ʂ��Ċm�F�����B�E�W�E�W�^�l�Ԃ��̂Ă����̂ł͂Ȃ��B
�i�X�j�u���������R�[�q�[�̂�����v���R�R�����@�S19��(�W�p�Е���)
�@1994�N���瑱���A26�N���̍Ό��������ăO�_�O�_�Ƙb��i�߂č�N�����������ҕ���B���҂̑��R�R�������̂��E�W�E�W�^�ł͂Ȃ����Ɗ��J�����B
�@�ƒ�̎���œ������n�߂����Z���́u�����v�ƁA5�ΔN��̏]�Z��́u�����v�̗�����B�Ƒ��⓯���A������C�o�����܂߁A��������̐l�Ɍ�����Ă�����l�B
�@�u�����v�̓X�|�[�c���D�ޖ��͓I�l���Ȃ̂����̐S�ȂƂ���ł͒��E�W�E�W�^�l�ԁB�u�����v�͉��Ő����Ȗ��͓I�����B����3�N�قǑO�ɂ��̍�i�̂��̑��݂�m��A17�����܂Ƃ߂ēǂB
�@
�@�j�������̎G���͗����̃v���Z�X���I�ɑ����i�߂悤�Ɛ�����̂��������A�u�����v�Ɓu�����v�̗��͂�����������炢�������i�ށB���́u�����v�̑ԓx�ɃC���C�����Ȃ���~�߂�ɂ���߂�ꂸ�S19����ǂݐ����A�Ƃ������ƁB
�@��l���Ɏ������d�ˍ��킹�āA�����̖��_������悤�Ȗ��킢��������A�V���[�Y�̐����œǂނ̂���߂Ă����ł��낤�B
�@�����̎p�̈ꕔ�����q�ϓI�Ɏ����Ă���悤�ȍ�i�ł���B
?
3/21�i�j�������~��A�ς��炸�@��J���Ӓʖ�̃g���u���Ō���?�@1:40�N���B�����֘A�������B9:00�Ɠ��ɓ���a�@�B�Ǐ��A10:00�a���Ɩ��A�V���@����B�މ@���҂̏��ށA�����ȂǁB13;30�����B14:30���@���ҏ��u�Ή��B�V���`�F�b�N�{���́B���W�I�ő告�o�����B�V�����S���͎m�s�ꂽ�B��J���Ӓʖ�̃g���u���Ō���19:30�A��A�[�H�A21:00�A�Q�B�k����3150���B??
�@���͖{���D�����B�����ނ��D�ށB
�@��ʓI�ɏ����͓o��l���̐S���I�`�ʂ����S�ɕ`����邩��A�E�W�E�W���i���o�Ă���Ǝ�����ǂ�ł���悤�ŐS�n�悢�B����ł́A�ǂ�ł��āu���ł���ȂE�E�v�ƃC���C�����邱�Ƃ������B
�@�E�W�E�W�ƌ��߂��Ȃ����͗D�_�s�f�̎�l�����o�ꂷ�镶�w���̑��̍�i�����͍D���ł���B
�@�����A�{�����������ɉ����I���⌈�f���������Ƃ͖w�ǂȂ��B
�i�P�j�Ėڟ��̍�i
�@�u��y�͔L�ł���v�͗�O�I�ɖ��邢���A�u������v�u���ꂩ��v�u�V�����v�u�����v�ȂǂȂǂ̍�i�͗D�_�s�f�̎�l�����o�Ă���B���ꂪ�ǂނ��̂ɁA����A���ɂƂ��ĉ����Ȃ̂ł���B
�i�Q�j�w�f�~�A���x�w�b�Z���A���������i�V���Ёj
�@�w������ɓǂ{�B
�i�R�j�w�~�b�h�i�C�g�E���C�u�����[�x�}�b�g�E�w�C�O���A��q����i�n�[�p�[�R�����Y�E�W���p���j
�@�u���f�̂��ׂĂ��Ђ����Ăv�ƌ���ɂ܂݂�A���E���悤�Ƃ���35�̎�l�����A�s�v�c�Ȑ}���قɖ������ށE�E�E�B
�@�l���͌��f�̌J��Ԃ��B�ǂ���̓���I��ł��A���̌�̍s���ɂ���ėǂ��ق��ւ��������ւ��]�����Ă����B���s������܂��V�����I������������̂����E�E�E�A�Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ��B
�i�S�j�w���̔N��i�Ƃ��j�������I�x���䏇�q���i�W�p�Ёj2012
�@�L������27�l�̓]�@�ƂȂ����N��ɃX�|�b�g�āA���̐l����ǂ݉����B�������猈�f���Ă��܂������B�Y��ł��鎞�Ԃ����������Ȃ��I
�i�T�j�w���肠�鎞�Ԃ̎g�����x�I���o�[�E�o�[�N�}�����A�������q��i���o�Łj2022�N��
�@������������x�̔N��ɂȂ��āA���Ԃ͑����Ă������̂ł͂Ȃ������Ă������̂ȂƁA�ł��������(����Ǝ���=�W���l�̖@��)�B������A�Y��ł���ɂ͂Ȃ��̂��B
�i�U�j�w�S�z����9���͋N����Ȃ��@���炷�A������A�Y���u�T�̋����v�x�e��r�����i�O�}���[�j
�@���������f����Ƃ��l�K�e�B�u�Ȃ��Ƃ���l���Ă��܂��������������A���̖{��ǂ�ł���A�����|�W�e�B�u�ɂȂꂽ�C������B
�i�V�j�w�䖝���Đ�����قǐl���͒����Ȃ��x��ؗT��i�A�X�R���j
�@���f�Ŗ����̂́A����ɋC�������A�U���āA�����̔��f���ł��Ȃ�����A�Ƃ��������Ɋ�Â��A�����������������@�������Ă���B���҂͐S�Ó��Ȉ�B
3/20�i���j �t���̓��@�~�J�����@
�@1:45�N���B�����`�F�b�N�A�{�ǂݒ��S�ɉ߂����B�Ǐ��A�f�[�^�����B13:30�s�[�R�b�N�ɍs���Ɠ��ɓ���a�@�B�a���͗��������Ă���B�Ǐ��A�����A�f�[�^�����ȂǁB18:30�A��E�[�H�A�؍��ł̃h�W���[�X�J����r���܂Ō���B�_���r�b�V��vs��J�B20;30�A�Q�B�k��1827���B��N�A�ŏI�����Ɩ��B??������Ƒ�2024(1) �D�_�s�f(1) �E�W�E�W�l�Ԃ̏����p?�@�D�_�s�f�Ȑl�����͌����ł���B�ہA����ǂ��납�����������o����B
�@�D�_�s�f�Ȑl�Ƃ́u�C��ŁA���܂ł����肪�������������������A�͂����肵�Ȃ����i�̐l�̂��Ɓv�B�����ς�l�̐��i��ԓx��\����ۂɃ��K�e�B�u�ȈӖ��ŗp������B
�@���`��Ƃ��āA�u���v�u�_��v�u�y�э��v�u�ς���Ȃ��v�u�ϋ^畏��v�ȂNj�������B�u���M���Ȃ��A�ӎu���ア�A���r���[�ȑԓx�v�Ƃ����Ӗ��������F�Z���B�u�ϋ^畏��v�́A�^���A���߂炢�A���̂��ߌ��f�ł����ɂ��邳�܂��Ӗ������Łu�ȋ^�S�v�̃j���A���X������B
�@�����g���D�_�s�f�l�Ԃ̓T�^�ł��邱�Ƃ��玩���Ƃ��Ă͕��G�ł���B
�@�D�_�s�f�قƂ�ǂ��ׂĂ̐l���A�����ꏭ�Ȃ��ꂱ�̗l�Ȑ��i�����˔����Ă���A���ꂪ�ז����Ď����̖{�������Ă���͂��o�����Ƃ��ł����ɂ���A�Ǝv����B
�@���̏͂Ƃ����A�������Ƃ����厖�ȂƂ��ɋْ����ăK�`�K�`�Ɍł܂��Ă��܂�����A���͂��C�ɂ��Ď����̃y�[�X�����߂Ȃ�������A�v���b�V���[�ɏk���܂�����A�ߋ��̎��s�ɂƂ���Ă�����A�����̓_���ȂƎ��Ȕے�ɂ͂܂��Ă�����ȂǂȂǁE�E�E�E�E�B
�@�܂�u�u���ꂽ�ɕ����Ă��܂��v�A�u�ł���ア�v�Ƃ������ƁB
�@�����g�́u���ӎ��ߏ�v�l�ԂŁA�c���̍�����A�u�Ԗʏǁv�A�u�ΐl���|�ǁv�ɔY��ł����B�w�����ォ�獡���Ɏ���܂ŁA�u���̂Ȃ̂��v�Ǝ�����ӂ߂��藎������ł����B
�@�{�̐��E���瓾���m���ŁA���邢�͑��l�̎p���Q�Ƃ��Ȃ���A�X�C�b�`��芷����H�v�����Ă����B
�@�������B�������_�́A
�@�����f�̂��߂̎������\���W�߂Č������邱�ƁB
�@��8�����S�����܂������_�ŁA�v�����Č��_�����߂Ă��܂��B
�@�����ɂ͐����̕��䂩���э~���A���Ƃɋ߂����f�̂��Ƃ�����B
�@������ȍ~�͊�����āA�E�W�E�W�Y�܂Ȃ����ƁB
�@��L�̉ߒ���ʂ��Ď��͎�X�̌��Ď����������Ă����B�����A���Ȃ�̌댈�f���A�㏈����K�v�Ƃ����B���ꂪ�A���l�ɂ͌������Ȃ������̏�Ȃ��p�ł���
�@���������āA�ǂ��܂ł��{���Ɏ����̊����̐��ʂ����f�ł��Ȃ��B�Ƃ����̂��A�N�ł��u�ł��ꋭ���Ȃ�v�f�{������Ǝv���B
�@�u�����͂���Ȑl�Ԃ���Ȃ��v�u�����͌��f�͂��Ȃ��ă_���Ȑl�Ԃ��v�Ǝv���Ă����Ƃ��Ă��A�������甲���o���͎͂����̒��ɂ���n�Y�A�Ƃ��v������ł���B
�@�����A���͑��l�̂��Ƃ͂قƂ�Ǖ�����Ȃ��B
3/19�i�j�����@51�N���N ���ʕa�@�O��?2:00�N���B�����`�F�b�N�ȂǁB�V���`�F�b�N�k�R�A�~�σf�[�^�����B5:50�R�S�~�p���͏����̂݁B6:40�o�X�a�@�A7:10-8:15�a���Ή��B8:40-12:15���ʕa�@�O���B12:30���n�ցB�����Ǐ��A15:00�a���Ή��B�V���`�F�b�N�A���́B19:00�ʒ����X�o�R�A�A��A�[�H�B20:45�A�Q�B�k����5627���B����52��ڂ̋L�O���B??�k�R�L�q��?
3/18�i���j�~�J�r��͗l�@���N�N���j�b�N�@���ʎ��ȉ����Ή�?1:30�N���A�����E�k�R�ق��������̔@���B6:40�o�X�ѐ�a�@�B7:10-8;20�a���@9:00-11;40���N�N���j�b�N�h�b�N�{���ʔ���15���B���ʃ��n�a�@�ɁB13:00�a�@�a���Ή��A15:00���ʎ��ȉ����Ή��B16:30�a���Ή��A�V���@���茳�q�q�����B�V���`�F�b�N�ł����B19:20�A��A�[�H�A20:00�A���B�k����5140���B��N���ʃ��n�a�@�����ƂȂ�@??�k�R�L�q��?
3/17�i���j�܂菬�J�@?2:30�N���B�����E�^���f�[�^�A�Ǐ��A���̑��̐����ʼn߂����BMISAWA�z�[�����C���e�i���X����B12:00NHK�̂ǎ����B�V���`�F�b�N�A�����B15:30�������̉Ɠ��ɓ���a�@�B���ԏ�ŕs���Ȏ�҂Ɖ�B�[���͊ւ�炸�B�a���͗����������Ă���B�H�c��w�@�֎��u�{���v�ŏ��ʈ�t�̋L�q��ǂށB19:30�A��[�H�A�����O�ꂽ�B20:30�A���B��800���A���C��ɖY�ꔼ���̂݁B�^���s���͑����B??�k�R�L�q��?
3/16�i�y�j�܂�����ƕs��@�Ɠ���H���������C���e�i���X?2:15�N���A�V���E�����E�k�R�ق��B�^���f�[�^�����B�ߑO�͓Ǐ��B�V���f�[�^�����A16:00-17:00MISAWA�z�[���X�^�b�t���K�A����̃��C���e�i���X�ɂ��āB19:15�Ɠ��A��[�H�A20:30�A���B�k����2519���B??�k�R�L�q��??
3/15�i���j�@�܂�����ƕs��@��Ȓ��ʕa�@�O��?1:50�N���B�����ǂ݁A�f�[�^�����Ȃǂ����̔@���B5:30�S�~�o��45L�̑�2�܁B7:40Taxi�H�c�w�����B8:12���܂��B�ŋߍ���ł����B�W:50�O���A15:45���艮�Ȃ��ŕa�@�B16:00�a���Ή��A�����ȂǁA�V���`�F�b�N�{���́B����2���B�Ǐ��B19:30�A��A�[�H�B21:00�A�Q�B�k����5520?�B??�k�R�L�q��
3/14�i�j���J�̂�����@�\���Ɠ����I���@iPhone7+�d�r�����@?�@2:00�N���A�Ǐ��A�����̔@���B8:30�Ɠ��ɕa�@�A�I���Ζ��A��ɋx����������B11:00���@���ґΉ��B12:30�ߗׂ̐\�����ɉƓ����̐\���͂����I���Ƃ����BiPhone7+�̓d�r�����h���L�z�[�e�X�ɂāB�V���`�F�b�N�A����2���B�Ǐ��A19:30�A��A�[�H�A20:30�A���B�k����3186���B??�����{��k�ЁE��������2024(4) �G�l���M�[����͌������A�Ɍ������Ă���
�����]����G�l���M�[����
�@���d�����̌������̂�1�N����A����}�����́u2030�N��Ɍ����[���v�̖ڕW���ł߂��B�^�]���Ԃ�40�N���������i�ɓK�p���A�V�݂�݂͂��Ȃ����Ƃ������Ɍf�����B
�@�d�͂̈��苟����R�X�g���l����Έ�C�ɑS�p�͖������Ƃ��Ă��A�Đ��\�G�l���M�[�𑝂₵�A�[���Ɍ������ׂ����Ƃ̍l�����Ŏ^���ł����B
�@2012�N11�������}�̐������A��A�����[���̖ڕW�͏������B����ł����{�E�������́u�����ˑ��x���\�Ȍ���ጸ����v�Ƃ��A�V���݂⌚�đւ��͑z�肵�Ȃ��Ƃ��Ă����B
�@�����A�ݓc�����́A�����́u�ő�����p�v�ւƐ���]�����A�V���݁E���đւ���60�N����^�]��F�߂���j�����߂��B������F�̊J��������������Ƃ����A�����ɗ��葱���铹��`���B60�N���錴���^�]�́A�o�ώY�ƏȂ��哱���A���q�͋K���ψ�����������ŔF�߂��B
�@�����̐����]������̉����Ă����������A���X�ɂ��������Ƃ�n�߂Ă���B�䂪���̃G�l����͂ǂ��Ȃ�̂��낤��!!!
�@���ăG�l�g�傱������
�@�E�Y�f�Ɍ����ẮA���z���╗�͂̓R�X�g�ቺ���i��ł���B
�@�L��ȊC�������m�㕗�́A�r���̕ǖʂɂ��g���鎟���㑾�z�d�r�B���R���ƋZ�p�͂��\���ɐ������A�����Ŏ����ł���ăG�l�̎�͉��ɖ{�C�Ŏ��g�ނ��Ƃ������A�������B
�@�����͊C�O�ł��o�ϗD�ʐ����������Ă���B�u�j�R���T�C�N���v�̍s���l�܂��u�j�̂��݁v�̏����ȂǁA�������̖����R�ς����܂܂��B
�@�������{�͒n�k��Ôg�A���ȂǍЊQ�卑���B�\�o�̐k���n�t�߂ɂ͂��Ď�F�����̌v�悪�������B�k�Ў��ɂ͓��H�����f����A���v�悪���藧���Ȃ�������������B
�@���̂̋��P��Y�ꂸ�A�����ɗ���Ȃ������i�ށB���̓���ۂĂ邩�̕���_�ɁA���{�Љ�͗����Ă���B
�@�ăG�l�͑��z�����d���������Ē��ɓd�C���]��n�߁A���ɂ͏o�͐�����K�v�Ƃ���܂łɂȂ����B�d�C�͒~�d������B ���̂��߁A�n�悲�ƂɕK�v�ȗʂƔ��d�ʂ̃o�����X�߂��Ă���B
�@���q�͂Ɛ��́A�n�M�ׂ͍��Ȓ����͂��Ȃ�(�ł��Ȃ�??)�炵�����{������?? ? ?�t�����X�Ȃǂł͔�r�I�ׂ₩�Ɍ����̏o�͂����Ă���Ƃ����B
3/13�i���j�܂�@���Ȏ��Á@�Ɠ�MRI �u����?1:30�N���A���������֘A�ق��B �Ɠ�MRI�̂���7:50�o�A11:00-13:00���Ȏ��ÁB�����A14:30�a���J���t�@�A���ҏ��u�A�L�M�Ԃ���Ή��B�����A�V���f�[�^�����A�����ǂ݁A�Ǐ��ȂǁB�u����̂��߂�18:20�o�X�_�����x���Taxi�ɂĖ̓��O����ʒ����X�o�R�A��A2280�~�B18:45�A��A�[�H�A20:30�A���B��5568���B ??�����{��k�ЁE��������2024(3) �p�F�̐i����ԁ@�\�o�n�k�Ō�����?
�@�����̏����͔p�F�̐i�s��Ԃɂ���Č��܂�ƌ����Ă����B
�@�Ƃ��낪���̔p�F�ւ̍H�����قƂ�ǐi��ł��Ȃ��B1-3���@�ɂ͐���880�g���̔R���Ńu��������B���{�Ɠ��d�͓���2���@��2021�N�x���ɐ�g�Ȃ��玎���I���o�����n�߂�\��ł����������{�b�g�A�[���Ȃǂ̊J�����x��3�x���������B�ʂ̑��u�Ŗ{�N10���܂łɎ��o�����n�߁A���{�b�g�A�[�����g�����j�Ƃ����B
�@�v����̓��d���������̔p�F��Ƃ͂قƂ�ǐi��ł��Ȃ��A�Ƃ������ƁB����ŕ������ǂ��Ȃ�̂��킩��Ȃ��ł͂Ȃ���!!!
�@����ȏ�ԂȂ̂ɁA�����ĉғ��葱�����S���Ői�߂��Ă���B����܂�10��ĉғ��ς݁B
�@����̔\�o�����n�k�́A���q�͖h�Ђɂ������̉ۑ��˂������B
�@�\�o�����n�k�ł͎u�ꌴ���͋x�~��Ԃɂ��������A
??????????????????????????
���g�p�ςݔR���v�[���̐������ڂꂽ�B
����p�|���v���ꎞ�~�܂����B
���O���d������ψ��킪���������B
�����ӂɎ����̂⍑���݂��Ă�����ː��ʂ̑���ݔ��̃f�[�^�̈ꕔ������Ȃ��Ȃ����B
���Ôg�̉e���ɂ��āA�~�n���ɊC������������ł��鐅���́u���ʕϓ��͊m�F�ł��Ȃ������v�Ƃ��Ă������A��R���[�g���㏸���Ă����B
���ψ��킩��R�ꂽ���̗ʂ��ŏ��̔��\��5�{�ȏゾ�����B
���������ӂ̃A�N�Z�X���H���j��A����~�����ł���Ȃ����B
??????????????????????????-
�@����͏Z���ɕs����^���A��Q�̉ߏ��]���͏d��Ȍ��ʂ��������˂Ȃ��B
�@�u�ꌴ����2011�N�ȍ~�x�~��Ԃɂ���B�K���������Ƃ����悤�B
�@�~�n���̒f�w�̕]�����߂���A2���@�̍ĉғ��̐R�����������Ă���B2016�N�ɗL���҉���u���f�w�Ɖ��߂���̂������I�v�ƕ]���������A�k���d�͂����_���A���q�͋K���ψ��2023�N�A���Ђ̌�����F�߂�����ł������B�ĕ]�����K�v�ł���B
�@����̒n�k�ł́A���H�̐��f�ɂ�锼���̌Ǘ������߂Ė��ɂȂ����B�l���d�͈ɕ������Ⓦ�k�d�͏��쌴���Ȃǂ������ɂ���B�������̂��N�����ꍇ�ɁA����~����W�����˂Ȃ����A�Ɖ��̌�����������݂�A���ː�������邽�߂̉��������ł��Ȃ����ꂪ����B
�@�K���ς͌��q�͍ЊQ��w�j�̌���������������Ƃ������A�ً}�Ή������̉ۑ���@�艺���Ăق����B
�@�n�k�卑���{�ł̌����̃��X�N���A���߂Ă����ɂȂ����B���{�́A�����̊��p�ɑO�̂߂�ɂȂ��Ă���悤�����A�čl����ׂ����A�Ǝv���B
??
3/12�i�j�܂菬�J�@���ʕa�@�O���@?3:00�N���A�����̔@���B��ƂɏW�����������ԂȂ��B5:50�R�S�~2�����̂݁A6:40�o�X�a�@�ɁA�܂������B7:10-8:00�a���B�Ǐ��ȂǁB8:45-12:00���ʑ����a�@�O���B12:15�a�@�B�����A15:00-18:00�a���B19:00�A��E�[�H�A21:00�A���B5329���B??�����{��k�ЁE��������2024(2) 13�N�ł��n��͍Đ����Ă��Ȃ�
�@���R�ЊQ�Ɍ������̂��d�Ȃ������������������ɂ���B
�@�������A���̖��͕���������B
�@�ݓc�����͌��������d������l���ł���B���̂̋��P�͐������Ă��Ȃ����A�j�S�~�̖�������i�W���Ă��Ȃ��̂ɁA�ł���B���������o�Ɋւ��Ă������Ԃʼn���i�W���Ă��Ȃ��B
�@�o�t���A��F���ɂ͊�Ƃ⋳��Ȃǂŕ������i�ށB�����A����ł������̋��Z�҂͐k�БO��1���ɖ����Ȃ��B�������̂ɂ��A�҂ł��Ȃ���悪�܂�7�s�����Ɏc��B���O�ւ̔��҂́A������2���l�ɒB����B
�@�������̂̉e���ŋ��Z�҂����������B�ߑa�⍂����i�ޒn��Ŏ��̂������A�������Ƃ��������Ԃɐl�������o���Ă��܂����B
�@�����{��k�ЁE�������̂́A�ߑa���i�ޒn��ő�ЊQ���N�������A�X���݂�Y�Ƃ̍ċ��������ɓ�����A�Ƃ�������������ɂ����B�ċ��͖������A�Ǝv���B
�@��Вn�Ől���p���I�ɐ����邽�߂ɂ́A�Y�ƂW�����A�Z����������ꏊ���m�ۂ��邱�Ƃ��K�v�ł���B�������A����͍�����ɂ߂�B�k�БO����ߑa�����n�܂��Ă����n��Ɋ��͂��Ƃ�߂��̂͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B
�@���́A�n��Ŕ�Ђ��ꂽ���X�ɂ͐\����Ȃ����A�{���ɐ\����Ȃ����ӔC�ȍl���ł��邪�A�ċ��E�����͕s�\���A�Ǝv���B
�@��Вn�̌ٗp�̑n�o�Ɋւ��ẮA���Ԃ̗͂����ł͕s�\���낤�B���{�b�g��q��F���Ȃǁu�����C�m�x�[�V�����E�R�[�X�g�\�z�v�ɗގ��������g�݂��Ȃ���Ζ����B���̑Ή����Ȃ���Βn��̕����͂��蓾�Ȃ��B
�@�ЊQ�̎��ɂ͂Ƃɂ��������̕������]�܂�邪�A����ł̓_�����B���Ɍ������̂ł͓y�n��n��̍l�������ς���Ă��܂��B�Ôg��Q�������ł��邪�A�ߑa������n��ł͐l���������������R���p�N�g�ȊX�ɂ��ׂ��Ǝv���B13�N���o���Ȃ��畜���o���Ă��Ȃ������͏d���B
�@�����̏����́u�p�F�v����������B�����A���́u�p�F�v�͐�s�������ʂ��Ȃ��B����ɐ\����Ȃ��l�����d�˂邪�A�j�S�~�̎��[�ꏊ���̔�Вn���ɐ݂��Ă�??�Ǝv���B
3/11�i���j�܂菬�J�@�����{��k�ЁE��������13�N ���N�N���j�b�N�@�@?2:00�N���A�����Ɠ����p�^�[���B�f�[�^�����A6:40�o�X�a�@�ɁB9:00-12:007:10-8:30�a���B9:00-12:00���N�N���j�b�N�h�b�N13���{���ʔ���14���{���ʐ���1���B�a�@�ցA�����A15:00�a���Ή��B�V���`�F�b�N�ȂǁA����19:30�A��A�[�H�A 21:00�A���B��5573���B??�����{��k�ЁE��������2024(1) 13�N�ŃC���t���͕�������ǐl�X�̐����͖߂�Ȃ�?�@�����{��k�ЂŁA�����d�͕�����1���������̂��N������13�N�B
�@�Ôg�̔�Q�Ȃǂ�22.000�l���鎀�ҁE�s���s���҂��o�������A�{�闼���̉��ݕ��ł́A�Z��̍Č��⓹�H�E�S���ԂȂǂ̃C���t���������قڊ��������A�Ƃ����B�������A�l���߂��Ă��Ȃ��B
�@���������ł́A���3���͑S������������X�s�[�h�Ől���������i��ł���B�������̂̉e���ŋ��Z�҂��������������̉��ݕ������łȂ��A�{�����ł��l����3-4�������������̂�����B�ߑa�⍂����i�ޒn��Ők�Ђ��N���A�������Ƃ��������Ԃɐl�������o���Ă��܂����B
�@�����{��k�Ђ́A�ߑa���i�ޒn��ő�ЊQ���N�������A�X���݂�Y�Ƃ̍ċ��������ɓ�����A�Ƃ�������������ɂ����B�l�����x�������A�o�ϊ����������ȓs�s���𒆐S�Ƃ�����_�W�H��k�ЂƂ̈Ⴂ�͂����ɂ���B
�@��Вn�Ől���p���I�ɐ����邽�߂ɂ́A�Y�ƂW�����A�Z����������ꏊ���m�ۂ��邱�Ƃ��K�v�ł���B�������A����͍�����ɂ߂�B�k�БO����ߑa�����n�܂��Ă����n��Ɋ��͂��Ƃ�߂��̂͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B
�@���́A�n��Ŕ�Ђ��ꂽ���X�ɂ͐\����Ȃ����A�s�\���A�Ǝv���B
�@�l�����ɔY�ޏH�c�̎�������n���ƁA�H�c�͑傫�Ȑk�Ђ����Ȃ�������͂قړ������A�Ƃ�����B
�@�k�Ђł͕����A�������������邪����ł̓_�����B�l���������������R���p�N�g�ȊX�ɂ���ׂ��������B��k�Ђ̌�͕������}�����V�������z�̒n��Â��肪�K�v�ł���B
�@��Вn�̌ٗp�̑n�o�Ɋւ��ẮA���Ԃ̗͂����ł͕s�\���낤�B���{�b�g��q��F���ȂǍŐ�[�̎Y�Ƃ��������ӂ̒n��ɏW�ς����鍑�ƃv���W�F�N�g�u�����C�m�x�[�V�����E�R�[�X�g�\�z�v�Ȃǂɗގ��������g�݂��Ȃ���Ζ����B���̑Ή����Ȃ���Βn��̕����͂��蓾�Ȃ��B
�@���ݕ��̊�Y�Ƃł��鋙�Ƃ͋ߔN�A��͂̃T���}��H�T�P���L�^�I�ȕs���ƂȂ��Ă���B����������ŊJ���悤�ƁA��茧��ƒ��Ȃǂł͋����Ɛ��Y�Ǝ҂����͂��A�M���U�P��g���E�g�T�[�����̗{�B��i�߂Ă���B�n��Œm�b���i��A�V���ȓ��Y�i�ݏo�����݂Ɋ��҂������B����ƂĒn���̃p���[�ɂ��������Ă��Ă͑啝�Ȕ��W���]�ݓ�B
�@���k�̔�Вn�����ʂ���ۑ�́A���A�{��A�\�o�����łȂ��A���{�̊e�n�悪���������ׂ����ł�����B
3/10�i���j��������ł�����?2:00�N���A�~�σf�[�^�̐����A�{�ǂ݁A�����ǂ݁B�ߑO�Ǐ����w�B10:40�o�X�a�@�A���҂͗��������Ă���B��ʂɃf�[�^�����B15:30�A��B�Ǐ��A�����A�{�ǂ݁B19:00�[�H�B20:00�A�Q�A��4830���B�锼�ɉƓ�����A��B��N����@�̐����Ǝ��[�A���]�Ԃ̐����A�E�I�[�L���O�V���[�Y�ցB���N�͂܂��B
�[��(1) �[�����˂͏H�c�ł���!�@���������l�Ƃ��֘A
�@���H���̔[�����D���ł���B���܂�Ȃ��D���ł���B
�@�������A���H���ȊO�̓_���B���̂��낤�ˁB
�@�܂��A�[����H������ɐH�퓙���甭����L���A���͂�����_���B���͐H��ɂ͔[�������Ȃ��B������A�L��Ȃ��B
�@�a�@�ł����H���Ɏ��ɔ[����������邪�A���̎��͕a�������[���̏L�����[������B���̂悤�Ȓ��͑����̉�f�̓L�����Z������B
�@�[���̋N���͏H�c���A�Ǝv���B�����܂ł��Ȃ���O�N�̍���ł���B�����������̗����E�o�H�i���k�n���j��Ƃ�������ł���B�ϓ���U�ɓ���n�ɂ�������Ĉړ����Ă�����n�̑̉��Ŕ��y���S���Ă����A�Ƃ����B���ꂪ���\����������(�n������??)�̂��傽����ł���B
�@�������A�H�c�N�����͑S����ł͂Ȃ��B���܂��ɔ[���̋N���͐��˂��Ǝv���Ă���l�������B����ł́A���|�̓a�l���H�c�ɕ��C����Ƃ��ɁA���̔�������������A��Ă��������̂��Ԃ��ɁA�[���̐��@�𐅌˂ɋ������A�Ƃ������Ă���B
�@���͏����ȃp�b�N�ɓ������Ђ����[��(40gx3�p�b�N��70-90�~�O��j���D�ށB
�@(�H�c�̃��}�_�t�[�Y�̂Ђ����[���̃f�U�C���@�C���X�g���[�^�[�⎁�̍�@�H�c���l�Ɣ[���̊W�����������)
�@�`���ʼn𓀂���80g�̂��т̏�ɏ悹���[���̉�ɏݖ���^���������Ɛ��炷�����B���ł����܂��Ȃ��B���ɂ͐������悹�邱�Ƃ����邪�A�����܂��Ȃ��B�ꔢ�ꔢ���ꂼ��̖����y���ށB�@�@
�@�͔̂[���ƌ����A���A�[�����肪�u�[���A�Ȃ��Ɓ[�A�i�b�g�[!�v�Ɣ��萺�������Ȃ��甄��ɂ����B���̂Ƃ��̔[���́A���Ō����Β����������B
�@���͂�����ρB�嗱���珬���A�ɏ����A�����ĂЂ�����B�I���ɍ���B
�@�����Ă��܁A�[���E�͏����S���̎���ƂȂ����A�l�Ɏv���B
�@���������Ă͂₳��鎞��ɂȂ����B�Ȃ���������ʑ�O�Ɏ����ꂽ�̂�??���R�͈ӊO�ɊȒP�ŁA����ɂ��ΐl�Ԏ��̂������ɂȂ�������A�Ƃ������Ă���B
�@�l�Ԃ͂ǂ����m��Ȃ����A�[���͏����̂ق����������������B�嗱�͈ꐶ���������Ă����܂莅���o�Ă��Ȃ��B
�@�[���̖��͎��ɂ���B�E����50��A������50��������̂��ǂ��ƁA�ꕔ�̗����{�Ő�������Ă���̂��������Ƃ�����B
�@�����̏ꍇ�͏\������f���o�����āA���������A�Ƌ��Ƀh�����Ƃ����ăS�n���ɂ�����B
�@�嗱�̏ꍇ�̓S�n���ɏ悹��B
�@�[���̗��̑傫���ɂ���ĐH�ו�����@���ς��B
�@�悹���嗱�[���̓S�n���ƈ�̉����Ȃ�����A���D���̐l�œ��̖��𖡂킢�����l�͑嗱�̂ق���I�Ԃ��ƂɂȂ�B
�@���݂��݁A�[���͉����[���A�Ǝv���B���{�l�ɐ��܂�Ă悩�����Ȃ��B
3/9(�y) �������g�@�Ɠ����m��\���@�Ɠ��̓]���^��c���?3:15�N���A���������A�k�R�ȂǁB�ߑO�͓Ǐ����S�A�f�[�^�����B10:30�Ɠ��̓]���^��c�ցB16:00�V�����ցB�ߌ�Ɠ����m��\���ɏW���I���B19:00�[�H�B20:45���Ԃ̃\�t�@�[�x�b�g�œ�����ە����ďA�Q�B��2583���B??�~�J��(2) �Ⓚ�~�J���̎v���o
�@����1965�N�i���a40�j�V����w�ɐi�w���A6�N�Ԑ���?���?�V���Ɖ��������B
�@�����A���k�{���͏��C�@�֎ԁA�։z�����̓f�B�[�[���ԂŕГ���10���Ԃ̍s���ł������B���ʂ̓N�b�V�����t���̕z����ł��������w������͍d���ؐ��A���p�ɌŒ肳��Ă��āA���������Ă���Ɛg�̂��ɂ��Ȃ������̂ł���B���R��[�Ȃǂ͂Ȃ��ď�͑�ςł������B���̐h�������ړ��̎������V����w�ɓ��������Ƃ����݂��ݍ����A���s���̐g�ł͎~�ނȂ������B
�@���̐h�������̍ۂ̍ő�̃I�A�V�X�A�ґ�͖{����������ǂ߂邱�ƂƉw�ŗⓀ�~�J�����w�����Ď��Ԃ������ĐH�ׂ邱�Ƃł������B
�@�~�J���͋G�ߐ��̉ʕ��œ~����t���ɂ����̔�����Ă��Ȃ������B�����ʔN�̔��ł��鏤�i�ɂ��悤�Ƒ�m���ƂƓS���O�ω�̋����J���ŗⓀ�~�J�����������ꂽ�B���a30�N-40�N�オ�o�ׂ̃s�[�N�ŁA����グ�͔N��1000���ɂ��B�����Ƃ����B
�@��Ԃ̒��ŗⓀ�݂���𖡂�����̂͂���70-80��O��̐l�B���낤�B
�@�Ⓚ�~�J���́A���̐���̗��s�̂�����Ƃ����y���݂̃V���{���ł������B
�@�Ⓚ�~�J�����v���o�����A�����̗�Ԃ̗l�q�����肠����S���Ă���B���Ȃ��m�ۂł����ꍇ�͂܂��������A�����̗�Ԃ͒x�������B��Ԃ����G����Ɛl�X�͏��ɐV������~�����������̂ł���B
�@�����͉w�ق��ґ�i�Œ����̏ꍇ�w�ǂ����ɂ��莝�Q�ł������B�y�b�g�{�g�����Ȃ��ԓ��̈��ݕ��Ƃ����A�}�{�̌`�����������̗e��ɓ��������������������B����15�~�������B
�@�����������́A�y���݂��Ⓚ�~�J���������̂ł���B�K�`�K�`�ɓ����Ē����ɂ͐H�ׂ邱�Ƃ��ł��Ȃ����A�₪�ĐH�ׂ��뎞������B���X�G���Ă͐H�ׂ����T�邪�Ⓚ�~�J���͔��𓀏�Ԃ́u�V�����V�������v�ɂ��������A���������V���[�x�b�g���͒Z�����A���̌�͂����̗₽���~�J���ɂȂ��Ă��܂��B
�@�Ⓚ�~�J�����Đ����₽�������B����́A�����������ۂ��̊�z�����A���M�d�Ȗ��ł������B������A�Y����Ȃ��B
�@���͍��ł����X�Ⓚ�~�J��������ē������v���o���A�y����ł���B
�@
3/8�i���j�����@��ȊO���@�@?2:45�N���A�����E�V���ǂ݁A�f�[�^�����ȂǁB5:30�R�S�~��o�A7:40Taxi�w�ɁA8:11���܂��A8:45��Ȓ��ʕa�@�O���ATaxi�ňړ��B�����Ȃ��B15:20�a�@�BiPhone7+�o�b�e���[�\��B19:15�A��A�[�H�A21:00�A�Q�B��4527���B??�~�J��(1) �u���u���E���킭���ᖨ�����D���Ȃ̂��������������������y���@
�@�~�J�������������G�߂ɂȂ����B�@ ?
�@2��-4���͎��ɂƂ��ă~�J�����������������ŁA���̎����ɏW���I�ɐH�ׂ�B
�@����ȊO�̎����ɂ͏]���͂قƂ�ǐH�ׂȂ��������A������10�������爤�Q���Y�̐^���������W�����ĐH�ׂ��B
�@�H�c���̍��|�m�����s�p�ӂɂ����Q�̂��Ⴑ�V�Ȃǂ�n�R�������Ɣ����������Ƃ��֘A���āA���͈ӎ����Đ^���������w�����Ă�������B
�@���͏��߂Ēm�����̂ł��邪�A���������͂��̎����̖����Ƃ��Ă͊O���̔炪�����Ĕ����₷���A�ƂĂ��Â��Ď��̍D�݂ɂ����āA�����D���ɂЂƑ������ɉ������B�V�N�ɂȂ��Ă���͓���ł��Ȃ��Ȃ��āA���̃u�����h�����ƂȂ����B
�@���̕Гc�ɂŁA���d���̓���A�Â��A���������Ƀ`�����`�����ƐԂ����������Ȃ���R����d�X�g�[���ƃR�^�c���g�[�@��̎���ł������B���̑��ɂ͐É��Y�Ȃǂ̃~�J�������̂܂ܖ�����ɒu����Ă����B
�@�H�̏{�̃~�J���́A�����̂������ĐV�N���̂��́B�����p���p���ɋl�܂��Ă��Ď��Ɣ�̊ԂɌ��Ԃ��Ȃ��A�͂�������ł���B���́A�V�N�ȊÎ_���ς��A�Ɠ��ł�����̂Ă��������A���͐��l���Ă���͂��̎����̃~�J���͒��߂邾���Ŏ�Ɏ�邱�Ƃ͂Ȃ������B�ʕ��ނ��L���ɂȂ������Ƃ����邾�낤�B
�@�Ƃ��낪�A2�����ɂȂ�Ǝ��͓ˑR�~�J����H�n�߂�B���̍��̖����͐����������Ď����ޏk���A��Ǝ��̊ԂɍL�����Ԃ��o�Ă���B�O�����n�������]�T�̕��͋C���Y���B�w��Ŕ���V�S���ƈ�w����₷���Ȃ�B�����Ȃ�ƉƑ��B�͂��܂�H�ׂȂ��Ȃ邩�玄�̓ƒd��ƂȂ�B�����_���ς��⋭��ȊÂ݂͏����A�}�C���h�ȊÂ����c���Ă���B���ɔ��������B
�@���̃~�J�����y���ލ��ɂȂ�ƁA�ǂ���Ƃ��Ă����H�c�̋��ɓ��ɏt�̑�����ттĂ���B���ɂƂ��ău���u���E���킭����~�J���͏t�̖K����ӎ�����H�i�ł�����B�@
�@3���ɓ���ƕ���₷���A�l�i���}�ɍ����Ȃ�B4���ɓ���ƃX�[�p�[�̓X������~�J���̎p�����낻�������B�ƂĂ��₵���B
�@�Ⓚ�ۑ��ł�������̂����䂪�Ƃ̗Ⓚ�ɂɂ̓~�J���p�̗]�T�͂Ȃ��B�c�O�ł���B
�@���킭����~�J����^�҂̓Ƃ茾�B
3/7(��) �����@���g�ɂށ@�]���^�Վ���c?2:00�N���C�l�R�Ή��B�������������ȂǁB�{�ǂ݁A�ȂǁA8:30�Ɠ��Əo�A�ߑO�͍��w�A�Ǐ��ȂǁB11:00�a�����ґΉ��B��r�I�������߂����A���������B�]���^�Վ���c�Ƃ̂��Ƃʼn@���őҋ@�A20:30�A��A�[�H�B21;45�A�Q�B��3500���B??���ɂ���(2) ����l�ƐH�ׂ�l���J
�@���ɂ��肪�D���A�Ƃ����l�͑����B
�@�H�i�W�̖^�A���P�[�g�ł́A���ɂ�����u�����v�Ɠ������l��0.1%�������Ȃ������A�Ƃ����B
�@���̗c�����ɂ͂��т͂��܂ǂŁA�d�Ő������B�����C���o���n�߂��������₵�Ȃ���A���ɐ��������Ȃ��理���オ��̂�҂������̂ł���B����ɁA���̊��ɂ͂��ł��Ƃ������܂������A���������������Ă��傤����ЂƐ��炵���ăL���b�ƈ���A�u�z���E�E�v�Ɠn���Ă��ꂽ��̂��ނ��тقlj��������̂͑��ɂȂ��B���̊y���݂̈�������B
�@���̎��ԂƖ����A�d�C���ȍ~�͎����Ă��܂����B
�@
�@���ʁA���ɂ���́A���Ɉ����āA�����ɐH�ׂ���́B��߂����ɂ��������ق��鎞�A�q�ǂ��̍��̖��A���v���o���B
�@���ɂ���ɂ܂��L���Ȏv���o�́A�����l�����߂����Ă����A�Ƃ��݂��݂Ǝv�킹�Ă����B
�@���{�l�Ƃ��ɂ���̂������͌Â��B�ΐ쌧�ɂ���퐶����̈�Ղ���́A���ɂ���́u���v���������Ă���B�ޗǎ���̏����A�u���y�L�v�̂ЂƂu�헤�����y�L�v�Ɉ��тƂ����L�q���c����A��������ɂ͏����������Ă�����ł߂��ԐH���������B�퍑����A�]�ˎ���ɂ͌g�s�H�Ƃ��čL�����ɂ��肪���y���Ă������B
�@���ɂ���̋�ނ��F�X�y���݂ł��邪�A���ɂ���̂��������͍��l�́u�ʂ�����v�ɂ�����A�Ǝv���B�u����v�u���ԁv�͒P�ɗ͂������邱�Ƃł͂Ȃ��A�C���������߂���ʂȍs�ׂł�����B���i�̈���Ƃ͎����ƈقȂ�B
�@�f�p�ȐH�ו��̂��Ƃ��ʂ��āA����l�ƐH�ׂ�l���݂����J��[�߂�Ӗ������������낤�B
�@�u���k�̃}�U�[�v�ƌĂꂽ�X���O�O�s�̍����������͊�؎R�̘[�ɗ��u�X�̃C�X�L�A�v�ŁA�l���ɖ����S����ꂽ�����������A���ނ��тƎ藿���Ō}�����B2016�N94�ŖS���Ȃ������A�����̒��Łu���ނ��т�����Ƃ������Ƃ́A�����ʂ��Ĉ���l�̐S��`���邱�Ƃł��v�Əq�ׂĂ���B
�@���ɂ���̋�ނň�Ԑl�C�͉��ɂ���B�H���ׂ��q�ǂ��ł��A���ɂ���ɂ���Ɗ��ŐH�ׂ�B
�@�R���r�j�ł͐F�X�̋�ނ̈��肪�����Ă��邪�A�@�B�ō���邩��₦�ĂȂ��Ƃ��₽���B��̃A���P�[�g�ł͉҂̖�4�����u�����������v�Ɠ������B
�@��ނ̐l�C�̓V���P�� �~�����z�������q>�E�E�E�Ƒ������A�̊p�ρA�J�c�A�`�[�Y�ȂǁA���ɂ���炵����ʋ�ނ��o�ꂵ���B
�@��ނŃ_���g�c�l�C�́u�T�P�v�͂��ɂ���̏ꍇ�u�V���P�v�ƌĂ�邪�A�ӂ��Ƃ��u���v�̐������ǂݕ����Ƃ����B�܂��A�u���v�Ɓu�T�[�����v�͕ʂ̋��Łu�܂��v����B
3/6(��) �����@��r�I���g �@���ʎ��Ȏ�f�@�a���J���t�@�@��i������?2:00�N���A�f�[�^�����A���������A�f�[�^�����ȂǁB9:30�Ɠ��Əo�A�a���Ή���A10:30-12:50���ʎ��Ȏ�f�A�����Ԃł������B��i������͊Ԃɍ��킸�B�������̐\�����ޒ�o�A���Ȃ��B14:30�a���J���t�@�A���ҏ��u�Ή��A19:30�A��A�[�H�A20:45�A�Q�B��5090���B??���ɂ���(1) �����I�Ȕ�������������s�v�c�ȐH�ו�
�@�Ƃɂ���� �y(��=�H��)�ɐ���т𑐖� ���ɂ�����Βł̗t�ɐ���?
�i���t�W�@����2-142�@�L�ԍc�q�@����܂݂̂��j
�@�ˑR�ɔ����I�H����������Ɠ��Ȃ��Ȃ����L�ԍc�q�̒Q���𖡂�����B
---------------------------------------------------------------------
�@���ނ��тƂ������́A���ɂƂ��Ă͂�����Ɖ�����ۂ�����B���ɂ���ƌĂԂ̂������A�Ǝv���B
�@���̎��̐����̒��ł͓���ɁA���ɂ���͂��܂�o�ꂵ�Ȃ��B
�@���Ďq���̍��A�����Ɏ����Ă����u�s�y�ٓ��v�ɂ����āA��H�͂قƂ�ǂ��ɂ���ł������B
�@����ꂽ���т́u�����v���A�����Ă��Ȃ����т́u����v���ے�����B
�@���ɂ���́A�����g�킸�u��Â��݁v�ŐH�ׂ邪�A����͖��炩�ɔ����I�ȏ�ԁB �u��Â��݁v�ŐH�ׂ邱�Ƃɂ���āA�����Ɠ������тł����Ă��A���̖��܂ň���Ă��܂��B�J���[���C�X��������Œ��ڐH�ׂĂ݂����Ǝv���Ă��邪�A�܂��ʂ����Ă��Ȃ��B
�@�����āA���{�l�ɂƂ��ĉ����ł��ɂ����H�ׂ�Ƃ������ƁA���̃E�L�E�L���́A������O�̓��킪�����ɂ��邩�炱���A���키���Ƃ��ł�����{�l���L���ґ�Ȋ��o�Ǝv���B
�@���ɂ���͒n�k��䕗�Ȃǂ̐܁A���ɉ^���B����͔��Ȃǎg���]�T����������ŁA�s�y�Ƃ͕ʂ̈Ӗ��ł̔�����ԁB��_��k�ЁA�����{��k�ЁA�\�o�n�k�ق��ł����l�ɐU�镑��ꂽ���A��Ў҂ɂ��ƒ����I�ɂȂ�Ƃ�����h���炵���B
�@���͔N��1-2�x�A�a�@�̔��X�Ȃǂł��ɂ�������Ƃ����邪�A���ɂ���́u�����v�Ȋ����͂��Ȃ��B�s�̂̃p���p�������C�ۂ̂��ɂ���̃A�C�f�A�́A�f���炵�����A�H���ƌ������C�ۂ̃X�i�b�N�̊��o�ŁA�H�ׂ��邩��A���ɂƂ��Ă͕ʕ��Łu�����v�I�H�ו��B
�@����ɑ��A�ƒ�Œ��A����ꂽ���ɂ���͒����ɂȂ�Ǝ���C��ттĂ���B���ꂪ������O�ł������B�ŏ�����C�ۂ������Ă��邵���Ƃ�n�̂��ɂ���A���̊C�ۂ���ɂ������č���A�ł������ƈ���Ċy���������������A�H�ׂ�x�Ɏv���o���B����������I�ł��邪�A�ŋ߂̓A���~�z�C����b�s���O�ł��H�ׂ₷���Ȃ��Ă���B
�@���͎������m���ŕ�܂ꂽ���ɂ���̗�^�҂ł���B
3/5�i�j�܂��⊦���@ ���ʕa�@�O���@
2:00�N���A�����̔@���A�����`�F�b�N�A�Ǐ����S�B5:30�R�S�~1�ܒ�o�B6:40�o�X�a�@�A7:10-8:15�a���Ɩ��A�Ǐ��A8:40-12:50���ʕa�@�O���B���a�B�a�@�A�����B16:00�a���Ή��A�V�����́A�����B�Ǐ��B19:30�ʒ����X�o�R�A��A�[�H�B21:30�A���B��5984���B??����(3) �ቷ�E�ۂ̋����͔����������E�E�E
�@�u�ቷ�E�ۋ����͖����ǂ��v�Ƃ����C���[�W�����l�͏��Ȃ��Ȃ��Ǝv���B�������̈�l�B
�@�����̎E�ە��@�͑傫�������Ĉȉ��̃p�^�[������B
(1)LTLT�@�iLow temperature long time pasteurization).�u�ቹ�����ԎE�ہv
�@63���`65���̊Ԃ�30���ԕێ�����ቷ�ێ��E�ۖ@�B��ϔM���ۂ͑�����ł�����̂́A�ꕔ�͎c������̂ŁA��ʓI�ȋ��������A��������͒Z���i5���O����x�j�B
�@�������A�^���p�N���̔M�ϐ��͗}������̂ŁA�����{���̕������قڂ��̂܂ܐ��������Ƃ��ł���B���Y�E�A���E�̔��ɂ�����i���Ǘ��ɍ����������ƃ��[�J�͖w�ǎ肪���Ă��炸�ቷ�E�ۋ����͏��K�͂̌���I���Y�ɂƂǂ܂��Ă���B
(2)HTST�@�iHigh Temperature Short Time)�u�����Z���ԎE��
�@75���E15�b�ԂŎE�ۂ���B�������R���̍y�f�͎������A���j�ہA���`�t�X�ۂȂǂ̕a�����ۂ͎��ł��邪�A���s�ۂ�ϔM���ہA��E�͐��c����B?
(3)UHT�iUltra High Temperatue�j�u�������E��
�@120�`130���E2�`3�b�ԁB�����̎E�ۏ������@�̎嗬�ƂȂ��Ă���B��ʔ̔�����Ă��鋍����9���ȏオ���̕��@�ɂ��B
(4)�u�������u�ԎE�ۖ@�v
�@135�`150��C�A1�`4�b�ԉ��M���ŋہB �����O���C�t(LL)�����ɗp��������@�ŁA �ŋۏ�����ɗe��ɏ[�U�����̂ŁA�퉷��60���Ԃ̒����ۑ����\�B
�@����(4)�̎E�ۖ@��p����LL�����������̈������A�A�o�ɂȂ���\�������邩������Ɛ������ׂ��ƍl���Ă���B
�@LL������2022�N�x�̐��Y��(�_���Ȃ܂Ƃ�)�́A�O�x��7.2%����4��628���b�g���ŁA3�N�Ԃ�ɑ����ɓ]�����B�A�W�A�����̗A�o���L�сA�����Ȃ̖f�Փ��v�ł�LL�����̗A�o�z��2022�N�x��20���~�ƁA�O�N�x���8�E4%���ƂȂ����B�����̍������v�̓R���i�Ђ╨�������ɂ�蒷�炭���v��������A�A�o�Ɍ������v�J��̕K�v�������܂��Ă���B���{�͋����E�����i�S�̗̂A�o�z�ڕW�Ƃ��āA25�N��328���~�ƁA2019�N��8�������f����B
�@���́A���̍D�݂őI�ѕ����Ă������ł���B�u�ቷ�E�ۋ����͐�ΓI�ɖ����ǂ��v�Ǝv���B
�@�������Ȃ���A���{���Ƌ���s���u���Ŏ�ޕʂ�E�ۉ��x�̈Ⴂ�����ݔ�ׂĂ�������Ƃ���A�ቷ�E�ۋ�����蒴�����u�ԎE�ۂ����������Ɠ�����������������Ƃ����B
�@���͒ቷ�E�ۋ������Z���ŃR�N������悤�Ɋ����邱�ƂƁA�قƂ�ǂ̋����������������Ƃ��邪�ቷ�E�ۋ����͂��Z���̂悤�Ȋ���������B�X�[�p�[�Ȃǂł͓��I�A���Z�E�E�E�Ȃǂ̕\���̐��i������ʔ������A�����̊�͖��Ƃ��Ă͎����ł��Ȃ��B
3/4(���j�܂芦���@���N�N���j�b�N�h�b�N�@�ϐ�Rcm�@�E�����f
2:15�N���A���]�����S���I���B�V���E�����`�F�b�N�B���̑��~�σf�[�^�����B�����B�]�|�h�~�̃X�p�C�N�A�_�v�^�[���p�A6:30�o�X�a�@�A7:10-8:15�a���Ɩ��A�Ǐ��A9:00-11:10���N�N���j�b�N�h�b�N14��+���ʔ���14���A11:30�E�����f�A�����A15:00�a���Ή��B�Ǐ��ȂǁB19:15�A��E�[�H�A21:00�A�Q�B��6160���B??����(2) ���͏T��2.7���b�g������
�@�䂪�Ƃł�30�N�ȏ����z�̋������Ƃ��Ă����B
�@�Ƒ��S���������D���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B���܂ɂ͗����Ɏg���������邪�A�������D���Ȏ����Ђ�������ށB
�@�����̓J���V�E�����L���ł��邪����Ȃ��ƂɊ��҂��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�q���̍�����̏K���ŋ��������g�߂ɂ��������Ƃ����R�ŁA�������Ȃ��Ǝ₵������ł���B
�@���̐��N�ԂŎ����c�����Ă��邾���ł���z�����X��3���p�Ƃ����B
�@����3�N�قǂ͏H�c�s�ł͗B��ƂȂ����q��Ő��Y����Ă���u��؋����v900ml�r������T3��a�@�܂Ŕz�B���Ă�����Ă���B
�@(�T��3�{��������ł���r���苍��)
�@�H�c�ߍx�ł͂��Ă�20�������݂����q��́A�����ؖq��݂̂ƂȂ����B�H�c�s�����R�̘[�ʼnƑ�3�l�Ŋ撣���Ă���A�Ƃ̂��Ƃł���B
�@���_�Ƃ̔p�Ƃ������Ă���Ƃ̃j���[�X�Ɋւ��Ď��͖��S�ł͂����Ȃ��B
�@�_���Ȃɂ��ƁA2022�N2�����_�̓��p���̍�������ː���1��3300�˂ƁA�O�N����3.6%�������B
�@���V�A�̃E�N���C�i�N�U�ɒ[�����������i�̍����ō̎Z���������A���_�ƌː��͖�14�N�O�̐����ɂ܂Ō��������B�Ō�̍ԂƂ��ė��_�Ƃ̎������x���Ă����q���̉��i�}�����d���̂�������B2020�N���͕���10���~�ȏ�ł������q������~���x�̂��Ƃ�����A�Ƃ����B
�@�䂪���̐H����@�͂���30�N�قǑO���猜�Ď����ŁA���͐S�z���Ă������A���҂���Ƃ������ȑ��ӂ��Ă������߂ɂ��̏͂ނ��눫���X���ɂ���B���̐l�����A����̒��ł����s�t�I��ԂɎ������Ǝv���Ă���B��قǃh���X�e�B�b�N�ȑ�����Ȃ��Ɖ��P���Ȃ����낤�B
�@
�@�����̑�z�X�͖�9�猬�B �s�[�N��2016�N����50%���������B
�@��z�X�����ʂ��Ă���̂́u���v���v�u���i�����v�u��p�ғ�v�u�K�\������̍����v �̎l�d��B?
�@���q���Ŋw�Z���H��ƒ�̋�������������A�Ⴂ�����ɂ́u����v�C���[�W�Ō���ꂽ�B
�@��z�X�ɂ̓R�X�g�����z������]�͖͂R�����A�l�o�c��������z�X�ɂ́A����̔g�������Ɖ����Ă���B
�@����͂���ɋ����̔̔��̓R���r�j��X�[�p�[�����S�ɂȂ邩���m��Ȃ��B�����̏���ʂ͈�w�s����ɂȂ�Ǝv����B
�@
3/3�i���j�܂�@�Ɠ��H�㒬�u����@�Ɠ����\�����쐬�@�ϐ�Rcm?�@2:15�N���A�f�[�^�`�F�b�N�B�֘A���������A�{�ǂ݂Ȃǂق������̔@���B�����ȂǁB9:00�H�㒬�̍u���A�l�I�j�R�`�m�C�h�֘A�A�ɂ����Ɠ��ɓ���a�@�A���w���S�A�V���f�[�^��ʓ��͏����A�Ǐ��O���B15:00�A��A�����B�Ɠ����\�����쐬�J�n�B20:00�Ɠ��A��B20:00�[�H�A21:00�A���B��3672���B??����(1)�@���������E���������H�@��肽�Ă̋����͔�����������
�@����1952�N(���a27�N)�ɏ��w�Z�ɓ��w�����B
�@�������̍��͉䂪���̐H������͂��Ȃ�ǂ��Ȃ��Ă��Ă������낤���A���H���ɃA�����J�̒E���������w�Z���H�Ƃ��ĐU�镑��ꂽ�B�㉺�������ŁA���͌����{�[�����ŏo������v�ȃh�����ʂ̒��ɔ��������������Ă���A���̈��ʂ��u���L�̃o�P�c�ɓ���A�ʂ�ܓ��ŗn���������̂ŁA�A���~�̊�Ŕz��ꂽ�B
�@�T2�`3��قǂ������悤�ȋC�����邪�A���̋L���ł͒Z���Ԃ����������C������B
�@�E�������́u���܂肨�������Ȃ��v�Ƃ����Ă������A���͊��ň��݁A�A�����J�Ɏv����y�����B
�@�㋉�������H�W��S�����Ă��ꂽ���A���Ƀo�P�c���Ђ�����Ԃ��Ă��̓��̋��H���p�[�ɂȂ鎖�����������A�����v���o�ł���B
�@���̒E�������̓A�����J�̃L���X�g���c�̂Ȃ�13�c�̂őg�D���ꂽ���{���������c��(LALA)�ɂ���āA1946�N�`1952�N�܂ł̊ԑ��z400���~�̋~���������͂���ꂽ�A�Ƃ����B���̂���4����3���E�������Ȃǂ̐H���i�ł������Ƃ����B
�@���̕Гc�ɂ̏��w�Z�܂ł悭�͂������̂��A�Ɗ��S����B
�@���������ꂽ�E�������͒����ۑ����\�ŁA�炿����̎q�ǂ��ɕK�v�ȃJ���V�E���₽��ς�����⋋�ł��A�����h�{���ɂ��A���̐H�Ɠ�̒��A�����̉h�{��Ԃ����I�ɉ��P�����A�ƌ����Ă���B
�@����Ƃ͕ʂɓ����A�䂪�Ƃł͏T��3��قǐe�ʂ̔_�Ƃ����肽�Ă̋����̒��Ă����B��7:00�ɋ��4���r�������ċ������Ƃ�ɍs���̂����w���̎��̖�ڂł������B
�@���̋����͎E�ۂ��Ȃ��ň��ނ̂͊댯�Ƃ���Ă���A�ꂪ����2��������ŕ��������Ă����B
�@�����͊ȒP�ɐ������ڂ��B�Y�̎��ւɂ������y����A��͌��߂đ҂��Ă����B�M���Ȃ��������̕\�ʂɃT���T���Ɣ����������Ă���B������͔��ŏ��ɗ��ߎ�菬���ȓ��ۂɈڂ��A���ʂ̋����𑫂��Ď��ɂ��ꂽ�B���ꂪ�����̊y���݂̈�ł������B�v�����ĉɂ�����O�̋��������ʂ������Ĉ���ł݂����Ƃ����邪�ƂĂ��������������B
�@�H�Ƀ��M�̓�������ł����B���l�ɕ������Ĉ��ނ̂ł��邪�A�G���ۂ����������Ď��͍D���ɂȂ�Ȃ������B
�@�q�l�R�̑���ɕ�l�R�̓��[���璼�ڋz���Ă݂��������邪�A�ʂ͏��Ȃ��A���Ȃ艖���ς�������ۂ��c���Ă���B
3/2�i�y�j���g��-3�x�@�܂菬��@�\���������I���@?2:45�N���A��J�H���q�ɏ�炸�O�_�O�_�߂����B�V���`�F�b�N�A4:00�����璲�q�߂�B��J�̉e�����H�@���܂ł͍��w���S�B�������̐\���ŏI�R�[�X�B�����A�V���`�F�b�N�B�\���I���B19:00�[�H�A20:30�A�Q�B��1805���B��������͂قƂ�Ǐo���A�^���s���B�����̎��Ԃ����������B
���h���E�Y����(2) �@���͗����l���猙���Ă���(2)
�@���͂ǂ��炩�Ƃ����ΐh�������D���B����ɉ����������[���ɂ͋C�ɂ��Ȃ����ł���B
�@������A���h����Y�������ʂɗp����B������A����������Ă����l�����̕]���͂悭�Ȃ��B
�@���h����Y�����̗�
??�Ă����A�`���[�n���Ȃǂƍg���傤��
�@���͏Ă����A�`���[�n���A�K�[���b�N���C�X�Ȃǂ��z�b�g�v���[�g�ō��Ȃ���H�ׂ�̂��D���ł���B���̍ۂ͍g���傤����Y���ĐH�ׂ�B�Ɛl�����͍g���傤���̗ʂ����čg���傤�������??�A�ƌ��ȕ\��ł���B
�@
(�����̏Ă����@����͈��)
??�J���[���C�X�ɂ͕��_�Ђ��ƃ��b�L���E
�@���̓J���[���D���ł���B���������Ȃ�h���^�C�v�������B����ł̓J���[�ɂ͕��_�Ђ��ƍׂ��肵�����b�L���E���ʂɂ܂Ԃ��B�Ɛl�����͕��_�Ђ��ƃ��b�L���E������łȂ���??�A�ƌ��ȕ\��ł���B
�@���͖ő��ɊO�H���Ȃ������̍ۂɃJ���[���C�X�𒍕����邱�Ƃ������B�e�X�̓�������J���[���C�X�𖡂���Ă݂邽�߂ł���B���̍ۂ̕s���̓J���[���S�̂ɏ��Ȃ����ƂƁA���_�Ђ���b�L���E���z���̂킸���������Ă��Ȃ����ł���B���Ȃ��Ƃ�5�{�͗~�����B�ʉ�v�Ń��b�L���E����]���Ă������͑Ή����Ă��炦�Ȃ��B
�@���̓J���[���C�X�ȊO�̃J���[���̗�����100%���B�J���[�p���A�J���[���ǂ�Ȃǂ��t���Ȃ����A�L���x�c�̐��ɃJ���[�������ĐH�ׂ�L���x�c�J���[�͂����B���̍ۂ��A������_�Ђ���b�L���E�͕K�{�ł���B
(�䂪�Ƃ̃J���[�@����͓��Ȃ��@�哤���������l�H���g�p�@���_�Ђ���b�L���E�̕r�����ɂ���)
??���[�����ɌӞ��Ƃ߂��
�@���[�����ɂ͂����Ղ�Ӟ����ӂ肩���A�߂�܂��ʂɍڂ���B�䂪�Ƃł̓V�i�������[�����ƌĂԁB
??�p�X�^�Ƀ^�o�X�R�ƕ��`�[�Y
�@�p�X�^�ނɂ̓^�o�X�R�ƕ��`�[�Y�ł��邪�A���ɂ͒��q�ɏ���đO�҂������߂��A�l�m�ꂸ�h���ɑς��鎖������B
??���@���ǂ�ɓ��h�q
�@�ꖡ�����������Ȃ��B�ǂ�Ԃ�̒�ɑ�ʂɎc������B
??�t���C�ɂ͐h�q�������Ղ�h��B
??�E�E�E�ȂǂȂ�
�@���͂ǂ��炩�Ƃ����Εs���N�ȐH�����Ƃ��Ă��邱�ƂɂȂ邾�낤���A���̖����D��������A������䂪�������������B
3/1�i���j���g���J�܂� ��Ȓ��ʕa�@�@�@?1:45�N���B�����E�{�ǂ݁A�k�R���A�f�[�^�����B�ϐ�1cm�B6:00�J�̒��R�S�~��ܒ�o�B7:35Taxi�w�A8:11���܂��B��Ȃ͉����^�N�V�[�A8:50��Ȓ��ʕa�@�O���B���Ғ����x�B�H�c�w�A15:30���艮�Ï��X�o�R�a�@7���w���A�����A�V�����͂ł����A�Ǐ��A���]�����S�B19:20�A��A�[�H�B20:30�A�Q�B����6617���B??���h���E�Y����(1) �@���͗����l���猙���Ă���
�@�䂪�Ƃ̐H��I�ɂ́A���h���̕r����������u���Ă���悤�Ɍ�����B �X�̍��h���A����͗����ɔ����ȍ���□��������̂炵�����A������S�����Ȃ����������̌��\�͖w�ǒm��Ȃ��B
�@�m���ɁA���̒I���������Ă���Ɖ䂪�Ƃł͗l�X�ȍ��h������g���Ĕ����������̂����܂����Ă���悤�Ȉ�ۂ�����B
�@�ł́A�Ȃ��䂪�Ƃɂ͍��h���̕r����������̂��B
�@����́A�䂪�Ƃł͎��ȊO�̎O�l�����������邩��X�l�ɂ���ėp���鍁�h�����قȂ邩��ł��낤�B
�@�H��I�ɕ��ԍ��h���́A���ɂ́u��������邼�E�E�E�v�Ƃ����ӗ~��グ�邱�Ƃɂ��Ȃ邾�낤���A���̓��̗����̑I���A�V���H�v�ɂ��ւ���Ă��邩������Ȃ��B
�@�����p�\�R����ō���Ă��鏑�Ђ̃��X�g�̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂��낤�B���̐�����ɂ��y�Ԋ��Ǐ��̃��X�g�����Ă���Ɖ������������ݏグ�Ă��邵�A�ēǂ��������Ђ������o�Ă���B
�@�H��I�ɂ��鍁�h���ɂ�����Ȍ��ʂ�����̂��낤�B
�@�H��I�ɂ��鍁�h���Ƃ͕ʂɁA���̐H��̏�ɂ͏�ɌӞ��A���h�q���u���Ă��鑼�ɁA�����ɂ���Ă͕��_�Ђ����b�L���E�A�^�o�X�R�A�m�a���̐h�q�ނ����ԁB
�@���͐H���œY������A���h����Y���������܂�ɂ���ʂɗp���邩�痿��������Ă����l�����̕]���͂悭�Ȃ��B�������������������䖳���ɂȂ�E�E�E�Ƃ̂��Ƃł���B���̋C�����͗����ł��邪�A���ɂƂ��Ă͈�w���������Ȃ邩��C�ɂ��Ă͂����Ȃ��B
�@���́A�����̔����Ȗ����悭�킩��Ȃ��B���������K���ł���Ή������������Ă������������A�f�ނ̖������\�������ł���B�[�H��̎��̊��z�̓����p�^�[���A�u�ƂĂ��������������E�E�E�v�����ŏڍׂ͌���Ȃ��A���⌾���Ȃ��̂��B
�@���ɂ͐H���̊��z���ڍׂɏq�ׂ��b�Ɍ����Ă���B������A����ɕ\�����悤�Ƃ������قǁu�������@�����т邳�ނ��@�H�̕��v(�m��)�A�Ɏ����l�ȐS���ɂȂ�B
2/28�i���j�܂�g�@�Ɠ����`�O�Ȏ�f�@��i������@��lj�@�a���J���t�@
2:15�N���B�����ȂǏ����B8:30�Ɠ��Əo�A11:00�a���Ή��A���ςȂ��B�Ɠ����`�O�Ȏ�f�A�V���`�F�b�N�A���́B12:30��i������@13:00��lj�@15:00���Ԏ��֘A�J���t�@�A15:30�a���J���t�@�A���@���ґΉ��B�Ǐ��B19:00�A��A�[�H�A20:50�A���B��5014���B
2/27(�j����t�߂��@���ʕa�@�O���@�@
1:45�N���A�����֘A�ȂǁB6:00�R�S�~�o���B6:40�o�X�a�@�A7:15-8:00�a���Ή��B8:45-12:30���ʕa�@�O���B�\�҂�5�l�Ə��Ȃ������B�X�l�ɂ�����莞�Ԃ������E14:00���@���ґΉ��B15:00�f�X�N���[�N�A�V���`�F�b�N�{���́B19:30�A��A�[�H�A20:20�A�Q�B��5875���B
�Β�(3) �@�Β��̌��\�@�{������??
�@����75�N�������ƗΒ������D���Ă����B�K�Ȃ��ˑ��ǂ��A�͂��܂����ł��H���ɂ͂킩��Ȃ��B
�@���{�̂����͒�����������Ă����炵���B����700�N��ɓ��̕��l�u���H�v���A����o�v�Ƃ����{���o���u�������߂A�͂��o�ċC�������悭�Ȃ�v�Əq�ׂĂ���B
�@�킪���ɒ����`����ꂽ�̂́A�����g��A����v�ɓn�����Ő��A��C�Ȃǂ̍��m�����{�Ɏ����A�����Ƃ����B���q����ɂȂ��āA�����͕����ƌ��т�����ɂȂ�A�V��@�̉h���T�t���u�i���{���L�v�Ƃ����{�킵�Ă����̌��p������A���������N��ۂ�ő�ϖ𗧂��ݕ��ł��邱�Ƃ������L�������Ƃ͑傫���B
�@�Ȋw�I���͖@�Ȃǂ��Ȃ���������̊��o�I��ۂ����炱���A���̒��ɐ^���������Ă��܂��B
�@�����͑傫�������āA�Β��A�g���A�E�[�������ɑ�ʂ����B���̎O�͂�����������c�o�L�Ȃ̃`���̗t�������A���y�̒��x�ŕ�������B���̒��t�ɁA100�xC�̏��C��30�b�قǂ��ĂāA�|���t�F�m�[���_���y�f�̊��������킹�Ă��݂��������̂��Β��ł���B
�@�Β��ł�����̏�����A��̐����ߒ��̈Ⴂ�ɂ���Ă������̎�ނ�����B
�@�ʘI ���̖ɕ��������Ē��˓����ĂȂ��悤�ɂ��āA�_�炩���ΐF�̑N�₩�ȗt�Ɉ�Ă����́B �V���������Z�����ԏ����ċ}���ɗ�܂��A���₩�ɂ���Ŏd�グ��B �a�݂��ł����Ȃ��A���܂݂̂��Ƃł���A�~�m�_�𑽂��܂܂�₩�Ȃ����ł���B
�@�����@���z�����[���ɗ��тĐ��炵�������݁A�����Ă���悭����Ŏd�グ��B ���܂݂̐����Əa�݂̐��������悭���a�������ŁA����₩�Ȗ��B
�@�Ԓ� ������Ɏc�����t��A �ӏH�ȂǂɐL�тď����ł��Ȃ����t����ł��钃�B
�@�s���A�_���@�s�������W�߂����́B
�@�Β��ɂ͊e��̉Ȋw�������܂܂�A�e��̌��\��������ꂢ��B
??�a�C�\�h���ʁA??�K���}�����ʁA??�����K���a�\�h���ʁA??�F�m�Ǘ}�����ʁA??�����Ǘ\�h���ʁA??�F�m�Ǘ}�����ʁA??�E�ی��ʁA??�_���\�h���ʂȂǂ��������Ă���B
�@�����̌����҂̐��ʂł��낤���A���ʂ͂��܂�ɒ��q�������B���v�w�I��@��p����ΗL�Ӎ����o��̂��낤���A���ɂ͐����ȂƂ���A������肱�������̂ł�?? �Ƃ������x�̊��o�������ĂȂ��B�q�g�̊ώ@�f�[�^�v�����Ɏ������ނɂ́A�l���͒������邵�A���������A�e��������q���������邩��ł���B
�@��\�I���������͐��������A��\�I�ɂ͈ȉ��̂悤�Ȃ��̂炵���B
??�|���t�F�m�[��??�J�t�F�C��??�^���j��??�V���E�_??�t���{�m�[��??�r�^�~��C�E�E�E�E�B
�@����琬���́A�����x���̐ێ�Ȃ�ߏ�ێ�ɂ͂Ȃ炸�A�}�C�i�X�̍�p�͂Ȃ��炵���B
�@2/26�i���j�������g�@ ���N�N���j�b�N�h�b�N�@�@
2:00�N���B�����`�F�b�N�B�k�R�ȂǁB�Ǐ��B6:40�o�X�ѐ�a�@�B7:10-18:30�a���Ή��A9:00-11:50���N�N���j�b�N�h�b�N14���A���ʔ���14���A�ӊO�Ǝ��Ԃ����������B12:00�a�@�B�����A14:00���@���ґΉ��B�f�[�^���͂Ɛ����A19:30�A��A�[�H�A21:00�A�Q�B��6091���B
�Β�(2) �@�S�s�S��ˑR�⒃���D�ނ悤�ɂȂ���
�@����75�N�������ƗΒ������D���Ă����B�K�Ȃ��ˑ��ǂ��A�͂��܂����ł��H���ɂ͂킩��Ȃ��B
�@���̗Β��ɋ��߂�����͑��Ɂu�Z���v���Ƃł���B�Z����Β��t�̃O���[�h�͂�قǂЂǂ����̂łȂ�����܂�C�ɂ��Ȃ��B�p���钃�p�̒��q�͓����͔��ł��邱�Ƃ��v���̈�ł���B������́u�₢�v���Ƃł���B
�@��N5���ɐS�s�S�ɂ��Ǝv����ċz�s�S�Ɋׂ������A�����̓��@�ő傫�Ȍ��ǂ��Ȃ������B�����A�S�̓I�ɑ̒��A�̗͂�1-2�����N??�قǒቺ�����B
�@�S�s�S�̌�A�s�v�c�Ȃ��Ƃɋ}�Ɋ������ɂȂ����B�H���ȊO�̐����ێ�A���̏ꍇ�͎�ɗΒ��ł��邪�M���M���ɗ₦�����̂łȂ���Ζ������Ȃ��Ȃ������Ƃł���B
�@�S�s�S�͏z��Q�̂��߂ɑ̂̕��M�ɏ�Q������Ƃ����B���̂��߂ɔM���ǂ̍ۂȂǂɂ͊댯���q�̈�Ƃ���Ă���B
�@���͔�r�I���������Ȃ����Œʏ�^�I���Ȃǎ����^�ԕK�v�͂Ȃ������̂ł��邪�A�S�s�S�늳����A�����A��ʒ��S�Ɋ������ɂȂ����B������Ə������ł͊������ꗎ���邽�߂Ƀ^�I�����K�v�ł���B
�@�P�ɉ���ɂ�鎩���_�o�̏�Q�Ȃ̂��A7�܂����p���Ă���S�s�S�̎��Ö�̉e���Ȃ̂��͂킩��Ȃ��B
�@����I�ɂ́A�����Ɠ����Z�����ꂽ������500ml�̃K���X�r2-4�{���Q���Ă����B�����{�����čs�����R�͗Ⓚ������邽�߂ł���B�y�b�g�{�g���͊���邱�Ƃ��Ȃ��֗������Β��̃C���[�W�ɂ͍���Ȃ��̂ŗp���Ȃ��B
�@�Ƃł��E��ł��Β��̈ꕔ��Ⓚ����B
(���͗Ⓚ���@�Ⓚ�ɂɓ����Ƃ��ɗe�ʂ����炵�߂ɕێ�����̂��R�c�@����ɗⓀ���Ă��Ȃ����𒍂��ň��ށ@�e�ʂ����炷�͕̂r������Ȃ��悤�ɂ��邽��)
�@�R�b�v�ɕX����ꃍ�b�N���ɂ��Ă������̂����A���ꂾ�ƗΒ������X�ɔ��܂�̂ł��܂�D�܂Ȃ��B
2/25�i���j��⊦���@�܂�@
1:50�N���A�{�ǂ݁B�f-�^�����B�Ǐ����S�B�f�[�^�����A�ߑO�Ɠ����\���J�n�B���j���_��8:00����A�E�N���C�i���B���}���\���ꕔ����B���߂̂ǂ��܂�A2�T�ԑO�ɒ��f���������̉�B�V�������`�F�b�N�A15:00-19:00�a�@�A�Ɠ��͔��e�@�ȂǁB�����A�Ǐ��ȂǁB19:00�[�H�A20:30�A�Q�B��3010���B
�Β�(1) �@�ˑR�⒃���D�ނ悤�ɂȂ���
�@���͏�����������Β��D���������炵���B
�@3-4�̂�����A�����Ȃ��炨��������ł��č��z�c�ɂ܂����ē]�|�A���q�̉��ŕ@������B�@�땔����ău���u���A���@���͔畆�ꖇ�Ŋ�ƂȂ����Ă����Ƃ̂��ƁB��t�̑c������肭�D�����킹���炵���B���܂ł��@�땔�ɂ͑傫�ȏ��Ղ��c���Ă���B�����A�@�������Ă�����A�܂��͕ό`���Ă��Ă����玄�̐l���͕ς���Ă������Ƃ��낤�B
�@�a��Ŗ��n�Ő��܂ꂽ���̖����Ȃ��ł��ꂽ�c���A�@�̎��Â̂��Ƃ��܂߂āA�c���ɂ͂ƂĂ����ӂ��Ă���B
�@�����Ȗ��⍁���y���ސH�i�Ȃǂ̕���͎���������B
�@�Ⴆ���C���A�R�[�q�[�A���{���ȂǁB
�@�Â��Ɉ�l�Ŋy���߂Ηǂ��̂ɐ��I�m��������A�E���`�N���������Ȃǂ�������B�n�D�̃��x���܂œ��荞�b��͖��f�ł��̂悤�ȕ��ɂ͋߂Â��Ȃ��l�ɂ��Ă���B
�@���y��I����ɉ��t���e��b��ɂ���̂������B
�@���t�̔\�͂͊��o�E�����\������̂ɂӂ��킵�����̂ł͂Ȃ��A�Ǝv���B
�@���̚n�D�i�́A�Ƃ����ƍŋ߂͗Β��B
�@�����^�o�R��炸�A�l�t���������w�ǂȂ����������������Đɂ����Ȃ�����ł���B���ɂ���ĈقȂ邪�䂪�Ƃ̒��t�w�����5-10���~���x�炵���B�����A���ɂ͂��ꂪ�D���Ƃ̒��łǂꂾ���̈ʒu�ɂ��邩�͕�����Ȃ��B���ׂĉƓ����I���̂ŎI�Ɋy����ł��邾���B���݂����Ƃ��ɗΒ����������Ŗ�������B
�@�Β��͒ʏ��100�O����������2000-5000�~�̕i�A���ɂ�8000�~-12000�~�Ɣ�r�I�����̂�p���Ă���炵�����A�l�i�ɂ��Ⴂ�����ɂ͋�ʏo���Ȃ��B
�@�����A�䂪�Ƃ̒��K���̔p���ʂ͔��[�ł͂Ȃ��B�}�{�̊W�������オ�邱�Ƃ�����قǑ�ʂɒ��t��p����B���|�p�̔엿����邽�߂ɉ䂪�Ƃł͖�؋��Ȃǂ̓R���|�X�g�ɒ~����̂ł��邪�A�����K���������߂����߂邱�Ƃ�����B
�@���͊T���ĈႢ���킩��Ȃ��l�Ԃł���B����I�ɍD��ł���̂����A�����̕���ł����͖����s�ł���B
�@�����Β��ɋ��߂�͔̂Z���B�����A���ɂ͐[���������D�ށB���������͈��܂Ȃ��B�Z�߂��āA���ɂ͈݂̋�������Ȃ邱�Ƃ����邪�A����ł��\��Ȃ��B
�@�Ɠ��͗ʓI�ɂ͂��܂���܂Ȃ��̂ɁA���̂��߂ɂ͐�ڂȂ��p�ӂ��Ă����B�������I�Ɉ��܂���镵�͋C���Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B�o�Ύ��ɂ�500ml�̃K���X�r��2-4�{�������Ă����B�����玄�͂��������ߏ�A������Ԃł���B
�@���͖��ȂǕ�����Ȃ�����ǂ�Ȃ��̂ł��y���߂�B�Ɠ��͎��̂��߂ɂ�2000�N���X�̒����A�����̂��߂ɂ͂�荂���Ȓ���p����悤���B
�@���̓y�b�g�{�g���̎s�̕i�̒��͍D�܂Ȃ��B�������Č��B�����ōw���������Ƃ͖w�ǂȂ��B
�@�u���z���̒��͈��ނȁv�A�Ƃ�����H���Ă������A1996�N�̃y�b�g�{�g���̂����������ɂȂ������̓V���b�N�����B����������߂Ȃ������B�y�b�g�{�g���̂����͉�c���Ŋ���ɔz�z�����l�ɂȂ�A���{�̂����������ς�������A���͖����ł��Ȃ��B������������ŁA������ɂȂ���x�̊S�����Ȃ��B
2/24�i�y�j�܂菬��@�\���{�l���쐬�J�n
�@2:00�N���B�����ߑO�͐V���A�����A�k�R�ȂǁA�����A�Ǐ��A�\���{�l���쐬�J�n
14:00�Ɠ��ƂƂ��ɕa�@�B19:00�A��A�[�H�A19:30�̂ǎ����`�����s�I�����ς�B������������ȉ̏��A�D��Ȃ��B21:15�A�Q�B������1990���̂݁B���ւ��������o���B
��(3) �@�J�b�g�� ���������֗��Ȋ۔����́u�݃\�[�X�v
�@�J�b�g�݂̐H�ו��͐F�X�B
�@�u���ȕ��݁v�A�u���ׂ���݁v�A�u�ݖ��݁v�A�u�g���݁v�A�u�[���݁v�A�u�̂�݁v�Ȃǂ̂ق��A�痿���̒��߂Ƃ��Ă��L�p�ł���B���Ƃ��čT���߂����牞�p�͈͍͂L���B����͓����������B
�@���͒��N�A�u���Ȃ��݁v�Ƃ��ĐH�ׂĂ������A����A�Ɛl���۔����́u�݃\�[�X�v�Ȃ���̂��X�[�p�[�Ō��������ɍw�����Ă����B
�@���ꂪ�ƂĂ����������A���֗��ȏ��i�ł���B
�@�w�������̂́A�u�������Ȃ��v�A�u�������v�A�u�����܂���v�A�u���܂�������v�A�u����݂���v�A�u�݂��炵�����v�ł����������ɂ�����ނ�����悤�ł���B
�@�e���i��3�������܂ɓ����Ă���130�~���x�B
(�u�݃\�[�X�v�e��)
�@���͒��H���Ɏ��܃J�b�g�݂�H�ׂ�̂ł��邪�A�I�����������Ċy�����B
�@�u�݃\�[�X�v���J�������۔����ɂ͊��ӂł���B�۔����͐H�i���H���[�J�[�B�ӂ肩���̍ő���ƂŁu�̂肽�܁v��u�����y�v�Ȃǂ̐��i���E�̔����A���݂ł͐������̃��g���g�̒����H�i�Ȃǂ����Ă���B
�@���̏ꍇ�A������10ml�قǂ̐��ƃJ�b�g�݈�����A800W �̓d�q�����W��50�b�B����Ɂu�݃\�[�X�v��܂̕����𗍂߂邾���ŏo���オ��B��������Ȃ��Ȃ������ł���B
�@���H�̑I�����������Ċy�����B
�@
2/23�i���j�V�c�a�����ŏj�� ���ኦ�g�@�ϐ�Ƃ��Ă�1-2cm
2:10�N���B�V�c�a�����ŏj���B���������Ɍ����L�O���ƍ��킹3�A�x2��B�l�R�Ή��Ȃǂ��Ȃ���g���g���O�_�O�_�߂����A5:30���[�`���ɁB�����E�Ǐ��B5:30�R�S�~�p���͏����݂̂ł��܂��B14:00�Ɠ��ƂƂ��ɕa�@�B���҂͗��������Ă���B�V���L���`�F�b�N�A���͂ق��B�����B�n�[�h�f�B�X�N�������R�s�[�J�n�B�A��܂ŊԂɍ���Ȃ������B18:30�s�[�R�b�N�o�R�A��A����͐Έ䂳��̒a�����B19:15 �A��A�[�H�A21:15�A�Q�B������2914���B�E�N���C�i�N�U2�N�B
��(2) �@�s�̕i�̃J�b�g�݂͏퉷�Œ����ۑ����ł��A�֗�
�@�����Ă̖݂̓J�r�₷���B
�@�N���̉Ɠ���Â̖݂��p�[�e�B�ŏo���オ����3�i�d�˂̂������݂͊�������ɁA�݂���Ƃ����ō�������ߏ�������Ēu���̂����A1�T�Ԃ��o�����ɂقڗ�O�Ȃ��\�ʂɗΐF�A�Ԃ⒃�F�̃J�r�������n�߂�B�A���R�[�������Ă݂������ʂ͂ǂقƂ�ǂȂ������B
�@�Ȃ�ł����Ă̖݂̓J�r�₷���̂��H�H���ꂾ���h�{�L�x�ł��邱�ƁA�o���オ��܂łɒ����ԋ�C�ɂ��炳��邱�ƁA�����̐l�肪�G�邱�ƂȂǂɊW���Ă���̂��낤�B
�@����̍�i�ł́A�u��B������A�Ȃ�Ŗ݂��J�r��̂ł��傤��???�v�A�����́u�n����Y!!!�A����Ȃ��Ƃ��������l���Ȃ��ő����H�����܂������E�E�E�v�Ƃ����̂����邪�A�����������ł���B
�@���t���זE�̔|�{�̎������d�˂Ă������́A���ɔ|�{�M�����t�זE�̃R���j�[�łȂ��J�r�̃R���j�[�Œu��������Ă��Ĝ��R�Ƃ������̂����A���ۃ`�F���o�[���ō�Ƃ����Ă��Ă���萔�̓J�r�ɂ��ꂽ�B���ꂾ����C���ɂ͍ۂ�J�r�����V���Ă�����̂��Ǝv���B
�@�ŋ߂͊e��̖݂��s�̂���Ă���B�ݍD���̎��ɂƂ��Ă͊������B�䂪�Ƃł͐V�����̖^�Ђ̐��i�����p���Ă��邪�A�퉷�ŕۑ����Ă��J�r�邱�Ƃ͂Ȃ��B����͕s�v�c�ł���A���قł�����B�ܖ�������1�N������B
(���p�̐��)
�@���̎Ђ̐��i�̓N���[�����[�����Ő������A�ܓ��ɒE�_�f�܂����A�ܓ��_�f��Ԃɂ��邱�Ƃɂ��J�r���̔�����h���ł���Ƃ̂��ƁB�ۑ��܂ȂǗp���Ă��Ȃ����ܖ�������1�N�ȏ゠��̂͋����ł���B
�@���݂ɃJ�r���������ꍇ�A�ܑ̖������玄�̓J�b�^�[�i�C�t�ŃJ�r�̕�����������ĐH�ׂĂ��邪����͂������Ƃł͂Ȃ��B�\�ʏ�̃J�r������Ă��A�J�r�͌��\���[���܂ŐN�����Ă���B�J�r��ڂŌ�����\�ʂ���������Ă��s�\���ł���B�X�̃J�r�ɂ��Ă͒��ׂĂ��Ȃ����A��ʓI�ɃJ�r�͗L�łƍl������������悤�ł���B
�@�����ܑ̖������Ђǂ��J�r���ꍇ�ɂ͏������ׂ��ł��낤�B
2/22 �i�j���C��@�l�R�̓�
3:30�N���B�ɂ��ɂ��ɂ��̌�C���킹�Ńl�R�̓��Ȃ̂��������B�����E�f�[�^�����A�Ǐ��B�������݂��w�p���B8:30�Ɠ��ƕa�@�B�����{�ǂ݁A�V���`�F�b�N�{���́B�A11:00�a���Ή��A13:30�����A�Ǐ��A���̂ق��B�����f�[�^���������B19:15�A��[�H�B20:30�A�Q�B��3098���B
��(1)�@�����Ă̂���
�@���͖݁A���₨�݂ƌĂڂ��A����D�����B
�@���N�O�܂ł͗Ⓚ�ɂɎs�̂̐�݂������Ă���A���H���Ɏ��܉������܂Ԃ��ĐH�ׂĂ����B�������N�A�Ⓚ���Ȃ��Ƃ��J�r�������Ȃ���݂�����悤�ŁA�H�i�_�i�̏�ɒ������Ă���B
�@�����Ă̂��݂ɂ͎��͋�������������Ă���B
�@�����Ă̂��݂́A�Ȃ�ł��w���ł��錻�݂ɂ����Ă��قƂ�ǎ�ɓ���Ȃ����ґ�i�ł���B
�@�����Ă̂��݂́A���̂ǂ����Ƃ��Ă��ψ�ȏ_�炩���ƒe�́A���炩�ȐH���A�ǂ��܂ł��L�т鐫���B����͏����ł��������Ă��܂���������키���Ƃ��ł��Ȃ��A��u�������킦�Ȃ��A�ґ�Ȋ��G�ł���B
�@
�@������̊y���݂͏���������������̖ݕĂ̔��������B�ɏ�Ȗ��ł���B�����ꕔ�����ĐH�ׂĂ����B
�@����Ȏ�������A���݂��@�Ƃ������̂ɑ��X�ɒ��ڂ����B���ł������Ă̂��݂��H�ׂ���Ƃ͂Ȃ���ґ�Ȃ��Ƃ��낤���B�@�̒��Ŕ����ď_�炩�Ȃ��݂��o���オ���Ă����l�q���y�����B�������A�o���オ�������݂ɂ͊��҂����悤�ȐH���͓����Ȃ������B�s�̂̐�݂Ƃ̈Ⴂ���w�E�ł��Ȃ����x���B�݂��@�̌����͂��Ăɍׂ����U����^���A���̒�ɂ����H���ŝ��a���Ȃ����������H���́A�n�݂Ƃ͎�������قȂ�B���݂��@�̏o�Ԃ͑啝�Ɍ��������B
�@�n�ł��������Ă̂��݂�H�ׂ邱�Ƃ��ł���@��́A�B��Ɠ�����ɂ��Đe�ʂ̎��ōs����N���̖݂������ɂȂ����B
�@��������29���O��ɁA�e�r�����˂āA���B�A�e�ʂ̎q�������ɖ݂��̕����𖡂���ė~�����Ƃ̂��ƂŊJ���ė����B����10����ɂȂ邾�낤���A�Ƒ����o�ŁA�V�������琬�l������҂��Q�����A�����ꍇ��30�����x�ɂȂ����B
�@�l�t�������͓���ł͂Ȃ����A���i�����b�ɂȂ��Ă���H�c�̐e�ʂ̕��X�Ƃ̌𗬂�����A���ӂ̈ӂ����߂Ď����K���Q�����ė����B
�@�����ł́A�̂Ȃ���̕��@�Ŗ݂����B
�@�O�����琅�ɐZ���Ă���ݕĂ������A�傫�ȉP�ł��B��P�A���ɂ͎O�P���B
�@��r�I�����ȎႢ�j���������S�ɁA���ɂ͎q�������ɂ��n���������Čo��������B���͌��Ă��邾���B
�@���オ�������݂́A���ꂳ����Ǝq���B�ɂ���Ē����ɁA�̂��݁A�������ɁA�啟�ɁA����݂ɁA���������ɁA�G�ςɕϗe���Ă����B�ł����ݗނ͌����Č��Ă���͗ǂ��Ȃ�������������͍ō��ł���B
�@���������o���Ή��ł���ɓ��鎞��ł��邪�A�����Ă̂��݂͓���ł��Ȃ��B�N�Ɉ��A���̉�ł������키���Ƃ��ł��Ȃ��M�d���ґ�i�ł���B�@
2/21�i���j����ߌ�~��@���g�@�Ɠ��u����
2:15�N���B��炸���������߂����B�{�ǂ݁A�����B���w��ʁB8:50�Ɠ��Əo�A���w�A�Ǐ��A11:30�a���B�V���`�F�b�N�A���́B�N���@�\�Ɍ����̍Ĕ��s�˗��B14:30�a���J���t�@�{EC�D���ґΉ��A16:30���҉Ƒ��ʒk�B17:00�Ɠ��u����A�퍂��فB�����f�[�^�����A�Ǐ������B21:00�A��[�H�B18:00���H�A21:50�A���B��3895���B�[���܂Őϐ�5cm�B
2/20�i�j���g�����g�[�s�v�@�~�J�@���ʊO���@
1:20�N���B�l�R�Ή������ȂǓǂ݁A�f�[�^�����A5:20�R�S�~��o�B��ƁE���s�Ƀw�b�h�����v�܂��K�v�B6:40�o�X�a�@�B�V:10-�W:20�a���Ή��A8:35-12:00���ʊO���B�����B�Ǐ��A�a���Ή��A19:15�A��A�[�H�A21:00�A���B�����v�F��6738���B
2/19�i��)�@���J�̂�����@ ���g�g�[�s�v�@���N�N���j�b�N�h�b�N�@�@
�@1:30�N���B���������A�k�R���B�����̔@���B6:40�o�X�a�@�ցB7:10-8:15�a���Ή��A�V���`�F�b�N�ȂǁB9:00-11:30���N�N���j�b�N�h�b�N14���B���ʔ���Ȃ��B11:45�a�@�B�����A�V�����́A�{�ǂ݂ق��A14:00�a���A�V���@�A���@���ґΉ��A19:20�A��A�[�H�A20:30�A���B�����v�F��7209���B
2/18�i���j���g�I�������@�~�T���z�[���X�^�b�t���K�@�Ɠ��]���^�o�U�[
2:10�N���A�̂�т�ƃ��[�`���B�����͕����֘A�B�f�[�^�����B8:30�Ɠ��]���^�o�U�[�ƏH�c�s��t��s�����J�u���B10:00�~�T���z�[���X�^�b�t���K���߂��܂Œ~�σf�[�^�����A�Ǐ��B�̂ǎ����A�V������B������B�����}���ĕ��ފJ�n�B19:00�[�H�A20:00�A���B��4280���B�Z���A�ɂĐڒ��܁B�K�i�Ƀl�R����s���S���B�o�����B���߂ĘA�x�B
���{�̐l�����2024(16)�@�j�Ƒ��̎q���(4)�@�玙�͊j�Ƒ��ł������A�܂��Ă�Аe�ł́E�E(2)�@
�@�P�ƂŎq��Ă͍���B������A�����͒N���̏��͂Ȃ���Ύq��Ă͌������B
�@���̂Ƃ��̉����̌��ƂȂ�͎̂O�ł���B
�@���F�Ǝ���玙�����̑���₪���e�ł��萫�̃p�[�g�i�[�ł���j���̈玙�ւ̎Q���ł���B���ꂪ�Z���ł���A���Ȃ�玙�Ɋւ��鏗���̘J�͌y������A�j�Ƒ��ł����Ă��A�ۈ珊�Ȃǂ̎Љ���𗘗p����A�q��Ă̘J�͈�w�y�������B
�@�������A�䂪���ł͈�ʓI�ɒj���̎Q���͕s�\���ł���B
�@���݂Ɏ����Ă��j���̈玙�ւ̋��͂́A���̍��̒j���̂���悤�̗��j���Z���Ɋ֗^���Ă���A�ٗp�@��ϓ�������Ă��A�Ǝ��͋ϓ��ɂ͕��S����Ă��Ȃ��B
�@�����{����J�Ȃ̒��������Ă��v���Ǝ��S���Ă����͏��Ȃ��悤�Ɏv����B�啔���̍Ȃ����́u�ƒ�Ǝd���𗼗�����̂͑�ς��v�Ǝv���Ȃ���A�u�����Ă����ʁE�E�v�ƕv�̖�������Q���Ȃ�����㉹���f����������Ă���B
�@�������A�ǂ����Ă��̂悤�ɕv�͉Ǝ����菕�����Ȃ��̂ł��낤���B
�@����ɂ́A�ȉ��̈��q���e�����Ă���Ǝv����B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
���v�̎����ƍȂ̎����̍����傫�����ƁA
�����{�̒j���̘J�����Ԃ�ʋΎ��Ԃ������A
���Ζ��O�̕t�������Ȃǂʼnƒ�؍ݎ��Ԃ��Z�����ƁA
�����ʖ����ρA�j�����ړI�S��Z���Ɏc���Ă���A
���Ǝ����d����艺�ɂ݂�S��Ȃ�
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�@�Ǝ��������������s��˂Ȃ�Ȃ��Ƃ�����A�ƒ�E�Ƒ��̑��݂͎d�������鏗���ɂƂ��đ傫�ȏd�ׂƂȂ�A���������������ɓ��ݐ�Ȃ�����̈�ɂȂ��Ă���B
�@�܂��v�w�Ԃł�������q���̐����N�X�������ċߔN�͕���1.9�l�ƌ������Ă��邪�A����͈�l�����q�����������Ȃ��v�w�������Ă��邱�Ƃ����܂��Ă���A���̂��Ƃ��l�����̑傫�ȗv���ƂȂ��Ă���B
�@���F��v�w�̏o���Ɋ֘A����e�ʉ��҂̊֗^
�@�]���͌������ƂƉƂƂ̉��k�Ƃ��đ������A���܂�Ă���q���͏����̐e�ʉ��҂̔ɉh�ɂ��ւ��d�v�Ȗ��ł������B�������Ȃ���A����Љ�ł͂��̂悤�ȍl�������A�����͌l�ƌl�̌��т��ɂȂ��ĉƑ��Ԃ��J�͌`�[��������B
�@��O�̎Љ�ۏ�̊֗^
�@���{�ł͎Љ�ۏ�Ƃ������ŋ߂܂ō���ґ��S�ł������B���A����ŏ��q����Ƃ��Ďq��Ďx�����_�c����Ă��邪�A���łɏ����̐����l���ێ��̃��x�������������Ă��܂��Ă���̂ŏ��q����̌��ʂ͖R�����B
�@�����A�ŋ߂܂Ŏq��Ďx�������ӂ��Ă����̂ł��̃c�P�͑傫���B�ǂ��܂Ŏq��Ċ����ǂ��Ȃ�̂��A���ʂ��y���݂ł���B
2/17�i�y�j���� ���g�@
3:30�N���B�l�R�Ή��Ȃǂ������i�߂�B�ߑO�~�σf�[�^�����A�Ɠ��͕a�@�ƕ���ŕs�݁B�ߑO����\���֘A�̎����W�߂ƕ��ށB�Ǐ��A�f�[�^���ȂǁB�ߌ������A�f�[�^�����B�\�������̂��߂̎������W������B19:00�[�H�A20:45�A�Q�B��2886���B�^���s���B
�o�����B
���{�̐l�����2024(15)�@�j�Ƒ��̎q���(3)�@�玙�͊j�Ƒ��ł������A�܂��Ă�Аe�ł́E�E�@
�@�����̏o�Y���̃��X�N�͉䂪���ł͈�Â̔��B�ő啝�Ɍy�������B
�@�������A�D�P�o�Y�ւ̐S�̕��S�A��X�܂ł̎q��Ă̐S���I���S�͒j�ɂ͗����ł���B���ɂ͎v�������Ȃ����E�ł���B�J��Ԃ����A���������h���Ă�܂Ȃ��̂͂��̕ӂ̂��ƂɗR�����Ă���B
�@����ɁA�q�g�̏ꍇ�A���܂�Ă����Ԃ����͂܂��������ŗ���Ȃ��A��l�Ő����邱�ƂȂ�100%�o���Ȃ��B�X�Ɏ������Ԃ���N�ƒ����A����Ɨ������I������Ƃ��Ă��A�����ĕ�������̂łȂ��B�쐶�̒��Ȃ�����^������30���قǂŗ����オ����s�ł��邪�A�q�g�̏ꍇ��1�N��������B
�@����̓��{�ł́A�q�ǂ���20�ɂȂ�܂Őe���ʓ|������̂����ʂł��邪�A�q�g�̎�����100�N�ƒ����Ƃ͂����A20�N�Ԃ���l���������Ȃ��q��Ă͏����ُ�Ɏv����B
�@�ŋ߁A���N�ɂȂ��Ă��e�Ăɂ��ēƗ����Ȃ��q���B���U�������B
�@��Y�ƁA�q��ĂɘJ�͂��������́A�q�g�̐����w�I�����Ƃ�����B
�@�������P�ƂŎq��Ă�����͕̂s�\�ɋ߂����A���ۂɂ͏��Ȃ��炸���̂悤�ȗႪ����B�C���A�Љ��������v���Ă���ꍇ�A���Č��ʐU�肵�Ă��鎖��炠��B���ʓI�ɑ命���̉ƒ�Ŋj�Ƒ��Ŏq��Ă���Ă���A�V���O���}�U�[���������Ă���B
�@�D�P���Ԃ��A�����͐g�d�ŕs���R�Ȑg�̂��������Ȃ��玩�����g���x���Ă����˂Ȃ�Ȃ��B����ɏo�Y��͎������x���A�Ȃ����玙�����邱�Ƃ́A�傫�ȕ��ׂɂȂ�B
�@�P�ƂŎq��Ă��s�\������A�����͒N���̏��͂Ȃ���Ό������B
�@���̂Ƃ��̉����̌��ƂȂ�̂́A
-------------------------------------------------------------------
���́A�q�ǂ��̕��e�ł���A���̃p�[�g�i�[�ł���j���B
���́A���ɁA�����̗��e�A�Z��o���A�e�ނȂǂ̉Ƒ��̃����o�[�A
��O�ɂ́A�Љ�ۏ�̊֗^�B
-------------------------------------------------------------------
�@���̕��@�����ՓI�ł��낤���A�������A���̎O�v�f�Ƃ�����������ׂ�����Ă���B
2/16�i���j���g�ė��܂萰�@ ��Ȓ��ʕa�@�O���@
2:20�N���B�l�R�Ή��A�����f�[�^�����A�Ǐ��B5:30�R�S�~�����̂݁B7:35Taxi�w�ɁB8:11���܂��B9:0�O��Ȓ��ʕa�@�O���A15:30���艮�Ȃ��ATaxi�a�@�B�V�������́B16:30���@���ґΉ��A19:30�A��A�[�H�A20:15�A�Q�B������4706���B
���{�̐l�����2024(14)�@�j�Ƒ��̎q���(2)�@�q�g�̏o�Y�͂ƂĂ��댯
�@�q�g�̏o�Y�E�q��Ă͑��̓����ƑS���قȂ��Ă���B
�@�q�g�̍s���́A���ɂ͐g�̓I�����ɂ̂ݗR�������A�����̉e����Z���Ɏ�B
�@�q�g�������Ă��鐶���Ƃ��Ă̓��ꐫ���Ċm�F���A������ӂ܂��A�q�g�̏o�Y��q��ĂɊւ�鐧�x��Љ�I���K�Ȃǂɂ��čl���Ă݂�B
�@�q�g�͂����炭400���N�ȏ�O���痧���Đ^�������ɕ����n�߂��B�葫�����R�ɂȂ�A�m�\�����B���A�]�͂ǂ�ǂ�傫���Ȃ��Ă������B
�@�������s������ƁA�l���ŕ����Ă�������ƈ���ĕ��o���̓����̏d�����x���邽�߂ɍ��Ւ�̑g�D����v�ɂȂ����B
�@���Սo�̑���̔z��̓R���p�N�g�ɂ܂Ƃ߂��A�q�{�͑O�����A�Y�����Ȃ���A�o�Y�ɖ�����������悤�ɂȂ����B�����āA�q�g�̔]�e�ʂ��ǂ�ǂ����A ���܂��q�ǂ��̓����傫���Ȃ�A�܂��܂��q�g�̏o�Y�͍���ɂȂ����B
�@�q�g�ɋ߂��`���p���W�[��S���������Y�Ŏ��ʂ��Ƃ͂قƂ�ǂȂ��Ƃ���邪�A�ߑ��w�����B����O�́A�q�g�̏����͂��Y�ō��p�x�Ŏ��S�����B
�@�l�����̘b�肩�猩�ė]�k�ɂȂ�̂ł��邪�A���̕t�߂ɂ��Ă̎������L�ڂ���B�@���j��̐l���ŁA���Y�Ŗ��𗎂Ƃ�����͖����ɉɂ��Ȃ��B
�@�����ʂ��猤�����ꕶ�����o�ł���Ă���B
�@���̂����̈���A�w�h�ԕ���x�͕����������̌ÓT�ŏ����̎�ɂȂ镨�ꕗ�j���ŁC�S40���A1092�N�܂ł�2���I�ɂ킽�鎞��ɂ��Ă̋{��M���Љ�̐����j�̋L�^������Ƃ���Ă���B
�@���̒��ɁA����V�c���{���q���甒��V�c���䓹�q�܂�47���̔D�P�E�o�Y���L�q����Ă��āA���{���q��M���Ɍ�鐝���{�܂�11�����D�P�E�o�Y�ɔ������S���Ă���B���S���͎���23.4%�ɂ��Ȃ�Ƃ����i������t�@���Y�̖����@���{�}�����s��@1996�j�B
�@���̓����̈�Â͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��������͑z�����o���Ȃ��B�g���̍������M�Ƃ������X�̊�������L�q�Ƃ��Ďc���Ă����ސ��ł��邪�A��ʏ����̏o�Y�͈�w�댯�ł������Ǝv����B
�@���ꂩ��m�邱�Ƃ��o����̂̓q�g�̔D�P�o�Y�������Ɋ댯�Ȃ��̂��C�Ƃ������Ƃł���B�D�P���̊e��̍����ǁA�o�Y����A�o�������łȂ��C�o�Y��̊����ǂɑ��Ă������͂Ȃ����ׂ͖��������͂��ł���B
�@�D�P�o�Y�Ɋ֘A���Ď��S�����Y�w�͐����ł����ɂ��̐����������ƌ��������b�⌾���`���������B���ɏo���������Y�w�̎��͔ߎS�������Ǝv���A�S��Ƃ��ĉ����g���܂݂�̏�ԂŌ���u���̐Ԃ���������āE�E�v�ƐԎq�������o���ƌ����l�Ȗ��b�͊e�n�ɓ`����Ă���B�����āA���������Ȃ������D�w�̖S��͎��̔D�Y�w�ɂƂ���D�P�o�Y�̎ז�������Ƃ���A���S�����D�Y�w�͓��ʒ��J�ɒ������Ƃ���Ă���B
�@�킪���̔D�Y�w�̒ᎀ�S���͂���50�N�Ō������o��10���l������3�l���x�ƂȂ��Ă���B�D�Y�w�ɂƂ��Ă���ÊW�҂ɂƂ��Ă���������A����������ē�����O�ƍl���Ă͂Ȃ�Ȃ��B����܂����Â̔��W�̂������ł���B
�@�q�g����Y�ɂȂ������ƂƂ́A�q�g�̐����w�I�����ƂȂ��Ă��܂����B
�@���R�̐ۗ��͌������B
�@�����D�P�E�o�Y�E�q��Ă�ʂ��āA�����h���Ă�܂Ȃ��̂͂��̕ӂ�̂��Ƃ���ł���B
2/15�i�j�~�J�@ Web�w�K��
2:15�N���B�����`�F�b�N���B�{�ǂ݁A�k�R�ȂǁB8:50�Ɠ��ƕa�@�B���@���ґΉ��B�����V�����̂ق��`�F�b�N�Ɠ��́B�����֘A�̏����B18:30Web�w�K��uACP�v�B20:00�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B3558���B
���{�̐l�����2024(13)�@�j�Ƒ��̎q���(1) �j�Ƒ��Ƃ͉���
�@�j�Ƒ��͉Ƒ��`�Ԃ̈�ŕv�w��e�q�����ō\�������Ƒ��̂��Ƃł���B
�j�Ƒ��Ƃ͋�̓I�Ɉȉ��̂悤�Ȍ`�Ԃ�����B
-------------------------------------------------------------------
��g�̕v�w�̂�
��g�̕v�w�Ƃ��̎q�ǂ�
���e�܂��͕�e�Ƃ��̎q�ǂ��i���q���т��q���сj
�i�q������݂āj���e�܂��͕���̂ǂ��炩����Ɩ����̌Z��o������Ȃ�Ƒ��B
-------------------------------------------------------------------
(5�l�ȏォ��Ȃ鐢�т͌������A1-3�l�̐��т����������B�Ƒ��Ԃ̏��������@�\�͎���ꂽ)
�@�×��̊j�Ƒ��́A�j�Ƒ��Ƃ����Ă����͂Ɍ����W�҂������Z�݁A��Ƒ��I�ȋ����������c��ł����B
�@����ɑ��āA����̊j�Ƒ��A���ɓs�s�ŐV���ɐ��т��\����j�Ƒ��́A�ߗׂɌ����҂����݂��Ȃ��Ǘ������j�Ƒ��ł���B
�@�j�Ƒ��ł͑�Ƒ��ɔ�r���āA�v���C�o�V�[���ێ����₷������Ƒ��Ɣ�ׂāA�e�q�O����ɂ��Ǝ��J����玙�A�Ɠ��J���̕��S�A����҂�a�l�̉��Ȃǂ����Â炭�Ȃ�Ƃ����Ƒ��@�\�̒ቺ���B
�@���{�̏ꍇ�A�n���̎�҂���s�s���ɓ]�����Ƒ�����������ƂŊj�Ƒ����т��啝�ɑ��������B
�@�Ƒ��ɑ���ӎ��̕ω�������
�@�ȑO�́A�e�Ƒ��̒n������Y���p�����邽�߂ɒ��j�͉ƂɎc��A�e�ƈꏏ�ɐ��������Ă������Ƃ�������O�Ƃ���Ă����B�������A�ߔN�ł̓��C�t�X�^�C���̕ω��ɔ����āA�Ƒ��ɑ���ӎ����ω����u�X�̍l����D�悷��X���v�������Ȃ��Ă��đ�Ƒ������Ă���B
�@�l�ԊW�̔ς킵��������镗��
�@�e�Ƃ��邢�͐e���ƂƋ��͂������ĕ�炷���Ƃɂ������o�����l�ԊW�̔ς킵�����������镗��������A�v�w�Ǝq�ǂ������Ƃ������т�������O�ɂȂ����B
�@���������ɑ��闝�z�ƌ����̃M���b�v
�@2021�N�ɍ��������������̒����ł́A���������ɑ��闝�z�ƌ����̃M���b�v���傫���A�������̏㏸�Ɋ֘A���Ă���ƕ���Ă���B
1.�����������n�߂�ۂ̃n�[�h���i�Z���j������
2.�q�ǂ����Y�݈�Ă�ɂ͑����̌o�ϗ͂��K�v
3.�j���Ƃ��Ɍ����E�o�Y�E�q��Ă͑�ς��ƔF������Ă���
�@��҂͌�������ꍇ�ɂ͑命�����e�Ɠ�����]�܂Ȃ��B
�@����ł͐g�̓I�E�o�ϓI�E���_�I�Ɏx���Ă���鑶�݂������A�����̎q�����Y�݈�Ă邱�Ƃɓ��ݏo���Ȃ��Ⴂ���オ�����B
�@���̂��Ƃ͓��{�̐l�����̈���ƂȂ��Ă���B
2/14�i���j���� ���Ȏ�f �@�a���J���t�@�@�@
2:20�N���B�����`�F�b�N���B�{�ǂ݁A�k�R�B8:50�Ɠ��ɓ���a�@�B10:30-12:45���Ȏ�f�A������A�����B�V���`�F�b�N���́A14:30�a���J���t�@�A���@���ґΉ��B�ȍ~���w�A�G�����������B19:15�A��A20:30�A�Q�B�����v��3279���B
2/13�i�j����@���ʕa�@�O���@
2:30�N���B�l�R�Ή��B�V���x�����B����ƒ��������Ȃ��Ă����Ƃ��������B�R�S�~��o�A6:40�o�X�a�@�B7:10-8:10�a���Ή��A8:35-12:15���ʊO���B12:30�a�@�A�����B�Ǐ��A�V���`�F�b�N�Ɠd�q���B�V���@����A�Ƒ��ʒk�B���@���ҏ��u�Ή��B19:15�A��A�[�H�B21:30�A���B�����v�F��7199���B
2/12�i���j�U�x���@�܂�@�@
�@2:10�N���B���������A�k�R���B�����̔@���B11:40�]���^��ɍs���Ɠ��ɓ���a�@�ցB�ȍ~���w��X�A�V���`�F�b�N+���́B�����A�{�ǂ݂ق��A14:00�a���Ή��A���@���ґΉ��B19:10�A��A�[�H�A21:00�A���B�����v�F��3507���B
2/11�i���j�����L�O�̓��@�I���܂�~�J�@�@�@
3:00�N���A�̒��قډ��P�B�{�ǂ݁A�k�R�B���̑������̂��Ƃ��B�{�ǂݒ��S�B��NHK�̂ǎ����y���݂V���`�F�b�N�A�r���Ŕ\�o�n�k�Œ��f�B13:00-15:00�����B���̌㕶���E�{�ǂ݁A����A���w���S�B19:00�[�H�A21:00�A�Q�B�����v�F��2467���B
���{�̐l�����2024(11)�@�ٗp�V�X�e���̕ω�(6)�@�x�r�[�u�[���̍��̐l�����̍l����
�@�Ȃ��A���{���l���������}���邱�ƂɂȂ����̂��B
�u�l���ߏ�_�v��������
�@�o���������߂�̂́A�傫���u�������v�Ɓu�L�z��o�����v�̓�ł���B���{�̏ꍇ�͍��O�q�����ɏ��Ȃ��̂ŁA�����������ځA�o�����ɉe������B
�@�I���A���{�͏o������4.0���A1949�N�ɂ͔N�ԏo��������270���l�ƍő����L�^�����B�����̐��{�͐l��������}�����邱�Ƃ��ً}�ۑ�ƍl�����B
�@�l��������}���������Ƃ��ėv�����ꂽ�̂��A�Ƒ��v��(��ْ���)�ł������B��ْ����́A1948�N�ɗD���ی�@�����肳��A���������Ă̎Y�������^���Ƃ��ĕ��y���Ă������B���́u���ʁv������o������1947�N��4.54�������̂��A10�N���1957�N�ɂ�2.04�ɂ܂Œቺ�����B
�@����܂ł̂悤��3�l�ȏ�̎q�ǂ������v�w������A�q�ǂ�2�l���吨���߂�悤�ɂȂ����B
�u�Î~�l���v��ڎw���Ē�����}�������E�E�E
�@�Î~�l���́A�o�����Ǝ��S�����������l�����������[���ƂȂ��Ԃł���B 1969�N�����Ȃ̐l�����R�c��͐Î~�l���̏�Ԃ��������邱�Ƃ��]�܂����A�Ƃ����B
�@�����̏�����ƁA�o������1957�N��2.00�ȉ��ɂȂ��Ĉȍ~�A1974�N���܂ł̊Ԃ͈���I�ɐ��ڂ��Ă����B����̏d�_���A�o�����̖�肩�猒�N���i�⎙�����S�琬�A����ɂ͍�����ւƈڍs���Ă������B
���{����Ƃ̏펯�����ቺ
�@1970�N�㔼�ɂ͓��{���u�Î~�l���v��B�������ƍl����ꂽ�B���ۂɂ́A���̏o�����̏́A ���̌�}���ɕ���Ă����B
�@1990�N�ȍ~�A�u�Ђ̂����܁v�̔N�������1.5�ɂ܂Œቺ���A���{�͂悤�₭���q����ɏ��o�����B
�@����Ɏ���܂ł�1970�A80�N��̊ԁA�l������Ƃ����_�ł́u���ԁv�ƌ����Ă��d�����Ȃ��B
�@2005�N�ɂ͏o�����͉ߋ��Œ��1.25���L�^�����B
�@�����ɂ͂��̌��30�Α�̖������͏㏸�������A�o���������邱�Ƃ͂Ȃ������B
�@���ʂ��猩��A�ߔN�̏o�����̒ቺ�́A�����̐��{����Ƃ̏펯���錻�ۂł��������A�����̌ٗp�V�X�e���̕ω��Ȃǂ��Љ�ɋy�ڂ��e����ǂ݂���Ȃ������A�Ƃ������Ƃł���B
2/10�i�y�j�܂菬��@�ϐ�1-2cm ���Ⴙ�� �@�Ɠ��]���^�{�\���v�`�u����
2:00�N���A�l�R�����ƌ𗬁B�����̂��Ƃ��B�̒��s�ǁB�S�g���ӊ������x�A�O�_�O�_�߂�������ēx�A�Q�A���H�ۂ炸�B ���˕����u�ɒ����x�A�ؓ��ɁA���ǏI�����[�`�����[�N�������O�_�O�_�g���g���I���珰���ĉ߂����B�����̂ݐێ�A���`�̐^������10���قǁB19:30�Ɠ��A��A�[�H�͖˂ɂ��Ă��炢�Ȃ�Ƃ����H�B20:30�A�Q�A�����v��2055���A�Œ�L�^�ɋ߂��B
���{�̐l�����2024(10)�@�ٗp�V�X�e���̕ω�(5)�@�q���̕n���͘A������
�@�e�̌o�Ϗɂ�����炸�A�q�������������Ɋ�]�����Ă�Љ���������������̂ł���B
�@���{�̍���������b������3�N��1�x�s���A�N�ԏ��������̕W���I�Ȑ����̔��� (127���~)�ɖ����Ȃ��l�̊����𑊑ΓI�n�����Ƃ��Ē��ׂĂ���B
�@����ɂ��ƁA�e���n���̏�Ԃɂ���18�Ζ����̎q���̊����́A2021�N�ɂ�11.5%�������B2018�N��14%�����P�������A�q����8.7�l��1�l���n���Ɋׂ��Ă��錻��͌������B���ɂЂƂ�e���т̎q���̑��ΓI�n������44.5%�ɏ�����B
�@���{�̓R���i�ЂŁA�ЂƂ�e���тɓ��ʋ��t�����J��Ԃ��x�����Ă������A�ꎞ�I�Ȏx���ł͍��{�I�ȉ�����ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�����A�e�̐�����Ղ����肳���Ă������Ƃ��s���B�K�ٗp���琳�K�ٗp�ւ̓]����A�p���I�Ȓ��グ���㉟�����Ă����˂Ȃ�Ȃ��B
�@�n�����e����q�Ɉ����p�����u�n���̘A���v�́A�[���Ȗ�肾�B
�@��ʂɁA��w�Ȃǂւ̐i�w����8�����Ă��邪�A��q�ƒ�Ɍ���A6�����ɂƂǂ܂�B
�@���ꂪ�u�q�ǂ����̕n���v�̉e�����c���Ă���̂��Ƃ���A�n���Ƃ����u�s���v�́A�m���ɁA�~�ς���Ă��邱�ƂɂȂ�B
�@ �܂�A�ȉ��̐}�������藧���ƂɂȂ�̂ł�??
�u15�Ύ��̕n���v���u����ꂽ����@��v �� �u�b�܂�Ȃ��E�v���u�Ꮚ���v���u�Ⴂ���������v�������̋@������q���B
�@�q�ǂ����n����Ԃň���Ƃ́A���̎q�ǂ��̊w�́A�����A�����̎��ȂǂɈ��e����^���邾���łȂ��A���̎q�ǂ����ꐶ�w�����Ă����u�s���v�ȏ����Ƃ��Đ��l����~�ς����B
�@�Â��f�[�^�ł��邪�A�����ی�����Ă��鐢�т̕n���ɂ͘A�����F�߂�ꂽ(��s���N����)�B �����ی���Ă���3924���тׂ����ʁA����25%���e�̐���ɂ����Ă������ی�����Ă����B��q���тɌ����Ă݂�ƁA���̐�����41%�ƂȂ�B
�@�Љ�w�̕���ł́A�e�̊K�w�Ǝq�ǂ��̊K�w�Ƃ̊Ԃɐ[���W�����邱�Ƃ͂��˂Ă���悭�m���Ă����B �e�̊w���Ǝq�ǂ��̊w���ɂ͑��ւ����邵�A�e�̐E�ƊK�w�Ǝq�̐E�ƊK�w�ɂ����ւ�����B
�@���{�̎q�ǂ��̕n���Ō����Ȃ̂̓V���O���}�U�[�B�ޏ��������u����Ă���́A�Љ�@�\���Ă��邩�ǂ����̎����ƂȂ�B
�@�Ⴍ�ē�����Ɣ��f������q���т��Љ�ۏႩ�炱�ڂꗎ���A�K�ٗp���g�債�Ă���B
�@���q����q��Đ���ɂ̓W�F���_�[�̎��_���s���ł���B
2/9�i���j�܂�~�J�@ ��ȊO���@COVID-19���N�`��7��ځ@���V����������
�@2:20�N���B�k�R�ȂǁB6:00�R�S�~�p���A7:35Taxi�H�c�w���A8:11���܂���ȂցB8:50�O���B14:45Taxi���ʕa�@COVID-19���N�`��7��ډƓ������Ƃ��Ԃɍ������B���@���ґΉ��A�V���`�F�b�N�B�����B19:15�A��A�[�H�A21:00�A�Q�B�����v6494���B���̎��_�܂ł͑̒��ʏ�B
���{�̐l�����2024(9)�@�ٗp�V�X�e���̕ω�(4)�@�p���T�C�g�V���O���A�Ђ�������Ȃǂ̑���
�ٗp�V�X�e���̕ω��͓��{�̏��q���ɑ傫�ȉe����^�������A���̒��ł����ڂ��ׂ��́A�u��s�N�̖��Ǝ҂��}���ɑ��������v���Ƃł���B
�@���S���Ǝ҂́u�d���ɂ��Ă��炸�A�d����������������Ƃ��ł���҂ŁA�d����T�����������Ă����ҁv(�����ȓ��v��)�������B
�@�������Ȃ���A���̎����́A���Ǝ҂݂̂Ȃ炸�A�u�A�ӗ~���̂��̂�r�����Ė��Ǝ҂ƂȂ�P�[�X�v�����債���B
�@��N�w�ɂ����āA�A�E���A�Ƃ�������߂Ė��ƂƂȂ��Ă��܂��P�[�X��A�K�ٗp�ŐE��ɋ߂����̂́A�Z���ԂŎ��߂�����قɒǂ����܂ꂽ�肵�āA���Ǝ҂ƂȂ�P�[�X�����������Ƃ��A��J���͐l���䗦�̏㏸�̗v���ƂȂ����B
�@�Q�l���ЁF�� �ɍK���@��҂͂Ȃ��R�N�Ŏ��߂�̂��H�`�N�����D�����{�̖����` (�����АV��)
�@�ꎞ�I�Ɂu���E�ӗ~��r���v�����l�X���A���̌�ٗp������P����ƘJ���s��ɎQ�����Ă������Ƃ����������B2012�N�ȍ~�̌i�C���ɂ����Ă��A45�Έȏ�̒j����25~44�̏����ɂ͂��̂悤�ȌX��������ꂽ���A�u25~44�̒j���v�̏ꍇ�͘J���s��֖߂��Ă��铮�����キ�A���̔N��̒j���͖��Ǝ҂ɂƂǂ܂葱���Ă���ɂ���B
�@�S���Ŗ�26�����тƐ��v����Ă���u�Ђ�������v�̒��ɂ��A���������l�X�����Ȃ�܂܂�Ă���ƍl������B�u�Ђ�������v�Ƃ́A�l�X�ȗv���̌��ʁA�A�w��A�J�ȂǎЉ�I�Q����������A6�����ȏ�ɂ킽���ĉƒ�ɂƂǂ܂葱���Ă����Ԃ��w���Ă���B�܂��ɁA25~44�́u�Ђ�������v�́A�ٗp�V�X�e���̕ω��������ʂ̈�ł��������B
�@����ɁA�K�ٗp�△�Ǝ҂ɂ����ẮA�����̂܂ܐe�Ɠ������A�e�̔�}�{�҂ƂȂ�e����������(�p���T�C�g�V���O��)���������Ă���B���������e���������҂́A�����ȓ��v���C���̒������͂ɂ��ƁA2000�N��̏��߂͎�N�w(20~34��) �ő����������A���̌�A�s�N�w (35~44��)�ɂ����đ������Ă���B
�@2016�N�ɂ͐e����������(�p���T�C�g�V���O��) ��288���l�ɂ̂ڂ�A�������13%���߂Ă���A����́A�c��W���j�A�N�オ��N�w����s�N�w�Ɉڍs���Ă������Ƃ��v���Ƃ���Ă���B���̂悤�ȓ����́A �������㏸�����N���铮���ł���A�o�����̒ቺ�ɐ[���W���Ă���B
���q��2022(5)�@���܂�ڗ����Ȃ��p���T�C�g�V���O���̉e��
���q��2022(6)�@�p���T�C�g�V���O��(PS)�@�Ȃ��Ȃ������o���Ȃ���
2/8�i�j�����@�H��X�^�b�t���K�@���N���f�[�^����
2:40�N���B�����͂����̔@���B8:30�Ɠ��ƕa�@�A��������B���@���ґΉ��A�ȍ~�Ǐ��B11:00�H��X�^�b�t���K�����Ɋւ���b��B14:00-15:00���N���f�[�^����B�a���Ή��B19:30�A��A�[�H�A20:45�A�Q�B�����v4550�����B
���{�̐l�����2024(8)�@�ٗp�V�X�e���̕ω�(3)�@�Љ�ۏႩ�炱�ڂꗎ����u�K�J���ҁv
�@���{�̎Љ�ۏ�́u�ٗp�v�Ƌ������ѕt���Ȃ������Ă����B
�@���Ắu���{�^�ٗp���x�v�͘J���ҋy�щƑ��ɂƂ��Ĉ��肵���g���ۏ�^������̂ł������B�@�I�ɂ������I�Ɋe��̕ۏ����Ă����B
�@���̂��߁A�����̘J���҂����͈��S���Č������ł��A�q��Ă��ł�����ɂ������B
�@�������A�o�u����̌ٗp�V�X�e���̕ω��A���ɔK�J���҂ɂƂ��Ă͌������������ɂ��炳��邱�ƂɂȂ����B
�@�u���K�ٗp�J���ҁv�ɂ́A���N�ی��E�����N���ی��E�ٗp�ی��̎O���Z�b�g�œK�p�����B
�@�u�K�J���ҁv�̏ꍇ�́A�����E��œ����Ă���ɂ�������炸�A���p�҈����ƂȂ��Ă���̂��ʗ�ŁA�����E��ɓ����Ȃ�����A�u�E��v�Ƃ̂Ȃ����ʂ��āA�Љ�ی��ɂ�鐶���̕ۏ���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�@���̂��߁A�z��҂̔�}�{�҂Ƃ��ăp�[�g�J�������Ă���P�[�X�������A�u�K�J���ҁv�͈�Õی��͍������N�ی����A�N���͍����N�����K�p����A�ٗp�ی��͓K�p�O�ƂȂ�B
�@�������A�u�K�ٗp�v�̏ꍇ�͈�Õی���N���̔������ԂɊׂ邨���ꂪ�����B���x�̏�ł́A��p�҂�ΏۂƂ������N�ی�������N���ی��̓K�p���Ȃ��l�́A�����F�ی����x�ō��ۂ⍑���N���������I�ɓK�p�����̂ŁA���������u��ԁv��������͂��͂Ȃ��B
�@�������A�u�K�ٗp�v��u��N���Ǝҁv�́A�����Όٗp�`�Ԃ�Ζ����ƁA����ɂ͏Z�����ς��P�[�X�������B���������ꍇ�A���̂��тɒE�ނƉ����̎葱�����Ƃ�K�v�������邪�A�葱����Y�ꂽ��A����ɂ͕ی����S���邱�Ƃ������āA�葱�������Ȃ��P�[�X������B
�@�킪���̎Љ�ۏ�́A��̊�Ƃɒ����ԁA���K�ٗp�Ƃ��ċ߂�ꍇ�ɂ͓��i�̎x��͂Ȃ��B�������A���K�ٗp�ƔK�ٗp���s�����藈���肷��悤�Ȑl�X�ɂƂ��ẮA���ɗ��p����d�g�݂ɂȂ��Ă���B
�@�����āA���́u���x�Ԉړ��v�̎��ɁA�܂��Ɂu���ی���ԁv����������댯���������B
�@�����A�Ƃ�킯�o�Y�E�玙�͒����I�Ȑ����̓W�]���Ȃ����������ƌ��f���ł��Ȃ��B
�@�䂪���̏��q���̔w�i�ɂ͘J�������Z���Ɋ֗^���Ă���B
�@���������āA�䂪���̏��q����́A���ɎႢ�J���҂̐������ɓW�]��^������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B
2/7�i���j�@�����@���Ȏ�f�@�a���J���t�@+�Ǘጟ����
�@3:00�N���B�l�R�Ή��ȂǑ����͂����Ɠ����B�W:30�Ɠ��ƕa�@�ցB9:30-12:30���Ȏ�f�A�r���ҋ@���Ԃ͂�������������A���������˂����ςł������B��������ꂽ�A�Ƃ����B12:45�a���Ή��A�����A14:30�a���J���t�@+�Ǘጟ����B�f�[�^�����B�V���`�F�b�N�{���́B19:30�A��A�[�H�A21:00�A�Q�B��3795���B
���{�̐l�����2024(7)�@�ٗp�V�X�e���̕ω�(2)�@�K�ٗp�̋}��
�@���Ɨ��͏��X�ɉ������A���̊ԂɁu�ٗp�V�X�e���v�́A�傫���ώ������B
�@�ł��傫���ς�����̂́A�h���Ј���p�[�g�A �A���o�C�g�Ȃǂ́u�K�ٗp�v���傫�Ȋ������߂�悤�ɂȂ������ƁB
�@1995�N�A���o�A�͐V����́w���{�I�o�c�x �Ƃ������\���A���{�̌ٗp�\���̌��������f�����B
�@��̍�Ƃ��Ĉȉ����Ă��Ă����B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�@�����~�ϔ\�͊��p�^(�Ǘ��E�����E��):�����p���ٗp�Ō������E��������
�A���x���\�͊��p�^(���c�Ɠ���啔��): �L���ٗp�ŔN�
�B�_��^�ٗp(��ʐE): �L���ٗp�Ŏ��ԋ�
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�@����������Ă��Ȃ��ꂽ�w�i�ɂ͊�ƂɂƂ��Đl����̗}��������ۑ�ƂȂ��Ă����B
�@���̕���A �J������ɂ�����K���ɘa���������ōs��ꂽ�B
��1996�N�ɑΏۋƎ�25��Ɋg��
��1999�N�ɂ͌������R��
��2003�N�ɂ́A�����Ƃւ̘J���Ҕh���̉��ցA�h�����Ԃ�1�N����ő�3�N�ւ̉�������e�Ƃ������
�@���̕���A���K�ٗp�����炳������A�K�ٗp�͋}���ɑ��債���B
�@�K�ٗp�̑����́A1995�N��1001���l�ł������̂��A2005�N�ɂ�1634���l�Ƒ������A�A�E��ɔY�ގ�҂𒆐S�Ƃ���h���J���҂��傫�Ȋ������߁A�K�ٗp�͑������Ă������B
�@�������Ȃ���A�K�ٗp���߂�����̈�́A�Љ�ۏ�ɂ��Z�[�t�e�B�l�b�g���Ǝ�Ȃ��Ƃł���B
�@����ȏA�Ɗ����ŁA�K����̎�҂ɂƂ��Č�����D�P�A�o�Y�͖�����ɂȂ��Ă������B���{�̐l�����̔w�i�ɂ͌ٗp�`�Ԃ̕ω����傫���B
2/6�i��)�@�������@���ʕa�@�O���@ �U���@
2:10�N���A�l�R�Ή��A�k�R���A5:00�R�S�~�܂Ƃߒ�o�B�H�n�͐�Ȃ��B6:40�o�X�ѐ�a�@�B7:10-8:15�a���Ή��A�W:45-12:15�O���͍��G�Ȃ��B�����ɂď��Ԃ܂A14:30�I���A�a�@�A15:00���҉Ƒ��ʒk�AALS��̉h�{���[�g�m�ۊW�B������A�Ǐ��Ȃ�,�A�V���f�[�^�`�F�b�N�s�B19:16�A��[�H�A20:30�A�Q�B��7659���B
���{�̐l�����2024(6)�@�ٗp�V�X�e���̕ω�(1)
�@�Љ�ۏᐧ�x�R�c���1995�N�̊�������20���N�o�������A���̌�ɓ��{�Љ�ɋN�������Ƃ͊����̗\�z���錃�k�N���X�ł������B
�@�u�Ƒ��v�̕ω��͂���ɐi�s�A�u�ٗp�V�X�e���v���傫���ς��A���҂��d�Ȃ荇�����ŁA�Љ�S�̂��傫���ϗe���Ă������B���̉ߒ��ŁA��3���x�r�[�u�[���͎����A�o�����͐i�s���Ɍ������Ă������B
�@����2�_���䂪���̐l�����ɔZ���Ɋ֗^���Ă���B
�@1991�N�Ƀo�u���o�ς����A�i�C�͌�ދǖʂɓ������B
�@�o�u�����ɑ啝�ɏ㏸�����s���Y���i���������A����܂ł̑�^�����̔����������āA���Z�ƊE��s���Y�ƊE�Ȃǂ𒆐S�ɕs�Ǎ�����ʂɐςݏオ�����B
�@1997�N�Ăɔ��������A�W�A�ʉ݊�@�Ȃǂ��d�Ȃ�A�R��暌��A���{�����M�p��s���j�]����ȂǁA���{�̋��Z�V�X�e�����傫���h�炮���ԂƂȂ����B
�@���̒��ŁA��ƌo�c�̈����A�ٗp�̏k���A����̒���A�����̎����I�ȉ����ȂǁA���{�o�ϑS�̂��}���ɕϒ������������B
�@�����́A�o�u���o�ς������炵���A��Ƃ́u�O�̉ߏ�v���o�ς̑������������Ă���Ƃ��ꂽ�B �u�ߏ���v�u�ߏ�ݔ��v�u�ߏ�ٗp�v�ł���B
�@���̂����u�ߏ���v�A�u�ߏ�ݔ��v�͕s�Ǎ������Ƃ��ĉ������}��ꂽ�B���̉ߒ��ő啝�ȃ��X�g�������������B
�@���́A�u�ߏ�ٗp�v�ł��̉��������������Ɂu���{�^�̈���ٗp�v���傫���h�炢���B
�@�O�́u�ߏ�v�̉������}��ꂽ���Ƃɂ��A��Ǝ��v�͉��P���A�o�ς͈ꉞ�̎����������}��ꂽ���A2008�N9���́u���[�}���V���b�N�v�Ő��E�o�ς͌��ς����B2012�N���ȍ~�悤�₭�i�C�ւƌ��������B
�@���������o�Ϗ�̕ω��ɍł��傫�ȉe�������̂́A�u�ٗp�v�ł������B
�@���������ٗp��̈������ł������\�ꂽ�̂��A�V���҂��͂��߂Ƃ����N�w�ł���B���̎����́u���A�E�X�͊��v�ƌĂ�A�V���҂̏A�E���͒ᐅ���Ő��ڂ����B
�@20����24�̎�N�w�̎��Ɨ��́A1985�N��4.1%�������̂��A1998�N��7.1%�A2001�N��9.0%�A2003�N�ɂ�9.8%�Ƌ}���Ɉ��������B
�@����ȕs����Ō������o�Ϗ��ł͌����A�o�Y�A�q��ĂȂǂ͎�҂����ɂƂ��Ė]�ݓ���̂ɂȂ����B
�@�䂪���̏ꍇ�A�q�������ɂ͍����W���d�v�ŁA���{�̏o�����̔w�i�ɂ͍��������傫���W���Ă���B
2/5�i���j�܂�̂������@���N�N���j�b�N�h�b�N�@�a���w�K��Ŏ��@
2:20�N���A������{�ǂ݂Ȃǂ����Ɠ����B6:40�o�X�a�@�A7:00-8:15�a���Ή��A9:00-11:15���N�N���j�b�N�A��f��12���A���ʔ���14���B11:30�ѐ�a�@�A�V���`�F�b�N�f�[�^���lj��A�{�ǂ݂Ȃǂ����̂��Ƃ��B14:30�a���w�K��Ŏ��B15:30���҉Ƒ��ʒk�A���@���ґΉ��B19:30�A��B�[�H�A20:30�A���B��7418���B
���{�̐l�����2024(5)�@�Ƒ��̕ω�(2) �u���{�^�����Љ�v�֊��҂Ɣj�]
�@�Љ�ۏᐧ�x�R�c���1995�N�̊����œ��{�̔��藈���@�̈�Ɂu�������̒ቺ�v�ɑ�\�����u�Ƒ��̕ω��v ���������B�����A�����͍���҉��̎��_�����S�ŏ��q���E�l�����Ɍq���鎋�_�͂Ȃ������B
�@����ɔ���������p�̑�����뜜���闧�ꂩ��A���{�͉Ƒ��ɂ��x������Ƃ���u���{�^�����Љ�v��ڎw���ׂ��ƂȂ����B ���̔w�i�ɂ́A���{�ł͍���̐e�ƉƑ��̓����������B������荂�����Ƃ��������Ă����B
�@�Ƃ��낪�A���̌�A�����̐������Ԃ͑傫���l�����قȂ��Ă������B
�@���݂̍j�ƌ���ꂽ�A�e�Ɗ����̎q�ǂ��̓��������A�o�ϓI�]�T�A�ƕ������̕���ƂƂ��Ɍ����ɓ]�����B1980�N�ɂ�52.5%���������A1990�N�ɂ�41.9%�A2016�N�ɂ�11.4%�ƁA�}���ɒቺ�����B
�@�Ƒ��́A�Љ�̊�b�I�ȍ\���P�ʂł���B
�@�Ƒ����ʂ�����ȋ@�\�͈ȉ��̔@���B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
���������炬�̏����鐸�_�I�ی�@�\
���Ƒ��̐������ێ����A�ۏႷ�鐶���ێ��@�\
�����Y�E�J���@�\
���Ƒ����a�C�ɂȂ����ꍇ�Ȃǂɏ��������}���@�\
���q�ǂ����Y�݈�Ă�{�狳��@�\�A
�����̐����S�������ލĐ��Y�@�\�ȂǁB
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
�@�Ƒ��@�\�͉Ƒ��̍\���������Ȃ��Ȃ�Ȃ�قǁA�Ƒ����m���x�������@�\���ቺ���Ă����B
�@
�@����������b�����ɂ��ƁA1975�N�����́A�u�O����ȏ㓯�����сv��23.1%�A2015�N�ɂ�13.0%��10�|�C���g���ቺ�����B
�@����ɑ���`�ő��������̂��A�u��l���сv��18.2%����26.8%�A�u�v�w�̂ݐ��ѣ ��11.8%����23.6%�A�u�ЂƂ�e���сv4.2%����7.2%�ł���B
�@���{�̉Ƒ��́u�l���v�ƂƂ��ɁA�}���Ɂu���l���v�����A�Ƃ�������B
�@���̂��Ƃ����q���Ɍ��т��Ă����B
�@
2/4�i���j�܂菬��@
2:30�N���B�l�R�Ή��A�Ȃ��Ȃ���炸�B4:00���܂Ńg���g���B���������A�k�R�A�^���f�[�^�����A�ȂǁB�{���͕a�@�o�̗\��Ȃ��B�ߑO�͓Ǐ����S�A���͂̂ǎ������Ȃ���V���A�Ǐ��B�����ȂǁB19:00�[�H�A20:30�A�Q�B��3143���B�Ǐ��O���A���W�I�[��֕ۍ⎁���a�V���[�Y�N�W�A����O���̈���B
���{�̐l�����2024(4)�@�Ƒ��̕ω�(1) �l���͎�����?�@�Ǘ������H
�@���{�̐l������_�����ō����̐����̈��艻�������Ƃ������Ă͌��Ȃ��B���̔w�i�ɂ͓��{�̎Љ�ۏᐧ�x�̐i�W���������B
�@���Ɂu���{�^�̌ٗp�`�ԁv�Ɓu�ƒ�̋@�\�v�͍����]������Ă����B
�@�Љ�ۏᐧ�x�R�c��͐��Ԃ�����GHQ�̎w���ō��ꂽ�g�D�ŁA2001�N�Ɍo�ύ��������c�����Ŕp�~���ꂽ���A1995�N�ɔ����������ł͂���܂ŎЉ�ۏႪ�ʂ����Ă����������O�������B
----------------------------------------------------------------------
���Ƃ��āA���������̑S�ʂɂ킽���Ĉ���������炵�����ƁA
���Ƃ��āA�n�x�̊i�����k�����A�Ꮚ���w�̐��������������グ�A���̌��ʁA
�u�����A�䂪���͐��E�ōł������i���̏��������̈�ƂȂ����v���ƁA
��O�Ƃ��āA�Љ�ۏ�͌o�ς̈���I���W�Ɋ�^����Ƃ��낪���Ȃ��Ȃ������B
----------------------------------------------------------------------
�@����ŁA���̊����́A21���I�̓�����ڑO�ɂ��āA���ڂ��ׂ��u�x���v�������Ă����B�ꕔ���p����B
�@�u21���I�Ɍ����ĉ䂪���͊�{�I�Ȗ��ɓ˂�������B���̈�͐��ɂ�����l��`�̐i�W�ł���B�X�l�̐l���A���含���d���A�����ʂ̓P�p���Љ�I�Ɏx�������悤�ɂȂ�B����͓��{�Љ�̐i�W�Ƃ��Ċ��}�����ׂ����̂ł���v�B
�@�u�������A�_���Ȃǂɂ������O����`������Ă����`���I�ȉƑ����x�̕���ɂ��Ƒ��ɂ��x���������ቺ����v�B
�@�u�l�����i�W������邾���A�����ŎЉ�I�A�ւ������A�A�ъW�������Ɍ`������Ȃ��ƁA�Љ�͉�̂���v�B
�@ �u�Љ�ۏ�́A�X�l����{�Ƃ���Ɠ����ɁA�X�l�̎Љ�I�A�тɂ���Đ���������̂ł���A���セ�̖����͂܂��܂��d�v�ɂȂ�v�B
�@�u�l���v ���u�����v�ƍm��I�ɍl���錩��������A�u�Ǘ��v�Ƃ��āA�ے�I�ɑ����錩��������B
�@���̊����́A�����̑��ʂ����邱�Ƃ�F�߂A�u�A�ъW�������Ɍ`������Ȃ��ƁA�Љ�͉�̂���v�Ƌ�����@����\���Ă����B
�@�������A��@��������Ɏ������w�i�̈�ɂ́A�u�������̒ቺ�v�ɑ�\�����悤�ȁu�Ƒ��̕ω��v���������B
2/3�i�y�j�܂�ڂ����@
2:30�N���B�����C�V���������A�^���f�[�^�����ȂǁB�ߑO���ԃv�����^�[�L���m��TS6330�Z�b�g����\�ɁD14:00�����㔃�����ɍs���Ɠ��ɓ���A�a�@�B��X�Ή����B�Ǐ��A�����ǂ݁A�V�����́ATS8130�����R�[�X�ɏ悹�鏀���B19:30�L�\�o�R�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B�����v��3387���B
���{�̐l�����2024(3)�@���߂̌��ʂ͑傫���������@�����̓f���P�[�g?�A���邢��?????
�@���߂͊��x(����)�̈�B
�@�u���ߎY�܂�̏��́A�C���������A�v���E�����Ƃ�����v�A�ƌ����Ă���B ���̓`���̔��[�́A�]�ˎ���ɔ��W�������l�����̂Ȃ��ŁA���Ύ������N���������S�������Ȃǔߌ��̏������A���߂ƌ��т����č�i�ɕ`���ꂽ���ƂōL�܂����B���j�̐����`���ł���B
�@60�N�Ɉ�x�����Ă��镸�߂�2�N��2026�N�ɔ������B���Ă͕��߂ł͏o�����͌��������B�O��̕��߁A1966�N�̏o�����͌��J�Ȃɂ���136��974�l�ŁA�O�N���25�����������B���v����o������1.58�ɗ������݁A���M�̉e�����傫���o���B
�@���́u�o�J�������b�E�E�v�Ǝv�����A�ŋ߂̖^�A���P�[�g�ɂ��ƁA���ߐ��܂�̏��������́u�C�������ƌ��߂���ꂽ�v�ȂǂȂǁA������̕��X�Ɍ��Ȏv���̌o�����������B�����A�啔�������c��A�f��Ȃǐg�����猾���Ă���A�P�Ȃ�ƒ���̘b��̃��x�����낤�Ǝv���B�����̎Ⴂ�����́u������o�Y�������ׂ����v�ƍl����͖̂w�ǂ��Ȃ������B
�@�O��̕��߂̒��O�A�����T���������ߓ��W��������Ƃ����B
�@���̓��W�́A�u�k�Ђ��o���Ă��������T�����u�����O���f�B�v 1965�N1��25�����B�L���́u60�N��1�x�̊댯!!�v�A�u���N�Ԃ������Y�ނ��Ȃ��Ɍx�����܂�!!�v�A�u���߂̐Ԃ������Y�炽���ւ�!!�v�A�u ���N���܂��q�������Ȃ�ꐶ���߂Ƃ��������w�����āA�����Ă䂩�˂͂Ȃ�܂���!!�v�A�ȂǃZ���Z�[�V���i���Ȍ��o���ł������Ƃ����B
�@��1�J����B����ǂ́u�T���T���P�C�v3��1�����ɁA�u���N�̓q�m�G���}�B ���܂Ȃ�o�Y���������̂ɊԂɍ����܂��v�A�Ƃ������l�Ȃ��̂������炵���B
�@�o�J�o�J�����B
�@���ߐ��܂�̈���������킯�ł��Ȃ��A�����������̔N��荂���킯�ł��Ȃ����낤�B
�@�������A�l�͊F���ꂼ��ł���B�F���X�e�[�V����������A���ɒ����D��������鎞��Ȃ̂ɁA�ꕔ�̐l�͖����ɖ��M�ɔ����Ă��܂��B
�@2�N��̕��߁A�ǂ��Ȃ�̂��y���݂ł��邪�A�[���͕K�v�ł��낤�B
�@�����̂Ȃ����M�ɘf�킳��ďo�Y�̋@������Ƃ͂��������Ȃ����Ƃł�B
�@
2/2�i���j�܂�~��@��Ȓ��ʕa�@�O���@
2:10�N���B�l�R�Ή������̂��Ƃ��B�����`�F�b�N�A�k�R�ȂǁB5:30�R�S�~�܂Ƃ߂���W�Ϗ��ɏo�����B�~��3cm�A�H�ʂ͓����A����Ȃ��B7:30Taxi�w�ɁA8:11���܂��B8:50�Ȓ��ʕa�@�O���A�w�a�@�ԉ���Taxi�B���艮�Ï��X�A8���B15:25-19:00�a�@�B�����A19:30�A��[�H�A21:00�A�Q�B�����v��6323���B
���{�̐l�����2024(2)�@���Ȃ�������O���x�r�[�u�[���@���̎���ɉ����������̂�??
�ϗe������{�Љ�A���Ƀo�u�������̌o�ς̕ω��́A���{�^�ٗp���x�̏��ŁA�o���s���̕ω��������炵�A�o�����ɑ傫�ȉe����^�����B
�@���̌��ʁA2000�N�O��ɗ���͂��̑�O���x�r�[�u�[���͗��Ȃ������B
(1995�N����2013�N�̊Ԃ�3�Ԗڂ̏o�����̃s�[�N������͂��ł��������E�E�E)
�@���̊ԂɎЉ�傫���ω������B
�@1980�N��ȍ~�i�s���Ă��� �u�Ƒ��̕ω��v �́A�P�g�҂Ȃǐ�����̃��X�N������鑽���̐l�X�݁A����ɁA1990�N��㔼����[���������u�ٗp�V�X�e���̕ω��v �́A ��Ƃ��]�ƈ��̐����S�ʂ��x����Ƃ����u���{�^�ٗp���s�v�����ł����A�E�ꂩ�琶���ۏႪ���Ȃ��K�ٗp���������B
�@�����āA�����ɔ���������ɂ�鐶����Ղ̕s���艻���A�A�E�A�����A�o�Y�̎����ɂ��Ⴂ����ɑ傫�ȉe����^���A �������̏㏸�Ƃ����`�Łu�Ӎ�����A����ɂ͗��e�Ɠ����̂܂܁u���v���ۂ������炵���B���̌��ʁA�o�������ߋ��Œ�ɂ܂ŗ�������ōs�����B
�@���{�̐l���\���Ō���ƁA����1947�N�O��̑�ꎟ�x�r�[�u�[���͔N��250���l�ȏ�̏o�����ɒB���A��̑傫�ȏW�c���`�����Ă����B
�@���̑�ꎟ�x�r�[�u�[������̎q�ǂ����������S�ƂȂ��āA1970�N��O���ɔN��200���l�ɒB�����׃r�[�u�[�����オ�`�����ꂽ�B���̓�̐l���̉A���{���l�������������Ă����B
�@
�@�������A1995�N����2013�N�̊Ԃŗ�����̂Ɗ��҂��ꂽ�u��O���x�r�[�u�[������v�̓������Ȃ��������Ƃł���B
�@ �Ӎ�������̗����1980�N��ȍ~���܂��Ă������A1997�N�ȍ~�̌o�ϒ���ɔ������������́A���傤�ǏA�E�A�����A�o�Y�̎����ɂ���������Ɍ���I�ȉe����^�����B
�@���ꂪ�A�Ӎ����ɒǂ��ł��������A2005�N�ɂ͏o�����͉ߋ��Œ��1.26�ɂ܂ŗ������B����ł����̍��͏o�����͂܂�120���l�ł������B
�@�䂪���́u�l�������v�́u�Ƒ��v�̕ω��Ɓu�ٗp�V�X�e���v�̕ω��̍s��������Ƃ��Đ������ł������B
�@���������āA�䂪���̐l�����̑�͂���2�_�Ɋ֘A�������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������ƂȂȂ�B�ɂ߂đ傫�ȍ�������̂ƂȂ�B
�@2022�N�̏o������2005�N�Ɠ���1.26�A�o�����͎j��Œ�̂V7���l�ł������B
2/1�i�j���g�@����@�ς���قǂłȂ�
1:50�N���B�l�R�Ή��B�k�R�ȂǍ��w�A�����B8:50�Ɠ��ɓ���a�@�B�d�NJ���S.F���A������͂悳���������卷�Ȃ��B14:27���S���ꂽ�B���̑Ή��B���Ѓf�[�^���ȂǁB�Ǐ��A�����B19:10�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B����5842���B��N�ϐ�20cm�قǁ@����4�A5��ځB
���{�̐l�����2024(�P)�@���҂͍Ō�̃`�����X�Ƃ������A�����Ԃɍ���Ȃ�
�@���{�͐l��������Ԃɓ������B
�@���{�������ɐl��������h���藧�Ă��l���Ă��A�Đ��Y�\�́A���Ȃ킿�A�q�����Y�ނ��Ƃ��ł���N��̏��������ꂾ������A�Љ�\�����ς��ٗp�������������Ȃ��Ă��錻��A�����Ɋւ���Ⴂ�j���̍l�������ς�����ȏ�A�l�����͐H���~�߂��Ȃ��B
�@���͓��{�̐l���������ɂ��ĐH���~�߂邩�̃��x���ł͂Ȃ��A8000���l���x�ō��������Ɉێ����邩�A���l���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���̃��x���̐l���ێ��ƂĎ����͍���ł���B
�@���A����ł͏��q���c�_����Ă��邪�A����ł����ɋc�_���Ă��Ă����{�̏o��������͊��҂ł��Ȃ��B�����A�]���A�_�c���ׂ��ł������q��Ăւ̔z���ɉ��߂Č��������������Ƃ͘N��ƂȂ�B
�@�ݓc�͍�N1���A�N���̋L�҉�ŁA�D��ۑ�Ƃ��āu�َ����̏��q����v�Ɓu �C���t����������グ�̎����v�Ɏ��g�ލl����\�������B
�@���D��ۑ�Ƃ��ď��q������������̂͂ƂĂ��������Ƃ����A�͂����茾���Đl������Ƃ��Ă͒x���Ɏ����Ă���B�����Ɂu�َ����v�Ƃ������������̂���Ȃ��B
�@�u�َ����̏��q����v�Ƃ��Ĉȉ��̐���𒌂Ƃ��ċ������B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
?�����蓖�Ȃ� �o�ϓI�x���̋����A
?�w���ۈ��a���ۈ�A
?�Y��P�A�Ȃǂ̎x���g�[�A
?���������v�̐��i�A
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�@�u�َ����v�Ɩ����������̂̏]���̐���Ƒ傫���قȂ�Ƃ���͂Ȃ��B
�@����͏��q����ł͂Ȃ��u�q��Ďx����v�ł����āA������d�v�Ȑ���ł͂��邪�A����͐l������ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�q��Ďx���ł�������܂���@�ł͌��ʂ͏オ��Ȃ��B�����Ɛ[���Ƃ��납��̑K�v�ł���B
�@���A��ꎟ�A��x�r�[�u�[�����N�����B
�@�������A��O���x�r�[�u�[���͗��Ȃ������B�Ⴂ���オ�\������̂ɏo�����͉��������������ł������B
�@��O���x�r�[�u�[�������Ȃ��������R���l����ƁA�䂪���̐l�����̖��_�����߂Č����Ă���B
1/31�i���j�܂莞�X����A�[�����J�@�@
3:00�N���B�{�ǂ݁A�k�R�Ȃǂ����̔@���B8:40�Ɠ��ɓ���a�@�B�ߑO�������A�����B�V���`�F�b�N�{���͂��̑����[�`���A12:30����A�]�t���[�U�A�]�R�[�o���B14:30�a���J���t�@�{�Ǘጟ����A���ҏ��u�B�Ƒ��ʒk�B19:20�A��A21:20�A�Q�B��4194���B
2024�N�͂ǂ�ȔN�H(10) �l�����̒��A����҂������Ӌ`
�@���{�͐l��������Ԃɓ������B
�@���{�������ɐl��������h���藧�Ă��l���Ă��A�Đ��Y�\�͂̂���N��̏��������ꂾ������A�Љ�\�����ς��ٗp�������������Ȃ��Ă�������A�����Ɋւ���Ⴂ�j���̍l�������ς�����ȏ�A�l�����͐H���~�߂��Ȃ��B
�@���ł͓��{�̐l���������ɂ���8000���l���x�ňێ����邩�A���l���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���̃��x���ƂĎ����͍���ł���B
�@���̍ہA�J���͐l����2030�N��5800���l�ɂ܂Ō�������Ƃ��Ă���B5800���l�Ƃ���������1980�N�㏉���̐����ł�����B���ɁA�ŋ߂̃j���[�X�͂����镪��ł̐l��s���Ɋ֘A�������̂������B
�@�J���͐l�����ւ̑Ή���i�߂�K�v�����邪�A���̂��߂ɂ͏����E����ҁE�O���l�̊��p���\���Ƃ��čl�����Ă���B
�@����҂̊��p�Ɋւ��ẮA�܂���60�Β�N�ȍ~�̌ٗp���������邱�Ƃ�A65�Έȏ�̍���҂̓�����̑n�o�Ȃǂ��ۑ�ƂȂ��Ă���B
�@��N���Ɋւ��Č����A2004�N�ɍ��N��Ҍٗp����@�̉����ɂ��A��Ƃ͈ȉ��̂̂����ꂩ�����邱�ƂƂȂ����B
--------------------------------------------------------------------
�@66�Έȏ�܂ł̒�N�̈��グ
�A65�Έȏ�̌p���ٗp���x�̓���(2013�N�̉����Ŋ�]�ґS����ΏۂƂ��邱�ƂƂȂ���)
�B��N���̔p�~�A
--------------------------------------------------------------------
�@
�@���N��Ҍٗp�m�ۑ[�u�̓����ɂ��60~64�̘J���͗��͋ߔN�A�Q���X���ɂ���(�j���̏ꍇ�A2005�N��70.3%����2015�N�ł�76.9%�ɏ㏸) ���̂́A65�Έȏ�̘J���͗��͂قƂ�Ǐ㏸���Ă��Ȃ� (��25.5%����31.1%)�B
�@����ɂ���ĘJ���Q�����ł��Ȃ�����҂������邪�A���N�����̐L���Ȃǂ���65�Έȏ�̍���҂̊��p������̉ۑ�ƂȂ낤�B
�@���̏ꍇ�A70������ɓ��ꂽ��N�����̈��グ���c�_����邱�ƂɂȂ�B�������A����ٗp�҂̑������A��N�J���͐l���̐V�K�A�Ƃ̖W���ɂȂ��Ă���Ƃ����w�E�����邱�Ƃ���A����҂����S�ƂȂ�悤�Ȋ�ƌ`�Ԃ̊J�����i�߂Ă����ׂ��ł��낤�B
�@65�Έȏ�̏A�Ƃ𑣐i���邱�Ƃ́A�P�ɏ������m�ۂ���Ƃ������ɁA����ɔ����Љ�ۏዋ�t��}���A�ی��������𑝂₷�A�Ƃ��������ʂ��l������B
�@�Ȃ��A�o�ϐ����������������⍂��҂̊��p���i�߂�2030�N�̘J���͐l����6362���l�ƂȂ�A2015�N����̌�������240���l���x�ɗ}������Ƃ��Ă���B
�@�܂��A�J���͐l���̌����ɑ��ĊO���l�̊��p���l������B
1/30 �i�j����@���ʕa�@�O���@���N�x�A�ƍX�V
2:00�N���B�V���A�{�ǂ݁A�k�R�Ȃǂ����̔@���B5:00�R�S�~�W�z���ɁB�U:40�o�X�a�@�B���s�͂��낻��ƁB7:15-8:00�a���Ή��A8:45-13:20�O���A�a�@�A�������BWeb�w�K��A�w�����s������J�����B�V���`�F�b�N�{���͂��̑����[�`���B�{���l�����K�A���N�x�A�ƍX�V�A19:20�A��A21:20�A�Q�B��9015���B��N����3��ځB
2024�N�͂ǂ�ȔN�H(9) �H�c���̍���ҏA�J�� �l�����ƍ���̋
�@2024�N�́H�Ƃ�����肩��͎����邪�A����҈�t�Ƃ��Ă̎��̏A�J�Ɋ֘A���āA�u�H�c���̍���ҏA�J�v�ɂ��ĐG���B
�@�H�c�J���ǂ����\����2022�N�̍���҂̌ٗp�����ɂ��ƁA70�Έȏ㓭���鐧�x�̂��錧����Ƃ̊����͑O�N��2.23%����50.7%�ƂȂ�A�S�����ς�11.6%�������B
(����҂̌ٗp�������ʁ@�@�V������ؗp)
�@2024�N�܂ŏH�c���̍���ҏA�J��8�N�A���őS��1�ʂ��������A����͏��ʂ�����Ƃ���2�ʂƂȂ����B1�ʂ͓�������51.8%�������B
�@�H�c�J���ǂ͏]�ƈ�21�l�ȏ�̌���2054�Ђ����A22�N6��1�����_�̌ٗp���܂Ƃ߂��B
�@�i�P�j70�Έȏオ�����鐧�x�̂����Ƃ�1042�ЁB
�@�@�@���̋K�͕ʂł́A
�@�@�@300�l�ȉ��̒�����Ƃ�50.5%(1978�В�998��)�A
�@�@�@300�l���̑��Ƃ�57.9% (76�В�44��)
�@�i�Q�j�A�Ƌ@��m�ۂ̎�ޕʁA
�@�@�@�u70�Έȏ�̊�]�ґS�����ٗp���鐧�x�v������̂�12.8% (263��)
�@�@�@�u���N��E�\�ʂ̊���� 70�Έȏ�̌p���ٗp���x�v��12.1%(249��)�A
�@�@�@�u��N���̔p�~�v��3�E3%(67��)�B
�@�i�R�j����J�����Ԃ��T20���Ԉȏ�́u��p�J���ҁv�A
�@�@�@ 60~64��2��258�l
�@�@�@�@65~69��1��1873�l
�@�@�@�@70�Έȏ��5244�l
�i�S�j�������N��Ҍٗp����@(21�N4���{�s)�ɂ��A70�܂ŏA�Ƌ@����m�ۂ��邱�Ƃ���Ƃ̓w�͋`���ƂȂ����B
���̊m�ۑ[�u���{��Ƃ́A�S�����ς�27.9%�A�{����31.5% (646��) �B
�@�H�c�J���ǂ͂���ɍ���҂̓������Ɋւ�����m��}���A ���Ɂu70�܂ł̏A�Ɗm�ۑ[�u�ɂ��ďd�_�I�ɌĂт����Ă����v�Ƃ����B���ǂ́A�����ӗ~�̂��鍂��҂������Ă��邱�Ƃ�A�����Ől��s�����[�������Ă��邱�Ƃ��e�������Ƃ݂�B�i��L�̋�̓I�f�[�^��2023�N1��24���H�c�@�V���̋L�����Q�Ƃ��������M�����j�B
---------------------------------------------------------------
�@�H�c�@�V���̋L���͓��{�ŗL���̍���ҏA�Ɨ���]������j���A���X�ō\������Ă���B�����āA����ҏA�J����8�N�A���őS��1�ʂ��������A����͓������ɔ����ꂽ���Ƃ��������Ă��邪�A�Ⴂ���x���ł̔�r�͔߂����B
�@���͏H�c�́A���������K�ٗp�œ����Ă��銄�����S�����ς������Ă���B �o�Y���@�ɗ��E���銄���͑S�����ς����Ⴂ�B
�@�������A����ҘJ���A�����̏A�J�̎��Ԃ͊e�ƒ�̒�����ɂ���A�Ǝv���B����ɁA���q����Ől�����������A�����āA����Ŏ�҂������ɏ��Ȃ����ƁA�̔��f�ł���B
�@���Ȃ݂ɁA������ƌÂ��f�[�^�ł��邪�A�H�c������l������̕��Ϗ�����255��3000�~�i2016�N�x�j�ŁA���k6���ōʼn��ʁA�S���ł�39�ʂł������B
�@������A���ʂƂ��č���ҏA�Ɨ��������̂��B
1/29�i���j�܂�͂�@�ϐ�0cm�@���N�N���j�b�N
�@2:00�N���B�{�ǂ݁B�����`�F�b�N���X�����Ɠ����B6:40�o�X�a�@�ցB7:00-8:15�a���Ή��B9:00-11;10���N�N���j�b�N�h�b�N�A13���A���ʔ���13���B11:30�a�@�Ɉړ��A�����ȂǁB14:00���@���ґΉ��A�x�����̑����ǂ���Ή��B�L���m���Ƀv�����^�[���C���e�i���X�\�����ނ��C�����2���~�B���̕��@�����TC-7334�w�����邱�ƂɁB19:10�A��A�[�H�B20:30�A�Q�B�v��7204���B
2024�N�͂ǂ�ȔN�H(8) �H�c���̈�t�s��(2)�@���̈�Ì��̍ĕ�
�@��Ì��͓s���{������Ö@�Ɋ�Â��Đݒ肷��a�������̂��߂̒n��P�ʁB
�@�ȉ��̗l�ɕ�������B
--------------------------------------------------------------------
�i�P�j1����Ì��F����I�ȊO���f�Â̈�Ãj�[�Y�ɑΉ����邽�߂ɐݒ肳�ꂽ�P�ʁB�s������1�P�ʁB
�i�Q�j2����Ì��F�~�}��ÁA���a�\�h�A���@���Âɂ�����܂ŕ��L���j�[�Y�ɑΉ����邱�Ƃ�ڕW�ɐ�������Ă���B�����̎s�������܂Ƃ߂�1�P�ʂƂ���B
�i�R�j3����Ì��F���x�ōŐ�[�̈�ÁA���_�a���⊴���Ǖa���A���j�a�������I�Ȉ�Â�����Ì��B�s���{����1�P�ʁB
--------------------------------------------------------------------
�@2����Ì��́A�{���ł�1986�N�A8��Ì���ݒ肵�Ă������A��N�A���k�A�����A�����3��Ì��ɂ���Ă����̈�ÐR�c��ŗ������ꂽ�B
�@�����ł��䂪���̐l��������肪���̌����̈�ƂȂ��Ă���B
�@�l�������͎Љ�̂����镪��ɉe����^����B�Ƃ�킯�H�c�ł͂��̉e�����傫���B
�@��Ì��̂����u�k�H�c�v�Ȃ�3����ł́A�l�����ɂ��ߑa���A���ӈ�Ì��ւ̊��җ��o���������A��Ë@�ւ̈ێ�������Ȃ����B
�@���J�Ȃ�2020�N�����ɂ��ƁA�{���̈�t���͐l��10���l������242.6�l�B��Ì��ʂł́u�H�c���Ӂv��333.2�l�Ƒ�������A�u�k�H�c�v124.0�l�A�u����E�Y���v126.2�l�ƕ݂��ۗ��B
�@�l�����������炷�����܂��A�����ɏ\���Ȉ�Â����ɂ́A�a�@�̏W��Ƌ@�\���S��}��K�v������B�Ⴆ�A�}�����̔]�[�ǂ�S�؍[�ǂȂǂ����Â���a�@�@�\�����̕a�@�ɏW�A���̕a�@���u���v�Ⓑ�����@�́u�������v�ɂ��邱�ƂȂǁE�E�E�ł���B
�@�����A����ĕ҂ɔ����A���҂ɂǂ̂悤�ȉe�����y�Ԃ��A����ɑ���{�����������Ǝ����K�v������B�Ƃ�킯�A����҂��͂��߂Ƃ����ʎ�҂̒ʉ@���S�������傫���Ȃ鎖�Ԃ͔��������B
�@�K��f�ÁE�Ō�〈���Ȃǒn���P�A�V�X�e�����x����@�\����w�[�������邱�Ƃ��d�v���B�����āA���u�f�Ây������ȂǐV���Ȏ��g�݂����߂���B
�@��ÊW�҂̑����́u��ނȂ��v�Ƃ̌����������B
�@�ĕ҂̃����b�g�́u��Ë@�ւ̋@�\���S���i�߂A���ꂼ��̏Ǐ�ɍ��킹�Ď�f�ł�����������Ă����B�f�Â̌����������܂�A��Ï]���҂̕��S���y������Ă����v�Ƃ���B
�@���̈�ÐR�c��ł͍ĕ҂̃f�����b�g�܂Ŋ܂߂Č������A���肵���̂��낤��???
�@��Î����ɂ͌��肪����B�����A��Â͏Z���̐����ɕK�v�ȎЉ���̈�ɂ����Ȃ��B�H�c���ł͂���ɐl�����������Ă����B�l�����͊��҂ł��Ȃ��B
�@�������Z�݊��ꂽ�n��ŕ�炵��������悤�A�l���������������V���Ȍ��������҂���邪�A���̂Ƃ��댩���Ȃ��B
�@1/28�i���j�܂萰��~��Ȃ��@���̃����Ƀ����h�Z������
2:45�N���A�l�R�Ή��B�Ǐ��ȂǁB�ߑO�͔��������݂Ȃ�����w�A�Ǐ��A�f�[�^�֘A�A12:00�������ɍs���Ɠ��ɓ���a�@�A�V���`�F�b�N+���́B�Ǐ��O���BCanon�v�����^�[�C�����ȁH17:00�N���[�j���O�X�o�R�A��A17:30���̃����Ƀ����h�Z������A�̒��s�ǂ炵�������B19:00�[�H�B20:00�A�Q�B��3780���B
2024�N�͂ǂ�ȔN�H(7) �H�c���̈�t�s��(1)�@������t�̍��
�@�����̈�Î{�݂œ�����t��2328�l(2020�N)�B
�@����10�N�Ԃ̐��ڂ�����Ƃ킸���ɑ����Ă�����̂́A�l��10���l������ł�242.6�l�ƌ��J�Ȃ̑S����t�ݎw���̓��v��ł͑S����41�ԖځB�S�����ς�256.6�l�B���k�ł͋{�錧������5����40�ʈȉ��ƂȂ��Ă���B
�@�f�Éȕʂł͎Y�w�l�Ȉ��8�l���������B�O�Ȉオ10�l�����A�����Ȉオ5�l�����̈�Ì�������B
�@��t�̍�����i�݁A��Î{�݂œ�����t�̕��ϔN���2020�N���_��50.7�A50�オ21.7%�A60��ȏオ30.5%�B���ǂ�����t�̍���ɉ��S���Ă���B
�@�H�c���͈�t���u����҂𑝂₽�߁A2006�N�x�ɏH�c��w�Ɂu�n��g�v���x��n�݁B���w��������ݗ^���A��t�Ƌ�������Ɍ����̕a�@�ň����ԓ����ƕԍς�Ə����Ă���B23�N�x�܂ł̒n��g���w375�l�������B
�@���̐��x�͑���w�ɂ��g�[���A2023�N�x���w�҂͏H�c��Ɗ���A���k��Ȗ�Ȃ̌v33�l�B
�@���������{��Ȃǂɂ��A���N70�l�قǂ̎���t������14�̏����Տ����C(2�N)�ɐi�ށB�����Ζ����钆�ʑ����a�@�a�@�����̈�B
�@�����Տ����C���I������t�̑����́A���x�Ȓm����Z�p�����u����v�̎��i����邽�߂̂���Ɍ�����C�A��匤�C�ɐi�ށB
�@���C�̒��S�ƂȂ��a�@�́A�w����̐���N�Ԏ�p�����Ȃǂ̌�����������邽�ߑ�s�s�ɏW�����Ă���A�n�������t����s��ɗ��o����v���̈�ƂȂ��Ă���B
�@�����ł͏H�c���w�����܂�6�a�@����a�@�Ƃ��Đ��㌤�C������Ă��邪�A����ɐi�ވ�t�͖��N50�l�قǂŒ���������������B
�@���J�Ȃ̈�t���v�ɂ��ƁA���{�̈�t����2002�N����2020�N�̊ԂɁA26��2687�l����33��9623�l�ƂȂ�A7��6936�l���������B
�@�ꌩ�A��t���͋}���ɑ������Ă���l�Ɍ����邪�A����͑��ς�炸��t�s����Ԃɂ���B���̗��R�̈�Ƃ��āA��Â̍��x���A���S���A�����̐f�ÉȂ̈�t���A�g����`�[����Â̕��y�Ȃǂ������ƂȂ��Ă���B
�@
�@�e�f�ÉȂɏ\���Ȉ�t������̐������߂��邪�A��t�͑�s�s���A�s�s���ɏW������X�������邽�߂ɁA�L��Ȗʐς����H�c���̈�Î���́A�S�̂Ƃ��Č���ނ�����Ă���Ƃ����悤�B
�@���̂��Ƃ����ǂ����A�J����������w�i�ɂȂ��Ă���B
�@�ɂ��y���A�ł���B
1/27�i�y�j�܂�@���܂ō~��2-3cm ����Ȃ�
3:00�N���B�̒��͂����肹��5:00�܂Ńl�R�Ή��ȂǁA�֎q�Ŕ����B������V���`�F�b�N�B�ߑO�Ǐ��A�����O���A�{�����V���`�F�b�N�B16:00�������ɍs���Ɠ��ɓ���A�N���[�j���O�X�A�a�@�B�r���ŕa�����犳�ҕs���̓d�b�A2�l�s���ł����đΉ��B19:00�A��C�[�H�A20:30�A�Q�B��N����8��B��4920���B
2024�N�͂ǂ�ȔN�H(8) ����(2)�@�o���Ȃ���Ύ��Ԃ͂����Ղ肠�邪�E�E�E�@
�@����1���̐����L�^�B
�@1��21���͓��j���A�V��͓܂菬�J�ł���قNJ����͂Ȃ������B
�@3:00�Ƃ�����ƒx�߂ɋN���B30���قǃl�R�B�ƃX�L���V�b�v�A�������y���݁A�Ǐ��A�f�[�^�����A�k�R�Ȃǂ����̂��Ƃ��B�����͓��@���҂����������Ă���A�a�@�֍s���\��͍��Ȃ������B
�@�ߑO���Ǐ��A�������S�A�O�_�O�_�߂����B
�@���ЂƂ��Ă͕��싨�q���u�����Ƃ��ĂȂ�Ȃ̂�����H�v�ɏW���B����TV�ɂčL���w�`���y���݁A�V���X�N���b�v�쐬�B�R��j�Y���u�l�������ƎЉ�ۏ�v�A����m�q���u�Ȋw�̔����m�b�N����v��ǂ݁A�����ȂǁB�{���\���ǂ߂����Ƃ͗ǂ������������n���̂Ȃ�1�����߂������B19:00�[�H�A21:00�A�Q��1�����I�������B
�@���Ԃ������Ղ肠���āA�Ǐ��O���A�H�ׂĂ͓ǂ݁A�����Ĕ������鐶���B�G�ߕ��O�d���͂Ȃ��g�C�������݂̂łقƂ�Nj��ԂɘU��������B1���̕��s��3999���ƒʏ�̔������x�B
�@���̓��͂������Ǝ��Ԃ��߂������A�Ƃ������A���Ԃ����ė]���Ďd���Ȃ��Ǐ����������Ƃ������ƁB
�@���͖{��ǂނ̂��D���ł���B�\���Ǐ��ł������Ǝ��͖̂������ׂ��ł��������A�S�̒��ł͉���������Ȃ����̂��������B
�@����1971�N(���a46) �N����53�N�Ԃ����ƋΖ��㐶���𑱂��Ă��ċx�������͐E��ɏo�������҂�f��l�ɂ��Ă����B���̂��߂��x���̉߂�������������ł���B
�@
�@��ƌ�������̂����낢�날�邪�A���Z�Ȏ��Ԃ̌��Ԃ������āA���Ԃ��C�ɂ��Ȃ���W���I�Ɋy����ł��鎞�̕�����т��傫���l�Ɏv����B
�@�K���A���N�x���]���Ɠ��l�̋Ζ��`�Ԃ�������ꂻ���ł���B
�@�{���̈���̉߂��������猩�āA�������������ǂ����̂̂��ꂪ�A���ƂȂ�Ƃǂ̂悤�ɕ�炵����ݒ肷��Ηǂ��̂�??
�@������͂����������X���}���邱�ƂɂȂ邾�낤���A�����s���ł���B
1/26�i���j�܂�@�ϐ�͑��<�H�c4-5cm�@��Ȓ��ʕa�@�O���@
�@2:00�N���A�����`�F�b�N���{�ǂݓ������ƕς�炸�B�k�R�L�ځB5:30�R�S�~��o�B7:20Taxi�w�ɁA���H����ɉ����đ��߂���7:45�v���Ă������������������B8:11���܂��B���Ґ��͏��Ȃ������B������炸�B15:30Taxi�a�@�B�V���`�F�b�N�ł��������A19:30�A��A�[�H�A21:00�A�Q�A�����v��6919���B��N��ȉw�^�N�V�[����œ]�|�A�i��������댯�ȏł����������͖����A���Q�Ȃ��A���Â��K�^�Ɍb�܂�Ă���B
2024�N�͂ǂ�ȔN�H(7) ����(1)�@�����t�̏A�J�ɂ��ā@
�@����A�@�l�̐l�������̖K������B
�@���ǂ���l�̘J���_��͈�N���̌_��ƂȂ��Ă���A���N�x�̊m�F�ɗ������́B�l�����̈ӌ����m���߂��Ƃ���A���������ł̏A�J�X�V��O���ɒu���Ă����l�ł���B���Ȃ��Ƃ����ǂ��͎ז��ȑ��݂łȂ������Ńz�b�Ƃ����B
�@�Ɠ��͗��N�x�����������ł̍X�V�̈ӌ����������炵���B
�@�ł���A�������l�ɂ��邱�ƂƂ����B�Ɠ��͎��̈�t�Ƃ��Ă̑��݂�����قǂ͑傫���͕]�����Ă��Ȃ��悤�ł��邪�A���̗��ꂩ�猾���ΉƓ���P�ƂŋΖ�������ɂ͑����̐S�z������B
�@�Ɠ��͎������͂邩�Ɏ��R�ȍl�����������Ă��āA���Ɏ��Ԋ��o�̏�ł͂��Ȃ�̎��R�l�ł���B�����T�ɂ��Ď��ɂ͐��䂵�Ȃ���Ȃ��B����ƕa��ŁA�����Ȃ���K�X�⏕������K�v������B
�@���ǂ���77�A78�̍����t�ł���B���̗l�Ȉ�t�ɏA�J��v������ɂ͂���Ȃ�̎������̂��낤�B
�@���͖@�l���̈�t�s���̖�肾�낤�B
�@���ǂ��̖@�l�͓��{�S��288�@�l�������F��(2017�N10��1�����_)����Ă���Љ��Ö@�l�̈�B
�@�u�Љ��Ö@�l�ɋ��߂�����v���̍�����Áv�́@�E�x���f�ÁA�E��Ԑf�Ó��̋~�}��Á@�E���Y����Â��܂ޏ����~�}��Á@�E�d�Ǔ�a���҂ւ̌p���I�Ȉ�Á@�E�����NJ��҂ւ̈�Á@�E�ȂǂȂǁ@��S���Ă��邩��ł���B���Ȃ�n�[�h���̍����v�����݂����Ă���B
�@����Ό��v���̍�����Ö@�l�Ƃ��ĔF�߂��Ă���̂ł��邪�A����ł��Ȃ��Ȃ��@�l���œ����Ă�����t���W�߂�̂�����ł���B
�@�H�c���͈�t�s���̌��ł���A��X�̕a�@�͏H�c���������A�H�c�s�̂ǐ^�ɂ��邪�A����ł���t���͏�ɕs���ł���B
�@����Ȃ��Ƃ��w�i�ɂ����Ď��ǂ������t�ɂ�������Ƃ��Ă̎��N�x�̏A�Ɨv�����������Ƃ͊m���ł��낤�B
�@�Ⴆ��t�s����Ԃł��낤�ƁA���ǂ��͈�t�Ƃ��Ă̋Ɩ��ɂ��������Ȃ�����҂���Ă��邱�ƂŁA���Ȃ��Ƃ���t�Ƌ���L���Ă��邾���́A���ɂ������Ȃ���t�Ƃ��Ă͑������Ă��Ȃ��炵���B��l�ň�̗×{�a���̈�Â�S���Ă��邩��܂��͍��i�ł͂Ȃ����Ǝv����B
�@�Ƃ������ƂŁA���N��Ԃ��ǂ���A���N�x�����l�̏����ŏA�J�������邱�ƂɂȂ肻���ł���B
1/25�i�j���g��ɂޓ���@�~��2-3cm
�@2:00�N���k�R�ȂǁB�~�σf�[�^�����B8:15�Ɠ��ɓ���a�@�A�܂��x������B�@���w�K��Ƀg���C�A���v�ł������B�a���Ή��ȂǁB�Ǐ��A�f�[�^�����A�V���`�F�b�N�{���́B�^���@����B�Ǐ����S�ɁB�v�����^�[�������B19:30�A��A�[�H�B21:00�A�Q�B��4453���B
2024�N�͂ǂ�ȔN�H(6) ����(6) �@�h�����(5) �@�������V�{���̉��v��
�@�W���p�[�e�B�Ɨ����������A�͊ݓc�h�̉��U��\�����A���{�h�Ɠ�K�h���������B�X�R�h�����U�����߂��B����A�����h�ƖΖؔh�͔h�𑶑���������j�����Ζؔh����͒E�ގ҂����o���Ă���B�h�̉^�c���̂ɂ���肪�������̂��낤
�@�l�X�ȕ��Q���w�E����Ă��鎩���}���h�������v���邱�Ƃ͖]�܂����̂�������Ȃ��B����ɂ���Ď����}�̉��v���i�ނ��Ƃ����҂������B
�@�������A�h���̉������̂��ŏI�ړI�ł͂Ȃ��B�h���ɂ͑��݈Ӌ`������͂����B�����_�����ɉ����������}�Ɍ��߂Ă���?? ����A�h���̐���������āA�}���ŕs���a�������܂�\��������B
�@�J�l�̗͂ƌ��͍\������X�̋c���̎��R�Ȑ����������W�����Ȃ��悤�A��������}�邱�Ƃ��ړI�̂͂����B�����}�������̐M��������ɂ́A���v�𒅎��Ɏ��s�ł��邩�ǂ�������������B�\�ʂ����U���Ă��邾���ł͂��߂��B
�@�h���͍ŋߎ���������A�Ƃ����B���̂��߃p�[�e�B�[���p��ɍs���ė������A����͋֎~����̂��B�����܂Ŕh�������U����Ύ����I�Ƀp�[�e�B�[�͂Ȃ��Ȃ邾�낤�B
�@�����}���ݒu�����������V�{���i�{�����E�ݓc�j���A���ԂƂ�܂Ƃ߂\�����B���̖`���ŁA�u�}�̉�̓I�o������}��o��ŐM���Ɍ��������g�݂�i�߂�v�Ɩ��L�����B�앶�\�͔͂��Q�ł���B
�@�h���ɂ��Ắu������l���̂��߂̏W�c�v�Ƃ����C���[�W�@���A�u����W�c�ɐ��܂�ς��v�A�Ƌ��������B
�@�h���ɂ�鐭�������p�[�e�B�[�̋֎~��A�l���̐��E�͔F�߂Ȃ����j�����荞�B����ŁA�\�͂����A�h�����ł̒n�ʂ���K�C�Ǝv���Ȃ���b�����J��ɓ��t���Ă����l�����Ȃ��Ȃ邾�낤��??
�@�ނ��A�����}�ł͕s�ˎ����N����x�ɔh���̉����_�����サ�����A�����������߂��͂Ȃ��B�����}�����N���[�g�������A1989�N�ɒ�߂��������v��j�ɂ́A�h���p�[�e�B�[�̎��l���A�h���̉��������L����Ă����B
�@���������̓������ɂ��āA���ԂƂ�܂Ƃ߂ł́A�c���̃p�[�e�B�[�����́A�L�^���c���s�U�荞�݂���{�Ƃ���A�ƒ�߂��B����ς�܂��p�[�e�B�[�����C�ȂE�E�E�B
�@�����}���}�͐��������K���@���������A��v�ӔC�҂��L�߂ƂȂ�A�c������������~�ɂ��ׂ����Ǝ咣���Ă���B
�@�ݓc�h�Ɍĉ�����悤�ɉ��U�����߂����{�h���K�h�ɂ͎ւ̕s���������Ԃ�B���t���������2�N4�����ԁA����ł̖�}�Ƃ̒�����^�}���̐��c�Ȃǂ�S���Ă����͎̂�Ɉ��{�h���K�h�̃����o�[�������B
�@���h�Ƃ��Ă̋c���̋��͂������Ȃ��Ȃ�A�����͗������������˂Ȃ��B
�@�c���͔h���Ȃ��ɐ��������ł���̂��낤���B
�@���͋^��Ɏv���Ă���B
1/24�i���j��r��\�z�ϐ�3cm�@���Ȏ�f�@��lj�
�@1:40�N���B�k�R�Ȃǂ����̂��Ƃ��B8:15�Ɠ��ɓ���a�@�B9:00-10:00���ʎ��Ȑf�Ï��A�����ق��V���`�F�b�N�A11:00�a���Ή��B13:00��lj�B19:30�A��[�H�A21:00�A�Q�B��5733���B��N�͌����[8�xC�A����8��ځA���N��6��B
2024�N�͂ǂ�ȔN�H(8) �H�c���̖��(2) ���|�m���̎�Ȕ���
�@2024�N�́A����4���ڂ̍��|�m���i76�j�ɂƂ��Č����ŏI�N�ƂȂ�B
�@���͌���t������̎��ɐV�^�C���t���G���U�̗��s������A���̊����NJ�@�Ǘ��̈���Ƃ��ĉ��x���ψ���ɏo�Ȃ��e�����ӌ��������A�m���̋L�҉�ɂ͓��Ȃ����Ă����������B
�@���|�m���͂Ȃ��Ȃ��C�����ȕ��ŁA���͐e���݂������Ă���B14�N�]��ɂ킽���Č����̂������߂Ă������A�ŋ߂͏�ɑ��������Ȃ��\�����ڗ��B
�@�m���̔����̈ꕔ�͈ȉ��̔@��(���ڂ͏H�c�@�V���̋L�����Q�Ƃ���)�B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[-
201011��4��
�@�u���q�������A�ق��̍����U�߂ĐH�����m�ۂ���B���蓾�Ȃ����Ƃ������ꂾ���Ĉ�̕���v�B
14�N 5��12��
�@�u�H�c�̐l�����̌����̓R�����B �R���̃E�G�[�g���傫���قǐl�����͒������v
17�N 7��24��
�@�������L�^�I��J�Ɍ������钆�S���t�����Ă������� �u����������������A�������Ƃ�����v
17�N 8��31��
�@������͂���10�N���炢�łȂ��Ȃ�B ���ނ�����̂͑����Ԃ������������v
18�N10��2��
�@�n��z���^�}���V�X�e���u�C�[�W�X�E�A�V���A�v�̔z���v�������u���ɔz���̐���̔��f�𓊂����Ă����飁B�u���̒��x�̂��ƂŐ��������Ƃ��傰���Ȃ��Ƃ͍l���Ă��Ȃ��v �B
20�N12��18��
�@SNS�ɏ������ސl�ɂ��Ģ��b�m�����Ȃ��A�v�l��H���������@���Ă��飁B
21�N 7��7��
�uIOC�͍��������ɂ��Ă���B IOC�ȂE�ނ�������v�B
21�N 7��19��
�@���̐V�^�R���i�Ή������� �u���t�{�͂��傹��A�f�l�̏W�܂�v�B
21�N 8��31��
�@���J�Ȃ̃R���i���N�`���ٕ������x���Ƃ��āu�������������ō���v
21�N 11��8��
�@�O�@�I�H�c2��Ŏ����}�O�E����������}�ɔs�k�������ʂ��u������͈�ʓI�ɗ^�}�ɐ����I�v�]������B ���茠�̂Ȃ���}�̃p�C�v�͗v��Ȃ��v�B
22�N 1��4��
�@�u���������́A�ǂ��̌������{���A �ڕW�����߂Ă���Ƃ���͂Ȃ��B ��̓I�Ȑ������o���Ȃ�Ă��Ƃ͌o�ϊw�I�ɔ�펯�ƌ����Ă���v �B
22�N 4��26��
�@�������̋L���Łu�j����ۗL���܂߁A�^���Ȗh�q����݂̍���̋c�_���n�߂Ă��炢�����v�B
22�N 8��26��
�@�L�^�I��J�Ő[���Ȕ�Q��������n�{�ɂ��āu�d���B �l�i�͈�ʂ̌{����3�{����3�{���܂����͕�����Ȃ��v�B
22�N 10��31��
�@�t�����X����A����ɃR���i�������������u�t�����X�ɍs���Ƃ݂�ȃR���i�ɂ�����v�B
23�N 1��4��
�@���̐H�Ɣ���̔��o�ɂ��������̈��H�����������ƂŁu�H�c�s�̗����̑傫���Ƃ��낪3�A4���Ԃꂽ��B
23�N10��23��
�@�ߋ��Ɏl���n���ŐH�ׂ�����������ɂ��āu�n�R�������v�A �u���܂��Ȃ��v�B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�@���|�m���̔����͎��Ƀ}�X�R�~���ɂ��킵���B
�@���͂������Ă��錧���̒n��Y�Ƃɑ��Ă̔����A�l���̐H�������Ȃ߂锭���͔�펯�ł������B
�@
�@�H�c���̍ő�̖��_�͐l�������ł���B�����ő�̌��Ăł���l�������ɂ܂��\����f���ĕ��c�������Ă����Ηǂ������A�Ǝv���Ă��邪�A����͖����Ȃ��B
1/23�i�j�������@���ʕa�@�O���@
�@2:10�N���B�{�ǂ݁A�����`�F�b�N�B5:30�R���ݒ�o�B6:40�o�X�a�@�A7:00-8:00�a���Ɩ��A8:45-12:00�O���A15���O��ŗ]�T�B�����B���@���ґΉ��A19:10�A��A�[�H�B20:30�A�Q�B�v��7660���B
2024�N�͂ǂ�ȔN�H(7) �H�c���̖��
�@�H�c���̍ő�̖��_�͐l�������ł���B
�@���������v�ۂ́A6��1�����݂̌��l����91��7525�l�i�j43��3534�l�A��48��3991�l�j�Ɣ��\�����B
�@�O���ɔ�ׂ�982�l�����A����1�N�ԂŌ��l����1��6507�l�������B��������1.77%�ŁA ��r���\��1981�N10���ȍ~�ōł��傫���B �������������͑S���ő�B
�@5����1�J���Ԃŏo�������玀�S�������������R���Ԃ̓}�C�i�X1063�l�i�o��344�l�A���S1407�l�j�B
�@�����ւ̓]���Ґ����猧�O�ւ̓]�o�Ґ����������Љ�Ԃ̓v���X3�l�i�]����905�l�A�]824�l�j�B
�@�ł��������̂͏H�c�s��121�l�A�����Ŕ\��s109�l�B
�@�S���̐��ѐ���38��5839���тőO������50���ё������B����̎��Ԃ͕s���ł���B
�@����1�N�Ԃ̎��R����1��3679�l�i�o����3892�l�A���S��1��7571�l�j�A�Љ��2828�l�i�]����1��2215�l�A�]�o��1��5043�l�j�B
�@�����Љ�ۏ�E�l����茤�����̗\���ł́A2045�N�̖{���l����80���l���x�Ɩ��������̐l���Ƃقړ����ł���B�������A�����̐������������̓����ɖ߂�킯�ł͂Ȃ����A���͓��������͂邩�Ɍ�������ԂɂȂ�Ǝv���B������l�����ɉ����č���A��N�w�̌����������Ă���B����ɁA�L�͂ȓy�n�A�l�����x�͂ƂĂ��Ⴍ�Ȃ�B���I�T�[�r�X�͉�肫��Ȃ��B
�@���̍��͂���Ɍ��̐Ŏ��͌������A�ێ���͍����Ȃ�B
�@�l���K�͂Ɍ������o�����X�̎�ꂽ�n����č\�z���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���̓����͌����Ȃ��B�{���̐l�������̗v���Ƃ��āA�i�w��A�E���@�Ɏ�҂���s�s�֏o�Ă��̂܂ܖ߂�Ȃ����Ƃ�����B���ɎႢ�����̗��o�̉e�����傫���B
�@����2023�N�x����A�����������ŕ�炷���Ƃ𑣂����g�݂������B�����������₷���E��Â���A�d���ɂ�肪�������Ă邽�߂̎x�����s���Ƃ��Ă���B�m���Ɉ�̕��@�ł��邪�A����Ȃ��Ƃ�50�N���O������ׂ��������̂ɁA�����Ԃɍ���Ȃ��B
�@���͏H�c�́A���������K�ٗp�œ����Ă��銄���͑S�����ς������Ă���B �o�Y���@�ɗ��E���銄���͑S�����ς����Ⴂ�B�܂�A������o�Y���o�Ă��d���𑱂��Ă��鏗�����������Ƃ̓A�s�[���ł��邾�낤�B�������A���Ԃ͊e�ƒ�̒�����ɂ���̂ł͂Ȃ����H�Ǝv���B
�@�H�c�͎Ⴂ�l�����ɂƂ��Ė��͂���E��͏��Ȃ��B �ʂ����Ăǂꂾ���̊�Ƃ��A�����A��҂�������肪������������d����ł��Ă��邾�낤���B
�@2024�N�́A����4���ڂ̍��|�m���i76�j�ɂƂ��ĔC���͎�����̌����ŏI�N�ƂȂ邪�A���͂��͂≽�����҂��Ă��Ȃ��B���|�m���͌��E����H�c�s�����o��2009�N�ɏ����I���Ĉȗ��A14�N�]��ɂ킽���Č����̂������߂Ă����B�C���͗��N4���B
�@�����ő�̌��Ăł���l�������ւ̑Ή��͂ǂ����������낤���B
�@�m���A�C��2009�N��110���l���������l���͌���91���l�ƁA17�����������B���N�̌������͊g��X���������Ă���B���������͍��S�̖̂��ł��邪�A���Ƃ��ėL���Ȏ��ł��o���Ă������Ƃ����A�^�╄���t���B
�@�l���������S���ōł������y�[�X�Ői�ތ��Ƃ��āA����10�N�̌��͕K�{�Ƃ����悤�B
�@�X�Ȃ鎟�̖��́A���ނ�\�����Ă��鍲�|�m���̌�o��S�����Ɏ��g�ސl�ނ��S�������Ȃ����Ƃɐs����B
1/22�i���j�܂菬�J�@���N�N���j�b�N�@
�@1:15�N���B�{�ǂ݁B�����`�F�b�N���X�����Ɠ����B6:40�o�X�a�@�ցB7:00-8:30�a���Ή��A9:00-11;10���N�N���j�b�N�h�b�N�A12���A���ʔ���15���B���@���ґΉ��A�V���`�F�b�N�Ɠ��́A�Ǐ��B�����ȂǁA19:10�A��A�[�H�B21:30�A�Q�B�v��6023���B
2024�N�͂ǂ�ȔN�H(6) ���ۏ�@�E�N���C�i�@�p���X�`�i���
�@���V�A�ɂ��E�N���C�i�N�U�́A�Ɨ������m�̐푈�ŁA�����Ŋ�2�N���}���悤�Ƃ��Ă��邪�A�܂������I��钛���������Ȃ��B
�@����A�p���X�`�i������K�U�ł̃C�X���G���ƃC�X�����g�D�n�}�X�̐퓬�A����͓���ɑ�������Ǝv���̂����A�J�n����3�J���ƂȂ邪�A����Ɏ��܂�C�z���Ȃ��B
�@���̓�̕����ɂ��A2024�N�̍��ۏ�͍��ׂƂ��Đ悪�ǂ߂Ȃ��B
�@�E�N���C�i�N�U�Ɋւ��ă��V�A���k���N������ꂽ�~�T�C�����E�N���C�i�Ɍ����Ĕ��˂��ꂽ??�Ƃ����B���V�A�͕ۗL����~�T�C���̐������Ȃ��Ȃ��Ă���A�k���N����̒��B�ŕ�����Ƃ݂���B�������K�I���Ē��I��]��k���s��ꂽ�̂�9������������A�~�T�C�����k���烍�V�A�ɋɔ�Ɉړ��������A�Ƃ���ΊĎ��@�\���@�\�s�S���Ǝv����B
�@���{���{�͍�N���A����ł̋c�_���Ȃ��܂܁A�h�q�����ړ]�O�����Ɖ^�p�w�j������B�E���\�͂̂��镐��A�o���\�ɂ����B�č��̗v���ɉ����A�n��~�T�C����č��ɗA�o�����B�č�����E�N���C�i�ɓn�邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ��Ă��邪�A�ԐړI�Ȏx���Ƒ�����ꂩ�˂Ȃ��B���a���ƂƂ��Ă݂̍��������悤�B
�@�C�X���G���ƃn�}�X�̕����ɂ��ẮA�ŏ��Ɋ�P���d�|�����̂��n�}�X�ł͂��邪�A�C�X���G���̍U���͉ߏ�Ɏv����B���G�ɏ@����肪����ł���A���̕ӂ̂��Ƃ͂����當����ǂ�ł������ł��Ȃ��B����Ȃ�퓬�̊g��A�����������O�����B
�@���A���S�ۏᗝ����͍�N11����12���A���̕����Ɋւ��l���x���̋�����i���錈�c�Ă��̑������B�K�U�̎S��͑z����₷����̂�����B���ێЉ�͂�������߂����Ă͂Ȃ炸�A����������l����@���~�߂����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���{�����̂��߂ɗ͂�s�����ׂ����B
�@���{���l����`���f���A�n��̘a���Ɣ��W�ɐs�͂��Ă������Ƃ́A�����ł��m���Ă���B
�@���O����11���A�C�X���G������_���Ȃǂ�K�₵�A���ꂼ��̊O����Ɖ�k�����B���{�̓p���X�`�i�ɑ��ẮA�Ɨ����ƂƂ��ăC�X���G���Ƌ�������u�Q���Ɖ����v���x�����Ă����B
�@�����A�K�U�̐l����@�͋Ɍ��ɒB���Ă���A�ꎞ�I�ɂł��퓬���~�߂āA�x��������͂��A���a�҂����S�ȏꏊ�ɔ�����K�v������B
�@���̈����S���ׂ��A�Ǝv���B
1/21�i��) �܂菬�J�@�����炸
3:00�N���B�l�R�Ή��A�Ǐ��A�k�R�Ȃǂ����̂��Ƃ��B�ߑO����Ǐ����S�A�O�_�O�_�߂����B�u����Ȍ��t�E�E�v�ɏW���B���͖݂ɂ��čL���w�`�A�V���`�F�b�N�A�Ǐ��A�����ȂǁB�H�ׂĂ͓ǂ݁A�����ĐQ�鐶���B�Ǐ��O���B19:00�[�H�A21:00�A�Q�A���s3999���B�g�C�������݂̂ŋ��ԂɘU��B
2024�N�͂ǂ�ȔN�H(5) ����(5) �@�h�����(4) �@�h���̃����b�g
�@�^�V���Ђ�1��16���A17���ɍs�������_�����ł́A�����}�̔h������̂��ׂ����Ƃ̖₢�Ɂu�����v���v��61���A�u�v��Ȃ��v��23���Ƃ������ʂƂȂ����B
�@����͔h���̃l�K�e�B�u�ȕ������N���[�Y�A�b�v����Ă��邪�A���������h���Ƃ͂ǂ�ȏW�܂�ŁA���̂��߂ɂ���̂��낤���B
�@�����̐��E�ɂ�����h���͂����̗F�l�I�W�c�ł͂Ȃ��A���m�ȗ��Q�W�̏�ɐ��藧���Ă���W�c�B�W�c�̃g�b�v�͏����̑��ٌ��܂��͂���ɏ������l���Ȃ��Ă���B�h���Ƃ́A�v����ɑ��ّI���̌��҂Ƃ��̎x���҂����̏W�܂�ł���B
�@�܂��A�h���ɑ����c���͑��̔h���Ɠ�҂������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�u�����͂��̃��[�_�[�̂��ƂɎQ�W�����[�_�[�𐄂��Ă����v�Ƃ������Ƃ̕\���ɂ��Ȃ�B
�@���ۂɐ�����w�ԕ�������邪�A���̏ꍇ�ɂ͑I���̍ۂ̔���Ȃǂ͂Ȃ��B���ꂪ�u�h���v�Ɓu����O���[�v�v�̑傫�ȈႢ�B
�@�h���́u����W�c�v�Ƃ������邪�A����͌��O�ŁA���ۂ́u�c���ɂȂ鎞�ɐ��������Ă���A���`�̂���l�v��u�I�������v��u�M�����Ă��y�v����������h����I�ԂȂǁu�l�ԊW�v�Ɓu�c���Ƃ��Ă̗��Q�W�v�Ō��܂��Ă���B
�@���ł͑��ّI���ƃ|�X�g�̔z���A�I�����̎����z�����A�h���̈Ӗ������Ƃ��đ�ɂȂ��Ă���B
�@�h���̃����b�g�E�����͎��4����Ǝv����B
------------------------------------------------------------------------
�i�P�j���ّI���ł͔h���c���̕[�����ʂ����E����B�����}�̑��ق͐��A�قƂ�Ǒ�����b�ɂȂ��Ă���B�h�����[�_�[�𑍗���b�ɂ��ׂ��[���W�߂�̂����A�h�������c���͂��̃��[�_�[�ɕK�����[����B�ǂ̔h���ł��ߔ��������Ȃ����ߕ����̔h���ɂ�鐔���킹���s�Ȃ��Ă���B
�i�Q�j�����I���͂��ꂼ��̋c�����키�l��B�h���ɏ������Ă���ƗL���c���Ȃǂ����������ɋ삯���Ă����Ȃǂ̑I�����̉��b������B�c���͗��I����ƌ��������Ȃ��Ȃ鑶�݂����ɑg�D�͏d�v�ł���B
�i�R�j���������̖��B�I���̎��͐��}���炾���łȂ��h��������������o��B����ɁA�h������͋G�߂��Ƃɖݑ�Ȃǂ̊������������炦��Ȃnjo�Ϗ�̃����b�g�͖��炩�B
�i�S�j�t���Ȃǂ̃|�X�g�z���B�h���ɏ������Ă��邱�Ƃł��炦��|�X�g�������B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�@����ŁA�h���ɏ������邱�Ƃ̉��l�������Ă��āA���h���c����77�l�ƈ�吨�͂ɂȂ����B
�@�h���͌��X�͐����I�l�ԊW�Ő��藧���Ă��āA�u���������̃��[�_�[�������Ɂv�Ƃ����W�c�ł��邽�߁A�p�~�Ƃ����Ă����ԂƂ��Ă͎c��Ǝv����B
�@�h�������U���������ŗ�����肪�Ȃ��Ȃ�͂��͂Ȃ��B���{�I�ȉ����ɂ́A�܂������Â���̐ӔC�̏��݁A�g�r�Ȃǂ𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B
1/20�i�y�j���ɂމ����@�@
�@2:30�N���B�l�R�Ή��ȂǁA�����ăO�_�O�_�߂����B4:30�ēx�z�c��1���ԁB���������̒��ƕς�炸�B12:00�]���^�̈�����Ƃ��Ԃɍ����A�Ɠ��ɓ���a�@�B���������ȂǁB�V���`�F�b�N�{���́B�Ǐ��A�f�[�^�����Ŕ�₷�B�ߌ������A�a���͈���A19;00�A��[�H�A21:00�A�Q�B�����v��3159���B�^���s���B
2024�N�͂ǂ�ȔN�H(4) ����(4) �@�h�����(3) �@�h�������Ŏ����͂���Ă����Ȃ�
�@�����}�̐��������p�[�e�B�[�����鎖���œ����n�����{���͐����������U�L���̍߂ŁA���{�h�A��K�h�̉�v�ӔC�҂��ݑ�N�i���A�ݓc�h�̌���v�ӔC�҂𗪎��N�i�����B�R�l�͔h���̐����������x���̍쐬��S���Ă����B���R������N�i�ł���B
�@���{���͈��{�h�����ɂ��ĉ�v�ӔC�҂ւ̊Ҍ����s�L�ڂȂǂ̎w�����m�F�ł����A���d�͖₦�Ȃ��Ɣ��f�B�������Ȃ������B����͂��������B�u�m��Ȃ�����!!!�v�ł͂Ȃ��A�u�Ǘ��s�s���͂��������������̂��v�̎��_���K�v�ł���B
�@����Ɋւ��ẮA���@�R����ւ̐R���\�����Ă͔������Ȃ����낤�B
�@�ݑ�N�i�A�����N�i���ꂽ�͔̂h���̋c��2�l�A��v�ӔC��3�l�A�鏑3�l�̌v8�l�B�u�����ƃJ�l�v���ł͂����鏑���\�Ɉ�������o�����B�Ҍ�����������������̋c���̏������K�v�ɂȂ�B
�@�ݓc�́u�ݓc�h���U�v��ˑR���炩�ɂ����B
�@���łɔh�����痣�E��\���������h�����U�̎w�����ł���̂�??�@��̂ɂ����āA�̗��E�͖{����������??�@���߂ċ^���������B
�@��K�A���{���h�������U���j������B
�@����ŁA�����A�Ζؗ��h�͑���������A�Ƃ����B���܂Ŕh������������Ă��������}���A�h���̐���������̃����b�g��S���_���邱�ƂȂ��ɁA�h�^�o�^�Ɣh�������ɒZ�������Ƃ���ɔh�������̒�������Ă���B
�@�����}�͔h������������Ԃœ������鐭�����ł���̂��낤���H�H
�@�����}�u�h�������v���ʂ����������͉����낤���H
�@�e���}���A�����}�̔h���͂����������Q�Ɋ�Â����W�c�ł���B
�@�Â��͔h���Ԃ̃C�f�I���M�[�̑Η����^���ŁA�h�����̋��琧�x�����܂������Ă������炱���e�h���ɂ̓J���[�A�咣���������B
�@����̍���������ɁA���͋c���X�l�̔\�͂��߂��鋣���͂���Ǝv�����A�悭�����Ȃ��B��}���ア�����߂ɁA���O���߂���_�����ǂ������Ȃ��B�����āA�{���̌��͓��������O����������œW�J����_�C�i�~�Y���͌����Ȃ��B
�@����Ӗ��ŁA���{���ƐΔj���Ƃ̑Η��W�Ɍ����������������̂́A�P�ɐ���̘H�����߂���Η��ɂƂǂ܂炸�A�^�����Ȍ��͓�������������B
�@���̎����}�ɂْ͋������R�����B������A���b��ɂȂ��Ă���h���̉������y���l�����Ă���̂ł͂Ȃ����H
�@������A�h���͕�������B�c���l�ł͉����ł��Ȃ��B�����A�������V�{�����肵���ĂɊ�Â��l�ς��͂��邾�낤�B
1/19�i���j�����@��Ȓ��ʕa�@�O���@
�@�Q:15�N���A�l�R�Ή��������ƕς�炸�B�ϐ�͂Ȃ��B5:50�R�S�~�܂Ƃ߂̂݁B�U:30Taxi�a�@�ɁA���S�f�f���L���ق��B7:45Taxi�w�����ɁA8:11���܂��B�w�a�@�ԓk���o�����B15:30���艮�Ï��X�o�R�ѐ�a�@�A�Ï�4���w���A�a���Ή��B�V���`�F�b�N�ł����B19:30�A��A�[�H�A21:00�A�Q�A�����v��6056���B
2024�N�͂ǂ�ȔN�H(3) ����(3) �@�h�����(2) �@�h�������͘_�_�̉B���H��łȂ���
�@���������p�[�e�B�[���߂���A�h���̍\���I��肪���炩�ɂȂ������A��v�ӔC�҂�̑i�ǂɂƂǂ܂�A�����c���A�֘A�c���̗����ɂ͎���Ȃ������B
�@�Ⴆ�A���K�̓����ł̍߂͖���Ȃ������Ƃ��Ă��A�����ւ̐M�������Ă������ӔC�͑傫���B�Q���ɂ��鐭���Ƃ̐����I�E���`�I�ӔC���s��ɂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����}�͐��������̓O�ꂵ�����������ʂ����˂Ȃ�Ȃ��B
�@�p�[�e�B�[�����̈ꕔ�𐭎��������x���ɋL�ڂ��Ȃ������Ƃ��ꂽ�z�́A���{�h����6.8���~�A��K�h����2.6���~�A�ݓc�h����3�疜�~�A�ƂȂ��Ă���B�����A���{���͐����������߂���ߋ��̌��Ă��Q�l�ɁA�u3�疜�~�ȏ�v����ɂ����炵���B����ȉ��Ȃ�Ȃ�??? ����͋^��ł���B�@�@
�@���{�h�ł́A�m���}���Ĕ̔��������ꍇ�A�c���֊Ҍ����邱�Ƃ����N�̊��s�ɂȂ��Ă���A�h�����������m���Ă������A���ւ̕s�L�ڂ͒m��Ȃ������Ƃ����B�{���ɔh���̃g�b�v�͕s�L�ڂ�m��Ȃ������̂��H�H�ٔF���Ă����̂ł͂Ȃ����H�Ȃ�Γ��߂ł���B
�@��K�́A���z�ȑg�D�I�ȗ����Â�������Ȃ���A�����Ƃւ̐ӔC����ؖ���Ȃ��悤�ł́A���������B��v�ӔC�҂��L�߂Ȃ���ւ̋L�ڂ����Ȃ������c���X�l�ɂ��ӔC������͂��B
�@���{�h�ł́A�����c���̑唼����������̂��Ă����Ƃ���邪�A��ɑߕ߂��ꂽ�r�c�c���̂ق���4000���`5000�疜�~�K�͂̊z���L�ڂ��Ȃ�����2�l�݂̗̂����ɂƂǂ܂����B
�@�ݓc�́A�ݓc�h�������Ώۂƕ����A�h�������U����ӌ��𓂓˂ɕ\�������B��K�h�̓�K����������A���{�h���h���̋c������ʼn��U�����߂��B
�@�����Â���̉����ƂȂ����h���̎��ԂɃ��X������͓̂��R���B�����A�����}�����E�ЁE���������A���Ő������A����1994�N���A������5�h�����u���U�v��錾���Ȃ���A����Ȃǂ̌`�Ŋ������ĊJ���A���ǁA���ɖ߂����ߋ�������B
�@�����Â���̎��Ԃ𖾂炩�ɂ��A���������̗����������ׂ������A�h�������ŒNjy��j�ނ̂͒f���ċ�����Ȃ��B
�@���܂Ŕh������������Ă�������}���A�h���̎��@����������̃����b�g��S���_���邱�ƂȂ��ɁA�h�^�o�^�Ɣh�������ɒZ�������Ƃ���ɔh�������̒�������Ă���B
�@�����}�͔h������������Ԃœ������鐭�����ł���̂��낤���H�H
1/18�i�j�܂�@����
�@2:00�N���A�l�R�Ή��������̂��Ƃ��B�~��0cm�B8:30�Ɠ��ɓ���a�@�A�܂��x������B10:00�a���Ή��A�V���E�����`�F�b�N���́B�ߌ���قړ��l�A���W�I�[��ւ��珺�a�𒊏o�B19:15�A��A�[�H�A�A�Q21:00�B23:00�S�����Ҏ����B����5656���B
2024�N�͂ǂ�ȔN�H(2) ����(2) �@�h�����(1) ����W�c�Ƃ��Ă̔h���͕K�v�@
�@�����}���ّI�Ŕh�����ʂ��������͂ƂĂ��Ȃ��傫���B
�@���{�̋c������`�͏�肭�@�\���Ă���̂��낤���A�Ƃ����v���قǕςł���B�@
�@�h���Ƃ́A��������◘�Q�Ɋ�Â��čs�����鍑��c���̏W�c�̂��ƁB
�@��ʂɐ������łȂ��g�b�v�̖��O���Ƃ��āZ�Z�h�ƌĂ��B����͂��������B
�@�����}�ɂ͂V�h��������B
�@7�h���̂����A�Δj����19���A�ݓc����47�l�̔h���̃g�b�v�̍��ɂ���B�����͖��h���ƌ����Ă���B
�@2020�N�̑��ّI�ł́A�דc�h�▃���h�A��K�h�Ȃ�5�h���������̎x����\�������B����ő��ّI���̕[�̂���264�[���l�������悤�Ȃ��́B��������C�Ɋݓc���A�Δj�������D�ʂɗ������B���ꂪ��������b�a���̗��b�ł���B
�@�h���́A���Ă͏����̑��ٌ����x�����A�S���W�c�Ƃ����Ӗ������������������A����ɋc���̎��ȕېg�̂��߂̌��͏W�c�̈Ӗ��Â��������Ȃ����B�X�ɁA�����̌q����ŋ��łɌ��т��Ă���̂łȂ����Ɗ����Ă���B
�@���{�̐����͔h�������Ƃ�����B
�@�l�X�ȏ�ʂŔh���Ԃ̐��͑����������A�}���ق̑I���ł��A�t���l���ɒu���Ă��l���̓K�������h���̗͊w�ɍ��E�����B
�@�t���s�ˎ���s�K�ؔ����������Ă����w�i�ɂ́A�l���Ƃ��Ă̎����ȏ�ɔh���̗͊W�Ő�������A�C��������قƂ�ǒm��Ȃ��l������b�ɂȂ邩��ł���B�@
�@���͊e�c��������W�c�Ƃ��Ă̔h���ɑ����Ċ������邱�Ƃ͕K�v�Ȃ��Ƃ��A�Ǝv���B
�@�����Ɍl�Ƃ��č�簂Ȑ������O�������Ă��Ă��ǂ�����Ă����������Ă����̂��H�H ������A���g�̐��������A�Ђ��Ă͋c���Ƃ��Ă̕ېg�̂��߂ɂ��h���̑����̂͂�ނȂ����낤�B
�@�������A�l�Ƃ��ėL���҂���M�C�ē��I�����c�����A�l�̔��f�����h���̘_���ɏ]���čs������Ȃ�A�c������`�̔j�]���Ӗ����邱�Ƃɂ��Ȃ�B
1/17�i���j���g�����@�ߌ�ѐ�a�@�@�~��Ȃ� �@���Ȏ�f
�@2:00�N���B�l�R�Ή��B�k�R�B�~�σf�[�^�����B��ԍ~��Ȃ��B�W:30�Ɠ��ɓ���a�@�B10:00�a���Ή��A11:00-12:00���Ȏ�f�B14:30�a���J���t�@�A���ґΉ��B19:32�A��A�[�H�A21:20�A�Q�B�����v��5708���B
2024�N�͂ǂ�ȔN�H(1) ����(1) �@���������p�[�e�B�֎~������
�@2024�N�͂ǂ�ȔN�H���܂Ƃ߂悤�Ǝv���Ă�����A�����̗[���A�\�o�����n�kM7.6���A2���[���ɂ͉H�c��`�ł̍q��@�Փˎ��̂ƁA�d��Ȏ����ŔN�����ƂȂ����B
�@���͋������B����Ȏ��������������U�ȂNjL���ɂ͂Ȃ��B�@
�@�O�҂́A�����H�c�ł̔������뜜���Ă����������̍ЊQ���̂��̂ł���A��҂͍ŏ�����q���[�}���G���[���Z���Ǝv���鎖�̂���������ł���B
�@�������ɖڂ��ڂ��B
�@���E�͔N���Ɍ������h�ꓮ�����B
�@�����}�̈��{�h�Ɠ�K�h�̐��������p�[�e�B�[�����闠����肪���o�B���{�h�̊t����}������������X�R����A�����n�����{���ɂ�鋭���{���Ƃ������Ԃɔ��W���Ă���B
�@���[��������シ��Ȃǁu�����ƃJ�l�v�̖��͐��������ɋy�ԁB
�@�����̐����s�M�͐[���ȏ�Ԃƌ����悤�B�Ĕ��h�~���܂߂��������v�͑҂����Ȃ��B�����ʐM�Ђ̐��_�����Ŋݓc���t�̎x������20����O���ɗ������݁A�ߋ��Œ�̐����B�ݓc���v�����������ƒǂ����v�������邩�ɍ���̑��S��������B
�@���́A���u���������p�[�e�B�̊J�È�؋֎~�v�̓ƒf�I�錾�v�Ŋ�@�����C�邢���`�����X���A�Ǝv�����A�ݓc�̖����͂Ȃ��B
�@�����ƌl�ւ̊�ƁE�c�̌����͐��������K���@�ŋւ����Ă���B�����������ň��{�A��K���h�́A�c�������p�[�e�B�[���̔̔��m���}���ďW�߂����𐭎��������x���̎����ɋL�ڂ����A�c�����Ɋҗ����Ă����Ƃ����B
�@
�@�����Ɣh���A�����c���l�ɂƂ��ăp�[�e�B�[���傫�Ȏ������ɂȂ��Ă����B������Q�����1�l20���~�ƍ��z�Ȃ����A���߂��猇�ȗ\��̍w���҂������A�o�Ȃ��Ă��ȑf�Ȃ��ĂȂ��������Ȃ�����p�[�e�B�[�̗��v�͂��Ȃ�̂��̂ɂȂ�B
�@�p�[�e�B�[���̔̔���20���~�ȓ��ł���A���x���ɍw���҂̎����Ȃǂ̋L�ڂ��s�v�B�����x�̒Ⴓ�͑傫�Ȗ��ł���A����ȏW�����@�͎~�߂�ׂ����B
�@�ݓc��2024�N�����ɁA�������v�Ɍ������}�̐V�g�D�u���V��c�v��ݒu�������x��!! �}�̕s��̉��P�̕������������c�_�Ȃǂ͂����ɂł��n�߂��邾�낤�B
�@����_��̐��퉻���傫�ȉۑ肾�B�\���Ȑ�����c�_���Ȃ��܂܁A�d�v�ۑ�̕��j�����܂��Ă��܂��B
�@���N12���ɍ����I�c�_�Ȃ��Ɉ��S�ۏ�֘A3���������肵�A�����\�͕ۗL�̖��L���t�c����B
�@��N12���ɂ́A�E���\�͂̂��镐��̊����i��A�o�ł��Ȃ��Ƃ��Ă����h�q�����ړ]�O�����̉���������A�������}�����Ō��߁A�A�o���ꕔ���ւ����B
�@��������A���̕��a���ƂƂ��Ă̕��݂�h�邪������̑�]���ł���B
�@���h�����u��������r���A�����琬����Ƃ����{���̖ړI����O��A����|�X�g�����߂��ɂȂ��Ă���v�Ǝw�E���A�ݓc�h�����U�������A�h���͋@�\�̐��퉻���K�v�ł��邪����W�c�낵�ĕK�v�Ȃ��̂Ǝv���B
1/16�i�j���g�@ ���ʕa�@�O���@����6��� �����v�_�˓���
2:00�N���B�V���`�F�b�N�A�k�R���B�������̐ϐ�6cm�قǏ���v���B5:00�R���ݏW�Ϗ��Ƀ\���Ŕ��o�B���\��ρB����6��ځB6:40�o�X�a�@�ցA�o�X�҂��͂�₫�������B�o�X�����G�B7:15-8:20�a���Ή��A8:45-13:00�O�������G�A25���ȏ�B13:02�a�@�ɁB15:00���҉Ƒ��ʒk�B���ґΉ��B19:30�A��A�[�H�A21:15�A�Q�B�����v��13073���B���ɓ����n�}44���A����܂�106Km�A3366�����A3037�� 26934Km�B
�H�c��`�����H��Փˎ��́i5�j�q���[�}���G���[��h�����߂�
�@1999�N�͉��l�s����w�̊��Ҏ��Ⴆ�����ȗ��A���Ŗ������Ċ��҂ɒ��˂����S���������̂ȂǁA��a�@�A�n�撆�j�a�@�̈�Î��̂��������A��Â̈��S�Ɋւ��Ĉ�ÊE�݂̂Ȃ炸�Љ�I�ɂ��S�����܂����B
�@�x�܂��Ȃ���A���̔N�ȍ~�A���̖h�~�A�����h�~�̑}�i�W�����B
�@��È��S�͈�Â̎��̊�{���Ȃ��B��Â̎��̎�v�ȗv�f�͈�t�E��ÊW�҂̒m���E�Z�p��o���ɂ��n���x���ɑ傫�������Ă���͓̂��R�ł���A���S�m�ۂ̊ϓ_���狳��E���C�ƍ��x�Z�p���܂߂��n�B�E�P���͏d�v�ł���B
�@�������A���ꂾ���ł͂Ȃ��B�Z�p�I���ʂ┻�f�̑Ó����A�g�D�^�p�̎��_�A��Î҂Ɗ��҂̑��݂̊W�A��Ò̏�̊������Ȃǂ̊ϓ_���瑍���I�Ɍ��������K�v������B
�@���͈�È��S�m���̕�����S�����Ă������A��{�ɂ����̂́u�N�ł���Ã~�X��G���[���N�������鑶�݂ł���v�Ƃ������_�B����ɍq��ƊE�̈��S�Ǘ��V�X�e������w�Ԃł������B�G���[�𑽊p�I�Ƀt�H���[������A�j�A�~�X���G���[�ɐ�������O�ɂݎ�����肷��@�\�͂��̓����͍q��ƊE���D���Ă����B
�@����̉H�c���̂͊ǐ��ƃp�C���b�g�Ԃɂ͋��łȐM���W�����Ď���B�M���W�������Ă͈�Â��q��ƊE�����藧���Ȃ��B
�@�����A���̐M���W�����������̂̉����ɂȂ����B
�@�M���W���j�]������悤�Ȏ��ۂ��������ۂɂ����⊮����V�X�e���̓����͕K�{�ł��邪�A�q��ƊE�ɂ͂������̂��낤���H
�@���ꊊ���H�ւ̌�N���͑����̗Ⴊ�~�ς���Ă���̂ɍ��{�I�ׂ��ꂽ���̂��낤���B�����ʐM�ł͎��ɂ͈ӎv���\���`���Ȃ����Ƃ�����_�ɂ��Ă��⊮�͂͂Ȃ��ꂽ�̂ł��낤���H�H���ɂ݂͂��Ȃ��B
�@
�@���͍q��@�̃f�B�X�v���C�Ɋǐ�����̎w�����e�̃|�C���g���\�������悤�ɂ��ׂ��A�Ǝv���B
�@�m���ɉH�c�͉ߖ���Ԃɂ���̂��낤�B
�@�����炱���A�l�̊��o�ɁA���f�ɑS�Ă��ς˂邱�Ƃ��Ȃ��悤���S�@�\�̓������K�v�ƂȂ�̂��B
�@
1/15�i���j�܂�~���⊦���@���N�N���j�b�N�@�V�G�R�[��z��Ȏ�f
�@1:20�N���A�{�ǂ݁A�k�R�B�f�[�^�����B6:40�o�X�a�@�A7:00-8:00�a���Ɩ��A9:00-11:���N�N���j�b�N�h�b�N�B15���A����͐�T�x�݂̂��߂Ȃ��B11:00�S�G�R�[�A�S�d�}��O����f�B���N�O���͋@�\�I�ɉ��P���Ă����B�Ǐ��ȂǁA13:00���҉Ƒ��ʒk�B���@���ґΉ��B�Љ��ȂǁB19:30�A��B�[�H�A21:00�A�Q�B�����v��8816���B
�H�c��`�����H��Փˎ��́i4�j�����Ă͂Ȃ�Ȃ����̂ł��������A�K�^��������
�@�q��@���m����`�̊����H�ŏՓˁA�]���҂��o���Ƃ����l������̂��N�����B
�@�C�ۋ@���ɂ͋]���҂��o�����AJAL�@���ɋq���斱��(CA)�̋@�]�A��q�̋��͂��������ċ]���҂͏o�Ȃ������͕̂s�K���̍K���ł������B
�@�S���E�o���m�F���čŌ�ɒE�o�����@�����f���炵���B
�@���̓_�͂�����^���Ă��d��Ȃ��قǂł���B
�@����A�C���@��5�l���]���ɂȂ����B����݂���Ȃ����Ƃł���B
�@(1)�Փˎ��̂͂��܂��܉H�c��`��C�����H��ŋN�����B
�@�H�c��`�̎��̑Ή��\�͂͑��̋�`�����[�����Ă���A�Ƃ����B
�@������A��s���Ƀg���u�����������ۂɂ��p�C���b�g�͋߂��ɑ��`�������Ă��H�c�Ɍ��������Ƃ���]����Ƃ����B�䑃��ɒė�����JAL123�ւ��ČR���c��n�A���É���`�ւ̒������N���ꂽ���A�@���͉H�c�ɖ߂肽���A�Ɖ��x����]���o���Ă����B
�@(2)���̋@�̑ωΐ����D��Ă����B
�@JAL�@�́A���B�q��@���G�A�o�X�Ђ�A350-900�^�@�B �V�����@��ŁA�@�̂ɒY�f�@�ە����ނ��g�����ƂŁA�y�ʉ���}���Ă���B�Y�f�@�ۂ͓S�����y���čd���A��ʓI�ɂ͑ϔM���ɂ��D��Ă���B�����A�q��@�͎����Ȃǂ��������Y�f�@�ە����ނ��g����B�G�A�o�X���{�@�l�ɂ��ƁA�@�̂̑ωΐ��́u�]���̃A���~�����Ɠ����x�v�ł���A�ƕ\�������B
�@������S���E�o����܂łɋq�����ɉЂ��y�Ȃ��������Ƃ͍K���ł������B
�@(3)JAL�@�́u���̔R���^���N�A�@�̒������̃^���N�̒��ڂ̔j���͖Ƃꂽ�A�Ǝv����B�ڍוs���A���̐���ɂ��B
�@JAL�@�ɂ́A���`�Ɍ��������Ƃ��ꍇ���l���������1���Ԓ��x��s�ł���ʂ̃W�F�b�g�R����ς�ł����Ǝv����B�S���E�o��10���Ŕ��������A�����̎��ɔR���^���N�����������̂ł��낤�B
�@(4)JAL�@�@���ɂ��ƏՓˌ㑀�c�s�\��ԂɊׂ����A�Ƃ����B
�@�����炭�O�ւ�������ѓ��̒����ɋ߂���Ԃł������ƍl�����邪�A�傫��C�����H������邱�ƂȂ��i�݁A�ŏI�I�ɍ����ɂ���đ��n�ɒ�~�����B
�@���n�ɒ�~�������ƂŒE�o�V���[�^�[�ɂ���Q�����Ȃ������A�Ǝv����B
�@(5)JAL�@�̐ڒn�_�߂��ŊC���@�ƏՓˁB
�@���^�̊C���@�ɂƂ��Ă͕s�K�Ȃ��Ƃł��������A300Km�قǂ̑��x�̑�^��JAL�@�������킳���Ă�����ԂŁA�C���@�͈�u�Ŕj�ꂽ�Ǝv����B����AJAL�@�ɂƂ��Ă͏Փ˂͏�v�ȍ\���̎�֕t�߂������Ő������A�Ǝv����B
�@(6)JAL�@�̋q���ɒ��ړI��Q���y�Ȃ������B
�@���̂��Ƃ͏d�v�ł���B���̂��ߏ�q�͔�r�I��Âɍs���ł����A�̂��낤�B
�@JAL�@��CA�̋@�]�A��q�̋��͂��������ċ]���҂͏o�Ȃ������͕̂s�K���̍K���ł��������A���̔w�i�ɂ͍K�^���������A�Ǝv���B
�@1/14�i���j���������@
1:45�N���A�f�[�^�����A�Ǐ��A���ɔ����B�I���Ǐ��A�����A�k�R�ȂǁB���ɋ��s���q�w�`����A�V���`�F�b�N�A14:00�Ɠ��ɓ���a�@�A�Љ��2���쐬�A�V��PDF����ʁB�����ō��w�p���B19:00�A��[�H�A20:20�A�Q�A�����v7086���B
�H�c��`�����H��Փˎ��́i3�j���Ȃ������H�ւ̂��N���͈ӊO�ƕp��ɂ���
�@�q��@���m����`�̊����H�ŏՓˁA�]���҂��o���Ƃ����l������̂��N�����B
�@���������H�Ɍ�N�����邱�Ƃ͏d��Ȏ��̂ɂȂ���B
�@�������猾���A�ǐ����������w�����o���A�p�C���b�g�����̓��e�ɐ������]���Ă���N���蓾�Ȃ����ƁB
�@���ۂɗގ��̎��ۂ���N���܂ł� 10�N�ɏ��Ȃ��Ƃ�23���N���Ă����B
�@�w�i�ɂ̓q���[�}���G���[�̗v�f���������ɂ��邾�낤�B
�@�����킢�d��Ȏ��̂Ɍ��ѕt������͂Ȃ��������A���ꂪ�����ɂȂ����̂������JAL�@�ƊC�ۋ@�̏Փˎ��̂ł������B
�@���ۂɂ����Ă͂Ȃ�Ȃ����ۂł��邪�A���ۂɂ͂��ꂾ���̌���������̂Ƀq���[�}���G���[�Ƃ��ĕЕt���A���{�I������Ă��Ȃ��������Ƃ������JAL�@�ƊC�ۋ@�̏Փˎ��̂Ɍq�������B����̎��͉̂ߋ��̎��Ⴉ��w�ёĂ���N���蓾�Ȃ������A�Ǝv���B
�@23���̓���͈ȉ��̔@���ł���B
�@�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�@12���́A�n��̍q��@���Ǝԗ��Ɍ���������Ƃ��ꂽ�B
�@5���͊ǐ����Ɍ������^������̂������B
�@2���͏��̍q��@���������ƍl����ꂽ�B
�@4���́A���̌��\�͂Ȃ��A���݂��^�A���S�ςɂ�钲���������Ă���B
�@��`�ʂł́A�ߔe��`��4���A�H�c��`��3���������B
�@�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�@���̎����Ɍ���������S��������Ȃ����A��\�I����͈ȉ��̔@���ł���B
���ߔe��`�ł�2018�N6���A���̗��q�@���������悤�Ƃ� �Ă��������H��ŁA�q�q���@�����������ɓ����Ă����B�@�͊ǐ�����́u�����H��O�v�̑ҋ@�w�����u�����H��v�Ǝv���Ⴂ���A�i�����Ă����Ƃ݂���B ����̊C�ۋ@�̌�N���̃P�[�X�ɗގ����Ă���B
��������`�ł�15�N4���A�q��ǐ����������H��̍�Ǝԗ��̑��݂����O���A���̍q��@�ɒ��������B�q��@�͒������O�Ɏԗ��ɋC�� ���A�S�[�A���E���h(�������Ȃ���)�������B
���F�{��`�ł�21�N8���A�q��@���ǐ�����̃S�[�A���E���h�̎w������ꂸ�A���̂܂ܒ����B���������H�̑O���ɂ͗����𒆎~�����w���R�v�^�[���c����Ă����B�q��@�͗������P�����ŁA�@�����P�����ւ̎w���ɏW�����Ă���A�w�����R�炵���\�����w�E�����B
���H�c�ł�18�N10���A���@�ɏo���� �������H���f�������@�����Ɗ��Ⴂ�������q�@�������H�ɖ����Ői���B
���H�c�ł�19�N6���ɂ́A�ǐ��������̗��q�@�ɒ��������o���Ȃ���A���������H�ɕʂ̗��q�@�̉��f�������Ă����B
�@��ɋN�����Ă͂Ȃ�Ȃ����ۂ����ꂾ������Ƃ����̂ɉ^�A���S�ψ�����{�I������肵�Ă��Ȃ��������Ƃ������JAL�@�ƊC�ۋ@�̏Փ˂̉����ɂȂ��Ă���B
�@��{�I�Ƀq���[�}���G���[�������ƂȂ��Ă���ɂ��ւ�炸�����⊮����@�\�̓�����ӂ��Ă������Ƃ�����̏Փˎ��̂ɂȂ������B
�@�q��s����̌��ׂł������B
1/13�i�y�j�܂菬��@
2:00�N���A�����ǂ݁B�ߑO�E�ߌ�͂Ƃ��ɓǏ��O���A�����O���B�a�@�ɂ͍s�����B�V���`�F�b�N�ȂǁB19:00�[�H�B20:30�A�Q�B�����v��3016���A�Q������ɋ߂��߂������������B
�H�c��`�����H��Փˎ��́i2�jCA�̔��f�A��q�̋��͂������~����
�@�q��@���m����`�̊����H�ŏՓˁA�]���҂��o���Ƃ����l������̂��N�����B
�@�ǐ����������w�����o���A�p�C���b�g�����̓��e�ɏ]���Ă���N���蓾�Ȃ����̂ł���A�ŏI�I���_�͂܂��ł��邪�A�q���[�}���G���[�̗v�f���������ɂ��邾�낤�B
�@�q���[�}���G���[�͑��̕⏕�I�V�X�e���̓����ɂ���ė\�h�܂��͔�Q�̌y�����ł���B���ꂪ�\���@�\���Ă��Ȃ������悤�����A�����w���ɗ����Ă��邾���ł͖h�����Ȃ��ꍇ�����肤��A�Ƃ̏؍��ł�����B
�@����ŁAJAL�@�̏�q���379�l�͂����l��̒��s�ǎ҂�������Ƃ������S�����E�o�����A�Ƃ������ƂŁA����ɂ͐S��������B
�@�@�����Ō�ɒE�o�����Ƃ����������͏Փ˂���18���ゾ�����Ƃ����B���̉��̒��ŋq�����ɒ��ډЂ��y�Ȃ��������Ƃ͂��������ƂŁA�����ɂ��q���斱��(CA)�̔��f�͂����������B
�@�S���E�o10����A�@�͔̂���������ɑ傫�ȉ��ɕ�܂ꂽ�B
�@����ɁA��q�̗�ÂȑΉ����������Ƃ����B
�@CA��9�l�o�ꂵ�Ă����BCA�͗�Âɋً}���̎菇�ɏ]���A���S�ɔ��ł�������f�B�@����ƘA�������Ȃ����A����S����CA�͎��g�̌��f�ŒE�o�V���[�^�[���~�낵���B��q�͍������Ȃ�����w���ɏ]���A��@�ꔯ�ŋ@�O�ɓ��ꂽ�B�@
�@���̋@��̓G�A�o�XA350-900�^���400���A2021�N11��JAL�ɔ[�����ꂽ�V�����@��ŁA�ً}�E�o����8�ӏ��ɂ���B���̒E�o����s�p�ӂɊJ����Ə�q�����Ɋ������܂�邾���łȂ������q���ɋy��ł���B
�@�@���ɏ����������L����B CA�͉�������邽�ߒႢ�p�����Ƃ�悤�w�����Ȃ���A���S�ɒE�o�ł���o�H��T��B �őO���̍��E�̔������g���邱�Ƃ��m�F���A�E�o�����J�������n�߂��B
�@�����CA�͍Ō���̉E���̃h�A�̊O�ɉ��������B�Ō�������̃h�A�̊O�ɉ͂Ȃ��A�X�y�[�X���������B�@���Ƃ͘A�������Ȃ��B�����ǂ�ǂ�Z���Ȃ钆�ACA�͌�������̒E�o�V���[�^�[���~�낷���f�����牺�����B
�@�u���������āE�E�E�v�A�u�ו��������Ȃ��ŁE�E�E�v�B ��q��͎w���ɏ]���A�X�}�[�g�t�H�����炢������������3�ӏ��̒E�o�����玟�X�Ɗ���~��A��ɒE�o�����l�̓V���[�^�[�̉��Ŕ�����`�����B
�@���̊Ԃ�CA�Ə�q�̍s���͊C�O���f�B�A����u��Ձv�Ə̂��ꂽ�B
�@�ʏ��CA�͏�q�ɂɂ��₩�ɐڂ��e��̃T�[�r�X���s���A��q�ْ̋����Ƃ邪�A��x���̂��������ۂɂ͕ۈ��v���ɕϐg����B
�@ ���q�ɂ��ƁA���E���ً̋}���̒E�o�P���͐��������čs���ƂĂ����������̂��A�Ƃ����B����ɔN��1��A��1���������A���p�h�A�̑���Ȃǂ̕ۈ��v���Ƃ��Ă̍ČP����������m�F����Ƃ����B���̕ӂ̂��Ƃ́A�R���q���F���q123�֒ė��[�^�f�̎n�܂�@�V��̐��B�ցA�ɏڂ����B
�@����̎��̂̓q���[�}���G���[�̉\�����Z���ŁA�N���Ă͂Ȃ�Ȃ����̂����A�K�^�ɂ��b�܂ꂽ���AJAL�̏����q�̖����~�����̂͏�q���܂߂��q���[�}���t�@�N�^�[�ł������B
1/12(���j�r��J����Ȃǖ͗l�@��Ȓ��ʕa�@�O���@
2:00�N���A�����`�F�b�N���{�ǂ݁B�~��Ȃ��B5:00�R���ݏ����̂݁A��⏭�Ȃ߂Œ�o�����B7:35Taxi�w���ɁB8:11���܂��B8:50��Ȓ��ʕa�@�O���B����Taxi�B���艮��炸�a�@�A�a�����@���ґΉ��B19:00�A��E�[�H�A21:00�A�Q�B�����v��7355���B
�H�c��`�����H��Փˎ��́i1�j������M�����ł̓G���[��h�����Ȃ�
�@�q��@���m����`�̊����H�ŏՓˁA�]���҂��o���Ƃ����l������̂��N�����B
�@�ǐ����������w�����o���A�p�C���b�g�����̓��e�ɏ]���Ă���N���蓾�Ȃ����́B2�@�������ɓ��������H�ɐi�����邱�Ƃ��Ȃ��悤�A�p�C���b�g�͊ǐ�����̎w�����e�����邱�ƂɂȂ��Ă���B
�@���̂̔�����1��2��17��47������B�H�c��`�b�����H�ŎD�y����JAL�@�����������ہA�C��ۈ����̍q��@�ƏՓ˂����B���͐E��̃��W�I�ň������B���̎��͏ڍוs���Ƃ̂��ƂŎ{�݂̉������R�����H�H�Ǝv�������A����ɋA���Ă���݂�TV�f���ł�JAL�@�����Ɖ��ɕ�܂�Ȃ��犊���H�𑖂葱����l�q���f���o����Ă����B
�@JAL�@�̏�q���379�l�͂����l��̒��s�ǎ҂�������Ƃ������S�����E�o�����A�Ƃ������ƂŁA����ɂ͐S��������B�����͏Փ˂���18���ゾ�����Ƃ������A���̉��̒���18���ȏ���E�o���[�g���m�ۂ���Ă����̂͋����ł���B
�@����A�C�ۋ@�ɏ���Ă���6�l�̂���5�l�����S�B�@���͒E�o�������d�������A�Ƃ����B�\�o�����n�k�̑Ή��ŁA�V���q���n�֎x���������������\�肾�����A�Ƃ����B�]���ɂȂ�ꂽ���̋`�������F�肽���B
�@���͈�È��S�m�ۂ̎��_����q��@���̂̎�������W���Ă������A���ł��q��@���̂ւ̊S�͍����B��Î��̂��q��@���̂����ʂ��l���Ɋւ�邱�Ƃ��������A���҂̓q���[�}���G���[�������₷�����Ƃ����ʂ��Ă���B���̂��������ۂɂ��e�����L����Ȃ��悤��d�O�d�ɑΉ�����m�E�n�E���ł��Ă���B����ł����S�ł͂Ȃ��Ƃ���ɓ���A�ꂵ��������B
�@�����H��̏Փˎ��͖̂ő��ɂ�����̂ł͂Ȃ��B
�@1977�N�A�吼�m�̃J�i���A�����e�l���t�F���̋�`�ŁA���V��ŋً}���Ă����W�����{�@���m���o�����Ɋ����H��ŏՓ˂��A�j��ő��580�l�]���]���ɂȂ������Ⴊ����B���̎��̂͒ʐM��Ԃ��������Ńp�C���b�g���ǐ��̎w�����e����F���Ĕ����������̂ł���B
�@2�@�������ɓ��������H�ɐi�����邱�Ƃ́A�厖�̂ɂȂ���B�ǐ����������w�����o���A�p�C���b�g�����̓��e�ɏ]���Ă���N���蓾�Ȃ����́B
�@JAL�斱���́A��������������ɒ�������������A�Ƃ����B�C�ۋ@�ɂ͊����H�̎�O�őҋ@�����w�����A�C�ۋ@�������̓��e�������B�����A�C�ۋ@�̋@���͋��Ċ����H�ɐN�������Ƃ����B
�@�𖾂����ׂ��^��͑����B
�@���͏d�v�ȓ`�B���e�������ɂ�閳����M�����ōs���Ă��邱�Ƃɖ�肪����A�Ǝv���Ă���B
�@������̏��͌������₷���B���������łȂ��A���c�ȓ��̃f�B�X�v���C�ɒʐM���e�������܂��͋L���Ŗ��������悤�ɂ��ׂ��ł���B
1/11�i�j�������@�_�ЂƂȂ������@
1:50�N���A���w�A�Ǐ��B���̂ق��������̔@���B8:40�Ɠ��ƕa�@�B���H�͊��S�ɏ��Ⴕ���K�B����ƍ����A����̌��ւŊ��C�ɂ���Č��C���Ȃ��Ȃ��Ă����A�}�����X��a�@��ǂɈڂ��B�g�[�Ɠ�������ɂ���Č��C�ɂȂ�������B11:00�a���Ή��A�V���@����B�ߌ�����@���ґΉ��B�����A�V���`�F�b�N�A���́A�Ǐ��A�^���f�[�^�����ȂǁB19:00�L�ʌo�R�A��A19:30�[�H�A�A�Q�B�����v��4470���B
�ߘa�U�N�\�o�����n�k(7)�@���~�͕��U���ׂ�
�@�]���҂�200�l�����\�o�����n�k�͒n�k�̋K�͂��傫���A�Ɖ��|��ɂ�鈳�������������悤�ł���B����ɋG�߂������~����̂܂������Ȃ��Ő��������ƂŔ�Ђ��ꂽ���X����̉��ǂȂǂł����𗎂Ƃ��Ă���A�悤���B
�@�n��̓d�C�␅���̃��C�t���C���͎~�܂�P�T�Ԍo�߂������ł�3���l�߂��̔�Ў҂��������ŕs�ւȏ�Ԃŕ�炵�Ă���B ���ꂾ���n�k�̋K�͂��傫�������̂ł��낤�B
�@����ɔ\�o�n���͓��H�Ԃ����X���Ȃ����ɁA����炪��œI�Ɋׂ����B���̂��ߋ~���̎肪�Ȃ��Ȃ�����ɓ͂��Ă��Ȃ��B
�@�A��������Вn�̌���͑�ςȏł���B
�@10���ߌ�̎��_�ł܂���3���l�������̔��ɐg���邪�A���������������̂��g�[���Ȃǂ��s�����A�f���Ńg�C���������Ɏg�����A�q���ʂł��q���ʂł��ň��A�Ƃ����B
�@���܂ł̍ЊQ�̒��ł͔�ЎҎx���������x��Ă����ۂ��ۂ߂Ȃ��B
�@���͂��āA10���N�܂��̌Â����Ƃł��邪�A�H�c����t��̖��������Ă������ɁA�H�c���̊�@�Ǘ��֘A�ψ���̈ψ��A�ψ����������������߂Ă������Ƃ��������B���͈ψ���̒��Łu���~���̎��R�ЊQ�ł͔�ЂƓ����ɔ�Ў҂̊���K�v�ɂȂ邪�A�H�c���̎���͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��H�H�v�Ǝ��₵�����Ƃ�����B���̎��Ɍ��̒S���҂́A�u���ł͏H�c��`�̌��L�n�Ɉ�萔���~����Ă���܂��B�܂��A���̌��Ɋւ��Ă͕ʂ̈ψ���Ō������Ȃ���Ă��܂��̂ł��̈ψ���ł͎��グ�܂���v�A�Ƃ̂��Ƃł������B
�@���~�̍Œ��ɑ�K�͍ЊQ�A���ɒn�k���������ۂ͔�Ў҂͊���ł����Ɋ�@�I��ԂɊׂ�B���H�̑����ƍ~��Ō�ʎ�����������邾�낤�B�l�I�ӌ��Ƃ��āu�~����������~����ӏ��ɂ܂Ƃ߂Ă����͖̂��B�\�Ȃ������U���~�ɂ��ׂ��E�E�E�v�Əq�ׂ������̌��Ɋւ��Ă͂��̂܂܂ɂȂ����B
�@���݁A�H�c���̍ЊQ��͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��낤���H�H����n�ɂӂ��킵������̂��H�H���͂����S�z���Ă���B���̐S�z������\�o�Ō������̂̂ɂȂ����B
�@�\�o������тł�2020�N12�����獡��̒n�k�܂łɁA�k�x1�ȏ�̒n�k��500��ȏ㔭���B��N5���ɂ́A�ő�k�x6���̒n�k���������B�ɂ�������炸�A�ΐ쌧���u�ЊQ�x�͒Ⴂ�v�Ƃ���26�N�O�̒n�k��Q�̑z��͍X�V����Ă��炸�A�s���̑Ή��̊Â��ɔᔻ���オ���Ă���B
�@�ΐ쌧�����肵���\�o�����̒n�k��Q�z���1998�N�Ɍ��\���ꂽ��A��������Ă��Ȃ������B��̓I�Ȕ�Q�͌����S�̂Ŏ���7�l�A�����S��120���A����2781�l�ȂǁA����̔�Q��啝�ɉ����\�������ԁB �s���̒n��h�Ќv����A���̑z��Ɋ�Â��č���Ă����B
�@�����j���[�X�Ȃǂ���Ă����ۂ͐���H�ƁA�g�[���A�K�\�����ⓔ���Ȃǂ̔��~�s���������̂łȂ��̂��H�H�Ƃ����_�ł���B
�@�H���͎��q���̗A���ȂǂŎ���ɍs���n��n�߂Ă���B���ɂ��ƁA���~�͈ȑO�ɋN�����n�k�Ɋ�Â��ė]�T���������Ă������u���ꂾ���傫�Ȕ�Q�͑z��O�v�Ǝߖ�����B
�@���q���̗A�����ڂɌ����Ė{�i�������̂́A4���ɑ������啝�ɑ�������Ĉȍ~���B��F�s�̔��ł�5���ɂ悤�₭�x���������͂����Ƃ�����B
�@�Ǘ����Ă�1�T�Ԃ͉߂�����悤�ɉƒ��n�悲�ƂɐH���A���A�R���A�ȈՃg�C��������~���Ă��������B��ЊQ�ł͍s���ɂ��u�����v�A���q���ɂ�鏉���Ή��ɂ͌��E������B����܂ł͎������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
1/10�i���j���g�ɂޏI���܂�@���ʎ��Ȑf�Ï�����f�@
2:20�N���B���Ȏ�f�̂��Ƃŋْ�������ł������B�f�[�^�����A�ߑO���w�B8:45�Ɠ��ɓ���a�@�ցA10:00-12:20���ʎ��Ȑf�Ï�����f�A�\�t�g�ȑΉ����B����������������ł������B13:00���҉Ƒ��ʒk�A�����A14:30�����J���t�@�B���ҏ��u�B�V���`�F�b�N���́B19:00�A��A�[�H�A21:15�A���B�����v��4335���B
�ߘa�U�N�\�o�����n�k(6)�@�Z��̑ϐk���Ƃ�������ǁE�E�E(2)
�@���̉Ƃ̓~�T���z�[��O�U�^��49�^�C�v�̐��i�ɉ��ς�������53�ɂ����v���n�u�Z��ł���B�z1979�N������z��45�N�ɂȂ�B
�@�����ϐk���ȂLjӎ����čw�������킯�ł͂Ȃ����A�\���I�ɏZ��S�̂̋��x���x����̂͒��ł͂Ȃ��ǂ̖؎��p�l���ł���B
�@���͈�ۂƂ��Ă̓_���{�[�����̋������l���āA�n�k�ɂ͋����\���Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ̈�ۂ��Ă����B
�@�Z��̋��ϐk�(1981�N)��1950�N-1981�N5��31���܂łɌ��z�m�F���s���������ɓK�p����A�V�ϐk�(2000�N)�͋��ϐk�̊��⋭���A�k�x6���`7�ɒB������x�̑�K�͒n�k�ɑ��Ĉ��S���m�ۂ���Ƃ����K���1981�N�ȍ~�̌��z���K���ƂȂ��Ă���B
�@������A���̉Ƃ͋��ϐk��ɉ����Ă���͂��ł���B
�@���I�Ȃ��Ƃ͂킩��Ȃ����A
�@�i�P�j1964�N�ɋN����M7.5�̐V���n�k�ł́A�S����Ɖ���8,500���Ƃ�����Q�ɂ����āA�~�T���z�[���������͖{�͖̂����Ƃ������ʂ������A�Ƃ����B����ɂ��呠�Ȋ֓������ǂ���u�ЊQ�����Z��v�Ƃ��ď��F����Ă���B
�@�i�Q�j2011�N3��11���B�j��Ŗ��\�L�̔�Q�������炵��M9.0�̓����{��k�Ђł́A�k�x6�ȏ���L�^�����n��̃~�T���z�[����12,000���ȏ゠��A�Ôg�E�y�n�̗��N�E�t�Ȃǂɂ�錚����Q�͔������Ă������A�n�k�̗h��ɂ��|��Ɖ��͌����Ȃ������E�E�E�Ƃ����B
�@�����̃f�[�^�͎��ɑ傫�Ȉ��S���������炵�����A�����܂ł��Г��̒����ł���A100%�M���Ă���킯�ł͂Ȃ��B
�@�����R6�\�o�����n�k��M7.6�ōő�k�x7�ł��������A�V�ϐk���ɐV�z�E���z�����Z��ł������̖ؑ��Ɖ����S�Ă������Ƃ������Ȃǂ̌��n�����ŕ��������B�����������c����(�n�k�h�ЍH�w)�́u�V������Ă��Ă��A��3�N�ԑ������Q���n�k�Ń_���[�W���~�ς��A�|��Ɏ������\��������v�Ƃ��Ă���B
�@���n������1��3���A���ɔ�Q���W��������F�s���@���̈ꕔ�̖ؑ��Ɖ�(��100��)��Ώۂɍs��ꂽ�B
�@40���قǂ����Z�s�\�ȁu�S��v�ŁA���̂����������V�ϐk�������ɐV�z�A�������͉��z���ꂽ�Z��Ƃ݂�ꂽ�B���`���Ƃǂ߂Ă��Ȃ��u�|��v����10���������B
�@�\�o������тł�2020�N12�����獡��̒n�k�܂łɁA�k�x1�ȏ�̒n�k��500��ȏ㔭���B��N5���ɂ́A�ő�k�x6���̒n�k���������B���̊Ԃɑϐk������Q����Ă����̂��낤�B
�@�Z��̑ϐk���͏d�v�ł���B�������A����̓|��Z��ɂ݂�悤�ɁA�J�������L���A1F�ɍL�����ԂƂ����~������A����ɓ�K���āA�����̌Â��l���̏Z��̑ϐk���͉��i�I�ɂ�������x���A�Ǝv���B
�@�Ƃ̒��ɑϐk���̍������^�̌��u�ϐk�V�F���^�[�v��u�����ƂŐ�����Ԃ����͊m�ۂ���A�Ƃ����H�v�͉��i���l����Έ���@�ł��낤���A��Ƒ��ɂ͌����Ȃ��B
1/9�i�j ���g�ɂޓ܂菬��@���ʕa�@���ȊO���@���X�؎��Ȉ�@�p�Ɣ���
1:45�N���A�����E�V���`�F�b�N�B5:15�R�S�~2�ܒ�o�B6:40�o�X�a�@�B7:00-8:20�a���Ή��A8:45-13:00���ʕa�@�O���B�V�N���ɂ��Ă͊��ґ����敾�A13:15�a�@�A�����Ɠ_�H�̃I�[�_�[�B�A�����Ȃ����X�؎��Ȉ�@�A���Ȉ�t��ʂ��p�Ɣ����B�@�l�����Ȑf�Õێ�f�����߂��B�ǂ��Ȃ邱�Ƃ��s������B���̌�ꎞ�������B�V���`�F�b�N�{���́B19:30�A��A�[�H�A21:15�A�Q�B�����v��9237���B
�ߘa�U�N�\�o�����n�k(5)�@�Z��̑ϐk���Ƃ�������ǁE�E�E(1)
�@���{�C�����n�k�A�����{��k�Ђ̏ꍇ�A�Ɖ��|�̊��ɂ͈��������]���҂͏��Ȃ��A�啔�����Ôg�̔�Q�ɂ���Ă����B
�@����A�����R6�\�o�����n�k�ł͎ʐ^�Ō������A����������̑�^�Z������|�A��_��k�ЂƓ��l�����ɂ��u���ڎ��v���啔�����߂�ЊQ�ɂȂ����B
�@��_��k�Јȍ~�̎�Ȓn�k�ɂ�钼�ڎ��̐�
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
1995�N�@��_��k�Ё@�@�@�@ �@5516�l(�Ђɂ��Ď��܂�)
2004�N�@�V�������z�n�k�@�@ �@�@16�l
2008�N�@���E�{������n�k �@ �@23�l
2011�N�@�����{��k�Ё@�@ �@18423�l(�Ôg�ɂ��]���܂�)
2016�N�@�F�{�n�k �@�@�@�@�@ �@�@50�l
2018�N�@�k�C���n�k�@�@�@ �@ �@�@41�l
�@�@�@(���s���s���҂��܂ށB �x�@������t�{�Ȃǂɂ��W�v)
2024�N�@R6�\�o�����n�k 168�l�@(1/8���_�A���ەs����323�l)
�@
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
�@����́AR6�\�o�����n�k��M��7.6�ō�_��k�Ђ�M7.3������B
�@�������A�ؑ��Ɖ��ɔ�Q���o�₷���n�k�g�u�L���[�p���X�v�ƌĂ��n�k�g���ϑ����ꂽ�A�Ƃ����B�h��̎�����1~2�b�ŁA�ؑ��Ɖ��ɑ傫�Ȕ�Q�������炷���ƂŒm���A��_��k�Ђł��ϑ����ꂽ�B
�@�l���̌����⍂����i�ޒn��ɋ��ʂ���̂́A�Â������ɍ���҂炪��炵�Ă��邱�ƁB
�@����̓|���̎ʐ^������ƁA���h�Ȋ������́A����^�̏Z������B���̂悤�ȏZ��ł͉�����2�K�̏d�ʂ��x����̂͒������S�̂悤�ł���B�������A1F�ŊԎ����L���Ƃ��Ă��邽�߂ɒ��̖{�������ΓI�ɏ��Ȃ��悤�Ɏv����B
�@�ŋ߂̏Z��̌��z���������ƒ����ׂ͍̂߂̖؍ނł��邪�A��������Ƃ����R���N���[�g�̓y��ɋ���Œ�����������ƌŒ肳��Ă���B
�@���̖{���������قǂ��k�����ŗ��Ă��A���ނō����l�p�`�̍\�������ɂ͎߂̋،������n����A���ɂ́uX�`�v�ɋ،����������Ă���̂�����B�ؑ������̏ꍇ�A�ϐk�v�f�Ƃ��Ă̑ϗ͂�2�{�ɂȂ�Ƃ����B
�@�������A�������͖w�ǂȂ��B�ŋ߂̏Z��͊J���ʂ������A�����������Ȃ邪�A���̃^�C�v�������V���z��̐��ʂȂ̂ł��낤�B
�@�ő�k�x7���ϑ������\�o�����̑ϐk������2018�N�x����51%���A�Ƃ����B���̐��l�̍����ɂ͋������B�{�����낤���H?
�@����A�É����̏ꍇ�A��C�g���t�̒n�k�ɔ����A2001�N����ϐk���𐄐i����v���W�F�N�g�uTOKAI 0�i�|��[���j�v�����{���A�����̑ϐk�f�f�Ȃǂ�i�߂Ă����B �É������ɂ�2018�N�̎��_��142���˂��܂�̏Z�����A�ϐk������89.3%�ƂȂ��Ă��āA2025�N�ɂ�95%��ڎw���Ă���Ƃ̂��ƁB
�@�ϐk����j�ރn�[�h��������B
�@���ϐk���ؑ��Z��̖�7����65�Έȏ�̍���҂��Z�ށB�����瑽�z�̔�p�������ďZ���ϐk�����邱�Ƃ��S�O����Ƃ���������B
�@�É�����1981�N5���ȑO�Ɍ��Ă�ꂽ�ؑ��Z��ɑ��A�����̑ϐk�f�f���s���A�⋭�H���ɍő��100���~���x������⏕���x��݂��Ă��čH���̎��{���Ăт����Ă���B
�@�����̂������܂ł��Ȃ���ΏZ���͓����Ȃ����낤�B
1/8�i���j���l�̓��@��⊦�g�I������`���`���@�ϐ�2cm
2:15�N���B�{�ǂ݁A�V���E�����`�F�b�N���B�ߑO�ߌ�Ƃ��ɓǏ����S�ɉ߂����B���H�Ɏ�������N�ɑ����H�������A�����Ă��܂����̂ł͂Ȃ��B����Ŗ��a���Ђʼn߂�����Ȃ炢���̂����A��͂莄�̖����͌����Ȃ��B�ߌ�͐V���`�F�b�N�A������A�^���f�[�^�C���f�b�N�X������ʁA�Ǐ��ȂǁB19:00�[�H�B20:15�A�Q�B�����v��4096���B
�ߘa�U�N�\�o�����n�k(4)�@�n�k�\�m�͂ł���̂�?? �܂��o���Ȃ�
�@�\�o�����ł�2020�N12�����납��n�k���������������A�Q���n�k���N���Ă����B
�@���Ƃ̊Ԃɂ͑�n�k�̃��X�N�����܂��Ă���Ƃ̔F���͂������Ƃ���邪�A����ł́A�Q���n�k����n�k�ɂȂ��鎖��͑����Ȃ��Ƃ̈ӌ�������B
�@��n�k�̉\�����������Ƃ̊�@���������́A�Z�������L�ł��Ă���A�Â������̑ϐk�⋭��Ƌ�Œ�A�W���̌Ǘ��ɔ��������~�ɂ����Ǝ��g�߂��͂��ŁA��Q���y���ł����̂ł͂Ȃ����E�E�E�Ǝv���邪�A�n�k�\�m�̔��f�ɂ͖��m��v�f������A�\�m�̔��\�ɂ���ĎЉ�@�\������A�Z����s�����Ȃ߂邾���ɁA�n�k�\�m���\�Ɋւ��Ă͍X�Ȃ�Ȋw�I�����A�u�w�I�����̊m�����K�v�ł��낤�B
�@���C�n���̑�n�k�̔����ɂ��Ă͂��̑傫���̗\�����܂߃}�X�R�~�ł��Ƃ肠�����Ă������A���ۂɋN�������͓̂����{��k�Ђł������B
�@���̌����C�g���t����ɘb��ɂȂ��Ă������A���ۂɋ���n�k�������̂͌F�{�n�k�ł������B
�@�䂪���̒n�k������������{�n�k�w��́A����͊w�҂��2000�l�ŁA1880�N�ɐ��E���̒n�k�w��Ƃ��đn�݂��ꂽ�B
�@����܂œ��{���ӂł�1707�N�̕�X�n�k������l8.6�ōő�ƍl�����Ă���AM9�K�͂̒n�k���N����\�����w�E���錤���҂͂قƂ�ǂ��Ȃ������B�ϑ��j��ő勉�̒n�k�ƂȂ��������{��k��M9.0�́A�����̒n�k�w�҂ɂƂ��āu�z��O�v�������B
�@�u�n�k�\�m�͂ł��Ȃ��v�A�u���{�����\����n�k�����m���͖��Ӗ��v�A�u�n�k�͕s�ӑł��ŁA�ǂ��ł����蓾��v�E�E�E��߂��ӌ��̊w�҂����Ȃ��Ȃ��A�Ƃ����B���Ƃ̖{�����Ă݂����B
�@�䂪���ɂ͂ɂ͂킩���Ă��邾����2000���̒f�w������B�����Ȓn�k�͍��p�x�ɋN�����Ă���A�Ƃ��ɂ͑傫�ȃG�l���M�[�ɐ������đ�n�k�ɂȂ邱�Ƃ�����B�傫���Ȃ邩�ǂ����͋��R�ɍ��E����A�������A�n���[���ɂ���f�w�̏�Ԃ𑪒�ł��Ȃ��A�Ƃ����B������A�n�k�̗\���͔��ɓ���B
�@���_�������A���Ƃ̌������ʂɂ͒n�k�ϓ��́u�v���X���b�v�v�u�X���[�X���b�v�v�Ȃǂ̃f�[�^���璆�E�����I�n�k�̔����ɂ��Ă͉\���͎������Ƃ��ł���悤�ł��邪�A�u�����v�u�����Łv�u�ǂ̋K�͂́v�n�k�������邩�𐳊m�ɒm�邱�Ƃ͌��݂̉Ȋw�Z�p�ł͕s�\�Ƃ̂��ƁB
�@���ꂪ�A���݂̒n�k�\�m�̌���ł���B
�@�����R6�\�o�����n�k������A�����l����������Ȃ��B
�@�n�k�̓��{�ɏZ�ވȏ�A�u�z��O�̒n�k�v���A�u�������邩�͗\�m�ł��Ȃ����A�g�߂ɋN���肤��Ƒz��v���āA��Q�����Ȃ����鏀�������Ă������Ƃ��̗v�Ƃ������ƂɂȂ�B
1/7�i���j�܂��r�I���g�@�~��w�ǂȂ��@
2:30�N���B�����ǂ݁E�^���EPDF�f�[�^�����ȂǁB�V���`�F�b�N�B14:00�Ɠ��ɓ���a�@�A
�V�����́A16:00�a���Ή��A���������Ă���B18:00�A��A19:00���Ε�ɂ���������
�{�Ð�G�̕r�ɓ������C�N��ސH����A���������ł������B20:15�A�Q�B�����v��3222���B���N�z�d�Ռ̏�������B
�ߘa�U�N�\�o�����n�k(3)�@�H�c���̒n�k�E�Ôg�z��@�����s���ɂ����ƌ[����
�@���{�C���̒n�k�́A�����m���ɔ�ׂĕp�x���Ⴂ�Ƃ����邪�A���f�͂ł��Ȃ��B
�@���ɁA�����R6�\�o�����n�k�ł͒Z���ԂɒÔg�������A���������S���Ă���悤��(�ڍוs��)�B
�@���{�C���Ôg�̎d�g�݉𖾂̂��ߒÔg�̔��������ׂ錤�����i��ł���B
�i�P�j�u���{�C�n�k�E�Ôg�����v���W�F�N�g�v�̒���
�@�����Ȋw�Ȃ̈ϑ������L���҂�2013�N����s���Ă��钲���B
�@�k�C�������B�܂Ŋe�n�_�̒n�w�̒Ôg�͐ϕ�����͂����B
�@�ŋߌ��\���ꂽ�X�����쌴�s�\�O�̌Β�̒n�w�����ł́A���{�C�����n�k��������1983�N���Ō�ɁA��7000�N�O�܂ł�9��̋���Ôg���������������Ƃ����������B����́A�k���k�n��ł̋���Ôg�̗������𖾂������߂Ă̐��ʂ��A�Ƃ����B
�i�Q�j���{�C���̒Ôg�F�Z���̔F�m�x��5��
�@���{�C���ɏZ�ސl�ł��A���{�C���Ôg�ɂ��Ă̔F�m�x�͍����Ȃ����Ƃ������ŕ��������B
�@��L�́u���{�C�n�k�E�Ôg�����v���W�F�N�g�v�ł́A2016�N�x�ɑS����Ώۂɓ��{�C�n�k��Ôg�Ɋւ��ăA���P�[�g���������{�����B���̌��ʂɂ��ƁA�H�c���܂ޓ��{�C���̏Z���� ���A���{�C���ŒÔg���N����\�������邱�Ƃ��u�m���Ă���v�Ɠ������l��51.8%�B���{�C���̒Ôg�͓��B�܂ł̎��Ԃ��Z�����Ƃ��u�m���Ă���v�Ɠ������̂�34.9%�������B
�i�R�j���{�C�����n�k�̕��������O
�@����A���O�o�g�w��59�l�œ��{�C�����n�k���u�m���Ă���v�Ɠ������̂�10%(6�l)�B�H�c���̒S���҂́u���o�g�̊w����6�����m���Ă��邱�Ƃ��l����ƁA5��26���������h�Ђ̓��ɂ��ċ��炵�Ă��邱�Ƃŕ������h����Ă����ʂ�����v�Ǝw�E�����B
�i�S�j������⎩��h�Бg�D�̈ێ��͍���
�@�n��̎���ɍ������h�Њ����̂��߁A������⎩��h�Бg�D�̖����͑傫���B�� ���A����Ȃǂ̗��R����A���������Z���g�D���ێ�����͓̂���Ȃ��Ă���A���D�]���Ă���n��͂Ȃ��A�Ƃ����B
�i�T�jM8.7��K�͒n�k��14m�̒Ôg�z��@ �Z�����B����
�@�H�c����2013�N�A���{�C���̎O�̊C���M8.7�K�̘͂A���n�k���N�����Ƒz�肷��Ǝ��̔�Q�z������\���Ă������A2016�N�ɐV���Ɂu�Ôg�Z���z��v�\�����B
�@���ɂ��ƁAM8.7�K�̘͂A���n�k�̔����m���͒Ⴂ���A�ő�Ôg�����ł������͔̂��������X��14.1m�A�����ŏH�c�s�V������13.5m�ȂǁB
�@�ő�g�����B���鎞�Ԃ͊e�n�_15~36���ƂȂ��Ă���B
�@���̍ő�Ôg�������������ꍇ�A���͒Ôg�ɂ���čŏ���1841�l�A�ő���2��1538�l�����S����Ɨ\�����Ă���(�ڍׂ͗����B2013�N�̒n�k��Q�z�蒲���@����HP�ɋL��)�B
�@���ɂ��ƁA���{�C���̒Ôg�͒n�k�̋K�͂ɔ�ׂĒÔg�������A���B�܂ł̎��� ���Z�����������邽�߁A�傫�ȗh�����������A�܂��������ɓ����邱�Ƃ��d�v�Ƃ��Ă���B�䂪�Ƃ̏ꍇ�͓V�����̍��䂪���ƂȂ邪���\����������B
�@�H�c���A�H�c�s�Z���̒n�k�E�Ôg�F�m�x�͍����Ƃ͌����Ȃ��B
�@�@��邲�ƂɌ����s���ɂ����ƌ[�������ׂ��A�Ǝv���B
1/6(�y�j�܂��r�I���g �@
3:15�N���B�����̔@���B�����ǂ݁A�{�ǂ݁B13:30�������Ɖ�f�ɍs���Ɠ��ɓ���a�@�ɁA�V���`�F�b�N���́B�[���܂ʼn@���ō��w�A�^���f�[�^�����B�����A16:30�a���Ή��A��r�I���������Ă���B19:00�A��A�[�H�B������4500���B
�ߘa�U�N�\�o�����n�k(2)�@�����o���������{�C�����n�k�@�Y�p��h�����߂�
�@���̋L���ɂ���n�k�A�L�^�ɂ��c���Ă�����{�C���ŋN�����n�k�̂����A�Ôg����Ȓn�k�͈ȉ��̔@���ł���B
�@1964�N�̐V���n�k�͐��s�Ōo�������B�k�x5�Ŗ{�I�������ݕ��ꂽ�B
�@1983�N���{�C�����n�k�͏H�c�s�Ōo�������B�k�x5�ŁA���H���A���͏H�c��w��3���Ȃ̌������A�������Ɉ�l�c���Ă����������Ƃ��ɓ|�����͓̂|��A���̓��ݏ���Ȃ��قǂ̏�ԂɂȂ����B���ɉt�̎_�f�A��_���Y�f�̃{���x���{���|��ăz�[�X���O��ăK�X�����o�A������ߕ����Ă��ƂȂ����B
�@�l�I��Q�͂Ȃ������̂��K���ł������B
�i�P�j�ŋ߂̓��{�C���̋���n�k
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�@ 1964�N �V���n�kM7.5
�A 1983�N ���{�C�����n�kM7.7
�B 1993�N �k�C���쐼���n�kM7.8
�C 2007�N �\�o�����n�kM6.9
�D 2007�N �V�������z���n�k M6.6
�E 2019�N �R�`�����n�kM6.7
�F 2024�N R6�\�o�����n�kM7.7
�@�@�@�@�Q�l�����u���{��Q�n�k�����֗��v(�ꕔ�NjL)
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�@���{�C�����n�k��1983�N5��26���ߑO11��59���A�j�������̖k����70Km�Ŕ��������B�ߔN�ł�93�N�̖k�C���쐼���n�k (M7.8)�Ɏ����A���{�C���ŋN�����ߋ��ő勉�̒n�k�B
�@����104�l(�H�c83�l�A�X17�l�A �k�C��4�l)�̂����A100�l���Ôg�ŖS���Ȃ����B�����̑S���924�� ����1616�����������̂ɁA�����̕���ɔ����]���҂͐��l���x�ł������B�K���Ђ͔������Ȃ������B
�@����ɑ��A�����R6�\�o�����n�k�ł͏�R�������A�{���̒i�K�̋]����200�l�]�͌����̕���Ɋ֘A���Ă���悤�ł���B�Ôg�ŁA���邢�͉ЂŏĎ����ꂽ���͂���̂��낤���H�H
�i�Q�j���{�C�����n�k�ƒÔg�̊W
�@���{�C���̒n�k�̍ő�̓����́A�k���n���߂��A�Z�����ԂŒÔg�����邱�ƁB
�@�n�k�����͌ߑO11��59���A�Ôg�x�o���ꂽ�̂�12��14���B�[�Y�A�\��ł͌x��ƑO�サ�đ��g���������B
�@�Ôg�̍ő�l�́A�\��`��194cm�A �R�`����c��82cm�A�[�Y��65cm�A�j����53cm�ȂǁB
�@�u���{�C�ɂ͒Ôg�����Ȃ��v�B���������M���Ă����l�����������B
�@�Z���ɂƂ��ĕs�ӑł��ɋ߂��Ôg���������Ƃ���Q��傫�������B
�@�j���s�̉��ΐ��C�݂ł́A�������̍��쒬���牓���ŖK�ꂽ����쏬��4�N����5�N���̎���13�l���]���ƂȂ����B
�@�\��s�ł͌�ݍH���̍�ƈ���36�l���]���ɂȂ����B
�i�R�j���ۂɂ͉ߋ��ɂ����{�C�������ł͒Ôg���������Ă���
�@���{�C���ɂ́u�n�k�̑��v�ƌ����銈�f�w�̏W���т�����A�n�k��Ôg���J��Ԃ��Ă����B���ɒn�k���������Ă���̂��A�k�C��������V�������ɂ����Ắu���{�C�������v�ƌĂ��G���A�B
�@ ���f�w�̓����̊������������w�W�́A�����m���������{�C�������̕����傫���A���f�w���������B���̂��߁A�n�k����������B
�@ ���{�C���̒n�k�̍ő�̓����́A�k���n���ɋ߂��A�n�k��Z���ԂŒÔg�����邱�ƁB�n�k�̋K�͂̊��ɒÔg�������Ȃ�̂��������Ƃ����B
1/5�i���j����܂�ƈ�肹���@��Ȓ��ʊO���@
�@2:20�N���B�~��w�ǂȂ��B5:30�R�S�~2�ܔp���B7:35Taxi�A8:11���܂��A��ȂɁB��ȉ���Taxi�A���艮�A�Ï��X5���B15:40Taxi�a�@�ɁB�a���Ή��B���Ĕ����B�V���`�F�b�N�ł����B19:30�A��B�[�H�A21:30�A���B �����v��7931���B
�ߘa�U�N�\�o�����n�k(1)�@���H���f�ł܂��S�e���킩���Ă��Ȃ�
�@���U��16:00�߂��A����ŐV���`�F�b�N+�蔲����ƒ��ɐk�x3���x�̗h��A���\�����Ԃ̗h���̂Ɋ������B�����W�I�ɂďm�F�A�\�o������k���Ƃ����n�k�ōő�k�x7���Ń}�O�j�`���[�h(M)��7.6�B�u���ɓ��{�C���݂ɒÔg�x������߂���厖�ɂȂ�Ƃ̗\���������B
�@�k�C�������B�ɂ����Ă̍L���n��ŗh��A�ΐ쌧�u�꒬�ōő�k�x7���ϑ������B�\�o�n���ɑ�Ôg�x��A���{�C���݂ɒÔg�x���Ôg���ӕꎞ���\���ꂽ�B�Ôg�͊e�n�ɓ��B���A�����֓��`�ł�1.2m�ȏ���ϑ������B
�@�����ł̐k�x7��2018�N�̖k�C���n�k�ȗ��B
�@��Ôg�x���\���ꂽ�̂�11�N�̓����{��k�Јȗ��ƂȂ�B
�@���{�C�����n�k�́A1983�N�i���a58�N�j5��26��11��59���ɁA�H�c���̔\��s������80Km�̒n�_�Ŕ��������n�k�B�K�͂�M7.7�B
�@�������{�C���Ŕ��������ő勉�̒n�k�ł���A�H�c�E�X�E�R�`���̓��{�C����10m����Ôg���P�����B���҂�104�l�A���̂���100�l���Ôg�ɂ��]���ҁB�Ɖ��̑S����3049���B
�@����̔\�o�����n�k�Ŗ{�����݂ɂ͒Ôg���ӕ��\����A�H�c�`��0.3m�̒Ôg���m�F���ꂽ�B��Q�͊m�F����Ă��Ȃ��B�k�C���̉��݂ɂ�0.6m�̒Ôg�����B�����B
�@�n�k��������5���o�߂����B
�@�\�o�����n�k�œ��H���傫�����������n�ւ̃A�N�Z�X������ȗl�q�ł��B
�@�\�o�n���͓y������Ȃǂœ��H���e�n�Ő��f����Ă���A�傫�ȗ]�k�������Ă��邽�߁A��Q�̑S�e���܂��������Ă��Ȃ��B�|�������̒��Ɏ��c���ꂽ��A�Ǘ������W���ɂƂǂ܂����肵���܂܁A�~����~����҂��Ă���l�������ɏ��Ƃ݂���B
�@5���ߌ�̎��_��370�����̔���3���l�ȏオ���A��d��27.000�ˁA�f����66.000�ˁB����92�l�A���ەs���҂�222�l�B
�@��Вn�͊������������Ȃ��Ă���B��Q���傫���ΐ쌧��F�s�ł́A�Q�������̋C�����X�_��1.2�x�܂ʼn��������B��Ў҂��g������悤�ɂ��邱�Ƃ��}���ł���B
�@���ɐΐ쌧����̍ЊQ�h���v���������q������Вn�ɓ����Ċ������Ă���B
�@�ݓc�͎��������S�ƂȂ��čЊQ���i�߂�Ƃ��Ă���B����H���A�R���Ȃǂ�n���̗v�]��҂����ɑ���u�v�b�V���^�v�őΉ�����Ƌ��������B�x�������̗A���ɊC�H���g�����j�������Ă���B
�@����̑O�ʂɗ��Ƃ������Ƃ͈ꌩ�i�D�����������ƂƂ��Ă̋@�\�̕��S��x���n�����s�\���ł��邱�̏؍��ł�����B
�@��Вn�̈�Ë@�ւɂ́A�����̕����҂���������Ă���Ƃ݂���B���C�t���C�����ǂ��Ȃ��Ă��邩�ڍׂ͕s���B�\�Ȍ���̈�Î����𓊓����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�n�k�̍ۂɂ����C�ɂȂ�̂����q�͔��d���ł���B
�@�k���d�͎��ꌴ���͐ΐ쌧�u�꒬�ɂ��邪�A2011�N�����������̈ȍ~�ғ����Ă��Ȃ��B����A�g�p�ς݊j�R���̗�p�p�̓d�͂ɖ�肪�������炵�����A�ق��̌n���œd�C����Ȃǂ��Ĉ��S��d�v�ȋ@��̓d���͊m�ۂ���Ă���Ƃ����B
�@�����Ȃ����Ђ��ꂽ���X�ɐS���炨��������\���グ�����B
1/4�i�j�I���������@�ʏ�Ζ��J�n�@���N�N���j�b�N���ʔ���
2:10�N���A�����`�F�b�N���A�{�A�����A�����B8:45�_�ЂƂȂ��������B�~�G�Ԃ̏H�c�ł͒������B8:30���n�a�@�B�V���`�F�b�N�Ɠ��́A11:00���N�N���j�b�N���ʔ���A�����A�����A�����ْf�Ǝ����B13:30�a���Ή��ق��Ǐ��B19:20�A��[�H�B20:30�A�Q�B���W�I�[����Ғ����B�����v��5957���B
���{�̉��y�E��2023�N�͂ǂ�ȔN�������̂�(2)�@�N����NHK���W�ԑg����
�@�N����NHK���W�ԑg�����Ȃ��狻�ɔC���Ċ��S�������t����s�b�N�A�b�v���Ă݂��B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
�g�E�K���E�]�q�G�t�w���@N���@���t�}�j�m�t���z�ȁu��v
��j�I�@Vn Vivaldi �u���a�̗슴�v
�����S�A�J���e�b�g�@�V���X�^�R�[�r�`�@���y�l�d�t��No5
���R�u�E�t���V���w���@N���@�h���H���U�[�N�u�t�X���k�v
�A�~�n�C�O���X�@Vla �@�V���[�x���g �u�A���y�W�I�[�l�v
�t�B���b�v�E�W�����X�@�J�E���^�[�e�i�[�@�����e���F���f�B �u�V�g���K�N�v
�������B�w���@N���@R�V���g���E�X�u�A���v�X�����ȁv
�R�����E�J���O���[�v�@18�l�̉��y�Ƃ̂��߂̉��y
�b��h���Y�@�o���g���@�u�h���J�����v���
���[���X�E�x�W���[���U��t���@�p���I�y�����o���[�c�u�{�����v
�m�Z�_�w���@N���@�J�[�b���u�֏��v
�E�C�[�����N�����c�@�u���������h�i�E�v
�e�B�{�[�E�K���V�A�@�M�^�[�@�o���I�X�u�����c�v
�W�����E�E�C���A���X�@�Z�C�W�I�U���R���T�[�g
�t�@�r�I�E���C�[�W�@N�����2000��L�O���t��@�}�[���[�u���l�̌����ȁv
���ց@���@N���@�V�x���E�X�u������No2�v
���������@N���@�u���[���X�u������No3�v
�W�����A�[�h�J���e�b�g�@�x�[�g�[���F���@�Z���I�[�\
�M���E�V���n���@Vn �t�H�[���\�i�^
�W�����E�A�N�Z�����b�h�@N���@�`���C�R�u����݊���l�`�v
�L�����E�y�g�����R�w���@�x�������t�B���@�u���[���X�u������No3�v
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
�Ẳ��y�ՃV���[�Y
�@�E�C�[�t�B���@�T���\���ƃf����
�@���C�v�`�q�o�b�n���y�Ձ@�R���M�E���W���p���@�~�T�ȃ��Z��
�@�����ƃr���[�l���y�Ձ@�l���\���X�w���x�������t�B���@���[�G���O����
�@�U���c�u���O���y�Ձ@�}�N�x�X
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
���̉��y��
�@���w�i���v���X�i�[�@Pn
�@�C���O���b�h�փu���[�@P
�@�O�R�Y�O
�@�ю���Y
�@�����@�N
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
No92���{���w�R���N�[���@�D���҂���5�l
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
�@���̔ԑg�ŏ��߂Č��邱�Ƃ��ł������t�Ƃ������B
�@�����Ƒ��ʂȋZ�\�̂��鉉�t�Ƃ����������̊y�Ȃ����グ�Ă���B
�@10�N�O�̃f�[�^�Ɣ�r���Ă݂�ƁA���t�Ƃ̊�Ԃ�A���t�Ȗڂ͈�ς��A���ɂƂ��Ď�����Ȃ��Ȃ������Ȃ��Ă��Ă���B
�@�D��͂����Ȃ����A�L�����E�y�g�����R�w���@�x�������t�B���̉摜�����߂Č��Ċ����������B�ނ͂킸��6��̋q���Ŏ�Ȏw���҂ɔ��F���ꂽ�A�Ƃ����B��ނȂ̂��낤�B
�@���ɂƂ��ċM�d�Ș^�掑���ƂȂ����B
1/3�i�j�܂菬�J�@�N�n�x��3���ځ@
2:20�N���B��Ԑϐ�[���A�V���`�F�b�N�A�����A�{�ǂ݁B�����Ɠ����B8:45���ւɒg�[����Đ����B�^���f�[�^�����B���H��14:00�Ɠ��ɓ���A�ѐ�a�@�K���[�W���̐A���������ɉ^�ԁB�a���`�F�b�N�A���҂͈���A�Ǐ��B19:00�A��[�H�A22:45�A�Q�B������5352���B�\�o�n�k�̑Ή��͌�ʃC���t���̔j��̂��߂ɑΉ����x�X�Ƃ��Ă���l�q�BJAL�ƊC���@�̏Փˎ��̂̌����͖��炩�ɂȂ����B
���{�̉��y�E��2023�N�͂ǂ�ȔN�������̂�(1)�@�N����NHK���W�ԑg����
�@���͉��y��S�ʓI�ɍD�ނ��A��{�I�ɂ̓N���V�b�N�ƌ�����W���������D���ł���B�����A�ŋ߂͂������ӏ܂��鎞�Ԃ��Ȃ��A����I�ɂ͉̗w�ȁA���s�́A���̂Ȃǂƕ��ނ����y�Ȃ����W�I��p�\�R�����ŕ��������Ă���B
�@���y�֘A�̌������u���y�̗F�v��1946�N���犧�s���ꂽ�Ƃ������A���͒���I�ɍw�ǂ����̂�1971�N����ł���50�N�߂��ɂȂ�B
�@���̎G���ɂ͑S���łǂ̂悤�ȉ��t��Â��ꂽ���A�I�[�P�X�g�����A�ǂ̂悤�ȉ��t�Ƃ���������̂��A�Ȃǂ̏���̂ɗL�p�ł���B
�@�e�n�̉��t��̗l�q�Ȃǂ����|�[�g�����B
�@�������Ȃ���A���������L�p�ł��邪�A���y�͉��t���Ȃ�����̉��l�͌�������B
�@�K��NHK�ɂ͉��y�֘A�̕����������B�u���y�̗F�v�œ������̂�������NHK�̕����ŁA���t��̑S�āA�܂��͂��̈ꕔ����������TV�AFM�A�C���^�[�l�b�g���W�I�Œ������Ƃ��ł���B���ɃC���^�[�l�b�g���W�I�͎G�����Ȃ��������ƂĂ������B
�@���̍ہA�u���y�̗F�v�̉��t����͂ƂĂ��L�p�ł���B
�@�Ƃ�킯�A���N�N���ɂ́u���{�̉��y�E�͂ǂ�ȔN�������̂��v�����_�C�W�F�X�g�ԑg�����������B
�@��N���N����12��31����A�uN�������ʉ��t��v�ɑ����ĕ������ꂽ�B�X�̉��t��2�|5�����x���������Ȃ����A����ł��������ʼn䖝���Ă������t��̗l�q�A���t�҂̎p���_�Ԍ��邱�Ƃ��ł����B
�@���N�������ł͑����̉��t��Â��ꂽ�B
�@���N�͕������ꂽ���t��̂������ڂ������t��≉�t�҂����X�g�A�b�v���Ă݂��B
1/2�i���j�I���܂�@�N�n�x��2���ځ@�ϐ�Ȃ��@�H�c�ŊC���@��JAL�@�Փ�
0:30�N���B�n�k�Ôg�̃j���[�X�����W�I�����������B���X�ɔ�Q�����炩�ɂȂ��Ă��Ă���B���������B�k�R�ȂNjL�q�B�����A�Ǐ��A�����E�ߑO�Ƃ��ɓǏ������w���S�B�ߌ�A���U�̐V���̂����t�^�I�����ǂށB14:00�Ɠ��ƂƂ��ɕa�@�ցB���@���҂͔�r�I���������Ă����B18:00���H�c�Ŏ��̂��������炵�����ڍוs���B19:10�A��A�[�H�A21:30�A�Q�B���s��4528���B�H�c���̂͊C���@�ƒ�������JAL�@�������H��ŏՓˁA�C���@��5�����S�AJAL�@�͉��サ����400���߂��̏�q����͑S���@�O�ɓ��ꂽ�A�Ƃ����B��ՓI�A�Ƃ����ׂ����낤�B
NHK�����y�c�̑�㉉�t��
�@1��1���ߌ�͏��ւ��Ă�12��22����NHK�z�[���ōs��ꂽ���엳��w���ANHK�����y�c�́u��㉉�t��v��^��Ŋӏ܂����B
�@���쎁�́A2001�N�Ƀu�U���\�����ێw���҃R���N�[���ŗD���A�ǔ��������w���ҁA���s�s����C���C�A���݁A�L�������y�c���y���ēȂǂ������B
�@N���Ƃ�2005�N���狤���B2023�N10����N�����w���҂ɏA�C�����B
�@���t�҂́AN��������Asp�����b���Amsp�e���ʁAtn��������Aba�͖�S���A�V�������ꍇ���c�B
�@
�@�ŏ��ɁA�o�[�o�[�́u���y�̂��߂̃A�_�[�W���v�����t���ꂽ�B�����̉��y�Ƃ��đt�ł��邱�Ƃ������ȁB
�@�����Łu��9�v�̉��t�B
�@����ɂ���ċ��X�܂ł悭�l����ꂽ�u���v�B���͂����ɉ��t�Ɉ������܂ꂽ�B�[�����̂���u���v�ŁA���͊��\�����B
�@�x�[�g�[���F���́u���v�̓o�[�o�[�́u���y�̂��߂̃A�_�[�W���v�ƂƂ��F�蕽�a�̋F��Ɗ���̋Ȃł���B
�@���[���b�p�ł͓�̕������N�����Ă��ĂƂ��ɏo���������Ȃ��B
�@����������āA���N�́u���v�͂ЂƂ������S�[�����������B
�@
1/1�i���j�I���܂�@�N�n�x�ɏ����@�t����Ɨ��H�@�[���\�o�n���ő�K�͒n�k�E�Ôg
1:30�N���B�l�R�Ή��A���������D�k�R�ȂǏ����B9:00�t����Ɨ��H�A�����B�l�R�Ή��A�Ǐ��B�ߌ�A���U�̐V���ǂށB10:00-13:30���ւ��Ă�uN�������ʌ����v���키�B�u�����t2023�v�����B���Z�łȂ��Ȃ����y�ԑg�������ł��Ȃ��Ȃ������ɂƂ��Ă͋M�d�ȋL�^�ł������B�[��16:10�\�o�n���Ők�x7�ȏ�̑�K�͒n�k�����A�����ɒÔg����߂��ꂽ�B19:00���݂Ƃ������ŗ[�H�A20:30�A�Q�B�a������h�{�̓��^���[�g�̎��Ȕ����̕���B���s��4980���B�^���s���B
2024�N���U�@�����܂��Ă��߂łƂ��������܂�
2024�N���U�@�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B
�@���N���ǂ��N�ł���܂��悤�A����Ă���܂��B
�@(���N�̌��ւ̂��ߏ���͐��E�Ɠ��{�̕��a�������2��f�����j
-------------------------------------------------------------------
�@�ߌ�A16:10�k���n���Ők�x7�قǂ̑�K�͒n�k�A�Ôg���������Ă���B
�@�]�k�Ǝv����h����p�����Ă���悤���B
�@�ڍׂ͂܂��s���B
�@���Y�n��̕��X�A��Ђ��ꂽ���X�ɂ͐S���炨�������\���グ�܂��B
�@
12/31�i�y�j��A���@
�܂菬�J�@�N���x�ɓ����
�@4:00�N���A�l�R�Ή��A�Ǐ����S�B�����̂��Ƃ��A7:00����̃I�[�h�u�����S�ɒ��H�B�Ǐ��A�����ȂǁB13:00�N�z�����Œ��H�B14:00�������A��f�ɍs���Ɠ��ɓ���a�@�ɁB�Ǐ��A�f�[�^���������ʼn߂����B�V���`�F�b�N�{���́B���W�I�̘^�������B�f�[�^�����E�E�E�B19:00�A��A�������H���钷����Ɗ܂�7�l�ő�A���̂��������������B
�[�H��A�v�XNHK�g���̍�����ς悤�Ƃ������ǂ���̐ݒ�ɂ��Ă��������X�ɓڍ��A21:00�A�Q�B�����v��4265���B
?
2023�N���̈�N(7) �@���ӂ̋C�����Œ��߂����@?�@���Ԃ̌o�߂͎��ɑ����B�{�N�����ɑ�A�����}�����B�@
�@�ŋ߂₽��ɐ����������Ă���B�g�̂����߂Ă���̂�����E�E�ƁA�Ɩ�������Ƃ̌��Ԃ���������̗~���ɂł��邾�������Ă���B�����ɋN���o���Ƃ����ϑ��I�Ȑ����̘c�݂��W���Ă���̂�������Ȃ��B
�@���̍D���Ȍ��t�́u�p���͗͂Ȃ�v�ł��������A�������N���A�u�����Ɩ��v��ɁA�K���ɐ����Ă݂����E�E�E�v�Ǝv���A��N�����肩��u�ł��邾���Y���������A�蔲���������A�y�������v�ɐi�������B
�@�����Ƃ���͔����������̂��A�ƃE�W�E�W�l����B���N��5���A���ŏ����v�������A���������g�������Ȃ肩�Ȃ�n���Ă��܂����B���ꂾ���ł��������B
�@�����v��23:30�������Ă���B�����邱�ƂɊ��ӂ̋C����������Ȃ���V�N���}���悤�E�E�E�ȂǂȂǁA�l����B
�@
�@���N�������I��肻���B�{�N���̋L�q�͂����܂łƂ��A�Y�������Ă��������B
�@���̈�N�A���肪�Ƃ��������܂����B
�@
12/30�i�y�j�܂艷�g�@�N���x�Ɉ���ځ@�P��̖݂����?
2:00�N���A�Ǐ����S�B�����̂��Ƃ��A7:00�R���|�X�g�����B9:30�I�[�h�u�����������A�ɍs���Ɠ��ɓ���A�a�@�ɁB�����̔@���B���H�͓c���ٓ��B15:00�a���Ή��B�Ǐ��A�V���`�F�b�N�A����3���B17:00�}������A���V�g�ɗ������x�ɁB�P��̖݂����+�e�r��A21;30�A��B22:00�A�Q�B�����v��1256���A����ɖY�ꂽ���߁B??2023�N���̈�N(6)
�@�䂪�Ƃ̏o����(2)�@���X�ɑ�
���ӂ̋C�����Œ��߂����@?�@���Ԃ̌o�߂͎��ɑ����B�{�N�����ɊA�����}�����B�@
�@�����Ԃ�{���w�����ǂB���������B�_���A����Ă��B�������A�z��O�̔M���̂��߂ɍ앿�͗ǂ��Ȃ������B
�@�H�c�̐��Q�͓��L���ׂ������ł��������A�����͒��ڂ̔�Q�͔��Ȃ������B
�@�����̐V���A�Ǐ��A�����������̑��Ȃǂ�ʂ��Ă��낢������d��������A�f�[�^�Ƃ��Ă��~�ς����B���m�ł�����������p���Ȃ���A�V�����j���A�������w��œ��X��l�Ŋ������Ă���B
�@�ŋ߁A�̗́E�C�͂̐����������ł���B�k�R���L�̍X�V�ɂ������J���悤�ɂȂ����B�o�����X���o�̐������ؗ͒ቺ���A���܂ӂ���B����Ɏ��͏�Q���i�B������̑Ή����K�v�Ȃ��Ƃ͗������Ă��邪�A�ƂĂ��ǂ������鋗��������A���̕����̎��͂����Âłǂ��Ȃ邩�킩��Ȃ��̂ł܂����߂��˂Ă���B
�@����A�܂��܂��Ǐ��~�͐����Ă��Ȃ��B���̈�N�ԂɐV�����w���������Ђ����ł�100�����Ă���B�S����̂��f�[�^����iPad�œǂށB�悭�ǂA�Ǝv���B
�@�{���[���������̔킹������������ꖂ��Ă���Ƃ��ɊO�ꂽ�B�V�N���X�ʉ@���K�v�ƂȂ����B�����������Ă��鎕�ȂɎ��̕������f��U�����Ă��ꂽ�̂��낤�B
�@�{���͉Ɠ��̔��ĂōP��ƂȂ��Ă���݂����x�ŊJ�Â���A�V��j��20�l�]���W�܂苌�������߂��B�H�c�ɉz���Ă��Ĉȗ����b�ɂȂ����Ɠ��̗��e�_�ɂ��ꂾ���̑����̐l�ԊW�����܂�Ă��Ă���B�����ł���A���ӂł���B
�@�䂪�Ƃ̃l�R�����͂ƂĂ����C�A�������邢�b�����Ă���Ă���B���l�ŏE��ꂽ18�̘V�l�R�́u���[�v�̓{�P�Ǐo�Ă��邪�Ȃ�Ƃ��撣���Ă���B
�@�����������Ė����N�����}�������̂́A��͂葽���̕��X�̂��A�ł���B
�@�����ŋ߂悭���ɂ���W��́u���e�v�A�u�E�ρv�A�u���Ӂv�ł��邪�A���̈�N�A�܂�������邪�������[���u���Ӂv�̋C���������߂Ē��߂����B
�@���肪�Ƃ��������܂����B
12/29�i���j�~��Ȃ��@��Ȓ��ʕa�@�O���@���n�a�@��p�[
�@2:00�N���A�����ǂ݂ق��B5:50�R����2�ܒ�o�A���N�Ō�́B�s�̈˗��������ݏ����Ǝ҂̃X�^�b�t�̕��X���̈�N�Ԃ���J�l�B7:30Taxi�w���ɁB���H�ɐ�Ȃ��X���[�Y�ɐi�s�B�W:11���܂��A8:50��Ȓ��ʕa�@�B���N�Ō�̊O���B�����Ƃ�Taxi�A15:30���艮�o�R�a�@�A��쎁�̂��ЂƂ�l�֘A���Ѝw���B�a���Ή��B�����ȂǁB���n�a�@��p�[�A�a���w���A���w���̗��h�Ȉ��A����B��C�B����X�C�[�c�Ƃ������������B���ǂ��͊��}����Ă���A�Ƃ̎������������B19:20�A��A21:00�A�Q�B������7432���B�锼���t���������\��B
2023�N���̈�N(5) �@�䂪�Ƃ̏o����(1)�@���N�E�E����@
�@���Ԃ̌o�߂͎��ɑ����B�{�N���A�����}�����B
�@(1)���̌��N
�@5��5���ߌ�A�}�Ɍċz������������Ζ����Ă���a�@�̋~�}�O����f�A�f�@���O�ɂ͈ӎ�����炵���B�S���R���̋}���ċz�s�S�Ƃ̂��ƂŎ����o�債�����A�_�f12L+���̋z���ق��Ŕ�r�I�Z���Ԃʼn��P�A���ʓI�ɂ͂��ƂȂ����B
�@���P��̐S�@�\�����ł͑S�ʓI�ɒቺ��Ԃɂ���A�^����3.7���b�c�ȓ��ɍs����}����悤�w�������B���������e�ł͋��������������A�X�e���g���Â͎Ă��Ȃ��B������A�悪�ǂ߂Ȃ��B
�@(2)�Ƒ������̌��N��
�@�a�g�̉Ɠ��͑傫�ȃg���u���Ȃ��قڌ��N�I�ɉ߂����Ă���B�ō��ł���B3�l�̎q�����������C�A5�l�̑���������������L���ɂ��������ƈ���Ă���B�N���̑��͂ł������Ȃ��ăW�W�C�̔w���������B
�@�d���̐Έ䂳�������Ă������Ȃ�Ƃ��撣���Ă���
�@(3)�ѐ�a�@�@
�@�Ɠ����b���@���A���͂��̕⏕��+��ƈ��Ƃ��Čߌ�ɋΖ����Ă����ѐ�a�@���ݔ��͘V���������R��3�����ŕ@�ƂȂ����B
�@���ǂ��ׂ͗̒��ʃ��n�r���e�[�V�����a�@�ɏ�����Ƃ��Čٗp���ꂽ�B���ʃ��n�r���e�[�V�����a�@�ł͓d�q�J���e�ʼn^�p����Ă���A�Ɠ�77�A��78�ŁA���܂��Ή��ł��邩�s�������������A���Ƃ��ׁX�ƑΉ��ł��Ă���B�ѐ�a�@�̃X�^�b�t20�����́A�e�X��J���Ȃ���@�l���̈�Ë@�ւœ����Ă���B
�@(4)���ʃ��n�r���e�[�V�����a�@
�@���C�㓖���͑O�C�̈�t���܂�3�l�̐��ł����������X��5F�a����2�l�ɔC�����悤�ɂȂ����B���a���͕w���𒆐S�ɉ^�c�͂ƂĂ��X���[�Y�ŃX�^�b�t�B�̗�V���悭�A�E��Ƃ��Ă̕��͋C���悭�A���S���A���K�ɓ����Ă���B
�@3�����{�ɂ͔ѐ�a�@����̊���10���l�Ǝ��ǂ������ꂽ�B
�@7���ɂ͏H�c�s�̐��Q�̂��߂ɐf�Âɍ���������������ʑ����a�@����̊��҂��ً}�ɐ������ꂽ�B
�@11���ɂ͕a������COVID-19�̃N���X�^�[�������A8�����x�̊��҂������������A��ꌎ�̌o�߂Ŏ��S�҂��o�����Ƃ��Ȃ��������B�X�^�b�t�����̗���ʃ`�[�����[�N������t�������ʂł���B���S�����B
�@(5)���͌����̌ߑO+���͌��N�N���j�b�N�A���ʑ����a�@�A��Ȓ��ʕa�@�̐f�Â����邽�߂����̓��͂Ɉ�C�ɑ��Z�ƂȂ����B�x�������p���ĉ��Ƃ��Ή����Ă���̂�����B�����A4���ȍ~���������S�������炸�x���͊J�����ɐZ���Ă���B
�@(6)�����͉��Ƃ��E��ł͊��}����Ă���(?)�悤�Ɋ�������B���̍ɂȂ��Ă̂��ƂŁA�Ђ�����������A�Ǝv���B
�@��������ӂ̕��X�Ɋ��ӂ��A���N�ɒ��ӂ���������Ɖʂ����Ă��������ƍl���Ă���B
12/28�i�j�܂�̂��������g�~��Ȃ��@ ���ʃ��n��p�[�@�@
3:00�N���A���N�I�����p�XPV-10�s���p���B�l�R���肵�Ĉ�w�����A�V���Ȃǃ`�F�b�N�B���w�A�f�[�^�ڍs�B8:30�Ɠ��ɓ���a�@�A�����A�{�ǂ݁A���̑��B�s���̊O�����o����RS�ᒆ�ʂ̎��@�ȂɁB13:00�a���Ή��A�V���@���ґΉ��B�Ǐ��B�V���`�F�b�N�A�f�[�^��19:30�A��A�[�H�A21:00�A�Q�B�����v��4978���B���ʃ��n��p�[�Ȃ�����ɍs���Ȃ��B�Â��ȔN���ɁB
2023�N�̏o�����̂܂Ƃ�(4) ���ۓI�j���[�X
�@�����ʐM�ДŁ@�H�c�@�V�������p�����Ă����������B
1�ʁ@�K�U�Ő퓬�����A����2���l��
�@10��7���A�p���X�`�i������K�U�������x�z����C�X�����g�D�n�}�X�̐퓬�����z�����Z�����E�Q�A������l���ɂ����B �n�}�X��ł�i����C�X���G���̓K�U�����n��N�U�B�a�@��w�Z�A���A�{�݂��U������K�U���̎��҂�2���l���ɁB�l��8���ȏ�̖�190���l�������������A����H���A�G�l���M�[�����R����l����@�������B 7���Ԃ̐퓬�x�~���ɐl������Ői�W�͂��������A�č��̋��ی������ō��A���S�ۏᗝ������@�\�����B�C�X���G�����̎��҂͖�1200�l�B
2�ʁ@�E�N���C�i�N�U2�N�ځA�푈������
�@��N2���Ɏn�܂������V�A�̐N�U�͒������̌��ʂ��B�ĉ��̕��틟�^����E�N���C�i��6���ɔ��]�U�����J�n�B�������A�틵���P����ԂɁB���͔��d���̋���_�������^����Q���B
3�ʁ@��J�����{�l���̕đ僊�[�O�{�ۑʼn��A2�x�ڂ̖��[MVP
4�ʁ@��FRB�����グ��~�B �ꎞ�~���~�܂炸
5�ʁ@�����̏K�ߕ����Ǝ�Ȃ�����3�I
6�ʁ@WHO���V�^�R���i�ً}���Ԑ錾�I��
7�ʁ@WBC�Ŏ��W���p���D��
8�ʁ@����A���荑�A�ŋK���Ɗ��p�̃��[�����c�_
9�ʁ@GDP���E��3�ʂ����{����h�C�c��
�@���ےʉ݊�� (IMF) �ɂ��ƁA ���N�̓��{�̖��ڍ��������Y(GDP) �̓h��
�x�[�X�Ő��E3�ʂ���4�ʂɓ]���A�h�C�c�ɋt�]����錩�ʂ��B �~���ɂ��h�����Z�̖ڌ����h�C�c�̕����㏸�����w�i�ɁB
10�ʁ@�k���N��ICBM���ˁA �R���q���ł��グ��
�@�嗤�Ԓe���~�T�C�� (ICBM)�u�ΐ�15�v�˂����{�̔r���I�o�ϐ���(E
EZ)�ɁB�ő̔R���^�́u�ΐ�1�v�����ˁB2�s�����R����@�q����11���u�����v�Ɣ��\���ꂽ�B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�Q�l�����@2022���E��10��j���[�X
�y1�ʁz�I�A�E�N���C�i�N��
�y2�ʁz�G���U�x�X��������(96��)
�y3�ʁz�؍��G������158�l���S
�y4�ʁz�J�^�[���@�v�t�J��
�y5�ʁz���ECOVID-19�@����6���l
�y6�ʁz�����}��100�h���˔j
�y7�ʁz�K��3����
�y8�ʁz���E�l��80���l
�y9�ʁz��C�s�s����
�y10�ʁz�}�X�N���A�c�C�b�^�[����
12/27(���j�܂�ϐ�Ȃ��@��lj�
�@�Q:10�N���B�l�R�Ή��A�k�R�ȂǁB8:50�Ɠ�����a�@�ɁA�����A���w�B11:00�a���Ή��B13:00��lj�A14:30�����J���t�@�����X�A���@���ҏ��u�B�V���`�F�b�N�A���́A���w���A19:30�A��A�[�H�A21:00�A�Q�B��5369���B�钷���Ƒ��A�H�B
2023�N�̏o�����̂܂Ƃ�(3) �����̃j���[�X
�@�����ʐM�ƑS���̉����V���Ђ̕ҏW�E�_���ӔC�ҁA�_������ǂ̕ӔC�҂炪
�I���N��10��j���[�X(�����ʐM�@�H�c�@�V��)�B
2023�N 10��j���[�X ������
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
1�ʁ@�����h���̗������A
�@ �����}�h���̃p�[�e�B�[�������B���{�h�t����̎�����̍X�R�A�W�c���̔C�ӂ̎����A�����Ĉ��{�h�A��K�h���������Ƒ�{�����ꂽ�B�����Ƌ��̊W�͌Â��āA����ɐV�������B���̐�i���͂ǂ��Ȃ��Ă���낤���H
2�ʁ@�W���j�[�Y�������̐����Q�ɔ�Q�̐����o
�@�̃W���j�[�쑽�쎁�ɂ�鐫���Q���ŋɂ߂ďd�v�ł��邪�A���ɂ͎��Ԃ������ł��Ă��Ȃ��B�Ȃ�����قǂ܂łɔ�Q�����������̂ɍ��N�܂ŕ\�ɏo�Ȃ������̂��H�H���̌�̕����Ă��A�ǂ�ł��悭�����ł��Ȃ��B
3�ʁ@�V�^�R���i��5�ނֈڍs�A�K���q����
4�ʁ@�����㏸����41�N�Ԃ�̐L��
5�ʁ@�����̉āA���ϋC�����ߋ��ō���
6�ʁ@������1�������������o�A �������A����~
7�ʁ@�����ꋳ��̉��U���ߐ���
8�ʁ@�����̓��䑏���������S8�^�C�g����Ɛ�
9�ʁ@�L����G7�T�~�b�g�A �[�����X�L�[������
10�ʁ@��_�^�C�K�[�X��38�N�Ԃ���{��
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�Q��
?��2022�N�̏\��j���[�X
�y�P�ʁz���{�������ꎀ�S
�y�Q�ʁz�m���ό��D���v����
�y3�ʁz�~��1�h��150�~�˔j
�y4�ʁz�����ꋳ��@������艻
�y5�ʁzCOVID-19�@����1��10���l
�y6�ʁz���C�h�~�m�A�t���X�R������
�y7�ʁz�ܗ։��E�A�g�D�ό�������ߕ�
�y8�ʁz�{��E�����Ők�x�U���A�V�����E��
�y9�ʁz�T�b�J�[�v�t���{��\16���A�싅�E�ő�J�A����A���X�ؘN��@
�y10�ʁz���䗳���@�ŔN���܊�
�y�ԊO�z
�k���ܗց@�~�G�ő����_��
�������@�{�s�A���l�N��P�W��
�R�Ώ����A�ʉ��o�X�Ɏ��c���ꎀ�S
�k�~�T�C�����ˑ������@
�R���E��������4630���~�닋�t
�Ă̍b�q���Ő���p�D���A���k�����@
����{�y���A�T�O�N
�ȂǂȂǁB
12/26�i�j�܂菬��ߌ�����@���ʕa�@�O���@���ҋ~�}�����@�@
2:20�N���B�{�ǂ݁A�f�[�^�����A�k�R�Ȃǂ������߂����B����Ȃ��B�T:30�R�S�~�W�Ϗ��ɁB�������������Č������B6:40�o�X�a�@�ɁB���ҋ�����ɂ̑i������B7:00-8:00�a���Ή��A8:45-12:40���ʕa�@�O���A���N�Ō�A���G�Ȃ��B13:00�~�}�O���֊���SF�������A14:30�A�@�A�����A�V�����́A�Ǐ����S�ɁB�a���Ή��B19:30�A��[�H�B21:00�A�Q�B��9286���B
2023�N�̏o�����̂܂Ƃ�(2) �H�c���Ɋ֘A����j���[�X
�@�H�c�@�V��Ђ��ǎ҂����W����2023�N�̏H�c���Ɋ֘A�̐[��10��j���[�X�����܂����B?
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
??1��:�����ŋL�^�I��J
�@�H�c�s�̎s�X�n�������A�a�@���~�}�f�Â��~����ȂǁA���R���҈Ђ�U�邢�A�Z���̓����D�����B
? 2��:�N�}�ُ�o�v�A�l�g��Q����
? 3��:�����ҏ��A�����39.2�x
? 4��:���|�m���A�l���̗������Ȃ���?
? 5��:���q�}���\���E��ؑI��p���ܗ֑�\��
? 6��:����s�̍ĊJ���r���Ɏ{�H�s��
? 7��:�H�c�`�A����13����Ɖ^�]�J�n?
? 8��:�H�c�s�̐l��33�N�Ԃ�30���l����
? 9��:�H�c�s�œ��ꍼ�\��Q�A�ߋ��ō�1��3600���~?
10��:1���Ĕ䗦58.2%
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�Q��
?���ߋ�3�N�̏\��j���[�X
�y2022�N�z
?(1)�~���n�X���O�����h�I�[�v��
?(2)�����A�L�^�I��J
?(3)�T�L�z�R�����f�r���[
?(4)�u���n�����̖~�x�v�u�єn���̖~�x�v�����`������Y�o�^
?(5)�H�c�̉čՂ�A3�N�Ԃ�ɊJ��
?(6)���ʑO���p�s���ߕ߁A�����k���^��
?(7)���k�J�܂�A�����11���l
?(8)�V�^�R���i�����ҁA�����v10���l������
?(9)�T�L�z�R���u��A�v
(10)�n�s�l�b�c������CS�i�o ??
�y2021�N�z
?(1)�����ސw�\��
?(2)�������A�\����
?(3)���N�`���ڎ�J�n
?(4)�ꕶ��ՌQ�A���E��Y��
?(5)�T�L�z�R����s�̔�
?(6)�R���i�����}�g��
?(7)���|�m��4�I
?(8)����Œ��C���t��
?(9)�������[�A�H�c�H�삯��
(10)�����ܗցE�p���A��������
�y2020�N�z
?(1)�����A��99��ɏA�C
?(2)�R���i�ЁA��ċx�Z��x�Ɨv����
?(3)�n��C�[�W�X�z���P��
?(4)�V�i��Ă̖��̂́u�T�L�z�R���v
?(5)�Ă̍s���A�����ݒ��~
?(6)�u���E�u���b�c�H�c��J2���i
?(7)����ƁE������Y���E
?(8)�R���i�����g��A�������ɉe��
?(9)�N�}�P���A�������̏������S
(10)�o�h�i���E���{�g�A�����ܗ֊m��
12/25�i���j���C��ɂށ@���N�N���j�b�N�@�@
2:00�N���B�k�R�Ȃǂ������߂����B����Ȃ��A�����A�ѐ�a�@�̃K���[�W�̓�����̐��ނ��邽�߂�7:50�Ɠ��ɓ���A�c���n�V�ƃX�R�b�v�����ĕa�@�ɁB���ɏ��Ⴓ��Ă���A��U��B9:00-11:30���N�N���j�b�N�A11:45�ѐ�a�@�B�f�[�^�����ȂǁB14:00-19:00�ѐ�a�@�Ζ��B���@���ґΉ��B�����ȂǓǏ��A�V���`�F�b�N�B19:30�A��A�[�H�B21:00�A�Q�B��7619���B�Ƃƌ��N���ő̒��s�ǁA�R���g���[�������ԂɊׂ����B���Ƃ��l�m�ꂸ�ɑΉ��ł������悪�v�������B
2023�N�̏o�����̂܂Ƃ�(1)�@�H�c�����A�����B���ہE�E�E
�@��N�̏o�������܂Ƃ߂�G�߂ƂȂ����B
�@���͂��̎������D���ł���B�V���𒆐S�Ƃ������f�B�A�͂������Ċe�E��10��j���[�X�Ƃ��ĎЉ�̏o�����Ȃǂ̂܂Ƃ߂����グ��B
�@���͖����̐����L�^�����Ă��āA�܁X�ɐ������Љ�̏o�����Ȃǂɂ��ăR�����g�������Ă��邪�A���̋L�^�ł͔N�Ԃ̓�������ՓI�Ɍ���邱�Ƃ͋��ł���B�����烁�f�B�A�̋L���͎Q�l�ɂȂ�B
�@���Ă̓��f�B�A�̋L�����Q�l�Ɏ����ōĕ]�����čĕҏW�����݂����������������A�ŋ߂͎��Ԃ��R�������̂悤�ȏC���͖����ƂȂ����B
�@���̂��߂ɋߔN�ł͐V���L�������̂܂܈��p���邱�Ƃ������Ȃ����B����ɑ��������̍l�����R�����g�Ƃ��ĕt�������邱�Ƃ�����B
�@����ɂ��Ă����̈�N�̒��Ő������o�������������Ȃ�����܂��v���o���Ȃ��悤�ɂȂ����B�����͂����Ă�����������������Ίe���ڂ͑N���Ɏv���o�����Ƃ��ł���B
�@������A����͔F�m�@�\��Q�ł͂Ȃ��A����ɔ����L����Q�͈̔́A�v���o���@�\�̒ቺ�̂��߂ł���B�����F�����邱�Ƃ��ł����B
�@�������Ԃ߂鎞���ł�����B
�@
12/24�i���j���g�܂������܂�~��@����5���
�@2:00�N���A�����̂��Ƃ��f�[�^�̍X�V�E�����A�R���s���[�^�[�֘A�Ǐ��A�V���`�F�b�N�B�k�R�ق��A�����B7:00-8:00����5��ځBNHK���W�I�ł͉��y�̐�B���j���_�Ɛi�ށB��҂͐l�����������グ���B���ł��ǂ��d�b���k�̗\��ł����������Z�w�`�̂��߂ɂȂ��BTV�ɂĊ��������B12:00�Ɠ��ɓ���a�@�ɁA���ԏ�����ꂸ�B������15:00-16:00�a���Ɩ��N���N�n�p�����A�_�H���́B19:00�A��A�[�H�A21:00�A�Q�B��9489������֘A�B�[�H���ɃP�[�L���o���B
�S�����Z�w�`���@�����ܗւ̉~�J�̎p��f�i�������f�b�g�q�[�g
�@NHK���W�I���j�̒���8:00�u���y�̐�v�A9:00�u���j���_�v�Ɛi�ށB��҂͍����͐l�������������グ���B10:00�u���ǂ��d�b���k�v�̗\��Ŗ��T�y���݂ɂ��Ă���̂����A�{���́u���ǂ��d�b���k�v�͑S�����Z�w�`�̂��߂ɂȂ������B
�@
�@TV�ɐ�ւ��Ċϐ킵���B���ɖړ��Ă̍��Z��I��Ȃǂ͂Ȃ��������A���Z���������͂��o�����đ���p�ɂ͖ڂ��䂫������B
�@�D�����̐���p��2��Ńg�b�v�ɗ�����4���p����2�ʂ̗����ىF����30�b�A3�ʂ̐_���w���ɂ�1��20�b�������Ă����B���̂܂ܓ����邩�ƂƎv���Ă������A�_���w���̃A���J�[�AC�J�����C�����͋����ǂ��グ�������A���Z��̃g���b�N��Ń��X�g100m�Ŏ�ʂ�D�����I�ȓW�J�ƂȂ����B
�@
�@�f���炵���������W�J���ꂽ�B
�@����1964�N(���a39)�����ܗւ̍ŏI���A�Q�l���łقƂ��TV�͌���Ȃ��������A�ŏI���̒j�q�}���\���͊ς��B�D���̓G�`�I�s�A�̃A�x�x�ł��������A�~�J�͍Ō�̍������Z��̃g���b�N��ŃC�M���X�̃q�[�g���[�I��ɔ����ꂽ���̂́A��3�ʂ̉h�����l�������B
�@���͍����̉w�`�����ē����ܗւ̍Ō�̃f�b�h�q�[�g�̃V�[�����v���o���A�~�J�̎��Ɠ��l�̊������o�����B
�@����p�̃A���J�[�̑I��͑傫�ȃV���b�N�����ł��낤���A�ޏ��̑�������h�ŁA�ޏ����ʂ����������͑傫�������B�������A1��20�b����ǂ��グ�A�ǂ�����C�J�����C���̑z��O�̎��v�́A�Ō�̃X�p�[�g�͋����ׂ����̂ł������B���͗��l���̂������B
�@
�@�����A�c�O�Ȃ��ƂɑS�����Z�w�`�������̎��s�ψ����24���A���N�̑���j���Ƃ��O���l���w���̋N�p���ŒZ������3�L����Ԃ݂̂ɐ�������Ɣ��\�����B�O���l���w���͂���܂ōŒ���1��i�j�q10Km�A���q6Km�������ċN�p�ł������A���N�̑���A���w���������̂͒j�q��2�悩5��A���q��3�悩4���3Km��ԂɌ����邱�ƂɂȂ����B
�@����̌���ɐ旧���A�s���{�����Z�̈�A���̗���W�҂Ɉӌ������߂�A���P�[�g�����{�����Ƃ���A���w���̋�Ԑ����ɉߔ������^�������A�Ƃ����B������ƊÂ��͂Ȃ����H�H
�@���͗D�ꂽ�I�肪���͓̂��R�Ǝv������A�O���l���w���̏o��l���̐����͂�ނȂ��Ƃ��Ă��A���̕����ɐ�����������͕̂s�����Ǝv���B
�@������A���I�ȏ�����W�J�����{���̊�������߂��ʂ����ɂ��̌��肪���\���ꂽ���ƂɁA���W�҂̔z���̂Ȃ������Ď���B
�@���ȋC������������B
12/23�i�y�j�܂�~���@�ϐ�10cm �@����4���
1:30�N���A�����̂��Ƃ��f�[�^�̍X�V�E�����A�R���s���[�^�[�֘A�Ǐ��A�k�R�ق��B
���������͋L�^�I���g�~��̗\��A��B���܂ߑS���I�ɑ����A�k�����ł�50cm���̐ϐႪ�\�z����Ă���B�H�c�s�����r�����B���N������A��N�͖����ł������B7:00-8:00����4��ځB�ꉞ�S�͈́B13:00�Ɠ��������A���͕a�@�ʼn߂����B�ۍ㐳�N���̏��a�̗��j�s�b�N�A�b�v�J�n�B19:00�A��A�[�H�B21:00�A�Q�B��9557���A����֘A�B
�G�߂̘b��(21)�@�Y�N��ɑ��镟�����@
�@���22���͒��ʃ��n�r���e�[�V�����a�@���������ł������B
�@COVID-19���s���2020�N�ȑO�͔N���ɂ͏H�c�n��̕a�@�֘A�{�݂𒆐S�Ƀz�e���̉����ŖY�N��Ȃ�ʔN����𗬑��Â���Ă������A����ȍ~�͊J�Â���Ă��Ȃ��B
�@���͖@�l�ɋΖ����Ă���38�N�ɂȂ邪�A�Y�N��ɏo��Ɓu���̔N�̂��Ƃ�Y��Ă��܂��v����ܑ̖����A�Ƃ������R�Ŗ@�l�̏H�c�n��̖Y�N��ɂ�1-2���Q�����Ȃ������l�Ɏv���B
�@�@���̎��͈�t�̔h�������肢���Ă����w�̈�ǂ̖Y�N�10��قǂ��肱����̏o�Ȃ͗���㌇�������Ƃ��o���Ȃ��������猋�\���Z�ł���A���̋L�������ł��܂����B
�@���̌�A���ʑ��������ɂȂ��Ă���̗l�q�͂킩��Ȃ��BCOVID-19�ȍ~�͑���Ɋe�a�@��{�݂��Ƃɏ����ȃC�x���g���͗l����Ă����l�ł���B
�@���N4�����璆�ʃ��n�r���e�[�V�����̏����ɂȂ��ď��߂Ă̔N���̉�ł���B���̕a�@�ł͖Y�N��̑���ɉ@���������s���Ă���A�Ƃ����B
�@�������ǂ�����p�ӂ���邩�킩��Ȃ����A��ʂ͏ۈ�́u�������ъ�v�A��ʂ��|�����{�b�g�́u�����o�v�A�O�ʂ́E�E�E�A�ȉ������A�u�H�c���܂�5Kg�v�A�u����Z�b�g�v�ȂǂƑ����Ă����B
�@���ǂ����i�i�̋��o�����߂��A�ڍוs���Ȃ̂Őh�q�����q�̃Z�b�g(�ܐ�~����)���\�{���o�����B
�@�����A���ɂƂ��ď��߂̍s���ŏڍוs���Ȃ̂�17:00����̒��I��ɏo�Ȃ����B��c���ʼn@�����S�E���̖��O�����������������Ƃ����������́B���̏�ZOOM�Ŋe�E��ɒ��p����A���I�҂����ɗ���A�Ƃ����`�ԁB�Ȃ��Ȃ��y�����ŁA���I�҂͎O�X�ߌ㓖�I�����i�i�����ɉ��ɗ��Ă����B
�@���͐������ł͉^�̂����j���A�Ǝ��F���Ă��邪�A���̂悤�ȃC�x���g�ł͉^�͂ƂĂ������B�哖���肵�Ċ�Ƃ����L���͂قƂ�ǂȂ��B
�@��������l�ł������B18:00�Ō�̂��������ł�������Ȃ��������Ƃ��m�F�������ɖ߂������A���I�҂͂��邱�ƂȂ���S�E�����y���݂ɂ��Ă������Ƃ��������A�����C���ŏI�����}�����B
12/22�i���j �~���@���g�ƍ~��@��Ȓ��ʕa�@�O���@�ϐ�7-8cm�@����3���
�@2:00�N���A�{���͊������~���B��������閾���������������Ȃ�B�ϐ�7-8cm�A����3��ځB�V�̂͌������Ȃ���C�����̏�łƂĂ��y�ɂȂ�B7:20Taxi�w���ɁB30���ȏォ�������B�W:11���܂��A8:50��Ȓ��ʕa�@�B�������~��A�����Ƃ�Taxi15:30Taxi�a�@�B�����ȂǁB17:00���n�a�@�������A�Ɠ�5���~���J�������B���������炸�B19:00�A��A����ؗ[�H�A21:00�A�Q�B������6507���B
�@��N2:40��d�A6:00�����B2F����_���}�X�g�[�u���낷�ۂɊK�i���݊O���\�t�g�ɓ]�|�A���������Ă����đ厖�Ɏ��炸�B
�G�߂̘b��(20)�@�~��2023�@���ɂ͑傫�Ȋ�т̓��@�M�q���E�J�{�`���������l�@
�@�{��23���͓~���B
�@�~����1�N�̂����œ��̏o�̎������ł��x���A���̓���̎������ł��������B����A�������邭�Ȃ邾���łȂ��A���̓����������X�ɗ͋����Ȃ��čs���B
�@�~�������k���ł͂��̓����u���z�̗͂��Ăї͂������ė�����v�Ƃ��ďj���B
�@�䂪���ł��A�Â��͓~����1�N�̎n�܂�̓������ƌ����B���̋C�����͂悭�킩��B
�@���ɂƂ��Ă͓~���͌��U�����傫�Ȋ�]�̓��ł�����B
�@���œ~�����d�v������̂��A�Ƃ����ƁA���̑����̍�Ƃ����\�������ʋ�����������B
�@���͉Ǝ����S�Ƃ��ĉƎ������֘A�͈���Ȃ��B��،������܂Ȃ��B�d���̐Έ䂳���邩��|���A������قƂ�ǂ��Ȃ��B���͋�����Ƃ������ł���A���S���Ă��镪��ɒ��r���[�Ȏ�`�������������B
�@����ɁA�O�d���A�Ƃ̃��C���e�i���X�͎����S���B�S�~�������S�ĒS���B�~����͑����̐Ⴉ�����S���B
�@����1:00-2:00���N�����A�U:30�O�ɏo����B
�@���̂��߂ɂT:00�߂��ɂȂ�ƒ��̍�Ƃ̊J�n�ł���B�Ηj�E���j�͉R���݂̓��A�T:30���ɏW�Ϗ��Ɍ������B10��������1�����܂ł͐^���Èł̒��̍�ƂɂȂ�B����̃w�b�h�����v�̓��̂��Ƃō�Ƃ�i�߂�B�����ē��H�ɉ����Ĉ�֎Ԃ܂��͂���ŏW�Ϗ��Ɍ��������A�Èł̒��ł͑��������邩���Ȃ��B
�@�S�@�\�������Ă��邽�߃S�~�p���͂�����Ɛh���B��50�������鏜���Ƃ��A����@��p����Ƃ͌������X�ɐh���Ȃ��Ă��Ă���B
�@�H�c�ł͓~���͐ϐ��ԂŌ}���A�����͂ƂĂ��������B�{�N�̓~���͐ϐႪ��⑽������͂���3��ڂł���B
�@���ۂ̋C����V��͓��Ǝ��ԂƂ͖�2�P���̃Y��������B������A�~�����}�����Ƃ͌����H�c�ł͂��ꂩ�炪�{�i�I�Ȑ�̋G�߂ł���B�@
�@����A��T�ԒP�ʂŌ���Ζ邪������̑����Ȃ�B���ꂪ���ɂ͂ƂĂ��������B
�@�~���Ƃ����u�J�{�`���Ə����v�A�u�M�q���C�v�ł���B
�@����̘d���̐Έ䂳���邩�炱�������G�߂̐����̐ߖڂ��������闿�������p�ӂ����B�M�d�ł���B�@
�@����̃X�g���X�ɔY�݁A�t��҂S���N�����������ɂƂ��āA�~���͈�N�̐V�����X�^�[�g���ł�����B
�@���ɂƂĂ͒g�����̎����͂܂��܂��������A�A���̂Ȃ��ɂ͂��������ԉ肪�p�ӂ���A���z�̉��b���A�J�Ԃ��n�߂�̂�����B
�@���͒g�����������ł���܂ł̓��X���A�����Ɛ�ƑΘb���Ȃ���ς��ĉ߂����B
12/21(�j�܂�ϐ�1?2cm�ߌォ�犦�g�~��@�@�@
2:00�N���B�����̂��Ƃ��A���@�C�I�����uHIMARI�v�̉��t�ɖ�����B12�A����ׂ��B���w���S�B8:30�Ɠ��ɓ���a�@�A���w�A11:00�a���Ή��B���@2���A13:00���҉Ƒ��ʒk�B�ēx�a���Ή��A���w�B19:30�A��[�H�B21:00�A�Q�B������4936���B
12/20�i���j�܂�@�ϐ�Ȃ��@
1:30�N���B�ق��A�قڂ����ƉƓ��������w��16���~�H�H�@�k�R�Ȃǂ������Ɖ߂����B8:30�Ɠ��ɓ���a�@�B�����A�V���`�F�b�N�B���͕ٓ��A14:30-16:30�a���J���t�@�A���ҏ��u�B19:00�A��[�H�B20:00�A�Q�B��4636���B
12/19�i�j�܂莞�ɐ���@�ϐ�Ucm�������ځ@���ʕa�@�O���@
1:30�N���A�l�R�ǂ���o�g���H�H���������̂�?? �����ǂ݁B�f�[�^�����A5:00�R�S�~�o��+��������2�܁A�������ځA�敾�����B6:40�o�X�A���Ԏ��ԓ��łӂ���B7:00-8:00�a���Ɩ��A�Ŏ��ꖼ�B8:45���ʕa�@�O��-12:50�A����̔��������Ĕ敾�B�����A15:07�Ŏ��X�Ɉꖼ�A19:00�A��A21:00�A�Q�B��11804���A�v�X���ɁA����̂��߁B
12/18�i���j�܂菬�ኦ�g�@���N�N���h�b�N�@�ϐ�Scm��������
�@2:20�N���A�k�R�A�����ǂ݁B�ϐ�Scm����ɔY�ނ����ƈꉝ���ő���ځB6:40�o�X�a�@�B7:00-8:00�a���A�_�H�������́A9:00-11;30���N�N���j�b�N�h�b�N13��+���ʔ���14���B11:45�a�@�ցB�����Ƃ��B14:00���@���ґΉ��B�ȍ~���w�A19:30�A��[�H�A20:40�A�Q�B��8742���B��N�p�p���Ă���I�����p�XPJ-20�̊O���o�͕������̏�
12/17�i���j�\���J�����g�I���@
�@2:00�N���A�{�ǂ݁A�k�R�B�\���J�����g�I���A���悢��~���R�����B�����@�A����p�Y�{���ȂǗp�ӁB�ߑO�͍��w�A�̂ǎ����B13:30�Ɠ��ɓ���a�@�B�Ǐ��A�f�[�^�����B�V���`�F�b�N�A�����B15:00�a���Ή��B�Ɠ��͖݂������A�����ȂǎZ�i�B���N�͓��V�g�̎d�o�炵���B18:00�A��A19:00�[�H�A21:00�A�Q�B��3614���B
���ĊJ��82�N(10) ���O�j(9)�@���ɊJ���
�@1940�N9��27���A���{�̓h�C�c�E�C�^���A�ƌ���ł����h���������������u�O���R�������v�ɒ����B���̓����ł́A���B�ɂ����Ă̓h�C�c�ƃC�^���A���A�A�W�A�ɂ����Ă͓��{���w���I�n�ʂɗ����Ƃ����F�������A����ɌR���E�o�ρE�����̑����ʂɂ킽�鑊�݉����W���z���ꂽ�B
�@�������������ɃA�����J�A�C�M���X���ԓx���d���������B
�@�����A���{�̓A�����J�Ƃ̖f�Ղ�����ŌR�������̑啔�����A�����J�Ɉˑ����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ɂ������B1940�N���ɂ́A�S�ނ�69.9%�A�Ζ�76.7%�A�@�B��66.2%���A�����J�Ɉˑ����Ă����B
�@�C�M���X�ł�1940�N11������̓A�����J�Ƃ̊ԂőΓ���Ɍ��������c���n�߂�ꂽ�B
�@���̂悤�ȓ����̒��œ��{�����オ��̂����Ԃ̊ԑ�ƂȂ�A����A�W�A�̎��������߂�K�v���͂�苭���Ȃ����B
�@����A���Č������~���ɐi�߂悤�ƍ����ł͑�O���߉q���t�����������B�������A���{�R�͓���A�W�A�ւ̐i�������s�B�����Ɏ���A�����J�́A�ݕē��{���Y�𓀌�����ƂƂ��ɁA���{�ɑ��Ă̐Ζ��A�o��S�ʋ֎~�A �C�M���X�E�I�����_������ɕ�����B
�@�߉q�͗��R��������Ē����嗤����̈ꕔ�P�ނ��Ă��A�����J�Ƃ̑Ë���}�낤�Ƃ�������R�̋��ۂɑ������������B�s���l�܂����߉q�́A����ȏ�̓w�͂������ɓ��t�𓊂��o�����B
�@���ɓV�c����喽�~�������͓̂����p�@�ł���B 10��16���ɐ�������������t�́A�푈�����Ɠ����ɁA�V�c�ɐ푈��̓���T��悤��������A���Č�����s���Đi�߂���j�ŃX�^�[�g�����B
�@�Ζ��̗A�����ł��Ȃ��Ȃ��������A���{�R��1���ɖ�1.2���g���̐Ζ�������Ă���A2�N�قǂŔ��~���͊�����ƌv�Z����Ă����B
�@������t�͑A�����J���̍ŏI������11�����Ƃ��A�Ë��_�����o���Ȃ����Ȃ畐�͍s�g��12�����{�ɊJ�n�ƌ��肵���B
�@�������A���{�����悤�Ƃ����Ë��Ă͏Ӊ�A�`���[�`���̔���������A�A�����J�͂����S�ʓI�ɋ��ۂ����͌���A12��8���ɕ��͍s�g�J�n�ƌ��肵���B
---------------------------------------------------------------------
�@�{�N12��8����82��ڂ̊J������}�����̂��@��ɁA����܂Œf�ГI�ł��������j�̗���������ł��������悤�Ɠ����푈�ȍ~�̗��j���ĕ������B
�@���{�����E�̒����̒��ŕK���ɓK�����悤�Ƃ��Ă������j�𗝉��ł������A2.26�������@�ɌR�����傫���䓪�����B��������e�����̂����{�Љ�ł������B
�@
�@�Ō�ɓo�ꂵ���L�[�p�[�\���̓����p�@�͎��Ɠ�������茧�ɂ��䂩��̂���l���ł���B�ނ̓`�L�A�]�_�Ȃǂ�ǂނƁA���i�E�����Ƃ��Ɍ����čɑ��Ƃ��đ��������l���ł͂Ȃ������Ǝv���B���̎��_�Ɏ����Ă͔q�������ނ��邱�ƂȂǍl����ꂸ�A����ɁA�ވȊO�̒N�������Ă����{�̍s�����͑傫���͕ς����Ȃ������A�Ǝv���B
�@���͋ɓ��ٔ��Ō����ӔC��F�߂����̎p����]���������B
�@���̓��{���~�������S�I�l���̈�l�A�ƕ]�����Ă���B
12/16�i�y�j�܂�[������\���J�@��N�����@
�@2:30�N���A�Ǐ��A�k�R�ق��B�V���`�F�b�N�A�����A���w�A�Ǐ��O���B�f�[�^�����A11:00�Ⴉ�����̂ǂ����p�ӁA12:00�������ق��ɍs���Ɠ��ɓ���A�a�@�ɁB�V�����͂ȂǁB16:00�a���Ή��A17:15�A��A19:00�[�H�B20:00�A���B������4879���B��N����ɗZ����g�p�B
���ĊJ��82�N(9) ���O�j(8)�@��ꎟ���E���(2)�@�����푈(�x�ߎ���)�Ŕ敾
�@���B���ς̂̂��ɁA���̓��{�͂��邸��ƁA�����嗤�ł̐�����g�債�Ă������̂�?? ?
�@���܂́u�����푈�v�ƌĂԂ��A�헪�����܂������Ȃ��܂ܒ����嗤�̉��n�։��n�ւƁA�����̒������܂Ƃ߂Ă����Ӊ��ǂ������čs�����B
�@1937�N(���a12�N)�ɂ������b�a���������N�����B���̌R���I�Փ˂��n�܂�Ƃ��āA�ꋓ�ɓ��{�R�ƒ����̏Ӊ�ΌR�ƖёR�Ƃ̐푈�ɔ��W���Ă����B
�@���̏����ɓ싞��s�E�Ƃ�������厖�����������B���̎����ł�30���l���s�E���ꂽ�Ƃ������Ă��邪�A���̋K�͂Ɋւ��Ă̒���͂܂��Ȃ��B�����A�싞�ȊO�̓y�n�ł����{�̌R�����A�����̐l���E�������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B
�@���{�R�͂�����������K�͂Ȑ푈�A�Ƃ��ɒ����Ԃ̎��v��ɂ��āA�܂������������Ă��Ȃ������B�����A���I�푈���킸��1�N�]��ŏI����}�������A���ꂩ���̂ɂ��Ẵm�E�n�E��������Ǝ����Ă��Ȃ������B
�@����ȏ�ɁA�������ɓ��{�́A����ȍL��ȓy�n�ő�K�͂Ȑ푈����邾���̍��͂��Ȃ������B����ł����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�����R�ɂ̓C�M���X�E�t�����X���͂ȃo�b�N�A�b�v������A���{�͎�������Ȃ������B�����ɏ��a�̓��{�������j�I�Ȗ�肪���݂��Ă����B
�@����̓��{�̔s�k�́A�키�O���猈�܂��Ă����Ƃ����Ă����B
�@�o�ϓI�ȃf�[�^�����Ƃɂ���A���{�ɓ��ꏟ���ڂ��Ȃ����Ƃ́A�J��O����R�̊��������͂悭�������Ă����B
�@����Ȑ푈���Ȃ�����Ă��܂����̂��B
�@���a14�N(1939�N)�ɁA���[���b�p�ł̓h�C�c�t�����X�A�C�M���X�A�\�r�G�g�̐푈���n�܂����B
�@���{�͓����u�O�������v���h�C�c�A�C�^���A�Ƃ̎O�ҊԂɌ��сA����Ƀ\�r�G�g�Ƃ͓��\�s�N��������ł����B���������`�œ��{�͍��ۓI�ȌǗ���������悤�Ƃ��Ă����B
�@�ދp��k�����D�܂Ȃ����{�̑g�D���A�q�g���[���̃h�C�c�̐�ʂɉߏ�Ɋ��҂��A�����c�邽�߂ɏ����ڂ̖R�����C�M���X�A�A�����J�Ƃ̐푈�Ɏ����ǂ�����ł��܂����B
�@�����ېV�ȍ~�A���{�̓C�M���X�̃o�b�N�A�b�v�ē����푈�A���I�푈�����������A�����푈�ł̓h�C�c�Ɠ������A�C�M���X�A�t�����X�ɑR�����B
�@���j�I����̒��ł͂��̂悤�ȍ��ۊW�̕ϑJ�͏��Ȃ��Ȃ��B
12/15�i���j�~�J�I���@��Ȓ��ʕa�@�@�@
1:20�N���A�ϐ�0cm�A�k�R�A�����ǂ݁B�R���݁A�������ݔp���B7:30Tax�w�ɁB8:11���܂��ő�ȁB��Ȃ͉���Taxi�B8:50�O���Ɩ��B15:30���艮�Ï��X�A�h�c�̒����w���B�o�R�a�@�B�����ȂǁB�V���`�F�b�N�Ɠ��́B19:30�A��A�[�H�A20:45�A�Q�B�����v��6692���B
���ĊJ��82�N(8) ���O�j(7)�@��ꎟ���E���(2)�@���B���i�������{���Ǘ���������
�@��2�����E���ɂȂ��闬����l���Ă����Ƃ��ɁA�u���B���ρv�������Ă͍l�����Ȃ��B
�@���B���ς́A���{�����I�푈�̌��ʁA���V�A������肤�����얞�B�S������邽�߂ɖ��B�ɒ��������Ă������R�̌R��(�֓��R)���A���{�ɂ͉��̂��Ƃ����Ȃ��ɁA�������B���x�z���Ă��������}�̒��w�njR���U�����Ēǂ������A�������{���{���ǔF���Ė��B���Ƃ��Č������� (1931~32�N)���ƁB
�@�v����ɁA���{�l�̓y�n�ł͂Ȃ��Ƃ���ɓ��{�l�����������Ă��܂����B���̂��Ƃ͐N���Ƃ������ʂ������Ă��邱�Ƃ͊m�����B
�@���̕��s��������̂����A�����̖��F�͂ǂ��Ȃ��Ă����̂��H�H���ɁA�A����������Ȃ��n��ł���B���̒n��Ɋe�������ꂼ��i�o���Ă��Ă����B
�@���V�A�l�A���{�l�A�C�M���X�l�A�����l�A�h�C�c�l�ƁA���܂��܂ȍ��̐l�Ԃ������悤�ɂ��Ă����X�����낤�Ƃ��Ă����B���̗��j�̍��Ղ͍�����A�Ȃǂɂ��̂܂c���Ă���炵���B
�@���{�͖��B�ɂ����̍��̐l�X�������ł�����̍��O�������낤�Ƃ����炵���B
�@���{�l�����B�ʼn�����낤�Ƃ��Ă����̂�??
�@�����A���{�͐��E�f�Ղ̂Ȃ����犮�S�ɕߏo���ꂽ�B
�@���{�����������ۖf�ՂƂ����̂��A�o�ς̎��R�ȗ̈�B�ɂ��낤�Ƃ������z���܂��������B���{���A���B���ɑ��Čf�������̃X���[�K���u�ܑ����a�v�͂��������Ӗ��������B���B���ς̓����҂����́A���ꂭ�炢�̃X�P�[���ōl���Ă����B
�@�������Ȃ���A���B�ɓƎ��̋�Ԃ����낤�Ƃ����Ƃ������Ƃ̉s���Η����n�܂���
�@�܂肻��܂Ő����̑卑�����鍑�ے����ɗ����āA���̂Ȃ��Ő����Ă������Ƃ��Ă���������A���������ŐV������Ԃ�����A���̂Ȃ��Ő����Ă������Ƃ����B
�@����܂ŁA �K���Ƃ����g�̎p���ō��ێЉ�ɑ��Ă������{���A�ˑR�A�Ǝ��̓�������������B�����̒����Ɖs���Η������A���{�������̕������������钧��ł������B
�@������A���B�����́A���l���S�̍��ێЉ�̔��������B
�@�����Ė��B���ς��A ���{�̌R���I�A�d�Ƃ��č��ۘA���ŒNjy����āA���B��
�����F����Ȃ��������߂ɁA���{�͍��ۘA�����痣�E�����B
�@���ہA���{���V���������������āA�V���������E�o�ϋ�Ԃ�����Ƃ����\�z�����������Ƃ��A���Ăɂ͋����Ȃ������B
�@���{�͌Ǘ��̓�����ݎn�߂����A�A���ʓI�ɑ�2�����E���Ɍ������čs���B
12/14�i�j�������g?
2:20�N���A�ϐ�0cm,�B�����ǂ݁B�k�R�ق��B8:30�Ɠ��ɓ���a�@�ցB�J�����_�[�^�сB�܂������A10:00���@���ґΉ��B11:00?12:00���@���Ғ��S�Ö��J�e�}���A�V���`�F�b�N�APDF���B�Ǐ������O���B14:00���ҍ̌��ȂǁB�Љ��쐬�B19:00�A��[�H�A20:30�A�Q�B�����v��5097���B??
���ĊJ��82�N(7) ���O�j(6)�@��ꎟ���E���(1)�@���E�����̕���
�@���a���N��1926�N����n�܂�B
�@��ꎟ���E��� (1918�N)�̓h�C�c�ƃI�[�X�g���A���A�C�M���X�A�t�����X�A���V�A�A�A�����J�Ɛ�����B���ɂ͓��{���Q�킵�Ă������̂́A������ƒ����̂ق��Ńh�C�c�Ɛ�������x���������A�폟���Ƃ��č��ە���ɏ��҂��ꂽ�B
��ꎟ���E���̉e���͑傫�������B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
(1)18���I���瑱���Ă����A���[���b�p�嗤���S�̐��E����������B
(2)�C�M���X�̎x�z�̗͂뗎�B
(3)4�鍑�A���Ȃ킿�A�h�C�c�鍑�A�I�[�X�g���A�E�n���K���[��d�鍑�A�g���R�鍑�A���V�A�鍑�̕���B
(4)�����鍑�̌�ɐV���ɍ�������K�v���������B
(5)�x���T�C����c�ŁA���ۘA��������ꂽ�B
�@���ۘA���͍��ێЉ�̑傫�Ȗ��́A�S�����J�̏�Řb�������Ō��߂悤�Ƃ�����|�ł������B�����푈���Ȃ����E�ɂ��悤�Ƃ������z���f�����B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
�@���{�������ېV�ȗ��A�����Ɛ������Ă��ꂽ���Ƃ̔w�i�ɂ̓C�M���X�̈��|�I�Ȏx�z�͂��������B�C�M���X���̍��ۓI�Ȍo�ς̗��ʂ����������炱���A���{�͏��߂Čo�ϓI�Ɏ����ł����B
�@���{�͍��Â���̂��߂̎�����A�푈�̂��߂̎������A�C�M���X���璲�B�����B���p����(1902�N)��w�i�ɃC�M���X�͂��܂��܂Ȍ`�œ��{���T�|�[�g���A���{�͓��I�푈�ɏ����ł����B
�@�Ƃ��낪�A��ꎟ���E���ŃC�M���X���͂��������B
�@����Ȓ��A���E�勰�Q���������E�o�ς͈ޏk�����B���̌��ʂƂ��ē��{�͖����ȗ��������Ă����o�ϓI��������ꂽ�B����܂ł́A���R�f�Ղ�O��Ƃ��������ł͓��{�͐����Ă����Ȃ��B���{�͊��S�ɔ����ǂ����ԂɊׂ����B
�@�ǂ�����H�H�B���̂Ȃ��ŏo����̓������B���������B
12/13�i���j�܂�@���J
1:30�N���A�����ǂ݁B�Ǐ��B�k�R�ق����w�B8:50�Ɠ��ɓ���a�@�A�ϐ�0cm�A�ߑO���w�B13:00�a���Ή��A�a���J���t�@�Ȃ��B15:00���@���ҏ��u�B19:00�A��A�[�H�A21:00�A�Q�B�����v��4738���B
���ĊJ��82�N(6) ���O�j(5)�@���I�푈(2)�@���N�����Ɏ���
�@���I�푈�͔��X�̏����ŁA�����ƒ������Ă�������{�ɏ����ڂ͂Ȃ������Ƃ����B�o�ϓI�ɂ����E���Ă����B�������A���{���o���`�b�N�͑�����ł������Ƃɂ�胍�V�A�͑����Ɍ`���t�]���N����i�������Ȃ�A���ۂ��Ă������{�Ƃ̍u�a�������ꂽ�B
�@���I�푈�͏��߂āu���l�̍��ɔl�����߂ď������v�A������������I�ȏo�����ł��������B18���I�A�鍑��`�̎���ɂ́u�L�F�l��͔��l�ɏ��ĂȂ��v�A�Ƃ����v�����݂�����A�u���l�͐��E�̎x�z�ҁv�ƐM�����Ă����B
�@�����ɁA���I�푈�ɏ��������ƂŁA���{�l�͎��������̍������������ƌ�������B
�@���I�푈��5�N�A1910�N(����43�N)�ɓ��{�͒��N�����A���{�����N�����������̗̓y�ɂ����B
�@���{�̊�Ƃ⊯�������N�����D�������A�ꉞ�̐��Ƃ��Ă͕����Ƃ����`���Ƃ��Ă�������A���N������ׂ����Ƃ͂Ȃ��A����ɁA����œ��H�Ԃ�S���A���d���A�w�Z�Ȃǂ̎Љ�C���t���̐�����ϋɓI�ɂ����Ȃ����B�Ȃɂ���A����E��킪�I�����A���{�̒��N�x�z�ɏI�~�����ł��ꂽ�Ƃ��ɁA ���Z�����Ă݂���A���{���͑啝�ȐԎ��������B
�@���������x�z����A����͗_�߂�ꂽ���Ƃł͂Ȃ��B�������A���{�l�͓Ɨ������ێ����邽�߂Ɂu���N���������V�A�⒆���ɓn���킯�ɂ͂����Ȃ������v�B������N�̐l�������A���͂ō�������Ă����Ζ��͂Ȃ������̂����A���̗͂��ӎu���Ȃ������B
�@�Ƃɂ������{�͓Ɨ����Ƃ��Đ����c�邽�߂ɒ��N�������Ȃ�Ƃ��Ă��ێ����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B
�@���N�����̂��̌�
�@1897�N����1910�N�܂ł͑�ؒ鍑�������ꂵ�Ă������A1910�N����́u�؍������v�ɂ����{�̓������ƂȂ����B
�@1945�N�̑���E���̏I���ƂƂ��ɓ��{�����N����P�ށB���̌�A���N�����̓����ɏ��o�����̂��A�A�������̃\�A�ƃA�����J�B�k��38�x�������ɁA�k�����\�A���A�쑤���A�����J����̂����B
�@1948�N8��15���A�����ӂ��錾���A38�x�����쑤�Ɂu��ؖ����v�����������B���N9��9���A���������u�k���N�v�̐�����錾�B
�@1950�N6��25���A�k���N���˔@�k��38�x�����z���ē쉺���J�n�B���N�푈���n�܂����B?
�@�؍��ɂ͓��{�ɒ��݂��Ă����A�����J���������A���ɖk���N�ɂ͒��������ʂ̐퓬�������ꍞ�݁A�퓬���������B
�@
�@���݂������͐펞���ɂ���B
�@�䂪���ɂƂ��Ē��N�����̕��a�͍��ł��������̈�ł���B
12/12�i�j�����~�J�̂�����@���Ҏ����@���ʕa�@�O���@�@
�@1:43�N���A���Ҏ����ɂċN���A�����`�F�b�N�ȂǁB5:30�R���ݏ����A�J�ɂĒ�o�Ȃ��B�U:00Taxi�a�@���S�f�f���쐬�A�a�����ґΉ��B8:45-13:00���ʕa�@�O���B�Љ��쐬�A�z�㉮�N�����āA�敾�����B�����A�a���Ή��A�Ǐ��A19:30�A��A�[�H�A20:45�A�Q�B�����v��6297���B
���ĊJ��82�N(5) ���O�j(4)�@���I�푈(1)�@�܂������N�������@�ߎS�Ȑ푈�ł�����
�@�����푈(1894�N-1895�N)�ɑ����� ���I�푈(1904�N�|1905�N)���������B���̐푈�����͒��N�����ł������B
�@���{�͓����푈�Œ���(����)�N���牟���Ԃ������A���x�̓��V�A���A���B���璩�N�Ɍ������Ă����B
�@���V�A�����N�������Ƃ��Ă��܂�����A���{�͂ƂĂ��Ɨ������Ȃ��B���������̎��_�ŁA���{�����V�A�Ɛ푈�����Ă��Ȃ���A���N�����̓��V�A�̂ɂȂ��Ă������낤���A���{�����V�A�̑����ɂȂ��Ă������낤�B
�@���ۂɁA�|�[�����h��t�B�������h�Ƃ������A���[���b�p�Ń��V�A�ƍ�����ڂ��Ă������́A�݂�ȕ������ꂽ��A�����ɂ��ꂽ�肵�Ă����B
�@������A���{���Ɨ���ۂƂ��Ƃ���A����V�A�̓쉺��h���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B
�@���m�̍��́A�ЂƂ��܂���Ȃ����{��������Ǝv���Ă����B
�@���V�A�͓����A�C�M���X�̐A���n�ł���C���h���_���Ă�������C�M���X�Ɖs���Η����Ă����B
�@�C�M���X�Ɠ��{�����p����(1902�N)�����сA���V�A�Ɛ�����̂����I�푈�������B���ڐ�����͓̂��{�ł��������A�C�M���X�͂��܂��܂Ȍ`�ŁA���{���T�|�[�g�����B�卑���V�A��ɔߎS�Ȑ푈�ƂȂ����B���{�͍��͂�100%���o�����Ă��܂������A�Ȃ�Ƃ����{�̓��V�A�ɏ������B�킢���������Ă�����A���{�͊m���ɔs�ꂽ���Ƃ��낤�B
�@�|�[�c�}�X�u�a��c
�@���V�A�̖��F�E���N����̓P���Ƃ������{�������������I�푈���͂��߂��ڕW���������A�V���Ȍ��v���l�����ċ����̒��ԓ�����ʂ������B���V�A���͔������x�����Ȃ��̍��ӂ���{������t�����B
�@�u�a���e�̍��q�́A�ȉ��̒ʂ�ł���B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
(1)���{�̒��N�����ɉ�����D�z����F�߂�B
(2)���I�����̌R���́A�S���x�����������Ė��F����P�ނ���B
(3)���V�A�͊����̖k��50�x�ȓ�̗̓y���i�v�ɓ��{�֏��n����B
(4)���V�A�͓����S���̓��A�����|���t�Ԃ̓얞�F�x���ƁA�t���n�̒Y�z�̑d�،�����{�֏��n����B
(5)���V�A�͊֓��B�i�����E��A���܂ޗɓ�������[���j�̑d�،�����{�֏��n����B
(6)���V�A�͉��C�B���݂̋��ƌ�����{�l�ɗ^����B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
�@���V�A�ł͐푈�p���̎咣�����Ȃ��Ȃ������B���{�͔������̕����Ő��_�̕s�������܂������A�����Ƃ�1905�N10���ɔ�y���A���������B
12/11�i���j �܂�[������~�J�@���N�N���j�b�N�@�z��Ȏ�f�@�@
1:20�N���A�~��0cm�B�����ǂ݁B6:40�o�X�a�@�B�V���x�����B7:00-8:50�a���Ɩ��A9:00-11:30���N�N���j�b�N�h�b�N�Ɩ��A14��+��������15���B11:40�a�@�A�z���f�Y��ēx���ʕa�@�B13:00-19:00�Ζ��A���@���ґΉ��B19:30�A��A�[�H�A20:30�A���B�������v��7867���B
���ĊJ��82�N(4) ���O�j(3)�@�����푈(2)�@���֏��Œ��N�Ɨ��������
�@�����A�����͎������ӂ�ɂ���A���{���͂邩�R���͋ߑ�I�ł������B������A���m�̍��́A�ЂƂ��܂���Ȃ����{��������Ǝv���Ă����B
�@�����A�����͓��{�Ƃ������āA�����ېV�̔@���̋ߑ㉻���v�������Ȃ��Ă��Ȃ������B�v����ɒ����̕����́A�R���⏫�R�̎蕺���W�߂ŁA���̂��߂ɐ키�Ƃ����ӎ����w�ǂȂ������B
�@����A���{�ɂ͖����ېV�����������G�l���M�[���[�����Ă��āA�Ɨ�����낤�A�Ƃ����ӎ��E�C�^�������S�̂ɐZ�����Ă����B
�@�����������Ƃ͌���I�Ɉ�����B
�@���̍����A�n�R���̓��{�ɏ����������炵���A�Ƃ���Ă���B
�@�����ԂɌ��ꂽ�u�a��A���֏��ł���B
�@1895�N4��17���A���ւœ��{�S���ɓ������E�����@���Ɛ����S�������͂̊ԂŒ������ꂽ�A�����푈�̍u�a���B�����ł͔n�֏��ƌĂԁB
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
(1)���͒��N�̓Ɨ������F����i�@�匠�̕����j�B
(2)���͗ɓ������A��p�A�O�Ώ�������{�Ɋ�������B
(3)����2�����̔���������{�Ɏx�����B
(4)�����C�D���K��j�����A�V���Ȓʏ������������B
(5)�J�`��E�J�s��ł̊O����Ƃɂ��H��o�c�𐳎��ɔF�߂�B
(6)�g�q�]�i���]�����j�̍q�s����F�߁A���s�E�d�c�E�h�B�E�Y�B���J�s�E�J�`��Ƃ���B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�@��������̂���̍��ێЉ�ł́A�푈�͑厖�ȊO����i�������B
�@���̎�i���s�g�ł��Ȃ����́A���ێЉ�̂Ȃ��Ő����c��Ȃ��������A�A���n�ɂ���Ă��d�����Ȃ������B
�@���{�͈ېV�ȍ~�A�푈�Ƃ����O����i���̂��悤���������ēw�͂ɓw�͂��d�˂����ʂ������푈�̏����ł������B
�@�������̂悤�ȏ������Ȃ��A����̗�������ɓI�ɑ����Ă�����A�䂪�����̔z���ɉ���ߎS�ȐA���n�ɂȂ��Ă����\���������B
�@�������I����ēˑR�������܂ꂽ�A�c������܂鐢�E�̂Ȃ��ŁA�Ȃ�Ƃ���
������낤�Ƃ����w�͂̌��ʂƂ��Ăɐ푈���������B�����ď��������ƌ������ƁB
�@�����푈�̏������Ȃ�����̓��{�͂Ȃ����A���R�������܂�Ă��Ȃ������B
12/10�i���j�܂莞�ɐ���@
�@2:00�N���A�����ǂݓ��W�X�Ə����BPDF�����ށA���W�I�[��ւ�MP3�f�[�^���B2F�B9:00�O�d���A�K���[�W�|���A���|�p�x�������A�_��A�d���_������A�Ԃ̐��A�U���p�z�[�X�d�����B����ŊO�d���̑啔���I���B11:00������ɍs���Ɠ��ɓ���a�@�A���҂͗��������Ă���B16:00�A��A19:00�[�H�A20:30�A���B�����v��4932���B
��N�͏���@�����A���N�͐�T�ς݁B
���ĊJ��82�N(3) ���O�j(2)�@�����푈(1)�@�Ȃ����{�ƒ������푈?? �d�v�ł��������N����
�@�����ɂȂ��ċߑ㉻�H�����~���ꂽ�Ƃ͂����A�����̐����͋ꂵ���A�푈������������B
�@�������Ǝ��̂��A���{�ƎF���A���B�Ƃ�����C�푈�̌��ʂłł������̂ŁA1877�N(����10�N)�ɂ́A�ߑ㉻�ɕs�������m�������̔����A�u����푈�v���������B
�@���̌���A�u ���������v�Ƃ��A �u���g�R�����v (�Ƃ���1884�N����17�N)�Ƃ������傫�Ȗ\���ƁA����ɂ������鋭���I�Ȑ����A���Y�{�s�Ƃ��������Ȃ܂������������������B
�@�ېV�ɂƂ��Ȃ������̍������炽����10�N�A�����푈�ō��x�͒����Ɛ�����B
�@���{�͂Ȃ������Ɛ푈���Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂��B
�@���{���������A���̂���ꐶ�����ߑ㉻���悤�Ƃ��Ă����B
�@
�@�ߑ㉻�Ɏ��g��ł��钆���Ɠ��{���A���N�������߂����ďՓ˂������ʂ������푈�ł������B
�@�����A
---------------------------------------------------------------------
�@(1)�����́A���N�� �u�����v�ƌ��Ă����B
�@(2)���N���A�����̐����╶�������̂܂�����A�����̐������ɂ������āu�Ɨ��v���Ƃ����p�����Ƃ��Ă����B
�@(3)���{�́A���N���u�Ɨ����v�ł���Ƃ���������Ƃ��Ă����B
---------------------------------------------------------------------
�@���{���Ɨ����Ƃ��Ă���Ă�����Œ��N�����������́u�����v�ɂ��邱�Ƃ́A�Ƃ��Ă��댯�Ȃ��Ƃł������B
�@���͖̏{���I�ɁA�����ς���Ă��Ȃ��B
�@1950�N�ɐ��������N�푈���A�k���N�������ƃ\�r�G�g�Ƃ������Y���̎x�z���ɂ����ꂽ��A���{��h�q�ł��Ȃ��ƃ}�b�J�[�T�[�͕K���Ŗk���N�R�̐i�U��h�����B
�@�v����ɁA�����푈�͒��N��������{�̐��͔͈͂ɂ������߂ɐ�����A�Ƃ������ƁB
12/9�i�y�j�܂莞�X����ߌ�~�J�@�Ɠ��̓]���^
1:30�N���A�{�ǂ݁A�v�`�Ή��A��w�����ǂ݂ȂǁB�ߑO�̓_���A�̌s�ْf�����A�܋l�A�O�����I���ƁB���҂͗��������Ă���炵���a�@�͌��B�V���`�F�b�N�A���w�A�{�ǂ݁A�����ȂǁB�ߌ���قړ��l�B�Ǐ��O���̌ߌ�B19:00�[�H�A20:45�A�Q�B�قƂ�Ǖ��s�����B�����v��6024���B
���ĊJ��82�N(2) ���O�j(1)�@���j���w�ђ����Ƃ�������
�@�ŋ߁A�j���������ɂ�����鎖�Ƃ��Ă��g�߂Ɋ����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă��Ă���B���d�˂��������H�H
�@���j�́A���Ă͎����Ƃ͉������A�ʐ��E�ɐ������ǂ��ł��������ۂȂA���j�͂����̔N�\�݂����ɂ܂Ƃ߂���A���܂����m���̐ςݏd�˂ɉ߂��Ȃ��A�Ƃ����悤�ɑ����Ă������Ƃ�����B���Ɋw������͂����ł������B
�@�ł�����Ȃ̂͗��j�ł͂Ȃ����ƂɋC�Â����̂͂����ƌ�̂��Ƃł���B
�@�j�����A�����̐��Ȋ��o�Ƃ����̂��A�����������Ă����̂ɊW���Ă���̐S�Ȃ��ƂƂ��Ċ�������悤�ɂȂ��Ă��Ă���B
�@�ǂ����āA�����������ɂ��āA�����������z�����Ă�悤�ɂȂ����̂��A���̂��Ƃ�������Ƃ������A���Ȃ��Ƃ��O���Ȃ���c�߂�悤�ɂȂ��Ă����B������ƒx�߂����悤�Ɏv���B
�@���j�̔w�i�ɂȂ��Ă���A���̖ʂ����̖ʂ��܂ߔw�i�S�̂������悤�ɂȂ������ƁA�����������ł���Ƃ������o�̔w�i���ׂĂ����j�̗���̌��ʂł���̂��A�Ƃ������Ƃɂ��C�Â����B
�@���j�͂����̔N�\�݂����ȁA���܂����m�������ł͂Ȃ��B����Ȃ̗��j����Ȃ��B
�@���j��ɂ����ɂ����l�����A�����Ă����l�����Ƃ����̂́A���ǂ��Ɠ����l�Ԃ��Ƃ������ƁB�܂�����ɒu�������B
�@���j��ł��Ắu�ǂ����Ɓv�܂��́u�Ƃ�ł��Ȃ��v���Ƃ������l�������A���Ƃ܂����������l�ԁB��{���y�������A������������l�ȂƎv���B
�@���Ɠ����悤�ɁA�����Ȃ��ƂŊ��A�߂���A������Ƃ������Ƃɏ�������A�l����������A����ꂽ�肵���l�����A�ւ荂�����낤�Ƃ��Ȃ���A�ڂ������Ƃ����Đ�������Ȃ��������l�����A�Ȃ̂��Ƃ������Ƃ��ŋߋ����ӎ�����B
�@���ꂪ�A����������A�˔\�̗L���A�Љ�I����A�u����Ă��闧��Ȃǂɂ���ċ����C������Ă���Ƃ������ƁB
�@�]��������A���a����ԑ厖���Ǝv���Ă���l�X�����āA���̏�ɂ�����ǂ��Ȃ������킩��Ȃ��B
�@
�@�����A�Ƃ������A���������ɒ��ڂ��������Ƃ��āA���a�́u���j�v���l�������Ǝv���B�ƌ����Ă��l����ׂ����Ƃ͑�������B
�@���ʁA���{���֗^�����ΊO�I�푈�ɓI���i���Č������Ă݂����B
12/8�i���j �����m�푈�J����@�������@��Ȓ��ʊO���@
�@1:50�N���A�{�ǂݑ������̔@���A6:00�ƒ�S�~�A�����ƂQ�ܒ�o�B7:30Taxi�w�ɁA8:11���܂��B8:50��Ȓ��ʕa�@�O���B��ȏH�c��Taxi�B15:20�w���璼�A�a�@�ցA�a���Ή��A�����A�V���`�F�b�N�A19:15�A��A20:30�A�Q�B�����v��7214���B��N11���d�q�J���e�Ɉڍs�A�Ȃ�Ƃ��Ή��ł��������т������B
���ĊJ��82�N(1) �����m�푈�Ƃ͈�̂Ȃ����̂��H�H���ɂ͂܂�������Ȃ�
�@�{���͑����m�푈�J��̓��ł���B
�@�����炿�傤��82�N�O��1941�N12��8�����W�I����^��p���U���������m�푈���n�܂������Ƃ���B���ۂɂ́A�^��p��2���ԑO�ɓ���Ń}���[�����㗤���J�n����Ă����B
�@��P�U���̐����͍��������g�������B
�@���҂̉�ژ^�Ȃǂ�����ƁA�����䂪���́uABCD��͖ԁv�ƌ�����ŌR���A�f�ՂȂǔ����ǂ���ɂ���o�ς͍������Ă������A�����ł��j��A�ǖʂ�ς���؊|�ɂȂ�A�Ƒ����̐l���v�����_�����g�����͎̂����������炵���B�����A�����V�����͂��߂Ƃ��郁�f�B�A�������ɓK���ȏ������Ă����̂��͋^��ł���B
�@���͏I��̔N�ɐ��܂ꂽ�B���a�̗��j�͉䂪���ɂƂ��ē����̎����ł������B���͏��a�̗��j���A����E���𒆉��ɒu���āA��͂Ȃ�������ł��邪�A�J�팈��Ɏ����I�������ʂ������L�[�p�[�\���̑��݂����܂��Ɍ����Ȃ��B
�@�u�����m�푈�Ƃ͂����������������̂��v�A�J���82�N�̌��������ꂽ�킯�����A�����ɉ�X���{�l�͂��̖₢�ɂ�����Ƃ����������o���Ă��Ȃ��悤�Ɏv����B
�@���N8��15���ɍs����I��L�O���̎��T�B
�@8:00�̎���Ƌ��ɉ��ł͈�Ăɖٓ��������B����́u���������i�v�ł���B�������N�S�̒��ő�풆�ɓ��{���x���������̕��X�A�]���ɂȂ�ꂽ300���l���̌��Ɉ����̈ӂƊ��ӂ̈ӂ�����Ă���B
�@�������A���͂ǂ��ɂ������l����Ɉ�a�����o����B
�@�L�����a�L�O�����ɂ��錴�����v�҈ԗ��ɋL����Ă���u���炩�ɖ����ĉ������B �߂��͌J��Ԃ��܂��ʂ���v�A�Ƃ����蕶�� ����i�������̂��A�悭�킩��Ȃ��B ���̕��Ɏ��͂Ȃ��B�J��̉ΊW������͓̂��{�ł��������A ���G�ȍ��ۏ�̒��A����������Ȃ������悤�Ɏd�������͕̂č��ł���A�č��͌����A�����ʎE�C�Ȃǐl���ɑ���߂��J��Ԃ����B�ɓ��ٔ��ł͓��{�͑S�Ă̍߂킹��ꂽ�B
�@�����m�푈�����ۂɂǂ����ĒN���ςɎv��Ȃ��̂��낤���B
�@���82�N�A�����m�푈�͗l�X�Ɍ���Ă����B
�@���������Ԃ���ǂB�������A���̖ڂ��猩�āA�����m�푈��{���I�ɑ��̂Ƃ��Đ[�������������ɏ��荇���Ă��Ȃ��B?
�@�u���̐푈�Ƃ͉��ł������̂��A�ǂ����Ďn�܂��āA�ǂ����ĕ������̂��H�H�v�A���͂��܂��ɔ[���ł��錋�_�������Ă��Ȃ��B
12/7�i�j�܂莞�܍~�J�@�_���A���������I���@�Ɠ���w��f
�@1:30�N���A�k�R�A�����E�摜�E�^���f�[�^�̐����E�����ȂǁB7:30��d���A�_���A�������ށA�����̂��ߔ��ɁB8:30�Ɠ��ɓ���a�@�A�����A10:00�Ɠ���w��f�A���Ȃ������炵���B11:00�a���Ή��A�ߌ�����@���u�B�����A�V���A�����ǂ݂ȂǑ����B19:00�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B�����v��5977���B
�^�T�v�������g�́u��t��85%�ȏオ����!!!�v�̍L���ɋ���(�R)�@���{�l�̃T�v�������g���p��
���{�l�̃T�v�������g���p���͒j��21.7���A����28.3���ł��邱�Ƃ����J��2019�N ����������b�����v(2020�N08��)�ł��߂��ꂽ�B
�@���͊O�����҂̎��Ԃ��猩�āA�V���L���̔h�肳���猩�Ă����Ƒ������̂Ǝv���Ă������A�ӊO�Ə��Ȃ����S�����B
�@���͑̕����ڂɂ킽��B
�@�����͑S���̐��ыy�ѐ��ш���ΏۂƂ����B�ڍׂ�2019�N ����������b�����̊T���i�����J���ȁj�Ɏ������B
�@�����͍�����������ɂ��A���N�����̑Ώۂ�301.334���тƂ�������Ȃ��̂ł���B
�@�ȉ��ɊT�v���������B
�@�u�L�i�җ��v�F�Ȃ�炩�̏Ǐ������302.5�l/1000�l�������B���ʂɂ݂�ƒj��270.8�A����332.1�ŏ����������A�N��ʂł�10�`19��157.1�ōŒ�ŁA�N������Ȃ�ɏ]���㏸���A80�Έȏ�ł�511.0�ł������B
�@�u�Ǐ�̎�ށv�Ƃ��ẮA�j���͍��ɂ�91.2��������i57.2�j�B�����͌����肪113.8�����Ɂi113.3�j���ߒɁi69.9�j���̂����邢�i54.5�j�����Ɂi50.6�j�B
�@�u�T�v�������g�̐ێ�v�́A60��j���A50�㏗�����ő��B
�@�T�v�������g�̂悤�Ȍ��N�H�i��ێ悵�Ă���l�̊����́A�j��21.7���A����28.3���ŁA�N��ʂł́A�j����60�`69��28.1���ōő��A������50�`59��37.6���ōő��������B
(�T�v�������g�̂悤�Ȍ��N�H�i��ێ悵�Ă���l�̊��� ? �ӊO�ƑS����ɂ킽���Ă���)
�@(�Q�l)�@�č�CDC�̃f�[�^
�@�Љ�ꂽ�_����60�Έȏ�̕o��̏������T�v���ɂ���Ăǂ̂悤�ȗL�v�E�s���v�����邩�ׂ����̂ŕo��̏���38.772�l��ǐՒ����������́B�������A���͘_���̓��e���`�F�b�N���Ă��Ȃ��B���Љ���Ɏ~�߂�B
27���̏�����4��ވȏ�̃T�v�������g�p���Ă���
����ł���T�v���̓J���V�E���E�}���`�r�^�~���E�r�^�~��C�E�r�^�~��E����������
�}���`�r�^�~���͎��S���X�N��2.4�����������Ă���
�}�O�l�V�E���͎��S���X�N��3.6�����������Ă���
�t�_�͎��S���X�N��5.9�����������Ă���
���͎��S���X�N��18�����������Ă���
�@�A�����J�͈�Ô�ƂĂ����z�ł���B���̂��ߌ��N�ێ��E�G�C�W���O�P�A�ړI�ŃT�v�������y���Ă���B�č��ł͐��{�n�̋@�ւ��T�v�������g�͌��ʂ��Ȃ������łȂ��A�댯�ł���Ƃ��Ă���B
�@���_
�@�T�v�������g�ɂ͌��ʂ��Ȋw�I�ɏؖ�����Ă��Ȃ��ꍇ�����邽�߁A����҂͎��g�̌��N�ڕW��j�[�Y�ɍ��������i��I�ԍۂɒ��ӂ��K�v�B��t����ƂƂ̑��k��ʂ��Đێ���������邱�Ƃ���B
12/6�i���j�܂�~�J�@Web�u����uCOVID-19�ƃC���t���G���U�v
�@1:15�N���A�����ǂ݁B�Ȃ����t�@�C�g�N�����v�`�ƃO�_�O�_�Ɖ߂����B�{�C���[�̐������ǂށB5:00�����炢���̃y�[�X�ɖ߂����B���w���S�B8:00�_���A�����@��o���Ή��B11:00�o�X�ɂĕa�@�A�Ȃ�ƂȂ��s���A�S�@�\���x�����������H�H������A14:00�a���Ή��A���w�Ǐ��B19:00-20:00Web�u����uCOVID-19�ƃC���t���G���U�v�A�m����V���ɂ����B20:30�A��A�[�H�A21:30�A�Q�B�����v��9364���B
�^�T�v�������g�́u��t��85%�ȏオ����!!!�v�̍L���ɋ���(2)�@
�@����A�����V���Ɂu��t��85%�ȏオ�A���N���ێ����������ɐ|�_�۔z���̖Ɖu��T�v���𐄏��v�A�Ƃ����^�H�i��Ђ̍L�����f�ڂ��ꂽ�B
�@���ʂɂ͖^�N���j�b�N�̒��N������t�̊�ʐ^��傫���f�ڂ��A���̕��̃R�����g���f�ڂ��Ă���B�����ɂ͏����Ȏ��ŁA�����܂ł���t�l�̈�ۂł���A���ʌ��\��ۏ�����̂ł͂���܂���A�Ƃ���B
�@�܂��A�Ɖu�זE (PDC)�ɑ���Ɖu�ێ��G�r�f���X�͂��\�Ƃ��Ď�����Ă���B�Ώێ҂͒ʏ퐬�l88���A�����2�Q�ɕ����āA�T�v�������g���^���Ԃ͋͂�12�T�Ԃŗ��Q�̔�r���Ă���B������蓝�v�����ɂɎ�������ۂ��ۂ߂Ȃ��B�_���f�ڕ����Ƃ���Jpn Pharmacol Ther2022:50:2237-48 �A�Ƃ���B
�@���o���ɗp����ꂽ�u��t��85%�ȏ�!!!�v�Ƃ������l�̈Ӗ�����Ƃ���͑�ςȂ��̂ł���B���͈�t�̗���Ŗ����ł��Ȃ������B
�@���Ȃ݂ɁAJ���{�̈�t����2020�N����33��9623�l(���J��)�B
�@���͂ǂ�����Ē��������̂��H�H�������������B
�@���̍L���̍����ɂ́A�ǂݓ�قNjɏ��̕����ŁA(�����Ώۈ�t��:165���A�����ϑ���:�}�N���~��KK�A���e:�����܂ň�t�l�̈�ۂɂ��E�E�E) �Ƃ���B
�@(���L���̈ꕔ���������@�T�v�������g�E�̍L���̈�ʓI�X�����������߂ł���A�̔�����H�i��Ђ̖��͕̂������j
�@���̍L���̍ő�̖��_��33���l�������t�̂����A�͂�165�l�𒊏o���������ł���Ȃ���u��t��85%�ȏオ����!!!�v�Ƃ܂Ƃ߂��Ƃ���ɂ���B
�@�����ΏۂɂȂ�����t�́A���o���@���s���A�N����j������s���A�Ζ��ォ�f�Ï���t���s���A�H�i��ЂƂ̊֘A���s���E�E�E�E�ł���B���������Ď��Ђ̊֘A��Ƃ̈�t��������Ȃ��B
�@�����w�i�ɍl����A���ʂɓo�ꂳ�����^�N���j�b�N�̒��N������t�͎��݂̈�t�Ȃ̂��H�@�L�ڂ̕��͂͂����g���쐬�����H�E�E�E�Ȃǂ̋^��������Ă���B
�@��ʓI�ɃT�v�������g�̍L���͑����ꏭ�Ȃ��ꂱ�̂悤�Ȍ֑���߁A�֑�L���̌X�����F�߂���B�������䂫���邽�߁A�Ǝv���邪�A����ł͋\�Ԃ̈�ł���B
�@
�@�T�v�������g��2016�N�A�����̈��{�̎��Ɍi�C���g�̂��߂ɑ啝�ȋK���ɘa���F�߂��A���Ђ̊�Ŕ̔���L�����F�߂�ꂽ�B��ʓI�ɂ͂��̒��x�̂��Ƃ͔F�߂��Ă���̂�������Ȃ��B���̂��߂Ɏ��̖ڂ��猩��Ɣ�Ȋw�I�\���������A�ʼn߂ł���B
12/5�i�j�܂�@���ʕa�@�O�� �@���C�{�C���[�����ݒu
�@1:30�N���A�f�[�^�������S�B�R���݁{�������ݎ}�t��܁B6:40�o�X�a�@�B7:00-8:10�a���Ή��A8:45-12:30���ʕa�@�O���A���G�Ȃ����敾�B12:45�a�@�A��͂܂��ɂ�!!! ���H����ʂĔ���1���ԗ]�A14:00�a���Ɩ����A�V���`�F�b�N�{���́A19:00�A��[�H�B20:30�A�Q�B�����v��4971���A�E�ߏ��ɖY��Ĕ����̂v���B
�^�T�v�������g�́u��t��85%�ȏオ����!!!�v�̍L���ɋ���(1)�@
�@����A�֑�L�����ċ��U�L���łȂ����Ǝv����^�Ђ̃T�v�������g�̍L���ɋ������B�����ɂ͌��o���Ƃ��āA�u��t��85%�ȏオ����!!!�v�ƋL�ڂ���Ă����B�@
�@�V���̈�ʂ���������p�����S�ʍL���͖ڂ������B��`���ʂ��傫�����낤�B
�@���Ă͎����Ԋ֘A�̍L���������������A�ŋ߂͗l�ς�肵�ăT�v�������g�̍L��������ɑւ���Ă���B
�@�䂪���ł͍���̍K���������́A����ɔ������N�s�������悤�ȋL���������̂ɂ͋����B
�@���N�s���͍���҂̎傾�����Y�ݎ��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ͏\�������ł���B����҂̌��N�ɑ��ẮA�{���ł���ΐH����^�����̒n���ȓw�͂��K�v�Ȃ̂ł��邪�A���̂悤�ȓw�͔����ɁA���ՂɃT�v�������g�ɗ���X��������B
�@���ʂƂ��ăT�v�������Ƃ̎s��͊g�債1���~�ɔ��낤�Ƃ��Ă���B
�@���N�ւ̊�^�͂Ȃ����A����҂̒~�ώ��Y���s��ɓ����o�����ʂ͖��炩�B
�@���͂��˂Ă���u����u�b��ʂ��āu�T�v�������g�ɂ͌��ʂ��Ȃ��B�Ȋw�I�������Ȃ��v�A�Ǝ咣���Ă��邪���̈ӌ��Ȃǂ͘I�قǂ̌��ʂ��Ȃ��B
�@���߂āA�T�v�������g���w������ۂɂ͈ȉ��̍��ڂ̃`�F�b�N������悤���߂Ă��邪�A�w���҂͌����������Ȃ����낤�B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
(1)���p�A �p�҂̓�̌Q�ɂ킯�Č��ʂ��r���Ă��邩?
(2)��r�����̌Q�������ɑI��ł��邩?
(3)���v�����Ɋ��������\���Ȑl����?
(4)��r�����͏\�������Ԃ�?
(5)�����ւ̉e���͖��炩�ɂȂ��Ă��邩?
(6)���v�f�[�^��S�ʂɎ����Ă���Ȃ炿����Ƃ͐M�p�\�����A����Ɋ������e�̌����͋H�B
(7)�l�I�L���k��O�ʂɏo���Ă���L���͋^���B
(8)�ȂǂȂǁE�E�E�E
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�@�ŋ߂̐V���L���ɂ͈ꌩ�M�p�ł���悤�ȃf�[�^���f�ڂ���Ă��邪�A�����͂̂���f�[�^�������Ă���P�[�X�͂قƂ�ǂȂ��B
�@���_�Ƃ��āA���������ł���T�v���͍��̂Ƃ������Ȃ��B
�@�A���`�G�C�W���O�͌��ʂȂ��B�������͕����̔��W�̌��ʂł���B
�@�Ȃ������̓T�v���ɗ���̂�!!!!
12/4�i���j�܂莞�X����@�]�|��1��� ���N�N���j�b�N�h�b�N�@
�@2:10�N���A�����A�Ǐ��B6:40�o�X�B6:50�u���b�N�A�C�X�o�[���A�]�|��1��ځB���ɂ߂��B�ɂ�!!! 7:00-8:45�a���Ή��B9:00-11:00���N�N���j�b�N�h�b�N�B�h�b�N13���A���ʔ��f15�����B11:15�ѐ�a�@�A�ɂ��B11:30�����ȂǁB15:00�a���A���@���ґΉ��B�X�~���`�b�N���炤�B�����ʁB19:15�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B�����v��6098���B
�t��2023(4)�t���G���@���܂��b�ɏ���Ă̓_���A�ˋ������邩��
�@2019�N�A�H�c�̐����Z���^�[�Ɋ�ꂽ���ŁA�ł������������k�́u�ˋ��v�̂͂�����[���A�V���[�g���b�Z�[�W���A�Ƃ����B
�@���ɂ��u�@���ȊNJ��x�� �����i�ׁ����Z���^-�v�Ɩ����@�ւ��疢�[�����𐿋�����͂��������x���͂����B �u�n���ٔ����Ǘ��ǁv�� �u����������Z���^�[�v�ȂǂƖ����ꍇ���������B
�@�܂��A�u�A�����Ȃ��ꍇ�́A������s���Y�̍����������������I�ɗ��s������
���������܂��v�Ȃǂ̕������L�ڂ���Ă����B
�@�����͑S���ˋ��̘A���ŁA���ɂ͐S�����肪�Ȃ�����S�Ė������Ă��邪���͐��������Ƃ��Ȃ��B
�@���ۂɖ�����������A���K�̎葱���̏ꍇ�ɂ́A�ٔ�������u���ʑ��B�v�Ƃ����X�ւ����t�����B�ʏ�̂͂����ŗ��邱�Ƃ͂Ȃ��B
�@�܂��A�p�\�R����X�}�z�Ɂu�L������̖��[����������̂ŘA�����������v �ƃA�}�]���̃J�X�^�}�[�Z���^�[����SMS���͂����Ƃ�����B������͂����B���݂��A�������L������ɂȂ��Ă���̂Ŗ����Ă��܂����A�����ł���B
�@���I�@�ւ⎖�Ǝ҂Ȃǂɕ����o�������邩��Ƃ����Ĉ��ՂɐM�p�����A���e�ɐg�Ɋo�����Ȃ���Ζ������Ă����B
�@�o��T�C�g��SNS�ł́A72�̂��k����22�̖��̂ӂ肵�đ��肵�Ă���邱�Ƃ�����悤���B�y������Ηǂ����낤���A��Ɍo������Œ���Ǝ҂���r�������������𐿋�����邱�Ƃ�����B�ˋ��͗��p�����o�����Ȃ���Ζ����ł���B
�@�u�T�|�[�g���\�v�Ƃ������������B
�@�p�\�R���̉�ʂɁu�E�C���X�Ɋ��������v�Ƌ��U�̌x����\�������A����ڂŋ��K�����܂����ꂽ�Ƃ�����Q����܂Ȃ��B
�@���������Z���^�[�ɂ��ƁA�{�N�x�̑��k�����͉ߋ��ő��y�[�X�Ő��ځB
�@�{�N�x�̑��k������10�������_��3573���ŁA21�N�x�͖�5��9�疜�~�
�@���葤�̎���Ƃ���
�@�x�����ŕs����������?
�A��ʂ������Ȃ��ݒ�ɂ���
�B�{���Ǝv�킹�邽�ߓd�b�Ń}�C�N���\�t�g�ЂȂǂ̎Ж����g��
�C��ʂɗL����Ђ̃��S���ڂ���
�ȂǁE�E�E�E�E�B
�@�x�����o����ċN���ł��邪�����Ȃ����Ƃ�����B�����Ȃ�Ώ���������OS�̓���ւ����K�v�ɂȂ��Ă���B
�@���̃p�\�R����Mac�ŁATimemachine�ŁA���������I�ɑS�f�[�^���o�b�N�A�b�v����邩��OS�̓���ւ��A���A�͔�r�I�e�Ղ��ł���B����͂ƂĂ��ǂ��@�\�ł���B
12/3�i���j���g�A�~�J�@
�@1:40�N���A�Ǐ��ȂǁB�V���`�F�b�N�A�����B�G�b�Z�C�W�ǂށB���̂ǎ����y���ށB�a�@�֓����]���Ė�4���ԁA�����16:30��f�o����Ɠ��ɓ���a�@�A�������҂����͈ӊO�ƕ����B�V���ق����͑����B19:15�A��A�[�H�B21:00�A�Q�B �����v��5178���B���N�]�|��1��ځB
�t��2023(3)�t���G���@�Y������̂͂������ׂ��b�ɏ���Ă̓_���@
�@���ꍼ�\��20�N�ȏ�O���瑱���ڗ�Ȕƍs�ł���B����ɓr�₦�Ȃ��B�u�ˋ��v�u���ꂨ�ꍼ�\�v�u�ҕt�����\�v�u�Z���ۏv�ȂǑ��l�ł���B
�@���̏ꍇ�́u���ꂨ�ꍼ�\�v�Ǝv����d�b��3�����Ă����B��x�͏H�c�g���a�@�@���𖼏��d�b�Łu���q����Î��̂��N�������B���k�̂��߂�300���~�K�v�v�Ƃ������́B����2����قړ��l�̓��e�B��������m�����N�����ƑΉ����Ă��邤���ɐ������d�b����ꂽ�B
�@�N���W�b�g���\�Ǝv���郁�[���́u�A�}�]���v�u�y�V�v�u�O�HUFJ��s�v�Ȃǂ��牽�x���͂������S���������A���Q�͐����Ă��Ȃ��B
�@���\�̎����m���Ă��āu���͑��v�v�Ǝv���Ă��Ă��A�u�z����������v�Ȃǂ̘b�����t�I�݂ɓ`������ΐM�p���Ă��܂����˂Ȃ��B�����̐E�Ƃ�Ƒ��̖��O���o�����A���Ȃ��炸��Â��������Ă��܂����낤�B
�@���ꍼ�\�ʼn��P�ʁA�疜�~�P�ʂ̋������܂�������Q��10���A�H�c�����ő��������B������̃P�[�X��SNS��l�b�g����ɕ\�����ꂽ�L�������������Ŕ�Q�ɑ����Ă���B���܂��b�͑S�ĉ������A�Ƌ^���ׂ��ł���B���ՂɃA�N�Z�X���Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@���x�ɂ��ƁA�H�c�s��60�㏗����7���ɃX�}�[�g�t�H���𑀍쒆�A�����Ɋւ���SNS�L���������ăA�N�Z�X�B�u���������Ă��������ł�������v�Ǝ����������A�v��1.36���~�����܂�����A1��������̔�Q�z�Ƃ��Č����ł͉ߋ��ō��ƂȂ����B
�@�H�c�s��50�㏗����7���A�u�������铊���v�u�����Z�~�i�[���ĉ҂����v�Ƃ�������SNS�L���������đ���ɐڐG�B�v��1.2���~�����悳�ꂽ�B�ʂ�60�㏗������������Ōv��3900���~��D��ꂽ�B
�@����܂ŔN�ԃx�[�X�Ŕ�Q�z���ł����������̂�2014�N��3.14���~�������B���N�͗��đ����ɍ��z�̔�Q���������A����3.5���~�߁B�ߋ��ň��̐[���Ȏ��ԂƂȂ��Ă���B
�@���͐l�Ԍ���������l�b�g��ł̐l�ԊW�����ł���B������A�t�F�C�X�u�b�N�Ȃǂ͗��p�������Ƃ��Ȃ��BSNS�̉���������猩�Ă��ĕ���邪�ASNS�𗘗p���Ď���̏��M����Ȃ�ǂ����Ɋ댯������ł���A�ƌx���S�����ׂ����낤�B
�@��Q��h����Ԃ̓�����́A�Ƒ��Ԃō��\�̎�������I�ɘb��ɂ��A��l�Ŕ��f���Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃł͂Ȃ����E�E�E�Ǝ��҃}�X�R�~�͌����B
�@����͖����A�ƌ������́B
�@���ɁA�X�}�[�g�t�H����p�\�R����p����1�l��炵�̍���҂͓��Ɋ댯�B���ƂȂ�l�b�g�ʼn������ȃT�C�g�𖧂��Ɉ�l�Ńj���P�Ȃ���y����ł���̂�����Ɛ��肳��邩��ł���B
�@���ꍼ�\�͔�Q�ɑ����Ă��p���������đ��l�ɂ͌�����B�����甭�o�������̂͂ق�̈ꕔ�̂��ƂƎv���B
�@����҂͎v���̊O���N�ŃG�b�`�Ȃ悤�ł���B����ƈꕔ�̐l�ł��낤�������Ԃ�������ŁA���~����ł��邱�Ƃ��킩��B
12/2�i�y�j�I���܂菬�J�@���C�ɂށ@����@����
2:45�N���B���������A�k�R���������Ɠ����B�f�[�^�������S�B�V���`�F�b�N�A12:00���H�A�����A11:00����@2�@�퐮���A���]�ԏ��������B�Ǐ��A�l�R�Ɣ����Ȃǃg���g���߂����B19:00�[�H�A20:00�A�Q�B�����v��7856���B�{���͏o�����B�d�b�Ή��ŁB
�t��2023(2)�@�t���G��(2)�@��≺�����̔��z�ɂȂ�
�@�����������҂ł���B
�@�{�N5��5���}���S�s�S�Ǝv����a�Ԃ�1�T�ԓ��@�����B����ȍ~�A�̒��͗ǂ��Ȃ��B�S���𔖂����ŕ���ꂽ�悤�Ȋ����A���ȁH�@
�@����ɁA����ɗR�����鏬���ȕs��͂���B���낢�날�邪�A���N�O�ʂɏo�Ă����̂����͏�Q�ł���B���������Ⴊ�i����ł��낤�B
�@����S�̂��ɂ�����������ԂŁA�����鐢�E���Ȃ�ƂȂ��Â��B���낻��N�v�̔[�ߎ����H��Ȏ�f���H��p�����߂��邾�낤�B���������ΑO��͔��N��ɗ���悤�����Ă���������2�N�ȏ��f���Ă��Ȃ��Ȃ��E�E�E�B
�@���N�͂ł��邾���S�g�ɑ��k���A���������ɁA�x�����Ƃ�Ȃ��琶������悤�S�����Ă���B
�@����́u�S�g�v�̋��߂ɉ����āu�o���邾���Y������A�������Ɖ߂����v�Ǝv���Ă���B�{���Y���Ƃ����̂́u��菭�Ȃ��w�͂ő傫�ȗ��v�邱�Ɓv�Ȃ̂Łu�Y�����v�̂ł��邪�A���̂����Y���͂Ȃ��l�ɖ��f�����Ȃ��`���`�Ȃ��̂��B���̃`���`���������B
�@11��25���A�H�c�s�ɏ��Ⴊ�~�����B����̊��ɂ͌��\�ȗʂ��~�����B��C�ɏ��Ⴊ�K�v�ȋG�߂������B����@�̐����͂܂��ǂ����낤�Ɩ��f���Ă����B�C�������ł�B12��2���A�{������@2�䐮�������B
�@�䂪�Ƃ̓A�N�Z�X���H�ɓ����B�ߋ��A�����N�O�܂ł́u���Ⴗ�邼�A��邼�v�̍U�߂̋C�����ł������̂����A�ߔN�́u�����܂ŏ��Ⴕ�Ȃ��ōς܂�����̂��v�ł���B�u�Y���������v�A�u�Y���o���Ȃ����v�̋C��������ɗ��B
�@���ꂾ�����͑f���ɂȂ����B
�@��N�͗Z��܂�p���Č����B�\���ȗʂ��U�z�o����Ηǂ��̂��낤���A�܂����鋰��̃��x���ł���B���N�͂���ʂȗZ��܂�p�ӂ��ĐϋɓI�Ɏg�p���Č������B
�@�Y��������Ǐ��ɏW���������B���́u�Y������v���Ƃ������ō����ґ�ɂȂ邾�낤�A�Ɗy���݂ɂ��Ă���B
�@�����A�Ǐ��͉^���s���ɂȂ�B����҂̉^���s���͏d��Ȍ��ʂ݂���B���������ŃR�P��̂͂�ނȂ����A�l���@�\�ቺ�Ŏ����ł��Ȃ��Ȃ�ΐl�l�ɖ��f��������B�^���@�\�́u�o���邾���Y���v���Ȃ��ňێ��������B
�@������Ȃ菬�Ȃ�ܗ~�ɒǂ����Ă��Ă����B�`���`�ȃ��x���ł��邪�ܗ~���瓦���ꂸ�~�j���s??���d�˂Ă����B
�@���̃~�j���s�͒N�ɂ��m���Ă��Ȃ�����̓I�ɖ��������Ƃ͂Ȃ����낤�B����̉ߋ��Ȃ��A�������ނ��@��Ɂu�I������l�v�ƁA�������Ȃ��Đ����Ă���B�@
�@�Ɠ��ɂ͈ꐶ�����ĕt�������Ă�������B���ӂł���B�M�����Ă���B�u�Ȃ�ŁA50�N�����������̉��ŁA��点���̂��낤�H�v�Ɠ��̂���ȏ������ǂ����ɂ������B
�@�|���Ă܂Ƃ��ɘb�����������Ƃ͂Ȃ����A�ޏ��͎��Ƃ̐����ɂ���܂薞�����Ă��Ȃ������݂������B
�@���ƈꏏ�ɂȂ��Ď��������̂͏������Ȃ��낤���A���X�ǂ����Ă����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�@���́u���e�v�E�u�E�ρv�E�u��d�v�ɓO���č�����ޏ����x���Ă����B
�@���N�A��Y�������u�ł��邪�A�܂��삯�����͑����B
�@�N�̕��ɂȂ�ƁA���������v��������Ԃ��Ă��邪�A���N�͉�������艺�����̂悤�ȋC������B
12/1�i���j�܂菬�J�Ȃǁ@��ȊO���@�@
�@1:45�N���B�ϐ�5cm�A�x�g��A���������A�Ǐ��A��w�����ǂ݁B�C�͍�������h���C�ɁB6:00�ƒ�S�~2���W���ɁB��֎ԍ���S���ɕ��S�������B7:20Taxi�w���ɁB�ׂ�����ɏo�Ă����B8:12���܂��B8:50��ȊO���A15:30�a�@�B���ґΉ��ACOVID-19�V����ᔭ�ǁB�S�a�@�ɍL�������B�Ǐ��A�V���`�F�b�N�B�����̓d�q�J���e�p�\�R�����j���[�A���B19:30�A��B21:00�A�Q�B�����v��6285���B
�t��2023(1)�t���G���@�o���邾���Y�����A�������Ɖ߂��������@
�@���Ɏt���ƂȂ����B�������̂��B2023�N���}���Ă��瑁����11�P���o�߂����B
�@�ƂƂ��Ɏ��Ԃ��߂���̂������Ȃ����B���g�̑̓����v���x���Ȃ��ĕ����I���Ԃɒǂ����Ȃ��Ȃ������ߎ��Ԃ��߂���̂�����������̂��B�Ⴆ�Č����ΐV��������ݍs�ɏ�芷�����l�Ȃ��́B�����������s���̂Ɏ��Ԃ����������Ď��ԓI�]�T����������A���Ԃ��R�����Ȃ��ċC���������ł�̂��B
�@���ׂĂ̓��삪�x���Ȃ��Ă���B�Ƃ�킯�������x���x���Ȃ��Ă���B
�@���̂��߈�w�Z����������̂����u�Z�v�́u�S��S�������Ɓv�B
�@�̂̐l�͑�������������n�������̂��B
�@���ꂩ�猩���猻��l�ȂǂȂ�ł����������ł���B�����f���C���Ȃ��B���ꂪ�i�D�ǂ��Ǝv���Ă���炵���B�ŋ߂̐V���͌���p�ꎫ�T�B���ꎫ�T�����ł͓ǂ߂Ȃ��B
�@�ŋ߁A���͏�Q���u�A�C�t���[���v�ƌĂԂ��������A���͏�Q�Ȃ�킩�邪�A����ł͂Ȃ��킩��Ȃ��B���{��̐^�̉��l���̂āA�Ȃ�ł���������������ՂȈ�t�B���o�J�����A�����C�����Ė��ᔻ�ɓ������郁�f�B�A���o�J�ł���B
�@�������N�A��t�Ƃ��Ă̋Ɩ����啝�Ɍy������A���Ȃ莩�������߂��Ă����B
�@�������A3�����{����͐E�ꂪ�ς��a���ł̎������҂��������Ԃ��ӂ����іR�����Ȃ����B�����̋Ɩ��͔��Ζʔ������A�ʓ|������������B
�@78�ɂ��Ȃ��ĕa���Ɩ����S���Ă���Ȃ�Ĉُ�ł���B�����A�Ⴂ�X�^�b�t�����ƈꏏ�ɓ�����͎̂h���I�Ŋy�����B
�@�ӊO�Ǝ����́u�Εׂɓ����Ă������A���͋ΕׂłȂ������̂��B����Ɍ}�����Ă����̂��v�Ǝv�������Ă���B
�@���͎t���̍Q�����������D���łȂ��B�����g�͒W�X�Ƃ��Ă���̂����A�t���ɂȂ�Ɛ��̒��������ɂȂ��Ă���B
�@�ʋΘH�̃C���~�l�[�V�����A���X�X�̃N���X�}�X�Z�[���A���Ε�Z�[���A�V���Ƃ����ݍL�����ڂ⎨�ɃE�������B���ΐe�A�������ł���B
�@���͍Ε�ȂǁA�Ӗ��̖������i�̂����͌����ł���B�������������S���ŏ����B���͒�����������ΕK���n�K�L�ŗ����o����������ʓ|�ł���B�����A�o�ϓI���͂̈ێ��͐����́u���̂��v�ɗ�炸�Љ�ɂƂ��ďd�v�ł��邱�Ƃ�����COVID-19�ЂŎ����ꂽ�B������A���͌�������킸�ɂ��̔N���̏K����Â��Ɍ�����Ă���B�@
�@���������x����}�ւ̃g���b�N�������悤���B
11/30�i�j�H�c�͏�����@��������@1F�V�����[�g�C������
2:20�N���B�f�[�^�����A8:00�u������1F�V�����[�g�C�������ɁB8:30�Ɠ��ɓ���a�@�ցB�Ǐ��A�����ǂ݁A�����B10:00�a���Ή��A���̌�����x���BCOVID-19�̂��߂ɂł��邱�Ƃ͌����Ă���B�V���`�F�b�N�A���́B�����Ǐ��B�ϐ�2-3cm����B19:30�A��B�[�H�A20:20�A���B�����v��4807���B
��N�A�ߕ��֘A�̓~�x�x�B�㒅�͍�ƕ�����X�L�[�E�G�A�ɁB����̃T�}�[�Z�[�^�[����ю��̃g�b�N���Z�[�^�[�ɁA�Y�{���͔���̍�ƕ��̂܂܁B
�t��2022 (1)�t���G���@�o���邾���Y���������@�S�g���ɂ������Ɖ߂��������@
�@���Ɏt���ƂȂ����B�������̂��B2022�N���}���Ă��瑁����11�P���o�߂����B
�@�u�@�t���Z�����A�����ɑ�����v���炱�̌����t���ƌ������B�N�̕��̍Q���������𗍂߂āA12���ُ̈̂Ƃ��Đe���܂�Ă���B�����A�X���őm�����������邱�Ƃ͂Ȃ��B
�@�ƂƂ��Ɏ��Ԃ��߂���̂������Ȃ����B���g�̑̓����v���x���Ȃ��ĕ����I���Ԃɒǂ����Ȃ��Ȃ������ߎ��Ԃ��߂���̂�����������̂��B�Ⴆ�Č����ΐV��������ݍs�ɏ�芷�����l�Ȃ��́B���Ԃ����������Ď��ԓI�]�͂���������A�ł�̂��B
�@���ׂĂ̓��삪�x���Ȃ��Ă���B�Ƃ�킯�������x���x���Ȃ��Ă���B
�@���̂��߈�w�Z����������̂����u�Z�v�́u�S��S�������Ɓv�B�̂̐l�͂悭����������������n�������̂��B���ꂩ�猩���猻��l�ȂǂȂ�ł����������ł���B
�@�ŋ߁A���͏�Q���u�A�C�t���[���v�ƌĂԂ��������A���͏�Q�Ȃ�킩�邪�A����ł͂Ȃ��킩��Ȃ��B���{��̐^�̉��l�ɋC�Â����A�Ȃ�ł���������������ՂȈ�t�B���o�J�����A�����C�����Ă��閳�ᔻ�ȃ��f�B�A���o�J�ł���B
�@�������N�A�Ɩ�����啝�ɉ������A���Ȃ莩�������߂��Ă���B�����Ȃ�ƐV���������Ă��镪�삪�L���Ȃ�B�ӊO�Ǝ����́u���͋ΕׂłȂ������̂��v�Ǝv�������Ă���B���͖Z�����ɐU���āu�������������Ă����v�A�Ǝv���B
�@���͎t���̍Q�����������D���łȂ��B�����g�͒W�X�Ƃ��Ă���̂����A�t���ɂȂ�Ɛ��̒��������ɂȂ��Ă���B
�@�ʋΘH�̃C���~�l�[�V�����A���X�X�̃N���X�}�X�Z�[���A���Ε�Z�[���A�V���Ƃ����ݍL�����ڂ⎨�ɃE���T���B���ΐe�A�������ł���B
�@���͍Ε�ȂǁA�Ӗ��̖������i�̂����͌����ł���B�������������S���ŏ����B���͒�����������ΕK���n�K�L�ŗ����o����������ʓ|�ł���B�����A�o�ϓI���͂̈ێ��͎Љ�ɂƂ��Đ����́u���̂��v�ɗ�炸�d�v�ł��邱�Ƃ�����COVID-19�ЂŎ����ꂽ�B������A���͌�������킸�ɐÂ��Ɍ�����Ă���B�@
�@�����������҂ɓ������B�̒��͂��������͂Ȃ�������ɗR�����鏬���ȕs��͂���B������A���N�͂ł��邾���S�g�ɑ��k���A���������ɁA�x�����Ƃ�Ȃ��琶������悤�S�����Ă���B
�@����́u�S�g�v�̋��߂ɉ����āu�o���邾���Y������A�������Ɖ߂����v�Ǝv���Ă���B�{���Y���Ƃ����̂́u��菭�Ȃ��w�͂ő傫�ȗ��v�邱�Ɓv�Ȃ̂Łu�Y�����v�̂ł��邪�A���̂����Y���͂Ȃ��l�ɖ��f�����Ȃ��`���`�Ȃ��̂��B�u�����̋C�������ɂ߂邾���ŁA�l�ɖ��f�������Ȃ��B�v���̃`���`���������B
�@�{���A�H�c�s�ɏ��Ⴊ�~�����B
�@����̊��ɂ͌��\�ȗʂ��~�����B��C�ɏ���̋G�߂������B�C�������ł�B
�@�q�K�̉̂Ɂu�������т���̐[����q�˂���v�A�ƌ����̂�����B�������x���O�����Đϐ�̏�Ԃ��m���߂��B
�@�ߋ��ɂ́u���Ⴗ�邼�A��邼�v�̋C�����ʼn��x���m���߂��̂ł��邪�A�ߔN�́u�ǂ��܂ŏ��Ⴕ�Ȃ��ōς܂�����̂��v�ł���B�u�Y���������v�A�u�Y���o���Ȃ����v�̋C�����D��B
�@���͂��f���ɂȂ����B
11/29�i���j�܂芦������p���p�����J
3:30�N���A�l�R���肵�܂������A���a�B5:00�Ǐ��A�����ǂ݁B8:30�Ɠ��ɓ���a�@�B11:00�a���A�ȍ~���w�B�V���`�F�b�N�Ɠ��́B���̏I���̈�Ƃ��ė����{�C���[�����̌��ɂ��ă^�J���X�^���_�[�h�ɑ��k�B�^�J���H�c�c�Ə� ���_�ސ�̃^�J���R�[���Z���^�[ ���H�c�c�Ə��S���� ���^�R���X�Љ�̃R�[�X��H�����B�ʓ|�Ȃ��̂ł���B���̐��Ō��肵�����B19:15�A��A�[�H�A20:45�A�Q�B�����v4104���B ���NFit�~�^�C���w���B
���ꍼ�\(1)�@�������z��Q
�@���ꍼ�\�Ő疜�P�ʂ≭�P�ʂ̊z�̋������܂�������Q�������A�H�c�����ő������Ŕ������Ă���B������̃P�[�X��SNS��l�b�g����ɕ\�����ꂽ�L���Ɉ��ՃA�N�Z�X���Ĕ�Q�ɑ����Ă���B
�@���x�ɂ��ƁA�H�c�s��60�㏗����7���ɃX�}�[�g�t�H���𑀍쒆�A�����Ɋւ���SNS�L���������ăA�N�Z�X�B�u���������Ă��������ł�������v�Ǝ����������A�w�肳�ꂽ�����Ɍv��1��3600���~�̌����U�荞�݂��܂����ꂽ�B1��������̔�Q�z�Ƃ��Č����ł͉ߋ��ō��ƂȂ����B
�@���s��50�㏗����7���u�������铊���v�u�����Z�~�i�[���ĉ҂����v�Ƃ�������SNS�L���������ăA�N�Z�X�A��1��2�疜�~�����悳�ꂽ�B�ʂ�60�㏗������������Ōv��3900���~��D��ꂽ�B
�@����܂Ŕ�Q�z���ł����������̂�2114�N��3��1455���~�������B���N�͗��đ����ɍ��z�̔�Q���������A����3��5�疜�~�߁B�ߋ��ň��̐[���Ȏ��ԂƂȂ��Ă���B
�@SNS��ł͋U�L���Ȃǂ����ӂ�Ă���A�S���Ō�����Í����Y�����܂�������Q���������Ă���B�A�N�Z�X���������ŁA�l��ƍߑg�D�ɓ`����Ă��܂����X�N������B�Â��b�ɂ͊댯������ł���A�ƌx���S��������SNS�𗘗p���ׂ����낤�B
�@���ꍼ�\��20�N�ȏ�O���瑱���ڗ�Ȕƍs���B����ɓr�₦�Ȃ��̂́u�ˋ��v�u���ꂨ��v�u�ҕt���v�u�Z���ۏv�ȂǍ��\�̎�������l�B
��Q��h����Ԃ̓�����́A�Ƒ��Ԃ�Z�����m�ō��\�̎�������I�ɘb��ɂ��A��l�Ŕ��f���Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃł͂Ȃ����B
�@���Ƃ������m���Ă��Ă��A�u�z����������v�Ȃǂ̘b�����t�I�݂ɓ`������ΐM�p���Ă��܂����˂Ȃ��B�����̐E�Ƃ�Ƒ��̖��O���o�����A���Ȃ��炸��Â��������Ă��܂����낤�B����͂��܂��̃v�����B�u�����͑��v�v�Ƃ����v�����݂͋֕����B
�@�d�b��SNS��̂��Ƃ�ł����̘b������������ꂽ��A�܂��͍��\���^���ׂ����B�A�������Čx�@�ɑ��k���Ăق����B�u�K����������v�Ȃǂ̘b�͐M�����A�A�N�Z�X���Ȃ����Ƃ��̗v���B
�@1�l��炵�̍���҂ɂ́A�Љ�S�̂Ŗڔz�肷��K�v������B
�@�h�Ƌ@�\�t���d�b�@�̓����𑣂��Ȃǂ��A�ł������̑���u�������B
�@
11/28�i�j�~�J�[�������ɂ��������@���ʕa�@�O���@�@
2:30�N���A�����E�V���ȂǁB�^���f�[�^�����B5:20�R���ݍ~�J�̂��߂ɔp���ł����B�U:40�o�X�a�@�B7:00-8:00�a���Ή��A��r�I�����B8:45-13:10���ʕa�@�O���B�����A�V���X�N���b�v�B�V�����̂ق��������́BCOVID-19�X�Ɉ��AS���A���M�ق��BWeb�w�K��u����҂̔]�v�A�u�Ă�v�ɂ��āA�ʐ��E�̕��������B 20:45�A��A�[�H�A22:00�A�Q�B�����v��8685���B
�G�߂̘b��(19) �@�{�N�Ō�̒�d���@�_���A�̋����@��N����
�@���N�͖ҏ��̉Ăł���A�H�̎c���������������B���̂��߂ɉ䂪�Ƃ̃_���A�͑傫�ȉe�������B
�@�_���A�͉��g�Ȃ�����⊦��ȋC����D�ށB
�@7���ɂ͑����J�Ԃ̂��̂͒ʏ�̂��Ƃ��炫�n�߂����A8���̖ҏ����ʼnԂ�������ɁA�ꕔ�͌s�͂ꂵ���B9���̖Ҏc�������l�ł������B���͂ł��邱�ƂƂ��ĎU�����������͏\���ɍs�����B�@
�@10���ɂȂ�}�Ɍ��C�ɂȂ�n�߁A���{�������C�ɊJ�Ԃ��A11�����{�܂Ŏ����y���܂��Ă��ꂽ�B
�i�j
�@11��25������͓V��Ɍb�܂�Ȃ��炵���B�����Ƃ������n���ɂ������������̂ł��邪
�@
�@���n���Ă݂�ƃs���|���ʂ���r�[�ʒ��x�̏��������P���t���Ă����B
(�����@���������s���|�������x�@䥂łĐH�ׂ����ƂĂ������������̂��~���@���������b�������ʂ���ӂ̗[�H�ɂȂ����@�������햡�̈��)
�@���̂悤�Ȓ��A������ƌ��C�������̂̓T�c�}�C���ł������B
�@���ɂƂ��Ă͏��߂Ă͔̍|�o���ŁA�傫���͊��҂��Ă��Ȃ������̂ł��邪�A�@��o���Ă݂ċ������B�^�����ȓy�̒�����召�̂��܂��܂̐^���ԂȈ������ꂽ�B
(�����ȃT�C�Y�̂��܂����@�����ӂ������A�V�Ղ�ɂ����@�����ł�����)
�@�T�c�}�C���͏����̈����y�n�ł��悭����A�풆���̐H�ƕs���̋~����ɂȂ����ƌ����邪�A�������������B
11/27�i���j�܂�ߌォ��~�J�@���N�N���j�b�N�@�H�c�s���ɔN���̃C���~�l�[�V����
�@3:45�N���B�����A�~�σf�[�^�����B�k�R�B6:40�o�X�a�@�A7:00-8:30�a���Ή��A��r�I�����B9:00-11:30���N�N���j�b�N�h�b�N15��+���ʔ���14���B�Ɠ��̍��z���͂���ꂽ�A�ƐV�h�x�@������A���������Ƃ����B�����͒u���Y��A���{�͂����������A�Ǝv���B11:45�a�@�B�����ق��B15:00���@���ґΉ��BCOVID-19�����҂���Ɉꖼ�A���Ҕ�r�I�����A�V���`�F�b�N�{���́B�Ǐ��B19:30�A��A�[�H�A21:40�A�Q�B�����v6319���B
�G�߂̘b��(18) �@�{�N�Ō�̔��d���@�����E���܂����̎��n
�@���N�͖ҏ��̉Ăł���A�H�̎c���������������B���̂��߂ɖ�ؗނ͑����ĉe�������B
�@�V���ɂ��ƈ�ʓI�ɖ�ؗނ͒l�i�����������悤�ł��邪�A�����̂Ƃ���̃~�j���̗l�q����������A�����Ɨސ��ł����B�@
�@
�@��r�I�������n����L�E���A�g�}�g�͉e���͏��Ȃ������B���̌�Ɏ��n�����}����i�X�͌s�̔w���Ⴍ�A�����S�̂ŏ��Ԃ�ł������B���ʂƂ��Ă͂���قlje�����Ȃ������B
�i���钩�̎��n�@����ł����Ȃ����j
�@��ԑ傫�ȉe�������̂͗����ł������B
�@�ʏ�ł����̂Ƃ���ł͊T���Ĕw�䂪�Ⴍ�����������̍����狹���x�܂ł����L�тȂ��B���N��50cm���x�܂ŁB����Ȓ��˓������A�L���t���ς͒[�̕����珙�X�Ɍ͂�n�߂��B�������A���̏��J�Ɠ����ł���B�����͗͂ɂȂ邾�낤�ƍl���A�Ζ��̍��Ԃ�D���ċ@���قǂɎU���E�����������A�傫���͉��P���Ȃ������B�ŏI�I�ɂ͖w�ǎ��n�͂ł��Ȃ����낤�ƒ��߂��B
�@���n���Ă݂�ƃs���|���ʂ���r�[�ʒ��x�̏��������P���t���Ă����B
(�����@���������s���|�������x�@䥂łĐH�ׂ����ƂĂ������������̂��~���@���������b�������ʂ���ӂ̗[�H�ɂȂ����@�������햡�̈��)
�@���̂悤�Ȓ��A������ƌ��C�������̂̓T�c�}�C���ł������B
�@���ɂƂ��Ă͏��߂Ă͔̍|�o���ŁA�傫���͊��҂��Ă��Ȃ������̂ł��邪�A�@��o���Ă݂ċ������B�^�����ȓy�̒�����召�̂��܂��܂̐^���ԂȈ������ꂽ�B
(�����ȃT�C�Y�̂��܂����@�����ӂ������A�V�Ղ�ɂ����@�����ł�����)
�@�T�c�}�C���͏����̈����y�n�ł��悭����A�풆���̐H�ƕs���̋~����ɂȂ����ƌ����邪�A�������������B
11/26�i���j�܂� ���g���ɂށ@�Ɠ��A�H
1:30�N���A�����摜�f�[�^�����B�摜���������B11:40�o�X�a�@�A�a��COVID-19�̓N���X�^�[�ɁB���R�ƑΉ�����A�X�̊��҂͖��Ȃ��B�V�����́A�Ǐ��A15:15�O�o�A�Ï��X�ȂǁB17:30�A��A�V���A�������́A�Ǐ��B19:00�[�H�B20:30�A�Q�B23;10�A��̉Ɠ��}���鏀���ŋN���A�����v��7881�B�����A��B���z��������Ǘ������y�x�A2:30�A�Q�B
���z���ꂿ�����!!(2)�@�Ɠ��̐l���^��Ȃ����i������
�@�u���z���ꂿ�����!!!�v�Ƃ����A�������C���ɓ͂����B
�@���z���ꂽ??�B���́u�܂���!!!�v�Ǝv�����B�ޏ��̂��Ƃ����炨���炭�X���ɍ������̂��낤�A�Ǝv�����B����őO�Ȃ����邩��ł���B�Ƃɂ������߂Ɍx�@�ɓ͂���悤�w�������B
�@�ۂ̓����A���������w�̔h�o���ł��낤���A�ɓ͂����A�Ƃ����B�ƂĂ��e�Ɏ�t���Ă��ꂽ�炵���B�J�[�h�̖������葱���͍�����������������Ă��ꂽ�悤�ł���B
�@�Ɠ��̍��z�Ǘ��͓��킩���肪�����B�l�������Ƃ������A�f���Ƃ������B��ʓI�Ɍ����Ċ�@�Ǘ��ɑ���z�������Ȃ��悤�Ɏv���B
�@���Ԋ��o�����ɂ̂�т肵�Ă���B
�@����Ȑ��i�͎��Ɛ����B�ޏ��̎����E�Ɏ��Ɍ����Ă��镔���������A���ڂ��Ă݂Ă����B
�@�ŁA���̕قɂ��ƁA�Ɠ��͎�͗�������ł����炵���B���́u���䂳����ꂽ�킯�łȂ��A�����ꂽ�킯�łȂ��E�E�E�v�ƈԂ߂��B
�@25��(��)23���߂��A�ŏI�̐V�����ŋA�H�����B�ʏ�Ȃ玄�͏n�����Ă��鎞�Ԃł��邪�A��������ŋA���Ă��邾�낤�Ɨ\�z���ċN���đ҂��Ă����B�ӊO�ƌ��C�ɋA���Ă����̂ň��g�����B
�@����k
�@26��(���j���͌��N�N���j�b�N�Ńh�b�N�֘A�̋Ɩ������Ȃ��Ă������A�Ɠ�����LINE�Ɂu�ۂ̓��x�@������d�b������A���z�������̕�����x�@���ɓ͂����A���g���S��(?)�����炵���B��}�֒������ő���E�E�E�v�Ƃ̂��ƁB
�@�Ƃ������Ƃ͓���ꂽ�̂ł͂Ȃ��ǂ����ɂ����Y��A�P�ӂ̕��ɏE��ꂽ�A�Ƃ������Ƃ��낤�B
�@�U��Ԃ��Ă݂�A�ۑP���X�ŃJ�����_�[���w��������g�C���ɓ���A���Ńp�[���[�Ɋ���Ă��̉�v�̎��_�ō��z���Ȃ����ƂɋC�Â����A�Ƃ̂��ƁB�����g�C���̉������ɂ����Y�ꂽ�̂ł��낤�B
�@�O��A���狳�P�Ƃ��ē������Ƃ͓���ꂽ�������������Ɋւ�炸�A�Ƃɂ����x�@�ɓ͂��邱�Ƃ��K�v�Ƃ������ƁB����͌x�@�ɓ͂��Ă��Ȃ���Ύ�����s���̈⎸���Ƃ��ď�������Ă����͂��B
�@����ɂ��Ă�����̌����A����̌����P�ӂ̐l�ɏE��ꂽ�K�^�ȃP�[�X�Ƃ����悤�B���������P�ӂ̐l������Ƃ������Ƃ��f���炵���B���{�Ƃ����̂͂����������A�Ǝv���B
�@����̂��Ƃł��邪�A�Ɠ���Apple��AirTag���������悤�Ǝv���B�����iPhone����AirTag�����̋����ȏ㗣���Ɖ��Ōx������A�Ƃ������̂ō��z�Ƃ��ɓ���Ă��������B�܂��ڍׂȋ@�\�͕s���ł��邪���ɗ��������Ɏv���B
11/25�i�y) �~�J���s����@����@�Ɠ�����
�@1:50�N���A�V�������`�F�b�N�Ȃǂ����̂��Ƃ��B5:30��ɂ͂�������Ɛ�B�܂����~��܂��Ǝv���Ă����̂����C�ے��������������B�Ɠ��͖������œ����A��w���ړI�B6:11�V�����ɂ͂Ȃ�Ƃ��Ԃɍ������炵���B�Ǐ��Ɣ����B���H�َ͉q�ōς܂��B�a����COVID-19�����Ҕ��ǂő�ςȗl�q�A�w������o�Εs�v�ƁB�V���`�F�b�N�B�Ǐ��B�~�������B14:00�Ɠ�����u���z���ꂿ�����!!�v�Ƃ����A�����C���ɂ������B���z���������炵���A���ꂽ�H�H�s���B�x�@�ɓ͂���悤�w���B�J�[�h�͖������葱���w���B19:00�[�H�A20:30�A���B��5555���B
���z���ꂿ�����!!(1)�@�ߋ��̌o��
�@�Ɠ��͎�����U���č���(24��)6:10���̐V�����ŏ㋞�����B
�@���N�P��ɂȂ��Ă���J�����_�[�̍w���̂��߂ł���B��N�A���l�ݏZ�̖���Ƃƍ������ĂQ�����Ă���̂ł��邪�A���N�͑��Z�̂��߈ꔑ�����Ƃ����炵���B
�@14:00�Ɠ�����u���z���ꂿ�����!!!�v�Ƃ������ڂ��C�̂���\���́A�[�����̂�������Ȃ��A�������C���ɓ͂����B
�@���z��������??�A���ꂽ??�B���͔ޏ��̂��Ƃ����炨���炭�X���ɍ������̂��낤�A�Ǝv�����B�O�Ȃ����邩��ł���B�Ƃɂ����x�@�ɓ͂���悤�w�����A�J�[�h�͖������葱������悤�Ɏw�������B
�@�Ɠ��̍��z�Ǘ��͓��킩���肪�����B
�@���z�Ɋւ��Ă͏����ȃG�s�\�[�h�͉��x�����邪�A2017�N10���ɂ͌����ɓ����Ă��܂����B
�@���̎��A���ǂ��͐V����w�̓�����o�Ȃ����˂ē���Ή��E�L��R�W�I�p�[�N��K�₵�Ă����B
�@�o�X��^�N�V�[�A���[�v�E�G�C���g���Ă̗��ł��������A�V��ɂ��b�܂�A�L��R�A����A���a�V�R�̎��R�𖡂�����B
�@�����͊O������̊ό��q���吨�ŁA���̒n���8�������A�W�A�n�̐l�X�ł������B���{�ɋ��Ȃ���O���ɍs�����悤�ȍ��o�����o�����B���̗��̊ԁA�o�X�ړ����ɒ����l�Ǝv�����҂����2��Ȃ�����ꂽ�B����I�ɂ͂߂����ɂȂ��������ɒ����A�؍����ł͍���҂�厖�ɂ��镶�����c���Ă����̂��Ɗ��S���A�D�ӂɊÂ����B
�@�S�Ɏc�闷�������Ǝv�����A�Ō�ɃI�`���t�����B
�@�L��R���瓴��w�Ɉړ�����o�X����~��Ă��炭���ĉƓ��̃n���h�o�b�O������z���Ȃ��Ȃ��Ă���̂ɋC�Â����B���G�����o�X�̒��œ���ꂽ�̂��낤�B
�@�Ɠ��̍��z�Ǘ��͂�����肪����B�o�b�O�̊W�A�t�@�X�i�[�ȂǕ߂Ȃ�����A���z���ی����̂��Ƃ��H�łȂ��B��X���ӂ͂��Ă����̂ł��邪���ӂ����������͕߂邪�A����I�ɂ͌��ʂ��Ȃ��B
�@�o�X�̒��̏��l����Ɠ��͍��Ȃ̘e�Ƀo�b�O��u���Ă�������㕔���Ȃ�����L���ΊȒP�ɓ�����悤�ȏł������B
�@�Ɠ��̓J�[�h����O�I�ɗp���邪���ς�炸�����h�ł���B���̂��ߍ��z�͑�^�ŊہX�Ɩc��Ă���B���z�ɂ͂���������Ă����̂��͂����肵�Ȃ����A�������Ȃ��͂Ȃ������炵���B���y�Y���ďH�c�ɑ�������ŗǂ������B�ꉞ�A����Ώ��ɓ���͂͒�o�����B
�@�A�H�̐V�����̐ؕ��͎��������Ă������A���̃f�B�o�b�O�̒�ɂ͎�̂������B�������Ă����̂ŁA�Ȃ�Ƃ�����܂ŋA�蒅�����B
�@���z�ɂ��Ă�100%���߂Ă����̂ł��邪�A������A����̏Z���ƌ����Ⴂ�j���̐��Łu�o�X�H���̖T�̑��ނ炩����z���E�������A���ɖ��h���������̂ŘA�����܂����B�J�[�h�A�ی��ؓ����������Ă܂���ł����B�x�@�ɓ͂��Ă����܂��v�Ɠd�b������A�����A����Ώ�������d�b���������B
�@�N���W�b�g�J�[�h���͂��̏�œ����̎葱�����̂Ō����ȊO�Ɏ��Q�͂Ȃ������B
�@7�N���O�̘b�B����Ή��͕������Z�ȗǂ��ꏊ�ł������A�Ǝv���Ă���B
11/24�i���j�I���~�J��r��\�z�@��Ȓ��ʕa�@�O��
1:30�N���A�{�ǂ݁A5:30����̎������݂���3�W�Ϗ��ɁB7:30Taxi�w���A���܂��B8:50��Ȓ��ʕa�@�O���B���艮�Ï��X�K��B15:30�A�@�BCOVID-19����3�l�ځB19:40�A��A�[�H�A21:00�A���B��7978���B
�� ���܂��@�^�}�S(6)�@���C���t�ŗ��̒l�i����2023�N�t
���a�������C���t���G���U(���C���t)�̗��s�͑S���E�Ő����Ă���B
�@�䂪���ŗ��̕s����l�i�̍����Ȃǂ������N���������C���t�̗��s����10��-3���ŁA���t�ЂƂ܂����������B
�@2022�N10���Ɏn�܂������G�̒��C���t�̊����g��ŁA�E�������ꂽ�{�̐��͉ߋ��ő��̖�1.771���H�A�S����8���ɂ̂ڂ����B�Ƃ��ɍ̗��{����Ă�_��ő������A���̋������啝�Ɍ��������B
�@ �X�[�p�[�Œl�i���オ��A�O�H�X�������g�����j���[����߂�Ȃlje�����L�������B
�@�{�{��̖h��[�u���I����Ă�������ԐV���ɔ������Ȃ��ƁA�����̔_��ɃE�C���X���Ȃ��Ȃ������Ƃ��Ӗ�����u���v ��錾�ł���B �_���Ȃ͂��̍��ۃ��[���Ɋ�Â��A6��20���ɐ���錾�����B
�@�ۑ�͍���̊����g��̖h�~�B
�@���C���t�̃E�C���X�͓n�蒹���H����ɉ^��ł���B���~�߂�͕̂s�\�Ȃ̂ŁA�{�{��ɃE�C���X���N������̂������ɖh�������d�v�ɂȂ�B
�@���s���x�ł́A���C���t�����������_��̂��ׂĂ̌{���E�����̑ΏۂɂȂ�B�����̗��s�ł͈�ӏ���100���H���{���E�����ɂȂ����P�[�X������B�{�{�Ƃ͏��X�ɑ�K�͉����Ă���s��ɗ^����e���͖����ł��Ȃ��B���ɖ��ʁA�ܑ̖������A�E�C���X�𑝂₳�Ȃ����߂ɂ͌���ł͎~�ނȂ��B
�@�_���Ȃ��������Ă���̂��A�{�{��́u�����Ǘ��v�̓����B �{�{����̋��ɕ����A�l��ԗ��̈ړ����������������Ĉ�S�̂Ɋ������L�܂�̂�h���B ����ɂ��A�E�����̑Ώی{�������������������ɗ��߂邱�Ƃ��\�ɂȂ�B
�@�u�����̗D�����v�Ƃ���ꂽ���̉��i�̈���́A�_��̑�^���Ɖ~���ɂ������Ȏ����̗A�����x���Ă����B �K�͊g��ɂ��������Ƀu���[�L�������Ȃ����߂ɂ��A�V�������[���̂��Ƃʼnq���Ǘ���O�ꂷ�ׂ����낤�B
�@����A�����Ɋւ��Ă͍��Y�䗦�����߂邱�ƂŁA���i�̕ϓ���}���邱�Ƃ����߂��Ă���B ���_���܂߂��{�Y�S�̂̌o�c�����肳���邽�߁A�ƒ{���������Y�����A���ۑ���̉e����a�炰��w�͂��������Ȃ��B
�@���N�����C���t�̔������ɓ������B���N�̓��������ڂ����B
11/23�i�j�ΘJ���ӂ̓��@����@COVID-19�z���Ҕ��ǁ@�둷��������
2:00�N���A�{�ǂ݁A9:00���ȂǍŏI��ƁA�����A���܂������n�B��҂̗��h���ɋ����B10:00��������COVID-19�z���Ҕ��ǁB12:00������������Taxi�B���t���A�t���A�@������ɁB���̌����͉A���ł������B���NJ��҂�2���ɁB���Â͉@���ɂ���Đi�߂�ꂽ�B�厡��͉e�����������B�Ǐ����̑��A18:15�A��A�[�H�A20:30�A�Q�A���s�v8180���B
�� ���܂��@�^�}�S(5)�@50g�̗��ɂ�50g�̐��̑S�g�����h�{���l�܂��Ă���
�@�����Ŏ�y�ɐH�ׂ��闑�B
�@�����̌��ɓ���悤�ɂȂ����̂́A�]�ˎ����������300�N�قǑO����B �����͍����H�ނƂ��Ē��d����A�H�ׂ��̂͏j�����ƂȂǓ��ʂȓ��݂̂ł������B
�@��������H�ƂȂ����̂́A�͂邩�͂邩�x���A���a30�N��̍��x�o�ϐ������ȍ~�B ���{�̌o�ϗ͂Ƌ��ɁA���ώ��������сA���̏���ʂ����������B
�@���{�l�͗��D���ŁA1�l������̐ێ���͂ق�1��1�ɑ����B����̓��L�V�R�Ɏ����Ő��E��2��(2021�N)�ł���B
�@50g�̗��͈�̍זE����50g�̐��̑S�g�����h�{���l�܂��Ă��邩�炻�̉h�{���ƃo�����X�̗ǂ��ɂ͋^�����Ȃ��B���̎������痑�ɂ͉��Ƃ����h�{�f��????mg�܂܂��Ƃ����h�{�f�ʂ̋c�_�͖��p�ł���B
�@�R���X�e���[���Ɋւ��Ă͌�����������Ă���B
�@�m���ɁA���A�Ƃ��ɗ����̓R���X�e���[�����ł������܂ސH�i�̈�B �������A����H�ׂ遨�R���X�e���[���l�㏸�������d���ǂɂȂ���@�Ƃ������ʊW���ؖ����錤�����ʂ́A���͑��݂��Ă��Ȃ��B
�@�R���X�e���[���́A�g�̂̍זE�����`���E�C�����A���z�������╛�t�玿�z�������A�_�`�_�Ȃǂ̌��o���ƂȂ邪�A�H���R���̂��͖̂�20%�ŁA��80%�͊̑��ō����B���Ƃ��H���łƂ�߂��Ă��A�̑��ō����ʂ��}������A�̓��̃R���X�e���[���͈��ʂ��ۂ����B���̂��߁A1��1-2�͐ێ悵�Ă����Ȃ��B
�@����҂́u�h�{�v�Ɂu�^���v�������Č��N���l���Ă����˂Ȃ�Ȃ��B
�@����ς������s������Ƌؓ��̌����ƂƂ��ɋؗ͂��ቺ���A�Ɖu�\���ቺ�� �u������(�T���R�y�j�A)�v�ɂȂ�B����҂̏ꍇ�͕͋ؗs���ʼn^���@�\���ቺ����ƁA�u�S�g�����������(�t���C��)�v��ԂɂȂ�A�F�m�@�\�̒ቺ�ɂ��Ȃ���B
�@��������ؓ��s�����������ƂȂ邽�߁A���ł���ς�����⋋���A�K�x�ɉ^������̂͗��ɓK�����b�B
�@����ς�����1����50~60g�K�v�Ƃ���Ă��邪�A��2��1���K�v�ʂ�20%��₦��B
�@���͋C�Â��Ȃ������ɁA�������̌��N���x���Ă���B
�@������ɓ���A�����ʼnh�{�L���B�����ł��H�ׂ����H�i�ł���B
11/22�i���j������r�I���g�@�@
�@1:55�N���A�{�ǂ݁A�k�R���B���ɖ{�A��w�����A�����B�l�R�̐��b�A���a�B8:30�Ɠ��ɓ���a�@�B�V���`�F�b�N�{���́A11:00�a���A�����A13:00��lj�A14:30�����J���t�@+EC�Ȃ�+���ҏ��u�B�Ƒ��ƒ�֘A�����ǂ݁B16:00���҉Ƒ�RS��ʒk�B19:20�A��[�H�A20:45�A�Q�B�����v5342���B
�� ���܂��@�^�}�S(4)�@�̗��{�̈ꐶ�A�U�X�Y�܂���đ����ׂ�A2�قǂŏ��������
�@���͗��D���Ȃ̂ł��邪�A���ʂ��Y�ޔ��F���O�z���A�ԋʂ��Y�ރ|���X�u���E���Ȃǂ̗̍��{�ɂ��čŋ߂܂ő傫��������Ă����B
�@��ɁA�_�Ɗ֘A�̖{��ǂ�ŏ��߂Ēm�����B
�@�̗��{�̗Y�͐��̒i�K�ŏ��������B
�@���̂����̕����{�̎��Y�ӕʎt�̖Ƌ�(?)�������Ă���A���X�b���Ă�������ł���B����͂���߂ē�����ɗY�{���������Ĉ��������̂��ƌ����Ă����B�{�{��ł͗Y�͖��p�Ȃ̂ŁA�ނ�͌����������_�ŏ��������B
�@�����j�̗���Őg�̖т��悾�B�l�Ԃ̐��E�ł̓W�F���_�[���Ƃ��Đ������ے肳�����A�Ƃ����̂ɁE�E�E�̗��{�̐��E�͌��������̂ł���B
�@�܂��A�{�Ō݂��ɉ��䂪�₦�Ȃ��B���̂��ߖ������Ś{���B���{�ł͖�80���Ŏ��{����Ă���A�Ƃ̎��ł���B
�@�̗��{�͐���5����������Y�����n�߂�B
�@���́A���̌ジ���Ɛ��N�Ԃɂ킽���ĎY������������̂��Ǝv���Ă����B
�@���ꂪ�A�Y���J�n��1�N�قnjo�Ɗ��H���ɓ��藑����Y�������ቺ���A�x�Y���ɓ���B���̎��_�ŏ�������{�{������邪�A���̗{�{��ł͐l�H�I�ɋ������H���s���B�{�����a�����ɂ��h�{�s���ɂ������
�H�������ւ��B���̏��u�Ő����c�����{�́A���̌�8�����قǎ��̗ǂ����ށB�ĂюY�����������邪�A���̎��_�ő����͏�������A�{���܂��͓����̉a�ƂȂ�B�������H�͓��{�ł͔����̎{�݂Ŏ��{����Ă���B
�@�̗��{�̈ꐶ���܂Ƃ߂�ƁA
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�����܂ꂽ���_�ŗY�͏��������B
���{������������B
���Y���J�n����N�ŋx�Y�����}���邪�A�ꕔ�͂��̎��_�ŏ��������B
���������Ȃ��ꍇ�͐l�H�I�ɉh�{������Ԃɂ������H������B�ꕔ�͉h�{����������B
���������H��8�����قǎY�����邪�ĂюY������������B���̎��_�ő����͎E���������B
�����̎��_�ł͂₹�ׂ�H���p�ɂ͂��܂�����Ă��Ȃ��B���̉��i�͈����B�ƒ{�̃G�T�p�ȂǂƂȂ�B
���{�̎�����20�N�قǂƂ���邪�A�̗��{�̎�����2�N�قǂł���B�C�̓�!!!�B
���ȂǂȂǁE�E�E�B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�@�������܂����B
�@�l�Ԃ͑��̐����́u���̂��v�����������Đ����Ă���B�D���̗����Y��ł��钹���������瑸�h���Ă��������ɁA�ޏ��炪����Ȍ������ꐶ�𑗂��Ă���Ƃ́A�m��Ȃ������B
�@�Y���{�͓�������̐��_���͂��Ȃ������̈ꐶ���Ǝv���B
�@����́A�S���ė����������������A�Ǝv���B
11/21�i�j�ߑO�܂�ߌ�����@���ʓ��ȊO���@
1:30�N���A�����܂ō~�J���オ�����B5:20�R�S�~��o�A6:40�o�X�ѐ�a�@�A7:00-8:30�a�������A8:45-12:30���ʕa�@���ȊO���A�Љ��쐬�A�X���[�Y�B12:45�a�@�B�ߐ��A15:00�a���Ή��B17:00���҉Ƒ��ʒk�B19:00�A��A�[�H�A21:30�A�Q�B���s�v��9414���B
�� ���܂��@�^�}�S(3)�@��ʐ��Y�ʼn��i����@�X�ɕt�����l�ō��ʉ�
�@���̒l�i�́A�����Ԃقډ����Łu�����̗D�����v�ƂȂ��Ă���B������w�w�����ŗL����������Ă����������10�~�O��ł������B
�@�X�I��10�P�����Pack���x���C���[�W����Kg������̉��i�����݂̉��i�ɕϊ����Ĕ�r���Ă݂��B
�@1950�N(���a25�N)�ɂ́u2,370�~�v�����̉��i���������A�ȍ~���i��������A1987�N(���a62�N)��200�~��ɓ������B���̌�͕ϓ��͂�����̂̉��i�͈��肵�Ă���B
�@�_���Ȃ̃f�[�^�ɂ��u2015�N(����27�N)�x4-6����219�~�v�ł������B
�����������̗D�����ł��闝�R
�@�Ȃ������u�����̗D�����v�ł��葱���Ă����̂��H�H
�@���̍ő�̗��R�́u�~���v�ɂ���炵���B�j���g���̎����͌��݂ł͂قƂ�ǂ��O������A������Ă���B�A������鎔���́A���{�̌o�ϗ͂�w�i�ɂ����~���ɂ���Ĉ����ɂȂ�A���ꂪ���̎s�ꉿ�i�ɔ��f����Ă����B
�@�������Ȃ���A���{�̌o�ϗ͂��Ȃ肪�o�Ă����ȏ�A�����͓ǂ߂Ȃ��B�ƒ{�p�H���͔��W�r�㍑�̌o�ϓI�헪�����ɂȂ��Ă��Ă���B���Y�������͖��Ȃ̂��낤���B
�@�܂��A�{�{��͑�K�͉����Ă���B���������Ȃ�����ł���B��ʓI�Ɍ{�������Y���������قǎs�ꉿ�i�͉���B�{�{�Ƃɂ͓��̒ɂ����Ƃł��낤���A����҂͍��܂ł͂���ŏ������Ă����B
�����̉��i���͉�����R�����邩�H
�@�{�{�_�Ƃł͗��ɕt�����l�����������グ�鎎�݂��s�Ȃ��Ă���B
�@���i�ɉe��������q�B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
���F�̗��@�����@���F
�������E���������@�����@�P�[�W����
���Ɣz����������@�����@�A�������A�H��z������
���[�h�����A�r�^�~�������Ȃǁ@�����@�ʏ헑
���g�̐F���@�@�Z���F����������
�E�E�E�ȂǂȂǁB
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�@�����̍����ǂ̂悤�ɍl���邩�͏���҂̎��R�ł����B�������A����҂������قǂ̍��͂Ȃ��B����҂̃C���[�W�͈ӊO�ɑ傫�����ꂪ�l�i�ɔ��f����Ă���B
���h�{���Ȃǂɍ��͂���̂��H
�@���F�����̕�����l�i�͍����B���ƂȂ��h�{�����������ŁA���������A�Ƃ������R�Œ��F�����̕����D�܂��X��������B�������A�^���Ă���G�T�Ȃǂ̏����������Ȃ�A���҂ɂ܂��������͂Ȃ��A�Ƃ����B
�@�����玄�͔��������D�ށB
11/20�i���j�܂�~�J�����@�������ҋ~�}�����@���N�N���j�b�N�h�b�N�@
�@2:00�N���B�Ԃ��Ȃ����ҕs���̘A���A�o���đΉ��B�s���ǃV���b�N�őΉ�����B5:00�����ʕa�@�~�}�Ɋ��Ҕ����B�v�X�~�}�Ԃɓ���B6:00�A�@�A�����A7:00�a���Ɩ��B9:00-11:30���N�N���j�b�N�h�b�N14��+���ʔ���14�����B���n�a�@�B�����̋��[�ɐ�ւ��B�Ǐ������B14:00�V���`�F�b�N�A15:00���@���ґΉ��A�a���p�\�R���̓���ւ�����A�����X�s�[�h�͑����Ȃ������]���̋@�\���g���Ȃ��Ȃ����B���P�����邪���삪�ʓ|�ɁB 19:00�A��A�[�H�A20:30�A�Q�A�����v6488���B
�� ���܂��@�^�}�S(2)�@�n�R�w���̒��̂��y���[������������
�@1965�N(���a40)�A���͐V����w�ɐi�w�����B�n�R�ł��������߂Ɋw�����ɓ��������B�����ŋ������H���͒����f�Ȃ��̂ł������B
�@���H��30�~�ł��сA���X�`�A���̉��F���������W���ł������B�T�̂������͋C�̂������F�l��l�Ǝ������킹�ĐH���ɏW�܂�A�e��10�~�o��������30�~�Ő����ƃp�b�N�[�����w���A�[�������������тƂ��A�O�l�ŕ��������ĐH�ׂ��B
�@���H�[�H�͊e�X50�~�ŁA���̓��e�͐����Ēm��ׂ��̃��x���ł������B
�@���͂��̗���6�N�ԍݐЂ����B��ɋ�����Ă����B�H�����e�ɍD�������Ȃnj����Ă���Ȃ��ŁA���ł��c�����ɐH�ׂ��B�H�i�ɍD�������͂�����邪�A�C���ŐH�ׂ��Ȃ��H�i�͂Ȃ��B
�@�[�������������тɂ͐[�����ӂ��Ă���B
�@�������͂��ꂱ��60�N�߂��O�̘b�ł��邪�A���ł����̒��H��1���������x�ɗ��������сA�܂��͔[���������тł���B
(�����������@���̉��g�̒���A�f���炵��)
�@�^�@���������тƔ[��������
�@���͓���͗����͂��Ȃ��B����ł��A����������A�d�q�����W���x�Ȃ�g���邵�A������������[����������������͂ł���B�킪�Ƃ̐��ъ�̓{�^�����������Ďg���Ȃ��B
�@���͒��������B5:30am�ɂ͒��H��ۂ�B���R�ǐH�ł���B���̒����͂�̈�Ԃ̕p�x�͍��ł��[�����������тł���B�����Ő����������сA�O�Ԗڂ͎O�������u�_���Ђ��v���ȁH
�@60g�̃`���ʼn𓀂������т̏�ŗ�������A�ݖ������X�����A������܂킵�āA�H�ׂ�B
�@
�@�W�����ĐH�ׂ�Έꕪ��������Ȃ��B
�@����̔������̓X�[�p�[�Ŕ�����200�~/Pack�̂��́A�����̒��F������1000�~/Pack�ł���B��҂͉Ƒ������̊�]�Œ���I�ɓ͂�����i�ł���B���̒l�i�̈Ⴂ�͉����H���ɍ��͂���̂��H�h�{�ɂ́H�E�E�E�Ȃǂƍl���邪�A���F�̕���������������B�傫�ȍ�������n�Y�Ȃ�����Ȃ���!!!! ������A��������Ƃ��͎��͔�������I��ŐH�ׂ�B�@
�@���g�Ɣ��g�͖��炩�ɖ����Ⴄ�B������A��̖����Ō�܂ő��Ȃ킸�ɐH�ׂ����B���т����������A�ݖ����Ȃ��Ȃ��ł���B�����S���ʁX�ɖ��키�B���̗��������т̃|���V�[�ł���B
�@
�@���́A�l�Ԃ̐����̒��ŏd�v�ł��邪���܂�ɒl�i�������A�H�ނƂ��Đ����ȕ]����^�����Ă��Ȃ��A�Ǝv���B�{�{�_�Ƃɂ͂�����Ƃ��������Ăق����B
�@�����A�l�i�����300�~�ɂȂĂ��A���͗��������т�H�ׂ�A�Ǝv���B
11/19�i���j�I���~�J
�@1:30�N���A��w�_���ǂ݁A�Ǐ��A�f�[�^�����ȂǁB11:00���t���̉�~���n�X�ɏo�Ȃ̉Ɠ��ɓ���a�@�B�a���Ɩ�����A�s���̊���2.3�Ή��B�ߌォ��V�K�ɕs������TS��A�����A19:00�A��[�H�A�s���̊��ҘA���A20:30�A�Q�A�����v4943���B
�v���E�X�V�t�g���o�[�����R�Ƀj���[�g�����ɖ߂�s�����_���A�����͈�{�̗փS���ł������B
�� ���܂��@�^�}�S(1)�@�c�����̉Ђ̃g���E�}�u����v�u�Ή��v�u���Ă����v
�@1952�N(���a27)4��10���A�ߏ��̉Ƃ�����܂ɂȂ��Ă���̂ɋC�Â����̂����H���ŁA���͐H�����ł������B�ڂ̑O�̎M�ɂ͕ꂪ�Ă����傫�Ȍ��Ă��̗��Ă����������B���ƂŐH�ׂ悤�Ɗy���݂Ɏc���Ă����̂ł��邪�A�H�ׂȂ��܂ܔ����B
�@
�@�c�����疃��̓���������ɂ������A200m�قǗ��ꂽ���̃����S���ł��̋��ɂ̏�ɍ����Ď���Ɛf�Ï����Ă�������ߒ��������ƌ��Ă����B400�قǂ̌������Ă��s���������͋��|���ƂƂ��ɁA�S�Ă�����p���[�Ɋ���������o�����B�R������M�C���ς�����ꏊ���ړ������B
�@���������炩���Ă����������ɉƑ���̑҂ꏊ�ɖ߂������A���̎��A���������������Ƃőc�������g�����\��͖Y����Ȃ��B
�@���̉Ђ͗c�����̎��Ƀg���E�}�Ƃ��Ďc���Ă���B���ɁA�u����v�E�u�Ή��v�E�u���Ă����v�ł���B
�@�u����v
�@�c�������ɖ����������^���ɂ�w���킵�����̐^���ȕ\��͖Y����Ȃ��B���w�Z�ɓ���������ŁA����̂��ƂȂǒm��R���Ȃ��������A�ڂ̑O�Ŏ���Ă������悤�Ƃ��Ă��钆�ł̂��̑c���̕\��ł���B���͎��̏d�v���𗝉������B
�@�@
�@��t�ɂȂ��Ă��犳�҂ւ̎��Ï�A�����t�B�l�𒆐S�ɖ����p����@��͑����������A�g�p�̎葱���͌��\�ώG�ŁA�g�p������̃A���v���A�c�t����������ȂǁA�Ђ̍ۂ̑c���̐^���ȕ\��̃��[�c�������ł����B�Ђ̍ۂɎ����S�����Ӗ����ʂ����������Ƃ͑傫�ȐS�̗ƂɂȂ��Ă���B
�u�Ή��ɂ��v
�@�S�Ă��Ă��s�����u�Ή��v�Ɂu���I���͂Ə́v�������A�s��Ȏ����Ă����z���A���g����B
�u���������v
�@������Ȃ��܂܂ɓ��������A���ɂł������Ĕ��������ł������E�E�B�R������Ύ��̍Œ��ɂ����Ă��̂��Ƃ������痣��Ȃ������B
�@
�@���ł����͐H�i�����ɁA�H��ɗ��Ă���o���������Ȃǂ�����ΐS�����킮�B����̐H��ł���A���p�ɑ傫�߂̃u���b�N���p�ӂ����B�ő��ɏo�����邱�Ƃ͂Ȃ������i�X�ł͗��̈���ȂǁA�Ɛ肷��B����Ȃ���Η��̈���A�܂��͗��Ă����̂��̂��u���b�N�Œlj���������B
�@�K���A�Ƒ������͂��܂藑�Ă����D�܂Ȃ�����A�W�߂ĐH�ׂĂ����܂蕶��͌���Ȃ��B
�@�ӂ�ӂ�̐H���A���Â߂̂������������D�ނ��A�����͉��͐[���悤�ł���B��������͂Ȃ������ł��邪�A�����ł͗������Ȃ��B�o���ꂽ�i��W�X�Ƃ��������B���C���O�ʂɏo�閡�̂͌��ł��邪�A���͖����ł���B
�@���̓x�ɉЂ̍ۂɐH��ɒu�����܂܂ɂ������Ă������v���o�����B���́A�\�ʂ̏ł��ڂ̖͗l����A�ڂ̑O�Ƀ`���`������B
�@�Ђ̐h���L���͂��낢�날��B
�@���ƂȂ��Ă݂�Η��ɑ���v������́A�Ђ��c���Ă��ꂽ�K���ȋL���̈�Ȃ̂�������Ȃ��B
11/18�i�y�j�I���~�J
2:20�N���B�����̔@���B�����������S�B�Ǐ��B9:00�Ɠ��͎��ȂɁB�Ǐ��ȂǏI���߂����B���V���`�F�b�N���̑��B�����A�Ǐ��B�[�����A�������ቹ�A�����Ԗ苿���B�n�����������B19:00�[�H�A20:30�A�Q�B�����v4259���B�{���͕a�@�ɍs�����A�قƂ�ǎ����ʼn߂������B
����Җ��(9) �u����ҒB��A�M�������͂ǂ����������̂�!!!�v(5) �Վ��̐Â���
�@����҂̉������Â̍������x�~����ɂ�����A�{���́u��ɂĉ]�Ӂv �Ƃ������𖡂킢�������B
�@�{���Ƃ����� �u�J�ɂ��������v�u��͓S���̖�v�u�����̑��������X�v �Ȃǂ̌��삪���邪�A���́u��ɂĉ]�Ӂv�ŕ\�����ꂽ�Վ����̐Â����̐S����D�ށB
�ȉ��Ɏ����B
�w��ɂĉ]�Ӂx�@�@�{��
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
���߂ł����@�Ƃ܂�܂����
���Ԃ��ԗN���Ă��ł������
��ӂׂ���˂ނ炸�����o�Â��Ȃ���ł�����
������͐�����Ƃ���
�ǂ����Ԃ��Ȃ����ɂ����ł�
����ǂ��Ȃ�Ƃ��T���ł���
�����������߂��̂�
����Ȃɐ��炩����肠�����ėN���₤��
���ꂢ�ȕ�������ł���
���݂��̛c��Ɩт̂₤�ȉԂ�
�H���̂₤�Ȕg������
�č��̂����a���̂ނ�������ł�
���Ȃ��͈�w��̂��A�肩�����͒m��܂���
�����t���b�N�R�[�g��������
����Ȃɖ{�C�ɂ��낢��肠�Ă����Ă����U����
����Ŏ���ł��܂Â͕��������܂���
�����łĂ��ɂ��T�͂炸
����Ȃɂ̂ŋꂵ���Ȃ��̂�
��鮂Ȃ����炾���͂Ȃꂽ�̂ł�����
���U�ǂ������̂��߂�
������]�ւȂ����Ђǂ��ł�
���Ȃ��̕�����݂��炸��Ԃ邯�����ł�����
�킽�������猩����̂�
����ς肫�ꂢ�Ȑ����
�����Ƃق���������ł��B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�@����҂̉������ÂƂ̊֘A�ł����ǂނ͔̂��������ł��낤���A�����ɕ\�����ꂽ�Վ���Ԃɂ���a�҂̐S�̐Â����A�����D���Ȏ��ł���B���x���f�����Ă�����`����Ă���̂��A�{�l�͈����̏�Ԃɋ߂��B
�@�����ՏI�O�ɑ����̊��҂ɖK���u�a�₩���v�̗l�q�̗l�Ɏv���邪�A���̈����̎��Ԃ𗐂��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ǝv���B
11/17�i���j�I���~�J�@��Ȓ��ʕa�@�@�����v���s�ɓ���
1:45�N���A�k�R���B5:30�R�S�~�A7:35Taxi�A�M���M���Ԃɍ������B8:11���܂��A��Ȓ��ʕa�@�O���B��ȕ�Taxi�B���艮�o�R15:30�a�@�B�x�����H�A16:30�a���Ɩ��B�V���`�F�b�N+���́A19:00�A��A�[�H�B21:00�A�Q�B�����v��7839���B�l�p�������K�B�����v���s�ɓ����B���ɂ܂�300Km�A3328�����A26630Km/3877���B
����Җ��(8) �u����ҒB��A�M�������͂ǂ����������̂�!!!�v(4) �������Â̍s������
�@�����̈�w, ��Â̐��E�ł͊��Җ{�l�̎��Ȍ��茠�̑��d����{�ɂȂ��Ă���B�ŋ߂͖{�l�̈ӎv�m�F������ȏꍇ�͉Ƒ����̏��ސ����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B
�@Advance Care Planning(ACP)�͐l���̍ŏI�i�K�ɂ����āA���Җ{�l�̈ӎv�d������ÁE�P�A������悤�ɂ��邽�߂ɍs����B�{�l�E�Ƒ��E��Ï]���҂Ƃ̘b�����������Ƃɖ{�l�̈ӎv���肪�s���邽�߁A���҂̊�]���Ƒ��E��ÁE�P�A�̊W�҂��������₷���B
�@���Ƃ��Ή������Â��邩�ۂ����d�v�ȑI������1�ł���B
�@�l�́A���ɍ���҂́A���A�ǂ�ȂƂ��ɐl���̍ŏI�i�K���}���邩������Ȃ����߁A�N����ACP���������Ă����K�v������B
�@ACP�ł́A�ӎv����ɂ������āA��Ï]���҂�����I�ȏ���������s���A���������Ƃɖ{�l���͂��߂��܂��܂Ȑl���ӌ����q�ׂĘb���������i�߂��čs���B
�@�������Ȃ���A���ɉ������Âɂ����Ă͂��̏��͕�I�ł��낤�Ƃ������قǓ���B���������l�́u���̂��v�͂���̂��̂��Ƃ������ɋA���邱�Ƃɂ��Ȃ�B�u���̂��v�� �@ �����̂��́A�A �Љ�̂��́A�B �_�l(?)�̂��̂Ƃ��A�����ȍl����������B��Ï]���҂ƌ������l�́u���̂��v�ɉ�����Ă������̂��H
�@���́u���̂��v�͍ŏI�I�ɂ͎����̂��̂ƍl���邪�A�e�l�͎Љ�̒��ʼnƑ��ȂǂɎ���Đ����Ă���킯�ŁA�Љ���Ă̎��Ȃł���B���̂悤�ɁA���҂̎��Ȍ��茠�̑��d�Ƃ����Ă��l�Ԃɂ� �u���ʌ����v ������̂��ƌ�����Ɠ��͓���A����������E������B
�@�����w�҂̒r�c���F���勳���́A�u���̂��͎����̏��L���ł͂Ȃ��B������A���ʌ����͂Ȃ��v�Əq�ׂĂ���B
�@���́u���̂��͎����̂��́A������A���ʎ��R������������v�Ǝv���Ă���B�������A�����ȒP�ɂ͎Љ�I�ɃR���Z���T�X�͓����Ȃ����낤�B
�@�������u�A���Ɍo�@�݊ǁA��ᑂ���̉h�{�⋋�A��Ö��I�h�{�⋋�̖��_�������Ă݂�B�����͎{�s�����͖�肪���Ȃ����A���Ԃ������Ȃ�ƈȉ��̂��Ƃ��̎�X�̖�肪�����Ă���B
--------------------------------------------------------------------
�Ώێ҂̑����̓x�b�g��̂قڐQ������̏�ԂƂȂ�
�`���[�u���s�p�ӂɔ�����Ȃ����߂Ƀx�b�g�ɔ�����
���̌��ʁA�S�g�̊߂��S�k����
�̈ʕԊ҂��܂܂Ȃ炸�A��ጂ��ł��₷���Ȃ�
�뚋�̂��߂ɔx���A�C�������ǂ������₷��
�\ႂ̋z�����p��ɂȗ��A���ɂ͋C�ǐ؊J��v����
�_�f�z�����K�v�ɂȂ�
�p��̊����A���M�ōR���ܗÖ@���K�v�ƂȂ�
�e��R���܂ɑϐ��������ϐ��ۊ����ǂŎ��Ì��ʂ��R�����Ȃ�
�S���Ƃ��Ő��_�����̈�w�̒ቺ��������
�s�K�؍R���A�z���������傪������Na�ǂɂȂ�ӎ���Q���i��
�h�{��Ԃ��������A�Ɖu�\�ቺ��ԂƂȂ�
�S�g�ɕ��������
�ȂǂȂ�
--------------------------------------------------------------------
�@����������Â������ėǂ������A�Ƃ����Ƒ�������B
�@�������A���͕K�����������v���Ȃ��B
�@�������Â̍s�����͂��̐��̒n��(?)�Ǝv���B
11/16�i�j�_��Ȃ������@�H��X�^�b�t���K
�@2:00�N���A���������A�k�R�Ȃǂ����̂��Ƃ��B8:30�Ɠ��ƕa�@�@�V��������B11:00�H��X�^�b�t���K�A�V�����͂ق��Ǐ��B14:00�a���Ή��A16:30���҉Ƒ��ʒk�A�Љ��쐬�B19:15�A��A�[�H�A21:00�A�Q�B�����v5646���B
����Җ��(7) �u����ҒB��A�M�������͂ǂ����������̂�!!!�v(3) ���O�w������ACP�ɂ���
�@���t�{�̒����ɂ��ƁA�a�C�����ɂ���Ė��̊�@�ɂ��炳�ꂽ�Ƃ��A����҂�91.1�����u�����݂̂�ړI�Ƃ�����Â͍s�킸�A���R�ɔC���Ăق����v�Ɖ��Ă���(�o�T�F���t�{�u����25�N�� ����Љ���v)�B
�@�������A���݂̍���҈�Â̎��ԂƂ͑S���l�����قȂ��Ă���B����҂͎��O�ɏ�L�̎|��\�����Ă����Ȃ��ƁA�ӂɉ���Ȃ�������Â���\�����傫���B�����������邽�߂ɂ͌��C�Ȃ����ɁA�s���̕a�C�⎖�̂̍ۂɂǂ����邩�A�F�m�ǂ��i��ňӎv�\�����ł��Ȃ��Ȃ������ɂǂ����邩�A�Ȃǂɕ����Ď����̍l�����L�ڂ��Ă����ׂ��ƍl����B
�@2018�N�����炻�̈ӎv����̉ߒ���⏕����l���������܂�ė����B���ꂪAdvance Care Planning(ACP)�̓����ł���B
�@ACP�́A�l���̍ŏI�i�K�Ŏ��Â�P�A�Ȃǂɂ��āA���Җ{�l�ƉƑ��A��Ï]���҂Ȃǂ����O�ɌJ��Ԃ��b���������g�݂̂��ƁB
�@ACP�̈ȑO����A�ꕔ�̐��҂Ȃǂ̊Ԃł́u���O�w�����v�ƌĂ�镶���ɂ��ӎv�\�����s���Ă����B���O�w�����́A�����a�C�₯���ȂǂŎ������ӎv����ł��Ȃ���ԂɊׂ����ꍇ�ɁA���f���ς˂�l���A������ÁE�P�A�A�����Ȃ���ÁE�P�A�Ȃǂɂ��ĕ������������ނ̂��Ƃł���B
�@���O�w������ACP�̑傫�ȈႢ�́A�ӎv����̍ۂɉƑ����Ï]���҂Ƃ̘b���������s�����ۂ��ɂ���B
�@�u���O�w�����v�ł͒N�Ƃ��b���������s���K�v���͂Ȃ����߁A���O�w�����ɋL�ڂ��ꂽ���e�ƉƑ��̈ӌ����傫���قȂ邱�Ƃ����肤��B���̏ꍇ�A��{�I�Ɏw�����ɋL�ڂ���Ă�����e���D�悳���B�܂��A���O�w�����̓��e����ÓI�Ɏ��{�s�\�ł�����ۂ����ꍇ������B
�@ACP�͉Ƒ��E��Ï]���҂Ƃ̘b�����������Ƃɖ{�l�̈ӎv���肪�s���邽�߁A���҂̊�]���Ƒ��E��ÁE�P�A�̊W�҂��������₷���B
�@
�@�l�͂��A�ǂ�ȂƂ��ɐl���̍ŏI�i�K���}���邩������Ȃ����߁A�N����ACP���������Ă����K�v������B
�@�������A���ɂ͐l���̍ŏI�i�K�ɂ��Ď��O�ɍl���邱�Ǝ��̂Ɍ�����������������B�܂��A�����̂��Ƃ𑼐l�Ƒ��k���邱�Ƃɑς����Ȃ��l������B���̏ꍇ�́A�܂��͎������ǂ��������̂��l���Ă݂邱�Ƃ���ł���B
�@���͂��łɎ��O�w�����͍쐬�ς݂ł�����J���Ă���B
�@���͎����́u���̂��v�͎����̂��̂ƍl���Ă���B������A���ɍۂ̂���悤�ɂ��ẮA�Ƒ����n�ߑ��l�ɑ��k���邱�ƂȂǂ͍l�����Ȃ��B������AACP�͂�藝�z�I�Ƃ͗������Ă��邪�A�����̂��߂�ACP�Ȃǖ��p�ł���B
11/15�i���j�܂菬�J�@
1:00�N���A�V��������ǂݑ����X�B�l�R�̐��b�A���a�B8:30�Ɠ��ɓ���a�@�B�V���`�F�b�N�{���́A11:00�a���A�����A14:30�����J���t�@+EC+���ҏ��u�B����Ҋ֘A�����ǂ݁B19:20�A��[�H�A20:45�A�Q�B�����v5348���B
����Җ��(6) �@�u����ҒB��A�M�������͂ǂ����������̂�!!!�v(2)
�@���݂̘V�l�́u�Љ�̃}�W�����e�B�v�Łu�Љ�̉B�ꂽ����v�ł�����B�ہA�B��ĂȂǂ��Ȃ��A�^�̎����������Ȃ��B
�@�䂪���̕��ώ����i�O�̕��ϗ]���j��2022�N�j81.05�N�A����87.09�N�Ȃ�B ���, ���������\�Ȑ����N��u���N�����v��2019�N�Œj��72.7�A����75.4�ł���B
�@�����̉����ƂƂ��Ɂu�Q������v�Ɓu�F�m�ǁv�̑������Љ��艻������B
�@������̕S���҂̌����ł́AADL(���퐶���@�\)�ʂ̊����́C�ǍD�Q�ƒ��ԌQ�����������20%�C�s�njQ����60%�ł������B�j�������������A�j��ADL�͗ǍD�B ADL���s�njQ�ł͔]���ǎ����ƘV�l���F�m�ǂ����������B�S���ґS�̂̍ݑ��66%�ł������B
�@�u���N�����̉��L�v����������҈�Â̖ڎw���Ƃ���ł��邪�A�������A����Ҋ֘A��Ï]���҂̎��Ԃ́A�����܂߂āu�Q������v�Ɓu�F�m�ǁv���҂̐��b�Ɖ����ɔ�₳��Ă���B��Ï]���҂Ƃ��Ă����̕���̋Ɩ��͏d�v�ł��邪�ꖕ�̋�����������B
�@�l�ɂ͂��ꂼ��, ��������, �l�Ԑ�������B�قȂ������l�ς��݂��ɔF�ߍ����鑽�l�Љ�Ȃ����Ă͗ǂ��l���͂Ȃ��B���C�Ȏ��́u �V��V���B��Ƒ��v�ł������A�l��, ���܂��Ɠ����Ɏ��ւ̗��H���n�܂��Ă��邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@ �Ō�܂Ŕ]�Ɛg�̂̊��͂�l�Ԃ炵���ۂ��Ȃ���A�ŏI�i�K�łǂ̂悤�ɐ����A�ǂ̂悤�Ɏ��ʂ̂�����邱�ƂɂȂ�B
�@���͒��ʃ��n�r���e�[�V�����a�@�×{�a���ō���҈�Â�S�����Ă���B
�@���͉Ƒ��ʒk���d������B�����댻�ݎ厡��Ƃ��Ď����Ă���20���̊��҂̂����A��f���Ɏ��Ɖ�b�\�Ȋ��҂�5�l�ɖ������o�ljh�{�A�Ȃ����_�H�A�_�f�z�����Ȃ���V��̖͗l�������ƌ��߂Ă��邾���H�H�����犳�Җ{�l���ǂ������l���ň�Â��Ă��邩�m�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�@���Җʒk�̍ۂɕK���m���߂�̂́A
�@(1)�u���{�l�ƔF�m�ǂ�v����ԂɂȂ�����ǂ����������̂��A�b�����������Ƃ͂���܂����H�H�v
�@(2)�u���{�l�̎����ς��m���߂����Ƃ͂���܂����H�H�܂��͂��̂悤�ȐS������������͂Ȃǂ͂���܂����H�H�v
�@�E�E�E�ł��邪�A���܂Ŗʒk�������Ƒ��̂�30�Ƒ��ȏ�ɂ��Ă����u����܂��E�E�E�v�Ɠ������Ƒ��͑S���Ȃ��B
�@���Җʒk��ʂ��ẮA���Ƒ����@���Ɋ��҂��ɂ��Ă��邩���M���m�邱�Ƃ��ł���B�e�F�s���q�A���B�ł���͂قڗ�O���Ȃ��B
�@�������A�u�e�̎����ς�m�炸���Đe�F�s�ł���̂��v�A�u�ǂ�ȏ�Ԃ��}���Ă��Ђ����璷�����肤�̂͐^�̐e�F�s�ƌ�����̂��H�H�v�A�������āu���ʓI�ɐe�ɋ�ɂ������Ă���̂ł͂Ȃ����H�H�v�A�u�E�E�E�E�E�v�B
�@���̑f�p�ȋ^��ł���B
11/14�i�j�I���~�J�@���ʕa�@���ȊO���@�@
�@1:15�N���B�V��������ǂ݂Ɩ{�ǂ݁B5:30�R�S�~�o���B6:40�o�X�a�@�B7:00�18:20�a���Ή��A8:45-13:00���ʕa�@�O���B���敾�B13:30-15:30�n���B�a���Ή��A�V���`�F�b�N+���́A���������B19:15�A��A�[�H�A21:00�A�Q�B�����v8387���B
����Җ��(5) �@�s���̕a�ɂ������t�̐Ӗ��̍l�����̕ϑJ
�@16~17���I�̃C�M���X�̎v�z��F�E�x�[�R���́A���� �u�w��̐i���v �̒�
�ŁA�u��t�͊��҂̌��N�������邾���łȂ��̌����݂̂Ȃ��a�C�ŋ�ɂɔY�܂���Ă��銳�҂ł͑����Ђ��Ƃ点��ɂ���菜�����Ƃ��C���ł��낤�v �Ƃ�, ��������y���ƌĂсA���m�̐l�X�̊S���W�߂Ă����B
�@�������A���ۂɂ́A���̍s�ׂ͎E�l�ɑ�������̂ŁA��t�͉��S�ł��Ȃ����Ƃł������B
�@�����̗�����ł��鏏���^��(1810�`1863)�̓h�C�c�l��t�t�[�t�F�����h�̒����ɂ����̓����ɂ��Ă̋L�q��u����v�Ƃ��čL�߂����A���̒��� �u���Ƃ��a�C���A���͂�d��Ȋ�@�Ɏ����Ă���Ƃ͂����A��t�Ƃ��Ă����S���~�ς̎肪�Ȃ��ȂǂƂ͒f�肷�ׂ��łȂ��B�q�g�̐�����ۑS���A�w�߂Ă�����L���߂�̂́A��t�̍ő�̖ړI�ł���v�Ƃ��Ă���B���̍l���͉䂪���̈�t�̗ϗ��Ƃ��Ē����ԏd������Ă���.
�@���オ����A 1960�N��㔼�ɂȂ�ƁA ���ɐl�H�ċz�킪�i�����y���A�ӎ����Ȃ��l�H�ċz��ɂȂ���A���R�Ɛ������炦��悤�Ȋ��҂��ڗ��悤�ɂȂ�A���̂悤�ȏꍇ�ɂ͐l�H�ċz������O���ׂ��ł���Ƃ����l�����䓪���Ă����B
�@���̂���A�����J�𒆐S�Ɉ�Âɂ����銳�҂̎��Ȍ��茠�̑��d�Ƃ����l�������y���A���҂̈ӎv����������e�F���悤�Ƃ����l�����N�����Ă����B�������A�I�����ɂ��銳�҂͂��łɐ���Ȕ��f���ł��Ȃ��ɂ��邱�Ƃ������A���̂悤�ȏɎ���O�ɂ��炩���߂��̈ӎv���ɂ��Ă����A �I�����ɂȂ������t�Ɉӎv�d���Ă��炢�������Â̍����T���⒆�~��F�߂����悤�Ƃ������ƂŁA���̎��O�w�����̍쐬�𐄐i����Љ�^��������ɂȂ����B����Ƀx�[�R���̌����A������ϋɓI���y�����e�F���悤�Ƃ����l���������Ȃ����B
�@ ���ɂ䂭�ߒ��ɂ��Ĉ�t�̖��������G�ɂȂ��Ă����B��t�͂��̐����ɂ��������ɂ��ĉ����d�v�Ȗ��Ȃ̂����\���ɗ������Ă������Ƃ��̗v�ł���B���̍ۂ̃L�[�|�C���g�͊��Җ{�l�̈ӎv�m�F�ɂȂ�B
�@���̍��A�ː��s���a�@���������炩�ɂȂ����B
�@2006�N3���ː��s���a�@�ŁA����50�̊O�Ȉ�t��78�̓��@���҂̐l�H�ċz������O�����Ƃ���A�s���R�ȓ_�����������߂ɁA�a�@���������n�ߌx�@�ɓ͂��o���B
�@2008�N�ɁA�x�@�͖���7���̂����Z���̎厡�ゾ�����O�ȕ�����l���E�l�e�^�Œn���ɏ��ޑ��������B
�@�ŏI�I�ɕs�N�i�ƂȂ������������Âɏ��ɓI�ȍl���������͎厡��ɋ����������̂ł������B
�@���̎������@�ɖ{�l�̈ӎv�m�F���ł��Ȃ��Ƃ��͉Ƒ����̘b����{�l�̈ӎv�𐄒肷��������F�߂���悤�ɂȂ�A�������u���f�̏����������ɘa����鎖�ɂȂ����̂͘N��ł������B
11/13�i��)�@�����~�J�I���@��������@���N�N���j�b�N�h�b�N�@�@
�@1:00�@�l�܂�ꂵ���ċN���B���������A�~�σf�[�^�����B�k�R�B6:40�o�X�a�@�ɁB7:00-8:45�a���Ή��B9:00-11:30���N�N���j�b�N�h�b�N13��+���ʔ���15�����B11:45�a�@�B�V���A��w�_���`�F�b�N�B�����B13:00���҉Ƒ��ʒk�A�C�ǐ؊J�W�B���@���ґΉ���B�f�[�^�����A19:15�A��A�[�H�B 20:45�A�Q�B�����v7347���B
����Җ��(4) �@�������ÁA�^�[�~�i���P�A�A�ɘa�P�A�Ƃ�
�@�l���̏I�������}�������҂̑I�����Ƃ��āA���͎��R������ԂƎv�����قƂ�ǎ^���������Ȃ��B
�@�H���������Őۂ�Ȃ��Ȃ������A��X�̎����Ōċz�̈ێ����ł��Ȃ��Ȃ������A�����̐t���̋@�\�Ő������ێ��ł��Ȃ��Ȃ������Ȃǂɂ́A�ꎞ�I�ɐ������ێ�������@���m�����Ă���B����ɂ́u�l�H�h�{�⋋�v�Ö@�A�u�l�H�ċz��v�Ö@�A�u�l�H���́v�Ö@���܂܂��B
�@��p��������B
(�P)�������ÂƂ�
�@�������ÂƂ́A�V����a�C�ɂ�萶���̈ێ�������Ȃ������҂ɑ��A��ÓI�[�u�ɂ���Ĉꎞ�I�ɐ������Ȃ��s�ׂ������B
�@�u�l�H�h�{�⋋�v�Ö@�͂��܂�ɂ���y�ɍs���Ă��邩�牄�����Â��Ǝv���Ă��Ȃ���ÊW�҂�����B
�@����ɂ���āA�����ł����������Ăق����Ƃ����Ƒ��̊肢�͎���������̂́A�l�X�Ȗ�肪�����Ă���B���҂ɂƂ��Ă͐Q������A�A�ւ̐��ꗬ���A�x�b�g�ւ̍S���ȂǂȂǁA���̐��̒n���̎n�܂�ł���B
�@�Ⴆ�A�{�l�̈ӎv���m�F�ł��Ȃ��܂܂ł̉����[�u�������������ƁA�{�l�ɋ�ɂ�^���Ă��܂��\��������A�����[�u�𒆎~����ꍇ�̖@�I��肪���邱�ƂȂǁE�E�E�̖��������B
�@������l�͑S�������}���邪�A���̍ۂɂǂ��܂ň�Â�������̂��A�{�l�̈ӎv���m�F���Ă������Ƃ��K�{�ł���B�q��@�ɗႦ��A�ړI�n�ɃX���[�Y�ɒ�������̂��A�r���Œė�����̂��A�s��������̂��E�E�E�ɑ�������d��Ȕ��f�ɑ�������B���҂���]����l�͂���̂��낤���H�H
(�Q)�^�[�~�i���P�A�Ƃ�
�@�^�[�~�i���P�A�Ƃ́A�]�����Z���Ɣ��f���ꂽ���҂ɑ��A�c��̎��Ԃ����҂������K�ɉ߂�����悤�A��ÁE�Ō�E���Ȃǂ̑��ʓI�ȃA�v���[�`�ŃP�A���邱�ƁB
�@���̎�ȓ��e�́A�ȉ���3��ނɓZ�߂���B
�u�g�̓I�P�A�v�͒ɂ݂̊ɘa����̉���
�u���_�I�P�A�v�͎��ւ̕s����c���ꂽ�Ƒ��ւ̔z���ȂǁA�S�̖��̊ɘa��}��
�u�Љ�I�P�A�v�͈�Ô�Ȃǂ̌o�ϓI�s����Љ�I�ȌǗ����Ȃǂɑ���P�A
�@��ÓI�ɂ͉����[�u�A���Âւ̈ڍs���\�ł��邪�A������]�܂Ȃ��ꍇ�ɂ̓^�[�~�i���P�A���d�v�ɂȂ��Ă���B
(�R)�ɘa�P�A�Ƃ�
�@�ɘa�P�A�Ƃ́A����Ȃǂŕs���̏�ԂƐf�f���ꂽ���ҁA�����̉\�������邪���Âɓ�a���銳�҂��邱�Ƃ��ł��鑍���I�ȃP�A�������B�ɘa�P�A�̖ړI�́A�g�̓I��ɁE���_�I��ɁE�Љ�I�s���Ȃǂ��ɘa�����邱�ƂȂ̂ŁA�^�[�~�i���P�A�Əd�����镔��������B
�E�E�E�E�E�E
11/12�i��) �܂芦���قڏI���~�J�@���ԃX�g�[�������Ə��_��
1:30�N���D�v�`����ɃO�_�O�_�B�Ǐ��B�����Ȃǎv�����܂܁B4:30���[�`���ɓ���B�����Ɠ��S���̊��Ҏ����ŏo�B���H�ANHK�̂ǎ����B�V���`�F�b�N�A�����㋏�ԃX�g�[�������Ə��_�A�����C���͕s�\�@��ł��邪�A�@�\�I�ɂ͖��Ȃ��B���N�����낤���B�@����Ӑ����B���������A�Ǐ����S�B19:00�[�H�B20:30�A�Q�B�����v��4984���B
����Җ��(3) �H�ׂ��Ȃ� �� ���������Â��J�n����邪�����ɍő�̖�肪����
�@�H�ׂ��Ȃ��Ȃ����@���@���������ÁA���Ȃ킿�h�{�⋋���J�n�����B
�@���̎��_�ʼn����Ɋւ��đ傫�Ȗ�肪����̂����A�N������[����������Ȃ��܂܁A���҂̈ӌ����m���߂邱�Ƃ��Ȃ������̉������Â��J�n�����B����A���܂�ɂ�������O�̎��ÂɂȂ��Ă��邩��A�������ÂƂ����ӎ�����قƂ�ǂȂ���ԂŁA�������Â��J�n����A���X�ɔߎS�ȏ�ԂɂȂ��Ă����B
�@�h�{�⋋�̃��[�g�Ƃ��Ă͏����ǂ̋@�\�𗘗p������@�ƐÖ����h�{�⋋������B������n���\���@�\�����Ԃł���Γ��R�����ǂ̋@�\�𗘗p���������莩�R�Ȃ����ł���B
�@��ʓI�ɂ̓J�����[�̏��Ȃ��_�H�Ő����𒆐S�ɓ��^���Ȃ���A�����P���Ȃ��ƌ���ƌo�@�o�ljh�{�Ɉڍs���A�����ɋy�Ԃ悤�ȏꍇ�Ȃ炻�̌�Ɉ݂낤���݂����߂���B�����ɂ͂���ł��뚋�������Ȃ�킯�ł͂Ȃ��B�뚋���x���͎��ɂ͐����邪�A���ʂ͂܂����炭�͐������邱�ƂɂȂ�B
�@�o�@�o�ljh�{�͈��3������A����ɗp���Ă���ǂ͕@������ꑱ���Ă���̂��ʏ�ł���B
�@�Z���Ԃł���Ƃ������A�����ԕ@�Ɋǂ������Ă���Ɋ��҂͑ς��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����͌����ėǂ����Ƃł͂Ȃ��B���҂��s�����������ɁA�@�Ɋǂ������Ă���͌��Ă����������l�ԓI�ł�����B���̖ʂŁA�������̂悤�Ȍ`�ʼnh�{�⋋����������}��̂ł���Έ݂낤���݂����߂���B
�@����2012�N�ɒ��ǂ��N���������A���̍ۂɕ@����C���E�X���Ƃ�����⑾�߂̃`���[�u������4���ԉ߂������B���̎��Ì��ʂ��Ȃ���p�������A�@�̃`���[�u�͉�������ɂ��s���A�\���ɖ��邱�Ƃ��ł��Ȃ������B��p�ɂ���ĕ@�̃`���[�u����������z�b�g�������A���ꂪ���Ɏ���܂ő�������Ƃ����犳�҂�QOL�͖����ɂɓ������A�Ǝ��������B
�@�X�ɁA�o�@�݊ǂ�2�T�Ԗ��Ɍ�������K�v�����邪���̑�������҂ɂƂ��Ă͐h���Ǝv���B
�@�ʂȕ��@�Ƃ��ē_�H�ʼnh�{��⋋����Ƃ������@�����邪�A����ɂ��Ă͕ʂɘ_�������B
�@���ǁA�o�@�݊ljh�{�⋋�ł����Ă��A��ᑑ��ݎ҂ł����Ă����̑Ώێ҂͂قڑS��������ɂ��g�̋@�\��Q��뚋���x���x���̌J��Ԃ��ɂ���ĂقƂ�ǐQ�������ԂŁA�r�����܂߂đS���Ԃɂ���B���̗l�ȕ��X���L�����U�����Ă���p�ȂǗ\�z���ł��Ȃ��B
�@�`���[�u������Ȃ��悤�葫���x�b�g�ɔ����A�I�������ƓV������߂Ă��邾���̐l���B
�@���������l���Đ����Ă���̂��낤���H���̖₢�ɑ��ē����銳�҂͂��Ȃ��B
�@���������͎����猩��ΔߎS�A�n���̈ꌾ�ł��邪�A���͈̏�Î҂̈��ՂȎ��Õ��j�ƉƑ��̈ӌ��Ō��܂��Ă���̂����낵���B
11/11�i�y�j�~�J�������犦�g�@�Ɠ��]���^��
1:45�N���B�Ǐ��A�摜�f�[�^�����B�����Ɠ����B�l�p�����A�Ƃ�������������K�B11;30�]���^���ɍs���Ɠ��ɓ���A�a�@�ɁA�J�b�v�J���[���H�ɁB�\���������B�Ǐ��A�����B�a���Ɩ��w�ǂ����B�����֘A�̕��B19:00�A��B�[�H�A20:30�A�Q�B�����v��5309���B
����Җ��(2) �H�ׂ��Ȃ��Ȃ��������I���Ȃ̂����E�E�E�E
�@�V�N�҈�ẪR�A�ƂȂ�_��, �u�����ǂ������A���Ɍ������{�l����т��̉Ƒ��̃P�A���ǂ��i�߂Ă������v�Ƃ������Ƃɂ���B
�@�܂��A���̃e�[�}�A��{�͉������Âɂ��Ăǂ��l���邩�A������Ƃ������Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂��E�E�E�ɓ��B����̂ł��邪�A���g�߂Ȗ�肩���̓I�ɍl���Ă݂����B
�@����҂͊e��̎����݂̂Ȃ炸����ɂ���Ă����������H�ׂ��Ȃ��Ȃ鎞�����}����B�H�~�������Ă����������܂������Ȃ��Ƃ�����Ԃł���B
�@�ʏ�͐�E�����̐_�o�E�ؓ��E�H�������݂ɘA�g���ĐH�ׂ����̂��݂ɑ��荞�ނ̂ł��邪�A���炩�̗��R�ł����̋@�\�̂����̂ǂꂩ������ɓ����Ȃ��Ȃ�ƁA�H�����C�ǎx�̕��ɂ������Ă������ɂȂ�B���ꂪ�u�뚋�v�ł���B�u�뚋�v�̌��ʁA�p�ɂɔx�����N���Ă��܂��B �x���͈�w�I�Ή����ň�U�͎��邪�A�Ăь뚋���Ĕx�� ���J��Ԃ��B
�@�u�뚋�v�͐H���������ɐ�����̂ł͂Ȃ��B
�@����҂̏A�Q���ɁA���t��ݓ��e�����������C�ǂɓ��錻�ۂ͕p�ɂɊm�F�����B���o����ꀋۂ��ɐB����s���ȏꏊ�ł���B���̂��߂Ɍ��o�P�A�����߂��Ă��邪�A�Z���Ԃł܂�ꀋۂ����B����B���̂悤�ȏ�ԂɂȂ�ƁA������H�ׂ�킯�ɂ͂����Ȃ��Ɣ��f�����B
�@���̏�Ԃ͐l�ԂƂ��Đ�����\�͂Ɍ��E���}�������Ƃ������Ă���B���͂��̏�Ԃ��q�g�Ƃ��Ă̈�̐ߖڂƍl����B
�@���̎��_�ł̎��Ï�̔��f���ƂĂ��厖�Ȃ̂ł��邪�A����҂̎��Âɂ������Ă���厡��̑啔���́A�[���l���������ɊȒP�ɉ������Âɓ����Ă����B�Ƒ��������m��Ȃ��܂ܑ啔�����̕��j�ɏ]���Ă����B
�@
�@���Ղȉ������Â̓����������A���҂ɋ�ɂƔE�ρA�n���̋ꂵ�݂������鎖�ɂȂ�̂����A��Î҂��Ƒ����[���ւ�邱�Ƃ����Ȃ��B
�@���͉������Âɂ͏��ɓI�ȍl��������t�ł���B
�@����50�N�قǂ̈�t�����ŒS������������ԁA�ߖڂ��}�������҂̂����A���{�l�y�т��Ƒ������̎��Õ��j�ɔ[�����ē_�H��o�ljh�{������Ȃ��Ŏ��S���ꂽ���҂�10�����ɖ����Ȃ��B
�@�_�H�Ő����݂̂𓊗^���A��r�I�Z���Ԃł��S���Ȃ�ɂȂ������҂͂�50���ɖ����Ȃ��B
�@�l�̏I�����̎��ÁE�P�A�̍l�����͖�肪��������ł���B
11/ 10�i���j�܂�ƍ~�J�@��Ȓ��ʕa�@�O���@
�@1:15�N���A�Ǐ��B5:30�R�S�~�A7:35Taxi�A8:11���܂��A��Ȓ��ʕa�@�O���B��ȕ�Taxi�B���艮�o�R15:30�a�@�A���H�̓X�e�[�L�������B16:00���҉Ƒ�PICC�ʒk�A�����B�V���`�F�b�N���͂ł����A19:00�A��A�l�p�����A�Ƃ�����������͂��B�[�H�B21:00�A�Q�B�����v��7215���B
����Җ��(1) �u����ҒB��A�M�������͂ǂ����������̂�!!!�v(1)
�@�{�N9��16���̌h�V�̓��ɂ��Ƃ��b�A�̘b�ɂ��鍂��҂ɂ܂��̘b���W�J�����B
�@���̍ۂ̌��_�Ƃ��ẮA�����̘V�l�́u�Љ�̖��҂̏����ҁv�ł��������A�̘b�̒��ł͂Ȃ�������ɂȂ��Ă���B����͖����̍��ɋ����̌��n���疳������ς�������ł���B
�@���āA����̓��{�͒�����Љ�E�V�l�Љ�Ƃ����A �V���E�G���E�l�b�g�ȂǁA�����郁�f�B�A�ɘV�l�Ɋւ���b�肪�オ��ʓ��͂Ȃ��B�����āu�V�l�����ߍ��ނ���o�ς����Ȃ��v�A�u�N���E��ÁE�������łڂ����˂Ȃ��v�A�Ȃǂǝ�������Ă���B
�@���݂̘V�l�́u�Љ�̃}�W�����e�B�v�Łu�Љ�̉B�ꂽ����v�ł�����B�ہA�^�̎����������Ȃ��B
�@���ꂩ��͌���̍���҂̏����A�Ƃ�킯����҈�Â𒆐S�ɂ��čl�@���Ă݂邱�Ƃɂ������B
�@�ߔN��킪���ł͏��q������������B
�@�����Ȃ�2023�N4���ɍ�N10��1�����_�ł�65�Έȏオ�̍���҂���3600���l�ŁA�������29.0%�Ƃ����\�����B�܂��A75�Έȏ�̐l���͖�1900���l�őS�̂�15.5%�ƂȂ����B
�@����1�l������̍��v����o������1.26�ʼnߋ��Œ�ƂȂ�A����1��2�疜�l�̐l����100�N��ɂ͔�����6�疜�l�ɂȂ�Ƃ����B
�@
�@�D�P�\�������������܂Ō������Ă��܂��Ƃ����ǂ̂悤�ȏ��q���Ă�������q�Љ�̓�����h�����Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�l�Ԃ̎����͖�120�����x�Ƃ����B�ߘa4�N�̕��ώ����i�O�̕��ϗ]���j�� �j81.05�N�A����87.09�N�Ȃ�B ������ƒZ���Ȃ��Ă���̂��������B
�@�����̉����ƂƂ��Ɂu�Q������v�Ɓu�F�m�ǁv�̑������Љ��艻������B
�@ ���, �����̂��Ƃ͎����łł���Ƃ������������\�Ȑ����N��u���N�����v�ł���, ���{�ł�2019�N�Œj��72,7�A����75.4�ƂȂ��Ă���B
�@���N�����̉��L����������҈�Â̖ڎw���Ƃ���Ƃ�����B�������A���Ԃ́u�Q������v�Ɓu�F�m�ǁv���҂̉����ɋ��o����Ă���B
�@�Â����u�Q��������@�@���₵�ā@���N�����E��(�ǂݐl�m�炸)�v
�@�l�ɂ͂��ꂼ��, ��������, �l�Ԑ�������B�قȂ������l�ς��݂��ɔF�ߍ�����Љ�Ȃ����Ă͗ǂ��l���͂Ȃ��B���C�Ȏ��́u �V��V���B��Ƒ��v�ł������A�l��, ���܂��Ɠ����Ɏ����n�܂��Ă��邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@�~��邱�Ƃ��l���Ȃ��ŗ��q�@���o�����邱�Ƃ͂Ȃ��B
�@ �Ō�܂Ŕ]�Ɛg�̂̊��͂�l�Ԃ炵���ۂ��Ȃ���A�ǂ̂悤�ɐ����A�ǂ̂悤�Ɏ��ʂ̂�����Ă��邱�ƂɂȂ�B
�@�������w�ҁE�g�쌹�O�Y�́u�N�����͂ǂ������邩�v��2017�N�ɖ��扻����ău�[���ɂȂ����B
(�������ǂ��������)
�@�u�[���̒[���ƂȂ��������́u�q�������ɐ�������l���̈Ӗ����l��������v��i�Ȃ̂����A���̏����̖₢�́A�ނ��덡�̃V�j�A����ɂ������ׂ��A�Ǝv���B
�@�u����҂�A�M���B�͂ǂ����������̂�!!!�v�ƁB
11/9(��)�@�������A��̉_�������@�@�@
�@1:50�N���A�����ǂ݂ȂǁB8:30�Ɠ��ɓ���A����R�C�ɋ��a�A�a�@���B9:30�a���Ή��A�Љ��쐬�B�����B�f�C���[���̐A�̂܂Ƃ߂ȂǁB14:00-15:00�K�X�a���Ή��A�G���ގ��������B19:20�A��A�[�H�A20:10�A�Q�B�����v��7300���B���ԃX�g�[�u��G���_�B���N�̏H�͔M�������B
�s�v�c�ȑ���u�]�v(7) �L���ɂ���(5)�@���������A�Ƃ������Ƃ͂ǂ��������ƁH
�@�l�Ԃ́A�ق��̓����������܂��܂ȓ_�ŗ���Ă��Ȃ���A������J�o�[���Ȃ��炱�ꂾ���̕����B����������A�l�Ԃ́u���������v�̂��낤�B
�@�����������玄�͂����Z�Ɣ�r����u�Z�������������E�E�v�ƌ����Ȃ������Ă����B�m����11�Ώ�̌Z�͎����͂悭���̂ƒm���Ă������A�b���Ă������Ƃ����X�܂Ŋo���Ă��ċ��������̂ł���B
�@�����́A�q���̎��́u�����ǂ��Ȃ�=�L���͂��ǂ��Ȃ��v�Ƃ����Ӗ��ő����Ă����B�R�����L���͎͂��Ԃ������邱�ƂŃJ�o�[�ł���Ǝv���Ă����B������A�����Z�̈�ɋ߂Â��ɂ͌Z�̉��{���w�͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��E�E�E�Ǝv������ł������A��w���I������܂ł͎��ۂ��̂悤�Ɏ����g�̕w������ݒ肵�Ă����B���ʂƂ��Ă�����ǂ������̂��낤�B
�@�������A11���̗��ꂽ�Z�Ɣ�r����Ă������Ǝ��̂��ُ�ł������̂����A���̎��o�͌��ʓI�Ɏ������������ɓ����Ă��ꂽ�B
�@���ƂȂ��Ă݂�u���̂悳�͋L���͂̂��ƂłȂ��v�A�u��C��ǂ߂đ��l�Ƃ��܂�����Ă����邱�Ɓv�ƍl���Ă���B ���l�ƐS��ʂ����킹�A���͂��ĎЉ�����肠���邱�Ƃ��A�l�Ԃ̓��̂悳�̖{���Ȃ̂��A�ƋC�Â����B
�@�l�Ԃ͈�l�ł͐������Ȃ��Љ�I�I�����ƌ�����B�u���̂悳�v�Ƃ����̂́A�Љ�Ɛ[���ւ���Ă���B�����������Ӗ��ł́A�ŋ߂̃R�~���j�P�[�V�����s���̕����͂ǂ�Ȃ��̂��낤���H�Ǝv���B
�@����̃R���s���[�^�͂�����v�Z�\�͂��f�����Ă��A�S�̗��_�������Ă��Ȃ��B ����AI�A�`���b�gGPT�Ƃ����ǂ��l�̐S��ǂݎ��A���܂��R�~���j�P�[�V�������Ƃ�\�͂ɂ����ẮA�l�Ԃ̓R���s���[�^�����͂邩�ɗD��Ă���B
�@���݂܂ł̒m���𑍍�����ƁA�����ȈӖ��ő��l�̐S��ǂݎ�邱�Ƃ��ł���̂́A���ׂĂ̓����̂Ȃ��Ől�Ԃ������Ƃ���Ă���B
�@����̍l�����e�Ղɔ��f�ł��Ȃ��ꍇ�ł����Ă��A����̐S�������邱�Ƃ��ł���̂͐l�Ԃ����ŁA�u������̌ċz�v�Ƃ��������t�́A����Ȕ����Ȑl�ԓ��m�̊W�������\���Ă���B
�@�u���̂悳�v�ɂ���đ��҂�����A�������Ă����B
�@�L�������鎞�͏W���͂��K�v�ł��낤�B
�@�W���͂�b����ɂ͂ǂ������炢���̂��B �]�Ȋw�I�Ɍ���A�l�Ԃ̑O���t�͂ǂ�ȏꏊ�ł��A�u�ԓI�ɏW���ł���悤�ɐv����Ă��邩��A���ł��W���ł���悤�]�ɃN�Z�Â�����̂������B
�@���͍z���W�I�̎���A���Ȃ킿���w�Z��w�N�̂��Ƃ���u�Ȃ���v�������Ă����B�m���ɁA�W�����Ă��鎞�Ԃ͕������Ă��Ȃ��B�����炱��10���N�̓��W�I�[��ւ͑S���^�����Ȃ��畷���Ă���B
11/8�i��) �܂�@�a�@�@
�P:45�N���A�����`�F�b�N�B�k�R���B�f�[�^�����ȂǁB����̉J�ŊO�d���s�K�A8:30�Ɠ��ɓ��旝�͕a�@�ɁB10:00�a���Ή��A11:15�V���`�F�b�N+ ���́A14:30�����J���t�@�A���@���ҏ��u�A�Ǐ��A�������A�����B19:15�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B�����v4350���B
�s�v�c�ȑ���u�]�v(7) �L���ɂ���(4)�@�N�ɂł�����u�ǖY��v�Ƃ̕t��������
�@���Y��A���̒��ł��́u�ǖY��v�͓��퐶���ŒN�ł��o�����Ă���n�Y�B
�@�m���Ă���n�Y�Ȃ̂Ɏv���o���Ȃ��̂��u�ǖY��v�B �Ȃ��Ȃ��v���o���Ȃ��B���ǂ������v�������邵�A�F�m�ǂ̑O�����ȁH�Əł��Ă��܂��B
�@�u�m���ɒm���Ă����v�Ƃ������o���u���m���v�ƌĂԁB���m���͋L���̓ǂݏo���̍ŏ��̃X�e�b�v�ł���B
�@�ŏ�����m��Ȃ��A���߂ĕ��������Ȃǂ͎v���o���悤���Ȃ��̂ŁA���������Ȃ����A�u���m���v�������Ďv���o�����Ƃ��ł��Ȃ��ƁA�����̋L���͂ɑ���M������h�炢�ł��܂��B
�@�]�̂����A���̈ʒu�ɋ߂��Ƃ���ɂ��鑤���t�ŋL���~�ςɊ֗^���Ă��邱�Ƃ��킩���Ă���B ���̑����t�Ɍ������āA�z�̌��ɂ���O���t����u���������L�����v���o�������B�}���Œ��ׂďo���Ă��āE�E�E�v�Ƃ������M���������t�ɂ����B
�@���m������ǂݏo���ւ̃o�g���^�b�`�����܂������Ȃ��Ƃ��Ɂu�ǖY��v���N����B
�@�u�ǖY��v������Ǝ����Ƃ�����!!!�Ǝv���B
�@
�@�������Ȃ���A�u�ǖY��v�����������v���o�����Ƃ��Ă���Ƃ��A�]���傫�����������Ă��邱�Ƃ��@�\�IMRI�����ȂǂŖ��炩�ɂȂ��Ă���B �ꐶ�����v���o�����Ƃ���Ȃ��ŁA�]�����܂��܂Ȏ�i�������v���o����Ƃ����Ă��邱�Ƃ��킩��B
�@���́A�v���o����Ƃ́A�V�������̂ݏo���n���́A�M�������߂�v���Z�X�Ɏ��Ă���B�v���o����Ƃ����܂��s�������A�B�����ƍ��g��������B���̎��A�]���ʼn��y�����̈�ł���h�[�p�~�������傳��A�������ƂƂ��Ɏv���o����H�����������B
�@�u�ǖY��v����ƁA�����ɐl�ɕ�������A�X�}�z�ȂǂŒ��ׂ����Ȃ邪�A �Ȃ�Ƃ����͂Ŏv���o�����Ƃ���]�̑n���͂�b����`�����X�ƌ�����B
�@�u�ǖY��v�ő����̘V�l�͔F�m�ǂɂȂ�̂ł́H�H�Ƌ����B
�@�F�m�ǂ̏ꍇ�͖Y��Ă���Ƃ������o���玸���Ă��邩��u�ǖY��v�Ƃ͈قȂ�B�����O�̐H���ʼn���H�ׂ��̂��v���o���Ȃ����A�w�E�����Ɓu�����������v�Ǝv�������ꍇ�́u�ǖY��v�B�����O�ɐH���������Ƃ����̂�Y��āu�܂��H�ׂĂ��Ȃ�!!�v�Ƃ����̂��F�m�ǁA�Ƃ������C���[�W�ɂȂ�B
�@�u�ǖY��v��Ƃ��ẮA�o���Ă����ׂ����Ƃ̓X�}�z�Ƃ��m�[�g�ȂǂɃ������Ă����̂��������A�Ȃ�ׂ�����ɗ��炸�v���o���̂������B
�@�u�ǖY��v��V�����ۂƌ��߂��Ē��߂��A�Ȃ�Ƃ��v���o�����Ɗ撣��A��X�����]�A�n���͂�ۂꏕ�ɂȂ邾�낤�B
�@���̏ꍇ�A�L���\�ቺ�̎��Ԃ͂Ђǂ��B
�@�����烁���̓}���Ɏ���Ă���B�������A�Ȃ�ׂ����Ȃ��B
�@���āA�X�C�X�o�g�̎w���҃V�������E�f���g���̖��O���v���o���Ȃ��Ĉ�T�ԋꂵ���A�v���o�����Ƃ��̒B�����͎��ɑ傫�������B
�@�u�ǖY��v���]���ɗL���ɗ��p���悤�B
11/07�i�j�I���~�J�������@���ʕa�@�O���@
1:45�N���B�������f�[�^�����A�k�R�B�f���f�[�^�����A�{�ǂ݁B�R���݂͂܂Ƃ߂����B
6:40�o�X�a�@�A7:00-8:20�a���Ή��A8:45-14:00���ʊO���BCFS�֘A�̊��҂��̑��\�����敾�B14:30���n�a�@�A������Ⓑ�߁B�V�������A�������������B16:00�a���Ή��A19:10�A��A�[�H�A20:45�A�Q�B�����v8055���B�I���~�J�������A�_���A���v���������H�H�Έ䂳�܂���炵���B
�s�v�c�ȑ���u�]�v(6) �]�͒P�זE����A�F���͐��f����n�܂���
�i�P�j�]�̏ꍇ
�@�l�̑̂͑����̍זE����Ȃ��Ă���B�]���܂����̗�ɂ��ꂸ�A�זE���W�܂��Ăł��������Ă���B���̎������F�߂�ꂽ�̂̓z����100�N�قǑO�̂��ƁB
�@�]�����͓��ʂȑ��݂ŁA�ق��̑���Ƃ͈قȂ��Ă��邾�낤�ƍl�����Ă����B�����āA�@���I�ȗ��ꂩ��A���̐���ɉȊw�̃��X�����邱�Ƃ��^�u�[���Ƃ��鎞����������B
�@����ƂƂ��ɍl�����ς��A�C�^���A�̉�U�w�҃S���W�ƃX�y�C���̑g�D�w�҃J�n�[���̓�l�́A�]�̍\�����Ȋw�I�ɒ��ׂ����A���ʂȌ`�Ԃ����u�_�o�זE�v���A�]�̕��G�Ő��I�ȋ@�\��S���Ă��邱�Ƃ������B��l�͂��̋Ɛт� 1906�N�m�[�x���܂���܂����B
�@����ȍ~�A�_�o�Ȋw�̋Z�p�i���͂߂��܂������B�����B
�@���̌��ʁA�l�̔]�ɂ͂Ȃ�Ɩ�1000�����̐_�o�זE�����邱�Ƃ��킩�����B
�@�l�̔����A�������l�����1000���̐_�o�זE���͋����ł���B
�@������1���̎�����`������邪�A�a���̑O��10�����Ԃɓ��W���ł͖�1000���̍זE�ɂ���Ĕ]���`������Ă���B
�@�������A�َ��̔]�̔��B�̎d���͐l�ɍ����Ȃ��B�N�̔]�ł��قړ������̐_�o�זE�������悤�Ȓ����ŕ���ł���B�]�̂���̐����l�ɂ�鍷�͂Ȃ��B����ɔ]���������ŏڍׂɊώ@���Ă݂Ă��A�זE�̕��ѕ���`�ɂ́A�܂������Ƃ����Ă悢�قnjl�����Ȃ��B
�@�l�̐_�o�זE�̐��́A�a�������ł������A���Ƃ�ɂ�Ăǂ�ǂ��Ă����B�_�o�זE������X�s�[�h�́A����ɐ����Ƃ����җ�ȑ����ł���B�]�זE�ɂ͍Đ��͂��Ȃ����猸�����ŁA���̌��ʁA�]�̏d���͐��܂�Ă���70�ɂȂ�܂łɖ�5%������B
�@���̑̍זE�ɂ͑��B�]�����邪�A�Ȃ��_�o�זE�ɂ͑��B�\���Ȃ��̂��B
�@�����炭�A�u�]�̌�=���Ȃ킿�l�̌��v���ێ��������邽�߂ƍl������B�_�o�זE�́A�܂��ɐl�̐��i��s�����i�ǂ��Ă��邩��A���ꂪ����ւ���Ă��܂�����A����܂ł̌o���ɂ��~�ρA�L���������A�������Ă��������ł�����߂ĕs���ɂȂ��Ă��܂��B������A�_�o�זE�����ւ����ɁA�����זE�U�����Ďg���̂��낤�B
�@�i2�j�F���̏ꍇ
�@�F���̒a���̍��͐��f�����Ȃ������B���̒i�K�ł͊����Ȃ��Ă���n���Ȃǂ͐�ɂł��Ȃ��͂��ł������B���͂܂��s���ł̂����J�j�Y���͂悭�킩��Ȃ����A���̑�ꐢ��A���f��R���ɂ����D����A���f��A�Y�f��A�]�f��A�S���������B�����̏W���̂ł��������������������ď��ЂƂȂ�A��T������A��O����̉F�������A�f�����ł��A�n�����ł��A��X�̐g�̂��ł����A�Ƃ������ƁB
�@���̃��J�j�Y���ɂ��Ă͍�������Č������Ǝv�����A�����̐g�̂̒Y�f�⒂�f�́A50���N�ȏ�O�ɁA�ǂ����̐��łł������́A�Ƃ������ƂɂȂ�炵���B
�@����炪�����̂̌��ɂȂ�A�������Ԃ������Đi�������̂������̂ł����l�Ԃł���B
�@�����̈ꐶ��ʂ��Č����ꍇ�A�]�̒��ɂ��F�����ʂ����Ă������W�ߒ��Ƌ��ʂ��Ă��镔��������A�Ǝ��͊����Ă��܂��B��͂�]�ɂ͉F�����h���Ă���̂��A�ƁB
11/6�i���j�����[������~�J�@���N�N���j�b�N�h�b�N�@�@
�@1:50�N���B�����E�V���������B�~�σf�[�^�����B�k�R�L�ځB6:40�o�X�a�@�A7:00-8:45�a���Ή��A9:00-11:30���N�N���j�b�N�h�b�N15���{���ʔ���14���B11:45���n�a�@�B�V���A��w�_���`�F�b�N�B�����ȂǁB14:00�a���Ή��A�V���@����A19:00�A��A�[�H�B 21:00�A�Q�B�����v6020���B��T���璷������̍�ƕ��ɁB
�s�v�c�ȑ���u�]�v(5) �X�l�̓��̒��ɉF��������
�@�]�̕��G�ȓ����́A�]�Ɋ܂܂�Ă����1000���́u�_�o�זE�v�̋@�\�ɂ���ĉc�܂��B
�@����ȏ����ȓ��̒��ɁA���W���ň��S�Ɏ��ꂽ��ԂɁA�n����̐l�Ԃ̐��E�E�E���l����80���l������ƌ����Ă��Ă���������������A�Ǝv�����A����80���l�ЂƂ�ЂƂ肪�A���̒��ɂ���10�{�ȏ�̐_�o�זE�������Ă��邱�Ƃ�m��Ƌ����Ă��܂��B
�@����A�l���̏ꍇ�͂����}�����Ȃ���A�n���͔��M��ԂɂȂ�A�A�ŏǂ�ċz�s�S�Ɏ����a�C�ɂȂ��Ă��܂��B�푈�Ȃ��Ă���ɂȂǂȂ��̂��B
�@�]�ɂ��āA����ɏd�v�Ȏ��́A�]�̕��G�ȓ����͂ЂƂЂƂ̐_�o�זE�������ʂȔ\�͂ł͂Ȃ��Đ_�o�זE���m���݂��ɖ��ڂɃl�b�g���[�N(�_�o��H)������ďW�c�ŋ@�\���Ă���Ƃ������Ƃɂ���B
�@�]�̐_�o�זE�ɂ́A�^�R�̎��̂悤�ɒ����R(����)�����Ă���B�_�o�זE���m�͂��̎�������đ��̍זE�Ɛڂ��Ă���B���̐_�o�זE���m�̐ړ_���V�i�v�X�ƌĂԂ��A��̐_�o�זE���V�i�v�X�����10000�̕ʂ̐_�o�זE�Ɛ_�o��H������Ă���Ƃ���A���̃V�i�v�X�̑����͐l�̔]�ł�1000���ɂ��y�ԂƂ����Ă���B�������A�X�̐_�o�זE�́A�ꕪ�Ԃɐ��S���琔��������̐_�o�זE�ƘA������荇���Ă���Ƃ����B
�@������A�X�l�����̒��ɏ����ȉF���������Ă���ƕ\�����Ă����B�܂��A�_�f��G�l���M�[�̏���������R�A�x���̂��߂̐����̏d�v�����킩���ė���B
�@�F���ɑz����y����ƁA��X����芪�����X����Ȃ鐢�E���A��͌n�ƌĂԁB ��͌n�ɂ͐���1000���A���傤�ǔ]�זE�̐��ɋ߂���������B19���I�����܂ł́A���ꂪ�S�Ă��Ǝv���Ă�����20���I�̏��߁A230�����N�̔ޕ��ɃA���h�����_�启�_�����邱�Ƃ����������B�A���h�����_�ɂ�3000���̐�������B�F���ɂ͂��̂悤�Ȑ��̑�W�c���܂��܂����݂���B
�@�܂��ɉF���ɂ͓V���w�I���l�����Ԃ��A�]�̍זE�͐������ł͂Ȃ����G�ȃl�b�g���[�N���`�����Ă��邱�Ƃ����X�̐��E�ƌ���I�ɈقȂ�_�ł���B
�@�]�̋@�\�̒��ŋL���͂ǂ̂悤�ɂ��Ĕ]�ɂ����킦����̂��B���������u�L���́v�Ƃ͉��Ȃ̂��B
�@�L���͂��R���g���[���ł���悤�ɂȂ�A�l�Ԃ͂�葽���̂��̂��Ƃ��K���ł���悤�ɂȂ�A�ƍl������B
�@�]�͒m��Βm��قlj��[������ł���B
11/5�i���j���� �@10�N�ԗp�����f�B�o�b�O���ނ�
0:30�n���ł����N���A22:00ALS��A23:00KK���s���̘A���B�Ƃ��Ɍo�ߊώ@�B�Ǐ��A�]�W�����`�F�b�N�B������B12:15NHK�̂ǎ����A�V���蔲���쐬�B14:00����̃R�C�ɋ��a�A���n�a�@�A�a���Ή��B�V���`�F�b�N�B�V���d�q���B���������ȂǁB�����ق��V�����́B18:30�A��[�H�A21:00�A�Q�B�����v5544���B
�s�v�c�ȑ���u�]�v(4) �]����邱�Ƃ͐l������邱��
�@��������ɂȂ�]�̋@�\�̗������݂��������Ȃ����Ǝ��o����B���ɋL���́A�L���͂͑啝�ɗ�������ł��Ď����ł����܂蓖�ĂɂȂ�Ȃ��Ȃ��Ă����B�]���A�S���A���̑��݂�����ő��Ɉӎ����鎖���Ȃ����������̔]�ɁA�ŋ߂ł͊��ӂ̋C���������߂Ēg�����������Ă���ł���B
�@�A���c�n�C�}�[�F�m�ǂ̕a�Ԃ��𖾂������A�a��̐i�s����}���ł�������F�����ȂǁA�]�̉Ȋw�I�m�����i�W���Ă���B
�@�l�H�m�\�̔��W������B�l�H�m�\�͌v�Z�\�͂͂������A�p�^�[���F���̔\�͂ł��A�l�Ԃ������Ă���B�l�H�m�\�̔��B�͂��炵�����A�l�Ԃ̔]�����������̂ł͂Ȃ��B���ɁA���l�Ƃ��낢��Ȉӌ������Ƃ肵����A��������L�����肷��u�R�~���j�P�[�V�����\�v��A�u�n�����v�ɂ����ẮA�܂��܂��l�Ԃ̔]�͑傫�ȉ\���������Ă���A�Ǝv���Ă���B
�@���͋L���̃��J�j�Y������łȂ��A�]�S�̂̋@�\�ɉ��߂ĊS�������Ă���B
�@�]�͎��ɕs�v�c�ȑ���ł���B
�u�]�v��m�炸�Ƃ������čs�����Ƃ͂ł���B�������Ȃ���A����Ȃ�1300g���x�̏����ȑ���ŁA�u�L��������v�A�u�l������v�A�u�Y��v�A�u�z��������v�A�Ƃ��������ʂȔ\�͂��ł���̂��A�s�v�c�Ɏv�킸�ɂ͂����Ȃ��B
�@�����̐g�̓I�̋@�\�͐����ێ��̂��߉�����Ƃ��Ă݂Ă��f���炵���Ǝv���B���̒��ł��]�͂Ƃ�킯���G�ʼn��[�����̂�����B
�@�]�̏d���͑̏d�̂ق��2%�Ȃ̂Ɏ_�f��u�h�E���Ȃǂ̃G�l���M�[���Ȃ�ƑS�̂�20~25%�������B���̂��Ƃ��炾���ł��u�]�v�������̂ɂƂ��Ĕ@���ɏd�v�ł��邩���킩��B
�@�]�̋@�\�̋��ɂ́A�_�o�זE�̏W���̂ł���]�ɁA�Ȃ�Łu�ӎ��v��A�u�S�v���h�邩�Ƃ������Ƃɐs����B�]�̐_�o�זE�̊����ɂ���Đl�Ԃ́u�ӎ��v�����܂�Ă��邱�Ƃ͋^���̂Ȃ��B �������Ȃ���A���܂��ɂ��̋@�����𖾂���Ă���Ƃ͌����Ȃ��ɗ��܂��Ă���B
�@��Ȣ�S��ݏo���Ă���̂��]������A�]���l����Ƃ������Ƃ́A���Ȃ킿�u�������̐l�����l����v�Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă���Ƃ�����B
�@���̂悤�ȕs�v�c�ȑ���u�]�v�ɖ��S�ł����悤��??
11/4�i�y�j��������~�J���������@
3:00�N���A23���ɕʂ̊���CHIKUNI���s���̓d�b��n���ł����B�����ǂ݁A�k�R�������̔@���B13:30�Ɠ��ɑ���ꃊ�n�a�@�A���@���Ҏ��Îw�������A���҂͔�r�I���������Ă���B�V���`�F�b�N�A���́B16:30�A��B�Έ䂳��E��s���ʼnƓ������B�����A19:00�[�H�A20:30�A�Q�B�����v��6338���B
11/�R�i���j�����̓��@�����@���ҕs��
1:45�N���A�l�R�Ή��A�f�[�^�����B8:45�R�S�~��o�B8:45�a����芳��TI���s���̘A���B10:00Taxi�ɂĒ��ʃ��n�ցBTI���Ƒ��ʒk�A�a������D�V���`�F�b�N+���́A�����w�B13:30-15:00�Ɠ��̓A�g���I���R���T�[�g�ɖ��Ȃ̂��߂ɓ���Ȃ������Ƃ����B���߂ď\���@�\�����A�����Ï��X�K��B�a���Ɩ��B17:30�Ɠ��ƋA��A���j���KAC�A�_�v�^�[�̌��ŁB�[�H�B20:30�A�Q�B�����v��7249���B
���@�@�c��������������������������
�����������L�Ƃ́A�N���ɓǂ܂�邱�Ƃ�O��ɏ������̂Ȃ̂��B
�����ȍ~�A��������œ��L�̏�������������Ă����B �ċx�݂̓��L�ȂǁA�u���L�͎����̂��߂ɏ����v�Ƃ�����`��m�����ŁA���t�ɓǂ܂��Ƃ킩���Ă��邽�߁A�q�ǂ��͍ŏ����狳�t�̎������ӎ����ē��L�������B
���������Ӗ��ł͓��{�l�͂قڑS���̂���悤�ɂ��Ă͒m���Ă��Ă������낤
�u�������������B�����Ă����������B�c�����������B ���҂̎������ǂ��܂őO��Ƃ��邩�ŁA���L�̓��e���ς��v�B
����Ȃ�A�N�ɂ������Ȃ���Ԃ��ۏ����A�l�́u�U�炴�鎩���v�������̂��B �u�����Ƃ͌���Ȃ��v�B�u���L��ǂݕԂ������̎������[�����邾�낤�������v�����������~�������݂��邩�炾�B
�O�o�̉ċx�݂̓��L�Ɠ��l�A������͎��s��閧���u�����Ȃ��v�ƑI�����邱�Ƃ��ł��邵�A���z�̎����������̎������̂悤�Ɏv������ŏ������Ƃ��ł���B
�Ȃ��l�͓��L�������̂��B
�c������́u���������~�������邩�珑���A�ƌ�������܂łȂ̂ł����v�ƑO�u��������ł������B
�@�����������炵���������Ɗm�F����B
���L�Ȃ̑��ݐ���邱��
������O�ƂȂ����B����ŁA�s����������ɂȂ��Ă����B����ꂽ���̂��A�����Ă������̂��A�c�����������Ȃ̂��B���̋�ʂ������܂��Ȃ܂܊����l���M
����A���ɔᔻ�△�S�ɏ����B
�茳�Ɏc���Ă��Ȃ��ȏ�A���������߂����͂��ˑR�A�����Ȃ��Ȃ�\�����[���ł͂Ȃ��B
���̓��L�������������Ȃ�A
�ܕ���X�u�a�C����v(���)�̑�r�߂��݂���Ƀg�����h��q�˂��B
�u3�N�A5�N�A10�N�̉^�p���L���������l�C�ł��v�B �����X�p���ߋ��̎�����U��Ԃ�y���݂�����A1���ɏ����X�y�[�X�����s���x�Ȃ̂Łu������ꂻ���v�Ǝv���l�������������B �u���������Ȃ���ƃv���b�V���[�Ɏv�����A�����o���̐U��Ԃ�A���̐����̂��߁A�����������ɏ����A�Ƃ����X�^���X�������߂ł���v
���L����SNS�A���L�A�v���ȂǏ������Ƃōl���⊴�������g�߂Ȑl�ɂ������Ȃ��v�����͂��o���ǂݕԂ����ƂŎ�����������A
1���̎d���A�����𐳒��ɕA���Ȃ���`��������Εׂ��A����S��������Ȃǂ����߂�
11/2(�j �����@���n�F�m�NJw�K���@
1:30�N���B�Έ䂳��]�|�E��s���A�Ɠ��͐܂�Ă͂��Ȃ����낤�Ƃ̔��f�B�����A�^���f�[�^�ҏW���B�k�R�ȂǁB8:30�Ɠ��ɓ��惊�n�B�����A�V���`�F�b�N�ق��͓Ǐ��O���B�f�[�^�����A�ߌ�͕a���Ή��A13:45���n�F�m�NJw�K��,�A�Ō�t�A�P���m��̔M�ӂɋ����B19:00�A��E�[�H�A21:00�A�Q�B�����v��5004���B
��HP�u���ꂩ��̈�Â݂̍�� �k�R���L�v23�N�ڂ̎G��(1)
�@�G��(1)�Ƃ��d�����邪�E�E�E�B
�@���͉��̃��N�ɓǂ܂�����Ȃ��ʕ�����L�Ƃ��ĒԂ葱���Ă���̂��H
�@����ɂ́A�������̎������B
�@�����̓���L�^�́A3��o�������x�@�̐E�����₩�����������ƂȂ��Ă���B
�@���p���͗͂Ȃ�
�@���͂��̌��t���D���ŁA�p�����Ă�����̗��R������B���ł��~�߂��邪�A�ɂ����Ď~�߂��Ȃ��B�������߂鎞�A���̐l�������̐��E�Ɉڂ鎞�ł��낤�B
�@���L�^���˂L�����ێ��ł��Ȃ�
�@���̋L�����u�A���Ȃ킿�u�]�݂��v�����ċL���̒~�ς�ێ�������ɂȂ����B�L�^���Ȃ��ƒ����ɖY���B�Y��Ă��܂��A�����̉ߋ��͑S�Ė��ɂȂ�B�k�R���L�́A���������ė������ɂȂ��Ă���B�L�^�̓n�[�h�f�B�X�N�ɒ~�ς���B���̑��蓪�͋���ہB
�@���Y�p�h�~�̂���
�@�v�������A�l���邾���ł͂������U����B������C�ɂȂ������Ƃ͕��͉����Ă����B���͉����邱�Ƃōl�����Œ肳���B�_����ɕς��A����ɖʂɕς���s�ׂł���B
�@�������L�^�A�~�j�G�b�Z�C�͎��j�I�����Ƃ��Ă��M�d
�@���͓��X�̋L�^��~�ς���̂��D�����B���́A�摜�A���y�ȂǁA�nj�̊��z�ȂǁB�o������Ȃ�����قڑS�Ă�d�q�I�ɒ~�ς���B
�@���V���X�N���b�v��2008�N����1��������������Ƃ��Ă��邩��30�����قǂ���B���x�[�X�ł͓���s�\�ȗʁB�������A�����ł����o�Ă���̂������B
�@�����������́A�����̏����Ȑςݏd�˂��y����
�@���͏�����Ƃ��čׁX�Ɛf�Â𑱂��Ă���B�Ǐ��ȂǂɎg���鎞�Ԃ��������B�Ǐ��ʂ��������B�w�������}���͂����Ɏ������邩�珑�I�ɂ͕��Ȃ��B�p�\�R���AiPad�̓d�q���I�ɕ��ԁB
�@���Ƒ��B�̓������y���݁A�����l�R�����Ƃ̓��X���y���݁A����≀�|��ʂ��Ď��R���ۂ̈ڂ낢�𖡂키�B
�@�������̑Ώۂ́A���j�A�����A�����E�o�ρA���ۖ��A���R�E�E�A�ƍ��ł��܂��L�����Ă����B��l�B�̑��Ղ͈̑�ł���B�����ɏ����ł������G��Ă݂����B�V���A�����A���Ђ�ʂ��Ė��키���X�͍ō��B
�@�������̎�C�A�ӗ~�ቺ�A�̗͒ቺ�ɍR���閈��
�@���͐l�Ƌ����E�R���͍D�܂Ȃ��B�Θb���D�܂Ȃ��B������A�����������Ԃł���B�ŋ߂͈ӗ~�̒ቺ����Ȃ�ł����Ղȕ����ɗ����X��������B�������A�w�i�ɂ͘V���ɂ��g�̏�̖��_�A�Ⴆ�Ή����̐����A�o�����X���o�̌�����ӎ�����B�C�͂��ێ��ł��鎞�Ԃ��Z���Ȃ����B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�@�ȂǂȂǁB
�@�����Ɏc���ꂽ���Ԃ͂��������͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���B�c���E���N����ɂ��A����ȍl�����������B�����炱���c���ꂽ���ԁA���ꂪ�ǂꂾ�����킩��Ȃ����A�������v���B�厖�ɂ��������̂ł���B
�@����HP�̍X�V�͂��܂ŏo���邩������Ȃ����A���̋C�́A�̗͂̑����I�o�����[�^�[�ł���B
11/1�i���j����@�@
1:30�N���B�V���`�F�b�N�A�����A�^���f�[�^�ҏW���B�k�R�ȂǁB�������BTS����ᑑ��݂ŏo�B8:00�_���A�̐��b�A8:30�Ɠ��ɓ���o�B�V���`�F�b�N�ق��B�@���l�b�g�B10:30��ᑑ����w�A14;00���҉Ƒ��ʒk�A14:30�����J���t�@�����X�C���ҏ��u�Ή����̑��B���y�^���ȂǁB19:00�A��[�H���H�B21:00�A�Q�B�����v��5300���B��N�`���́B
��HP�u���ꂩ��̈�Â݂̍�� �k�R���L�v23�N�ڂ̎G��(1)
�@���z�[���y�[�W�u���ꂩ��̈�Â݂̍���v�́A2001�N11��1���ɊJ�݂����̂Ŗ{����22�N���}�����B
�@�{����23�N�ڂ̃X�^�[�g���B������Ƃ����L�O���ɓ�����B
�@�����Łu�G�L��Blog�v�͖�19�N�ځA�ŋߍX�V�����Ă��邪�u�C���X�^�O�����v��6.5�N�ł���B
�@
�@23�N�ڂ̎G��
�@�ω��ɖR�������X�̐ςݏd�˂ł��������A��N10���ɂ́u�咰�e������o���v�����@�B�ꎞ�A����Ń_�����H�H�Ɗo�債�����K���厖�Ɏ���Ȃ������B
�@���N5���ɂ́u�}���S�s�S�ɂ��ċz�s�S�v�œ��@���Â����B�������Ƀ_�����H�H�Ɗo�債�������̎����K���厖�Ɏ���Ȃ������B���̌��ǂ̐S���@�\�ቺ�ʼn^���������ɂ��邪�A�S���ɕ��S�������Ȃ��悤�������s�����邱�ƂłقƂ�ǎ��o�Ǐ�Ȃ��ʏ�̓��퐶����x���Ă���B
�@���܂ő������킩��Ȃ����A���͂��Â��u�^�������v�l�Ԃ��Ǝv���B�ߋ��́u�]�[�ǁv�u���ǁv�u�����O���v�̎��������ł������B�����ɒg�����삳��Ă���悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B����c�l���A�͂��܂�����l�R�̃^�����E�E�E�E�B
�@�S�̂Ƃ��Ă͖��N�����悤�Ȋ��z�ɂȂ�̂͂�ނȂ��B
�@�����K���I�ɑ����Ă��鍀�ڂ͈ȉ��̔@���B
----------------------------------------------------------------------------
�@�� �����L�^��50�N�ȏ�A����20�N���͓k�R�Ƃ��ċL�q�B
�@�� �����ɋN���o���B��30�N���B�ŋߋN����2:00�O��Ƃ��Ă���B
�@�� �V���E�����X�N���b�v�~�ς�20�N���B
�@�� ���W�I�[��֘A��3���Ԙ^���~�ς�14�N���B���̂���6�������Ă���B
�@�� ���֖�������������t��12�N�B���z�͔N�X���Ȃ����A�ŋ߂�5���~/���B
�@�� �I���B������@�ɓ�����s�s���ȓd�q�f�[�^���폜�����B
�@�� ���g�̉ߋ��Ȃ��A��������������10�N�ȏ�B
�@�� �k���ʋ͌��N��̖��Œ��~���o�X�ʋɁB
�@�� ����I�ɕ��s���ӎ��B�ɔ\���h�̑��Ղ�ǂ������{����͌���2���ڂŕx�R�r��B
�@���E�E�E�ȂǂȂǁB
---------------------------------------------------------------------------
�@�ŋ߁A����ɂ��ӗ~���ނ�����A��������ɂ����Ԃ�������B���s���x���x���Ȃ����B���|�E����Ƃ͉����ɂȂ����B
�@����ł���4������E�ꂪ���ʃ��n�r���e�[�V�����a�@�Ɉڂ�A�Ɩ��͑啝�ɑ��������B
�@�I�������˂����Ђ╶���̔p�����t�ɓǏ��~�ɉ������B�t���[�̎��Ԃ͏��Ȃ��Ȃ������قƂ�ǎ����������Ђ̓Ǐ��ɏ[�ĂĂ���B
�@�����ɕ��ׂ��Ă���K���A���ׂ��d�������Ȃ��̂�1��24���Ԃł͑���Ȃ��B
�@�ł��A����ȍl���͂�߂��B�S�̂��~�j�����A�ȑf�����A�x����厖�ɂ��Ă���B�@
10/31(��) �u�₩�ȉ������˗�p�@���ʕa�@�O���@�U��
1:45�N���A���������A�Ǐ����S�A���˗�p�ŗ₦��B5:30�R�S�~�W�Ϗ��ɁB6:40�o�X�a�@�ցA7:00-8:15�a���Ή��A8:45-12:50���ʕa�@�O���A�敾�B�@�������ŎU���B14:00���n�a�@�B���H�A�V�����́A16:00�a���Ή��A19:30�Ђ�̂⏑�X�o�R�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B�����v��7614���B
10/30(��) ����@���N�N���j�b�N�h�b�N�@
1:30�N���B�����Ɠ����A6:40�o�X�ѐ�a�@�A7:00-9:00�a���Ή��A�r��8:44����SY�������B9:10-11:30���N�N���j�b�N�h�b�N15��+���ʔ���B11:45�a�@�A�����A14:00�a���Ή��A���������ȂǁB�V���`�F�b�N+���́A�@���̃C���^�[�l�b�g�s���ɁB19:30�A��E�[�H�A20:30�A�Q�B �����v��7114���B
10/29(��) �܂�
1:30�N���B�k�R�ȂǁB�ߑO�͔������݂Ȃ�����w�B10:20�a����芳�҂̕a��B12:00�V�����w�茔�w���ɍs���Ɠ��ɓ���A���n�a�@�B�a���Ή��B�����A13:45�V���蔲��+���́A�Ǐ��B�G�������A�^���A�f�[�^���������B17:00PICC�p�Љ��쐬�A19:00�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B�����v��5306���B
�s�v�c�ȑ���u�]�v(4) �]����邱�Ƃ͐l������邱��
�@��������ɂȂ�]�̋@�\�̗������݂��������Ȃ����Ǝ��o����B���ɋL���́A�L���͂͑啝�ɗ�������ł��Ď����ł����܂蓖�ĂɂȂ�Ȃ��Ȃ��Ă����B�]���A�S���A���̑��݂�����ő��Ɉӎ����鎖���Ȃ����������̔]�ɁA�ŋ߂ł͊��ӂ̋C���������߂Ēg�����������Ă���ł���B
�@�A���c�n�C�}�[�F�m�ǂ̕a�Ԃ��𖾂������A�a��̐i�s����}���ł�������F�����ȂǁA�]�̉Ȋw�I�m�����i�W���Ă���B
�@�l�H�m�\�̔��W������B�l�H�m�\�͌v�Z�\�͂͂������A�p�^�[���F���̔\�͂ł��A�l�Ԃ������Ă���B�l�H�m�\�̔��B�͂��炵�����A�l�Ԃ̔]�����������̂ł͂Ȃ��B���ɁA���l�Ƃ��낢��Ȉӌ������Ƃ肵����A��������L�����肷��u�R�~���j�P�[�V�����\�v��A�u�n�����v�ɂ����ẮA�܂��܂��l�Ԃ̔]�͑傫�ȉ\���������Ă���A�Ǝv���Ă���B
�@���͋L���̃��J�j�Y������łȂ��A�]�S�̂̋@�\�ɉ��߂ĊS�������Ă���B
�@�]�͎��ɕs�v�c�ȑ���ł���B
�u�]�v��m�炸�Ƃ������čs�����Ƃ͂ł���B�������Ȃ���A����Ȃ�1300g���x�̏����ȑ���ŁA�u�L��������v�A�u�l������v�A�u�Y��v�A�u�z��������v�A�Ƃ��������ʂȔ\�͂��ł���̂��A�s�v�c�Ɏv�킸�ɂ͂����Ȃ��B
�@�����̐g�̓I�̋@�\�͐����ێ��̂��߉�����Ƃ��Ă݂Ă��f���炵���Ǝv���B���̒��ł��]�͂Ƃ�킯���G�ʼn��[�����̂�����B
�@�]�̏d���͑̏d�̂ق��2%�Ȃ̂Ɏ_�f��u�h�E���Ȃǂ̃G�l���M�[���Ȃ�ƑS�̂�20~25%�������B���̂��Ƃ��炾���ł��u�]�v�������̂ɂƂ��Ĕ@���ɏd�v�ł��邩���킩��B
�@�]�̋@�\�̋��ɂ́A�_�o�זE�̏W���̂ł���]�ɁA�Ȃ�Łu�ӎ��v��A�u�S�v���h�邩�Ƃ������Ƃɐs����B�]�̐_�o�זE�̊����ɂ���Đl�Ԃ́u�ӎ��v�����܂�Ă��邱�Ƃ͋^���̂Ȃ��B �������Ȃ���A���܂��ɂ��̋@�����𖾂���Ă���Ƃ͌����Ȃ��ɗ��܂��Ă���B
�@��Ȣ�S��ݏo���Ă���̂��]������A�]���l����Ƃ������Ƃ́A���Ȃ킿�u�������̐l�����l����v�Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă���Ƃ�����B
�@���̂悤�ȕs�v�c�ȑ���u�]�v�ɖ��S�ł����悤��??
10/28(�y)����̂��[�����珬�J�@���ۃ_���A���K��
1:30�N���A�̒��ǍD�B�������Ɠ����B�f�[�^�����A�Ǐ����S�A������B10:30����R�C���a�A�Y�a�_���A���ɁB12:30�t���[���Œ��H�A�r�|�t�J���[+�R�[�q�[���ɔ����ł������B14:00�a�@�A������ꂽ�B17:50�a���Ή��A19:00�A��A�[�H�B20:20�A�Q�B�����v��6634���B ���N���Ԃ̃X�g�[�u�����A���_�B���N�͂܂��B
�s�v�c�ȑ���u�]�v(3) �L���ɂ���(3) �����Ƌ���(2) ���q123�֒ė����̂ɂ���
�@1985�N(���a60�N)8��12��(���j��)�AJAL123��(�{�[�C���O747SR-100�^�@�j���Q�n������S��쑺�̌䑃��R�w�ė������B
�@��q���524���̂������S�Ґ���520���A�����҂�4���B�P�Ƌ@�̍q�̂̎��Ґ��Ƃ��ĉߋ��ő��B
�@���͏��̂͌�������s�@���̂��̂͑�D���ŏ��Ђ�ʂ��Ĕ�s�@��q��ƊE�ɂ��Ă����Ɗw��ł����B
�@����Ȓ��A1987�N(���a62�N)6���A�^�A�ȍq�̒����ψ����1978�N�i���a53�N�j�ɒO��`�ŋN�������u����������́v�Ŕj���������͊u�ǂ́A�{�[�C���O�ɂ��s�K�ȏC���������Ő������Ĕj�����ė����̂̌����Ɛ��肳���A�Ƃ��������܂Ƃ߂��B
�@���̍��q�́A�ȉ��̂��Ƃ��B
--------------------------------------------------------------------------
�@�u�ǂ̏C���~�X��������
�� ���̕t�߂ɔ�J�T�i�s����
�� �q���̉����ɑς����˂Ċu�ǂ��Ĕj���A�����J����
�� ��������C�̗��ꂪ�����@���́u�}�����v����
�� ���̕����Ő����������Ŕj��
�� �S�����V�X�e���j��
�� ���c�s�\�Ɋׂ���
-----------------------------------------------------
�@���̘_���̍ŏd�v�_�͐��������𐁂�����قǂ̋�C�̗���̑��݂ł��邪�A���̎������q�ϓI�Ɏ����؋����S����������Ȃ��B ���̗����ɍ���Ȃ��_�|�����̕��̍ő�̎�_�ł�����_�ł���B
�@���̎��̒������ɑ��Ă͎��ҁA�p�C���b�g��q��֘A�E��c�̂���٘_���o���ꂽ���^�A�Ȃ͂��̂悤�Ȑ��ɑS������݂����A����������j�����A�������I�����B
�@���̎��̂�30���߂����������[�����O (���h��)�A�t�S�C�h�^��(�c�h��)���J��Ԃ��A���������W�F�b�g�R�[�X�^�[�ɏ���Ă��邲�Ƃ��̌������h��𑱂��Ȃ���ė������B
�@��q�����̋��|�͔@�����肩�Ǝv���B
�@���q123�֎��̂́u����������́v�ŏC���������Ƃ��������@�̂�s���悭���p�������U�̌��_�ŁA���Ƃ̌��͂̂��ƂɌ��_�͂˂��Ȃ����A�������^���𖾂̓��͕����ꂽ�B
�@�]���҂̐l���͖��E���ꂽ�ɓ������B
�@����l�ɋy�Ԃł��낤�]���҂̉��̂̕��X�A���̂̊֘A�̕��X�ɂƂ��Ă����l�ł���B����38�N�̍Ό��͋ꂵ�������Ǝv���B
�@���͌��������200��قǗ��q�@�ɓ��悵�����A���̓x���ƂɎ�̋��|���E�s�����𖡂������O�҂ɉ߂��Ȃ��B
�@����ł����̎��̂̋]���҂̕��X�̐l���ɂ��āA���̂̏����^���ɂ͋^�����������Ȃ��B
�@���̎��̂Ŏ����ǂ֘A���Ђ�30����D�ɒ�����B���̂͒��ׂ�Β��ׂ�قǗ����ł��Ȃ��`�ŏ�������Ă���B
�@������L���ɂƂǂ߁A�ڂ𗣂����ɊS���������������B
10/27(��) �����~�J�̂������@ ��Ȓ��ʕa�@�O���@
1:40�N���B�̒��ǍD�B�����A�V���`�F�b�N�A�摜�f�[�^�m�F�A�k�R�B5:30�R�S�~�o���B�܂��Â��B7:35Taxi�w�A8:11���܂��A���Taxi�B8:50��Ȓ��ʕa�@�O���A�]�T�Ȃ��B15:30���艮�o�R�A�@�B�Ɠ��p�ӂ������H�ۂ�B�V���` �F�b�N�ł����B16:00�a���Ή��B19:15�A��E�[�H�A20:30�A�Q�B�����v��6834���B
�s�v�c�ȑ���u�]�v(2) �L���ɂ���(2) �����Ƌ���(1) �[�����܂��L��
�@�L���ɂ͐[��������B
�@��������߂�̂͑��ɂ��̎��ۂɑ��鋤���ł��낤�B�����Ɩڂ̑O��ʂ�߂������ۂ́A���Ƃ���u�ڂ��������A�Ƃ��Ă��L���Ɏc���B
�@�����́A��ەt����ꂽ�����Ƃ̊ԂɁA�u���I�ɐ��܂����̂ƁA�Ӑ}�I�ɗ������悤�Ƃ���w�͂̒��ň�܂�čs�����̂�����B
�@�u���I�����͖ڂ܂��邵�������̒��ň�u�Ő��܂����̂��B���̂悤�ȋ����������N�������鎖�ۂ͓���I�ɂ��ӂ�Ă���B
�@
�@���ɁA�����Ɛ[���ւ��̂��鎖�ۂɂ��Ă͂Ȃ��̎��A�����̊���I���x�͑����ɈႢ�Ȃ��B�u���I�ɐ����鋤���ɂ͂���������Ŕ��f����s�����x�̃A���e�i�Ƌ�������f�{��������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ�
�@�����͒��w�K���������邱�Ƃł��[�܂��Ă����B
�@��������������炳�Ȃ��������ۂ͔w��ɒǂ�����A�₪�ĖY�ꋎ����
���ƂɂȂ�B
�@�����Ƌ����̋����́A�����Œ������邱�Ƃ��ł���B �T�d�Ƀs���g�����킹�A����̓��ɑ�������ł䂭���ƁB ���̍ۑ�Ȃ̂́A�u��������v�p���ł���B
�@ �S�̑��̔c���̂��߂ɏ����W�߁A�����ƐM���ł�����̂�I�яo���A������v�l�̋N�_�Ƃ��Đ��܂��̂��A�����Ƃ������̂ł͂Ȃ����낤���B �����ɋ����������������Ƃ�����B
�@���R�Ȃ���A����ɂ͎��Ԃ�������B �����Ɍ��_�ɂ��ǂ蒅���A�u���������v�Ɩ������邱�Ƃ��ړI�ł͂Ȃ��B
�@�܂�A�������邽�߂ɑ�Ȃ̂́A�����ɂ��ǂ蒅�����A��ɖ₢�����邱�Ƃ��낤�B
�@����������A�����̎v�����ݎv�l����m�̊፷���̕����������S�ɐM�����Ȃ����ƂȂ̂��B�����Ɋ��Y���������A����������u���Č��߂邱�ƁB���̉ߒ��ŕ�����ł��鑜�����������̌`�ł���A�₪�Ă͋����A�L���Ƃ��Ď���ɍ��ݍ��܂�邱�ƂɂȂ�B �����������ɖ��m�ł��邩�̎��o���X�^�[�g���C���ɂȂ�B
�@�����̌����Ŗ��������A�����̑��ŕ����Č��A�N���̐��Ɏ����X���A�Ǐ��⒲���ȂǓƎ��̕��@�ŁA�����ɑ��鎋�_��z���グ�邱�ƁA���ꂱ�����u�L�����邱�Ɓv�Ȃ̂ł���B���̂悤�Ɏ��Ԃ������ďo���オ�������̂́A�ȒP�ɉ��͂��Ȃ��B �����āA�V���ɉ�����x�Ɍ`��ς����A�[�����t����܂�邱�ƂɂȂ�B
�@�ʂ̌�����������A�L������Ƃ����s�ׂ́A�ȒP�ɏ����čs���悤�Ȃ��̂����������߂邱�ƂȂ̂�������Ȃ��B
�@�����ɂ͕��������ݍӂ��A�����𑣂���p������B
�@�Ӑ}�I�Ɏ����ʼn��������āA�����s�ǂ��N�����A���ɗ��܂���̂ɖڂ������邫�������ƂȂ�B���̎��A��ߐ��̂��̂ł͂Ȃ��A�����Ɉ˂鋤���I��������܂�Ă���ɈႢ�Ȃ��B
10/26(��) ����
1:20�N���C����ɗ��܂������ނق������A�ق������̂��Ƃ��B7:50�Ɠ��ɓ���a�@�A�V���`�F�b�N�{���́B11:00�a�����ґΉ��A14:00���҉Ƒ��ʒk�B�̗w�X�N�����u���C���f�b�N�X�쐬�A�������A19:00�A��A�[�H�@20:45�A�Q�B�����v��5499���B��N����������w�Ŏ�p�B
�s�v�c�ȑ���u�]�v(1) �L���ɂ���(1) ��������푈��ЊQ�̋L��
�@2022�N6���A���̎q���̍�����p���Ă����{�I���}�ӂ̏d�݂Ȃǂʼn�ꂽ���߂ɁA�C����2�K�ɏオ�����B �{�I�̏�ԂƏC���H���ɂ��Ċm�F�������A�₪�Ď��̊�ƐS�͂����ɂ��܂����܂�Ă����Â��{��A���o���A�ʐ^��莆�A�ȂǂɌ��������B
�@�ߋ��̐����̍��ՁA�L���ɐG��Ă䂭�����ɁA�ӂ��Ɍh�i�ȋC�����ɂȂ����B
�@���̖{�I�͎��̑̌���L��������������ɕ����Ă���̂��B
�@�����̏o�����ɂ��Ďv���o���Ƃ������Ƃ́A���̌��ɒ����A�Ȃ�ߋ��̋L�����������ƁB�����玟�ւƌÂ��L���ɒ���ł��鐺�������o���čs���B �L���́A�l�̌��t�A���ɂ���ė��̓I�ɂȂ��Ă䂭�B
�@�ߋ��́A������e��̋L�^�A�f���Ȃǂ�ʂ��Ċm���߂��邪�A�^�̉ߋ��͉ӁX�l�̋L���̒������ɂ���B
�@�����{��k�ЂŒÔg�ɂ���œI�Ȕ�Q�����ꏊ�ł́A�k�Ј�\���ۑ�����A��������̐��⌾�t�Ƌ��ɋL���𗯂߂悤�Ƃ��Ă���B�����̋A�ҍ�����̂悤�ɁA�k�Ђ̐��X�����܍������݂���ꂽ�܂܂̏ꏊ������B
�@�ؐl�̐����W�߂��A �f�W�^���A�[�J�C�u�����鎎�݂��n�܂��Ă����B
�@�Ôg�̋�̓I�ȃ��[�g��n�}�ɕ\���A�،��҂̖ڌ��ꏊ���d�˂ē��肵�Ă䂭�B
�@���t�␔���A�o�����̊T�v�̊Ԃɂ�����A������������Ŗ��߂Ă䂭�B �N�₩�ɁA�����ė��̓I�ɗ��߂�ꂽ�L�^�́A�����ŏ��߂ēy�n�Ɛl�̋L���ƂȂ�̂��낤�B
�@����o�����Ǝ��ԓI�ɋ������߂���A����͋L���ɗ��܂�₷���B�������A���Ԃ��o���������邤���ɁA�����͕��ʓI�Ɏ~�߂��A�L�����炷�蔲���Ă��܂��B�����炱���A��\�Ȃǎ��o�I�ȋL�^��y�n�ɖ��ߍ��݂A���g�̌��t����ł���̈Ӌ`�����������Ă䂩�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@���̂悤�ȕ��@���K�v�ƂȂ�̂́A�������������ɋ������߂����̂ɖڂ����������ŁA���������₷�����炾�B ���̏ꍇ�̋����Ƃ͋�ԓI�Ȃ��̂����ł͂Ȃ��A���ԓI�Ȃ��̂��܂܂��B
�@�g�߂ȕ����́A�����͈͓̔��Ɏ��܂邩�炱���Y��ɂ����B
�@��������̐푈�A�����̎��R�ЊQ���A�����ߋ���ꏊ�̏o�����ƕ��ʓI�Ɉʒu�Â��Ă��܂����˂Ȃ��B
�@�����ɋ������鎞�A���X�܂Ŏv�������������̂ł��邪�A�������A���Z�Ȑ����A���ߑ��̒��A���ۂ̊S���e�Ղɕʂ̂��̂֒u��������Ă��܂��B
10/25(��) �u�₩�����@
1:45�N���A�܂����C���邢�B�l�R����ɂ��炾��B3:00���[�`���ɁB�Ǐ����S�A�Ɠ��ɓ���8:40�a�@�ցA���Ȍ��C�A11:00�a���Ή��B�����A�V���`�F�b�N�A14:00�a���Ή��A�����J���t�@+�A���t�@�A���@���ҏ��u�B�f�[�^�����B19:30�ʒ����X�o�R�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B�����v��4911���B
��ȉƁE�w���҂̊O�R�Y�O���������ꂽ(2)�@�s�сA�����ԐړI�ɉe������
�@�O�R�Y�O��(1931-2023�N)�͓����o�g�B1952�N�ɓ����Y���ȉȑ��BN���̑Ŋy����K���A1954�N�w���������ƂȂ�A25��N�����w�����ăf�r���[�B1958�N����1960�N�ɂ����ăE�B�[���ɗ��w�B
�@1960�N�H�ɍs��ꂽN�����E������t���s�ł́A���G�V���ƂƂ��ɑ����̌����Ŏw���߂Đ��E�̞w����ɗ�����A���̃c�A�[�̃A���R�[���ʼn��t���邽�߂ɍ�Ȃ������{���w�Ɋ�Â��s�nj��y�̂��߂̃��v�\�f�B�[�t�͊e�n�̒��O�ɔM���I�Ɍ}�����A��ȉƂƂ��Ă̖��������܂����B
�@���������w������N�������̂�1958�N���Ǝv���B�����D�u�Ƃ����w���Ԃ�ł��̊i�D�ǂ��Ɉ�x�ɖ������ꂽ�B���̌�y����n�߁A��w�I�[�P�X�g���̈���Ƃ��ăA���T�u���𗐂��������͎̂��̉e���ł�����B
�@����1979�N�ɂ�N�����w���҂ɏA�C�B�����������{�e�n�ł̌����ł��т��юw����ɗ����A���㉹�y�̐U���ɂ��M�S�Ɏ��g�B
�@N���ȊO�ł����t�B���A���s�s�����y�c�A���É��t�B���A�_�ސ�t�B���A���t�B���ŗv�E�߂��̂��͂��߁A���{�����̃v���E�I�[�P�X�g���𐔑����w�����A�܂�����҂Ƃ��Ď��w���҂̈琬�ʂŎ��̍v���͌v��m��Ȃ����̂�����A�Ƃ����B
�@���̑�\�I��i�Ƃ��ă��@�C�I�������t�ȁA�����Ȃ�����ق������Ȃ������B
�@�w���̃��n�[�T���ł͑�������炸�t�҂����āu�ɂ��Ɣ�����ۂ������v��A�u�M�����b�Ƃɂ��v�B ���̂��тɊy�������͐k��������A���ʂƂ��ċ����̂Ȃ��y�Ȃ����ꂽ�A�Ƃ����B
(�ӔN�̊O�R���@yahoo�L�����ؗp)
�@NHK��7����FM�����Ŏ��̒Ǔ��ԑg�����Ԃɂ킽����4���ԂԂ���������B���̃C���^�r���[�̂ق������w�������M�d�ȉ������������ꂽ�B���͂����^�����Ă������B��������Đ����Ȃ��瓖������ڂ����̏������L�ڂ��Ă���B
10/24(��) �u�₩�ȉ������˗�p�@���ʕa�@�O���@�C���t���N�`���ڎ�
1:45�N���A���������A�Ǐ����S�A���˗�p�ŗ₦��B5:30�R�S�~�W�Ϗ��ɁB6:40�o�X�a�@�ցA7:00-8:15�a���Ή��A8:45-12:50���ʕa�@�O���A�敾�B13:00���n�a�@�B�����A�V�����́A�C���t���N�`���ڎ�A15:00�a���Ή��A��厏���́B�f�[�^�����B�V���`�F�b�N�{���́A�C���邢�A���N�`���֘A���B19:30�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B�����v��8626���B
��ȉƁE�w���҂̊O�R�Y�O���������ꂽ(1)�@
�@�O�R�Y�O����2023�N7��11���A�����t���a�̂��ߒ��쌧�̎���ł��S���Ȃ�ɂȂ����B���N92�B
�@���͎������߂Đ��̃I�[�P�X�g���������̎w���҂ō��ł����̎��̗l�q�͑N���Ɏv�������B
�@�䂪�Ƃɂ͒~���@2��Ƒ�ʂ�SP���R�[�h������A���̊i�D�Ȃ�������ł������B�q���p�̃��R�[�h��20-30���͂��蓶�w�𒆐S�ɂ悭�������B���R�ƁuG����̃A���A�v�u�^�C�X���ґz�ȁv���A�N���b�V�b�N�̏��i�ɂ��e����ł����B
�@����Ȏ������y�ɂ̂߂荞�܂��錈��I�@��͒��w1�N���ɖK�ꂽ�B
�@����[���A�����������I�C�Q���E���b�t���w���A���X�e���_���E�R���Z���g�w�{�E�nj��y�c�̉��t�NHKTV�Œ��p���ꂽ�B�ŏ��̋Ȃ̓x�[�g�[���F���́u�G�O�����g���ȁv�B�薼���璮�������Ƃ��Ȃ��������A�ŏ��̋��t�a�������r�[�ɑS�g�ɒ������������B
�@���ꂩ��Ԃ��Ȃ��A������NHK�����y�c���t����@��K�ꂽ�B
�@���w1�N��2�N���͖Y�ꂽ���A�s�̎s���̈�ق�NHK�����y�c���t��J���ꂽ�B�s���̈�قɃp�C�v�֎q����ׂẲ��ݒ�ŁA�Ȃ͑O1/3�قǁA���E���̓����Ȃł������B
�@���t��͎w�����O�R�Y�O���A�Ƒt�҂͐[��i�����A���j���q���B�R���T�[�g�}�X�^�[�͊C��`�Y���B�Ȃ̓E�G�[�o�[�u���e�̎ˎ菘�ȁv�A���[�c�A���g�u�s�A�m���t��20��K466�v�A�h�{���U�[�N�u�����ȁ@��X�ԁi�V���E���j�v�B�A���R�[���́u�t�B�K���̌������ȁv�A�O�R�Y�O��ȁu�nj��y�ׂ̖̈ؔ҂��́v�B
�@�u���e�E�E�v�̕s�����������Ă�悤�Ȍ��̃g�������ɂ�邤�˂�A�u�s�A�m���t�ȁ@K466�v�̓Ɠ��Ȍ��̍��݁A�u�V���E�����ȁv�̃_�C�i�~�Y���E�E�E�B���̊ԁA���͑S�g�ɁA�p�ɂɒ��������̂������Ȃ��璮���Ă����B�R���}�X�̊C�쎁�̉��͏I�n�ۗ����Ē��������B
�@�����S�Ă����ɂƂ��đN��ȑ̌��ł���A���̌�A���y��A���Ƀo�C�I�����A�`�F���ɋ����������A��w�ł̓I�[�P�X�g���ɑ����A�����̉��t��ɒʂ��A���Ɏ���܂ő�\�I��̈�ƂȂ��Ă���B
�@N�����t��̌�ALP�p�̃��R�[�h�v���[���[���w�������B�������R�[�h�͂�������Ƃ͍w���ł��Ȃ��قǍ����ł���A�X�e���I��3200�~�A���m�����ł�2800�~�قǂœ����̃��R�[�h�͒������Ȕ������ł������B2�N�قnj�́A����3�H�t���̉��h�����z5500�~����������E�E�E�B
�@�ŏ��ɍw���������R�[�h�́u�^���v�B���b�V���E�z�[�����V���^�C���w���A�E�C�[���v�����W�J�nj��y�c�̉��t�B�{���Ƀ��R�[�h�����茸��قǒ��������̂ł���B
10/23(��)�@�u�₩�ȉ��� ���N�N���j�b�N�h�b�N
1:45�N���A�����̔@���B6:40�o�X�a�@�A7:00-8;45�a���Ή��A9:00-11:30���N�N���j�b�N�h�b�N14��+���ʔ���14���B1145�a�@�A�����B�Ǐ��A���H�͒Y�������n���o�[�O�B�V�����́A���q123�֊֘A���R���q���u�ė��̐V�����v�����B�Ǐ��B15:00�a���Ή��B���������ȂǁB19:10�A��E�[�H�A20:30�A�Q�B�����v��7598���B
��ځ@���N�̏H�c�͏�������(12)�@�N�}(6)�@�N�}����{�����Ăǂ����낤
�@�ǂ�����ΐl�ԂƃN�}�Ƃ������ł���悤�ɂ��邱�Ƃ��o����̂�!!!
�@�N�}�̌̐����͕K�{�Ǝv�����A�N�}�̑ΐl�Ԋς��ς�����̂ł��ꂾ���ł͕s���Ǝv���B
�@�N�}�ɑ��Đl�Ԃ͔�͂ł���B�Ȃ�A���͑N�}����{���͂��Ă͂ǂ����A�Ǝv���B
�@���ĎR�`���ł͍������ƌĂ��D�G�ȃ}�^�M�������āA�F�Ȃǂ̏b�Ɏg���Ă������A���a�����ɐ�ł����B
�@�ː�K�v�̏����w����������x�́A�������̍Ō��1���Ƃ��ꂽ�u�`���v�̎p��`������i�ł���B�����ǂނƍ������̗��Ƃ��Ă̗D�ꂽ�Z�\���悭�킩��B
�@�}�^�M���́A�Â�����}�^�M�ɂ���ăN�}��V�J�̎�ړI�Ŏg���Ă������{�̒��^�̗��̂��ƁB
�@���k�̃}�^�M�ɂ͌����g���ĒǐՂ��d���߂��@���������B�e�����y�����ȍ~�́A�Ìy���A��茢�A�������Ȃǒn�挢��A�ꂽ����s���Ă����B�������Ȃ���A����14�N�i2002�N�j�ɒ��b�ی�@����������A���Ɋ��݂����ĕߊl������@�͋֎~����A����ƂƂ��ɗ�����@�͔p��Ă��܂����B
�@��T�A��Ȓ��ʕa�@�̊O���ɍs�������A��k�n���ł��N�}���p�ɂɏo�v���邽�߂ɔ_�Ƃł͊댯�Ŕ_��Ƃł��Ȃ���ԂŁA���Ƀ����S�̔�Q���傫���Ƃ����B
�@��͂Ȑl�Ԃ���邽�߂ɁA���Ƃ܂ł͌���Ȃ����N�}�ɑ���Њd���̋Z�\�����������{�����Ă͂ǂ����A�Ǝv���B
�@�l�Ԃɑ��Ă̓r�r��Ȃ��Ȃ����N�}�����^���Ƃ��̖i���鐺�ɋ�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���B
�@�H�c���ɂ͏H�c��������B
�@�H�c���͍��̓V�R�L�O���Ɏw�肳��Ă���B��̑�^���ŁA�i�]��Ȃǂł͎p�`�̔����������d����Ă���B�m���ɉ����\��ł͂���B
�@���Ƃ��Ă̋Z�ʂ͂ǂ����낤���H���͂��̒m�����Ȃ����A�N�}�Ƃ��Ă̋Z�\����������ɕ]�����傫���Ȃ邾�낤�B
10/2�Q(��) �~�J�قڏI�� ���X�܂�
�@1:30�N���A3�������烋�[�`����ƁB�Ǐ��A�ߑO���w�A�Ǐ��B12:00�j���[�X�A�̂ǎ����B���ۃ_���A���ڎw�����~�J�̂��߂ɒ��߁A���n�a�@�ɁB�Ɠ���17;00���܂Ŕ������ق��B�V���`�F�b�N�{���́B�����ی��֘A���ރ`�F�b�����B19:00�Ђ�̂⏑�X�o�R�A��B20:30�A�Q�B�����v3450���B
��ځ@���N�̏H�c�͏�������(11)�@�N�}(5)�@�N�}���l�Ԃ�����Ȃ��Ȃ���!!!
�@�ߍ��A�N�}���̂��ς���Ă��܂����A�Ƃ����v���Ȃ��B
�@���ẮA�l�ԂƃN�}�Ƃ̋��Z�悪���m�ɕ�����Ă����B���ꂪ�Öق̗����ł����������̊W���ˑR�ɔj��ꂽ�B
�@���N�O����\�������������A���ɍ��N�̏H�c�̃N�}�����͉������Ȃ��B
�@�q�A��œ��X�ƁA�ʎ�����Z��n�ɁA���ɂ͎s�X�Ɍ����B�����Đl���P���B
�@�]���N�}�͉��a�Ől�Ԃ�����Ă����B�l�Ԃ̋C�z������Ǝ�������R���ɓ����Ă����B
�@�H�c�����N�}�̔�Q���_���g�c�ɑ����B ���ł��A�V���ł���Q�������Ă��邻�����B���̕ω��́A�N�}�̌̐��������A���H���ł���h���O����u�i�̎������Ȃ����炾�Ƃ��������������ł͗������������B
�@�N�}���g�̑ΐl�Ԋ��o���ω����Ă���Ƃ����l�����Ȃ��B
�@�N�}�͖{���ɊÂ����̂��D�����B�Ó}�̃N�}���A���̃X�C�J��ʎ����̃u�h�E�A�����S�̖������ڂ����B�����ɍs���Ώ���ɐH�ׂ���B���N�͎��ʂ������ȉ��̂�_���A�u�h�E�_��������A�Ƃ����B
�@�l�Ԃ͏���W�I��炷�����ŏP���Ă��Ȃ��B�l�Ԃ͎����B�ɂƂ��Ď育�킢�G�łȂ����Ƃ��o�����B
�@�t�ɁA����W�I�̉������������炻���ɐl�Ԃ����Ă��ĉ������������̂������Ă���̂ł͂Ȃ����H�@������Ƌ������Ă݂邩�A�Ƌ߂Â��Ă���̂ł͂Ȃ����B
�@�l�Ԃɕ߂炦��ꂽ�N�}�͋쏜����Ė߂��Ă��Ȃ��̂ŁA�l�Ԃ͕|���A�߂Â��ȂƂ��������͓`���Ȃ��B
�@�l�̏Z�ނƂ���ɂ͔����Ȃ��̂������Ղ肠���āA�l�Ԃ͓����邾���Ŏ����B���P���Ă��邱�ƂȂǑS���Ȃ��B�l�ԂȂ�Ď��͕|�����Ȃ��̂��B
�@�����A�~���܂ł̎��Ԃ������Ă���B���������������Ă���q�ǂ���A��ďo�����悤�B
�@�N�}�����͏���ň��S�ȉa���m�����̂��B
�@�ˑR�A�l�Ԃɋ߂Â��Ă����B��������l�ς�肵���B�ٕςƌ����Ă����B
�@ �������ƃN�}�͂��������W�ɂȂ��Ă��܂����A�ƍl����ׂ��ł͂Ȃ����낤��?
�@�����Ȃ�ƑN�}��͒P�ɋ쏜�ɂ���Č̐������点����ōςނƌ������̂ł��Ȃ��B�ʎ��������ȂǍ���ł��낤�B
�@�ǂ�����ΐl�ԂƃN�}�Ƃ������ł���悤�ɂ��邱�Ƃ��o����̂�!!!
�@�N�}�̌̐����͕K�{�Ǝv�������ꂾ���ł͕s���̂悤�ȋC������B
10/21 (�y) �~�J ��O�ғ��ȓ�����(��)
�@2:00�N��������v�`����ɃO�_�O�_�߂����B��������~�J�����ƁB5:00������ʏ�̍�Ə����ɁB�V���`�F�b�N�ȂǓǏ��B9:30���o�U�[�ɍs���Ɠ��ɓ���A�A�g���I���o�R���n�a�@�A�V���`�F�b�N�ق����w�B�Ǐ��B13:00�a���Ή��B�Љ��쐬�A���̌�͐����ی��W���ސ����B19:00�A��[�H�A20:30�A�Q�A�����v7124���B
��ځ@���N�̏H�c�͏�������(10)�@�N�}(4)�@�R�c�d�b�E���[�����ޖ@(����)
�@3���쏜�����H�c����������4���[������5���ɂ���450���ȏ�̍R�c�d�b���������Ă����Ƃ����B�u�ǂ����Đ��������܂ܓ������Ȃ������̂��v�u�l�Ԃ̓s���Ŗ���D���ȁv�Ȃǂ̏펯�I���_�A���A�I�O��̓��e�ŁA���[����130���ȏ�͂����A�Ƃ����B
�@���̒��ɂ͉ɐl��������̂��A�Ǝv���B����ȓd�b�Ɏ��Ȃ�ǂ��Ώ����邩�B�ɂȂ̂ōl���Ă݂��B
(����)
�u���������A�O��������ł��B�v
�u�N�}�ɑ��邲�ӌ��ł��傤���H�H�S���҂ɉ܂��̂ł��҂����������B�����d�b����ύ��ݍ����Ă��܂��̂ŏ��X���҂����������i�E�E�E�ƌ����Ă��̂܂�5�����炢�҂�����j�B�v
�u���������A�N�}�S�������ł��B�v
�u���������A�������ܒS���҂��s�݂ł��B����̃N�}�쏜�ɑ��邲�ӌ��ł��傤���H�H�@��ς��肪�Ƃ��������܂��B�������肨�f���������܂��B���̓d�b�͘^������Ă���܂��B�c�[���Ƃ����M�����̌�A���p����10���ȓ��ł��b�����������B�S���҂���قǂ��Ԏ��������܂��̂ŁA�M���l�̏Z���A�����A���ʁA�N��A�d�b�ԍ������b�����������B�v
�u����ł͂�낵�����肢�������܂��B�v�u�c�[���c�[���E�E�E�E�E�E�E�u�c�b�B�v
�@����ő��̓d�b�͑ގ��ł���B���M�҂��L�ڂ���Ă��Ȃ��s���̃��[���͖�����������B
�@���f�d�b�Ȃǎ����ǂ��m��Ȃ��T�ώ҂������Ă�����̂ł���B�^�ʖڂɑΉ�����K�v�͂Ȃ��B
�@������ꌴ���ŏ����������o���ꂽ8��24�������1�J���ԂŁA�k���̓��{��g�ق������R�c�̓d�b��40�����ȏ�ɂ̂ڂ����B�܂��A���������𒆐S�ɁA���{���̊e��̍s���@�ւ�A�ʂĂ͈�ʂ̏��X�ɂ܂ŁA�������瑽���̌����点�d�b���|�����Ă����B�قƂ�Ǐ������ɂ��Ă̒m�����Ȃ���҂���ł������B�����ł͍ŋߎ�҂̏A�E��ʼnɐl���������������Ƃ����낤�B
�@�������A�����������O���鑬���������قǑ��������B���̗��R�͔ނ炪�ǂ�����ׂ������u�O�����v���߁A�ƍl�����ق����ǂ��悤���B
�@�l�b�g��̉���A�R�c�d�b�Ȃǂ���Ȃ��̂��B
�@�^�ʖڂɈ����K�v�͂Ȃ��B
10/20(��) �~�J�I���@ ��Ȓ��ʕa�@�O�� �@��N��ʉ���
2:00�N���A������ƃO�_�O�_�߂����B�q�̊֘A�{�ǂ݁A5:30�R�S�~�o���B�܂��Â��B7:35Taxi�w�A8:11���܂��A���Taxi�B8:50��Ȓ��ʕa�@�O���B�ߌ㉺���ؓ����z���������B15:30���艮�Ȃ��ŋA�@�B�Ɠ��p�ӂ������H�ۂ�B�����A�V���` �F�b�N�ł����B16:00 -17:30�a���Ή��B19:15�A��E�[�H�A20:30�A�Q�B�����v��5103���B
��ځ@���N�̏H�c�͏�������(9)�@�N�}(3)�@�쏜�̎����̂ɍR�c�d�b���[���E��
�@10��4���H�c���������̏��X�̍�Ə����ɃN�}3�����N�������̂܂ܗ��܂����B3����5�����ɕߊl����A���̌�쏜���ꂽ�B
�@�s����1�����߂������ߗZ����͈��g����ƂƂ��ɁA�g�߂ɔ���N�}�̋��Ђɉ��߂Čx���������߂Ă����B
�@��叐�⒬�ɂ��ƁA�N�}�͑̒���1m�Ɩ�50cm��2���Őe�q�Ƃ݂���B3����4���ߑO7��������A��Ə����ɓ����Ă����̂E���������A��叐�ɒʕ��B�쏜�̂��ߔ��|��炷�Ȃǂ��ĊO�ɗU���o�����Ǝ��݂����A���v�܂łɂ��܂��������A���ɕ����߂���şB���d�|�����B
�@5���ߑO6�����뒬�E����F��W�҂��B��3���������Ă��邱�Ƃ��m�F�B�l�����ꂽ�R���ŋ쏜�����B���́u�R�ɓ������Ă��A�Ăѐl���ɖ߂��Ă���\��������B�����̈��S����邽�ߋ쏜����ׂ��Ɣ��f�����v�Ƃ��Ă���B
�@����͔���������̓���350m�B�c��ڂ̒��ɏZ��_�݂��Ă���B
�@3���쏜�������Ƃ̓j���[�X�ŕ��ꂽ���A��������4���[������5���ɂ���450���ȏ�̍R�c�d�b���������Ă����Ƃ����B
�@�d�b�̓��e�́u�ǂ����Đ��������܂ܓ������Ȃ������̂��v�u�l�Ԃ̓s���Ŗ���D���ȁv�Ȃǂ̓��e�ŁA���O���炪�����Ƃ݂���B�܂��A���l�̓��e�̃��[����130���ȏ�͂����A�Ƃ����B
�@���́A���ꂪ�F�肱�ǂ����̋߂��ŏZ����ی�҂̕s�����傫���������Ƃ�A����F��Ȃǂ̈ӌ������܂��đΉ������B�u��������́w���S�����x�Ƃ����������������Ă���B�����肾���A�������Ē��������v�A�ƌ����Ă���B
�@���͏H�c���ł͍��N�N�}�̐l�I��Q��50���ȏ���������Ă���B�N�}�̋��Z��ƃq�g�̋��Z�悪�����荇�������ƂŃN�}�̊댯���͑����Ă���B�N�}�̋쏜�͂����ƐϋɓI�ł����Ă����Ǝv���B�I���ɓ������N�}�����̂܂ܓ����Ȃǂ̑Ή��͍l�����Ȃ��B
�@���ł͋��d�b�Ɏ��ɒ��J�ɑΉ������悤�ł���B����J�Ȃ��Ƃ��A�Ǝv���B�������A�ڍׂ͂킩��Ȃ����A���ɂ͋y�э��A�㍘�̑Ή��̂悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B�����ƋB�R�Ƃ��Ă����B
10/19(��) �܂�͂�@
2:00�N���B�N���A�����̔@���B�Ɠ��ɓ���8:40�a�@�ցA���Ȍ��C�A11:00�a���Ή��B�����A�V���`�F�b�N�A14:00�a���Ή��A15:00���҉Ƒ��ʂ���A�݂낤�ɂ��āBAlb1.2�̊��Ҏ��S����B�{�@���@�ȂɏЉ��쐬�A18:00�Ɠ�Web�w�K��A�d�NJ��҂ɂ�����h�{�Ǘ��B19:30�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B�����v��5154���B
��ځ@���N�̏H�c�͏�������(8)�@�N�}(2)�@���������Ō��͋쏜���j����
�@�H�c�����ŃN�}�̖ڌ����A�l�g��Q���������ł���B
�@NPO�@�l�u���{�c�L�m���O�}�������v(�L����)�̕ēc��\�́A�N�}�Ƒ������Ȃ����߂ɂ͎����̃z�[���y�[�W�Ȃǂŏo�v�����m�F���邱�Ƃ��厖���Ƃ���B�������A�H�c�����ł͂���Ȃ��Ƃ��K�v�Ȃ��قǂ̍��p�x�Ŗڌ����A��Q�����B�S���ł��L���̔�Q�����Ă���B
(�H�c���̃N�}�ɂ��l�I��Q�p�x�͊��ƂƂ��ɓˏo���Ă���)
�@�l�ԑ��̎���Ȃ̂��A�N�}���̎���Ȃ̂��H�H
�@ �u�N�}�悯�v�̗�̓L�[���ƍ���������ނ���^�̂��̂����ʓI�ŁA�u���W�I�͑剹�ʂɂ��Ă��R���ł͉����z������ĉ��̒ʂ肪�����A���ʂ͔����v�Ƃ����B
�@�N�}�̊������ԑт͖�������[��ꎞ�Ƃ������Ƃ��o���Ă��������B
�@�N�}�Ƌߋ����ő��������ꍇ�A�z�[���Z���^�[�ȂǂŐ���~���甄���Ă��铂�h�q�������������N�}���ރX�v���[���L���B
�@�o�v������
�@9�����܂łɑS����1��4943���A�O�N�������4210�����������B
�@���Ȃ͐l�����⍂��Ȃǂɂ�藢�R�̉����肪����Ȃ��Ȃ�B��₷����Ԃ̑����A�k������n�̑����Ȃǂ������Ă���B
�@������g��
�@�N�}�̐����悪�L�����Ă���B���Ȃ̓N�}�̐������19�N�x��10�N�x�̔�Ŗ�1.4�{�Ɋg�債���̂Ƃ̒������ʂ\�����B
�@�̐��g��
�@�N�}�̌̐����������A�ǔ��V����17�N�x�ȍ~�Ƀc�L�m���O�}�}�̐��������������{�����s�{���̌��ʂ��W�v�����Ƃ���A�����4��4000���B17�N�x�͐����15000���ł��������A��3�{�ɑ������B
�@�N�}�����������R�ɂ����_�w����̍�������(�쐶�����w)��1990�N��ȍ~�ɂ̎��R�ی�ӎ��̍��܂�ɂ��A�ߏ�ȋ쏜���狤����ڎw���ė}���X���ɂȂ������Ƃ��w�E����B�����́u�l�����ӂɌ����N�}�ɂ́A�蒅�����Ȃ����߂̒ǂ�������쏜�ߊl���ׂ��B���ɂ������x�����K�v���v�Ǝw�E����B
�@�H�c���́u�N�}���w��Ǘ����b�Ɂv�ƍ��ɋ��߂Ă���B
�@�w��Ǘ����b�̃V�J��C�m�V�V�́A���̌�t�������ƂɌv��I�ɋ쏜���Ă���B
�@�H�c���͑�5���c�L�m���O�}�Ǘ��v��ŁA�ߊl����𐄒萶������23���i�N��1012���j�ƒ�߂Ă���B�N�x���Ƃɏ�������Ē������Ă���B
�@��N�x�̕ߊl����442���Ə��Ȃ��������߁A�{�N�x�̏����1582���B����9�����_��1032����ߊl���Ă���B
�@���|�m���͐l�Ԃ̈��S���ŗD��A�ƌ�����߂�ߊl����ɂ�����炸�ɕߊl��i�߂�l���������A�e�ۂ̔�p���x��������j�𖾂炩�ɂ����B�����ߊl�ɉ����Ďx�����ԘJ���i1��������5000�~���x�j�Ƃ͕ʘg�ŁA���z�͍���l�߂�B
10/18(��) �@���� �@�@
1:45�N���A���������A�Ǐ����S�A�Ɠ��ɓ���8:40�a�@�ցA���Ȍ��C�A11:00�a���Ή��B�����A�V���`�F�b�N�A14:00�a���Ή��A�����J���t�@+�A���t�@�A���@���ҏ��u�B�f�[�^�����B19:30�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B�����v��5587���B
��ځ@���N�̏H�c�͏�������(7)�@�N�}(1)�@�a�s��(?)�Ńq�g�̐������ɏo�v
�@�H�c�����ŃN�}�̖ڌ����A�l�g��Q���������ł���B
�@�Z��n�ł��N���Ă���A���͂�ُ펖�Ԃƌ����Ă����B
�@�H�c�����A���H�̍��L�ђ����ŔM���̂��߂��N�}�̉a�ƂȂ�̎����u�勥��v�ŁA�w�ǎ������Ă��Ȃ��A�Ƃ����B
�@�N�}�͐H�ו������ߗ��֍~��Ă��Ă��邱�Ƃ��N�}��Q�̊g��̈���ƂȂ��Ă���\��������B�N�}���~�����T���Ĕ牺���b��~�ς���K�v������A�a�����߂čs���͈͂��L���A������Z��n�Ɍ���鋰��͏\������B
�@10��9���͏H�c�s�V���̏Z��n�ŁA�U���Ȃǂ����Ă����j��4�l�����ꂼ��ˑR�N�}�ɏP���A����r�ɂ��������B����1�l�͎���~�n���Ŕw�ォ��P��ꂽ�B�P�����N�}�̍s���͕������Ă��炸�A�Z���͕s����������܂܁B����͌��x�^�]�Ƌ��Z���^�[�̂��ŁA���ӂɂ͏����w�Z��ۈ牀������B�Z���������ł����S�ł���悤�A�x�@�͖ܘ_�̂��ƕی�҂̕��X�������ɁA�����̑��}�ɗ͂����Ăق����B
�@
�@���ɂ��ƁA���N�̌����̃N�}�ɂ��@���N�A�H�c���x�Ɋ�ꂽ�N�}�̖ڌ��������A15�����_��2144���ƂȂ�A�L�^�̎c��2009�N�ȍ~�ŏ��߂�2000�������B
�@�l�g��Q�͓������݁A��Q�̗v��41��45�l�B�����A�l���Ƃ��ߋ��ő����X�V�����B
�ŋ߂̒n�����H�c�@�V���̌��o�������ł��قژA���ȉ��̔@���ł���E�E�E
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
?�N�}�A�������߂��Ő��������l�ւ̋��|�S�����Ȃ��@
?�H�c�����ŗ�ԁE�ԂƃN�}�̏Փˑ����@�����l�Ȃ�
?�H�c������ÃZ���^�[�̕a�@�o������ɃN�}�@�F������ߊl
?�{�����a�@�̌��ւɃN�}�N���@�ߊl�A�쏜
?�������H�Q�A�H�c�E��قŔ���n�{30�H�H����@�n�E�X�ɂ����N�}3�����쏜
?�N�}�ɏP��ꎭ�p�̏������S�@�v�͓������܂�d���A�L�m�R�̂蒆�A
?�k�H�c�E�鑃�s�X�n�ŃN�}�ɏP���5�l�d�y���@�o�X�҂��̏��q�����炯��
?��َs������ŃN�}�̐l�g��Q�������@17���A�N�}�ɂ��l�g��Q���������A80�㏗����40��j����2�l�������������B
?�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�@�N�}�̍s���͈͂͑����L�����Ă���ƌ����������B
�@�]���̓N�}������͂����Ȃ��Ǝv���Ă����n��ɂ�����Ă��邱�Ƃ�F�����Ȃ��Ă͂����Ȃ��Ȃ����B�܂��͎����̏Z�ޒn��ɃN�}�͗��Ȃ��Ƃ̎v�����݂�r�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@���́A����܂ł̃N�}�l�g��Q��h�����߂ɗ��W�I�Ȃǂ��ʼn����o���Đl�̑��݂��A�s�[�����邱�ƂŔ����킹��h���悤�ɂƍĎO�Ăт����Ă���B����ł����������ꍇ�́A�������ジ��������āA�Â��ɂ��̏�𗧂�����悤�ɂƂ̌Ăт������A�J��Ԃ����M���A���N�͊w�Z�ł��w�����Ă���B
�@�������A���ꂾ���ł͕s�\���ł��낤�B
10/17(��) �܂莞�X�~�J�@���ʕa�@�O��
1:45�N���A���������A�Ǐ����S�A�J�̂Ȃ�5:15�R�S�~�W�Ϗ��ɁB6:40�o�X�a�@�ցA7:00-8:15�a���Ή��A8:45-12:45���ʕa�@�O���A�Ή�����҂���敾�B�r����J�ł��ԔG��A13:00�a�@�B�����A�V�����́A15:00�a���Ή��A��厏���́B�f�[�^�����B19:30�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B�����v��8344���B
��ځ@���N�̏H�c�͏�������(6)�@�������B�@�Z�~�A��͏��Ȃ�����
�@���N�̉Ă̓Z�~�̖��������܂蕷���Ȃ������B
�@��N�܂łƖ��炩�ɈقȂ�B
�@��͂肱����L�^�I�Ȗҏ��̂��߂��Ǝv���B
�@�Z�~�̈��D�Ƃ⌤���҂ł�����{�Z�~�̉�(�_�ސ쌧) �ɂ��ƁA�����ɐ�������Z�~��30��ȏ�B�H�c�����ł͏��Ȃ��Ƃ�10�킪�m�F����Ă���B ���n�ɂ��ޑ�\�I�ȃZ�~�́A�����F�̉H�����A�u���[�~��~���~���[�~�ȂǁB
�@���Ƃ̓Z�~���u�ăo�e�v�����\����������B
�@���̎���ɂ͌��\���������B���N�āA�P���L��C�`���E�ɃZ�~���W�܂�A���~���ɂ����Ė����������܂�������ԂɂȂ�B�Ƃ��낪���Ă͂قƂ�ǃZ�~�̖������������Ȃ������B
(�䂪�Ƃ̒�̈�p�@�����������N�䂪�W�܂������̂�)
�@�H�c�s�ł͖ҏ���(�ō��C����38�x�ȏ�)�����������B���̏������Z�~�ɉe����^�������Ƃ͏\���ɍl������B
�@���{�Z�~�̉�̊����̈ӌ��ł́u�Z�~�Ɍ��炸�����͏����ɋ����킯�ł͂Ȃ��A���N�̂悤�Ȍ������������ƃ_���[�W�����\��������B �����̂��߂ɖ��Ƃ������Ƃ��܂߁A�Z�~�̊������̂��̂ɉe�����o��B�A�u���[�~�͂��Ƃ��Ə��������ł͂��܂芈�����Ȃ���ނ��Ƃ����A�C����35�x���Ă������ȃZ�~�͏��Ȃ��v�Ƙb���B
�@�Z�~�̗c���͓y����5-6�N�߂����A�ď�ɒn�\�ɏo�Ė�ɉH������B�y���ł͂܂����H�c�̋C��������Ȗҏ��ɂȂ��Ă���Ƃ͍l���Ȃ������ł��낤�B���X�Ƃ��Ēn��ɔ��o�Ă݂��炠�܂�̏����ɜ��R���A�낭�ɔɐB�������ł��Ȃ��܂܂Ɏ������}�����̂ł͂Ȃ����A�Ƒz����y�����B
�@���Ă͉�����Ȃ������B
�@���͐^�Ă̊ԁA����ł͂قƂ�Ljߕ������Ȃ��B�ŏ����̈ꖇ�����ł���B����Ȏ��͉�̉a�H�ɂȂ�₷���p��Ɏh�����B�������y�������ɂƂ��Ă͂ǂ�قNj�ɂł͂Ȃ��B�r�Ɏ~�܂����ꍇ�Ȃǂ́A�����z���Ă������Ԃ��c���ł����̂������ƌ��āA���������Y�ނ̂���A�ƌĂт����邱�Ƃ�����B���͏����ɁA���X�̓����B�̔ɐB�@�\�Ɍh�ӂ������Ă��邩��ł���B
�@�����A���Ă͂قƂ�ǎh����Ȃ������B
�@�E���܂̃��[�J�[�u�t�}�L���[�v(����)�̍L��S���҂ɂ��ƁA6~8���͉�i�̔���グ���L�єY���A9���ɓ��莝���������Ƃ����B�u9�����ɉ�̏��i���L�т�̂͂܂�v�Ƌ����B
�@�{�B�Ől�Ԃ��悭�h���̂́u�q�g�X�W�V�}�J�v�B�l���ċz�ŏo����_���Y�f���I�݂Ɋ��m���A�����ɂȂ�Ɛl��ǂ��B25~30�x�Ŋ����������ɂȂ�A38�x�ȏ�Ŗ؉A�ŋx�ނ炵���B������2�T�Ԃ���1�J���B���X�͋z�����������邱�Ƃŗ����Y�ށB
�@��������L�����Ă���B���������nj������̒����ł́A�q�g�X�W�V�}�J�̖k����1950�N����͓Ȗ،����������A2016�N�ɂ͐X���ł̒蒅���m�F���ꂽ�B���g���Ŗk�サ�Ă���炵���B
10/16(��) �܂莞�X�J�@���N�N���j�b�N�h�b�N
1:45�N���A�����̔@���B6:40�o�X�a�@�A7:00-8;45�a���Ή��A9:00-11:15���N�N���j�b�N�h�b�N14��+���ʐ���1���B11:30�a�@�A�����A�V�����́A���^�����t�H�[�[���J�n�B14:00�A1�V:00�a���Ή��B���������ȂǁB19:10�A��E�[�H�A�Ɠ���Web�u������_�o��Q�����A20:30�A�Q�B �����v��7214���B
��ځ@���N�̏H�c�͏�������(5)�@�_�Ƃɂ͌�������������(2)
�@�H�c�̓_���A��L�N�͔|������Ō��̓��Y�i�̈�ɂȂ��Ă���B
�@�����ő������L�^�I�Ȗҏ��ƉJ�s���ŁA���Y�̃_���A��L�N�Ȃǂ̉ԙ��Ɉ��e�����o���B���s���r���ł��͂�Ă��܂�����A�Ԃ��������Ȃ��Ă��܂����肵���B�Ԃ��܂�ɂ����炩�Ȃ��Ȃǂ̔�Q���m�F����Ă���A�H�̔ފ݂⌋�����Ɍ������o�������}���钆�A�_�Ƃ͑Ή��ɒǂ��Ă���B
�@�H�c�s�Y�a�ɂ��镽��t�@�[���ł͔��ƃn�E�X7����4��5000�{�̃_���A���N�o�ׂ��邪�ҏ��̒�3�����͂�Ă��܂����B8���̏o�חʂ�6000�{�قǂŁA��N��1��~2���{�̔������x�܂ŗ������B
�@���N�H��700�i��7000���̃_���A���炫�ւ�H�c���ۃ_���A��(�H�c�s) �ł��A�t��Ԃ����Ă�����ȂǁA����Ɏx�Ⴊ�o�Ă���B9��������10���ɂ����ĉԂ��炩���邽�߁A7-8���ɂ͊J�Ԃ����Ԃ�藎�Ƃ������Ȃ������A�Ƙb���B
�@JA�H�c�Ȃ܂͂��j���n��c�_�Z���^�[(�j���s)�ł́A�ފ����̏o�ׂ̏������{�i�����Ă��邪�A�ҏ������ŊJ�Ԃ��x��A1�����肽��̏o�חʂ͗�N�̔��o���قǂɂƂǂ܂�B
�@�����|�U���ۂɂ��ƁA�ҏ��ɂ�鐶��s�ǂ͌����S��ɋy�сA�����d�_�i�ڂƂ���_���A�A�����h�E�A�g���R�M�L���E�A�L�N�ށA�����ނŏo�חʒቺ������ꂽ�Ƃ����B
�@�������K�͂Ƀ_���A���͔|���Ă��āA�����̊Ԃ͌͂炳�Ȃ��悤�����𒆐S�Ɉێ����邾���Ő���t�ł��������A�����̐��_�Ƃł����l�̉e�������Ă����A�Ƃ̂��ƁB�ێ��Ǘ��͂������ςȂ��Ƃ��������낤�A�Ǝv����y�����B
�@�L�^�I�Ȗҏ�������������s�ŁA���n�����}���郊���S��C���m�R�A�卪�ȂǓ��Y�i�̐���s�ǂ��m�F����_�Ƃ͕s�����点�Ă���B
�@�R���y���̃C���m�R���Y�҂͌͂ꂽ�t�����Ċ��܂点���B��N�Ȃ�g�����Ă��鑐����A���N��1m�قǂŐ������~�܂��Ă���B�����ɂł����C���m�R�͏��Ԃ�Ő������Ȃ��B���ʂ͗�N�̔������x??�Ƃۂ�B
�@���̃C���m�R���w�䂪50cm�قǂ����L�тȂ������B�������m���߂�̂��|���Ă܂��@��N�����Ă��Ȃ��B�y�̉��ł͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��낤��??
�@���Ԃ肪�����p�̃_�C�R��������͂܂炾�Ƙb���B
�@���c���̃����S�_�Ƃł́u����v�̎��n���Ő��������A���܂��ɉʎ����F�Â����A ���ɔ����Ԃ��܂�����x���B�u����̉��x�������������߂��A���F���i�܂Ȃ��B�u���Ă��⍂����Q�őʖڂɂȂ����ʎ�����N��舳�|�I�ɑ����v�ƌ�����B
����ł͎s�ꉿ�l�͂قƂ�ǂȂ��A�W���[�X����H�p�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����v�Ɨ͂𗎂Ƃ��Ă���B
�@�䂪�Ƃ̃����S�͌����قƂ�ǃ[���ł������B
10/15(��) �����@�[������~�J�@�Ɠ��̈֎q�̃L���X�^�[����
1:30�N���B�Ɠ��̈֎q�̃L���X�^�[�����A�V�S�~���̒�ɃL���X�^�[�����B�k�R�ȂǁB
�r���Ŕ������B12:00�j���[�X�A�̂ǎ����͑�Ȏs�A�V���蔲���A�Ǐ��B14:30��f�Ɠ��ɓ���A�H�c�X�ǁA�v�ۓc�V���̃R�C�o�R�A���n�a�@�BPicc�p�Љ��쐬�A19:00�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B�����v��5790���B��N�̓}���`�O���A�i�X�������A������{�@��o���A�ȂǂȂǁB
��ځ@���N�̏H�c�͏�������(4)�@�_�Ƃɂ͌�������������(�P)
�@���Ȃǔ_�Ƃ̐^�����������Ă��Ȃ����A����ł����낢��e�����������B
�@�L�^�I�Ȗҏ��Ɍ������Ă��錧���ŁA�ƒ{��_�앨�ɏ����̉e�����o���B �i���ቺ����ʌ����������܂��앨������A�_�Ƃ͑�ɒǂ�ꂽ�B
�@���ł͈�̐��炪�����i�݁A�o�䂩����܂ł̊��Ԃ���N���1�T�Ԃ���10���قǒZ���Ȃ肻���Ƃ����B����ȏ�Ԃ��Ƃ�1��������̏d�ʂ��y���Ȃ�X�������邽�߁A���N�͎��ʂ���������\��������B����Ƃ��ɕ��ϋC���������������Ƃ���A�R���ɏ\���ȓb�����~�ς��ꂸ�����ۂ��Ȃ�����A�����ׂ��Ȃ����肷�锒���n���̔��������O�����B
�@JA�H�c����(�{�X���s) ��2023�N�Y�Ă�1���Ĕ䗦���A9��28�����_��1.4%�ɂƂǂ܂��Ă��邱�Ƃ����������B����JA�ł������ቺ���ڗ����A��Q���u�z���ȏ�v�Ƃ��鐺���オ���Ă���B
�@JA�H�c�����ɂ��ƁA28�����_�̏W�חʂ͖�2��2400�d�B �H���ɉe���͂Ȃ�
���A�قƂ�ǂ�2���āB ���ʂ��������ތ����݂��Ƃ����B
�@
�@JA�H�c�Ȃ܂͂�(�{�X�H�c�s) �Ǔ��̎�H�p�Ă�1���Ĕ䗦�͗�N�Ȃ��90%�قǂł��邪�A9��28�����_��67.5%�ɂƂǂ܂��Ă���B
�@�u�h�E�Ȃǂɂ��e��
�@�����V���C���}�X�J�b�g�Ȃǂ��͔|���Ă���Y�n�ł́A����������т�u���Ă��v�␅�s���Ŕ炪����Ă��܂��u��ʁv�A�����ߒ��Ŏ��������I�ɕϐF����u�k�ʏǁv�Ȃǂ���N��1.5�{�قNJm�F����Ă���B
�@�u�h�E�͔|�͓����Ɩ�Ԃ̊��g�����d�v�Ƃ���邪�A���Ă͔M�і邪�����C�������L����Ȃ��������߂Ƃ݂���B��Q���ŏ����ɗ}���悤�Ə��܂߂ɐ����܂�����A���ɉh�{���s���n�点�邽�ߐL�т��}������肷��Ȃǂ̍�Ƃ�i�߂��B
�@
���_�ɂ��e��
�@�����A��280���̂����炷�钹�C�����ԗ��q��ł́A8�����{������1��������̍���ʂ��ʏ���1���قǗ������B�����Ǝ��x�ŋ����o�e�Ă��A�Ƃ����B���ɓ��ł͐�@���t���ғ����Ă��邪�A����ł����̓����͓݂��A����������{�b�g�ł̓���肪�X���[�Y�ɂ����Ȃ��B�E���Ȃǂɂ����ӂ��K�v�ŁA�K�v�ɉ����ďb��ɓ_�H�Ȃǂ����Ă�����Ă���A�Ƃ����B
�@����n�{�̎Y�n�E��َs�̎���_�Ƃ�8���Ɍv1770�H�����B���s������̔_�Ƃł���880�H���ҏ��̂ق��A�����ݏ�ɏW�܂肷���Ĉ��������B 7����������ُ�ȏ����������A���~���߂��Ă��{�����͌����J���ăO�^���Ǝ���Ă���A�Ƃ����B
10/ 14(�y)�@�������g�@��ǂ�SP�ݒu�@��s�A���ۊ֘A���ސ���
2:30�N���A�����A�k�R�A���̑��A�������ƁB11:00�]���^�ɂ����Ɠ��ɓ���A�v�ۓc�V���̃R�C�ɋ��a�A�p�����o�R�a�@�ցB�X�s�[�J�[�ݒu�A���̂܂܍��w�A�V�����́B�f�[�^�����B��s�A���ۊ֘A���ސ����B�Ɠ��͂���ɏ�����K���֘A�u���o�ȁA18:30�A��A�[�H�A20:55�A�Q�B�����v6025���B
��ځ@���N�̏H�c�͏�������(3)�@����҂̔M���ǒ���
�@���̉āA���܂ő̌��������Ƃ̂Ȃ��قǂُ̈�ȏ������������B�������Ȃ������A�����Ă����댯�ȏ����͉߂����������A�߂��������ł����Ƃ������̂ł͂Ȃ��B
�@���̉ĂɊ��������Ƃ�U��Ԃ�L�^�����ɔ��������B
�@���̉āA�댯�ȏ����������������ŁA�M���ǂ̋^���ɂ��~�}�����Ґ����}�������B
�@5~8���͍�N�����̖�2.7�{�ɓ�����1048�l�ɏ��A���̂���8���͖�7���ɓ�����747�l�B���h�����L�^�����J���Ă���2010�N�ȍ~�ōő��ƂȂ����B
�@9���ɓ����Ă��C���̍����������������݂ŁA���Ȃǂ͗\�h��̓O����Ăт������B
�@8��3���́A������7�l���M���ǂ̋^���Ŕ������ꂽ�B���̂����̈�l�̏����͓Ƌ��ŁA�|��Ă��������ɃG�A�R���͂Ȃ������B�������Ɉӎ��͂Ȃ��A�̉���41���ƍ�����Ԃ������Ƃ����B
�@�������h�Љۂɂ��ƁA���N5������8��30���܂łɔ������ꂽ�̂�1048�l�ŁA���҂�2�l�B65�Έȏ�̍���҂�727�l�őS�̖̂�7�����߂��B
�@�Z����Ŕ��ǂ�������586�l�ʼn��O�ł̔��ǂ�123�l�ł������B
�@8����747�l�́A����܂ōő�������2010�N��374�l��啝�ɏ������B
�@�������ꂸ�ɖS���Ȃ�����9�l�B�������h�Љۂɂ��ƁA���c������18�Ζ����̎q�ǂ��̔��ǂ͍�N��茸���Ă������ŁA����҂�3�{�߂��ɑ����Ă���B
�@�H�c�s���h�{���͍���҂̔����ɂ��āu�����ŃG�A�R���������ɂ���ꍇ�������B�����ɑ̂��������Â炭�A�댯�ȏ�ԂɂȂ�܂ňُ�ɋC�t���Ȃ��X��������̂ł͂Ȃ����v�Ƃ݂�B
�@�M���ǂő̉����オ��ƁA�g���������ǂɂ����Ղ茌�t�𑗂邽�߂ɐS���Ɣx�̓t���ғ�����B�S���̓������ǂ����Ȃ��Ȃ�ƁA�������}�ቺ���A�߂܂���������A��낯����A�������Ȃ��Ȃ�B
�@ ��ʂ̔����ʼn����������邽�߁A �ؓ��̂��������N����B�����̊��҂͈ӎ����������āA�����ɂ��������K�v�ȏd��ȏł��邱�ƂɋC�Â��Ȃ��B
�@��v�Ȑl�͐[���̉���42���܂ŏオ���Ă������Ԃ��͑ς����邪�A���c���ƍ��������ቺ����ɂ�āA�ӎ����������Ƃ�����B
�@�����܂ŗ���ƐS���܂߁A �ؓ��g�D������ɋ@�\���Ȃ��Ȃ�B
�h�䔽�����ቺ���������ǂ���őf�������ɓ���n�߁A���ǂ̒��Ō��t���ł܂�n�߂�B���̌��ʁA�]��S���A�t���A�t���Ȃǂ̏d�v���킪�@�\��Q�Ɋׂ褂₪�Ď����}���邱�ƂɂȂ�B
�@���̂悤�ɁA�M���ǂ͒P�ɒE���ǂ̔��e�ɂƂǂ܂�Ȃ����G�ȕa�Ԃ����B������������s�S�̏�Ԃɐi�s������댯�ȏ�ԂȂ̂��B
�@���������A�����̑Ή����K�v�ȏ��Ȃł���B
10/13(��)�����@��Ȓ��ʕa�@�O�� �@���҉Ƒ��ʒk
2:00�N���A��Ê֘A�{�ǂ݁A5:30�R�S�~�o���B7:35Taxi�w�A8:11���܂��A���Taxi�B9:10��Ȓ��ʕa�@�O���B15:30 ���艮�Ȃ��ŋA�@�B�����A�V���` �F�b�N�ł����B17:00 -18:00���҉Ƒ��ʒk�B�Ђ�̂�o�R19:15�A��E�[�H�A20:30�A�Q�B�����v��6678���B
��ځ@���N�̏H�c�͏�������(2)�@�䂪�Ƃ̃_���A�Ɍ��錃���̉e��
�@���͂�����Ƃ������|�Ɣ��̖�؍������Ă��邪�A���̂��Ƃ�ʂ��ċC�̎��R�ƑΘb����B�A���������Ȃ��Ƃ�\�����Ă����B
�@�䂪�Ƃ̃_���A�͔|�͎��̗̑͌��ނɉ����ď��X�ɏk�������邪�A���N�͒�̓쑤�ɖʂ�����p�ɂ����A�����B���̕����͓�����������ʂ����ǂ��A�_���A�ɂƂ��Đ�������������炵���B���N�����ȉԂ�����B
�@���N���{�A�����Ă���2�������7������A�w��͏�������Ԃ��牠���ɊJ�Ԃ��A���N�͏\�Ɋy���߂�\���������B
(7�����{���̐����ƊJ�Ԃ̗l�q�@�A���Ă���2����������Ԃ̔w��͏�����)
�@7�����{�������������̂ł��邪8���ɂȂ��Ă���������͋���ɂȂ�A�C���͖ҏ��ł͕s�\���Ō����ƌ����ׂ���Ԃɂ܂ŏ㏸�����B
�@�_���A�͗��������Ő������邩��8���̋���ȓ������̌��ł݂͂�݂錳�C�������āA7���ɂ��ꂾ���炢���̂�8���͂قƂ�NJJ�Ԃ��Ȃ������B����ǂ��납�A�J�ԓr���܂Ő��������Q�����̂܂܊J�Ԃ��邱�ƂȂ����F�ɕϐF���ė����Ă������B
�@
�@�_���A�͔|�̃v���ł������ȓ������������Ռ��l�b�g�Ȃǂ̗p�ӂ͂��邾�낤���Y�u�̑f�l�̎��ɂ͂��̂悤�ȏ����͂Ȃ��B
�@���ɂł��邱�Ƃ͒��̐����݂̂ł���A8���A9������1�������������A���͂��ꂾ���͏\���ɂ��������ł���B�������Ȃ���A�����̌��A�_���A�̎}�t�݂͂�݂�ނݎn�߁A�ꕔ�͌͂�n�߂Ă����B
(8�����{���̃_���A�̗l�q�@�t�͏k�ݏオ�茳�C���Ȃ��A�}���͂�A�قƂ�NJJ�Ԃ��Ă��Ȃ�)
�@���ۂɃ_���A�����C�ɂȂ�n�߂��̂�9�����{���납��ł���B���̎����͎��ǂ��ɂƂ��Ă�8���ɑ��������̍Œ��ł��������A�_���A�����͈�C�Ɍ��C�����߂��w���L�сA�t���L���J���\���ɗz�𗁂т��B
�@���̓_���A�̉Ԑ��̕ω����猃���̏I����\���ł����B
(9�����{���̃_���A�̗l�q�@�悭�����ɑς��Ă��ꂽ���̂��Ǝv��)
(�̏����̃_���A�̊J�Ԃ̗l�q�@������!!!)
�@���͏o�ΑO�Ƀ_���A�����̗l�q�����邪�A�ƂĂ��������B
�@���N�͂��ꂪ����ł���B
10/12(��) ���� �@��
1:30�N���B�����`�F�b�N�B�����̔@���B�f���ɂ͎���Ȃ������l�q�B���������̓����B
8:50�Ɠ��ɓ��惊�n�ɁA�����B10:00���@���ґΉ��B�{�ǂݒ��S�B15:00���@���ґΉ��B18:00�ˑR�̍��M���NJ��҂���B19:30�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B�����v�Čv���J�n�A�{����2933���B��N������ƕ����ɁA�����j���O�V���c���p�B���N�͂܂������B
10/11(��) �����@�H�c�s�k���n��f���\��ƂȂ�
1:30�N���B�Ǐ��A�^���f�[�^�����Ə����ȂǁB�O�d���͕s�v�ŁA8:30���`��Ȏ�f�Έ䂳��A���n�ցB�I�[�f�B�I�A���v�ݒu�BLo-D�X�s�[�J�[�ڑ��A�����ɂ��s���B���ʏグ���Ȃ�����܂��������B�����ǂ݂ȂǁB�����ȂǁB11:30�a���Ή��A�V���@����B12:30-13:15�V���@���҉Ƒ��ʒk�B14:30�a���J���t�@�A���@�Ή��B�����f�[�^�`�F�b�N�B19:10�A��A�[�H�A20:15�A�Q�B�H�c�s�k���n��f���\��ƂȂ�����ۂɂ͒f���Ȃ��B
�J���[���C�X(3) ���Ё@�d�� �����@�J���[���C�X�@�V������
10/10(��) �����~�J�̂������@ ���ʕa�@�O��
1:30�N���A�f�[�^�����Ȃǂ����̂��Ƃ��B�Ǐ����S�A5:00�R�S�~�W�Ϗ��A6:40�o�X���n�a�@�ցA7:00-8:30���@���ґΉ��A8:45-12:30���ʕa�@�O���A�敾�B12:45���n�a�@�B�����A�V���`�F�G�b�N�A���́B�V���@����B19:00�A��[�H�A20:30�A�Q�B
��ځ@���N�̏H�c�͏�������(1)�@�H�̑��z�͂�ח��Ƃ��@�������[�͔�����
�@10���ɂȂ��Ă���}���ɗz���Z���Ȃ����悤�ȋC������B
�@���͒��͎����6:20�ɏo��B���̏o��5:50�Ȃ̂ŗ��ɖ��邢���A��̗l�q�ɂ���Ă͂�┖�Â��B�[��19:00�߂��ɒʏ�͉Ɠ��̎Ԃɓ��悵�ċA��̂����A���̓s��������Ȃ����ɂ�18:30�H�c�w���̃o�X�𗘗p����B���̊�20���قǓk���ɂȂ邪�A�H�̎��͂����^���Âň��S�̂��߂ɑ������Ƃ炷�����d�����K�v�ł���B
�@����ɔ������[�̋C���͋}���Ɋ����Ȃ����B
�@��2�T�ԂقǑO�܂ł͎c���Ƃ����ɂ͂ӂ��킵���Ȃ��قǂ̖ҏ��������Ă������A���̌�́u�H�̑��z�́A��ׂ𗎂Ƃ����̂悤�ɑ�������ł��܂��v�ƌ����\�����̂܂܂ł���B�[��ꂪ����������B�����āA�����Ƃ����ԂɈÈł�����B
�@��͈�邲�ƂɐL�тĂ����B�G��Ƃ��Ắu�钷�v�͏H���A�~�ɂ́u���Z�v��p����B
�@�H�̗[���A���͐��ꂽ���̗[�i���D�����B�����ːF�ɐ��܂鐼���̋�̔������ɂ͕\�����ׂ����t��������Ȃ����Ƃ�����B�������A���������قȂ��i���J��Ԃ���Ă����B�������A���̊��Ԃ͒����͑����Ȃ��B���̂����ɏ��~�̐Â����Ɍ������Ă����B
�@�u��ח��Ƃ��v�͈�˂̐����݂Ɂu��ׁv���g���Ă������Ƃ�m�鎄�ǂ��̐���ɂƂ��ẮA�����̂��鎞�Ԋ��o�̕\���ł���B
�@���āA���N�̏H�c�͏��������B
�e���ɉe�����y�ڂ����������̖��c�������͎c���Ă��Ȃ��B�u�A���߂���ΔM����Y���E�E�E�v�A�̌����`��������B�ϖシ��قǂ̋�ɁA��J���A���ꂪ�߂��Ă��܂����̒ɂ݂�ꂵ�݂���������Y��Ă��܂��A�Ƃ������Ƃ����A���N�̍����Ŕ_�앨�Ȃǂɔ�Q�������X�̎v���͂����ȒP�ɖ�������̂ł͖����B
�@�H�c�n���C�ۑ䂪����H�c�s�ł�1882�N����̃f�[�^�����J����Ă���B
�@���̊Ԃ�140�N�]��̌����ϋC�����r�����Ƃ���A�u���N8���̋C���v�͂���܂ōō��������u1999�N8���v�Ɓu1985�N8���v��27.3�x��2.7�x���������B
�@2023�N8���͊ϑ��j140�N�ōł�����1�����������A�Ƃ������ƁB
�@�����̍ō��C���̏㏸�����łȂ��A�Œ�C�������������B�Œ�C����25�x�ȏ�ŐQ�ꂵ���M�і��25���Ԃɏ��A�ߋ��Œ����X�V�����B
�@�H�c�n���C�ۑ�̒S���҂�8���̖ҏ��ɂ���
---------------------------------------------------------------------
�@�t�B���s�����ӂ̊C�����������Ȃ�A�ω_�Ȃǂ̔������Η����������������A�����m���C�������܂���
�A�ΐ����̎֍s�ɂ��쓌����̒g������C�̗���
�B�R�z�����Ċ����������������ރt�F�[�����ہ\�Ƃ������v���������I�ɏd�Ȃ�B�u1����ʂ��Ēg������C�����荞�ޏ�Ԃ��A�ق�1�J���ɂ킽�葱�����v�Ɛ������Ă���B
-------------------------------------------------------------
�@ �܂��A�C�ے��ُ̈�C�ە��͌�����́A�n�����g����k���{�t�߂̊C�����̍��������Ă̖ҏ��ɉe�������Ƃ̌����������Ă���B
�@�ʂ����Ă��̌��ۂ͍��N�����̓��قȂ��̂Ȃ̂��낤���H�H
�@���͂����͎v���Ȃ��B
10/9(��) �X�|�[�c�̓��@����
2:30�N���B�������Ɠ��l�A���ޏ��ЁA��w�_���Ȃǃ`�F�b�N�B9:00-11:00����12��ځA���k���B���̊ԗ�2�P���Ƃ̘b�������A�����܂ߎO�҂ŋ��E���̍��Ӑ����B����̈ʒu�ŁB���E�ɂ̓u���b�N�H������A��p�͐ܔ��B�Ɠ��͉�f�ɁB�ߌ�͔����㏑�ւʼn߂����B�Еt���A18:15�Ɠ��A��A19:00�[�H�B20:15�A�Q�B�a�@�o�Ȃ��B
�����v �@�₵���ĕ����v�v����������
�@�����v�u�����̈ɔ\���h�v�͎����������Ǝv����C�ݐ��ɂ����ē��{���������Q�[���@�B
�@���{�̊C�ݐ��̑�������19.044.18Km�ƃZ�b�g����Ă��邩��A�������̂�1��1������7-8�N������B
�@�������o�����đ����m���C�ݐ���k��A�k�C���A���{�C����쉺�A��B�A�l�����o�ĉ�����܂ޓ��{�����B�������̂�2020�N4��14����7�N���������B
�@���̎��_�ł̃f�[�^�B
-------------------------------------------------
���v���ԁF2.565���i7.03�N�j
�������F��2.411���� (����9.399��/��)
���s�����F��19.292Km(����7.52Km/��)
-----------------------------------------------
�@�����A�Œ�1��10.000����ڕW�ɂ��Ă������A���ʓI��9.480���ƖڕW�ɂ͒B���Ȃ������B
�@���{����B����2���ڂɎ��|�������B
�@2���ڂɓ����Ė�3�N�A2023�N4��23������C���x�R�ɓ������B
�@2023�N5��5���A�S�s�S�ǁA�p�����킪�ł��Ȃ��Ȃ����B2023�N7���Ōv������߂����A����10�N�ԓڍ����Ȃ��������Ƃɖ������Ă���B
�@�S�s�S�ǂ��Ă���N�o���̒��������Ȃ��B
�@10�N�߂��ςݏd�˂Ă������т��̂Ă�ܑ͖̖̂����ƍl���A�{������ēx1���̕����v�����J�n�����B
�@�{���̎��_�ł̃f�[�^
-------------------------------------------------
�������F��3.306���� �A��26.453Km
���v���ԁF3.842���i10.05�N�j
-----------------------------------------------
�@���́u�p���͗͂Ȃ�v�Ƃ������t���D���ł���B
�@����10�N�ԁA�ߑO2:00�߂��ɖ����������m�F���Ď��̌��N�x�A�������̃o�����[�^�[�Ƃ��Ė𗧂ĂĂ����B
�@���̏K�����̂ĂĂ���Ȃ₵���B
�@���ǁA�{������1��������̕����̃`�F�b�N���ĊJ�����B
�@���{2���ڂ����A���邩�A��������܂Ŏ����͕s���ł��邪�E�E�E�B
10/8(��) ����
2:30�N���B�����`�F�b�N���B�������̂��Ƃ��B8:30���d������ƁA���̃r�j�[���A�}���`�������A�G�������A������܋l�߁B10:30�Ɠ��A��A11:00 -12:00Nrs���쎁�̑��V�ɏo�ȁB����̖\���J�œ|�ꂽ�_���A�~�o�B12:00NHK�j���[�X�A�̂ǎ����y���ށB�V���X�N���b�v�A�����B15:00����ƌ�Еt���B�Ǐ��A���w���S�B19:00�A��A�[�H�A20:00�A�Q�B�a�@�o�Ȃ��B
���e���F(2) ���̏ꍇ�A���͏�Q���F�m�@�\�ቺ���֗^
�@���͐l�̊���o����̂����ł���B�悭�Ɛl����w�E�����B�������A��ȊO�̓����ɂ���Đl������ʂ��邱�Ƃ͂ł���B
�@���e���F�Ƃ́A�l�̖��O��������Ă��A������v�������Ȃ��A�C���[�W�ł��Ȃ���ԁA�ʐ^���݂Ă��A���ږ{�l�ɉ���Ă����ꂪ�N�ł��邩��ʂł��Ȃ���Ԃ��w���B�]��Q�ɂ�鎸��ǂ̈�Ƃ���A1947�N�h�C�c�̐_�o�w�҂ɂ���Ď����Ƃ��Ă̊T�O���m�������B
�@���e���F�͍��x�̔F�m�ǂł�������B
�@�F�m�ǂ��i�s����Ύ����̉Ƒ����F���ł��Ȃ���ԂɊׂ邱�Ƃ͍���҈�ÂɌg����Ă���ƕp�ɂɂ݂��錻�ۂł���B
�@���̏ꍇ�͗c�������炾����F�m�ǂɔ��������̂ł͂Ȃ��A�܂��A���̒��x�͌y���B�������A���̋L���ɂ��鑽���̕��X�̊�͂̂���ڂ��œ����I�Ȗڕ@�����Ă��Ȃ��B�ʐ^���݂Ă���Ǝv���o�����������B
�@�Ƃ��낪�A�s�v�c�Ȃ��Ƃɂ���Ȏ��ł���W�⏑�Ђɕ`���ꂽ��͖��ĂɋL�����Ă���B�������̐l���̕��e�̋L���Ə��Ђ̉摜�̋L�����قȂ��Ă���̂����m��Ȃ��B
�@���́A���Ė��h�����������@������������A���O�����̖��h�͂قƂ�ǖ������Ă��Ȃ������B
�@���͎��͂��ɓx�ɒቺ���Ă���B����I�ɂ̓��K�l��p�����ɂڂ₯������̐��E���y����ł���B
�@�d����ł�������ł����͎��͏�Q��������ɂ��Ă��Ȃ��E�E�E���A�K�i��~���Ȃǂł́A���ɖ铹�́A�悭�������댯��������B�o�X�̍s��\�����������ɏ��Ȃ�������A�s������ԈႦ�ď�������Ƃ��������B
�@���͋L���͂��ɒ[�ɗ����Ă���B����I�ɂ͂��ꂪ�O�ʂɏo�Ȃ��悤�ɘb���I�ѓW�J������B�����Ƃ��Ă͍j�n��I�����ł���B���̃X�}�t�H��p�\�R���̓������炯�B�L���łȂ��L�^���ăJ�o�[���Ă���B
�@���Ė^���K�l�X�ŏ����X�^�b�t�̑��e�̔F���͂ƋL���͂ɋ����A���S�������Ƃ��������B
�@
�@���X���ăJ�E���^�[�ɍ������r�[�Ɂu���c���܁A��������Ⴂ�܂��E�E�v�Ɛ����|�������B���̃��K�l�X�ł�3�N�O�Ɋዾ��V�����������̌��x���K��Ă��Ȃ��B���̓l�[���J�[�h�Ȃǒ����Ă��Ȃ��̂ɁE�E�E�B
�@�����Y���j�ꂽ�����b������A�X�Ɂu���̃��K�l�͉^�]�Ƌ��X�V�̂��߂ł����ˁE�E�v�Ƃ�����ꂽ�B
�@���͂��̓X�ōw���������͊o���Ă������A���̊Ԃ̂��Ƃ�Ȃǂ͑S���Y��Ă����B���̎��S�����Ă��ꂽ�X�^�b�t�ł��낤���A���̊���L���ɂȂ��A���̂����͋L�����ނƑ��e���F�����F���Ă��鎄�ɂƂ��ăV���b�N�ł������B
�@���́A���̂Ƃ��͌��ς��肾���̂��藧��������̂����A�����ɏC����\���o���B�X�^�b�t�̑��e�̋L���͂ɂقƂقƊ��S��������ł���B
10/7(�y) ��ԍ~�J�A�܂�~�J�A�ߌ�����@�Ɠ��]���^���É�
2:20�N���B�f�[�^���͐����B�����ߑO�͍~�J�ō��w���S�A�����f�[�^�����B10:00�s���Y��ЃX�^�b�t�̖K�₠��B�_���A���{�܂�Ă����B�����C���v���B13:28�o�X�a�@�A���@���ґΉ���A���҂͗��������Ă���B�����A�V���f�[�^���A19:00���艮�o�R�A�Ï�10���قǍw���B19:30�A��A�[�H�A�L���`��A20:30�A�Q�B
���e���F(1) �V�����E��ō����Ă���
�@���͐l�̊���o����̂����ł���B
�@�q���̎�����Ȃ̂ŁA����Ƃ���ΐ�V�����e���F(?)�Ǝv���邪�ڍׂ͌������Ă��Ȃ��B��V�I���e���F�ǂ���m����2�����x�Ɛ��肳��Ă���A��ʓI�ɑz��������肩�Ȃ葽���A�炵���B
�@�l�Ԃ̌̎��ʂ͊�̔F�������łȂ��A���A�̊i�A�U�镑���A���߁A�ȂǗl�X�ȏ��𑍍����čs���Ă���A��̔F���ɏ�Q�������Ă����̋@�\�ő㏞���A���퐶���Ɏx����������Ȃ����߁A���e���F�����o���Ă���l�͏��Ȃ��A�ƍl������B
�@�������A���͂͂����莩�o���A�ƂĂ��s�ւ��Ă���B
�@�X�ŁA���邢�͕a�@���Ŋ��҂���ɐ����|����ꖼ����邱�Ƃ͏��Ȃ��Ȃ����A�ӈ��z�悭�Ԏ����b������킹�Ă��A���ۂɒN�ł��������Ō�܂Ŏv���o���Ȃ����Ƃ��p��ɂ���B
�@��������ƍ����Ă���̂́A�V�N�x�ɂȂ��ĐV���ȐE������A�X�^�b�t���X�̊炪�o�����Ȃ����ƁB
�@���ɎႢ�����Ō�t�̊炪�o�����Ȃ��B�������N�o������30�l�]�̃X�^�b�t�̔����قǂ����o���Ă��Ȃ��B
�@�F������A�����ăX������(?)���Ă���A�����悤�Ȕw�i�D�ŁA�R���i��̃}�X�N�z�����猩����ڂ̓A�C���C�N��������ŁA���ɂ݂͂�ȓ����悤�Ȕ��l�ɂ݂���B
�@����Ɏ����S�����Ă���a���ɂ͉�앟���m��P���m���p�ɂɏo���肵�Ă��邩�炨��グ��Ԃł���B
�@�߂��ɂ���X�^�b�t�͖��D������������A���͋ɓx�Ɏ��͂�����20cm�܂ŋ߂Â��Ȃ���悭�����Ȃ��B���D�̈ʒu�͔����ȏꏊ�ɂ���B�W���W�����Ă���ƃZ�N�n���s�ׂƌ������ăG���W�W�C�Ǝv��ꂻ���B�{���͂��̍ŃG���W�W�C�ƌĂ�邱�Ƃ͖��_���Ǝv�����A�E��ł͎x�Ⴊ�o��B
�@���͐E������̊�ʐ^��iPad�ɓ���ĐE��Ŏ��X���߂Ă��邪�A����ł��o�����Ȃ��B�p��������ꍇ�ɂ͖��O���Ăт����̂ł��邪���ꂪ�ł���B�����Ƀ[�b�P����w�ԍ����~�������炢�ł���B
�@����āA�悭��l�ł��ATPO�ɂ���āA���ς╞����������肷��ƁA�܂��A�}�X�N�Ȃ��ł͔��f�ɖ����B�@�O�ł��܂��܉�X�^�b�t�͂悭�킩���B
�@�������Ƃ͊��҂ł��N����B
�@�d�����A���Ҏ��Ⴆ�͑�ςȂ��ƂɂȂ�B���O����������m�F���A�_�u���`�F�b�N�����āA�ԈႦ�Ȃ��悤�C��t���Ă���B
�@���܂ł̂Ƃ��늳�ҊԈႢ�͌o�����Ă��Ȃ��B
10/6(��) �������~�J�@ ��Ȓ��ʕa�@ �@���N�N���j�b�N�`�F�b�N�@�Ɠ��]���^���É�
1:30�N���A�����̔@���B5:00�R�S�~�������ݔp�������̂݁A�~�J�Ŕp�������B7:35Taxi�w�����ɁA�~�J�ŏa�A8:11���܂��ɏ��x��A�X�^�[�o�b�N�X�ɂĎ��ԑ҂��A9:12�ɂđ�ȁB����Taxi�A10:10�O���A���n���@�̊��ҁA�q�f�Ő��`�厡��̔��f�ŋ~�}�O���ցB13:30-14:30Taxi���N�N���j�b�N�Ƀf�[�^����A14:45�A�@�B�~�}�������ꂽ���ҋA�@�B�߂܂��ɂ��q�f�ƁB15:10�a���Ή��A�V�������B18:40�`��ʁA�Ђ�̂�o�R�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B
�E�G���u���[��(3) �䂪�ƂɂƂ��Ă�Apple Watch(2)�@���ǁA�Ɠ��Ɉ������w����
�@�Ɠ��͓������B
�@�����͒����Ԃɋy�R����܂̐_�o��Q�Ɖ���낤�B���x���⒮��̎g�p�����߂����p���Ă��Ȃ��B��b�͑��肪�傫�Ȑ����Ƃ���قǕs�ւł͂Ȃ������ł��邪����͂�����ƃX�g���X���낤�B
�@��ԍ���̂͌g�тɂ������Ă����d�b�ɋC�Â��Ȃ����Ƃł���B
�@��c���ȂǂŃT�C�����g���[�h�{�U���ɐ�ւ����ꍇ����Ԗ��ł���B�����g�т͐U�����킩��悤�ɐg�̂ɐG�ꂳ���Ă����悤�i�����Ă��A�Ɠ��͓���g�т��o�b�O�ɓ���Ă��邱�Ƃ������B������d�b�ɋC���t���Ȃ����Ƃ��p�ɂɂ���B���ɕa������̓d�b�A���̏ꍇ�͏d�v�ŁA����Ɏ��ɂ������Ă��邱�Ƃ��܂łł͂Ȃ������B
�@Apple Watch�w�������̍ہAiPhone�ɒ��M������ꍇApple Watch���U������@�\�����邱�Ƃ�m���Ď��ȏ�ɉƓ��̕������K�v���A�ƍl�����B
�@�������Ȃ���A���Ɠ�������ōw���͒��߂���Ȃ������B�Ɠ���iPhone 7plus�͎���iPhone8���^���Â�����Apple Watch�Ɠ����ł��Ȃ�����ł���B
�@�Ɠ���iPhone 7plus�̋@�\�ɉ���s���������Ă��Ȃ�����A���̂��߂�����15-20���~�̏o��͕s�v�Ƃ̂��ƁB�����[�����A���g�����B
�@���ǁA�䂪�Ƃł͐V�^��Apple Watch�͍w�����Ȃ����ƂɂȂ����B
�@���̉ߒ��ŁAApple Watch�ɗގ��̋@�\��������Smart Watch�A�����͒������Ȃ̂����A���������ɂȂ��Ă������ƂɋC�������B
�@�����܂Ō��������̂�����A�_�����ƂƎ����Ɉ����̈���w�����Ă݂��B
�@����������2900�~�B�X�Ƀ^�C���Z�[������1000�~�����Ŏ���1900�~�œ���ł����B
�@����ɂ́A���@���iPhone�Ƃ������ł���Ƃ������_���������BApple Watch���͑S�̂ɋ@�\�͊ȑf����iPhone�̒��M���ɂ͐U�����A�N����d�b�����Ă���̂���\������@�\�͂��Ă���B
(����w������Smart Watch�̊�{��ʁBApple Watch���͓��R�ȑf�ł��邪�A�������A�̉��A�����Ȃǂ͏�ɕ\�������)
(�d�b���M���A���v���̂��Z���ԐU�����A����̖��O���\�������)
�@���_�Ƃ��āA���M���U���Œm�点��@�\�͉Ɠ��ɂƂ��ėL�p�ł������B�Ɠ��ɂƂ��Ă͍��̂��Ƃ낱��ŏ\���ł���B
�@���̋@�\�͐M�ߐ��͊m�F�ł��Ă��Ȃ����A�S�����A�̉��A�����_�f�Z�x�A���b�Z�[�W�ʒm�A�����Ȃǂ̋L�^���\�ƂȂ��Ă���B
�@�E�G���u���[���͓d�q�@��̒��ŁA���p�[�\�i���ȏ������W�����͂��ĊҌ�����ȂǁA���V�������z�̋@��ł���B
�@���コ��ɔ��W���Ă������Ƃ����҂������B
�E�G���u���[��(3) �䂪�ƂɂƂ��Ă�Apple Watch(2)�@���ǁA�Ɠ��Ɉ������w����
�@�Ɠ��͓������B
�@�����͒����Ԃɋy�R����܂̐_�o��Q�Ɖ���낤�B���x���⒮��̎g�p�����߂����p���Ă��Ȃ��B��b�͑��肪�傫�Ȑ����Ƃ���قǕs�ւł͂Ȃ������ł��邪����͂�����ƃX�g���X���낤�B
�@��ԍ���̂͌g�тɂ������Ă����d�b�ɋC�Â��Ȃ����Ƃł���B
�@��c���ȂǂŃT�C�����g���[�h�{�U���ɐ�ւ����ꍇ����Ԗ��ł���B�����g�т͐U�����킩��悤�ɐg�̂ɐG�ꂳ���Ă����悤�i�����Ă��A�Ɠ��͓���g�т��o�b�O�ɓ���Ă��邱�Ƃ������B������d�b�ɋC���t���Ȃ����Ƃ��p�ɂɂ���B���ɕa������̓d�b�A���̏ꍇ�͏d�v�ŁA����Ɏ��ɂ������Ă��邱�Ƃ��܂łł͂Ȃ������B
�@Apple Watch�w�������̍ہAiPhone�ɒ��M������ꍇApple Watch���U������@�\�����邱�Ƃ�m���Ď��ȏ�ɉƓ��̕������K�v���A�ƍl�����B
�@�������Ȃ���A���Ɠ�������ōw���͒��߂���Ȃ������B�Ɠ���iPhone 7plus�͎���iPhone8���^���Â�����Apple Watch�Ɠ����ł��Ȃ�����ł���B
�@�Ɠ���iPhone 7plus�̋@�\�ɉ���s���������Ă��Ȃ�����A���̂��߂�����15-20���~�̏o��͕s�v�Ƃ̂��ƁB�����[�����A���g�����B
�@���ǁA�䂪�Ƃł͐V�^��Apple Watch�͍w�����Ȃ����ƂɂȂ����B
�@���̉ߒ��ŁAApple Watch�ɗގ��̋@�\��������Smart Watch�A�����͒������Ȃ̂����A���������ɂȂ��Ă������ƂɋC�������B
�@�����܂Ō��������̂�����A�_�����ƂƎ����Ɉ����̈���w�����Ă݂��B
�@����������2900�~�B�X�Ƀ^�C���Z�[������1000�~�����Ŏ���1900�~�œ���ł����B
�@����ɂ́A���@���iPhone�Ƃ������ł���Ƃ������_���������BApple Watch���͑S�̂ɋ@�\�͊ȑf����iPhone�̒��M���ɂ͐U�����A�N����d�b�����Ă���̂���\������@�\�͂��Ă���B
(����w������Smart Watch�̊�{��ʁBApple Watch���͓��R�ȑf�ł��邪�A�������A�̉��A�����Ȃǂ͏�ɕ\�������)
(�d�b���M���A���v���̂��Z���ԐU�����A����̖��O���\�������)
�@���_�Ƃ��āA���M���U���Œm�点��@�\�͉Ɠ��ɂƂ��ėL�p�ł������B�Ɠ��ɂƂ��Ă͍��̂��Ƃ낱��ŏ\���ł���B
�@���̋@�\�͐M�ߐ��͊m�F�ł��Ă��Ȃ����A�S�����A�̉��A�����_�f�Z�x�A���b�Z�[�W�ʒm�A�����Ȃǂ̋L�^���\�ƂȂ��Ă���B
�@�E�G���u���[���͓d�q�@��̒��ŁA���p�[�\�i���ȏ������W�����͂��ĊҌ�����ȂǁA���V�������z�̋@��ł���B
�@���コ��ɔ��W���Ă������Ƃ����҂������B
10/ 5(��) ��闋�A�������~�J�@�Ɠ����É�
4:00�N���A�̒��͂��Ȃ���P�B������V���蔲���B����̒�����ƕ��ɒ��ւ��B6:40�o�X�ȊO�ɂ͏�肽���Ȃ���8:00�`��ʈ˗��A2400�~�B8:15-9:00�a���Ή��A�̂������ŋx�{�A���w����C���������ɁB11:50�퍂��ك��X�g�����ŃJ���[�B15:00���@���ґΉ��B�Ƒ��ʒk�������B�V���X�N���쐬���́B���N�N���j�b�N�͖����ɐL�����B�̒��͉��P�X���A18:20�o�X�A��E�[�H�A�܂��J���[�ł������B20:00�A�Q�B
�E�G���u���[��(2) �䂪�ƂɂƂ��Ă�Apple Watch(1)�@���ǁA���͍w�����Ȃ�����
�@Apple Watch�̂�2014�N�ɔ����ɂȂ������A���̐�i���͂��ǂ낭����ł���B���͓����͕ςȋ@�\�������ґ�Ȏ��v(?)�Ƃ��������Ă��Ȃ��ċ������킩�Ȃ������B
�@�{�N5��5���ɖ����S�s�S�̋}��������ԂɂȂ������Ƃł�����ƍl����ς����B8�����_�Ő^�ʖڂ�Apple Watch�̍w�����l����.
�@�������A9���ɐV���i�����\�����\��ŏo�ג�~��Ԃɂ���w���ł��Ȃ������B
�@
�@�����������������@�\�Ƃ��Ă͈ȉ��̔@���B
-----------------------------------------------------------
������̕��s�ȂNJ������̊Ǘ��[�[�[���͏z��̎厡�ォ��^����2.7Mets�ȓ��ł̐������w������Ă���B
���S�d�}�̋L�^�ȂǐS���̏�Ԃ�m��[�[�[���͖����S�[�ד��ł���B�������͏����E�p���Ƃ��Ɋ댯�ȏ�Ԃ������B���̔��f�ɗL�p�B
�������_�f�Z�x�ȂǐS�x�̏�Ԃ�m��[�[�[�S�s�S�}�������̑����m�F�̂��ߗL�p�B
�����N��ً̋}SOS��119�Ԃ�Ƒ��A���̑��K�v�ȂƂ���ɘA������@�\�B
-----------------------------------------------------------
�@���̋@�\�̑�����iPhone�ɂ�������Ă��邩�炠�܂�K�v�łȂ��B
�@���┭������10�N�AApple Watch�͉��ǂ��d�ˉ��l������p�i�ɂȂ����B
�@����A�X���[�g�����A�z��n�ɖ��̂���l�����̌��N�Ǘ�����K�v�ȃA�C�e���ƂȂ��Ă���B
�@9���̐V���i�����\�ƂƂ��ɍēx�V�^��Apple Watch�͍w�����l�������A���̎��_�ŒP���ȗ��R�ōw�����Ă����ʂł��邱�Ƃ��킩�����B
�@Apple Watch��iPhone�Ƌ@�\�������ėp���邪�A���̓����̑���Ƃ��Ď���iPhone8�͌É߂��Ċ��ɑΏۂ���O��Ă����B
�@�m����iPhone8��2018�N6���ɍw���������̂ł�����5�N�g���Ă���B����iPhone8�͒ʐM���u�t���̉��y�v���[���[�Ƃ��Ă̈ʒu�t���ŁA���܂��ɉ���s�ւ������Ă��Ȃ��BApple Watch�������w������ƂȂ��iPhone���̂��X�V���Ȃ���Ȃ�Ȃ��BApple Watch�ƍ��킹��Ɩ�16-20���~�ƂȂ�B������~�߂��B
�@���N�Ǘ��̂��߂ɗL�p�Ƃ����Ȃ���Ō�̓P�`��̂��H
�@����A�����ł͂Ȃ��B�����g���S���Ɋւ��Ă̒m���ƗD�G�ȃZ���T�[������Ă���Apple Watch�͂��̊m�F���x������K�{�Ȃ��̂ł͂Ȃ�����ł���B
10/4(��) ����A�I���̒��s�� �a���J���t�@�����X
1:20�N���A���j�A�����B9:00���d������B�ƂĂ���ꂽ�B�M������A�S�g���ӊ����x�A11:00�o�X���n�ɁB�����B14:30-15:30�a���J���t�@�����X�B�����A�����A�����̓��[�`���d���S���ł��������A��B19:30�A��A�[�H�B20:00�A�Q�B
�E�G���u���[��(1) Apple watch�̎���
�@���̓p�\�R���Ȃǂ̑啔���̓A�b�v�����i��p���Ă���B
�@�����A�R���s���[�^�̐��E�ŃV�F�A��20%���x�ƕ��y�͍��ЂƂB
�@���̐E��ł��d�q�J���e��Windows����{�ɂȂ��Ă��邩�瑀��ɖ����l�ꔪ�ꂵ�Ă���B
�@�A�b�v�����i�̐�i���͂��ǂ낭����ŁA���i��ʂ��Đ��E��ς����A�ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B
�@�p�\�R������ł��@�\�I�ɂ͐�[�𑖂��Ă���B�S����ɂ����鐻�i�̃f�U�C�����G��ŁA�X�}�[�g�t�H���ł�iPhone�ŏ�ɐ�[�𑖂�A�^�u���b�g����ł�iPad�V���[�Y�m���A�I�[�f�B�I�̐��E�ł����z�̐�i������\�j�[�̃E�I�[�N�}���V���[�Y����������쒀���Ă��܂����B
�@2014�N��Apple Watch�Ƃ��Ď��v�^�̒[�������\����Ęb���������Ă���B
�@���͂��ɃA�b�v�������v�ƊE�i�o���Ă��������b�������A�P�Ȃ鎞�v�Ƃ͑S���قȂ�A���v�^�̃R���s���[�^�[�[���ł������B
�@���̓R���s���[�^�[�[���Ƃ���iPhone�ŏ\���������Ă����̂ł��܂苻�����킩�Ȃ��������A���N9���V���i�����\����A���̋@�\����C�Ɋg�����������o���A�S���ɂ���������Ă��邩��w�������������B
�@�����A���z�ł���BApple Watch SE��34,800�~����ASeries 9��59,800�~����AUltra��128,800�~����ŁA���ɂ͌��N��Ԃ̃`�F�b�N�̂��߂ɂ�Series 9�������Ǝv�����A�]�����������Ȃ����ɂ͍��z�߂��ĔY�܂����Ƃ���ł���B
Apple Watch�̋@�\�������Ǝ����ƈȉ��̔@��(SE�ɂ͌�����@�\��)�B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�����v�@�\��ʁA���ێ��v�A�^�C�}�[�A�ڊo�܂��A�X�g�b�v�E�I�b�`�Ȃ�
������̕��s�ȂNJ������̊Ǘ�
���S�d�}�̋L�^�ȂǐS���̌��N��Ԃ�m��
�������_�f�Z�x�̑���
�������̎��̃��j�^�����O
���}�C���h�t���l�X�Ő��_��Ԃ��`�F�b�N����
�����o�����̋L�^�Ɨ\��
�����N��ً̋}SOS��K�v�ȂƂ���ɘA������
���]�|����/�Փˎ��̌��o���K�v�ȂƂ���ɘA������
��������Ǘ�����
���������璮�o��ی삷��
��Navi�œ��ē����Ă��炤
���d�b��[���̒��M��U���Œm�点��
���d�b��[���ŘA�������
��Apple Pay�Ŕ�����������
����ʋ@�ւ𗘗p����
�����y��W�I��
������K��������
�������d���ɂ���
��iPhone��Mac��T��
��iPhone�̃J���������u���삷��
���Ɠd�𑀍삷��
���f�����^������
���ȂǂȂ�
�@���┭������10�N�A�r���v�^�E�G���u���[���͉��l���錻���̎��p�i�ɂȂ����B
�@���⌒�N�Ǘ�����K�v�ȃA�C�e���ƂȂ��Ă���B
10/3(��) �����@ ���ʕa�@�O�� �@�K���̉�
1:45�N���A�f�[�^�����Ȃǂ����̃p�^�[���B5:30�R�S�~�W�Ϗ��ɁA6:40�o�X�a�@�B�_�c���������4�{�B7:00-8:30���@���ґΉ��A8:45-12:45���ʕa�@�O�B�敾�����B13:00���͕a�@�A12:30�����B15:00�a���Ή��A�K���̉�͎��O�B19:30�A��A�[�H�A21:00�A�Q�B
�u�J���[���C�X�v(3) ���Ё@�d�� �����@�J���[���C�X�@�V������
�@��l���́u�Ђ낵�v�͏��w�Z�Z�N���B
�@�����w���̍���`������i��ǂނƁA78�̖ꂶ�������̍��̐����Ƀ^�C���X���b�v����B
�@���ƒ��̗l�q���A���ی�̋�C���A�搶��F�����̐����A��݂������Ă���B�{����9�҂̒Z�҂����^�B�V�l�ɂȂ��Ă������ĖY��邱�Ƃ͂Ȃ��A�q�ǂ��̐S�Ƃ��Ƃ��v���o�����Ă��ꂽ�B�����̊����c���Ă����Ƃ̊��ƕM�͂ɂ͂قƂقƊS����B
�@���̏����o���� �u�ڂ��͈����Ȃ��v�B ����͕���̎�l���ł���u�Ђ낵�v�̐S���n�܂�B
�@���҂̏d��������1963�i���a38�j�N�A���R������B�o�ŎЋΖ����o�Ď��M�����ɓ���B2001�N�w�r�^�~��F�x�Œ��؏܂���܁B����̉Ƒ���`�����Ƃ��e�[�}�Ƃ��A�b�������X�ɔ��\���Ă���B���e�̓]�ʼnƑ���9��̈����z�����������N���̎��̌��Ȃǂ��ӂ܂��A�����߂�e�q�̒f��A�v�w���ꗂƂ������V���A�X�Ȗ���`�������Ă����B
�@�u�J���[���C�X�v�́A���ȏ��̂��߂ɏ������낳�ꂽ���́B �q�ǂ��̐����Ɛe�q�̐S��A�v�t���̎q�ǂ��̔����ȐS���ǂݎ�邱�Ƃ̂ł����i�ł���B
�@�[�H����Q�[�����������Ƃŕ��ɓ{��ꂽ���A�f���Ɏӂ�Ȃ��A���R���ɍ����|�������u�Ђ낵�v�B���x���ӂ낤�Ƃ��������t���o�Ă��Ȃ��B
�@����A�����̒�����������ɁA�ꏏ�ɃJ���[����邱�ƂɂȂ����B���߂ĕ��Ɠ�l�ō���������B���͂��̎��Ɂu�Ђ낵�v���u���h�v�̃��[��I���Ƃ�ʂ��Ďq���̐�������������B ���߂͂������Ă��ċC�܂������������A�I�Ղł͂ق̂ڂ̂������͋C�ƂȂ��Ă���B���̓�l�̊Ԃ̋�C���u�҂���Ɛh���āv�ł��u�ق�̂�Â��v�Ƃ����J���[�̐h���̋L�q�Əd�˂ēǂ݉������Ƃ��ł���B
�@�u�Ђ낵�v����傫���J���ăJ���[���ق��������B��l�ō���������J���[�́A�҂���Ɛh���āA�ł��A�ق�̂�Â������B
�@�v�t���̐����ƐS��ɏd�ˍ��킹���J���[�̐h���\���B
�@�u�Ђ낵�v�ƕ��͕��i���������킯�łȂ����Ƃ́A���ׂ��݂̕��̎p�����Ă����ɐS�z���Ă���l�q��A�u�Ђ낵�v���Ȃ��Ȃ����������Ă���Ȃ�����Ƃ����ڂ肵�Ă��镃�̗l�q����e�Ղɑz�������B
�@�v�t���ɂ������������u�Ђ낵�v�Ɉ���J���Ȃ���e�q�̊ւ�肠�����ɂ��悤�Ƃ��Ă��镃�A�����Ă��̓�l�̎p���O�ғI���ꂩ�猩����Ă����̎p��ǂ݉������Ƃ��ł���B
�@�����̉Ƒ��\���Ƃ͈قȂ��Ă���o��l���̉Ƒ��\���ł������Ƃ��Ă��A�������Ȃ���ǂ݂₷���e�[�}�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B �Ƒ��Ԃɂ����鏬�����y���Ȃǂ�����������q���g������߂��Ă���B
�@�����ł����邭�炢�u���߂�Ȃ����v���������茾���Ȃ��Ȃ�̂����R���������̂��B�g�Ɋo�������邵�A�䂪�q3�l���݂�Ȓʉ߂����B�����Ȏ����������̂��A�Ƃ��݂��݊����������B
10/2(��) �܂莞�܍~�J �ߑO���N�N���j�b�N�h�b�N
1:30�N���B�����`�F�b�N�B�f�[�^�d�q�������B6:40�o�X���n�a�@�A7:00-8:45HD�R�s�[�J�n�ƕa���Ή��A9:00-11:30���N�N���j�b�N�A�h�b�N�f�@15���B ���ʔ���15�����B11:45�A�@�����B 14:00���@���ґΉ��B�V���`�F�b�N�A���͂Ȃ��BHD�R�s�[14���ԗv���Ă���B19:15�A��A�[�H�B20:30�A�Q�B
�J���[���C�X(2)�@���Ё@���c�~�q�ҁ@�A���\���W�[�u�J���[���C�X�v�吷��@�����ܕ��� 2018
�@50�]�l�̍�ƁA�|�p�Ƃ������J���[���C�X�ɂ��ď����Ă������M���W�߂��{�B�����Ɍ��{�̖ژ^�ƊȒP�Ȓ��҂̃v���t�B�������Ă���B������L���ȑ��Ƃ́A�Ȃ��Ȃ������ȃG�b�Z�C�����ڂ���Ă���B����قǃJ���[�ɂ͖��͂�����ł���B
�@���{�l���Ă݂�ȃJ���[���D���Ȃ̂��A�Ƃ��炽�߂Ďv���B���ꂼ��́u�J���[�ɑ���v������v���ɂ��ݏo�Ă���B
�@�S�Ă̕��X�̃J���[�ɑ����]�~�����[�łȂ��B
�@
�@�X�̍�i�͐�����l�X�A���X�̃J���[�ɑ���]������A�q���̍�����e����ł�����̖��̃J���[�A�����ō��H�v�ɖ������J���[�ȂǂȂǁA�c�ɂ̂͂��Ȃ��J���[������̎�l���A����10���Ԃ��ʂ˂����u�߂č���Ă���Ƃ����J���[�Ȃǂ��E�E�E�E�B
�@���ȂǃJ���[���D���Ȃ����ŒP���Ɋ��Ŗ���y���ނ����B�ƂĂ����̂悤�ȕ��͍͂��Ȃ��B�������A�Ǝv���B
�@��҂Ƒ薼�݂̂��L�����B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�r�g�����Y�@�@�@�J���[���C�X
���c�M�q �@�@ �@ �̃J���[
�ѐ^���q�@�@�@�@�J���[�Ɖ���
�����@�@�@�@�@�ق�Ƃ��̃��C�X�J���[
�������ہ@�@�@�@�J���[�͂ڂ��ɂƂ��ăA�w���ł���
�ɒO�\�O�@�@�@�@�����l�͕ЂÂ��Ȃ���d��������
�k�m�v�@�@�@�@�@�J���[���C�X
���썲�a�q�@�@�@�J���[�D��
�����m�q�@�@�@�@�Ă͂���ς�J���[�ł�
�F���� �@ ���̃J���[�E���C�X
�h��Y�@�@�@�@�@�J���[���C�X (������)�A
�����F���@�@�@�@�J���[���C�X (�C���h��)
�g�s�~�V��@�@�@�J���[���C�X���`���P�ɐH��
���R�C�i�@�@�@�@���C�X�J���[ �����̎v�z
���q���Z�@�@�@�@�c�_
�_�g��Y�@�@�@�@�J���[�}�ٕ�
����O�V �@�@�@ �Ă̖��E�J���[�̖�
�g�{�����@�@�@�@���ȃJ���[�����
���C�т����� �@ ���u���R���v�̃J���[
�����V��@�@�@�@�A���v�X�̗ՊE���ۃJ���[
�R�{��́@�@�@�@�m�H������̃L���O��
�ܖ؊��V�@�@�@�@�J�c�J���[�̏t
���c�S��@�@�@�@�H�q��
��������@�@�@�@�q���̍��̃J���[
��c�䂤�@�@�@�@���C�X�J���[
���v�@�@�@�@�����̃��C�X�J���[
���c�N�@�@�@�@�@�J���[�̒p�J
�ÎR����Y�@�@�@�r���}�̃J���[
�Γc�䂤�����@�@�J���[���� �W���f�B�̃J���[
�ΐ쒼���@�@�@�@�C���h�̃J���[
�p�c����@�@�@�@�J���[�A�ł����c
�Έ�D�q�@�@�@�@�J���[���ꂱ��
���ٖq�q�@�@�@�@�J���[���C�X
�ɏW�@�Á@�@�@�@�J���[���C�X
�Ԑ��쌴���@�@�@�C���h�l���т�����
�v�Z���V�@�@�@�@�J���[���C�X
�l�@�@�@�@�@�J���[�̃}�i�[
���Ђ����@�@�@�Z���g���C�X�E�J���[���C�X�E�u���[�X
���È���Y�@�@�@������O�ド�C�X�E�J���[
�R�����@�@�@�@�@�J���[���C�X
�˂��ߐ���@�@�@�J�c�J���[�̒�
�悵���ƂȂȁ@�J���[���C�X�ƃJ���}
�F�앐��@�@�@�@���̂悤�ȃJ���[�̖�
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�@���̐��M�W�͓K���Ƀy�[�W���J���ǂ݂������̂��y�����B
�@���x�ǂ�ł����̓x�ɃJ���[���H�ׂ����Ȃ閼���ł���B
10/1(��)�@�~�J�@�]���^�o�U�[
3:00�N���B�������Ɠ��l�A���y�֘A�f�[�^�����A��w�_���Ȃǃ`�F�b�N�B�Ǐ��B
9:30�]���^�����ۊ֘A�̃o�U�[�ɁA�Ɠ��ɓ���A���ׂցA�ו��^�сB10:00���n�a�@�A�މ@�\�芳�҂̐g�����⑫���L�ځB���͔��X��肨�ɂ���+���q�����B�V���`�F�b�N�{���́A�̂����w�A19:00�A��A20:30�A�Q�B�o�X�_�C���ύX�B����҃R�C���o�X���ƍ�N����A�֗��B
�u�J���[���C�X�v(1) ��̖�
�@���̓J���[�ƃ��[��������D���ł���B �O�҂͐���h������h�������܂�Ȃ��B�����H�ׂĂ����ɂȂ鎖�͂Ȃ��B
�@
�@�䂪�Ƃ̃J���[�͔����ł���E�E�Ƃ������Ђǂ��J���[�ɓ����������Ƃ͂Ȃ��B�J���[�Ƃ����������H�ނ��L����ݍ��ށA�t�g�R�����[�����ƂƁA�䂪�Ƃł͑����o�������̃��[���g���Ă��邽�߂Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B
�@���[�H�ɏo��̂ł��邪�A�ǂ����Ă����ő�ʂɍ��قǔ��������o����̂ł͂Ȃ����B������A�]�邩��A���̗ʂɉ����ė������疈��3-4�������ĐH�ׂ�̂���ł���B
�@�J���[�D���̕��͂������ł��邱�Ƃ��}��Ȃ��炵�������͍��Ȃ��B���N�O�ɉƑ������Ȃ����Ƀ��g���g�J���[�����ĐH�ׂ������Ō�ł���B�{���̓J���[���X�Ƃ��L���X�ɍs���Ĉꗬ�̖��Ȃ���̂𖡂���Ă݂����̂ł��邪�A����ȏ�ɊO�H�����Ȃ��̂�����ʂ�����Ă͂��Ȃ��B���Ȃ݂Ɏ�����������ɊO�H�ŐH�ׂ����̂̓��[���������ł������B���ꂪ�A�V���ɍs���ď��߂ăX�p�Q�b�e�B�~�[�g�\�[�X��H�ׂ��u�ԁA���̐l���͂�������ς���Ă��܂����B
�@1953�N�Ɏ��ꂪ������J���[�͔����������A�Ƃ��������ɔ����Ȃ��̂����������������ゾ�������炩�J���[�Ƃ����ƐS�Ƃ��߂������̂ł������B
�@�����A���̓c�ɂœ���ł����̂̓o�����ƌ�����悤�Ȓዉ��(??)�ؓ��ł��������A������u�߁A�Ԃ�̃j���W���ƃ^�}�l�M����肱�݁A�^�}�l�M�������ʂ��Ă���ƁA���������A�傫�߂̃W���K�C���𗎂Ƃ��ASB�J���[���p�E�_�[�������Ɨn�����A��������Ǝς��ށB ���Ƃ͂��̂Ƃ��̋C���œ�������܂킵�Ă����B����ƁA�܂��Ȃ��J���[�̎h���I�ȍ��肪������ɕY���͂��߂�B�����Ȃ�ƁA����𖡂���Ă��邾���ŖL���ȋC���ɂȂ��Ă������̂��B
�@�������A���̃J���[�̌��_�͉��F���āA�Ԃ�̃^�}�l�M���Ƃ���ǂ���ɕ����ԁA�ǂ��Ƃ����J���[���B ���A���̖��͕�̖��ł���B
�@�ŋ߂̃J���[�ɂ͌��\�����ȐH�ނ��������Ă��Đ̖̂��Ƃ͎��Ă������Ȃ��̂��낤�B���ْ͖͍f�������b�L���E���ʂɂ܂Ԃ��B
�@�J���[��H�ׂ鎞�ɕ�̎p���v�������ׂĂ��܂��B�Y����Ȃ��B
�@�����A���{�l�̃J���[���C�X�����ɂ���E�E�̊��ł���B
9/30�i�y�j�ߑO�܂�@�ߌ�~�J�@���߂ăJ�~�\���ŕE���
�@1:00�N���B�����`�F�b�N���B�������̂��Ƃ��B�Ǐ��A������Z�łł��Ȃ������V���`�F�b�N�B���d��������z����Ăł��Ȃ������B14:00�Ɠ��ɓ���A���n�a�@�A�����A�@�a���Ή��B���߂ăJ�~�\���ŕE���A���K�ɂł����B18:20�̃o�X�ŋA��B19:00�[�H�A20:30�A�Q�B
9/29�i���j�����@��Ȓ��ʕa�@�@Zoom�w�K��
�@1:50�N���B�����ǂ݁E�k�R�ȂǁB�摜�d�q�f�[�^�����B5:20�R�S�~�Ɣ��̉�����p���A7:35Taxi�w�ɁB8:11���܂�12���ATaxi�A9:00�O���A��r�I�X���[�Y�A15:20���艮�o�R4���قǍw���A�A�@�B15:30�a���Ή����B18:30�A��A�Ɠ�Zoom�w�K��A�]�O�Ȋ֘A�A20:30�A�Q
9/28(�j�܂莞�ɍ~�J�I���@�Ɠ��^�]�Ƌ��X�V
�@1:30�N���B�������B�������������B8:45�Ɠ��ɓ��惊�n�a�@���A�����A�V���`�F�b�N�A���́B10:30���Җʒk�A11:00�a���Ή��B12:00�Ɠ��^�]�Ƌ��X�V�ɁB�V���@����Ή��B19:10�A��A�[�H�A20:30�B
9/27�i���j�����~�J�̂������@
�@1:45�N���B�Ǐ��A�^���f�[�^�����Ə����A�f�[�^���ނȂǁB�O��Əo�����A9:00�ߑO�͉Ɠ��ɓ��惊�n�a�@�ցA�����A�V���`�F�b�N�A���́B11:00�a���Ή��A13:00��lj�A���H�A14:30�J���t�@�����X�A���@���ҏ��u�ȂǁB��ǎ����̊��������A�d�q�J���e�̃m�[�g�p�\�R����ʏ�g�p�ɃZ�b�g�A��͋Ɩ����P�ɂȂ낤�B19:30�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B��N���������ăt���[�X�Z�[�^�[���p�B
9/26�i�j�����@���ʕa�@�O���@
�@1:30�N���A�����`�F�b�N�A�k�R�ȂǁB5:10�ƒ�S�~1�܂Ɣ��̃L�E���̌s�ȂLj�܁B6:40�o�X�ѐ�a�@�A7:00-8:15�a���Ή��A8:45-12:50���ʕa�@�O���A�敾�B13:00���n�a�@�A�����A���@���ґΉ��A�V���@�A���`�O�Ȃ���l�B19:00�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B
�����E(2) �E�̌��\�͂��낢��
�@�C�`���[�����僊�[�O�ő劈�Ă������A���������E�ł��闝�R�����āA�u�Ȃ߂��Ȃ��悤�Ɂv�Ɖ����Ă����A�Ƃ����B�u���{�ɋA��I�I�v�R�[���𗁂т����h�����������ɁA����̔ނ������ł����C���h�ȕ��͋C������悤�Ǝv��������Ɛ��@����B�ٍ��Ŋ��邽�߂ɂ́A����ȋC�������K�v�������ɈႢ�Ȃ��B
�@��ʓI�ȓ��{�̒j�����͖����E������B�����E�͑��l�ɂ���������^���Ȃ��B�������l�̖����E�d���Ȃnj��������Ȃ��B���͎����̊�����Ō��邱�Ƃ��ő��ɂȂ����玩���̖����E�ɑ��Ă̕s�����͂Ȃ��B
�@���͎Ⴂ�Ƃ�����E����ɂ��ẮA�S�Ďd���Ȃ��ł������B
�@�@
�@���A�����E�ł͂Ȃ��A�{�i�I�ɕE��~����j���������Ă���炵���B�u�j���v�����A�s�[������̂Ɏ����葁������ł��낤�B
�@ �퍑�����▾���̌��M�́A���Ђ̏ے��Ƃ��ĕE��~���Ă����B
�@�ߔN�͌������߂��A�����炵���������c�[���Ƃ��Ď�҂𒆐S�ɕE�X�^�C�����L�������B���ꂪ���N�w�ɂ�������A�Љ�S�̂̋��e�x���オ�����B
�@�����A���Ⴂ���Ă͂����Ȃ��B
�@���̂悤�ȁu�P�Ȃ閳���E�v�����炵�Ȃ���ۂ�^���邱�Ƃ́A�����ς��Ȃ��B
�@�E�𐮂���ƁA�Ȃ肽�������Ɉ���߂Â����Ƃ��ł���B�Ȃ肽�������Ƃ́A�u�ј\���������v �u���C���h�ɂȂ肽���v�u�E�E�E�E�v�ȂǂȂǁB
�@���Ƃ��A���E�����̃X�^�C���͊ј\�����ۂɁB�ۊ�A�ʒ��ȂNJ�̌`�ɍ������E�ɂ��邱�Ƃ�S������B�ۊ�Ȃ炠���E�Ƃ��݂������Ȃ���ƃV���[�v�ɂȂ�B���������l�́A�E��~���邱�Ƃœ��Ɏ������s���ɂ����Ȃ�E�E�E�ȂǁB
�@�j���̕E�͏��Ɋ��p��������̃R���v���b�N�X�̉����ɂ��Ȃ��邾�낤�B
�@
�@�����ς�ƒ����悵�B ���I�ɐ�������悵�A�ł���B
�@�ŋ߂ł͖э�����苎��A������ɂ����҂������Ă���Ƃ����B���܂������Ȃ��Ō��ǂɔY��ł���������Ȃ��Ȃ��l�q�B
�@���̕E��蓹��͊ȕ֒P���A�������ł���B
�@�E���Z�����͓d�C�E��肪�����BT�^�̂͐n�ƃz���_�[�̊Ԃɖт����܂��Ă�����Ȃ��Ȃ��Č����������B����L���߂����̂ŏ��߂Ē����̃J�~�\����p���Ă݂��B������ƕ|���������o�����邱�Ƃ��Ȃ��Y��ɒ��Ċ��������B�����Ƒ����g���Ă����Ηǂ������B
�@
�@����A�E���̃X�g���X���������ꂻ���ł���B
9/25�i���j�����@���N�N���j�b�N�h�b�N�@�@
�@1:30�N���A�����`�F�b�N�B�f�[�^�����A6:40�o�X���n�a�@�B7:00-8:00�a���Ή��A30�������B9:00-11:15���N�N���j�b�N�h�b�N15�l�A���ʔ���Ȃ��B11:30���n�a�@�A�Ǐ��A�����ق��A14:00���@���ґΉ��B�V���`�F�b�N+���́A�Ǐ����B5-8���̋Ζ�������B19:15�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B���Y�{�����甖��̍�ƕ��ցA������ƕ����p�B�}���Ɋ����Ȃ��Ă���B
�����E(1) ���\�͂��낢��
�@���͂��̂����ł���B�Ƃ�킯�E����̂������ł���B
�@�������Ȃ�����{�ł͖����q�Q�͎Љ���̒��ł͉���X�֎���ɂȂ�B������A�����̍��͖����܂��͊u���ɁA�Z�����ɂ͓d���J�~�\���ŁA�����Ȃ����ꍇ�ɂ�T�^�̈��S�J�~�\���Œ���Ă����B
�@���ނ��Ă���͕E���̕p�x�͂ǂ��ƌ������B�T�ꂭ�炢�ɂȂ����B�a�@���̋Ɩ����ɂ͖����E���B���ړI�Ń}�X�N�𒅗p�����B
�@���̂����A���u���Ă����{�E��20cm�قǂɂ܂łȂ����B
�@���̃q�Q�₵�����B���ɂƂ��ēs�����ǂ����\������������ł���B
------------------------------------------------------------------------
(1)�v����ɁA���̂����Ŗʓ|���ƌ�������
(2)����ʐl�ɂȂ����悤�ȋC���𖡂킢��������
(3)���l���疳�������悤�ɂȂ����B���l���猩��A�܂��Ƃɂނ��ꂵ���A���ꂵ���W�W�C�Ɍ����邩��ł��낤�B���R�l�����F���鎄�ɂ͍D�s���ł���B
(4)�ɓ����̓N���X�o�C�N�Œʋ��Ă������E�����ɓ������Ă��悮�̂��C�����悩�����B
(5)�l�R�ǂ����e�����Ɋ���Ă���悤�ɂȂ���(?)�E�E�E�E�E�B
------------------------------------------------------------------------
�@���ꂪ��̗��R�œڍ������B
(1)2016�N9���l�a�w���j�A�̎�p�ɂ͑S�g�������K�v�ŁA�C�Ǔ��ɓ��ꂽ�`���[�u����ʂɌŒ�ł��Ȃ����疃���Ȉォ��E�𗎂Ƃ��悤�w�����ꂽ�B��3�N�Ԃ̌������A�Ə������B
(2)2020�NCOVID-19���s�ƂƂ��Ƀ}�X�N���p��������O�ƂȂ�A�E���L�тĂ���Ɗ�ʂɖ��������ɑ������ʂ������邩�犴���\�h�̂��߂ɂ��E��L���Ȃ��Ȃ����B
�@�{�N5���ȍ~��COVID-19��5�ނɂȂ������Ƃ������Đ^�ʖڂȕE���͎��X�T�{���Ă���B
�@����A�q�Q�Ƃ���������������Ȃ��č��ꎫ�����������B
�@�q�Q�ɂ�3��ނ̊������������B�E�͂����Ђ��A颂͂����Ђ��A陂͂ققЂ����w���Ƃ����B ���{��Ƃ������A�����Ƃ������A�@�ׂȕ��ނƕ\���ɉ��߂ċ������B
�@���Ă̈̐l�B�� �E��颂��̂��Ă��Č`�ǂ������Ă���B���s�������������m��Ȃ����A���炭�A�����̃G���[�g�ӎ��Ƃ��Ќ��̕\���ɗp���Ă����Ǝv���B
�@
�@����A�C�X�����Љ�ł͒j�B�͕E�A陁A� �̓�҂܂��͎O�҂��قڑS�����₵�Ă���B�����ł����\�悭����ꂳ��Ă���B���̎Љ�ł͒j�̓q�Q��L���Ȃ��ƈ�l�O�Ɉ����Ȃ��Ƃ��B
�@�ǂ����ɂ��斳���E�͑S���]������Ȃ��悤�ł���B
9/24�i���j�����@�Ɠ��a�����@�@
1:40�N���A���\�����B�f�[�^�����A�Ǐ��ȂǁB�W:00���d����2��ڍ�ƃR���|�X�g���爧���������]�|�A�傫�ȉ���͂Ȃ��B11:30���ҕs���Ƃ������Ƃʼn�f�ɍs���Ɠ��ɓ���A���n�a�@�B15:00�a���Ή��A�މ@���ҁA���M���҂���B�V���`�F�b�N�{���͂ق��������A�Ǐ��ȂǁB20:00�Ɠ��a�����ē����A�[�H�B21;30�A���B�叹���l�l�A�Ȃ��Ȃ������B
�h�V�̓��Ɏv��(9)�@�̘b�A���Ƃ��b�͂Ȃ��n�b�s�[�G���h���@�V�l�̊�����������������
�@���Â̘̐b�A�u��萝�v��u�}�n����A�u���������R�v�A�u������P�v��u�����Y�v�͎q�̂��Ȃ��V�v�w�P�Ɛ��сA������ ��l��炵�̘V�l�̘b�����Ȃ��Ȃ��B�Ƒ��Ƃ��ǂ��a�C�\�X�Ƃ������W�J�̘b��͂قƂ�ǂȂ��B
�@
�@�̘b�̘V�l�͕n�R�ŁA�����������������Ă���B
�@�X�ɁA�̘b�̘V�l�́A�����q�⑷�����Ă��A�u�W�̂Đ��b�v�ɑ�\�����悤�ɁA�u����v���Ă��邱�Ƃ������B
�@�v����ɐ̘b�̘V�l�̒n�ʂ͂ƂĂ��Ⴉ�����B
�@�ɂ�������炸�A �ނ�́A����̢����v�ƂȂ��Ă���B�������A�قƂ�ǂ��n�b�s�[�G���h�ł���B
�@�̂̐l�A���Ȃ��Ƃ��ÓT���w�ɕ`���ꂽ1700�N���̐̂̕��ώ�����30�Β��x�ł��������낤���A�����ɐ��l���}�����҂͒�������70�Έȏ�̒����҂����Ȃ��Ȃ������B�@
�@���̎���A���̒����҂����ł������B���N�œ����邤���͂Ȃ�Ƃ�������ꂽ���A��x���N���Q����Ɛ��b����邱�ƂȂ���C�ɂǂ��ɗ����A�쐂�ꎀ���Ă��܂��B���̂���������邱�Ƃ��Ȃ����u����Ă����B
�@�̘b�̘V�l�̓����́u�n�����v�Ɓu�ǓƁv�ɂ������B
�@������������ł́A�����͂ǂ�Ȃɓw�͂��Ă������P���邱�Ƃ͊��҂ł����A�����ɂ͍K���ɂȂ�邾�낤�Ƃ������҂��Ȃ��琶����Ƃ�����Ԃł������B
�@�����������ł͌����ł́u�v�������Ȃ����������ň�C�ɍK���ɂȂꂽ��E�E�E�v�Ƃ������Ƌ��ɐ����邵���Ȃ������B����Ō����A���z�̕��̈ꓙ�ɓ���Ƃ������̂悤�Ȃ��̂ł���B
�@�ꖇ�̂ӂ�ǂ��ɂ���ĕx����A�͂�ɊD��U�肩������Ԃ��炫�a�l���狐�z�̖J�������炤�E�E�E�A�����͑S�ď����̖��A���z�ł������̂��B
�@�̘b�̑����͕s�q���A�s���A�����ƋQ���A����Ɖ쎀�A�G���O���A�c�s�s�ׁE�E�Ȃǂ��`���Ă���B�����͖�������ɂ����͍킬���Ƃ���A�q���̋���p�Ƀn�b�s�[�G���h�ɂȂ�悤�ɉ��ς���Ă����B
�@�����̌��T���ɐG���Ɓu����ɐ��܂�ėǂ������v�A�Ƃ��Â��v���B
�@����ł�����̘V�l�͂��낢���������Ă�����̂��B
�@����A�V�l�����ł͂Ȃ��B�ǂ�ȔN��̃q�g���A�ǂ�Ȏ���ł����Ă��A������ɂ͏�ɍ���������̂��A�Ǝv���B
�@�h�V�̓����@��ɂ��낢��l�����B
9/23�i�y�j�����ߌ�ꎞ�~�J�@
�@1:00�N���B�����`�F�b�N���B�������̂��Ƃ��B�Ǐ��A�V���`�F�b�N�B10:00�Ɠ��ɓ��掀�S�f�f���s����������ɕa�@�B11:00�A��A���d�����ɒ���B�x���������S�B���H�����Ԃɍ~�J����B���ւʼn��y�֘A�^��ӏ܁B19:00�[�H�A20:30�A�Q�B
�h�V�̓��Ɏv��(8)�@�V�l�̒n�ʂ͒Ⴍ�H�Ɗ�@�̍ۂ͐H��ꂽ!!
�@1687�N�Ɂu�̂ĕa�l�v�̋֗߂��o��܂ł́A�a�l���̂ĂĂ��߂ɖ���Ȃ������Ƃ����B���C�ȘV�l���̂Ă邱�Ƃ͗��ɂȂ������ɂ��Ă��A�m���̘V�l���A�R���Ɏ̂Ă邱�Ƃ́A�����ɂ������ɈႢ�Ȃ��B
�@�u�W�̂āv�`����̘b���S���ɂ���̂́A??�u�a�l�ɑ����q��ӎ��v��??�u�ɒ[�ȕn�����v�A??�u�����I�ȐH���s���v�Ƃ����w�i�����������炾�낤�B
�@�L�j�ȗ��A���{�͂��т��ыQ�[�ɏP���Ă���A�����ɋL�^���Ƃǂ߂������Q�[�́A�Ñォ��]�ˎ���܂łɁu��3�N�Ɉ�x�̊����v(�e�r�E�v�w�Q�[�x)�Ƃ����B
�@��200�N�O�́u�V���̑�Q�[�v���̓��k�n���ł́A�q�Ɏ̂Ă��ĉ쎀�����e�������B����ǂ��납�A���ɂ����ȑ��q��H�ׂ悤�ƗƂ̒j�Ɂu�E���Ă���B�������v �ƌ����ĎE�����ē������Ђ��ɂ������e������(�k��殁u���V�L ���x)�B
�@�u�ꂪ�쎀�����炠���܂�����E�E�v�ƁA�쎀�҂̓������߂�҂�����A�u�e�͎q�������ΐH�͂��v�ЁA�q���e�̓���H��Ƃ��v�Ƃ����悤�ȋɌ���Ԃ��J��L�����Ă��� (���R�F��Y�w�k�s���L�x)�B
�@�V�l���̂Ă��闝�R�̈�ɐH�ƕs���ɂ��Ɍ���Ԃ��������A�ƍl������B�s���ŋQ������ԂŎ����ɂ�������݂��������Ă����̂Ɂu���Ă𓐂�Ŋ���ł���v�ƌ������̂Ă�ꂽ�e������A���܂����܂ł̕n�����ƐH���s���A�Ƒ��̒��̘V�l���u�݂��߂ȗ���v �u�Ⴂ�n�ʁv���������B
�@�V�l�ɉƑ�������ꍇ�ɂ́A�q���̐��b�ɂȂ��Ă��邾���ɐH�Ɠ�̎���ɂ͐��_�I�ɂ͂ނ���炩�����̂��낤�B
�@1878�N�A���������C�M���X�l���s�Ə����C�U�x���E�o�[�h�́A��������Ñ��ŁA�u�N�z�̒j�����n�����đ̗͂������đ�Ƒ���{�����A���݂����v �Ƃ����b���A�u�Ƒ�������҂����E����b�͂悭���邱�Ɓv�Ə����L���Ă���(�哇�Ђ���)�B
�@����̓��v�ł��A���E�҂́u�قƂ�ǂ��O���㓯���̘V�l�ŁA�S�̂�60%�����߁v�A�u��l��炵�̘V�l�̎��E�҂͑S�̂�5%�ȉ��ɉ߂��Ȃ��v�Ƃ����B
�@�S�g���ʂ̐��������o���A��������Ƒ��Ɂu�Ō����̕��S�������邱�Ƃւ̉�����������v���ƁA�X�ɁA�M������g�����痝�����ꂸ�A�₽���a�O����Ă����т����������A�V�l�ɂƂ��đς����Ȃ����E�̌����ɂȂ��Ă���B
�@���Â̍��͕n�����ŘV�l�͑j�Q����A����ł͊Ō����ւ̕��S�A�V�l���L�̎₵���ȂǁA�V�l���͂��̐��ł����������Ă����B
�@���݂��Љ�ۏ�̖ʂŎ���������A�����A�������A�Ƒ���Y�܂��Ă���B
9/22�i���j��Ȓ��ʕa�@�@
�@1:50�N���B�����ǂ݁E�k�R�ȂǁB�摜�d�q�f�[�^�����B5:20�R�S�~�p���A7:40Taxi�w�ɁB8:11���܂�12���ATaxi�A9:00�O���A��r�I�X���[�Y�A15:20���艮�o�R10���قǍw���A�A�@�B16:10�a���Ή����B17:20�A�~���C�h�̊��Ҏ����A19:30�A��A20:30�A�Q�B
�h�V�̓��Ɏv��(7)�@�����͒��n�R�@������̂�����
�@���̘͐b�A���Ƃ��b�A���b����A��̂̏����́w�V�l�x���ɂ��Ă����Ƃ����C���[�W������Ă����B�������A�����ł͂Ȃ������B�����́A�����͂���������V�l�́A�i�K�I�Ɂu�a�܂�Ă������v�������������������B
�V�l�͈������Ă����H�H�E����Ă����H�H
�@1945�N�ɏo�ł��ꂽ�V�����Y�̏��Ђɂ��ƁA�V�l�̈���Ɋւ��ď��̂���39�Љ�A18�ŘV�l��������{���Ă����B
�@����ɘV�l�E���ɂ��Ă�44�Љ�A �u�p�ɂɂ���v�A�u���Ȃ�p�ɂɂ���v��11�Љ�A�u���Ƃ��đ��݂���v ��11�Љ��������(�哇�Ђ���)�B
�@�܂��A�u�V�l�͎Љ�̎�����? �Љ�̏d�ׂ�?�v�Ƃ���1981�N�ɔ��\���ꂽ����_���ɂ��ƁA57�̖��J�Љ�̂�����84%�͘V�l���u����v�u ���́E���Y�D��E
�u���E���u�E����E�E�l�Ȃǁv���Ă����l�ł���B�����ł͘V�l�E����19%�Ō��炽�B
�@���̑命���ł́u�}�{�ƘV�l�E���Ƃ��������Ă���v�Ƃ����A���������͘V�l���u���N�v�����������Ƃ����B
�@�܂�A���S�ȘV�l�́A���h�����̑Ώ�(?)�ƂȂ���̂́A�u�V�l�ɐS�g�̐�����A�V���E�s���Ȃǂ̏Ǐ���n�߂�ƁA�ނ�͎Љ�̉ו��ƂȂ�A�₽���������ꂽ�v(���܂���)�B
�@�v����ɖ������Љ�ɂ�����V�l�͊�{�I�Ɂu�Љ�̂��ו��v�ł���A�V�l���厖�ɂ����̂́A�_�k�⋙���Ȃǂɂ����肵���H�̋���������A�y�n�̏��L���Ȃǂ̑̌n���m�����A�N�������K���Ȃǁu���G���v�����Љ�ɂȂ��Ă���A�Ƃ����킯�B
�V�l�������n�������R
�@���{�ɐl���Z�ݎn�߂��̂�3���N�ȏ�O�A�_�k���n�܂����̂�3500�N�قǑO�Ƃ����A����ȑO�͐H�̊m�ۂ͋ɂ߂ĕs���肾�����Ǝv����B
�@����̘͐b�̘V�l���������ʼn������悤�ɕs����ȕ�炵�����Ă��邱�Ƃɂ��\��Ă���B
�@���c���j�́w���{�̘̐b�x(�S106�b)�ɂ́A�V�l����l���ƂȂ��Ă���b��28�b�B�����ł͂��̓���炵�Ƃ����̂��قƂ�ǂŁA�������������V�l�̘b�͊F���B
�@�����V�l�̘b��17�b�B ����ɂ��̒��ŘV�v�w��������4�b�B���Ƃ�������15�b���A�c��̌���肪1�b�A���d����1�b�A�R�Ŕ��d����3�b�A�R�Œ|�E�d�E�Ė�����Ȃǂ̎R�d����7�b�A��ŎG���߂��R�Ŏ���肪1�b�A��73%���R�d���ł�����(�哇�Ђ���)�B
�@����ł́A�قƂ�ǐH���ɂ���Ƃ̎������������Ȃ��������낤�B
�@��L�̔@���A�̂̏����̘V�l�̓����́u�H���ɍ���v�قǂ̕n�����ł���B
�@�̘b�����ł͂Ȃ��B
�@������̗��j�ɂ��܂��A�̘b�ȏ�ɁA�����ꂽ�����̌������������`����Ă���B
9/21�i�j�I���~�J�@�Ɠ���w��f
�@2:00�N���A�摜�f�[�^�����A�V���A��w�������ǂށB�k�R�B8;30�Ɠ��ɓ���A���n�a�@�A�����A�V���`�F�b�N�A10:30CV�}���A10���N�U��B���@���ґΉ��A19:00�ʒ����X�o�R�A��A�[�H�B20:30�A���B�B��N�K�X����������B
�h�V�̓��Ɏv��(6)�@������`�����̘b����m��w�l�Ԃ̐^���x
�@���͂���20�N��������ŗ��j���w��ł���B
�@���̒��ŌÂ����b�₨���b�̒��̏����̐����𒆐S�Ƃ������j(?)�̕����D���ł���B
�@�����Ƃ��āA��c�_��u���{�̂Ȃ��ʊρv�A���c���j�u�����œ��{�̂Ȃ��v�A�H�c�����ꋳ�猤����u�H�c�̘̐b�v�A�哇�Ђ��莁���̒����ق��𗘗p���Ă���B
�@�c�����ɐe���̘b�͖�������Ɏq���p�ɑ啝�ɉ��ς��ꂽ���́B�����͘V�l�������o�ꂵ�A�ꌩ����҂̃p���_�C�X�̂悤�ɂ���������B�������Ȃ��猴�T�ɐڂ���Ƃ����ɂ́u�n���E�ǓƁE���i�v�̐��E�ł���B
�@�̘b����m�邱�Ƃ��ł���V�l�́u�n�ʂ͂ƂĂ��Ⴍ�v�A�u������̂ɓ�a�v���Ă����B�����͌����Ă������ɁA�l�Ԃ̌��_�Ƃ������ׂ��^������{�l�̗��j���Ђ���ł��āA���͂����̂��������q���̍��̎v���o�ƂƂ��ɉ���������������Ă���B
�@�̘b�̘V�l�ƌ���̘V�l�̊Ԃɂ͋��ʓ_���������邪����𖡂키�̂��y�����B
�@70�ō����ɐ����o���V�l�A ���ړ��Ă�3-40�ΔN���̓�Ɠ������E���ꂩ������70�̑m���A80�Ή߂��̎��̏Z�E���E�����Ƃ���70�̎��ȑm�ȂǂȂǁA�ǂ��������Љ�̌�����{�ɂ�����V�l�B�ŁA�̘b��ÓT���w�ɕ`���ꂽ�V�l�ƌ���̘V�l�̋��ʓ_�ɂ����������B
�@�u�̘b�ł́A�Ȃ����ꂳ��Ƃ��k������Ȃ̂�??�v�A������s�v�c�Ȉ����ł���B����͑����̘V�l���g�����Ȃ��A�H�ׂ���̂��Ȃ��쐂�ꎀ�ɂ����ł��낤�Љ�ŁA�N�������������A���z�A��u�̐S�̃p���_�C�X�Ȃ̂��A�Ǝv���B
�@���̂悤�Șb�̓W�J�͐��m�ɂ�����B�I�����_�̖���A���f���Z���́u�}�b�`����̏����v�̓}�b�`�̉��R���Ă���u�Ԃ����K���Ȗ�������A�Ƃ������z�̐��E�����A���{�̘̐b������Ɏ��Ă���B�n��������������q�g�̐S���ɂ͋��ʓ_�����Ȃ��Ȃ��B
�@�u�F�s���q�v���Ȃ��R�ɘV����̂Ă�̂��B
�@�u�Y�����Y�v��40�̓Ɛg�j�B�u�Ȃ���╽�ڂ̕����x�鉃�v�ɏ����ꂽ�̂��B
�@�u�ǂ�����(�k)����v�Ɓu��������(�k)����v���Z�b�g�ɂȂ��Ă���̂��B
�@�u�����Y��͐�ɗ���Ă����̂ł͂Ȃ��A��Ԃ�����k���撣���č�����q���B
�@�u���������R�v�ł͖ꂪ�k��H�����B
�@�u�ꐡ�@�t�v�͏�Q�̂��߂ɐe��������̂Ă��A�����߂��Ă����B
�@�u�E�E�E�E�E�E�v
�@�ȂǂȂǂ̍�i�͖�������Ɍ����ɋ���p�ɕҎ[����A�u�n���E�ǓƁE���i�v�͌����ɍ킬���Ƃ��ꂽ�B
�@���T�͊y�����B
9/20 (��)�@�����@
�@1:30�N���C�܂���~�J����A�ߑO��������B�����ǂ݁A�摜�f�[�^�����B�k�R�L�ڂȂǂȂǂ������߂����B�O�d���ł��Ȃ��B9:00�Ɠ��ɓ��惊�n�a�@���A�S�Ă̒n�����ʍs�����ɂȂ��Ă����B�V�����n�����o�R�B���ɏa�Ȃ��E�ߑO�����ŁB12:00�Ɩ��ɁA�Љ��ȂǁB14:30�J���t�@�����X�B���ґΉ��A�����B�Ǐ��A�Ɠ��̓]���^�A18:30�o�X�A��A21:00�A�Q�B
�h�V�̓��Ɏv��(5)�@�Â̎���͂�����V�l�������̂�
�@�Â̎�����������̐l�����͏��Ȃ��Ȃ������B�V�l�����������A�Ɛ��肳���B
�@�����Ȃ�Ɓu�V���v�Ƃ݂Ȃ��N����ɂȂ��Ă���B
�@�u�V�l�Ƃ͉��Έȏ���w�����v�̔F�����A�������j��ʂ��ČÍ������Ƃ��ɕς���Ă��Ȃ��B������ӊO�Ȃ��Ƃł���B
�@����͏����̂��Ƃł͂Ȃ��A�����̎Љ�̍��M�Ȃ��̂����̋L�^����̗ސ��ł���B
�@�Ñ�̗���(�u�˗߁v)�ł́A�u61��V�ƈׂ��A66���˂ƈׂ��v�Ƃ���Ƃ����B
�@�u�V�v�Ɓu�ˁv�͋��ɘV�l�̂��Ƃ��w�����A������ۖ��̕��S�ɍ������邽��66���u�ˁv�Ƃ��āu�ۖ���S�Ƃ����v(���{�v�z��n�w���߁x �⒍)�B60�Έȍ~��V�l�Ƃ�����66�܂ł͓����A�Ƃ��錻��̓��{�̊��o�Ƒ卷�Ȃ��B
�@����͂��̔N��̍�����N�����x�������B�u�����ȁA���̍���҂́E�E�v�ƌÂ̍���҂͎v�����낤�B
�@�̂̐l�͂���Ȃɍ��N��ɂȂ�܂Ō����������̂��Ƌ����B
�@���߂̋K��łͤ���l��70�Έȏ�ɂȂ��đސE���������A�Ƃ���B�������A70�Ŏ��߂邩�ǂ����͔C�ӂł��������߂Ɉӗ~�ƌ��N��������A����������l�͂����Ƃ���Ă��� (���{�v�z��n �w���߁x �Z��)�B
�@��Ƃ��āA���������̓��������̒��j�������ʂ�28����76�܂Ŋ֔��E�ɂ������B��̓������ʂ��֔��E�ɏA�����̂�73��80�Ŏ��ʂ܂Ŋ֔����Ƃ߂Ă����B
�@���͎҂����͎��ʂ܂Ō��͂̏�ɋ����낤�Ƃ��Ă������Ƃ��M����B
�@���Ȃ݂ɁA�����̐��Ȃ̗ώq��90�A���̕�e�̖s�q��86�A�����̂�����l�̍Ȃ̖��q������N��85�܂Ő������B���q����̌�[���@��T�R�@�̕���c��̓�����q��107�Ŏ��S���Ă���B
�@80�Ή߂��܂őn�슈���������V�l�������������B�w���ΏW�x�̒��Җ��Z��80�̎��A�w�G�k�W�x�Ƃ������b�W�����������Ă���ȂǘV�l�p���[�͐����������Ƃ��M����B
�@���͎҂����͎��ʂ܂Ō��͂̏�ɋ����낤�Ƃ��Ă����悤�ł��邪�A���݂̐����Ƃ������悤�ȂƂ��낪����B�����̐��E�ł͌��������̔N��肪�̂����Ă���B�����Ƃ̓����Ȃ̂��낤���H�H
�@���͘V�Q�𗈂��ʂ����Ɂu�V���͋���ׂ��E�E�E�v�Ǝv���Ă���B
�@�����̏����͔N�V���Ă��A�Ⴂ�҂��A�d�E����s���Ƃ��������N�ɋ��ɂȂ�Ȃ��d�������čׁX�Ɖ䂪�g��{���Ă����̂ɁA�Ǝv���B���������ɒʂ���b�B
�@���̐����A�l�Ԃ́A�Љ�͕ς���Ă��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ�m��̂ɑ傢�ɎQ�l�ɂȂ�j���ł���B
9/19 (��) �ߌ㌃�����~�J�@�A���_�[�p�X���� ���ʕa�@�O���@�@
�@1:30�N���C�����A�f�[�^�����ȂǂȂǁB5:00�R�S�~�p���B6:40�o�X���n�a�@�A7:00-8:10�a���Ɩ��A8:45-12:45���ʕa�@�O���B���\�敾�����A�~�J�̑O�Ƀ��n�a�@���B14:00�������~�J�A�ׂ̃r�������ނقǁA�����A�a���Ή��A19:00�A��A�V�����A�����c�̃g���l�������Œʂꂸ�A�V�����E���R��o�R��19:40�A��A�[�H�B21:00�A�Q�B�H�c�s2��ڂ̊����B
�h�V�̓��Ɏv��(4)�@���\�������������Â̓��{�@���l�͌���ɋ߂�������
�@����������̂��Ƃ͂悭�킩��Ȃ����A�����ŋL�^�������悤�ɂȂ������̘V�l�́A����l���l����ȏ�Ɍ��C�Œ������������A�Ǝv����B
�@����͈�Â����B���N�ł��C�y�Ɉ�Â����鎞��ɐ����Ă��邪�A�F���ȊO�̈�Ís��(??)���Ȃ���������̐l�͂����Ȍ����ő����������낤����A �V�l�Ƃ����Ă�40���炢?�A�Ǝv��ꂪ���B
�@����ݒ肪���̂��Ƃ��킩��Ȃ����A���w���̂ɂ���u���̓n���̑D������͍��N60�̂���������B���D�𑆂����͌��C��t�E�����Ȃ�E�E�E�v�ƈꌩ�V���Ă��Ă����C�ȗl�q�ł���B
�@���j�����҂̋S���G���ɂ��A���{�́u�S���l�������߂Ē������ꂽ�̂�1721�N�̂��Ɓv�ŁA����܂ł͐��m�Ȑl���͂������A�N��\�����s���ł��邪�A�@��l�ʉ���(���̌ːВ���) �⎛�̉ߋ����Ȃǂ��琄�v�ł���1600�N����̕��ώ����́A30�Β��x�Ƃ��Ă��� (�w�l������ǂޓ��{�̗��j�x)�B
�@���̐��l�́A�u�̂̐l�͑����Ɂv�Ƃ�����ۂ𗠂Â��Ă��邪�A���ώ������Z���̂́u���ɍ������c�����S���v�̂����ł���A�u���S���̍����댯�ȔN��A������ʓI�ɂ�8�Ǝv���Ă����E�E�E���A���̎��������z�����l�X�̕��ϗ]���͈ĊO�����A70�Έȏ�̒����҂��܂�ł͂Ȃ������v (�S����)�Ƃ����B
�@�S�������쐬�����A�M�Z�����M�́u�N��ʕ��ϗ]���v����v�Z����ƁA1675�N����1796�N�ɂ����āA21�܂Ő������т��҂̕��ώ����͒j�q59.�U�A���q55.�T�B61�܂Ő������т��҂̕��ώ����ƂȂ�ƁA�j���Ƃ�74�ɒB���Ă���B
�@������������̓��[���b�p�ł����l�ŁA�u��\���I�ȑO�̂����Ȃ鎞���ɂ����Ă��A���ώ����͂ǂ��ł��킸��40-45�Β��x�ł������v���A�u�댯�̑������c�������߂���A60������ȏ㒷����������\���͏\���ɂ������v (�o�b�g�E�Z�C���w�V�l�̗��j�x)�B
�@���{�ł͕��ώ����i2023�j���j�� 81.05�A����87.09�ɂȂ��Ă��邪�A���̒l�͒������ቺ�������c�����S���̔��f�ł���B����1-2�N��COVID-19�̗��s�ō���҂̎��S�����������߂Ɏ�����Z�k�����B
9/18�i���j�h�V�̓��j���@���܌������~�J�̐���@���Ҏ���
�@1;45�N���B�{�ǂ݁A5:00���Ҏ����̓d�b�B5:20Taxi���n���A��X�葱���A7:30Taxi�A��B�~�J�̂��ߔG��đ����s�\�A10:00���ҕs���ʼn�f�ɍs���Ɠ��ɓ���A�ēx���n�ɁB�V���L���`�F�b�N+���͌�����A���̌�͓Ǐ��A�a���Ή��A�_�H�ƒ�������I���B19:00�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B
�h�V�̓��Ɏv��(3)�@�ߎS�������̂̍���ҁ@�Ȃ̂ɐ̘b�ł͎��
�@���͂���20�N��������ŗ��j���w��ł���B
�@���̒��ŕ��s���ő傫���������Ă�������Ƃ������o������������ł���B�������Ȃ���A�L���l�𒆐S�Ɍ�����ʓI���j���͌Â����b�₨���b�̒��̏����̐����𒆐S�Ƃ������j(?)���D���ł���B
�@�悭�ǂގ����Ƃ��ẮA��c�_��u���{�̂Ȃ��ʊρv�A���c���j�u�����œ��{�̂Ȃ��v�A�哇�Ђ��莁���̒����A���̂ق��𒆐S�ɓǂ�ł���B
�@�̘b�̎���͂��ꂳ��E���k����ŁA�����ĘV�l�ł���B�Ⴂ�s�`�s�`�̐l�̘b�͂��܂����Ă��Ȃ��B���̓o��l���̘V�l�B�͂����Ί�ōK�������Ɍ����邪�A����͖��������Ɉ�C�ɂ���ꂽ����p�̕Ҏ[�ɂ����ς̌��ʂŁA������������ŋ߂܂��x����Ă����B�@
�@���ۂ̘̐b�̌��T�ɂ���V�l�̎p�́u�n���E�ǓƁE���i�v�ɂ���悤���B
�@�̘b����m�邱�Ƃ��ł���V�l�́u�n�ʂ͂ƂĂ��Ⴍ�v�A�u������̂ɓ�a�v���Ă����悤���B
�@�u��萝�v��u�}�n����A�u���������R�v�͍���ҒP�ƕv�w���сB
�@�u������P�v��u�����Y�v�͎q�̂Ȃ��V�v�w���A���R�A�q����������b�B
�@�u���������Ёv�̔@���̓Ƌ��V�l�̘b�A�����Ȃ��Ȃ��B
�@�̘b�̘V�l�͂ƂĂ��n�R�ŁA�����Ă���Ԃ͂������������˂Ȃ�Ȃ������B
�@�u���ꂳ��͎R�֎Ċ���ɁA ���k����͐�Ő���ɣ�̘͐b�̒�Ԃł���A���ꂳ��͊������Ă�w�����Ē��ɏo�Ĕ����čׁX�Ɛ������Ă���B�̗͓I�ɑ�ςȏ��ǂݎ���B
�@�u�}�n���v�̂��ꂳ��Ȃǂ́A��A���̂��肬��܂Ŋ}��ɒ��֏o�����Ă���B����ł��H�ׂ���̂ɂ����ƌ����Ă���B�ǂ��炩���|�ꂽ��悪�Ȃ��B
�@�̘̂V�l�́A�q�⑷�����Ă��A���ɗ����Ȃ��Ȃ�Ζ��҂Ƃ��āu�̂Ă���v���Ƃ����������悤���B
�@�X�ɁA�̘b�̘V�l�́u�P�ǂȘV�l�v�Ɓu�����V�l�v���ߏ��ɏZ�݁A�Ō�́u�����V�l�v���i�݂̂��߂ɔj�ł���B
�@�v����ɁA�ߍ��ȁu�����c��v�̐��E�������ɂ������B
�@�̘b�̍��̘V�l�́u�Љ�̖��҂̃~�m���e�B�v�ł������Ǝv���邪�A�̘b�̒��ł͂Ȃ�������������Ă���B���āA���̓��{�͒�����Љ�E�V�l�Љ�Ƃ����A �V���E�G���E�l�b�g�ȂǁA�����郁�f�B�A�ɘV�l�Ɋւ���b�肪�オ��ʓ��͂Ȃ��B���݂̘V�l�́u�Љ�̃}�W�����e�B�v�Łu�Љ�̉B�ꂽ����v�ł�����B�u�V�l�����ߍ��ނ���o�ς����Ȃ��v�A�u�N���E��ÁE�������łڂ����˂Ȃ��v�A�Ȃǂǝ��������Ȃǂ̖��������Ă���B
�@�A�̎���Ȃǂł͂Ȃ��^�̎����������Ȃ��B
9/17�i���j�����@�@�@�@
3:30�N���B�����ǂ݁B�摜�f�[�^�Ȃǐ����B�ߑO���ҕs���̘A��������A�Ή����w����
�ߌ�Ɋ��҉Ƒ��ʒk���Z�b�g�B�V���`�F�b�N���Ȃ���̂ǎ����y���݁A13:30�Ɠ��ɓ���A����R�C�ɋ��a�A���n�a�@�ɁB14:00-15:00���҉Ƒ��ʒk�A�ȍ~�͍��w�Ǐ��A19:00�܂ʼn@���ō��w�A�Ǐ��B19:30�A��[�H�B20:30�A�Q�B
�h�V�̓��Ɏv��(2)�@����Ғ�`�̍Č�����
�@���{�l�̕��ώ��������сA����҂̑��݂��܂��܂����܂��Ă���B
�@������{�Љ�̢����v�ƂȂ��Ă���B
�@���N�ňӗ~�̂���l�������B���̂܂A�Ƃ������邱�Ƃ��ł���Љ�͖ܘ_�̂��ƁA�V���ɏA�Ƃł���Љ��ڎw���ׂ����낤�B���ہA���N��Ҍٗp����@�́A70�܂œ�����悤�A��Ƃɓw�͋`�����ۂ��Ă���B70�Έȏ�̎Ј���������Ƃ����Ȃ��Ȃ��B
�@����u����ҁv�̒�`��ς���ׂ��Ƃ������Ă���B70�Έȏ�ł����̂ł͂Ȃ����B
�@�Љ�S�̂����̔N��̕��X��{���ɑ厖�Ɉ������ۂ��B����҂ƈꊇ��ɂ��ׂ��ł͂Ȃ��B����҂̊�����O���A�L�ѐL�тƎЉ�Q�����Ăق����B�w�Ȃ�!!! �����܂Ŋ撣���Ă�������҂��X�ɂ����g�������E�E�E�x�Ƃ������ӌ��͓��R���邾�낤���A���ꂩ��̓��{�̎Љ���ێ��������͍���҂��A�Ƃ������o���~�����B
�@�����ȂȂǂɂ��ƁA65�Έȏ�̐l��3623���l�ŁA���{�̑��l���̖�3���B���ώ����͒j���Ƃ�80������A100�Έȏ�̐l��9.2���l�����B
�@���q�����i�ތ���ł́A����҂͋M�d�ȘJ���͂ł���B��Ƃ́A����҂��̗͂ɉ����Ĉ��S�ɓ�������𐮂��A�ӗ~���\�͂�����l�̏A�J���㉟���Ă��炢�����B
�@�L�x�Ȑl���o�������ƂɃ{�����e�B�A�Ŋ��铹�����邾�낤�B����A�L�`���ƕ�V���x�����ׂ����B�{�����e�B�A�Ƃ������t�̗��ɂ́A���Ƃ��D�ӂɂ��\�o�ɂ�����Ƃ��Ă��A���̓��������Č����B�ܘ_�A�ЊQ�Ȃǂ̎x���̏ꍇ�Ȃǂ͕ʂł��邪�B
�@����҂���肪���������Ċ������邱�Ƃ́A�l�݂̂Ȃ炸�ƒ�ɂƂ��Ă��A�n��ɂƂ��Ă��A���̊������ɂ��Ȃ���B���⎩���̂́A�V�j�A����̗l�X�Ȋ������x������悤�Ȏ{���W�J���Ăق����B
�@2021�N4���{�s�̉������N��Ҍٗp����@�ɂ��A70�܂ŏA�Ƌ@����m�ۂ��邱�Ƃ���Ƃ̓w�͋`���ƂȂ����B
�@�H�c���͍���A�l�����ɂ��l��s�����[�������Ċ��͂������Ă��܂������A�H�c�J���ǂ����\����2022�N�̃f�[�^�ł́A70�Έȏ�܂œ����鐧�x�̂����Ƃ̊�����50.7%�A1042�ЂƑS����2�Ԗڂł������B1�ʂ͓������B
�@�����Ώۂ̑S��Ƃ̏A�Ƌ@��m�ۂ̕��������ƁA�u70�Έȏ�̊�]�ґS�����ٗp���鐧�x�v��22.8%(263��)�A�u���N��E�\�ʂ̊����70�Έȏ�̌p���ٗp���x�v��12.1% (249��)�A�u��N���̔p�~�v��3.3%(67��)�������B
�@�H�c���ł����N�Ɍb�܂�A�ӗ~�̂��鍂��҂������Ă���B����Ɛl��s�����w�i�ɂ���B�X�l�̐����v�A���N��ԂɌ��������A�Ə�����I�юЉ�Q���𑱂��ė~�����B
�@���͂���78�ł���B4������E�ꂪ�ς��A�A�Ǝ��Ԃ������A�d�q�J���e�̈����ɂ������Y��ł���B�Ǐ��̎��Ԃ͑啝�ɏ��Ȃ��Ȃ����B����ł����ȏ[����������B
�@�����o��������ꏊ�����邱�Ƃ����ł��K���Ȃ��Ƃ��A�Ǝv���B
9/16�i�y�j����@��H�ԉ@���m�F�l�Ɖ�H
�@1:50�N���B�摜�f�[�^�����A�����ǂ݁E�k�R�ȂǁB�V���`�F�b�N������A�d�q�f�[�^�����B�ߑO��SmartWatchi�̒����ɁB�����V���`�F�b�N�{�����A�Ǐ��B14:27�o�X�ɂă��n�a�@�A15:00 -16:00�s���̊��ґΉ��A�V�����́B��T�ԉB7:00Taxi�T���r�[���ցB���m�F�l�Ɖ�H�A3�N�Ԃ�A21:35Taxi�A��A22:00�A�Q�B
�h�V�̓��Ɏv��(1)�@���Ă̌h�V�A�ŋ߂̌h�V
�@9/18�i���j�͌h�V�̓��ł���B����������҂̈�ɒB�������A�h�V�̓��͌����ē��ʂȓ��łȂ��A���������̂ł͂Ȃ��B
�@�䂪�Ƃł͘d���̐Έ䂳����܂ߎl�l�Ƒ��ł��邪�A���̂����O�l���������҂Ő������̂Ƀ��`�ł��ċ��͂��Đ������Ă���B������l�Ⴂ�̂����邪�A���̑��݂͕�ł���B
�@���͍���Җ��ɂ͎Ⴂ�����狻�����������B�������Ȃ���A���̊ώ@�⒲���̖ړI�̂��߂ɏ��O�����K�ꂽ���Ƃ��Ȃ��̂ŊO���̘V�l���̎��Ԃ͂킩��Ȃ��B�������A�����I�l�@�͂����Ƒ����Ă������A���������Ă���B������A���܂�傫�Ȃ��Ƃ͌����Ȃ����A�e���̘V�l���ɂ͎�ʂ��Ă�����ł��낤�B
�@�����ē��{�̍���҂͌b�܂�Ă���ƌ����悤�B�������A����ҁA�Ƒ������ɂ��̎��o���R�����悤�Ɏv����B
�@���Ă͌h�V�̓��ƌ����Βn��ɂƂ��ďd�v�ȓ��ł����āA�e�����P�ʂł��j���̉����ɍs��ꂽ���̂ł���B�q���̍��͂��������Ƃ��̏o�����ɋ�肾����Ă����B
�@�����A����҂͏��Ȃ��A�n��̍Ղ��s���A�������Ղ̍ۂɂ͌������Ȃ����݂ł���A�n��ő��h����Ă����B���̈�����n��ł͓���I�Ɍh�V�̐��_���������l�Ɏv���B�䂪�Ƃł͑c�����ƒ��Ƃ��ČN�Ղ��Ă����B
�@����҂͎q���ɂƂ��ĕ|��������A����Ɛ��q�̔O��������݂ł������B
�@���͂܂������Ƃ��ďT5�������Ă���B���ۂɂ͋x�����E��ɏo������قǑ��Z�ł���B����3�N�قǑO����n��̌h�V��̉���ɂȂ����B�ŋ߂͒n��ʼn����Â����邱�ƂȂ��A���j���̋L�O�i�Ƃ��ĊC�ۂ̋l�ߍ��킹�Z�b�g�������Ă��邾���B������A�����ƈ�ۂ������B�N�Ɉ��h�V�Ɏv��������x�ł���B
�@�m���ɁA�����������قǂɂȂ�ƍ��E�����Ă��V�l�A�O������Ă��V�l���炯�ł���B���͍��͍���҂̈�Â�S�����Ă���B�O�����҂�7���A���@����15���S����70�Έȏ�ł���B������A�h�V�̐��_�͎������킹�Ă��邪�A����ȏ�Ɍ����I�A��̓I�ȍ���ґΉ��ɐS���ӂ�����Ȃ��B
�@�h�V�̓����j���ƂȂ����̂�1966�N�Ŗ�60�N�O�B���̍��̓��{�l�̕��ώ����́A�j��68.35�A����73.61�ł��������A���ꂪ���≽�ƁA�j81.05�A��87.09�Ƒ啝�ɐL�т��B������X�ɉ��тčs���ł��낤�B
�@100�Έȏ�̕������N�S����9���l���ƂȂ����Ƃ����B
�@���ꑽ�����Ƃł���B
9/15�i���j�����@��Ȓ��ʕa�@�@���N�N���j�b�N�f�[�^����
�@1:20�N���B�����ǂ݁E�k�R�ȂǁB�d�q�f�[�^�����B5:20�R�S�~�p���A7:40Taxi�w�ɁB8:11���܂�12���A9:00�O���A15:20���N�N���j�b�N�f�[�^����B���ă��n�܂�Taxi�B1�U:10�������B19:30�ʒ����X�o�R�A��A20:30�A�Q�B
�������C�m���o(12) �@�����͓��J�̃K�X�����ɗ��p??�@
�@���������o���߂����āA�����͑Η���[�߂Ă���B
�@�Ȃ��������{�͉䂪������̋֗A���݂̂Ȃ炸�A���������̊C�Y���֘A�Ǝ҂̌o�c����������悤�ȋ��d�p�������̂��B �����ɂ͂����Ȏ�������Ă���B
�@������2021�N�A�������̖��͑Γ��O���̃J�[�h�ɂȂ蓾��ƍl���A���o�ɔ����鍑�ې��_�̌`�����������Ō���U��グ���B�Ƃ��낪�AIAEA�́u���ۓI�ȁu���S��ɍ��v�v�Ɠ��{�ɂ��n�t����^���A�e���������̎咣�ɓ������Ȃ������B
�@�����͌v�悪�����A�������ł͌Ǘ����邱�ƂƂȂ�B
�@�����������������Ɂu�댯�ȉ������v�Ɣ��M�����������ʁA���������͔��ɋ����悤�ɂȂ����B���̐��_���ł����A�����[�u�ɏo����Ȃ��Ȃ����A�ƍl������B
�@�K�����͍�������Ƃ��āA���s���Y�s��̗₦���݂Ȃǂɂ��o�ϒ�A����҂�20%�ɂ��̂ڂ鎸�Ɨ��A��8���̍^���ւ̑Ή��A���č�����̌o�ϐ��قȂǂŁA�����̐��{�ւ̕s���͑傫���Ȃ��Ă���B
�@�������œ��{�ɔᔻ�̖��悪�����A�u�K�X�����v�ɗ��p���Ă���A�Ƃ����l���������藧�B�����A��t���L���̎��̂悤�Ȕ����f�����N����悤�Ȏ��Ԃ͔��������B��t�̎��͐��{���̂������f��������Ă����B
�@�����f���������{�f���ɔ��W����\�����ے�ł��Ȃ������ɂ��̂悤�Ȏ��Ԃ͔��������B
�@�܂��A���������̓f�}���Ɋ�Â��A���ꂽ��������ł��邪�A���������̂��ƂɋC�Â��Ɛ��{�̌o�ϐ���A�����̊����ɔ�щ���\��������B
�@�Γ��W�����P������Ƃ����K�����̊�{����͕ς���Ă��Ȃ��͂��ł���B���炭�A���{�ւ̔ᔻ���s���߂��Ȃ��悤�ɒ����͂��Ă������낤�B
�@�����������^�c�̗v�͌o�ρB���̂��߂ɂ͓��{�Ƃ̈���I�ȊW���s�����B
�@���{�����O���E���S�ۏᐭ��̊�{�͈ێ����A�����Ƃ̊W���d������p�����܂ɐG��Ď����ׂ����B
�@�����A���{�����ł͒�������̏��������ɑ��錙���点�s���ɕs�������L����B�@
�@���������̈��H�X�Ⓦ���̌��I�{�݂Ȃǂɑ��A�������̂��₪�点�d�b�������������Ă����B�����̓��{�l�w�Z�̂������ł́A��^�}�S�����������ꂽ�Ƃ����B
�@�������{�͔�Ȋw�I�ȏ��𗬕z���A�����̕s�������A�������\���Ɏ������ɓ��{�̐��Y����S�ʋ֗A�Ƃ����B
�@�������{�̑Ή��͍��ۊW�̒��ł͑傫���ӔC�����������̂Ƃ��킴������Ȃ��B
9/14�i�j���X�~�J���ɐ����@
�P:45�N���B�{�ǂ݁A������C�{�ǂ݂ȂǁB8:30�Ɠ��ɓ���A���n�@���A�V���`�F�b�N�Ɠ��́B�����A14:00���N�N���j�b�N�f�[�^����Y�ꂽ�B�����ɉ����A���Җʒk�����A15;00�A16:00���Җʒk�Ή��A�Ǐ��i�߂�B19:30:�A��[�H�A20:45�A�Q�B
�������C�m���o(11) �@���������߂����Ă̍��ۏ�@�����͌Ǘ����Ă���@
�@�������̊C�m�����������Ē����̓q�X�e���b�N�Ȕ������Ă���Ǝv�����A���̔w�i�ɂ́A�����������鍑�ې��_�`���Ŕ��̌����グ�����̂̎^����ꂸ�ɗ�������Ă������Ƃւ̏ł肪���낤�B
�i�P�j2021�N�A�������C�m�p���ɑ��Ē���������\�������ێЉ�ɖ���N�������Ƃ����������A���ێЉ�̎^���͓����Ȃ������B���̍ۊ؍������̗���ł������B
�i�Q�j���������͍�N�ɂ�2�x�ɂ킽��20���ڂɂ��킽�鎿��X�g����{���{�ɑ���A��C�ւ̐����C���o����������悤�ɔ����Ă����B
�i�R�j����ɁA�{�N7���ɒ��������{�����{���{�ɐ����C���o�͊C�m���o���u���ӏ����ւ̉e�������Ȃ��v�Ǝ咣�����B�TAEA�ɂ����l�̕����𑗂����B
�@�����C���o�͕��ː������g���`�E�����܂ޏ�����������������C���ɔr�o������@�B ���{���{���ňꎞ�������ꂽ���A��C���̕��ː������̃��j�^�����O���C�m��������ȂǂƂ��Č�����ꂽ�o�܂�����B
�i�S�j�����͑�C���̕��ː������̃��j�^�����O��@�͋Z�p�I�Ɋm������Ă���Ǝw�E���A�C�m���o�̌o������C���o��1/10����1�Ƃ�����{���̎��Z�����p���āu���{�̓������@�̑I�����R�X�g�Ɋ�Â��v�Ǝ咣�����B
�i�T�jIAEA�̃O���b�V�����ǒ��͊C�m���o�ȊO�̑I�����ɔے�I�Ȍ�����\�����Ă���B
�i�U�j�u���{�͍��ێЉ�̌��O�ɂ������艞���A�j�������̊C�m���o�̋��s����߂�ׂ����v�B �E�B�[����7�����ɊJ�������j�g�U�h�~���(NPT) �Č�����c�Ɍ�������1���ψ���ŁA�����O���Ȋ����͊C�m���o�v��ւ̌��O�����߂ĕ\�������B
�@�����A�����̎咣�ɑ��鍑�ێЉ�̎^���͍L�����Ă��Ȃ��B����8���̓��ψ���ŏ��������c��ɏオ�����ۂɂ͓��{�̌v��ɗ����������ӌ����e�����瑊�����A���d�ɔ����钆���̌Ǘ����ۗ������B
�i�V�j8��15���ɃI�����C���`���ŊJ�Â��ꂽ���Ċ؊O����k�B�u���{�̊C�m���o) �v��͈��S�ō��ۓI�Ȋ�ɍ��v���Ă���A�������Ă���v�B��k��̋L�҉�Ńv�����P���č��������͋��������B
�i8�j�����ɂƂ��āu�ő�̌�Z�v�������̂͊؍��̎x���������Ȃ��������ƁB
�@���{���{���C�m���o�����𐳎����肵��2021�N4���A���ؗ����͂�����Ĕ����B �����̕��哝�͍̂��ۊC�m�@�ٔ����ւ̒�i�����܂Ŏw�����Ă����B�Ƃ��낪22�N5���Ɋ؍��ś���������������Ɠ��؊W�͈�C�ɍD�]�B�؍��̎x���͓����Ȃ��Ȃ����B
�i9�j�����̏K��Ȃƃv�[�`���哝�̂�3���̎�]��k��ɏ����������������ŁA �C�m���o�v��ւ́u�[���Ȍ��O�v��\�������B
�i�P0�j���̗l�ɁA�������{�͓��{���{�̑Ή��ɕs����\���A���{�������̎���X�g�ɉ����ɊC�m���o�ɓ��ݐ�u���Ӎ��̋^����������Ȃ��܂܊j�������̔r�o�����s�����v�Ɣ���̂͊m���ł������B
�@���ꂪ�A�������̊C�m���o�ɑ��Ē������ˑR���{�̐��Y���̑S�ʋ֗A�[�u���Ƃ������Ƃ̔w�i�ł���B
�@�Ƃ͂����������{�������ɖ������߂�Ƃ͍l���ɂ����A�Ë��_�����������̂͗e�Ղł͂Ȃ����낤�B�֗A�������ɋy�Ԃ��Ƃ��o�傷��K�v������B
�@
9/13�i���j��������~�J
1:45�N���A���Ѓf�[�^�����B8:50�Ɠ��ɓ��惊�n�ɁB�V���`�F�b�N+���́B�����B14:30�J���t�@�ƏǗጟ���B���@���ґΉ��A�����ǂ݁A�V���`�F�b�N�ق��B19:15�A��A�[�H�A20:45�A�Q�B
�������C�m���o(10) �@�����̋֗A�Ή��ɂ͕ۏ��������肹��@
���������o�J�n��A�������{�́u��������ȍs�ׁv�ȂǂƓ��{�̕��o�ɔ��B�������\���Ɏ������ɓ��{�̐��Y����S�ʋ֗A�Ƃ����B
�@����͍��ۓI�Ȗf�Ղ̃��[���������\���ƌ����Ă����B
�@�������ݎY�݂̂Ȃ炸���{�̂��ׂĂ̊C�Y�����֗A�̑ΏۂƂȂ����B���̂��낤�B
�@�q�X�e���b�N�Ȕ����ł����Ȃ��B
�@�����̋��D�����{�̋ߊC�ő��Ƃ��Ă��邪�����͋ւ����Ă��Ȃ��B�{���Ɉ��S�Ȑ��Y�����A�Ƃ����l�����ł�������̑��Ƃ���u���Ă�����j�͖������Ă���B
�@����ɒ��������ł̉��H�����̔����֎~�ƂȂ����B
�@�����̓��{����̐��Y���̗A���ʂ�871���~�A���`��755���~�Ƌ���ł���A���̒��ł̓z�^�e���������߂�Ƃ����B���{�̐��Y���A�o�S�̂�4���ɑ�������B
�@�����̃z�^�e�͒����ʼn��H��������A���ĂɌ����ėA�o�����Ƃ����B������A���{�Y�z�^�e�̋֗A���u�͍����̉��H�Ǝ҂̌o�c����������B
�@��ʓI�ɖf�ՂŗA��������������Ƃ��͎����̎Y�Ƃ����ړI�����ŁA�����̎Y�Ƃɋ��������鐭��͋H�ł���B���̖ʂ�����A���͍���̋֗A���u�͒������Ȃ��̂ł͂Ȃ���??�Ɨ\�z���Ă���B
�@���{�̐��{�́A���Ńz�^�e������ėⓀ�ۑ�������A�����Ńz�^�e�����H���Ē��ڗA�o������@�C��������̊����Ȃǂ��l���Ă���悤�ł���BEU�Ȃǂ͗A�������������Ă��Ȃ��B���̂��߂ɕ��]��Q��800���~�Ƃ͕ʂ�200���~�̒lj������肵�Ă���B
�@�e��������{�̐��Y�Ƃɑ��ď\���Ɏx������K�v�����낤�B
�@���Y���̍�������𑣐i���A���Ă��܂ސV���Ȕ̘H�J��ŁA�����s��ւ̈ˑ������߂Ă����w�͂����߂���B
9/12�i�j���@���ʕa�@�O��
�@2:00�N���B��w�_���`�F�b�N���f�[�^�����B���Ў����f�[�^�����A5:00�S�~�o���B6:40�o�X���n�a�@�A7:00-8:15�a���Ή��A8:45-12:45���ʕa�@�O�����G�Ȃ��B�p�\�R���������ݓk�R�ȂǁB13:00���n�a�@�A�����B15:00�a���Ή��A�V���`�F�b�N�{���́B�f�[�^���������B�����A�Ǐ��B19:15�A��A20:45�A�Q�B
�������C�m���o(9) �@�����̋֗A�Ή��@�����͕挊���@����
�@���o�J�n��@�������{�́u���ۓI�Ȍ������v�������ɂ߂Ď�������ȍs�ׁv�Ȃǂƕ��o�ɔ��B�������\���Ɏ������ɓ��{�̐��Y����S�ʋ֗A�Ƃ����B
�@�����O���Ȃ́u�C�m���ƐH�i�̈��S�A�l�X�̌��N��f�Ŏ��v���߂Ƃ��u���{���{�͍��ێЉ�̋����^�O�Ɣ������Ă���v�ƌ����������B
�@����͘_�����������S�������_���ł���A����s���ɁA�f�Ղő����Ɉ��͂�������u�o�ϓI�Ј��v�ł���B�䂪���ł͂��˂Ă��珈�������o�̖��_�����ی��q�͋@��(IAEA)�Ƌ��͂��Ĉ��S���̕]����i�߂Ă����B
�@���̌��ʁA�Ȋw�I�_�������m�Ȃ̂ő����̗��������X�ɍL�����Ă����B
�@�����A�Ȋw�Ɋ�Â������c�ɒ����͉����Ă��Ȃ������B����͌��N����S���߂��鐳�m�ȏ���~���钆���̏���҂ɑ��Ă��A�����ȑԓx�Ƃ͂����Ȃ��B
�@���܂łɒ��������䍂�ȑΉ��ɂ��Ă������Ƃɂ͑����̑O�Ⴊ����B
�@3�N�O�ɂ͍��B�̎�COVID-19�̔������̒��������߂����Ƃɒ����������B���B�Y���C���Ȃǂɍ��ł������A����ʂ������������B
�@���{�ɑ��Ă���t�����̍��L�����߂����ă��A���^���̗A�o�����������Ă������Ƃ�����B
�@���������o�ϓI�Ј��͒������߂���o�ψ��ۖʂ̃��X�N�̈�Ƃ��āA��̂f7�T�~�b�g�̋c��ɂ��Ȃ����B
�@�����O���Ȃ́u���{���{�͏������C�m���o�Ɋւ��č��ێЉ�̋����^�O�Ɣ������Ă���v�Ɣ��邪�A����͐��E�̗���̒��ŁA�܂��Ȋw�I�Ɍ��đS�R�������Ȃ��_���ł���B
�@���͍���̋֗A�[�u�́A�������{�̐����I���f�����̎���ɂȂ��Ă��q�ϓI�����łȂ��A����_���D�悵�Ă��邱�Ƃ�S���E�Ɏ��猖�`�����A�Ƒ����Ă���B
�@���ۓI�Ɏ����̐M�p�\�z�Ɋւ��āA�܂������I�ɂ͎����̐��{�̂�����ɑ��āA�����͎����ŕ挊���@�����A�Ǝv���B
�@�m���ɁA���̂��N���������R���̏��������C�m���o����̂́A�O��̂Ȃ����E���̎��݂ł���A�e���̐��{�����O��������͓̂��R�̂��Ƃł���B�������Ȃ���A�ʏ�^�]����Ă���S���E�̌����ł̓g���`�E�����܂ޏ���������O�̂悤�ɊC�m�ɓ������Ă���B�����̌������R��ŁA�N�Ԃ̓����ʂ͉䂪���̌�������̓����ʂ����͂邩�ɑ����B
�@���o�������̂��N���������Ƃ��āA���i�ȊĎ��Ə��J����s�����d�ӂ��̂͂����܂ł��Ȃ��B
9/11�i��) �����@���N�N���j�b�N�h�b�N�@�@
�@2:00�N���A�����`�F�b�N�B�f�[�^�����A6:40�o�X���n�a�@�B7:00�|�W:00�a���Ή��A�V���`�F�b�N�A9:00-11:00���N�N���j�b�N�h�b�N15�l+���ʔ���12�l���B11:15�a�@�A�����ق��A13:30�V���`�F�b�N+���́A�a���Ή��A�Ǐ����A19:15�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B
�������C�m���o(8) �@���������o�ɂ������ē��d�̉e�͂��܂�ɂ�����
�@�������̕��o�̎�̂͐��{�Ɠ��d�ł��邪�A�������̕��o�Ɋւ��Ă͐��{���O�ʂɗ����Ă��邪�A���d�̊֗^�ւ̈�ۂ͋ɂ߂Ĕ����B
�@��̓I�ȕ��o�p�̊C��g���l���Ȃǂ̍H���ɂ��Ẵn�[�h�ʁA���S�Ǘ��̐��Ȃǂ̃\�t�g�ʂł͐ӔC���ʂ����Ă���̂ł��낤���A���o�Ɋւ���S�̑��̊֗^�͐��{��̂ɂ���l�Ɍ����A���d�̎p�͂Ȃ��Ȃ������Ă��Ȃ��B
�@���d�͐��{�ƂƂ������������̑S�ӔC��Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ��Ă���B���ɁA���O�ւ̐����ƑΘb��ʂ��A���S�m�ۂ╗�]��Q��ɐӔC��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���d�̏�����В��͕��o����܂ŋ��ƊW�҂ɉ���Ƃ����A7���̋L�҉�ł́A�u���Ǝґ�����v�]������Ή���A�����������玝����������̂ł͂Ȃ��v�Ɛ������Ă���B�����҈ӎ��̌��@�ɋ������肾�B����Ȃ��Ƃł͐M�����͐��܂�Ȃ��B
�@�������Ɋւ��Ă͌��_�Ɠ������肫�̎菇���s�M�������߂��B
�@���������A�Ɛ��{�Ɠ��d���͊��S�ɔ��̂ɂ��ꂽ�B
�@���]��Q�����O���鋙�Ǝ҂ɑ��A�ݓc�́u����A���\�N�̒����ɂ킽�낤�Ƃ��A�S�ӔC�������đΉ�����v�ƐV���������ɂ����B��̖��ʂ�����Ȃ������̂ɁA�Ǝv���B���̖́A�K�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���d�́A���̌����ł��s�ˎ����J��Ԃ��Ă���B
�@30�N�]�̒����ɋy�ԏ������̕��o�ɍۂ��A�ϋɓI�ȏ����J�Ɛ�����s�����邩�B
�@�z��O�̎��Ԃ��N�����Ƃ��ɏ\���ȑΏ����ł��邩�B��̓I�ɓ����C�������J���Ȃ���ΐM���͓����Ȃ����Ƃ����o���ׂ����B
�@������ꌴ���ɂ́A���������܂ߏd����肪�R�ς���B
------------------------------------------------------------------
�@?�n�����j�R�������o�����ʂ��͍��������Ă��Ȃ��B
�@?30�N�]�̒����ɓn�艘�����E�������^���N�̈��S�͊m�ۂ����̂��A
�@?���������F������̒n�k�⎩�R�ЊQ�ł���ɉ��鋰�������B
�@?���������ɂ��鏜���y��2045�N�܂łɌ��O�ōŏI��������Ƃ���������Ă��邪�A�������͂��ߋ�̓I���͕s���B
�@?�ȂǂȂǁB
------------------------------------------------------------------
�@���������o�̌���ɂ�����A���{�́u�p�F�ƕ����v��i�߂邱�Ƃ��`�����ɂ����B
�@���̏ꂵ�̂��́u�v������ɏd�˂�悤�Ȃ��Ƃ́A���͂⋖����Ȃ��B
�@���͕����������́A���d�̎p���A���{�̕��j�ɂ͏�ɊS�������Ă���B
�@���������o�Ɋւ��Ă̓��d���ʂ����Ă����R�����̂��c�O�ł���B
9/10�i���j�����@�I����d���@�Ƌ��ؕԔ[3�N�o��
3:00�N���A��ꂪ�c���Ă��荡�ЂƂC�͂��N���Ȃ��B�l�R��ɂ��炭�O�_�O�_�Ƃ������B8:00���̑�����11��ځB�����̋߂��܂ŁB�����͋ɂ߂Ĉ����B���w�A12:00NHK�j���[�X�A�̂ǎ����������A14:00����R�C�ɋ��a�A���n�a�@�B���ґΉ��A17:�T�O���Ҏ����B19:00�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B
�������C�m���o(7) �@���킳�ꂽ���t�V�с@��a�̋��ƊW�� vs �y�����{�̉���(2)
�@���ۂɂ͑S���ƘA�͈�т��ĕ��o�ɔ����Ă���B����ɂ�������炸�A���{���C�m���o�����s���{�����B�͔��̂ɂ��ꂽ�B
�@������Ɨ����߂��čl���Ă݂�E�E�E�A
�@���������o�̔��f�͑S���A���^���������ł����̂�?? �Ƃ������ɂ��Ԃ�������B
�@�C�͉ʂ����ċ��Ǝ҂̂��̂Ȃ̂�??
�@���Ǝ҂̗�����������Ώ���������o���Ă����̂��H
�@�����s�݂̂���肪�d�˂�ꂽ�B
�@������A���́A���{�̂��̈�A�̂��������w�������ɂ��̐�����Ă݂Ă͂ǂ����낤���A�Ǝv���B�u���̉��l�v���w�E�ł��鏬�w���́u�͔j��ꂽ�v�A�Ɣ��f���邾�낤�B
�@���͒��ڊ֘A�������Ȃ����ӔC�ȗ���ł��邪�����̈�l�Ƃ��Ď��̗l�ɂ������낤�B
�@�u���{�A���d�Ƃ̊ԂɌ��킳�ꂽ�͊��S�ɔ��̂ɂ��ꂽ�B���{�̏ꓖ����I�����A���s���s�͋����!!�E�E�E�v�ƁB
�@�����ł��邪�A���͋��Ǝ҂Ɛ��{�̊Ԃł͐��ʉ��Ō��������ăM���M���̐܂荇���������t����肠�����̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���Ă���B���҂������Ȃ��ʒ��F�̌��t�̂悤�ȋC������B�⏞��������ł���̂ł́H
�@�������A�Ȃ�ł킪���͂Ȃ�ł��ʒ��F�́A�ۂ������߂���@���Ƃ�̂��A�s�v�c�łȂ�Ȃ��B
�@���̍ł�����͍̂L���E����̕��a�����̖��̂ł���B���Ȃ�u��l���I�����ʎE�C���i�v�ɖY��Ȃ����߂̌����v�Ƃł����O�����邾�낤�B
�@�������ɂ��Ă��A���r���[�ɂ����Ɂu���{�̓E�\�������B���{���x���ꂽ!!!�v�Œ��߂�����B�����I�����͂Ȃ������̂����琭���I���f��҂����Ȃ���������A�Ȃ�ƌ����Ă����ʂ͓������Ƃł������B
�@�Ȋw�I�ɂ͏��������o�͊��ɂ��A�l�̌��N�ɂ����͂Ȃ����낤�B������A���m�ɐ��{�̂�����ӂ߂�ׂ��������B���͂����v���B
9/9�i�y�j�������H�̂������@����35���@�]���^����r��R���T�[�g�@
1:30�N���B�����~�J�B�~�ώ��������B�T�˂����̔@���B8:20�Ɠ��͏I���]���^�ɁB12:00NHK�j���[�X�A�f�[�^�����ȂǁB�����A14:00������10��ځA��ɍL��A�_���A���ӁA�U���B15:30�o�X�A�a�@�A���X�A19:00�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B
�������C�m���o(6) �@���킳�ꂽ���t�V�с@��a�̋��ƊW�� vs �y�����{�̉���
�@���{�́A�Ȋw�I�ɂ͈��S�ł��邱�Ƃ�n���Ɂu���J�ɐ����v���Ĕ��f�����A�Ƌ�������B�n���ł͂��̂悤�ɗ������Ă��Ȃ��B�������A���������łȂ��A�{��A���e���̋��A�������͕s�\���Ŕ���\�����Ă���B
�@���{�Ⓦ���d�͂́A���o�ŕ��]��Q����������A�K�ɔ�������Ɛ�������B�������A�����B�͋��K�I�ۏႾ���ł͔[���ł��Ȃ��A�Ɛ��{�̔������j�ɕs�M���点��B���d�̌������̂̕⏞�ɂ��[���ł��Ă��Ȃ��B
�@���{�́u���J�Ȑ����v�Ƃ͓��������̌J��Ԃ��̂��Ƃ��w���B
�@���āA�H�c�s�̏Z��n�ߗׂɃ~�T�C���}���V�X�e���u�C�[�W�X�A�V���A�v�ݒu���v�悪�������B2018�N����20�N�ɂ����Ę_�c���d�˂�ꂽ���A�Z���A���A�s�ւ̐�����ł͉��x�������Ă��������e�̌J��Ԃ��ɏI�n���A����ɑ���ԓ��������p�^�[���A�����V�����Ȃ��B�����ق����h���Ȃ����B
�@2020�N6���A���{�͓ˑR���̌v���P���B���̓P��̗��R�̐������s�\���ŁA���͈��R�Ƃ����B
�@�������Ɋւ��Đ��{�Ɠ��d��2015�N�A�u�W�҂̗����Ȃ��ɂ͂����Ȃ鏈�������Ȃ��v�ƒn�����ƊW�҂Ɩ����B
�@���̕��������킳�ꂽ�����̌������ۂǂ̗l�ȏɂ������̂����͂킩��Ȃ��B�������A���̖͎����ł��낤�B�������A���S�ɔ��̂ɂ���Ă���B�����̉����Ƃ̐��g���͏��X�ɑ����Ă��邪�A�������̑O��2���قǂɂƂǂ܂�B�r��ł̕��o�ŁA���ƊW�҂̕��]��Q�ւ̕s���͑傫�����낤�B
�@�ݓc�͑S���A�̍�{��Ɩʉ�A�������C�m���o�ɗ��������߂��B
�@�S���A��́u�����Ȃ鏈�����s��Ȃ��A�Ƃ����͉ʂ�����Ă����Ȃ����A�j���Ă����Ȃ��B�C�m���o�ɂ͂����܂ł����ł���v�Ƃ����A�Ӗ��̂킩�����t�Ŗ������[�������l�ł���B
�@���{�W�҂͂��̌��t�āu���Ǝ҂̗����͓���ꂽ!!!�v�Ɛ^�ӂ�����ɔP���Ȃ��ĉ��߂����X�Ƃ��Čv������艟�������B
�@���͋��Ǝ҂ł��Ȃ��A�������l�ł��Ȃ��B�������A�����̈�l�Ƃ��ē���[������o�߂ł���B
9/8�i���j�����@��Ȓ��ʊO���@�@
�@2:00�N���A�V����������A�{�ǂ݁B���ЁB5:10�R�S�~��o�B�L�E���A�i�X�̎��n�A7:40Taxi�H�c�w�����A8:11���܂��A���HTaxi�B8:50��Ȓ��ʕa�@�A���������X�^�b�t���@�ACOVID-19�̉e���͐r��Ȃ��̂ł������A�Ƃ����B15:30���艮�o�R�B�Ï��X�Ŏ���10���w���A���n�a�@�A�a���Ή��B�[����r�I�傫�Ȓn�k�B19:15�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B
�������C�m���o(5) �@�Ȃ�ł��摗��̉䂪���̐��{
�@��ʘ_�Ƃ��āA�䂪���̐��{�͌��Ď�����摗��ɂ���X��������B�䂪���ɂ͑����Ɏ��������ׂ��ۑ肪�R�ς݂̂܂ܑ摗�肳��Ă����B
�@���̔w�i�ɂ͒����̈�}�ƍق̐����`�Ԃ��������悤�B�ߖڂ��Ȃ�����A�Y���Y���Ɠ������Ď��������������B
�@�扄���ɂ��Ă������Ď����������Ƃ�����Έȉ����������邪�A����������ʓI�ɉ䂪���ɂƂ��Ă͊�@�I��ԂɂȂ肤����̂���ł���B
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
�@�����q������l�����A���łɎЉ�e���ɐl��s���̘c�݁B
�@���o�ύČ��A����ɑ��傳���Ă���B
�@���V�������Ǒ�A����Ɗ�@�Ǘ������������������B
�@���H���������̌���A�܂����ʂȂ��B
�@�����ē����A���S�ۏ�A�h�q���B
�@���������̏������܂ޒ����̃G�l���M�[����
�@���c���T�͉����A
�@���ȂǂȂǁB
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
�@�������̏������j�͊C�m�p�����x�X�g�A�Ƃ��Ȃ��牽�̖�10�N���ŏI���肹�����邸��ƕ��u���A98���܂Ŗ��^���ɂȂ�܂Ń^���N�𑝂₵�Ă����̂��H�H
�@����܂ŁA���q�F�����ւ̒n�����E�J���̗��������炷���߁A�n�����̂��ݏグ�Ⓚ�y�Ǔ��A�d�w�I�Ȏ�g�݂����{�������ʁA�����������ʂ́A���O�̖�540m3�^���i2014�N�j����A��140��3�^���i2020�N���ρj�܂Ō������Ă��邪�A���������Ă��邱�Ƃ͊m���B���t�ɂȂ�{�N�A����ƊC�ɕ��o����v��ƂȂ����B
�@
����ȏ�C�m���o��҂ĂȂ����R
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
�@?�����p�^���N�̒u���ꂪ���E�ɒB������B
�@?�p�F��Ƃ̂��߂Ƀ^���N�ݒu�ꏊ����K�v������B
�@?�^���N�̕��H���n�܂��Ă���B
�@?�V���Ȓn�k�̍ۂȂǂŃ^���N�̈��S�����m�ۂł��Ȃ��B
�@?�ȂǂȂ�
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
�@�S�����Ƌ����g���A����͈�т��ĕ��o�ɔ����Ă���B����ɂ�������炸�A���{��21�N�ɊC�m���o�����肵���B�����܂Ő؉H�l�܂�A2015�N�A���{�Ɠ��d�́u�W�҂̗����Ȃ��ɂ͂����Ȃ鏈�������Ȃ��v�ƒn�����ƊW�҂Ɩ����A���ƂȂǔ��̂ɂ���������Ȃ��B
�@���Ă̕��o�J�n���n���̔[���̏�Ƃ͌�����B
9/7(�j�����g�C���ɂށ@�@�@
1:30�N���B���������A�����ȂǁA���w�B8:50�Ɠ��ɓ��惊�n�ɁB�V���`�F�b�N�{���́A�a���Ɩ��A���@���ґΉ��B��r�I���������Ă���B���������A�Ɠ��]���^�A18:30�o�X�A��A�o�X�⑤�̃g���J�c���X�X�ɃV���b�N�B�[�H�A20:50�A�Q�B
�������C�m���o(4) �@�䂪���̃g���`�E���r�o�ʂ͐��E�̒��ł����Ȃ���
�@�����͒�������Ԃ̊j�F�S����ɐ��ŗ�₵�ăR���g���[�����Ă��邩��K�����˔\��тт���p������������B
�@���E���̌����ł͂������������Ƃ��ĊC�m��͐�ɕ����A�ꕔ�͋�C���ɕ�������Ă���B
�@�g���`�E���͐��E�̉^�]���̌�����ď����H�ꂩ����p������Ă���B����������N�Ԑ����Ȃ�����10���x�N�����͈̔͂Ƃ����B
(�o�Y�Ȃ̎���������p)
�@�g���`�E���͓V�R �̕��ː������̈��� �V�R�g���`�E���́A��ɋ�͒��S������鍂�G�l���M�[�F�����ɂ���āA��C���ŏ펞��������A�J�ƂȂ��č~�蒍���A���R�E�̐��̒��ɑ��݂���B
�@���R���p���̒��ɂ��܂܂�A���ǂ��͒m�炸�m�炸�ɐێ悵�Ă���B
�@���{�ɂ�����~�����̃g���`�E���͔N�Ԗ�223���x�N�����B ���{�S���̌����ɂ��C�m�ւ̃g���`�E���r�o��(��380���x�N����/�N)�́A�~�����Ɋ܂� ���g���`�E����(��223���x�N����/�N)�̖�1.7�{�ɑ�������B
�@�����̃^���N���̃g���`�E���̑��ʂ�900���x�N�����ŁA���̕��o���6���x�N����/L��1�^40�܂ŊC���Ŕ��߂ĔN��22���x�N�����p������\�肾����A�J�n�㉽10�N�������邱�ƂɂȂ�B
�@���������āA����C�m�p�������܂�������Ƃ����Ē����ɉ���������ł͂Ȃ��A������������1������100�g�����܂��Ă��邩��^���N���Ȃ��Ȃ邱�Ƃ͂Ȃ��B
�@
�@����̏������C�m���o�ɍR�c���Ăł��낤�A�������{�����{�Y���Y���̗A����S�ʒ�~�����B�������A������ꌴ��������o�����N�Ԃ̃g���`�E���ʂ́A�����̐`�R����������o�����g���`�E���ʂ̖�1/10�ł����Ȃ��B
�@���������āA�����̐��Y���̗A���֎~�[�u�́u�Ȋw�I�����Ɋ�Â����̂ł͂Ȃ��A�����I�S�������v�B�w�i�ɉ�������̂��������Ƃ���B
(�Q�l)���̏����������̊�{�I���j�͈ȉ��̒ʂ�ŁA�ɂ߂ĐT�d�Ȃ��̂ł���B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
�@���p���͊C�m���o�Ƃ���B
�@�����̊�ȉ��ɔ��߂Ĕp���B
�@���g���`�E���̔N�Ԕr�o�ʂ�22���׃N�����ȓ��Ƃ���B
�@�����ʂ���n�߃��j�^�����O�ŊĎ�����B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
�@�{�N�̔r�o�ʂ͂���ɐT�d�ŁA5���׃N�������x�B
9/6�i���j�����~�J�ߑO�܂�@����u�ߊ����N�����Ö�v�@COVID-19�u����@
1:20�N���B��Ƃ��č��w�A�r�������B�^���f�[�^�����A�~�J�̂��߂ɑ�����ł����ߑO����o�A�V���`�F�b�N�A���́B12:30����u�ߊ����N�����Ö�v�A14:30-15:30�����J���t�@+�Ǘጟ����B�V���`�F�b�N���͂ق��B18:30�o�X�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B
�������C�m���o(3) �@������3�����@�@�C�m�����A�n�������A���o
�@�����ꖞ�t�ɂȂ邱�Ƃ�10�N�߂����O����킩���Ă������ƁB
�@2013�N���珈���������̌�����i�߂Ă����B
�@�������̏������@�͎�Ɉȉ��̎O���@������B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
�@���C�m�����A
�@����C�������A
�@���n�w�����A�Ȃ�
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
�@���̒��ł͐��Ƃ�6�N�Ԃ̌������d�ˁA���̌��ʁA�Z�p�I�ɂ��\�ŁA��p���ł������ł���C�m�������Ó���2019�N�ɔ��f�����B������āA���{��2021�N4��13���ɊC�m�����𐳎��Ɍ��肵���B
�@���́A��������10�N�Ԃ��������̏������j�����肹�����u�����̂�!!!
�@�n�w�����͏ꏊ�̑I�肪�ɂ߂č���ʼn䂪���ł͂قƂ�Ǖs�\�B
�@��C�������͔�p������ŁA���j�^�����O������A���ۓI�ɂ���葽���̍����甽��������\��������B
�@�C�m�����͐��E���̌����ł��łɍs���Ă�����@�ł���B
�@�v����ɍŏ�����I�����͌����Ă����B
�@���Ƃ͊C�m���������܂�6�N���Ԃ������A���{�͂����2�N�ԕ��u���č��N�̎��{�ɓ��ݐ������ƂɂȂ�B
�@���̊ԁA���ƁA���{�͉�������Ă����̂�?? �^���N�����t�ɂȂ�̂�҂��Ă����Ƃ����v���Ȃ��B
�@�������@���낭�Ɍ����������Ɍ��_�����������ɂ��A�^���N��98�������t�ɂȂ�A����ȏ�͑҂ĂȂ��؉H�l�܂����ɒǂ����܂�Ă�����{�����f�����B���̂��߂ɓ����ɗv������Ԃ͑啝�ɉ������A30�N�]���v���邱�ƂƂȂ����B
�@���͊C�m�������n�܂��ăz�b�Ƃ��Ă���̂����A���̐����Ƃ����̎��Ԋ��o���댯�Ǝv���B
�@���{�͍ЊQ�卑�ł���B�^���N1,000���ї���������Ԃł��������A���̊Ԃ�10�N�ԑ傫�ȍЊQ�ȂǂɌ������Ȃ��Ă悩�����B�n�k�����x�������A�V�����܂Ŕ�Q�����B���͂��̓x�ɒ����^���N�����Ȃ���������S�z���Ă����B
�@����30�N�ԁA�p�����v��ʂ�ɐi�߂���Ζ��͏��Ȃ����A���̊ԂɍЊQ�Ɍ��܂�A�v��ʂ�ɔp���ł��Ȃ��Ȃ�Α�ςł���B2050�N�I���\��̔p�F�v�������ɉ����ƂȂ�B
�@���{�C�a�E�瓇�C�a�n�k�́A��C�g���t�n�k�قǒm���Ă��Ȃ��̂��c�O�����A�����{��k�ЂƓ����̃}�O�j�`���[�h (M) 9�����z�肳��Ă���B�k�C�����k����7�����Ŏ���1��9��l�A �����S��2�����Ƃ����Ռ��I�Ȑ����𐭕{�����\�����B
�@���ꂪ�������{���甭�\���ꂽ���Ƃ������ł���B
�@���̒n�k�ɍۂ��A���������֘A�̊�@�Ǘ��͂ǂ̂悤�ɑ����Ă���̂�??�@�m�肽�����̂ł���B
�@���������v��ʂ�ɁA���S�ɏ�������邱�Ƃ�]�ނ����Ȃ��B
�@�Ȋw�̒m���ɉ����A�ЊQ�������Ȃ��悤�F�邵���Ȃ��̂��B
9/5�i�j�����@ ���ʕa�@�O���@�@
1:30�N���A�Q�ꂵ���Ȃ��A�ǖ��ł����B��w�����E�V���ǂ݂ق��B�k�R�L�ځB�R�S�~�p�������̂݁A��o�s�v�B6:40�o�X�A7:00�a���Ɩ�+�����A8:45-12:40�O���B���ґ����Ȃ���X�Θb�ł����B12:50���n�a�@�B�����B���@���ґΉ��B�����A�V���X�N���b�v+���́A19:10�A��E�[�H�A20:30�A�Q�B
�������C�m���o(2) �@�������ɂ̓g���`�E�����c���Ă���@�����g���`�E����p���Ă����@
�������̒�`�͊ȒP�ɕ�����A�ȉ���3�킪����B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
�@���������@�j�R���ɐG�ꂽ��p���ɒn�����ȂǍ����������̂ō��Z�x�̕��ː��������܂ށB
�@�������ς݉������@���������e�폜���ݔ�(ALPS)�ŏ���������ɒ����^���N�ɗ��߂��Ă���B���o���1���{�ȏ�̕��ː��������܂�������B
�@���������@�����ς݉��������Ă�ALPS�ŏ������A�Z�V�E���A�X�g�����`�E���Ȃǂ������������̂Ńg���`�E���͏�������Ă��Ȃ��B�C�m�p���̑ΏۂƂȂ�B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
�@���ː������ō��x�ɉ������ꂽ���͉������ƌĂ��B
�@�������͒n�����������ɓ���O�ɑg�ݏグ����A���y�Ǔ��̃o���A���݂Ȃǂ̑Ή��ł���5�N��1�^3�Ɍ����������A���Ȃ�1������90�[100t���܂葱���A2023�N�ɂ͖��t�ƂȂ�B
�@���̉���������唼�̕��ː���������菜���������������B�g���`�E���͕��˔\�����ʂ����A�������I�Ɏ��͂̐��Ƌ�ʂł��Ȃ��B�����珜���͂ł��Ȃ��B
�@�g���`�E������o����ː��͎キ���ꖇ�ŎՂ鎖���ł���B��������12.3�N�B���R�E�ł�����Ă���B
�@�g���`�E���͓V�R �̕��ː������̈��ł���B �V�R�g���`�E���́A��ɋ�͒��S������鍂�G�l���M�[�F�����ɂ���āA��C���ŏ펞���������B�g���`�E���͐����q���\�����鐅�f�Ƃ��đ��݂�����̂������A��C���̐����C�A�J���A�C���A�������ɂ����ʂȂ���܂܂��B
�@�g���`�E���̃q�g�̐g�̂ɋy�ڂ��e���́A���̕��o���6���x�N����/L�̐���2L�A70�N�Ԉ��ݑ����Ă��픚�ʂ͍��ۊ�ɒB���Ȃ��Ƃ����قǎア�B�̓��ւ̒~�ϐ����Ȃ��B������قڐS�z�Ȃ��A�ƌ����Ă����B
�@�������Ă͍זE�|�{�̎�����2�N�Ԃɓn��T�����x�g���`�E����p���Ă����B�������A���ː������戵�K��ɉ����Č����Ɉ����Ă͂������A�c�t�Ɏc�����g���`�E���͈��̔Z�x�ɔ��߂ď��ɗ����Ă����B�����ŕ��˔\�̑����ɉ����ɔp�����ꂽ�A�Ǝv����B�����ւ̕��˔\��Q�͐S�z�����Ă��Ȃ������B
�@����̏������C�m�p���͉Ȋw�I�������猾���A�������������ߏ蔽�����Ă���Ǝv���B�������A�l�Ԃ̊���͉Ȋw�I�������炾���ł͊����Ȃ��B�g�C���̎�̐��́u���ōς݁@���p�v�Ƃ����Ă��C���ǂ����߂�̂��낤��??�@�����Ȏ��т��������Ȋw�҂̑����̂͐_�̑��݂�M���Ă���Ƃ������B����͉��̂��낤��??
�@���ꂪ�l�Ԃ̐S���̕��G�ȂƂ���ł�����B
9/4�i���j�����E�܂�@���N�N���j�b�N�h�b�N�@
�@2:00�N���B���ށA�^��f�[�^�����B6:40�o�X�A���ʃ��n�B7:00�|8:00�a���Ɩ��A9:00-11:00���N�N���j�b�N�h�b�N12�l+���ʔ���15�l���B11:30���n�a�@�ɂď��߂Ă̐E�����f�A�����ق��A�V�����́A���@���ґΉ��B�Ɠ��x�ɉԓ͂��ɁA19:45�A��[�H�A21:00�A�Q�B5F�w���L�����A�A�b�v���C�ɂĎb���s�݂Ƃ����B
�������C�m���o(1) �@�I�����̂Ȃ��ɒǂ��l�߂Ă���̌��f�@���{�͂��邢
�@������ꌴ���ł͎��̒����2011�N4���A���Z�x�̉��������C�ɗ��o���Ă���̂����o���n����C�O����Ҕ��������B
�@���d�͂�������Ə������ĕۊǂ���Ƃ��A�^���N��1000��p�ӂ�137���g�������ł���܂łɂ������A���݁A���ꂪ98�����t��Ԃł���B�܂��^���N�̈ꕔ�͘V�������Ĉ��S���ɂ���肪�����Ă���B���Ȃ����100t����������B
�@�p�F�̂��߂ɂ��L��Ȗʐς̊m�ۂ��K�v�ł���A�^���N���ǂ̂܂܂ɂ��Ēu���Ȃ��Ƃ�������������Ă����B
�@���ꂪ���]�Ȑ܂��o�Ȃ���A�u����ȏ�҂ĂȂ��v�Ƃ̘_����8��24������C�m�ɓ�������n�߂����R�ł���B
�@����10�N�ԁA������p�����K�v�ł���A���Ƃ�5�N�Ԃɂ킽�錟�����ʁu�C�m�p�����x�X�g�v�Ɩڂ���Ă����B
�@���̌�A���܂Ŏ��ӂ̑�A���Ɍ����A�ւ̐����̓��f�B�A�ɂ���ĕ��邱�Ƃ͂Ȃ��������A����قǐϋɓI�ɐi�߂Ă��Ȃ������炵���B
�@�����āA���ԓI�ɂ������I�ɂ��u����ȏ�҂ĂȂ��v�Ƃ����؉H�l�܂����ɂȂ������̎��ɁA�����I���f���Ȃ��ꂽ�Ƃ������ƁB
�@���������̑����͐����s���Ƃ̊����������Ԃł̕��o�ł��邪�A���̑I���������Ԃ��Ȃ��ȏ��ނȂ��Ƃ������߃��[�h�̂悤�ł���B
�@�ŏ�����^���N���̏������͗��ߎn�߂����_���珫���I�ɂ͂Ȃ�炩�̏������K�v�Ƃ킩���Ă������A�N��������Ȃ������B���{������������͉������Ă����̂��B����͐��������ŕ����ׂ��ӔC�ł���B
�@(�Q�l)���̌�̌o�߂ƍ���̗\��
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
2011�N3���@�����{��k�Ђ������A������1����1~3���@�ŘF�S�n�Z����
2011�N4���@���Z�x�̉��������C�ɗ��o���Ă�
�@�@�@��̂����o�B
2013�N3���@�g���`�E���ȊO��62��ނ̕��ː������������ł�����u �@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�uALPS�v���ғ�
2014�N6���@�����܂��̓y��𓀌����ĉ�����������h�� �u���y�ǁv�̒��H
2015�N�@�@ �W�҂̗����Ȃ��ɕ��o���Ȃ���
�@�@�@�����A�ƕ������킷
2020�N2���@���{�̗L���҉�c���C�m���o���u���m���v �Ƃ̕�
2020�N2��-10���@�����Ɠ����ňӌ����f�����
�@�@�@7��J��
2021�N4���@�������̊C�m���o�𐭕{������
2022�N3���@�����y��̒��Ԓ����{�݂ւ̔������T�ˊ���
2023�N8��24���@�������̊C�m���o�J�n
�@�@�@��30�N��������\��
2023�N�㔼�@2���@�̔R���f�u���̎����I���o���ɒ���̗\��
2024�|26�N�@2���@�̎g�p�ςݔR�����o���J�n�̗\��
2031�N�@�@1~6���@�Ŏg�p�ςݔR�����o�������̗\��
2045�N�@�@���������̏����y��̌��O���o�����̗\��
2051�N�ȍ~�@�p�F�����̗\��
9/�R�i���j�����@�����@
�@2:00�N���A�˂��邵���͂��y���B�{�ǂ݁A�摜�A�^���f�[�^�����ق������̔@���B�Ǐ��i�߂�B����̍~�J�Œ��̎U���s�v�B�ߑO�͏��ւ��Ă�^��f�[�^�����AN�������������ӏ܁B���߁ANHK�j���[�X�A�̂ǎ����ȂǁB14:00���쑝���ŋ��a�s�A��H�����R�C�A�n�g�ɋ��a�v�X�B14:30���M���҂���a���Ή�1���ԁA�V���f�[�^�������B19:00�A��[�H�B20:00�A�Q�B
���N�̏H�c�͏���(11)�@����140�N�Ԃ�ɋL�^�h��ւ��@���j�I�Ă�
�@���N8���̏H�c�s�̕��ϋC����30.0���ƂȂ�A�C�ے��̓��v������1882�N�ȍ~��140�N�ԂŁA1�J���̕��ϋC���Ƃ��čō��������B
�@8���͍ō��C����ҏ������Ȃǂ��ϑ��j��1�ʂ��X�V�B�u���j�I�v�ȉĂɂȂ����B
�@�H�c�����ɂ͋C�ے��̊ϑ�����37�n�_����A���̂���26�n�_�ŋC���𑪂��Ă���B�唼��1976�N�ȍ~�ɓ��v�����n�߂��A���_�X�n�_�B
�@���̊�140�N�]��̌����ϋC�����r�����Ƃ���A���N8���͂���܂ōō�������1999�N8����1985�N8����27.3�x��2.7�x������A�ߋ��ō��ƂȂ����B
�@�H�c�s�ł�8��23���ɍō��C����38.5�x�ɒB���A�ϑ��j��1�ʂ��X�V�B�ō�35�x�ȏ�̖ҏ�����13���ɏ��A����܂ōő���1999�N��9�������B
�@����18���Ԃ��ō�30�x�ȏ�̐^�ē��ŁA��������������ڂȂ��������B�ō��C���̌����ς͖ҏ����̊�ɍ��v����35.0�x�������B
�@�����������₷�������̍ō��C�������łȂ��A�Œ�C�������������B
�@�Œ�25�x�ȏ�ŐQ�ꂵ�������̔M�і��25���ɏ��A�ߋ��ő����X�V�B���̌���25�n�_�Ɣ�ׁA23�N8���̔M�і�̓����͏H�c�s���ł����������B�Œ�C���̌����ς�26.2�x�ɏ�����B
�@�H�c�n���C�ۑ�̒S���҂�8���̖ҏ��ɂ��āu1����ʂ��Ēg������C�����荞�ޏ�Ԃ��A�ق�1�J���ɂ킽�葱�����v�B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
�@�t�B���s�����ӂ̊C�����������Ȃ�A�ϗ��_�Ȃǂ̔������Η����������������A�����m���C�������܂����B
�A�ΐ����̎֍s�ɂ��쓌����̒g������C�̗����B
�B�R�z�����Ċ����������������ރt�F�[�����ہB
�C�v���������I�ɍ�p�����B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
�@�܂��A�C�ے��ُ̈�C�ە��͌�����́A�n�����g����k���{�t�߂̊C�����̍��������Ă̖ҏ��ɉe�������Ƃ̌����������Ă���B
�@�C�ے��́A7�����S���̕��ϋC���͉ߋ��ō����������A�H�c�s�ł͒��{�̑�J�̉e��������A���9�ԖڂɂƂǂ܂����B
�@�������A8���ɓ����Ă���C���̏㏸�������ɂȂ�A�ߋ��ō��y�[�X�Ő��ځB���ɗ�N�C����������n�߂�20���ȍ~���������ɂ܂��A�ҏ�����M�і邪�����܂ő������B
�@���ʓI��8���̖ҏ����đS�̂������グ�A�H�c�s��6�`8���̕��ϋC����25.4�x�ʼnߋ��ō��ƂȂ����B
9/2�i�y�j�锼����~�J�E�I���@���N�`���ڎ�e�����x�̌��ӊ��@
2:40�N���B�锼����~�J�����B���J�ł���B��̍~�J��8��13���Ȃ����ł������B�N�������ӊ����x�A���炭�̓��N�`���̂��߂Ƃ͋C�Â����B���r�̋ؓ��ɂł���ƋC�Â��B�ꉞ�N�������̂̃O�_�O�_�߂����ēx�珰�B���H�A���H�͎�炸�Ƀx�b�g�ʼn߂����B10:00����a�����獂�M���҂ɂ��Ă̘A������B�����Ȃ�x���o����̂ł��邪�t�@�C�g�ł��x�ށB�d�b�Ŏw���̂݁B15:00���ɑ̒��A�H�~�߂�y�H�Ƃ�B�[������ƌ��C���o�ď��ւ̃p�\�R���̐����B�^���f�[�^�����B19:00�[�H�B20:30�A�Q�B
COVID-19���N�`���ڎ�̘b��2023(2) ��͂蕛�����̌��ӊ�
�@�{��9��2���́A�N��������S�g���ӊ����x�ł������B
�@�����̐Q�ꂵ���̂��߂��ȁH�Ǝv���Ă������E��r���̋ؓ��ɂ�����B������������̌ߌ�COVID-19���N�`����6��ڂ̐ڎ����������B��͂荡������̕������Ƃ��Ă̑S�g���ӊ��Ȃ̂��낤�Ǝv�����������B
�@�������C�͐������C�^�Y���Ɏ��Ԃ����o�߂����B�ꉞ�N�������̂̃O�_�O�_�߂����ēx�珰�B���H�A���H�͎�炸�ɐ��������ێ悵�ߌ�܂Ńx�b�g�ʼn߂������B15:00���ɂȂ����Ƒ̒��A�H�~�߂�y�H���Ƃ�B
�@����Ȏ��͉ʕ��̊ʋl�������B�q���̍��͂��ꂪ�y���݂������B�����͓��̃V���b�v�Ђ����J�������ʋl�łȂ����~�l�[�g(?)�̑܋l�߂̕i�ł������B���ゾ�ˁB�����������B�q���̍����v���o�����B
�@�[���قډ����B
�@����COVID-19���N�`���������6���������d�˂邲�Ƃɕ���p�̑S�g���ӊ����Ђǂ��Ȃ����B���̂���4��ڈȍ~�͐ڎ�������j�ɐݒ肵���B4��ڂ͎���ŐQ�ĉ߂����A5��ڂ͐ڎ헂���ɔѐ�a�@�̓��������������Ă������A�I���������̃x�b�g�ʼn߂������B���Ɩ�̌��H�ɂ͎�������Ȃ������B
�@����Ȃ��Ƃ������č����6��ڂ����j������]�����B�y�j�͐H������炸�ɔ����珰���ĉ߂������B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�@�ŋ߂̃��N�`���Ɋւ��閾�邢�j���[�X
�@�{�N8���ɍ��Y���N�`���̏����F���Ȃ��ꂽ�B���O��KK���̃��N�`���ŁAmRNA���g�����^�C�v�B�����ɗ��s�����u�]�����v�ɑΉ����Ă���B
�@�E�C���X�͕ψق��J��Ԃ��A���݂̓I�~�N�������́uXBB�v�n�����嗬�ƂȂ��Ă���B���J�Ȃ͂���ɑΉ������C�O�̃��N�`����A�����A9������S�����Ώۂɂ����lj��ڎ���n�߂�B
�@���ƂȂ��Ă͑��O��KK�����N�`���Ɏ��v�͂Ȃ��B
�@�������Ȃ���A���ł�XBB�Ή��̃��N�`���J�����J�n���A�N���̋�����ڎw���Ă���Ƃ����B����̏��F���X�e�b�v�Ƃ��āA�J���ɒe�݂����Ăق����B
�@���{�͊����ǂɑ����@�Ǘ����Â��A���N�`���̌����J�����肪�����Ƃ��w�ւ̍��̎x�����s�\���������B���ʓI�Ƀ��N�`���J���ŏo�x��邱�ƂɂȂ�A�R���i�Ђœ��{�͎��O�̃��N�`����p�ӂł����A�č�����̗A���ɗ��炴����A�ڎ�̊J�n�͉��Ă����x�ꂽ�B
�@����ɑ��A�č��̓R���i�O���獑�Ɛ헪�Ƃ��Ċ����nj����ɋ���𓊂��Ă����B���̌��ʁA�R���i�Ђ̈�N�̂��ɂ̓��N�`���̎��p���ɂ��������Ă���B
�@�n�����g���̍����A�V���������ǂ����P���Ă��邩�킩��Ȃ��B
�@���N�`���J���ɂ́A���Ԃ�������A������Ȏ������K�v�ł���B����Ԋ�ƂɊۓ����ł͐i�W�͖]�߂Ȃ��B�x�����C�ɔ҉�̐������Ő����Ă��炢�����B
9/1�i���j�����H�c�[���~�J�@��Ȓ��ʊO���@COVID-19���N�`���ڎ�@
�@2:15�N���A�Q�ꂵ�����y���B�f���f�[�^�����A�������A�{�ǂ݁B�k�R�B5:35�R�S�~�p���A�V:35Taxi�H�c�w�ɁAiPad�Y��`��ʂ��玩��ɓ͂����A�Ƃ����B8:1�P���܂��A��Ȏs�����������Taxi�A�W:50��Ȓ��ʕa�@�B���X�K��A15:00���ʕa�@�ACOVID-19���N�`��6��ڐڎ�B���n�a���Ή��B�V���`�F�b�N�B�����B19:30�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B���N�`���ڎ�e���Ȃ��B
COVID-19���N�`���ڎ�̘b��2023(1) �{��6��ڂ̐ڎ���Ă���
�@���͈ꉞ��Ï]���҂Ȃ̂Ń��N�`���͗D��I�ɐڎ킷��@��^�����Ă���B����ƁA������x�̕������͗e�F����������Ȃ�����ɂ���B
�@���܂�5��ڎ킵���B����d�˂邲�Ƃɕ��������Ђǂ��Ȃ�A3-5��ڂ͒��˕��ʂ̋Ǐ��ɂƐH�~�s�U�A���x�̌��ӊ��Ȃǂœ���I�����͂قƂ�ǂł��Ȃ������B
--------------------------------------------------------------
��1��ځ@2021�N3��23��(��)�@�t�@�C�U�[
�@�@�@���˕����u�Ɍy�x�A�����܂�
��2��ځ@2021�N4��13��(��)�@�t�@�C�U�[
�@�@�@���˕����u�Ɍy�x�A���X���܂Ł@
�ؓ��Ɍy�x�A���X���܂�
��3��ځ@2022�N2��9��(��)�@�t�@�C�U�[
�@�@�@���˕����u�ɒ����x�A���X���܂Ł@
�ؓ��ɒ����x�A���X���܂Ł@
�@�@�@�S�g���ӊ����x�A�����܂ŁB
�H�~�s�U���x�@�[�H�ۂ炸�A��シ���ɉ珰�B�����͉��P�B
��4��ځ@2022�N8��19��(��)�@���f���i
�@�@�@���˕����u�ɂɂĘr�����@�ؓ��ɁA����3���ԁ@
�@�@�@�H�~�s�U���x�ɂē�����A�����������݂̂ŐH����ؐۂ炸�B
�@�@�@���x�S�g���ӊ��ɂċA��セ�̂܂܉珰�A�������I���珰�B
�@�@�@���X���͉��P�B
��5��ځ@ 2023�N1��13��(��)�@ �R�~�i�e�B2���@BA 4/5
�@�@�@�悭�m��Ȃ��R�~�i�e�B2���@BA 4/5���N�`��
�@�@�@�����N��������S�g���ӊ��A���M���B
�@�@�@�H�~���F���A�قƂ�lj珰�ʼn߂����B
�@�@�@�ѐ�a�@�̓����Ɩ��͂Ȃ�Ƃ����Ȃ����B
�@�@�@�����͉��P�B
��6��� 2023�N9��1��(��)�@�t�@�C�U�[
�@�@�@�{���A�Q���܂ł͖�薳���B�����͂ǂ��Ȃ邩�B
--------------------------------------------------------------
�@���̏ꍇ�̕������͔��M�Ƃ����ɂ͂Ȃ����̂̑S�g���ӊ�������d�˂邲�ƂɂЂǂ��Ȃ��Ă���B���ׁ̈A�ڎ����I���ł���ꍇ�͋��j���ɂ��Ă���B
�@3��ڂ͑S�g���ӊ������x�ł���������ӂʼn��������B
�@4��ڂ͑S�g���ӊ����O��Ɠ��l�A���x�Ŏ������Ԃ����������B�ڎ킪���j���ł悩�����B�����͔ѐ�a�@�̓������ł��������A�قƂ�lj珰���ĉ߂������B�ʏ�Ζ��Ȃ炩�Ȃ�h���������낤�Ǝv���B
�@COVID-19���N�`���ڎ�͍�������炭�������낤�B���͊O���f�Â�ʂ��Ċ��҂ɐڂ���@����邵�A��b������L���鍂��҂ɂ���������B
�@������ڎ킹����Ȃ��B
�@�{��6��ڂ̐ڎ���Ă����B�{���̏A�Q���܂ł̗l�q�ł͓��ʂȕω��͂Ȃ��B
�@�����͂ǂ��Ȃ邾�낤���B
8/31�i�j�����@�����@
2:00�N���C���Q�ꂵ�������B��w�������Ǐ��A�v�X���y�ő����߂����B�k�R�B8;45�Ɠ��Ƌ��Ɉ���R�C�ɉa�A���ʃ��n�B10:00���҉Ƒ��ʒk�B�ߑO���w���S�B�����ȂǁA13:30���H�A���@���ґΉ��A���Ȃ��B���w�Ǐ��O���A19:15�A��A�[�H�A20;30�A�Q�B
��(5)
8/30�i���j�@�ߑO�x�ɂȂ���I���a�@��
1:45�N���C���ӂ͐Q�ꂵ�����Ȃ�y���B�摜�f�[�^�����ȂǁB7:00�U���ق��A���Ȃ菋���Ȃ��Ă���B��w�������Ǐ��A�k�R�B����̎d�������A�Ɠ��ƂƂ��Ƀ��n�a�@�ɁB�����ȂǁA�V���`�F�b�N�A���́B14:30�����J���t�@�B���@���Ҏ�X�Ή��B���M�Ґ����A���w�Ǐ��A19:15�ʒ����X�o�R�A��A�[�H�A20;30�A�Q�B
��(4)
�W/29(�j�����@�O���@�@
2:00�N���A��w�����E�V���ق��B5:15�R�S�~��o�A6:40�o�X�a�@���A7:00�a���Ή��B�B8:45-12:45�O���A13;00�a�@�A�����A15:00���ґΉ��A�V���@�B�V���`�F�b�N�Ɠ��́A���w���S�B19:30�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B
��(3)
8/28�i���j���@���N�N���j�b�N�h�b�N
1:45�N���B�Q�ꂵ�������������P�A���͂т������B�V���E�����`�F�b�N�B�f�[�^�����A��w�����E�V���ق��B6:40�o�X�a�@�A7:00�a���Ɩ��A9:00-11:30���N�N���j�b�N�h�b�N15�l+���ʔ���14�l�B11:45���n�a�@�A�����ق��A�V���`�F�b�N+���́A�G���ގ��������A�Ǐ����A���ґΉ��B19:15�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B
��(2)
8/27�i���j�����@�����@
�@3:15�N���A���j�{�A��w�_���ǂ݁B�l�R�Ɣ����A�U���ȂǁA���w���S�A12:00NHK�j���[�X�A�̂ǎ����B13;30�Ɠ��ɓ���A���ʃ��n�a�@�ɁB�a���Ή��B�������҂͕����A�Ǐ��A�V���f�[�^���B�~�σf�[�^�����B�����ƓǏ��O���B19:00�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B
��(1)
8/26�i�y�j�����@Apple ID�ύX�@��ȉԉ��Z��@
2:20�N���A��Ԃ̏����R�z�����H�H�@�Ȃ��Ȃ���炸�E�_�E�_�ƁB�V���`�F�b�N�A�����ǂݑ��A�e��f�[�^�����B2��ڂ̐V���`�F�b�N�B8:35�U���ȂǁB11:30�Ɠ��ƕa�@�ցB�Ǐ��A�f�[�^�����B16:00-18:00Apple ID�ύX��2���ԗv���BWi-FI���̖����������B�S���҂���ρB19:00�A��A�[�H�A�Ɠ��̓]���^�֘A��ZOOM��c�A��ȉԉ��Z���TV�Ō��Ă��܂��B20:30�A�Q�B
���N�̏H�c�͏���(12)�@�ƒ�؉��E���|�ւ̉e��(2)�@�A�������͑����̐������߂Ă���
�@����3-4�T�Ԃقǂ܂Ƃ܂����~�J���Ȃ��B���A�H�c��35���������ҏ����������B���A����v�����^�[�̉ԁA�Ԓd�̖X��ԁA��������̔��̍앨�͊ȒP�ɐ��s����ԂɊׂ�B������A���[�̐��T���͌������Ȃ��B�������Ȃ��玄�Ɏ��Ԃ̗]�T���Ȃ������A�U���͒��݂̂ɂ��Ă����B
�@�����ׂ����ώ@���Ă���Δނ炪�����ق������Ă��邱�Ƃ͈�ڗđR�ł���B����������l�ɎU�������߂Ă���l�ɁA�A�������͎��ɐ������߂Ă���B���Ă������Ă������Ȃ��Ȃ�̂����A�@������Ή��ł��Ȃ����Ƃ�����B
�@���Ă����A���̉Ԃ̂��������͂炵�Ă��܂����B
�@�ڂ��͂����ɐ��s���ɂ��Ă��܂�������ŁA�����Ȃ���h���C�t�����[�ɂ����B�h���������낤�B
�@�����������O���A����B�����Ȕ��̒��͌��Ԃ��Ȃ��قǍׂ����A���A���G�ɍ������菄�炳��A���̌`��ۂ��ĂȂ��Ȃ�����Ȃ��B���̈ꕔ�̍���L���Č����甫�̐[����10�{�͂��肻���ł���B�������̒��ɂ��ꂾ���̍��������Ă���Ƃ������Ƃ͉����Ȑ��̋z���̂��߂ł��邱�Ƃ��\�z�ł���B
�@���̐������߂鍪�̗l�q�����āA���͏������������ɑ���A����̂͐l�Ԃ̃G�S�ƌ�����B����ŁA�ŋ߂ł͔��̃T�C�Y�����X�ɑ傫�߂̂Ɉڂ��ւ��A�ԁX�ɗ]�T��^���Ă���B
(���@�������Ő��N�Ԍ����ȉԂ��炩�����A�}�����X�@
�@�E�@����3���ɕ������]�T��^�����@�S�Ȃ����t���L�ѐL�т��Ă���l�Ɏv����)
�@�Ă̏������A�l�͓�����������A��@��N�[���[�Őg�̂��₷���A���V���ł��A�������͋������z�𗁂тȂ���ς��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�s��t�͐G���Ă݂Ă�����قǔM���Ȃ��Ă��Ȃ��B����͎��ɕs�v�c�Ȃ��Ƃ��Ǝv���Ă����B
�@����ɂ͉��x���߂Ɏ��̒m��Ȃ����J�j�Y�����������B
�@�A���̑̉����߂͐����L���łȂ��Ƃ��͗t�����ڂ߂Ď鑾�z�������Ȃ����A�����L���ȂƂ��͑�ʂ̐���̕\������������Ă��̋C���M�ő̉��߂��Ă���Ƃ����i�b���w�����@�c���C���ɂ��j�B
�@���V���ŐA�����������C���Ȃ����̂͂��ׂĐ��s���Ǝv���Ă����̂ł��邪�A�m���ɐ���^����O�ɓƂ�ŃV�����Ɨt�̒��肪�߂��Ă��邱�Ƃ�����A���Ȗh�q�̂��߂ɂ����ėt���ނꂳ���Ă����A�Ɨ��������B
�@���͐A�����������߂�̂͑̓��ɐ�����������ێ����邷���߁A�Ǝv���Ă���������������邽�߂ɑ�ʂ̐������������Ă����B�A�������͎����v���Ă����ȏ�ɑ����̐������߂Ă����B
�@������v���m�����̂�2010�N����Łu�n�X�v����ĂĂ������ł������B
�@���܂߂ɐ��Ǘ��������J�Ɉ�ĂĂ����B�t�͋����قǁA1m�ȏ�̒����ɂ܂Ő��������B7�����{�A���C�ȉԉ肪���{�p���������B
�@2010�N7��27��(�y)�͔ѐ�a�@�̓�������11:00�����痂��10:00�߂��܂łق�24���ԗ���ɂ����B���̓���30�x���������ł������B�A���Ă݂�Ɓu�n�X�v�̗t�̑啔�����ނ�Č��C���Ȃ��Ȃ��Ă����B�����������Ă������̂����オ���ēy���ł��Ȃ��Ă����B���̌�A���\�ɋ��������������A�ꌎ�قǂŌ͂�Ă��܂����B�܂����A22���ԂقNj������Ȃ��������ƂŊ��オ�����̂͗\�z�O�ł������B
�@�u�n�X�v�͒r����ɐ��炷��Ԃł��邱�Ƃ́A��ʂ̐����K�v�Ȃ��Ƃ������Ă���B
�@�q�g�͎��R�̐ۗ������Ď����̂��߂ɕs���R�ȏ����Ȋ��ŐA�����琬����B�����̃y�b�g���������ł��邪�A���ǂ��̎��Ȗ����̂��߂ɁA�ł���B���̂��Ƃ̖��_�A�ߐ[����������Ă�������B
�@���U�ɂ킽���Đ��b���K�v�Ȃ̂̓y�b�g�����A���̑��������ł���B
8/25�i���j�����@��Ȓ��ʕa�@�@
3:00�N���A�������A�{�ǂ݁B�܂��Q�ꂵ���B���Q�߂����B�摜�����B5:10�R�S�~��o�B7:40Taxi�A8:11���܂��A9:00��Ȓ��ʕa�@�O���A����Taxi�A�����͑�ȉԉ��Z��Ƃ����̂ɊX���Ɋ��}�̊Ŕ�̂ڂ�Ȃǂ��Ȃ����̂悤�ȕ��͋C�͈�Ȃ��̂��s�v�c�B15:30�����Ï��X2���w���B���ʃ��n�a�@�B�����A19:30�A��A�y�[�H�A20:30�A�Q�B
���N�̏H�c�͏���(11)�@�ƒ�؉��E���|�ւ̉e���@�N���@�������@�����S
�@�䂪�Ƃɂ͌I�̖A�`�̖A�������e1�{�A�����S�̖�2�{����B���̂����`�̖͍�N�H�ɗׂ̔��̓��A�ɂȂ�Ƃ����̂ő啔���̎}�𗎂Ƃ������A�c����������V�����}�������Ă��Ă���B�����͂��������B������]���������炻�̎}�͑厖�Ɉ�Ă悤�B
�@(1)������
�@��N�͉䂪�Ƃ̒�̏�������200-300�P�قnj��������B���܂�^�����ɂȂ�߂��Ď}�܂ꂷ��قǂł������B���͔엿��������虒�肵����͂����̎v�����܂܂Ɉ�ĂĂ���B�X���ꐶ�����ɊJ�Ԃ��A�������Ă������̉ߒ�������̂͊������B
�@�ʎ��̏n���Ƌ��Ɏ��̎��ӂɂ͊Â������̓������Y�����B
(�ƂĂ���������̏���)
�@�Ƃ��낪�A���N�͂قƂ�nj������Ă��Ȃ��B��������20�|30�����x�B���������n���邱�ƂȂ����ʂ��Ă��܂����B���͈���}�ɂ��Ă��Ȃ��B
�@(2)�����S
�@2�{�̃����S�̖ɂ͍�N��100���قǂ����������B�����S�����Ɠ��l�Ɏ��R�ɔC���Ă���B
(��N�̌����̗l�q)
�@���͐����S���D���ł���B�n���̉ߒ��Œ������B���̑O�ɁA�Ɩ���2���قǍ̂��ĐH�ׂĂ���B�s��ɂ�������S�͗��h�ł��邪�A���͓���n�߂Ă��Ă������肷�邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B�䂪�Ƃ̍̂肽�Ă͌ł��āA������Əa���čō��ɔ����ł���B
�@�Ƃ��낪�A���N�͂قƂ�Ō������Ă��Ȃ��B��������20�|30�����x�B���̐���������w�ǐH�p�ɂȂ�Ȃ��B
�@(3)�N��
�@�I�̖͂ǂ����B�䂪�Ƃ̌I�͑�^�̎�������B���N�I���т𐔉��邾���ۂ��̂ł��邪�A���N�͏����ȃC�K�I��Ԃ̂܂��X�Ɨ����Ă���B�����グ�Ă��c���Ă���Ⴂ�C�K�I�̒��ɂ͉��������Ă��Ȃ������B
(��N�̂ꂽ�N��)
�@�䂪�Ƃ̉ʕ��̖͔M���̔�Q�����A�Ǝv�킴��Ȃ��B
�@���́A���������Ȍo���������猋�_���o���Ȃ����A������������ƋL�^�I�Ȗҏ�������������s�𒆐S�ɁA���n�����}���郊���S�_�Ƃ��Ή��ɋ�S���Ă���悤�ł���B
�@�����S�u����v�̎��n���Ő��������A���܂��ɉʎ����F�Â����A���ɔ����Ԃ��܂�����x���A�Ƃ����B����ł͎s�ꉿ�l�͂قƂ�ǂȂ��A�Ɛ��𗎂Ƃ��Ă���A�Ƃ����L�����ڂ����B�����⏭�J�A����̉��x�������������߁A�Ƃ݂��A�u���ʂ��啝�Ɍ��肻�����v�ƃ����S�_�Ƃ͕s�����点�Ă���B
�@��͂荡�N�̔M���͐A���ɂƂ��Ă��q��ł͂Ȃ��炵���B
8/24�i�j�����@ 3:55�k���N���q��??�@��J�̏Ⴉ
2:15�N���B�Q�ꂵ���������N����͂��������͂Ȃ��B3:55�k���N���q��??���s�B��J�}篍~�A�Ȃ����B�f�[�^�����B�^���f�[�^�����B�_���A�U���ȂǁB8:30���ʃ��n�ɁB���҉Ƒ��ʒk�����B15:00�ʒk�A���@���ґΉ��B�����]�@�̊��҂̏��ʏ����A19:00�A��A�[�H�A21:00�A�Q�B
���N�̏H�c�͏���(10)�@���̏�����(2)�@��@�Ɨ①�ɂ�
�@���̓G�A�R���Ȃ��̊��ł̏�����͈ȉ��̍H�v�����Ă���B���铹��͐�@�Ɨ①�ɂł���B����ŏ\���߂�������B
(1)�J���J���Ƃ�A�������͎����ɘU��Ǐ����S�A���w�ɋ��ށB���y�������B
(2)�x���Ƃɂ��Ă��O�d�����ł��Ȃ����Ƃ��B���̏ꍇ�A�a�@�ɍs���Ďc���������Ȃ����Ƃ��B
(3)�A�Q���͍ŏ����̉����݂̂ŁA��ɂ͉����|���Ȃ��B�O�C��������邽�߂ɐ�@�����p����B
(4)���ɕX�������p�B
(5)������u����Ί��v(�A�Z��)�������Ղ��B���܂߂ɐ@����邩�����B
(6)�ʂ�߂̉��x�ŁA���ɂ͐����C�Ŋ��𗬂��g�̂��₷�B
(7)����1.5L�̒����B500ml�̃K���X�r�O�{�ɕ����A���̂����̈�{�͂��̂܂܈��ނ��A2�{�͗Ⓚ���A�K�X�������Ȃ�����ށB
(8)500ml�̋��Y�_���A�~�l�����E�I�[�^�[�𓀂点�A�z�ɕ��ő̂ɂ���B�������s����������߂����B
(9)�����ێ掞�ɂ͕X��ꖂ�B�K���K���Ƃ�����鎄�͌b�܂�Ă���B
�G�A�R����������͐����Ȃ��Ƃ��͂�߂����₷���B
(1)��l�̎��̓G�A�R���͍ŏ���28���ŁB�₦�Ă�����29�|30���ŁB
(2)��@�p����B�n�������߂Ȃ��悤�z������B
(3)�Ԃł̓G�A�R����p����������̕��𗘗p����B�J�����đ��s���Ă���Ԃ��قƂ�ǂȂ��̂����낵���B���g���A�ُ�C�ۂ͎��Ǝ����B
�@�����͍�����C���̍����������������݁B �G�A�R���̑��ɂ��H�v���ׂ����Ƃ͑����A�Ǝv���B
8/23�i���j�����@���d�̓�����ǁA����̈ꕔ�p���@�ߌ�a�@�@
2:20�N���A���������A�f�[�^�����B8:00�_���A���b��A�Â��͂ꂽ�ԕٔr���A�T���ق��A���d�̔z�����Ă���댯�A�����A������ǁA����̈ꕔ�p���B11:10�o�X�A�a�@�ցB�����B13:00��lj�B14:30�����J���t�@�A�Ǘጟ����A���̂ق��B�a�����ґΉ��B�Ǐ��Ə��Ѓf�[�^���i�߂�B�V�����́A����5���B���w�B19:30�A��A�[�H�A21:00�A�Q�B
���N�̏H�c�͏���(9)�@���̏�����(1)�@�G�A�R���ɗ���Ȃ�
�@���N�̏H�c�͏����B���N�͑ς���قǁB���ɓ��{�ōō��C���̂��Ƃ��B�]���Ȃ�ҏ��ƌ����Ă�����Ȃ̂͂��������P�T�Ԃقǂł������B�������A���N�͏]���Ƃ͈قȂ�A�����ꃖ���߂��Q�ꂵ������߂����Ă���
�@���̏��ւ͐Q�������˂Ă���B�G�A�R���͂Ȃ��B
�@�����͐����ɖʂ��Ă��邽�߂ɉĂ̌ߌォ���ɂ����Ă͂ƂĂ������B8�����{�A�A�Q���Ɏ����x�𑪂��Ă݂�ƘA��35�����ł���B���͂����ŐQ��̂ł��邪�A���ꂪ���\��ρB�������킢�̂悤�Ȃ��́B
�@���ۂɒu������@�ŊO�C��������A����ɂ������̐�@���h�A�̊O�ɒu�����悩��̊O�C���������B����ł����Ȃ�\���Ȃ̂ł��邪�A���N�͊O����̕��A��@�̕��͗����Ȃ�ʉ����A���ɂ͔M���ł���B
�@�[�H���Ɉӎ��I�ɂ�⑽�߂̐�����ۂ�A21:00�����ɍŏ����̉����p�ŁA��ɂ͉����������ɏA�Q�B�X�ɁA0:00�����ɐ�����⋋���邽�߂Ɉ�x�N����B�Q:00�����̋N�����ɂ͑S�g���܂݂�A�~���z�c�͑�U���Ɍ����i���قǎ����Ă���B
�@�N������Ƃ܂���������������B����ł����̃y�[�X�ő����̃X�P�W���[�������Ȃ����Ƃ��ł���B
�@���͏����̂��D���ʼnĂł��x���Ȃǂ͎ԌɂȂǂł����ȍ�Ƃ����Ă����B�������A���Ă͏������Ė����A�M���ǂ�h�����߁A�����ɂ����_���A�̐��b�Ƃ��̎��Ƃ��s�������B�����ƒ��˓����Ŕ�J�������������A��ꂪ���ɂ����Ȃ����B
�@�����͂قƂ�NJO�ɏo�Ȃ��B�X�����K���K���炵���B
�@����̐l�ԃh�b�N�̎�R�̕��̂���l�́A�s���ŃP�[�L�����c��ł���v�w�ł������B�u�i�C(�P�[�L)�͂ǂ��ł���?�v�A�Ə�k�����ɘb����������u���̉Ă͓����ɂ͏o�����l���قƂ�ǂȂ��̂őS������܂���B�[������ڂ��ڂ��Ƌq�����邾���v�Ɨ͂Ȃ��b���Ă����B
�@�����͋L�^�I�ȏ����������A�M���ǂ̋^���ɂ������҂��������ł���B���Ɏ����܂ߍ���҂͔M���ǂɂȂ�₷���B
�@���h���ƌ������h�Љۂ̂܂Ƃ߂ɂ��ƁA�����ł�5�����獡��20���܂ł�783�l���M���ǂ̋^���Ŕ�������A���̂���65�Έȏ��551�l��7�����߂��B�������͍�N�ɔ��6�{�قǂƂ����B
�@����҂͑̓��̐����ʂ����Ȃ��A�����Ȃǂ̊��o�̂��݂��Ă���B����ɏ����ɑ��銴�o���݂��Ȃ��Ă���B����҂́A�����܂߂āA�ӎ��I�ɔM���Ǒ������K�v������B
�@�\�h�Ƃ��Ă̓}�X�R�~�⎯�҂́A���܂߂ɐ����⋋���s���A�G�A�R���ŏ���������邱�ƁB�����͒����ԉ߂���������28�x���Ȃ��悤�ɁA������������Ȃ���Ԃ��G�A�R�����ɂ₩�Ɏg�p�������������E�E�E�Ȃǂƃ����p�^�|���ɐ��_�ŌĂт�����B
�@�����O���Őf�Â��銳�҂̈ꕔ�͂ƂĂ��n�����B����2�N�قǂ̐��������̒l�オ���3�H��2�H�ɂ�����Ɛ������ł��Ă�����X�������ł���B�G�A�R�����Ȃ��l�͂ǂ���������̂��B�����Ă��d�C���̍����Ŏg�p���T��l������B
�@�G�A�R���ȊO�ɉ����͂Ȃ��̂��H�H
�@�ŋ߂̎��̊O���̘b��͏������C���ł��邱�Ƃ��B
8/22�i�j���� ���ʕa�@�O���@�Ɠ��͒�F�������
2:50�N���A�摜���������B5:00�R�S�~�W�Ϗ��ɁB6:40�o�X�a�@�A7:00�a���Ή��A8:45 -12:50���ʊO���A�����x���G�B13:00���n�a�@�B�����A15:00���@���ґΉ��B�V�������`�F�b�N�s�\�A�����Ґ���u���̂����v�ӏ܂��Ă���19:10�o�X�ɏ��x��Taxi�A��A2500�~�A19:30�[�H�A21:30�A�Q ������38.�T�ŐQ�ꂵ���B
���N�̏H�c�͏���(8)�@���̃G�A�R�����@
�@���N�̏H�c�͏����B���N�͑ς���قǁB�]���Ȃ�Q�ꂵ����͂������Ƃ��Ă��P�T�ԂقǂŁA����Ȃ�ɉĂ炵����搉̂ł��Ă����B�������A���N�͏]���Ƃ͈قȂ�A�����ꃖ���߂��Q�ꂵ������߂����Ă���
�@
�@���́u�Ă����̏����͓̂�����O�A�H�c�ł̓G�A�R���Ȃǂ����E�E�E�v�A�ƍl���Ă������A2019�N�ɋ��ԂɃG�A�R����ݒu�����B
�@82�ɂȂ�d���̐Έ䂳�����������B�u�ŋ߂͏����ė[�H�����̂���Ɂv�Ƃ����B�Ȃ�قǁA���̏����̒��ʼn��g���̂͐h�����낤�B�G�A�R�������̎��́u����ҋs�҂����Ă���v��������Ȃ��B�u�G�A�R�����Ȃ��E��͌��E�E�E�v�Ɩk�C���ɋA��ꂽ�玄�ǂ�����ςł���B
�@�G�A�R����ݒu������X�g���X���������̂��낤�A�Έ䂳��̕\����ǂ��Ȃ����B
�@�ݒu�����I�ɗp�����Ă���悤�ŋA���Ɨ������[�H���͎��ɉ��K�ł���B
�@�����A���͂܂��u�G�A�R�������v�̍l�����c���Ă���A�����ł͎���̃G�A�R���̃X�C�b�`����ꂽ���Ƃ͂Ȃ��B
�@
�@���́u�G�A�R�������v�Ȃ̂��A�Ƃ����ƁA���͏����̂͂��܂��ɂȂ炸�A�Ă͏����ē��R�ƍl���Ă��邩��ł���B
�@���̋G�߁A���͉��K�Ƃ͌����Ȃ��قǂ́u�������v�ʼn߂����˂Ȃ�Ȃ������h���A�s���ł���B
�@����1�������߂��������̉��x�������Ǝ����ƁA
-------------------------------------------------------------
?�N�����A2:00���̋��Ԃ�25���A�����Ƌ��ɏ㏸�����������畗��������K�B
?6:00�S�~�p���A�_���A�̎U�����B���łɏ����Ȃ��Ă�����Ɠ����Ɗ������ɁB
?6:40�̒ʋ̃o�X���ߏ�ɗ₦�Ă����B25���O�ォ�A�s���B
?7:00����̉�f���A�i�[�X�Z���^�[�̉��x�ݒ肪24���ɃZ�b�g����A�s���B
?8:45���璆�ʑ����a�@�O���ł����������x�ݒ肪25���œ��l�Ɋ��������B
?13:00���ʃ��n�a�@�̈�ǂ̎�����35���B�����ăG�A�R����29���ɃZ�b�g�����B
?19:30�A��B���Ԃ̉��x�ݒ��27���قǂʼn��K�ł������B
?21:00�A�Q���̎�����35���B�������ɂȂ��Ė������B
-------------------------------------------------------------
�@���̓G�A�R������ے肷����̂ł͂Ȃ����u��ʂɗ�₵�߂���v�A�Ǝv�����C�����������猾���o���������Ƒς��Ă���B
�@�u���N�����A�����K�ɉ߂������Ƃ���̂͂��̎��㓖�R�����A�G�A�R���͒n�������߂�傫�ȕ���p�����邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�A�u���ɁA�K���ŗp����ׂ��v�Ǝv���B
8/21�i���j����34���@���N�N���j�b�N�h�b�N�@
�@2:00�N���B�����A�V���`�F�b�N�B�f�[�^�����B�U�����A6:40�o�X�a�@�B7:00�a���Ή��A�V���`�F�b�N�A9:00-11:00���N�N���j�b�N�A�h�b�N�f�@14���B��T���̌��ʔ���Ȃ��B���ʃ��n�a�@�ցA�����B�V���`�F�b�N�Ɠ��́A�����B 15:00�a���Ή��B���S�f�f���̈����ɂ��ĕw�����w�E����B���_���낤�B�_�H���T�܂ŏI���B�f�[�^�`�F�b�N�B19:10�A��A�[�H�B20:30�A�Q�B
���N�̏H�c�͏���(7)�@�������āu���k�J�ǁv�Ȃ�ʁu���ljJ�ǁv�̖����@
�@���N�̏H�c�͏����B���͏����̂��D���Ȃ̂������N�͑ς���قǁB
�@�H�c�����ł�7��24���ȍ~�A18�������čō��C����30�x�ȏ�̐^�ē����ϑ��B����3������8���܂ł�5���A����35�x�ȏ�̖ҏ����ƂȂ��Ă���B 7���͌����ϑ�26�n�_��9�n�_�Ŗҏ����ƂȂ�A�H�c�s�ł͍��N�ō���38.4�x�܂ŏ㏸�����B
�@�H�c�n���C�ۑ�ɂ��ƁA�����m���C���̐��͂������A�����ԍ��C���ɕ����Ă��邱�Ƃ��ҏ��̌����ƌ��Ă���悤���B���͍̏���������\��ƂȂ��Ă���B
�@�C�ے���2�T�ԋC���\�z(8��7���ߌ�5�����_)�ł́A12���܂ōō��C����38�x��
��A���̌��30�x���鏋���ɂȂ�Ƃ��Ă���B
�@�{���̂ق��A�V���╟��ȂǓ��{�C���𒆐S�ɖҏ��������Ă���A�u�t�F�[�����ہv���������Ă���Ƃ݂Ă���B�u�t�F�[�����ہv�Ƃ͍����R�̏ォ��[�Ɍ������āA�M������������C�����ꍞ��ł��錻�ۂ̂��ƁB����������������A�C�����㏸�����肷��B
�@���͂���Ƃ�̓������Ə����Ă��D���ŁA���˓����Ə���������Ȃ���O�ʼn߂����̂��D�ނ̂����A���N�͑ς���B8���ɂȂ��Ă���͑�����������������A�������o��A8:00�O��ɂȂ�Ƌ}���ɋC�����㏸����B�����Ȃ�S�n�悢���̓�����������ł���B
�@���͗�N�_���A����ĂĂ��邪�S���Ƃ����C���Ȃ��B�ꕔ�͌͂ꂩ�����Ă���B�����ɎU���Ȃ�ʋ��������Ȃ���Η������Ɍ͂�邾�낤�B�����ɎU�����ς܂��̂����ۂƂȂ��Ă���B���̂ق��ɁA�����Ȃ琰�ꂽ�x���ɂ͔��̖�̐��b�A��̑����������̂ł��邪�A���̌����̒��ł͈ӗ~���N���Ȃ��B�@
�@�����炱��2�����قǂقƂ�NJO�d�����ł��Ȃ��B�����������̂��炢�قǑ��ڂ��ڂ��ł��邪��ނȂ��B���n�����͂Ȃ�Ƃ����Ă���B
�@���́u���k�J�ǁv��O���ɐ�����V��C���ɂ��Ă���B�ʂɔ_�Ƃł��Ȃ��̂ł���قǍS��킯�ł��Ȃ���Ɨʂ�����قǂȂ��̂����A���R�ɔC����̂��S�n�悩�����B
�@�������Ȃ���A���N�͐���Ă��Ă��������ĊO�d���͖����ł���B�����̌��N���l���ĊO�d���͍T���Ă���B
�@�u���k�J�ǁv�Ȃ�ʁu���ljJ�ǁv�ʼn߂����Ă���B
8/20�i���j�����@����
2:30�N���A���w�����̂��Ƃ��B�������Ҏ��S�B8:00�U���A�����U�z�A�����Ɣ_�����S�ɁB10:30�Ɠ��ƒ��ʃ��n�B����̃R�C�ɋ��a�A�H�~�����B�a���Ή��A���S�f�f���쐬�B���̌�����a�@�ŁB�V���`�F�b�N�A���́A�����A�~�σf�[�^�����A�G���ގ����Ƃ����̃p�^�[���ɋ߂��Ȃ�B18:30�[�H�ʏ�ʂ�A20:00�A�Q�B
3�N�Ԃ�̕�Q��2023(4)�@���������ς��Ȃ��A���N�̕�Q��͖����I��
�@COVID-19�����ŕ�Q�ł��Ȃ�����3�N�Ԃ́u���z�{�v�������肵�Ă����B���̕�����͎�����|�̘A�����Ȃ��ꖕ�̎₵�����������B���ꂪ�@���E�̂�������Ȃ̂��낤������ɍ���Ȃ��悤�ȋC�������B
�@���N���O�A���ڂ��ڂ���Ԃ̒��ɕ悪�������B����A������p�̑�^�̃n�T�~��3���قǎ��Q�������A���͊����Ă��肻���p����܂ł͂Ȃ������B
�@��͎���ɂ܂݂�Ă����������Ɛ��ŐA���Q�̉ԁA�낤�����Ɛ���������������A�{���ŏZ�E�a����njo���Ă����������B�Z�E�a�͎�ۂ݂�ттĂ������A���ɂ��n�������肨���C�����ň��S�����B
�@���̕�Q�͍��Ōォ���A���̍ۂɂ͂�낵���A�Ɠ`��������ɂ����B
(�䂪�Ƃ̕�͎������w3�N���Ɍ����������́@�݂�Ȃ��Y��ɂ����@����ǂ����邩�͎�����Ɉς˂�)
�@3�Ƒ��͂��̌�ʍs���ɂ����ꂼ��H�c�Ɍ��������B
�@���́A���Z�ł���̐������K��A��O�Ɏ�����킹���B�Z�ł�80�]�œƂ��炵�ł��邪���C���Ƃ��Ŏ���C���Ȃ������̂��C������ł������B
�@
�@���̌�A���Ɏ��̃f�B�o�b�O��Y�ꂽ���ƂɋC�Â���U�߂�Ȃǂ̃~�j�A�N�V�f���g����������17:30���ɕa�@�ɒ����A���@���҂Ɋւ���Ɩ�����������19:30���A��A��A�̕�Q����I�������B
�@���j�̎Ԃ������s���Ō̏Ⴕ�A�ꕔ�͐V�����ŁA�ꕔ�͑�ԂŏH�c�ɖ߂����Ƃ����B�܂��A�V����������Ԃɕς��Ȃ��A��Q��~�j�c�A�[�͖����I���ł����B
8/19�i�y�j���������@2TB�n�[�h�f�B�X�N�s���o�b�N�A�b�v
�@2:25�N���A�������A�{�ǂ݁B�U���A�g�}�g���n�A11:30�s���̘A���Ń]���^�ɍs���Ɠ��Ƌ��ɕa�@�B��f���A���̂܂ܕa�@�ŁA���w���S�A�{�ǂ݁A����3���A2TB�n�[�h�f�B�X�N�s���o�b�N�A�b�v�A�I�����B19:00�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B
3�N�Ԃ�̕�Q��2023(3)�@�h���C�u�C���A�z�e������COVID-19���s3�N�Ԃ̉e����������(2)
�@��Q�r��ŗ���������h���C�u�C���A�h�������z�e���Ŏ���ۂ�COVID-19���s��̋q���̗������݂ƁA�q����������ŋ߂̐l��s���̗��҂̉e�����[������������̂ł������B
�@���̊Ԃ͗��فE�z�e���ƊE�͌���������ɂ�����Ă����Ƃ������Ƃ̓��f�B�A�̋L�q�Œm���Ă������A���͊ό��Ƃ��ɂ͑S���������Ȃ����߂Ɏ������Ȃ������B
�@���͗��s�����ł���B���Ă͊w��A��t����Ŋe�n��K�₵�����A������ނ��Ă���͗��s�Ƃ����ΔN�Ɉ��̐V����w�̓�����݂̂ƂȂ����B���̓������2017�N����A2018�N�V�����Ō�ŁA�ȍ~��COVID-19�̂��߂ɒ��f���Ă���B
�@����2019�N�ȍ~�A�H�c�s������o���A�Ƃ����L���͂Ȃ��B
�@�ό��n�Ƃ����A2017����Ŏ���ۂ͋���ł������B
�@�V���ٖk�l�w�ōݗ����ɏ�芷�������A�w�E��Ԃ̈ē��͓��{��ƒ�����ōs���ٗl�Ɋ������B
�@����ʼn߂������Q���ԁA���͂������������𗷍s���Ă���̂ł́H�Ƃ������o���������B�z�e���͖����ł���A�h���q�̌��t�͂قƂ�ǂ�������A�؍���ł���A���{��͂قƂ�Ǖ�����Ȃ������B���a�V�R�A�L��R�Ƃ��̖����͒����G���Ă����B
�@�����A�L���ό��n�̊O���l�ɂ����킢�ɐS�ꂩ��������Ƃ����̂������ł������B
(���{�̓��v�ɂ��O���l���s�҂̐��ځ@2020�N�ȍ~�͌����A�ŋ߉X���ɂ���)
�@2017�N�Ƃ����ΖK���ό��q��3000���l�ɂ��͂����Ƃ����E���オ��̎����ŁA����ߕӂ̊ό��q��9���͊O���l�Ǝv��ꂽ�B�ނ�̎p����͓��{����D���A�Ƃ������F�D�I�ȕ��͋C���������A���̑Β����A�Ί؍��̕��X�ɑ����ۂ⊴�o�����̓���Ԃ̌o���ł��Ȃ�ς�����B
�@���ꂪ2020�N�ȍ~�ACOVID-19�ɂ���ĖK���q�͌��������B
�@����܂Ŋg���������Ă����z�e���E���ًƉ�͑�Ō������ł��낤�B�p�Ƃ����Ȃ��Ȃ������悤�ł��邪�A�ƊE�ł̓��X�g���A�o�c�������łȂ�Ƃ����������Ă����Ƃ���������B
�@COVID-19����i���������A�ό��q�͖߂���邪�A���͐l��s���ɔY��ł���Ƃ����B
�@��ÂƂ�����r�I���肵���ƊE�ɐg��u�����́A�K���ό��q�����ɂ���قǂ̎������N���Ȃ��������A����̕�Q��ʂ��Đڂ�������ό��ƊE�A�z�e���E���ًƉ�̌������������Ԃ��_�Ԍ����B
�@�܂��A���{�ɂƂ��Ċό������o�ϓI�d�v���ɂ��Ă��l��������ꂽ�B
8/18�i���j�����@��Ȓ��ʕa�@�@
�@2:20�N���A�s�[�N�͉߂����悤�����܂��Q�ꂵ���A���܂݂�B�f���f�[�^�����B�������A�{�ǂ݁B5:10�R�S�~��o�B7:40Taxi�w���A8:11���܂��A9:00��Ȓ��ʕa�@�A�w�a�@�ԉ���Taxi�A�����̂��߁B���X�K��9���w���A15:30���ʃ��n�B�V���`�F�b�N�Ɠ��́B�a���Ή��A19:00�A��A�[�H�B20:30�A�Q�B
3�N�Ԃ�̕�Q��2023(2)�@�h���C�u�C���A�z�e������COVID-19���s3�N�Ԃ̉e����������(1)
�@��N��2��3���̗\���g��Ōq����ƉԊ��u�˕�����ʼnƑ�12���ō��e����̂ł��邪�A���N�͎��j��̎������A�N���̃{�[�_�[�R���[�̌��N��Ԃ��ǂ��Ȃ��ĐS�z�Ƃ̂��ƂŁA�Ȃ������T�z�e��1���݂̂Ƃ����B
�@���̌��N��ԂɊւ��Ă͋C��������b�肪�N������o��������Ǝ₵�������B
�@�Â������킯�ł͂Ȃ����A�ꌩ�ʏ�ƕς��Ȃ��l�q�ʼn߂����Ă��邩��Ƒ��B�̈ӎ����玄���������łӂ�ӂ�Ɛ����Ă���悤�Ɍ����Ȃ����炾�낤�B�����v��������鎄�����̌��N��Ԃ��C������ł������B
�@���ǂ�3�l��8��12�����O�A�a�@�Ŏ������҂̑Ή��̂̂����j�̉^�]�Ő����Ɍ��������B���͎Ԃ̈ړ��͋�ɂŁA�{�S�ł͐V�����ōs�����������̂ł��邪�A������Ԃ�ʂ��킯�ɂ͂����Ȃ��B���͎Ԃ̌㕔���Ȃɕz�c�Ɩ����������݁A�y�Ȏp�����m�ۂ��Ăقډ��ɂȂ��ĎԒ����߂������B
�@�p�قɂ͏�����Ќo�c�̃h���C�u�C��������A�ݖ����̃\�t�g�N���[���������Ŗ��N�y���ނ̂ł��邪�A3�N�O�ɔ䂵�X�܂�����K�͂��k�������悤�Ɋ������B
�@15:30���z�e���ɓ����A������ƁA���j��Ƃ��Ԃ�����������3�N�Ԃ�ɐe�������߂��B
�@�[�H�͑�L�Ԃł̃r���b�t�F�X�^�C���ł��������A���ǂ���12�l�Ɛl�����������Ƃ������Č���^�����A���̌`���̒��ł͐Â��ɗ[�H���y���߂��B
�@�Ȃ������T�z�e����2018�A19�N�����p�����B�q�̓��킢�Ƃ��Ă͂����ƕς��Ȃ��������A���~�O�̈ꎞ�I�ɂ��킢���ȁH�H���ɂ͂킩��Ȃ������B
���q�̓��킢�Ƃ��Ă͂����ƕς��Ȃ��������A���~�O�̈ꎞ�I�ɂ��킢���ȁH�H���ɂ͂킩��Ȃ������B
�@�z�e���̃T�[�r�X�ɂ͏]���Ə����ȈႢ���݂�ꂽ�B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
�@?�]�ƈ������S�̂ɏ��Ȃ���ہB
�@?���{�ꂪ�\���ʂ��Ȃ�����A�W�A�n�̏����̃X�^�b�t�����݂��Ă����B
�@?�t�����g�̒����ɂ͗��߁A�^�I���Ȃǂ̂ق��A�A���j�e�B�ƌ����鎕�����Z�b�g�Ȃǂ̏������R�ς݂ƂȂ��Ă����B�����͒ʏ�e�����̐��ʑ�ɗ\�ߐl�����z�z����Ă�����̂ł���B
�@?12����3�����m�ۂ����B������ɒʏ�͒��Ȃǂ̃T�[�r�X������A�h����̒��ӓ_�Ȃǂ̐��������邪�A����͂��ꂪ�Ȃ������B
�@?�e�����̕ǂ���ɂ͂��炩���ߐl�����̕z�c�������܂�Ă������B�]���Ȃ�H�����ɒS���҂��e����������z�c�̏������Ă������̂ł���B
�@?�r���b�t�F�X�^�C���̗[�H�A���H�͓��e�I�ɂ͕s���ł͂Ȃ��������A���ɏ]�������i�������Ȃ��悤�Ȉ�ۂ����B
�@?�������̐����ɍ��킹�ĉ�v�敪���ς�����B�S�̂������Ȃ��Ă���B�ꔑ��30�]���~�ł������B����͂����̔@����ẪW�W�o�o�̕��S�B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
�@�����̕ω���COVID-19���s��̋q���̗������݂ƁA�q����������ŋ߂̐l��s���̉e���ł��낤�B
8/17�i�j��������1���ԂقǍ~�J�����@�t����Ɨ��H�@���ʃ��n�����NJw�K��
1:20�N���B���������A�Ǐ��B8:30�t����Ɨ��H�A�i���̕ʂꂩ���B�Ɠ��ɓ��悵�Ē��ʃ��n�B���@���ґΉ��A�V���`�F�b�N���́A�a���Ή��A13:30���ʃ��n�����NJw�K��A���ܑϐ��ۂɂ��āA�u�t�͒��ʕa�@���ˈ�t�A���w�I���A19:30�A��A�[�H�A21:00�A�Q�B
3�N�Ԃ�̕�Q��2023(1)�@���~�̕�Q��̈Ӌ`
�@���N��COVID-19��5�ނɈڍs�������Ƃ������āA�܂������Ґ����S�̓I�ɏ��Ȃ��Ȃ�s���������Ȃ��Ȃ����B���l�ݏZ�̒�����Ƃ�3�N�Ԃ�ɗ��H���鎖�ƂȂ����B�����������2020�N���璆�f���Ă������ɂ����ւ̕�Q����s�����B
�@����1983�N(���a58)�̕��e�a�v�̐��N�O����ꉞ�䂪�Ƃ̑�\�҂Ƃ��ĕ�Q����s���Ă����B���̊ԁA�Ɩ��̊W�Ŏ����������������O�������Ƃ͂����������܂Ō��������͂Ȃ������B
�@���͓�l�Z��ł���B�Z�Ƃ�11������Ă���B2015�N���Z�����������B����܂ł͂��̕�Q��͔N�Ɉ��̌Z��Ƃ��̉Ƒ��̐e�r�̏�ɂȂ��Ă����B�Z���̗͋C�͂������Ď�����2�|3�N�O����͎Q�����鎖�͖����Ȃ�A�Z��Ԃ̐e�r��͎��R���ł����B
�@����ȍ~�͖~�̕�Q��͎��ǂ��̂����̉Ƒ������̍s���ƂȂ����B
�@���ǂ���3�l�̎q���Ɍb�܂ꂽ�B���݁A�����Ƒ��Ə̂���̂͂����3�l�Ƒ�5�l���܂�12�l�̂��Ƃ��w���B�������3�l�͉��l�ݏZ�ł��̂ق��̃����o�[�͏H�c�ݏZ�ł���B
�@�ŋ߂̕�Q�Ƃ��̑O��̃~�j�Ƒ����s�́A�����o��ɏ]���Đ�c���ÂԂ��߂̕�Q�̈Ӌ`�͏������Ȃ�A���𒆐S�Ƃ����Ƒ��e�r��ɃV�t�g���Ă���B�����뎄�̗��e��m���Ă���͉̂�X�v�w�݂̂ł���A�q�����������w���Ŗő��ɉ���Ƃ��Ȃ����������̓I�v���o��L���Ƃ��Ă͂Ȃ����낤�B
�@����ł��Ƒ��ꓯ�͖~�̕�Q��s���ɂ͎Q�����Ă����B
�@�c���������ɂƂ��Ă��̖~�̎����ɉƑ��S�����c�ɂɂ����ɏW�܂�A������ꂢ�ɂ��A�Ԃ�����A�{���Ō����ɓnjo�������Ă��炤���́A���̈Ӌ`�Ȃǂ͂قƂ�ǒ��ڋ��������͂Ȃ����A���̉Ƒ�12�l�����̕�𒆐S�Ɋɂ₩�Ɍ���Ă��邱�Ƃ����o���Ă����ߒ��ɂȂ�̂��낤�B�܂��A���{�̏@���I�����̈���ɐڂ����̕��͋C�𖡂���Ă������ƂɂȂ邾�낤���A�������ɂƂ��Ă���͐l���̒��ł̏d�v�ȑ̌��ƂȂ�B
�@���̈Ӌ`�͍���̐l���ɂƂ��Ă̐S�̋��菊�ɂȂ���́A�Ǝ��͐M���Ă���B�����A���͂��������Ӗ��ł̏@�����͂��邪�A�����Ύ��͂ǂ̏@���ɂ��A�˂��Ă��Ȃ��A�ǂ��炩�ƌ����Ζ��@���Ȃ̂����A���{�̏@���I�s���ɂ͑f���ɉ����Ă��邾���E�E�E�A�Ɠ�����s���҂̈�l�ł���B
�@���ۂɂ́A�������ɂƂ��Ă͂ɂƂ��Ă͕�Q��O��̃~�j���s�̕����y�����̂͘_��҂��Ȃ��B
8/16�i���j���������@
1:30�N���B�Q�ꂵ����B�����E�Ǐ��B�ߑO�x�݂Ȃ���M���J�ǂ̈�Ƃ���8:30���ʃ��n�ɂċƖ����Ȃ��B�����A�V���`�F�b�N�A���́B���ޓ������B13:00�A14:00�Ƒ��ʒk�A14:30-15:30�����J���t�@�A�Ǘጟ����B�a���Ή��A19:00�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B
8/15�̓|�c�_���錾�����(2)�@�����̋]���Ґ������ڂ����悤�ɂȂ��Ă���
�@����E���ł͈�ʎs����80���l���u��P�⌴�q���e�������Ŏ��S�����v�Ƃ���Ă���B�������A���̎��Ԃ͒肩�ł͂Ȃ��B�����̐틵�ł͎��҂̋�̓I�Ȓ����Ȃǂ͍s���Ȃ������ł��낤�B
�@����ɑ��āA����̃��V�A�̃E�N���C�i�N�U�ł͔�퓬���̋]���Ґ��͕s���S�Ȃ���A���̂��Ƃ�����Ă���B
�@���A�̏��@�ւ�l��NGO��������Q�̃f�[�^�����I�ɒ����E���\���A��l�ЂƂ�̎s�������V�A�R�̐푈�ƍ߂��X�}�z�Ɏ��߂Ă���B
�@�l���Ď��c�̓E�N���C�i�푈�̊J�n����500���Ԃ�9��l�ȏ�̕������E�Q���ꂽ�Ɣ��\�����B���ۂ̋]���҂͂͂邩�ɑ������낤�ƕt���������B�����Ƃ͐E�ƌR�l�łȂ����̂��w���B������Q�̐��m�Ȕc���͗e�ՂłȂ��B
�@�댯�Ȑ��Ő��m�ȃf�[�^�����W���邱�Ƃ͂�������������A�����Đ푈�������́A�s���������f�[�^����₂�����A������퓬�����ƋU�����肷��B����ł��A���X�̐�������z���A������Q�̐��m�Ȕc���ւ̎��݂͒����ɔ��W���Ă����B
�@���̐��i�͂́A�l��NGO�⍑�ۑg�D�A���Ƃ��`������O���[�o���Ȑl���l�b�g���[�N���A�Ƃ����B
�@������Q���L�^����A���������悤�ɂȂ����̂͂������\�N�̂��Ƃ��B
�@��2�����E����̃W���l�[�u�����(1949�N)�ł悤�₭�펞�̕����ی삪���������ꂽ���A���̗��s���Ď����鐧�x�݂͐����Ȃ������B
�@�l���@�ᔽ���E��������NGO���o�ꂵ�A�O���[�o���Ȑl���Ď��̃l�b�g���[�N���`�����n�߂��̂́A1970�N��ȍ~�̂��ƁB
�@ �펀�҂ɂ��Ă̎������𖾂��Ă����͖߂�Ȃ��B
����ł��A�L�^������L��������m�炸�m�炸�̂����ɖ��������Ƃ����ň��̖\�͂��炻�̐l���~����B
�@��l�̐l�Ԃ̎��͔ߌ������A100���l�̎��͂��͂ⓝ�v�ł���B
�@�푈�͐l�Ԃ̎��̏d�݂�ς���B ���������̂Ȃ����𐔂���̂Ɂu��v�����\�c�ꗍ���Ɉ�����B
�@�펀�҂��Ƃɕ����̔�Q�͂ǂ̂悤�ɂ��Đ��l�ɒu���������Ă������B
�@ �u�펀�ҕی�v�܂��̂�ی삷�鍑�ۋK�͂����������ꂽ�̂�1906�N�B ����ԏ\���A���͍��A�Ȃǂ����̈�́A���m�̐g�������L���^�O�A�◯�i�A�����ꏊ�̋L�^�Ȃǂ͂��A���Ґ��𐄒肵�Ă����B
�@�����Q������ō��Ƃ��R�����Ǘ�����O�����ƁA ���Ґ��̐���͂�荢��ɂȂ�B����NGO��l���c�̂̃l�b�g���[�N�A���v�w�Ɛl����肪�L�ӂɌ��т����B
�@�ނ�͐����҂̏،���O�O�Ɏ��W�A���H�҂̖c��ȃf�[�^�x�[�X�ƁA������̐����҃��X�g���Ƃ炵���킹�Đ����m�F���s���B DNA�����Ȃǖ@��w�̎�@�Ńo���o���̈�̂��č\���A���E�⍉��Ȃǂ̎����܂œ��肷��B �Ȋw�I�ϋv���̍����f�[�^�͍ٔ��Ŗ@�I�؋��ɂȂ�A���_�����������ƂɂȂ�B
�@��������}���Ȃ��R�����͈͂�̂����x�����ߒ����ȂǂŒ�����W�Q�B �t�F�C�N�j���[�X�Ŏ��Ԃ𝘗����A���ɒ������̖��܂ő_���B
�@�V���e�Ђ͍ŋ߁A�E�N���C�i�̖��ԋ]���҂��u��1���l�v�Ɠ`�����B�f�[�^�̌��������ɂ́A�����Ȃ��]���҂̑��݂𖾂炩�ɂ��悤�Ƃ���҂����̂����ЂƂ̓w�͂�����B
�@�푈�̔�l�����𖾂炩�ɂ���ɂ́A�����̋]���҂̔c�������������Ƃ͂ł��Ȃ��B�M�d�ȓw�͂Ǝv���B�@�@
8/15(��) �|�c�_���錾������@���������@���ʕa�@�O���@
1:30�N���C�Q�ꂵ�������B�_���ǂ݁A�f�[�^�����E�������A5:30�R�S�~��o�A�g�}�g���n�A6:40�o�X�͖����܂ŋx���̐��A40���ߏ��̌����̓��A�ő҂B7:17�ɏ��B���̊�iPad�Ŗ{�ǂ݁B�a���Ή��A8:45-12:00���ʕa�@�O���A��ȍ������@������!!! AMI�Ƃ����B���ʃ��n�a�@�A��������ȂǁB�����A13;00-15:00�r�X�C��a���Ή��B19:30�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B������Ƃ͎��j��̃o�[�x�L���[�ɁB
8/15�̓|�c�_���錾�����(1)�@�������I�����9��2���@�䂪���Ɛ��E�̋]���Ґ�
�@�����m�푈�I������{����78�N�B���N�͊J�킩��82�N�ɓ�����B
�@�����O�̑����̋]���҂Ɉ����̈ӂ�\���A���a�̑������Ċm�F���A����ւ̐����ɂ��čl�������B
�@���N8��15���̓|�c�_���錾������ł��邪��ʓI�ɂ͏I��L�O���Ƃ��đ������Ă���B��̑��ɂ����ĖS���Ȃ�ꂽ���X��Ǔ������a���F�O���邽�߁A�u��v�҂�Ǔ������a���F�O������v�Ƃ���Ă��ĒǓ����T�������Ȃ���Ă���B
�@���T�ɂ́A�ݓc�������n�߁A�O�c�@�c���A�Q�c�@�c���A�ō��ٔ��������A�W�c�̂̑�\�A�⑰�̕��X�Ȃǂ��Q�A��̑��ɂ�����S��v�҂ɑ��ĒǓ��̐������������B
�@�Ǔ��̑Ώۂ́u����E���i�����푈/�x�ߎ��ρE�����m�푈/�哌���푈�j�Ő펀���������{�R�R�l�E�R����230���l�v�ƁA�u��P�⌴�q���e�������Ŏ��S������ʎs����80���l�v�́A�u���{�l��v�Ҍv��310���l�v�ł���B
�@ ���T�͐��{��Âōs���B
�@����E���̍��ʂ̐펀�Ґ��́A�\�A��1450���l���}�����đ����A�h�C�c��280���l�A���{��230���l������Ɏ����B
�@�A�W�A�E�����m�n��̌R���̋]���Ґ��̓t�B���s��100���l�A�x�g�i��200���l�A����1000���l�ȏ�E�E�E�ȂǂƂ����B
�@
�@���{�l���҂�9����1944�N�ȍ~�̐푈�����ɏW�����ĖS���Ȃ����Ɛ��Z�����B���̂قƂ�ǂ͐퓬���ł͂Ȃ��B30���l����C�v�������B�R�̖R�����⋋�͂�w�i�ɍl����قǂ̕��m���h�_���r�߁A�쎀�E�a���Ŗ����������B�܂��A���U�Ȃǂ̗��s�s�ȍ��Ŗ����������B
�@�Ȃ��䂪���̎��҂�����قǑ�����Ƃ̎��𐋂����̂��A���ɂ�镪�͂͂���̂��낤���B���͖��w�ɂ��Ēm��Ȃ��B
�@���̌����┽�Ȃ��Ȃ��A�]���ҒB���܂Ƃ߂ĒǓ�����͎̂��҂̗�Ɏ���ł͂Ȃ����A�Ƃ����v���Ă���B
�@��l��l�̐l�Ԃ̎��͔ߌ������A100���l�̎��͂��͂ⓝ�v�ł���B
�@�푈�͐l�Ԃ̎��̏d�݂�ς���B ���������̂Ȃ����𐔂���̂Ɂu��v�����B
�@�Ԏ��ЂƂŋ��o����̋���Ƒ��ɕʂ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��������m�����A�����ɂ͂����̐l�����������͂��ł��邪�S�Ė��E����ē��v�I���l�ƂȂ��Ă��܂��B��ނȂ����Ƃ��Ǝv���Ȃ���A���͐S�₷�炩�ɂ͑������Ȃ��B
�@8��15���́A�قƂ�ǐ푈��m��Ȃ�����̎��ɂƂ��Ă��d�������̓��ł���B
8/14�i���j ���N�N���j�b�N�x�f�@���ʃ��n�x�f�@
�@3:00�N���B������V���A��w�_���`�F�b�N�A�^���f�[�^�����B10:00��f�ɍs���Ɠ��ɓ���A����̃R�C�ɋ��a�B���ʃ��n�a�@�B12:00�y�H�A�Ǐ��A�����A�V���蔲���ȂǁB18:00�A��A19:00�[�H�A20:30�A�Q�B
�픚78�N�ڂ̉�(5) �@���A�@�\�s�S�ō��ۖ@�͂قڌ`�[��(2)
�@���ێЉ�ɍ��ۖ@�Ƃ����K�͂����݂��邱�Ƃ������B�������A��{�I�����̊m�F�����ł���������͖R�����B
�@���ۖ@�̗��������ƁA19���I�ȍ~�A���ۓI�̏��i����A���{�A�o�����債�A��ʁE�ʐM��i�����B����ɂ�āA���ۖ@�̕K�v���͑����Ă���B
�@�ʏ��q�C�����͂��߁A�̎��W�A�ƍߐl���n���A�X�ցA�d�M�A�S���A���쌠�A�H�Ə��L���Ȃǂ��K�����閳���̏��������A���ۖ@�̓��e��L�x�ɂ��Ă����B
�@�����̒��ł͍��ۖ@�͈ꕔ�@�\���Ă���A�ƌ�����B
�@���ۖ@�͍��ƊԂ̑Η��W�Ɋւ��Ă͖��͂ł������B
�@?��ꎟ���E���ȑO
�@�푈���̂��̂����s���鍑�Ƃ̍s�ׂɂ��ẮA�܂��������C���A�@�I�K���̑ΏۂƂ��Ȃ������B����ΐ푈�́A���Ƃ̑�`��F�߂�����Ō�̎�i�Ƃ���Ă����B
�@?��ꎟ���E���ȍ~
�@�N���푈���Ȃ킿�U���푈����@�������ʓI�ȏ����Ă����B���ۘA���K��A�s����A���ۘA�����͂͂��̑�\�I�ȗ�ł���B
�@?�ĉp�̃C���N�U���@
�@2003�N3���A�ĉp�Ȃǁu�L�u�A���v�͈���I�ɃC���N�U�����n�߂��B2001�N�̃A�����J���������e�����������������ɁA�A�t�K�j�X�^���ɑ����āA�C���N��W�I�ɂ����B����ɂ���ăt�Z�C���̐����A�������Ȃ������B
�@�����ł͐N���푈�̈�@���́A���E�̂��ׂĂ̍��ɂ���Ė@�I�Ɋm�M����Ă���E�E�E�ƁA���V�A�̃E�N���C�i�N�U�܂ł͎v���Ă����B���������v���Ă����B
�@�������Ȃ���A���ׂĂ݂�\�A�A���V�A�������ƌ����Ȃǂ�������������Ă��Ă���B�����ɂ��Ƃ܂��Ȃ��قǂł���B
�@������2���Ԃ̏���͂��Ẵ\�A�A���V�A�ɂ���Č����ɔj��ꂽ�B���V�A�̕s�M���͎��ɂ����邪�A���ׂĂ݂�Ή��Ă̗��j�͑��s�M���Ɋ�Â��Ă���ƌ����Ă����B
�@�䂪���Ƃ̊Ԃł��A�\�A�͓��\���������ɂ�������炸1945�N�i���a20�N�j8��8���ɑΓ����z�����s���킸��1�T�Ԃŋ��v�̗����B
�@����ɂ����{�͐�㒾�ق��A�ƍߐ���₤���ƂȂ��L�떳��ɂ����B�V�x���A�}���Ƌ����J�������l�ł���B�V�x���A�}���ɑ��鍑�̌��������͕��������Ƃ��������Ƃ��Ȃ��B
�@����̃��V�A�̃E�N���C�i�N�U�͍��A�̏�C�������ł���A�j�ۗL���ł��郍�V�A���A�����̗̓y�̈�̐�����I�Ɨ����������͂̍s�g���ւ������A���͂⍑�ۖ@�����A��K�͂ȕ��͍s�g�ɂ���Č���ύX�������B
�@���V�A�͊j����ȂǑ�ʔj��̎g�p����������Ă���B
�@����ɁA���V�A�R�͖��Ԑl��W�I�Ƃ����l���I�ȍU���������炳�܂ɍs���Ă���B
�@���V�A�͔ᔻ���Ă��邾���ŁA�ǂ�������R���I�����I�}�����Ă��Ȃ��B�v�[�`���ᔻ�͉���������ʂ����Ă��Ȃ��B
�@���ۖ@�͖��Ƃ͌����Ȃ����A���̒��x�̗͂����Ȃ��B
�@���{�̑�w�ɂ����ۖ@���w�҂��吨���邪�A�قƂ�ǒ��ق��Ă���B���̂Ȃ̂��H ���Ƃ��Ɗw�҂̑��݈Ӌ`�͂���قǂȂ����A�����������M���Ă����̂ł͂Ȃ��낤���B���݈Ӌ`�������B
8/13�i���j�����ߑO�܂�̂������A�����@��Q��@�A�H�@�r���o�b�O�Y�ꎛ�Ɏ���
5:00�N���A�����A�Ǐ��A10:30��ϔ��]�ݎ��ɁB11:30�Z�E�̓njo�����������B12:30���U�A�R�̌Z�M��K��A�Z�ŏ�C�����ŕs���ƁB�r���o�b�O�Y�ꎛ�Ɏ��ɁB���j�̎Ԃ��̏Ⴕ���A�Ƃ����B�ڍוs���B17:00���ʃ��n���A�a���Ή��B20:45�A��[�H�B21:45�A�Q�B
�픚78�N�ڂ̉�(4) �@���A�@�\�s�S�ō��ۖ@�͂قڌ`�[��(1)
�@���ۖ@�͑��݂���B�������Ȃ���A�ƂĂ��Ǝ�ł���B�ƂĂ��@�ƌ�������̂ł͂Ȃ��B
�@�e�Ɨ����ł͍����@�͏[�����Ă��Ă���B
�@���{�̍����@�ƍ��ۖ@���r���Ă݂�Έȉ��̂悤�ȍ��ق�����A���ۖ@�̖�肪��������ɂȂ�B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�@�����@�@�ւ��Ȃ�
�@���ێЉ�ɂ͊e���̋c��ɑ�������悤�ȗ��@�@�ւ��Ȃ��B
�@���̂��߁A���ׂĂ̍��Ƃ��S�����鋭���@�ɂȂ肦���A���O�I���K�I�̌`�Ԃł������݂����Ȃ��B
�@���ٔ��@�ւ����Ȃ�
�@���ێЉ�ɂ͍ٔ��@�ւ��Ȃ��B
�@���݂ł͍��ۘA���̎�v�Ȏi�@�@�ւƂ��č��ێi�@�ٔ������݂����Ă���B����̃��V�A�̐푈�ƍ߂�_����ۂɂ����ܘb��ɂȂ��Ă���B�������A�������Ԃ̍��ӂ��Ȃ���ٔ��ł��Ȃ����ƂɂȂ��Ă���B
�@���̌��ʁA���ۖ@�Ɉᔽ���镴���ł��A�ٔ����̔��f�ɕ�����Ƃ͌���Ȃ��B�ʂĂ��Ȃ����|���_���J��Ԃ��ꂽ��A���_�܂Ŏ��炸�ɐR�c���I������\��������B
�@���@�̎��s�@�ւ��Ȃ�
�@���ێЉ�ɂ͖@�̎��s�@�ւ��Ȃ��B
�@���Ƃ̏ꍇ�ɂ́A�x�@�Ȃǂ������Ĕƍ߂�h�~���������ێ����邩��ٔ����̔����������I�Ɏ��s�ł���B���ێЉ�ɂ́A����I�Ȍ��͓I�@�ւ͑��݂����A���ۖ@�ᔽ�������I�ɊĎ��E���s���鐧�x���Ȃ��B
�@�N���푈�ɑ��č��A���h�~�[�u�⋭���[�u���Ƃ鐧�x�͂��邪�A���̎������͕ۏ��Ȃ��B
�@����`�b�N�ʼn��z�̘b�ł��邪�A���A�ɍ��A�R�������č��ۏ��ᔽ�̍��ɗ͂��s�g�ł���Η}�~�͂ɂȂ邪�A�����ɂ͂��蓾�Ȃ��b�ł���B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�@���ۖ@�ɂ́A���̂悤�ȐƎ㐫������B
�@������A�@�̕��͂ɂ�����Ȃ����x���̋@�\�����Ȃ��B
8/12�i�y�j�H�c���ꏋ��!!�ߌ㐷���~�J�������@�Ȃ������ς�
�@2:15�N���A�����`�F�b�N���A�{�ǂݓ��B�U���A���n�B10:00���ʃ��n�A12:30�����Ɍ����o���B14:00�����������~�J�B�䕗�̉e�����H�H�@15:00�z�e����ϒ��A�l���ɕω�����B15:30���j������Ƃƍ����B�{�ǂݒ��S�A�����A19:15�[�H�A�r���b�w�X�^�C�������ŁB21:00���U�A�A���B
�픚78�N�ڂ̉�(3) �@�����ٔ��̗e�F�̉e�����ł����������Ă����@
�@���́A�����ɂȂ��Ă��郍�V�A�̃E�N���C�i�N�U�A��퓬���̎E�C�A�j����g�p�̋����́A�����ٔ��ŘA���R�A�Ƃ�킯�A�����J�̐푈�ƍߍs�ׂ�L�떳��ɂ��ė������{���{�̑ԓx�ɒH�蒅���A�Ǝv���B
�@�����ٔ�(�ɓ����یR���ٔ�)�́A1946�N�i���a21�N�j5��3������1948�N�i���a23�N�j11��12���ɂ����čs��ꂽ�B�폟�����s�퍑������I�ɍق��Ƃ����I�ȍٔ��ł������B
�@A���u���a�ɑ���߁v��25�����L�ߔ������A����7�������Y�ƂȂ����B
�@�������Ȃ��ƂɁA��ɓ��{���{�͂��̔�����������A�u�ًc��\�����Ă闧��ɂȂ��v�Ƃ����������������B
�@�Ɨ��̂��߂̐������f�������Ǝv�����A���{���u�l�ނ̗��j�I�ƍ߂�e�F�v�����Ƃ����p���ō��ۓI�ƍߍs�ׂɑ傫�����S�����A�Ǝ��͎v���B
�@�����ٔ��ł́A
?���q���e�̎g�p�A
?���Ԑl��W�I�Ƃ��������ʔ����A
?�E�E�E�E�E
�Ȃǂ̍��ۖ@�ᔽ�s�ׂ͈�؎��グ��ꂸ�A�ؐl�̋U�؍߂����ꂸ�A�ߌY�@���`��@�̑k�y���Ȃ������B
�@�����������ׂ̑�������A�����ٔ��́u�ٔ��̖��ɂӂ��킵���Ȃ��A�P�Ȃ����I�ȕ��Q�̋V���ł���A�S�ے肷�ׂ����v�Ƃ̈ӌ������Ȃ��Ȃ��A���ۖ@�̐��Ƃ̊Ԃł͖{�ٔ��ɑ��Ă͔ے�I�Ȍ���������҂������B
�@�T���t�����V�X�R���a���́A1951�N9��8������A1952�N4��28�������������A����ɂ��A�����ɂ���̂͏I���A���{���͎匠�������B
�@���{�́A�����ٔ��̔��������ꂽ���A�����ɐ����I���f���s��ꂽ�B
�@�������Ȃ���A���{�͍ٔ��Ƃ͕ʂɘA�����R�̍s�ׂ̖��_�𖾂炩�ɂ��ׂ�����͎c���Ă����ׂ��������B����A���ꂩ��ł����炩�ɂ��ׂ��ł���B
�@�ܘ_�A���{�̐푈�ƍ߂ɂ��Ă����炩�ɂ����ł��낤���A���ꂪ���j�w�҂ɉۂ���ꂽ�g���ł���B
�@�ݓc��t���́AEU��o�C�f���Ɠ������ĊO����ɐi�߂Ă���B
�@���̍ہA�e���ɑ��u���V�A�̃E�N���C�i�N�U�͖��炩�ɍ��ۖ@�ᔽ�ł���E�E�E�v�Əq�ׂĂ��邪�A����E���̈�@�s�ׂ�e�F���Ă����Ƃ������j���l����A���{�̑Ή��͐����͂������B
�@�m���ɁA�����ٔ��̎���͍��ۖ@�͂܂��\���Ȃ��̂ł͂Ȃ������B
�@���͂ǂ��Ȃ̂��H���ł������͂�Ȃ��������@�łȂ��̂��H
�@����Ȍ��̖͂����@��O�ʂɏo���Ď咣���ĉ��ɂȂ�H�Ƃ͎v�����A���ꂵ�������悤���Ȃ����Ƃ������ł���B
�@���{�͓����ٔ���������A�č��̐l�ޏ��̔�l���I�s�ׂ�s��ɂ��Ă����B���̂��Ƃ����V�A�̃E�N���C�i�N�U���Ɍ��т����B���ꂪ���̊��z�ł���B
8/11 (���j�R�̓��j���@�����@
�@1:45�N���C�����E�V���`�F�b�N���̑��B9:30��ʃS�~��o�Y��Ă����B�m�F���ĊԂɍ��������ʓI�ɏ����݂̂ōςB11:00�Ɠ������R�C�ɋ��a�㒆�ʃ��n�A�a���Ή������B���M�Ґ����B�V���`�F�b�N�A�d�q���A����3���B19:30�A��[�H�A20:30�A�Q�B
�픚78�N�ڂ̉�(2) �j�����p���Ă͂Ȃ�Ȃ��Ɩ��m�Ɏ������͂����??�@
�@�L��/����͔픚����78�N�ڂ̉Ă��}�����B
�@���͂قږ��N�L��/����̕��a�L�O���T���p�����W�I�Œ����Ă���B�Ɩ��ŕ����Ȃ����ɂ͘^������B�]���܂ł͂��}���l�����������T�ƍl���Ă������A��N����͐V�����C�����Œ����Ă���B
�@���N�܂ł͉ߋ��ւ̐U��Ԃ�̗l���A�픚���̔�Q�҈ӎ����傫���������A��N����͖����Ɍ����Ă̊m����ӎv���������T�̂悤�Ɋ���������B
�@�L�����a�����ɂ���L�O��i�������v�҈ԗ��j�͏��a27�N�i1952�j8��6���ݗ����ꂽ�B�����ɂ͌������v�Җ����[�߂��Ί����u����Ă���A�Ί��̐��ʂɂ́A�u���炩�ɖ����ĉ������@�߂��͌J�Ԃ��܂��ʂ���v�Ǝ��̂Ȃ����t�����܂�Ă���B�N�̉߂��Ȃ̂��H�H�܂����픚�҂����ł͂Ȃ��낤�B���{�̌R�����H�H���������A�����J�Ȃ̂��H�H�A�����J�Ȃ�A�g���[�}���Ȃ�[���ł��邪�A�͂����肵�Ȃ��s�v�c�Ȕ�ł���B
�@���̔�̌��t�������{���A���E���j����L�떳��ɂ��Ă������Ƃւ̏ے��̂悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B
�@�Ɨ����ɑ��͂ŐN�����邱�Ƃ͋�����Ȃ��B����������Ȃ��A�Ƃ����̂͂����܂ł����O�����̃��x���ł��邱�Ƃ�����̃E�N���C�i�N�U�ɂ���Ď����ꂽ�B���ۖ@�ᔽ�Ƒ����ł��A�N���v�[�`�����A���V�A���J���Ȃ��B���A�ł���J���Ȃ����A�~�߂��Ȃ��B
�@���A�̋@�\���Ăǂ����Ă����Ȃ��Ă���̂��H�卑�ɋ��ی���^�����w�i�͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��H�H���͂܂����s���ł��̕ӂ̎���͒m��Ȃ��B�����炭�卑���S�l�����ʂł��낤�B�����̉������͂���ȋ@�\�𗝕s�s�Ǝv���Ă��Ă��u�������͂����v�Ƃ������ƂŐ��������̂ł��낤���B
�@��`�咣�͈قȂ��Ă��A���Ƃ��A���V�A�ƗF�D�W�ɂ����Đ����o�ϓI�ɗ��Q�W������Ƃ��Ă��A�ꍑ�̎匠��͂ŔƂ��u���V�A�̖\���ɑ��Ė��m�ɔ����Ȃ����X������v�̂͋����ł���B���̂悤�ȍ��̓��V�A�̍s�ׂ���e�F���邾���łȂ��A�����n���Ύ�������̂悤�ȕ��@���Ƃ�\���������Ă���B
�@����ȍ��͐M�p�ł��Ȃ��B
�@�L���A����̎S�Ђ��o�āA��㐢�E���������Ă������̂̒m��Ȃ��A���Ԃ̂Ȃ��K�͂�����B
�@�u�j������g�����Ƃ͖{���I�ȉ߂��v�Ƃ���A�s�����ł���B�z���Ă͂Ȃ�ʈ���Ƃ��ċ��L����Ă����B�������A���̋K�͂����v�[�`����l�̂��߂ɑ傫���h�炢�ł���B
�@�u�Ȃ�ƂȂ��`����Ă����v�K�͂ǂ��납�C���[�W�I���x���̋K�͂ł����Ȃ������B���͂����v���B�j�����p���Ă͂Ȃ�Ȃ��Ɩ��m�Ɏ������͉������ɂ���̂��낤���B�����Ȃ����낤�B
�@����ł��A���܂ł́A���̃C���[�W�I�K�͂����E���Ă����B
�@����ȃ��x�����������A���̋K�͂�^��������ے肵���̂̓v�[�`���ł������B
8/10(�j���������@���N�N���j�b�N���ʔ���
2:00�N���C�k�R�ق����Ȃ��B������������ނ��늦���B���H���߂��������͏H�̖K�ꂪ�|���B���ʃ��n�A��������B11:00�a���Ή��B14;00���N�N���j�b�N���ʔ���B�����̕��s���M���ł������B19:30�A��[�H�A20:45�A�Q�B
�픚78�N�ڂ̉�(1) G7�𒆐S�Ɋj����ւ̍l�������ς�����@
�@�L���A����Ɍ�������������č��N��78�N�ƂȂ�B
�@��N���܂ł̐��v���҂͍L���Ŗ�14���l�A����Ŗ�7.4���l�B���Ȃ������̔픚�҂����˔\�̉e���ɂ��a�C�ɋꂵ��ł���B��N1�N�Ԃ̔픚�҂̎���5.300�]�l�ɏ��B
�@�L���s��6���A����s��9���ɂ����̕��a���T���J���ꂽ�B
�@�L����5���ɊJ���ꂽG7�L���T�~�b�g�́u�j����̂Ȃ����E�֓����J���v���Ƃ�ڕW�Ɍf�����B�j�R�k�ɏœ_�Ă����̓Ɨ������u�L���r�W�����v�́A�E�N���C�i�N�U�ŕ��f����w�[�߂鐢�E�̌���������ɂ�����̂������B
�@���V�A�̃E�N���C�i�N�U���u�ǂ��Ȃ����Ɓv�ƍl���Ȃ����X�����Ȃ��Ȃ��̂͋����ł������B
�@���V�A�̊j����g�p��F�߂Ȃ��͓̂��R�B���̏�ŁAG7���������j����͗}�~�͂Ƃ��Đ��F����p���������ꂽ�B
�@�]���̊j�֎~�Ɋւ���c�_�͎��Ԃ̂Ȃ����z�_�ł����Ȃ������Ǝv���B�m���Ɋj����͂Ȃ����������B����͈�����ݍ���Ŋj�}�~�L�����B
�@���E��̊j�e�����ۗL���̃��V�A�A����Ɋj������g�[���悤�Ƃ��Ă��钆���A���V�A�Ɠ��l�Ɋj�ɂ��Њd���J��Ԃ��k���N�Ȃǂ̃g�b�v�́A�ȒP�Ɍ����Ή������ׂăo�J���A�Ƃ��������悤���Ȃ��B���̕\���@�͂Ȃ��B�����̃o�J�ɂ́A�j�������Ȃ����a��`�ҒB�����z�_��������q�ׂĂ��Ȃ�̉e�����Ȃ��̂��낤�B
�@���Ȃ��Ƃ����܂ł̊j�֎~�Ɋւ�����j���������Ă���B
�@�Ȃ�A���̖������z���邽�߂̕����T���Ă������Ƃ�����B���̂��߂ɂ͉����K�v���H�H
�@���ӔC�Ȉӌ��Ȃ̂�������Ȃ����A���͊j�̗}�~�̗͂͂���邵���Ȃ��Ǝv���B
�@�j�}�~�́A�p�j����ۗ̕L���A�Η�����ԊW�ɂ����Č݂��Ɋj����̎g�p���S�O���������o���A���ʂƂ��ďd��Ȋj�푈�Ɗj�푈�ɂȂ���S�ʐ푈����������A�Ƃ����l�����ł���B
�@G7�L���T�~�b�g�ł̓��V�A�̊j�Њd�A�g�p�͋�����Ȃ��ƒf��������AG7�Q���������j����́u�h�q�ړI�̖������ʂ����A�N����}�~����͂�����v�j������̕ێ��𐳓��������B
�@���̖����ɖ������s�����A�l�����͊e���ʂ��猵�����]�����Ă��邪�A���͘b���ʗp���Ȃ��悤�ȍ��A�o�J�Ȏw���҂�����j�ۗL�������邩����A�j�}�~�͂ɗ��炴��Ȃ��Ǝv���Ă���B
�@G7��]�݂̂Ȃ炸�A�C���h���̃O���[�o���T�E�X�ƌĂ��V���E�r�㍑�̎�]�炪G7�L���T�~�b�g�ŗ������A�픚�n�ɗ����A�K�ꂽ���������قŔ픚�̎S�Ђ�ڂɂ����Ӌ`�͑傫���B�������A���ꂾ���Ŋj���킪�Ȃ��Ȃ�Ƃ͓���v���Ȃ��B
8/9�i���j�����@���茴������77�N�@
2:00�N���C�Ǐ��A�摜�f�[�^�����A�����E�V���ق����Ȃ��B�r����������B
�����Ȃ�O�Ƀ_���A�̐��b�A���n�A�U���Ȃǂ��Ȃ��B11:50�o�X�A���ʃ��n�a�@�A14:00�a���Ή��A14:30���̃J���t�@�A�]����c�B19:00�ʒ����X�o�R�A��E�[�H�A20:30�A�Q�B
���N�̏H�c�͏���(6)�@40�����̔M�g���p��������Ńq�g�͐����Ă�����̂�?? �\��������
�@�l�̑̉��ێ��̎d�g�݂͔��Ɍ����Ȃ����݂ɂ���Ă���B�Ƃ������Ƃ́A�q�g�͑̉��̋��e�͈͂͋����A�Ƃ������ƁB
�@�������Ȃ���A�q�g�ɂ͒m�b������A�ߕ��⌚�z�A�y�̍H�v�ɂ���Đg����邱�Ƃ��\�ł���B
�@�����A������Ƃ������ƂŁA�̉����߂��j�]����B
�@�M���ǂ́A�k���ȑ̉����߂��j�]����d�Ăȕa�C�ł���B�@
�@�Ɋ����ɂ��̉��ێ��̔j�]�͐V�c���Y�u���b�c�R���̜f�r�v�Ȃǂ̕��w��i�ɏڂ����B
�@�M���ǂ̉����̎藧�Ă͖��m�ɂ���A�M���ǂ����炷���Ƃ͂ł���B
�@�|�C���g�́A?�ُ�ȍ��̉��ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ���B?�M���ǂɂȂ�����A�ł��邾���Z���Ԃɐg�̂��₷���ƁA�ł���B
�@����6���ȍ~�A�}�X�R�~�𒆐S�ɔM���Ǘ\�h�̌Ăт������p�ɂɍs���Ă���B�ɂ��ւ�炸�����̊��҂��~�}�a�@�ɔ�������Ă���B
�@�u�G�A�R����K���ɗp���܂��傤�v�A�Ƃ����Ăт��������ł́A�|�C���g���Y���Ă���B
�@���{�̏��q����͈ꕔ�̎��҂������甼���I���O����w�E����Ă������A�א��҂����͑����Ƃ�Ȃ������B�����镪��ł��̏�Q�������ɂȂ�A�����s�t��ԂɎ��������ɂȂ��ă|�C���g�����ꂽ���q����ő����ł���B����Ɏ��Ă���B
�@�q�g�̑̉��ɒ��ڗ^����e�����d�v�ł��邪�A�ȉ��̗v���̕������傫�Ȗ��ɂȂ�A��K�͂ɐl�ɉe����^����ł��낤�B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
?�C�ʂ̏㏸�ɂ�鍑�y�̍������A
?���\�L�̋C�ی��r���ɂ��V�Ђ̕p���A
?���m�̊����ǂ̐V���Ɩ����A
?�H�Ɛ��Y�ɏd�v�ȐA���������_�ƂȂǂւ̉e���A
?���̐����ւ̉e��
?���s��
?�E�E�E
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\-
�@���݂̏����̖��́A�l�Ԃ̍ی��̂Ȃ��G�S�ɗR�����鐶���K���Ɋ֘A���邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�@�܂��������ׂ��́A?�s�s�̍\���̉��P�A?�l�����z��W���A?�J���⋏�Z�n��̏W���A?�Βn���A?�ړ���i�̍������E�X���̌������A�Ȃǂ��K�v�Ɏv����B �����́A�Z���I�ȓw�͂ʼn��P���\���Ǝv���B
�@40���ɂȂ�̂R�ƗJ�����A���ł�����P��ɑ����������ׂ��A�ƍl����B40�������̓��{�Ƀq�g�͏Z��ł����Ȃ��͂Ȃ����A�G�S�̂܂܂ɂ��Ă�40 ����������ԂɂȂ��Ă��܂��B
8/8�i�j���������@��ԍ~�J��@���ʕa�@�O���@
1:45�N���C�����E�V���ق����Ȃ��B5:30�ƒ�S�~�W�Ϗ��B�Ԓd�̑Ή��U���A���H���߂��A��������������K�A����A���͏H�̑����ɋ��|�����o����B6:40�o�X���ʃ��n�a�@�B7:00-8:00�a���Ή��A8:45-12:45���ʕa�@���ȊO���B�l���̊��ɔ敾�B13;00���n�a�@�A����1���ԁA�Ǐ��ق��B�a���ł͂��~��O�ɂ����_�H���̃I�[�_�[���߂���B�V���@����B���ܕ��p���ҁB19:20�A��[�H�B20:30�A�Q�B
���N�̏H�c�͏���(5)�@������G�A�R���͓��{��
�@���݂̃G�A�R���͐l�Ԃ̖���M�g������ɂ͕K�{�̃A�C�e���ɂȂ��Ă���B
�@��1���I�̗��j�����̑�Ȕ����ł͂��邪�A�g�p�����}���A�d�͂̏���̖ʂ�����n�����ւ̕��ׂ��傫������B
�@�l�Ԃ̌��N�ƒn��������邽�߂ɐV�����A�C�f�A�̃G�A�R���̕K�v���͖��炩�ł���B
�@�č��̃V���N�^���N�A���b�L�[�}�E���e���������͂��̂��߂ɍŋ߁A���ۃR���y���J�Â����B�D�������͓̂��{�̃`�[���A �����̃`�[���ł���������̋C���M�𗘗p���ăG�l���M�[��������炷�������̗p���Ă���B ���̕����̃G�A�R����2025�N�܂łɏ��i������錩���݁B
�@�É��s�ɂ���GF�Z���͏]���Ɣ�ׂĔ����̏���d�͂ŁA��[�@�\�Ɗ��C�@�\�𗼗����A��r�M�Œn�����g���h�~�ƌ��N�I�ȎЉ�̎����ɍv������V�X�e���A�t���b�V���E�t���[�E�G�A�R���wFFA�x���J�������B�����I�ɂ́AGF�Z�����J���������z�����d�ƔM������ɍs����̌^�p�l����g�ݍ��킹�邱�ƂŁA����d�̓[����ڎw���A�Ƃ����B
�@FFA�͐��̏����ɂ���ċ�C���₷���߂Ƀt�����Ȃǂ̗�}�s�v�ŁA������C��ʂ������ŗ�[���\�B�d�͂͑����ɂ������p����Ȃ��Ƃ������z�I�ȍ\��������(�ڍׂ͏ȗ�)�B
�@���E�̋V�X�e���s��́A2019�N�̖�9.7���~����2025�N�ɂ͖�14.1���~�Ɋg�傷��Ɨ\�z�����B���Ђł͕����q�ɂ�H��A�I�t�B�X�Ƃ��������ƎҌ����𒆐S�Ɏ��Ƃ�W�J���n�߂Ă���A���̂�����10%���x�́uFFA�v�ւ̒u���������\���ƌ�����ł���B
�@�ƒ�p�G�A�R���Ƃ��Ă��������\�肳��Ă���Ƃ����B
�@�H�c���ߔN�����Ȃ��Ă��Ă���B������S���Ă���Ă���Έ䂳��̊�]�������ĉ䂪�Ƃł�2019�N6���ɋ��ԂɃG�A�R����ݒu�����B�m���ɂ��̋G�ߑ䏊�ʼn��g���̂͑�ςł��낤�Ǝv�����B���̐������ԑт͑����̂Ȃ̂ł��܂�K�v���������Ȃ����A���ɂ͂���Ȃ�ɗ��p����Ă���悤�ł���B
�@���̏��ւ͌ߌォ��[���ɂ����Đ��z��������B�A�Q���͂ƂĂ���������@�����p���Ċ�������ԂŖ����Ă���B�H�c������Ȃ�Ƃ��Ȃ��Ă���Ǝv���B�����Ə����n���ł̓G�A�R���ɗ��炴��Ȃ����낤�B
8/7�i���j�����܂�̂�����A�����@�[���~�J�@���N�N���j�b�N�h�b�N�@�@
�@1:30�N���B�����`�F�b�N���B�G�b�Z�C�ǂ݁A�f�[�^�����B5:00�A�}�����X�����A1������3���ɁB��肭���t���������B�U���B6:40�o�X���ʃ��n�a�@�A7:00-8:10�a���Ή��B9:00-11:30���N�N���j�b�N�B15�l�A���ʔ���12���A11:45���ʃ��n�a�@�ɁB�����A�Ǐ��A�f�[�^�����B15:00�a���Ή��B16:00�H��X�^�b�t2�����K���k�B19:10�A��A�[�H�A21:00�A�Q�B
���N�̏H�c�͏���(4)�@���݂̃G�A�R���̖��_
�@�M�g���疽�����ɂ̓G�A�R���̈Ӌ`�͑傫���B�G�A�R���̐ݒu�䐔�́A���E���Ō��݂�16���䂩��21���I���܂ł�56����ɑ�����ƁA���ۃG�l���M�[�@�ւ͗\�����Ă���B
�@�����A���������ƂɁA ���̃G�A�R���̕��y�͒n�����g������������B
�@���ďZ��ɃG�A�R����ݒu����̂́A�x�w�����ɋ����ꂽ�ґ����B������
�ł͐��E�e�n�ŁA�G�A�R���͔M�֘A���̗\�h�Ɍ������Ȃ����u�ɂȂ����B
�@�唼�̃G�A�R���̎d�g�݂́A�t�̏�̗�}���z���t�̂���K�X�ɋC������ߒ��ŁA�����̋�C����M�Ǝ��C��D���B �����̊O�ɂ͎��O�@���ݒu����Ă��āA�K�X�ɂȂ�����}���Ăщt�̂ɖ߂��A�M����o����B
�@1���I�̗��j�������̓Ƒn�I�ȕ����ɂ͎l�̖�肪����B
--------------------------------------------------------------------
?��ڂ́A��ʓI�ɗ�}�Ƃ��Ďg����n�C�h���t���I���J�[�{�� (��փt����) �͂��ꎩ�̂��������ʃK�X�ł���A�����ɘR��o���A���q1�Ŕ�ׂ�Ɠ�_���Y�f�̉���{�ɂ��̂ڂ�Ƃ݂��鉷�����ʂ�����B
�@�����g���I�[���c�菑�Ɋ�Â��A��i���͗�}�Ɏg�p����t�����ނ�2011�`2013�N�̕��ϒl����2024�N�ɂ�40%�ȏ�A2029�N�ɂ�70%�ȏ�팸���Ȃ���Ȃ炸�A�Ή��̂��߂ɑ���ȃR�X�g����������B�܂��A�t������}�ɂ͉Ў��ɗL�ŃK�X���������錜�O������B
?��ڂ́A���̃G�A�R���ł͔M�����O�Ɏ̂Ă邾���B��ԂɃG�A�R���̎g�p�ɂ��A���O�̋C�����ő�1���オ���Ă���Ƃ����f�[�^������B
?�O�ڂ́A�G�A�R�������ɂ͑�ʂ̓d�C���K�v�B ���̗ʂ͐��E�̓d�͏���̖�8.5%���߁A�唼�͍������ΔR���œ����Ă���B 2016�N�ɂ̓G�A�R���̎g�p�ɂ�鐢�E�̓�_���Y�f�̔r�o��11��3000���g���ɂ̂ڂ����B2050�N�܂łɂ��̐�����2�{�߂��ɂȂ�Ɨ\�z����Ă���B
�@���̂܂܃G�A�R���̐��E�I���y���i�W����A�n�����g��������ɉ������邱�Ƃ��z�肳���B
?�l�ڂ́A���ʓI�Ȋ��C���ł��Ȃ����ƁB��}�g�p�̃G�A�R���ɂ́A���̉ۑ�ɑ�������������Ă��Ȃ��B
--------------------------------------------------------------------
�@���܁A������̃G�A�R�������p���r��ɂ���A�䂪���̋Z�p�����҂���Ă���B
8/6�i���j�������� �Ɠ��ŏI���@�L����������78�N
�@1:30�N���B�Ǐ��A�k�R�A���y�֘A�f�[�^�����B���ɉ̗w�ȂɏW���B�k�R�ȂǁB7:30�_���A���ɎT���A�A�}�����X���������A�f�[�^���͂ق��B8:15�ԗ�ՁA���̌�͕����Ė����A�Ǐ������w�ɁB�̂ǎ����y���ށB14:30�Ɠ��ƂƂ��Ɉ���R�C�ɋ��a�㒷�艮�Ï��X�o�R���ʃ��n�ɁB�a���Ή��B���M�Ґ����B19:00�A��A�[�H�B20:30�A�Q�B
���N�̏H�c�͏���(3)�@���O���M�g����
�@�Â��b�ł��邪�A���e�I�ɂ͌Â��͂Ȃ��B�߁X�̖��ł�����B
�@2003�N�āA�t�����X���P�����M�g�ŋC�����댯���40���ɒB�������8���Ԃ��������B�����̃t�����X�̓G�A�R���̕��y�����Ⴍ�A����҂�����ŔM���ǂɂȂ��Ď��S���鎖�Ⴊ���������B
�@�a�@�ɂ͊��҂����ӂ�A��̈��u�������t�ɂȂ��āA�①�g���b�N��H�i�s��̗①���ɂ܂ň�̂��^�э��܂ꂽ�B
�@�ŏI�I�Ƀt�����X�ł͔M�g�ɂ�鎀�҂�1��5.000�l�]��ɂ̂ڂ��� �B
�@���B�嗤�S��Ŏ��҂�7���l�ȏ�B���̌�̕��͂ŁA���̔N�̉Ă̏����͉��B�ł͉ߋ�500�N�Ԃōō����L�^�������Ƃ��킩�����B
�@���ُ̈�Ȗҏ��͖��炩�ɋC��ϓ��Ɗւ�肪����B
�@�C��ϓ��ł́A�З͂𑝂��M�ђ�C���A���A �C�ʏ㏸�A�X�щЃV�[�Y���̒������ȂǁA�n�����g���Ɋ֘A����Ƃ݂���ٕς����X�Ɩ��炩�ɂȂ��Ă��邪�A���̂Ȃ��ł��A�M�g�̑����͓��퐶���ɂ����ɋ����B
�@���B�ł́A2003�N�̔M�g�͂��͂�ٗ�ł͂Ȃ��B �Ȍ�5�����K�͂ȔM�g���P
���A2019�N�ɂ̓t�����X��46���ȂǁA������6�J���Ŋϑ��j��ō��̋C�����L�^�����B
�@�n�����g���ɑ��������͉������ʃK�X�̑啝�Ȕr�o�팸�ł��邪�A����̂܂ܔr�o�������A�č��ł�2100�N�܂łɔM�g�֘A���҂͔N��10���l����Ɨ\������Ă���B�C���h�ł͔N�Ԃ̎��҂�150���l�ɂ̂ڂ�\��������Ƃ����B
�@���Ƃ��r�o���팸�ł��Ă��A�C���̏㏸�͍��㉽�\�N�������B �ɒ[�ȋC�ی��ۂ͂����ɂ͎��܂炸�A�l�X�̐����͑傫�ȕω��𔗂���B
�@���̍��ۏ���猩�Ĕr�o�팸�͍���ł���A�ُ�C�ۂ͍���������Ǝ��͎v���B
�@���̒��Ől�ނ͐����Ă����˂Ȃ�Ȃ��Ȃ����B
�@�ҏ��́A���Y�����o���̏d���A���Y�̑����Ɗ֘A������Ƃ����Ă���B �ҏ��������Ƥ �����������킸�l�X�͂��\�͓I�ɂȂ�B�q�ǂ��̊w�K���т͉�����A��l�̘J�����Y���͒ቺ����B�_�앨�̎��ʂ͌������H�Ɗ�@�͈�w�Ђǂ��Ȃ�B
�@�l�Ԃƍ앨�Ɖƒ{�͉ߋ�1���N�ɂ킽��A�N���ϋC��13���߂��𒆐S�Ƃ����r�I�����C������̊��Ői�����Ă����B�l�̂͂����荂���̋C��ɂ��K���ł��邪�A�����\�ȋC���Ǝ��x�ɂ͏��������B
�@�G�A�R���̌����������ʼn߂��������Ǝv����������Ȃ����A����͈ꕔ�̕x�T�w�̍l�����ł���A���̃G�A�R���͂��ꎩ�̂��n�����g���𑣂�����ƂȂ�B
�@�������G�A�R�����ł��K�v�Ƃ��Ă���l�����̑����̓G�A�R�����o�ϓI�]�T���Ȃ��B������́A�Z��␅�̊m�ہA��ÃT�[�r�X�̒ȂǁA���L���Љ���Ɛ藣���Ȃ��̂��B
�@�o�ϔ��W���i�߂A�G�A�R���̕��y�����オ��A�N�Ԃɉ��S���l���̖����~����Ƃ����B
�@�G�A�R���̐ݒu�䐔�́A���E���Ō��݂�16���䂩��21���I���܂ł�56����ɑ�����ƁA���ۃG�l���M�[�@�ւ͗\�����Ă���B
�@�����A���������ƂɁA ���̃G�A�R���͒n���ɂ₳�����V�X�e���Ƃ͂ƂĂ��ĂׂȂ���莙�ł�����B
8/5�i�y�j���������@�Ɠ�3����
�@3:00�N���C�Q�ꂵ�������B�����Ɠ����B�Ǐ��A�����A���w�ȂǁB8;00�_���A�ɎU���A�����n�ȂǁB�g�}�g��ʂɎ��n�B�����ɂČp���͖����x���B���w�A�V���`�F�b�N�A�Ǐ��ȂǁB13:00�Ɠ��ɓ���A����R�C�ɋ��a�A�ʒ��o�R���ʃ��n�B�a���Ή��A�V�����́A����3���B19:15�A��B19:00�[�H�A20:30�A�Q�B
���N�̏H�c�͏���(2)�@�M���ǂ͒P�Ȃ�E���ǂł͂Ȃ��A�ɂ߂ďd�ǂȕa�ԂȂ̂�
�@�l�Ԃ̑̂ɂ́A�̉����댯���x���܂ŏ㏸�����Ȃ��悤�A�M����o����d�g�݂���ɓ������Ă���B
�@?��́A���ǂ��L����A �畆�ɔM�������ĕ��o�����Ƃ������́B
�@?���̈�́A ��ʂɔ������������������Ƃ��̋C���M�Ŕ畆���₷�B
�@���������d�g�݂����܂������Ȃ��Ȃ�Ɛl�͎��Ɏ���B
�@�M���ǂő̉����オ��ƁA�g���������ǂɂ����Ղ茌�t�𑗂邽�߂ɐS���Ɣx�̓t���ғ�����B�S���̓������ǂ����Ȃ��Ȃ�ƁA�������}�ቺ���A�߂܂���������A��낯����A�������Ȃ��Ȃ�B ��ʂ̔����ʼn����������邽�߁A �ؓ��̂��������N����B�����̊��҂͈ӎ����������āA�����ɂ��������K�v�ȏd��ȏł��邱�ƂɋC�Â��Ȃ��B
�@��ʂ̌��t���畆�ɑ�����ƁA�E��ɗ��ꍞ�ތ��t������B����ƌ����̒ቺ�������N������A�̔����ŁA�����̑���̍זE���j���B
�@��v�Ȑl�͐[���̉���42���܂ŏオ���Ă������Ԃ��͑ς����邪�A���c���ƍ���҂͊T���ĔM�Ɏア�B���N�ł����Ă��A����ɂȂ�ƔM���ǂ̃��X�N�͍��܂�B
�@����҂��ア���R�̈�́A����ɔ����Ċ��B���������Ȃ褊����o�ɂ����Ȃ邱�ƁB �܂��A �A�̊�������������߁A�\���ɐ�����ێ悵�Ȃ��ꍇ�������B �����Ȃ�Ƒ͎̂c�����킸���Ȑ���������Ȃ��悤�������~�߁A�t�Ɋ��C�����Đk���邱�Ƃ�����B
�@���̎��_�ŐS��������N�������Ƃ����邪�A��茒�N�Ȑl�����싷��⌶�o�ɏP����B�܂��A�_�o���ߕq�ɂȂ��āA�ߕ������ɐG�ꂽ�����ł��Ђ�Ђ�ɂ݁A ���Ă�����̂����X�ɒE���̂Ă�B�������ቺ����ɂ�āA�ӎ����������Ƃ�����B
�@�����܂ŗ���ƐS���܂߁A �ؓ��g�D������ɋ@�\���Ȃ��Ȃ�B
�h�䔽�����ቺ���������ǂ���őf�������ɓ���n�߁A���ǂ̒��Ō��t���ł܂�n�߂�B���̌��ʁA�]��S���A�t���A�t���Ȃǂ̏d�v���킪�@�\��Q�Ɋׂ褂₪�Ď����}���邱�ƂɂȂ�B
�@���̂悤�ɁA�M���ǂ͒P�ɒE���ǂ̔��e�ɂƂǂ܂�Ȃ����G�ȕa�Ԃ����B���Ɍ�����������s�S�̏�Ԃɐi�s������댯�ȏ�ԂȂ̂��B
�@
�@8/4�i���j���ꏋ���@��Ȓ��ʕa�@�@�@�Ɠ������
�@1:05�N���C�����E�V���`�F�b�N���̑��B5:30��ʃS�~�܂Ƃߒ�o�B�U���A���n�ق��B7:40Taxi�w���B8:11���܂��B��Ȃ͉���Taxi�B�A�H�X�ǂŃ��L�֖�B8:55��Ȓ��ʕa�@�O���A���G�B�A�H�̐V�����͏�q���G�A���X�K��Ȃ��A15:20���ʃ��n�a�@�B�a���Ή��B�V���`�F�b�N�A�d�q���̗]�T�Ȃ��B19:30�A��A�Ԃ̓X���[�Y�A�[�H�A20:30�A�Q�B
���N�̏H�c�͏���(1)�@�������͔M���@�C����38�xC���邱�Ƃ�
�@���������������E�I�ɑ����Ă���B
�@�H�c���ƂĂ�����!!! �����͉����ɂ���䕗�̉e������⋭�߂̕����������B�ʏ�Ȃ畗�������Ɛ����o�����ɓ������ė��������̂ł��邪�A�����̂��M���Ȃ̂łނ���h���B����Ȍo���͎��͏��߂Ăł���B
�@�C��ϓ���́A�ً}�I�Ή��Ƃ��̌������ɘa�̓������B�O�҂͉��g���ŋN�������ۂւ̑Ώ��A��҂͋C���㏸��}���銈�����B
�@�ڂ̑O�̖��⌒�N�����s�����K�v���B�����ɁA�C�ی��r���̌����ł���n�����g����ɂ��͂����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̓�̂��Ƃ݂͌��ɖ������܂ށB
�@���g���ɂ��C�ۍЊQ�ւ̉e���͋ߔN�X�p�R���Œ��ׂ���悤�ɂȂ����B���g�������n���ƁA���Ă��Ȃ��n�����X�p�R���̒��ɍ��o���A��r����v�Z���J��Ԃ��ƁA���J��ҏ��̋N����₷���̈Ⴂ���킩��炵���B
�@���̎�@���g���������`�[���́A���Ẳ��B�암��č��̔M�g�́u�n�����g�����Ȃ���N���肦�Ȃ����ۂ������v�Ǝw�E�����B�[���Ȍ�������ڂ����炳���ɁA�C��ϓ��ɐ��ʂ�����������K�v������B
�@�͂����茾���Đ푈�ȂǁA�R�g�Ȃǂ��Ă���ɂ͂Ȃ��̂��B
�@���A�̋C��ϓ��Ɋւ��鐭�{�ԃp�l���iIPCC�j�����N�܂Ƃ߂����́A�C�����Y�Ɗv���O�ɔ�ׂ�1.5�x�㏸����u10�N�ɂP�x�v�̔M�g�̊m����4.1�{�ɂȂ�Ǝw�E�����B���ł�1.1�x�㏸���Ă���A���܂̂܂܂Ȃ�2030�N�܂ł�1.5�x����Ƃ��Ă���B
�@��Ƃ��āA�ҏ��Ȃ�A������⋋���A�K�ɗ�[���g���B���V���ł̊O�o���Ȃ�ׂ������ɂ��ނ悤�ȎЉ�����̂��K���B�T�}�[�^�C���̓K��������@���낤�B
�@����ŁA�����̎�����q�������̂��߂ɁA�Đ��\�G�l���M�[�̗��p���L���ĉ������ʃK�X�̔r�o�����炷�Ƃ����ɘa����}���K�v������B
�@���{��7���̋C���́A�ϑ��j��ō��̏����ɂȂ����B
�@�M�g�͐��E�I�ŁA���A�ł͊e���ɋ�̓I�Ȍ��ʂ����҂ł���s�������߂��B
�@�����A���E�I�ɂ݂Ĕr�o�팸�͒x�X�Ƃ��Đi��ł��Ȃ��B
�@���V�A�̃E�N���C�i�N���ɂ��G�l���M�[��̕ω����e�𗎂Ƃ��B
�@�ăG�l�̉ۑ���������Ȃ��B�����A�ł��邱�Ƃ͂܂������B
�@���z���╗�͂Ȃǒn�Y�̓d�͍͂ЊQ��ɂ��Ȃ�B
�@���Y�G�l���M�[�ł���ăG�l�̊g��ɑS�͂𒍂��ׂ����B�������A�䂪���ł̃G�l���M�[��͌����Ɏw�����Ă���B������C�ɂȂ�Ƃ���ł���B
8/3�i�j���������@�Ɠ�����
2:00�N���A�^���f�[�^�����B9:00���ʃ��n�A���@���ґΉ��A���G�]���ȂǁB10:30-12:30 IVH�}�����w�B13:00�|14:00���҉Ƒ��ʒk2���A�V���`�F�b�N�A�����ȂǁB19:00�A��A�[�H�A20:30�A�Q�B
�ŋߎ��Ԃ�����Ȃ�(2)�@�M���@�u�p���͗͂Ȃ�v����܂���
�@�ŋ߁A���̎��R���Ԃ��s�����Ă���B
�@���̗v���́A?�A�Ɗ��̕ω��A?���N��Ԃ̗A?�������Ԃ�L�����A?�Ǐ��Ɋ������Ԃ����A?���|�┨�͎��̓s����҂��Ȃ��A?����ƂƂ��Ɏ��Ԋ��o���Z�k�E�E�E�ȂǁA�܂��܂����邪�A�債�����Ƃ�����Ă��Ȃ��̂Ɏ��Ԃ���������������B
�@���ʂƂ��ău���O�̋L�q�̎��Ԃ��R�����Ȃ�A�A���X�V�͍���Ȃ悤�ł���B
�@����A��L�̂��Ƃ��̂��܂��܂ȗv�����d�Ȃ����B
�@�����蔲�������肵�Ă����Ԃ����b�`�ɂȂ�킯�ł͂Ȃ����A�����N�[���Ɂu����ȏł̓_�����v�Ƃ��v����悤�ɂ͂Ȃ����B
�@�u�����N��͖߂�Ȃ��v�̂��B������A�f���Ɂu�C���y�ɁE�E�v�A�u���ɂ͑ӂ���ׂ��E�E�v�Ƒ�����ׂ����낤�B
�@�������Ȃ���A���Z���E��w���̎�����ێ��������Ă����u�p���͗͂Ȃ�E�E�v�Ƃ������̐M���̒n�ʂ��t���t���Ɨ������Ă����̂������A�ƂĂ��c�O�ł���B
�@���ꂩ��ǂ������邩�B����͂��܂��Ɍ����Ă��Ȃ��B�N�����A�ǂ�ȔN��ł����Ă��������낤�B�������A7����������V�����X�^�C������ݏo�����Ƃ��Ă���͎̂����B
�@���̐����p�^�[���͑��l�Ƃ͂���Ă��邪�A�u�K�������������ɂ��ĐS�g�𐮂���v�Ƃ����œK�Ȏ�i�������Ă��ꂽ���̐S���̌������Ƃ�f���ɕ����āA�����邱�Ƃɂ���B
�@���́u�p���͗͂Ȃ�v�ƌ������t���D���A�Ƃ������M���Ƃ��Ă����B�Ƃ������A���̏ꍇ�ɂ͍D���̃��x�����z���āA���̌��t�Ɏ��Ɂu��܂���v�A���Ɂu�ǂ��������v�A���Ɂu�Ղ܂�v�Ă����A�ƌ����Ă����B���͂��̌��t�ɂ���Ĉ�Ă�ꂽ�B
�@�v�������ĉ������n�߂��ہA�����ԑ����Ă��܂��ƁA�u�p���v���邱�Ƃ��傽��ړI�ƂȂ��Ă����~�߂��Ȃ��Ɋׂ��Ă��܂��B��q�]�|�ł��邪�A���ɂƂ��Ă͎����ɑ����݂ɂ��Ȃ��Ă���B
�@���́u�p���͗͂Ȃ�v�̍���(�ꕔ)
-------------------------------------------------------------------
�� ���Q���N����s�i1965�`�p�����j
�� �A���o�C�p�����L�^������(1968�` �p����)
�� �k�R�E�u���O�L�ځi2001�` �p�����j
�� �V���X�N���b�v(2008�N�` �p����)
�� ���W�I�[��֘^���ƍĒ�(2008�N�` �p����)
�� ���֕��������Ƃ��Ď�����10���قNJ�t(2011�` �p����)
�� �k���ʋƘA�������L�^(2001�N�`2023�N7���@��26.220Km�ŏI��)
�� �ȂǂȂǁE�E�E
8/2�i���j����@
1:30�N���C����قǐQ�ꂵ���炸�B�Ǐ��A�^���̃f�[�^�������S�B8:50�U���A�_���A�R�Œ��ߏグ�B������9��ړ����A���؎�����B�o�X11:10���ʃ��n�a�@�A�V���`�F�b�N�A14:30�a���J���t�@�B���@���ґΉ��B19:00�����njo�R�A��A�[�H�B20:30�A���B
���̖{�Ɠd�q������
�@���͎����Ă������Ђ̂قڂ��ׂĂ������ł炵�ăX�L���i�[�Ŏ�荞�ݓd�q�������B�������������肵�āA�{���ɂ悩�����Ǝv���Ă���B
�@����A���͂܂��{��G���̓d�q�łقƂ�Ǎw�����Ă��Ȃ��B��͂�w������{�͎��̏��Ђ������B
�@�d�q���Ђɋ^��������Ă���B���͉��i�ʂł���B���̖{�̓G�R�ł͂Ȃ����A�d�q���Ѝ쐬�ߒ����啝�ɏȗ͉��ł���͂�����������ƈ����Ă���������Ȃ����낤���B���������̏��Ђɕ�������炸���z�ł���B
�@�c��������̏K���ŁA�{�͎��œǂނ��̂Ǝv���Ă����B ���̖{�͏d�����A��G�肪�������邵�A���ꂼ��̖{�ɂ͓���������B �������d�v�ȗv�f�ŁA���߂邾���ł��y�����B���̖{�͓��e�͂������A�O����������ł���B
�@�����������n�߂������͂܂��A�d�q�����Ђ�ǂޒ[������ʓI�ɕ��y���Ă��Ȃ������B �^�u���b�g�͂������A�X�}�z�����݂̂悤�ɁA�w����q�ǂ��܂ł����悤�ȏł͂Ȃ������B
�@
�@���������̌�̃X�}�z��^�u���b�g�̕��y�͂����܂����A�����Ƃ����ԂɍL�����Ă������B
�@���������̏��Љ����n�߂��̂͏I���̈�Ƃ��Ă��̐��Ɏc�������I�ȉו������炷���߂ł����āA�����͓d�q��������̂̏��Ђ��^�u���b�g�œǂދC�ɂ͂Ȃ�Ȃ������B
�@���̂����ɕK�v�������Ă��̈ꕔ��ǂݎn�߂��̂ł��邪�A�����͂����ڂ��^�u���b�g��̎��ʂ�ǂ��Ă��邾���ŕ��͂��܂��������ɓ����Ă��Ȃ��̂ɂ͎����ł��������B
�@���X�Ɋ���A���ʓI�ɂƂĂ��֗��ȑ��݂ƂȂ����B����10�N�قǂ͍w���������Ђ͑����⊴�G���y���シ���Ƀo�����ēd�q�������ړǂނ��Ƃ͂قڊF���ɂȂ����B
�@�������A�d�q�����Ђ̏ꍇ�A�C�ɂȂ������͂����Ƃ���T�����Ƃ��Ă��A�ǂ��ɂ������̂��������B���̖{���ƁA�p���p���߂���Ȃ����̂��̂�����ɂ������͂��ƁA�����������邪�A�p���p���߂��肪�s���ӂȃ^�u���b�g�ł͂��ꂪ�ł��Ȃ��̂ŁA�ړ��Ă̕��͂��Ȃ��Ȃ������炸�ɂЂƋ�J����B���ꂪ�d�q���̑傫�Ȍ��_�ł���B
�@����ւ̑�Ƃ��Ėڎ����������茩�Ė{�̍\���ɓ���ēǂ݁A���X�܂��ڎ��ɖ߃��Ċm�F����B�]���قƂ�nj��Ȃ������C���f�b�N�X�����p����B����œd�q���̌��_�����Ȃ�J�o�[�ł���悤�ɂȂ����B
�@���ẮA�����͂��ׂēd�q���ЂɂȂ邾�낤�Ƃ������ЕҏW�҂������B�����������͂Ȃ�Ȃ������B�d�q���Ђɂ���������̗��_�͂���B
�@�������A���̏��Ђ̖��͂�d�q���Ђ͗��킷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ������A�Ǝv���B
�@���̖{����ɂ�����A���e�͂������A���̐G������l�X�ȑz������B���̖{�͎��o�����ł͂Ȃ��A�G�o�A�k�o�Ȃǂ̌܊���ʂ��Ď��ǂ���{���Ă����B ���ꂪ�{�̖��͂ł���B
�@�Ǐ��́A��y�ɕ��͂��ǂ߂�����̂ł͂Ȃ��B�ǂ�@��ăA�E�g�v�b�g���Ȃ��ƓǏ��̉��l�͔����ł��Ȃ��B������A���͎��̖{�̂悳���ł��Ȃ��B
�@
�@������A�܂����̏��Ђ��w�����A���̑��݂��\����������Ă���d�q�����鏊�Ȃł���B
8/1�i�j����������[���~�J�@���ʕa�@�O���@�@
2:00�N���C�~�J�̂��߂��C���ቺ�A�Q�ꂵ�����P�����B���͂����̔@���B5:00�R�S�~�p�������̂݁B6:40�o�X�ѐ�a�@�B7:00-8:10�a�����ґΉ��A8:45-12:30�O���A�\��25�����x�A�敾�B12:45�ѐ�a�@�A15:00���҉Ƒ��Ή��A�x�䎁�B19:15�Ђ�̂�o�R�A��A�[�H�B20:30�A���B�Ɠ���������B
�ŋߎ��Ԃ�����Ȃ�(1)�@��X�������E�ȗ͉������݂Ă���@�u���O�̘A���X�V������
�@�ŋߎ��Ԃ��s�����Ă���B
�@�ܘ_�A�����I�Ȏ��Ԃ��Z���Ȃ��Ă��邱�Ƃ͂Ȃ����A�������R�Ɏg���鎝�����Ԃ��R�����Ȃ��Ă��邱�Ƃ͊m���B���̂����Ńu���O�̋L�ڂ��x������ł���B�A���̍X�V�͍���ɂȂ����B7����10�����قǒx��Ă��܂����B
�@���ԕs���̗v���̑��͏A�Ɗ��̕ω��ł���B
�@����4���ȍ~�Ζ��悪�ς�����B�@�l�̏����E���Ƃ��Ă͕ς�肪�Ȃ����A�傽��Ζ��悪���ʑ����a�@�{�ѐ�a�@���璆�ʃ��n�r���e�[�V�����a�@�ƂȂ����B���܂ł̌��N�N���j�b�N(���j���ߑO)�A���ʑ����a�@���ȊO��(�Ηj���ߑO)�A��Ȓ��ʕa�@�O��(���j���I��)�͓����ł���B
�@�Ζ����Ԃ�����Ώ]���܂łƑ卷�͂Ȃ����A���e�I�ɂ͑傫�ȕω�������B
�@���ʃ��n�r���e�[�V�����a�@�ł͖�10�N�U��Ɏ厡��Ƃ��Ċ��҂�10���l�����Ă���B����Ɋ��Ґ���20���O��܂ő�����\��ł���B��{�I�ɂ�24���ԐӔC�����̂Ō��\��ςł���B
�@
�@���̗v���͎��̗̗̑͂ł���B
�@5��5���ɋ}���S�s�S�ǂ���1�T�ԓ��@�����B�K�����Ȃ������A���������̌��ʐS�@�\�̒����Ȓቺ������A�������ɋ��ʂ����������B�Ĕ��h�~�̂��߂�1���̉^���ʁE�����ʂ�啝�ɐ������ꂽ�B
�@����҂̏ꍇ�̊����ʂ�10Mets���x�Ƃ���A���̏ꍇ��2.7Mets�ȓ������߂��Ă���B���s�Ō�����3Km/���ȉ��ŁA�Ƃ������x���ł���B����Ŏ��̈ړ��\�́A�d�������͂ƂĂ��Ⴍ�Ȃ����B�V�����Ζ���̃X�^�b�t�B�͎���厖�Ɉ����Ă���Ă��邪�A�ނ�̂��߂ɂ��s�p�ӂɍĔ��������Ȃ��B
�@��O�̗v���͌��N���l���Đ������Ԃ�������������ƁB
�@�]������am1:00�N���ł�������am2:00���ɂ����B����ł�����Ǝ��R���Ԃ��Ȃ��Ȃ����B
�@��l�̗v���͓Ǐ��𒆐S�ɁA��X�̕����ɑ��鋻�������i���Ă��邱�ƁB
�@���낢��ȃW�������̏��Ђ�20���ȏ�����݁A��������iPad�œǂ�ł���B���W�I�[��ւȂǂ̘^���f�[�^�̍Ď������������Ȃ��B
�@���W�����Ă���͍̂O�����j�̓��k��V���[�Y�̃}���K�ł���B�����100�����z�����ň�l�̃T�����[�}���̐l�����w�����ォ���N��܂Œǂ������҂ŁA���͎����̐l������l���ɏd�ˍ��킹�Ė��킢�Ȃ���ǂ�ł���B
�@��܂̗v���͉��|�┨�d�����ׁX�Ȃ������Ă��邱�ƁB
�@������Ƃ̑���ɏ����܂��L���g�p����Ȃǂ��Ȃ����Ă��邪�A�A�������͎���҂��Ă���Ȃ����猋�\��ςł���B�ނ�͌����ȊJ�Ԃ⌋���Ŏ��ɉ����Ă����B
�@��Z�̗v���͔N�ƂƂ��Ɏ��Ԋ��o���Z�k���Ă��邱�ƁB�債�����Ƃ�����Ă��Ȃ��̂Ɏ��Ԃ���������������B
�@�܂��܂��v���͂���B
�@���ʂƂ��ău���O�̘A���X�V�͖����Ȃ悤�ł���B
�@�u���O�̊J�ݓ����͍������n�[�h�ɋƖ�������Ă��Ď��ɍX�V�ł��Ȃ����Ƃ͂��������A����10���N�͘A���X�V���Ă����B
�@�挎�������͎c�O�Ȃ�����߂邱�Ƃɂ����B
�@���ꂩ��͘A���X�V�ɂ������Ȃ��悤�ɂ������ł���B
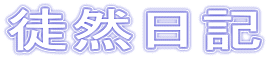
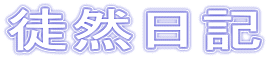
![]() �g�b�v�y�[�W�֖߂��@�@�@
�g�b�v�y�[�W�֖߂��@�@�@![]() �k�R���L�o�b�N�i���o�[
�k�R���L�o�b�N�i���o�[