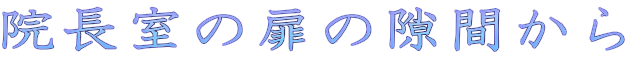
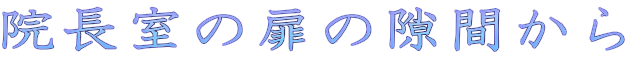
| 巻頭言:医療事故、医事紛争を防ぎたい(2011.5.26) |
| 私は本年5月末日をもって雇用契約が満了し退職する。長い間共に働いてきた全職員の方々に感謝申し上げたい。 今まで数多くの文章をこの中通病院医療に掲載してきたが、これが最後となる。 医療事故関係、医事紛争関係については折りにつけて講演等を行ってきた。退職数日前の5月26日には医療安全に関する全体学習会で最後の講演をする予定になっている。今回、医報の巻頭言を担当するにあたって、講演の内容整理をかねて「医療事故や紛争を防ぐにはどうすればいいのか」などについてまとめてみた。 |
(中通病院医報43(1):1-3.2010に掲載)
ご意見・ご感想をお待ちしています